| はやし浩司メインHP | マガジン過去版INDEX |
| 2011年 12月号 |
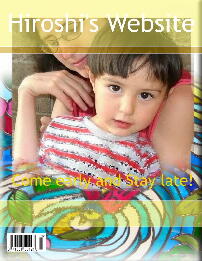 |
 |
| |
|
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 30日号(2)
================================
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
(前号からのつづきです。)
【シャドウ論2】
++++++++++++++++++++++
●人形子(にんぎょうし)(2008年6月記)
++++++++++++++++++++
A小学校のA先生と、電話で話す。
その中で、東京のA原で起きた、凶悪事件が、
話題になった。
あの事件を起こした男性は、中学生のころまで、
非のうちどころのない、優等生であったという。
成績は優秀で、まじめで、従順で……、と。
そんな男性が、トラックを借り、通行人の中に
突っ込んでいった!
何人かの人を殺した。
そんな話をしながら、私は「人形子」という言葉を使った。
++++++++++++++++++++
ペットというよりは、人形。
そんな子どもが、10人のうち、1〜2人はいる。
イプセンの『人形の家』にならって、私は「人形子
(にんぎょうし)」と呼ぶ。
できは、よい。
見た感じ、人格の完成度も高い。
ものわかりもよく、先生の指示に対しても、すなおに
従う。
やることに無駄がなく、ソツがない。
宿題もきちんとやってくる。
何か質問をしても、いつも模範解答が返ってくる。
先生「拾ったお金は、どうしますか?」
子 「交番へ届けます」
先生「自分で使ってしまう人もいますが・・・」
子 「そんなことをすれば、落とした人が困ります」と。
学習面でもすぐれている。
「あなたは家から帰ったら、何をしているの?」と
聞くと、「お母さんが買ってくれた、本を読んでいます」
などと答える。
そんなわけで、幼稚園でも学校でも、「いい子」という
評価を受ける。(・・・受けやすい。)
冒頭で、「10人のうち、1〜2人はいる」と書いたが、
もちろん程度の差もある。
もし基準をさげたら、10人のうち、2〜3人に
なるかもしれない。
が、反対に、「これではいけない」と思う子どもも、いる。
そういう子どもが、20人に1人とか、30人に
1人とかいる。
というのも、人形子になるには、ひとつの条件がある。
子ども自身、ある程度、できがよくなければならない。
できがよいから、親が、子どもの教育にますます
のめりこむ。
つまり子どもは、親の期待にこたえようと、ますます人形子に
なっていく。
「いい子」を演ずることによって、自分の立場を確保しよう
とする。
わかりやすく言うと、仮面をかぶる。
が、そのうち、その仮面をはずせなくなってしまう。
幼稚園や学校に教師に対しても、そうである。
こうして幼稚園の年長期を迎えるころには、独特の
雰囲気をもった子どもになる。
一口で言えば、子どもらしさそのものが、ない。
子どもっぽさを、感じない。
子どものはずなのに、妙に、おとなびている。
が、親は、そういう自分の子どもを見ながら、むしろ
できのよい子どもと思ってしまう。
反対に、そうでない子どもを、できの悪い子どもとして、
遠ざけてしまう。
親の過関心、過干渉、それに溺愛が混ぜんいったいとなって、
その子どもの世界を包む。
明けても暮れても、頭の中にあるのは、子どものことばかり。
「ゲームのような低劣なものは、家には置きません」
「うちの子は、受験勉強とは無縁の世界で育てます」
「歌は、プロの先生に指導していただいています」
「毎週、1冊は、本を読ませています」などなど。
「ある程度は、俗世間に融和させないと、お子さん
自身が、つらい思いをするのでは?」と、教師がアドバイスしても、
聞く耳、そのものをもっていない。
自ら厚いカプセルの中に入ってしまっている。
その狭い世界の中だけで、独自の教育観(?)を、
熟成させてしまっている。
「英語の先生は、ネイティブでないと困ります」
「理科教育は、何でも実験を先にしてから、教えてほしい」
「備え付けの楽器は、不潔だから、使わせないでほしい」などなど。
学校の教育についても、あれこれと注文をつけていく。
しかしこういう親が一人いるだけで、その教室の教育は
マヒしてしまう(A先生)。
では、どうするか?、・・・という問題よりも、そういう
親は、一度、先に書いた、イプセンの『人形の家』を
読んでみたらよい。
が、その程度ではすまない。
幼児期から、思春期前後まで、「いい子」で通した子どもほど、
あとがこわい。
何度も書いているが、子どもというのは、その発達段階ごとに、
昆虫がカラを脱ぐようにして、成長していく。
第一次反抗期には、第一次反抗期の子どものように、
中間反抗期には、中間反抗期の子どものように・・・。
非行が好ましいというわけではないが、非行を経験した
子どもほど、あとあと常識豊かな子どもになるということは、
この世界では常識。
(そもそも「非行」とは何か? その定義もあやしい?)
たとえば思春期前後から、はげしい家庭内暴力を繰りかえす
ようになる子どもがいる。
このタイプの子どもほど、それまで、「いい子?」だった
というケースがほとんどである。
だから子どもが家庭内暴力を繰りかえすようになると、
ほとんどの親は、泣きながら、こう叫ぶ。
「どうして?」「子どものころは、あんないい子だったのに!」と。
しかしそれは親の目から見て、「いい子?」だったにすぎない。
(以上、A先生の許可をいただき、A先生の話の内容を、
まとめさせていただきました。08年6月23日。)
++++++++++++++++++++++++
【引きこもりvs家庭内暴力】
++++++++++++++++
将来的に、引きこもったり、家庭内暴力を
起こす子どもというのは、その前の段階で、
独特の雰囲気を、もつようになる。
それについては、何度も書いてきたので、
ここでは省略する。
問題は、そういう雰囲気を感知したとき、
それをどこまで親に告げるべきか。
教師は、その問題で、悩む。
この段階では、たいていの親たちは、
「自分の子どもはできがいい」とか、
「うちの子にかぎって」とか思っている。
大半は、「私の育児のし方こそ、ぜったい」と
思っている。
思っているというよりも、信じている。
そういう親に向かって、「お宅のお子さんには
問題があります」などとは、言えない。
言ったとたん、親はパニック状態になる。
ついで、教師と親の人間関係は、終わる。
そんなわけで、たいていの教師は、「もしまちがっていたら・・・」
という迷いもあり、かたく口を閉ざす。
つまりここに書いた、人形子も、そうである。
人形子とわかっていても、それを口にするのは、
タブー中のタブー。
が、このタイプの子どもほど、思春期を迎えるころ、
はげしく豹変する。
年齢的は、12〜14歳前後か。
ふつうの豹変ではない。
ある日を境に、突然、狂ったように暴れだしたりする。
「オレをこんなオレにしたのは、テメエだア!」と。
中には、豹変しないで、人形子のまま
おとなになる子どももいる。
イプセンの『人形の家』の中の主人公が、
その一例かもしれない。
そういう意味では、この時期にはげしく親に
抵抗する子どものほうが、まだマシという
ことになる。
心の内にたまったエネルギーは、できるだけ
早い時期に吐き出したほうがよい。
が、反対に引きこもるタイプの子どももいる。
よく誤解されるが、引きこもるから暴力をふるわない
ということではない。
ちょっとしたことで錯乱状態になって、暴れたりする。
そこであなたの子どもは、どうか?
あなたの前で、子どもらしく、自由に、伸び伸び
しているだろうか。
言いたいことを言い、したいことをしているだろうか。
もしそうなら、それでよし。
が、反対に、「うちの子は、できがいい」と思っているなら、
ここに書いたことを、もう一度、読みなおしてみてほしい。
子育てというのは、自分で失敗してみて(失礼!)、
はじめて失敗と気づく。
これは子育てそのものがもつ、宿命のようなものかも
しれない。
賢い親は、それに事前に気づき、そうでない親は、
失敗(失礼!)してから、それに気づく。
(「失敗」という言葉を使うのは、好きではないが・・・。)
+++++++++++++++++++++++
●「人形の子」論
+++++++++++++++++++++++
●あるお母さんからのメール
++++++++++++++++++
親から受けた子育てが原因で、
長い間、大きな心のキズに苦しんでいた
お母さんから、こんなメールが
届いています。
読者のみなさんの力になればと、
公開してくださいとのこと。
喜んで、そうさせていただきます。
お名前を、Vさん(母親)としておきます。
Vさんは、子どものころ、親からきびしい
教育としつけを受け、それが原因で、
心に大きなキズを受けてしまいました。
Vさんは、「私がしたような経験を、ほかの
子どもたちにはしてほしくない」と言っています。
本当に、そうだと思います。
最近の研究によれば、うつ病の(種)のほとんどは、
その人の乳幼児期にあるということまで、
わかってきました。
乳児期から幼児期にかけては、
(1) 心豊かで、穏やかな家庭環境、
(2) 愛情豊かで、静かな親子関係、
この2つが、とくに重要かと思います。
Vさんからのメールをお読みください。
++++++++++++++++++
【Vさんより、はやし浩司へ】
はやし先生、こんばんは!
今日はレッスン前に、少しだけしたが、私がかかえる障害のお話を聞いてくださって、
ありがとうございました。
私は 先生のEマガによる「自己開示」でいえば4〜5レベルに入るほど、
まわりの人たちに、いろいろなことを話しています。
隠していなくてはならないことなど、そんなにはないし、
自分を知ってもらうことは 息子であるY男にとっても
良いことのように思ったりするからです。
先生が、私の経験を多くの人たちにお話してくださるのももちろん、歓迎です
良い例として、あるいは悪い例として、
私の経験してきたことが今、どんな風に私の人生で活かされているのか、
また、少女時代の私と同じ思いを、今まさにしている子供たちが今いるとしたら、
保護者の方に気づいていただきたいからです。
両親の教育が厳しく 過干渉で 私にとっては、長くて、辛い少女時代でした。
特に厳しかったのは母でした。しかし母だけを責めているのではありません。
母は 明治生まれの姑の前で、私たち姉妹を懸命に育て、
社会に出ても恥ずかしくない子に育てをしなくては……という使命のもとでの
思いだったわけです。
当時は今のように、相談できる機関や話を打ち明けられる相手もなく、
母も苦しんだと思います 父も相談相手にはならなかったようです。
というのも 父は自分の父親を第二次世界大戦で亡くし、
顔を見た事もないまま育ったそうです。
私は今でも、ラバウル上空を通過するときは 胸が苦しくなります。
そして実の母は 姑に父を残して 再婚して出て行ってしまったそうです。
どれほどの想像を絶する悲しみを乗り越えたでしょう。
父は曾祖母に対して異常なまでの執着心を持ち妻より子供より、曾祖母
という感じでした。
そんな生活の中で 母は私たちを厳しく育てることと、しつけることで、
自分なりのアピールをしていたのかもしれません。
また 別の観点からすると 母は私たちの子育てを、はけ口としていたかも
しれません。そのことも否定できないと思っています。
では、姉にはなぜ私のような障害が起きなかったか。
私の姉は3歳年上のキャリアウーマンですが、
何をするにも要領がよく、賢く、そして心優しく 暖かい人間で、
身内の私が言うのも恐縮ですが 尊敬しています。
母やきびしい習い事の先生がおっしゃる非道徳的な言葉ですら、
「あの人、なにいってるんだろ。私のどこまでしってるっていうの?」と
冷静な受け止め方が子供の頃からできたようです。
私はといえば、まったく正反対。
母の期待にこたえよう。今、Dropoutしてしまえば お母さんが悲しむかとか、
そんなことばかり考えていました。
生真面目で いつも良い子でいなくてはならない。いつも良い点を取らなくてはならない。
お母さんが悲しむから。クラス代表に選ばれなくてはならない。母が望むから、と。
小学校3年生のとき、サンタさんに手紙を出しました。
サンタさんの存在を信じていたころ書いた、最後の手紙だったと思います。
内容は、「お願いです プレゼントはいりません ただ習い事を全部やめさせてください」
というものでした。
サンタさんが願いをかなえてくれなかったのは、これが初めてでした。
心療内科の先生はおっしゃいました。
「あなたのお父様もお母様も 強迫性障害 の可能性がある」と。
思い当たる節はいくつもありました これは遺伝する可能性のある
障害だそうです。
今年前半は、T市にある児童心療内科まで、Y男をつれて、月に一度通っていました。
Y男のためというよりは 私が息子と、どう向きあえばよいのか、
どう育てていけばよいのか、全くわからなくなり、心は八方塞になったからです。
今思えば あの半年間の通院は 心療内科の先生に会って私がカウンセリングを受ける
私のいわば治療であったように思います。
時がたつにつれて、私は私の方法で Y男と向き合っていけばいいと思うように
なりました。
なぜなら、私はY男の母親なのだから……。
こんなシンプルな答えにたどり着くのに 随分と遠回りをしたし、
これからもしてしまうことがあるのかもしれませんが、今は 安定した気持ちで、
Y男に接しています。
父はY男がおなかにいるときに脳内出血で倒れ、現在は、右半身不随の生活をしています。
それがわかった当時は、みんな私のBabyではなく、
父の病気のことにばかり関心をもって、情緒不安定になり、
母や夫に当たったこともありました。
しかし母は立派に父のパートナーとして、父の治療に徹底的につき合っています。
ひところは東京のホテルに3か月ほど暮らして、有名な先生の治療を受けていました。
けれど回復には限度があり 今は良くも悪くもならないように、
リハビリとして、朗読や華道、陶芸など様々なことにチャレンジしています。
また 現在では障害者対応の施設も多く 年に3回ほど旅行に出かけています
障害者仲間の皆様との出会いも 両親を大きく支えてくださっていると思います
で、父もあきらかな強迫性障害者です。
強迫行為といって 鍵を閉めたか、ガスの元栓は締めたか、
冷蔵庫はちゃんとしまっているか、
出かける前もふだんの生活の中でも、あまりにもしつこいこれらの行為に
私たちは障害のことは何も知らずに、へきえきしていました。(以上、2008年6月記)
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●講演では……
次回の講演時間は、90分。
シャドウ論にはふれても、ここに書いたことまでは、話せない。
あちこちを端折(はしょ)る。
あるいは時間の関係で、話せないかもしれない。
(ここまでのページ数は、34頁(40字x36行x34頁)。)
もともに話したら、これだけで講演会は終わってしまう。
どうしようか?
言い換えると、講演というのは、いかに端折るかの闘い。
時計を見ながら、「ここまで!」とか、「ええい、ままよ!」と投げ捨てるような形で、そ
の話題から遠ざかる。
で、最後に一言。
心の別室というのは、実はだれにでもある。
大小、程度の差はあるが、だれにでもある。
だから大切なことは、まず自分の心の別室に気づくこと。
子どもについても、そうである。
あなたの子どもは、どうだろうか。
心の別室をもっていないだろうか。
もっているとしたら、その別室には、どんな思いが入っているだろうか。
この原稿を手がかりに、それを探ってみたらよい。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教
育評論 はやし浩司 心の別室論 ユング シャドウ論 シャドー論 抑圧された心、は
やし浩司 いい子論 よい子論 心をゆがめる子ども 子供)
(付記)
●ゆがむ子どもの心
+++++++++++++++
F県に住んでいる、YSさん(母親)から、
こんな相談が届いた。
転載許可がもらえたので、そのまま紹介する。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
おはようございます。
前回は夫との事についての返信ありがとうございました。
今のところ、ごくごく普通に(?)過ごしています。
(腹の立つこともありますが…。)
今回は、小1から不登校中の次女(小5)のことで、少し気になることがあったので
相談させてください。
つい最近、次女がとても怖いことを言い出しました。
「ナイフとか銃とかで、人を殺してみたい。あと、魔法が使えたら一回死んでみたい。
一回死んで、魔法で生き返る。飛び降りるのとか楽しそう。」
とか、さらっと普通の口調で言ったんです。
「魔法が使えなかったら、生き返らないね。」って言ったら、
「魔法が使えなかったらそんなことしない。」とは言っていましたが、とても不安で
怖くなりました。
「この世がつまらない?」って聞いたら、「べつに。」だそうです。
毎日家で普通に元気に過ごしているようにみえますし、会話も普通に
しています。
他に気になるような症状などはないと思っているのですが…。
これが本音ならどうしたらいいのか怖くなってしまいました。
5年生になってからの担任が熱心(?)で、今までよりも少し学校に関する
刺激は増えているかなとは思いますが、そのせいもありますか?
学校のことを聞いてみても、特別嫌そうな顔はしませんし、イヤだと言ったことは
すぐに引いてしつこくはしていません。
最近アニメが大好きで、アニメばかり見ているのですが、(ガンツという殺し合いの
映画も見ました)、戦いモノがあったりもするので、その影響?とも思ってはいますが…。
半年ほど前にも「火をつけてみたい。」と言ったことがあったので、
次女の心の中はどうなっているのかとても不安です。
どうぞよろしくお願いいたします。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●「抑圧は悪魔を作る」
イギリスの教育格言に、『抑圧は悪魔を作る』というのがある。
心理的な抑圧感が長くつづくと、ものの考え方が悪魔的になることを言ったもの。
その一例として、H・フォスデックも、つぎのように言っている。
『Hating people is like burning down your house to kill a rat(人を恨む(憎む)と
いうのは、ネズミを殺すために、家を燃やすようなものだ)』と。
ゆがんだ感情(劣勢感情、陰性感情、劣等感情)は、脳内ホルモンの分泌そのものにも
大きな影響を与える。
サイトカインを例にあげるまでもない。
サイトカインは、脳内ストレスを引き起こす。
それだけではない。
低体温を引き起こし、免疫機能を低下させる。
もちろん精神活動にも大きな影響を与える。
YSさんの子どものばあい、表面的にはともかくも、かなりこころがゆがみ始めていると
みる。
が、このタイプの子どもは少なくない。
●I君(小6)のケース
I君は、父親が中学校の教師だった。
それもあって、教育熱心な家庭環境で生まれ育った。
ふだんは静かで、それなりに勉強もよくできた。
私の指示にも、素直に(?)従った。
が、ある日、そのI君のノートを見て、びっくりした。
そこには血を出してもがき苦しむ人間の顔が、実にリアルに描かれていた。
ほかに「死」「殺」などの文字も並んでいた。
現実にそこに見る(I君)と、ノートに見る(I君)は、あまりにもかけ離れていた。
私はそれに驚いた。
●M子さん(中1)のケース
M子さんは早熟で、体格もすでにおとなになっていた。
そのM子さんが、教室にプリクラ・ブックを置き忘れていった。
で、私はそれを「忘れ物コーナー」に置いた。
が、翌日、そのブックが、騒動の種になった。
別の子どもがそのノートを開いた。
見て、ワーワーと騒ぎ出した。
ほかの子どもたちも騒ぎ出した。
見ると、メモページには、全裸の女性が椅子に縛られ、性的拷問を受けている絵が、何
枚も描かれていた。
残虐な絵もあった。
そのM子さんの絵も、絵というよりは、写真を思わせるほど、リアルな絵だった。
ただM子さんは、頭もよく、行動的で活発。
絵から想像するような陰湿さは、みじんもなかった。
M子さんは、脳内で起きている性的エネルギーを、自ら抑圧し、それが原因で、心をゆ
がめていた。
●抑圧
心理学でいう「抑圧」を、安易に考えてはいけない。
私は「心の別室」と呼んでいる。
それについて書いた原稿をさがしてみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●「抑圧」の恐ろしさ(Another Room in the Mind)
(電子マガジン・2009年7月15日より)
++++++++++++++++++++
よく兵士、あるいは元兵士の残忍行為が問題になる。
最近でも、アメリカの収容所で、アメリカ兵が
イラク軍捕虜に対して暴力、暴行を繰り返したという事件が
問題になった。
こう書くからといって、アメリカ兵を擁護するわけではない。
が、こうした問題は、常に戦争について回る。
戦時中には、日本軍もした。
ドイツ軍もした。
その多くはPTSDに苦しみ、さらには心そのものを
病んでしまう兵士も珍しくない。
昨年見た映画の、『アナザー・カントリー』も、そうした兵士を
題材にした映画だった。
が、こうした問題も、心理学でいう「抑圧」を当てはめてみると、
理解できる。
++++++++++++++++++++
●抑圧
自分にとって都合が悪い記憶があると、人はそれは心の別室を用意し、そこへそれを
押し込めてしまう。
そうすることで、自分の心が不安定になったり、動揺したりするのを防ぐ。
こうした現象を、心理学の世界では、「抑圧」という。
「隠ぺい記憶」と言う人もいる。
もともとは乳幼児期の不快な思い出や記憶について起こる現象を説明したものだが、
もちろんおとなになってからも、ある。
何かのことで失敗したり、いやなことがあったりすると、それをできるだけ早く
忘れようと、心の別室を用意し、その中に押し込んでしまう。
●上書きされない
ふつう記憶というのは、どんどんと上書きされていく。
たとえば不愉快なことがあっても、そのあと楽しいことがつづくと、過去の記憶を
忘れてしまう。
が、心の別室に入った記憶には、その(上書き)という操作が働かない。
別室に入ったまま閉じ込められているから、修正されるということもない。
だから何かの拍子に表に出てくる。
たとえば高校生になった子どもが、5年前、あるいは10年前にあったことを持ち出し、
「あのとき、テメエは!」と言って、親に対してどなり散らすことがある。
また最近聞いた話では、ともに70歳前後の夫婦なのだが、喧嘩するたびに、30年前、
40年前の話を持ち出して、たがいに責めあうという。
それを横で聞いていた娘(50歳くらい)は、こう言った。
「どうしてそんな昔の話をして、喧嘩するのでしょう。
頭がボケてきたのでしょうか」と。
もちろん頭はボケていない。
(あるいはボケとは関係ない。)
抑圧された記憶というのは、そういうもの。
●子どもの世界でも
「いい子ほど心配」とは、教育の世界では、よく言う。
先生や親の言うことに従順で、すなお。
ハイハイと指示や命令に従う……。
しかしこのタイプの子どもほど、あとあと心をゆがめやすい。
(あるいはその過程で、すでに心をゆがめている。)
思春期前夜、あるいは思春期になると、突然変化することも珍しくない。
はげしい家庭内暴力や、引きこもりにつながることもある。
何かのことで突発的に爆発して、こう叫んだりする。
「こんなオレにしたのは、テメエだろう!」と。
心の別室には、キャパシティ(容量)というものがある。
そのキャパシティを超えると、隠ぺいされた記憶が、そこから突然、飛び出す。
本人ですらも、コントロールできなくなる。
そんなわけで、子どもを指導するとき大切なことは、子どもに、
心の別室を作らせないこと。
まず言いたいことを言わせる。
したいことをさせる。
常に心を開放させる。
それが子どもの心をゆがめないコツということになる。
●兵士のばあい
話を戻す。
もちろん私には戦争の経験はない。
ないが、おおよその見当はつく。
つまり兵士たちは、戦場では、慢性的に恐怖感にさらされる。
そのとき兵士は、その恐怖感を、心に別室を作り、そこへ押し込めようとする。
その上で、勇敢な兵士を演じたりする。
が、これが心をゆがめる。
何かのきっかけ、たとえば相手が捕虜であっても、敵の顔を見たとたん、隠ぺい
された記憶が暴走し始める。
それは「記憶の暴走」と言うような、簡単なものではないかもしれない。
暴走させることによって、心の別室にたまった、恐怖感を解消しようとするの
かもしれない。
それが捕虜への、暴力や暴行へとつながっていく。
●教授の殺害事件
今年(09)に入ってから、ある大学で、ある大学の教授が、元学生に殺害
されるという事件が起きた。
動機はまだはっきりしていないが、その学生は教授に対して、かなりの恨みを
もっていたらしい。
この事件も、「抑圧」という言葉を当てはめてみると、説明できる。
というのも、その元学生のばあいも、元学生とはいっても、大学を卒業してから、
すでに10年近くもたっている。
ふつうなら、いろいろな思い出が上書きされ、過去の思い出は消えていてもおかしく
ない。
が、先にも書いたように、一度心の別室に入った記憶は、上書きされるということは
ない。
いつまでも、そのまま心の中に残る。
そこで時間を止める。
●心の別室
ところで「心の別室」という言葉は、私が考えた。
心理学の正式な用語ではない。
しかし「抑圧」を考えるときは、「心の別室」という概念を頭に描かないと、どうも
それをうまく説明できない。
さらに「心の別室」という概念を頭に描くことによって、たとえば多重人格性などの
現象もそれで説明ができるようになる。
人は何らかの強烈なショックを受けると、そのショックを自分の力では処理することが
できず、心の別室を用意して、そこへ自分を押し込めようとする。
「いやなことは早く忘れよう」とする。
しかし実際には、「忘れる」のではない。
(その記憶が衝撃的なものであればあるほど、忘れることはできない。)
だから心の中に、別室を作る。
そこへその記憶を閉じ込める。
●では、どうするか
すでに心の別室を作ってしまった人は、多いと思う。
程度の差の問題で、ほとんどの人に、心の別室はある。
暗くてジメジメした大倉庫のような別室をもっている人もいる。
あるいは物置小屋のような、小さな別室程度の人もいる。
別室が悪いと決めつけてはいけない。
私たちは心の別室を用意することによって、先にも書いたように、
自分の心が不安定になったり、動揺したりするのを防ぐ。
が、その別室の中の自分が、外へ飛び出し、勝手に暴れるのは、よくない。
その瞬間、私は「私」でなくなってしまう。
ふつう心の別室に住んでいる「私」は陰湿で、邪悪な「私」である。
ユングが説いた「シャドウ」も、同じように考えてよい。
あるいはトラウマ(心的外傷)も、同じように考えてよい。
そこで大切なことは、まず自分自身の中にある、心の別室に気がつくこと。
そしてその中に、どんな「私」がいるかに気がつくこと。
シャドウにしても、トラウマにしても、一生、その人の心の中に残る。
消そうとして消えるものではない。
だったら、あとは、それとうまく付きあう。
うまく付きあうしかない。
まずいのは、そういう自分に気がつかないまま、つまり心の別室にきがつかない
まま、さらにはその中にどんな「私」がいるかに気がつかないまま、その「私」に
振り回されること。
同じ失敗を、何度も繰り返すこと。
たとえば夫婦喧嘩にしてもそうだ。
(私たち夫婦も、そうだが……。)
もうとっくの昔に忘れてしまってよいはずの昔の(こだわり)を持ち出して、
周期的に、同じような喧嘩を繰り返す。
「あのときお前は!」「あなただってエ!」と。
もしそうなら、それこそ「愚か」というもの。
が、もし心の別室に気がつき、その中にどんな「私」がいるかを知れば、あとは
時間が解決してくれる。
5年とか、10年はかかるかもしれないが、(あるいは程度の問題もあるが)、
時間が解決してくれる。
あとは心の別室を静かに閉じておく。
その問題には触れないようにする。
心の別室のドアは、開かないようにする。
対処の仕方は、シャドウ、もしくはトラウマに対するものと同じように考えてよい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW BWきょうしつ 心の別室 はやし浩司 抑圧 抑圧と
心の別室 シャドウ はやし浩司 トラウマ)
(付記)
心の別室といっても、けっしてひとつではない。
そのつど人は、様々な大きさの別室を、作る。
作って、自分の心を救済しようとする。
……と考えていくと、心の別室というのは、脳の問題というよりは、習慣の問題
ということになる。
心の別室を作りやすい人と、そうでない人がいるということ。
何かあるたびに、心の別室を作り、そこへ自分を閉じ込めようとする人もいれば、
そのつど自分を発散させ、心の別室を作らない人もいる。
だから「習慣の問題」ということになる。
もちろんできれば、心の別室など、作らないほうがよい。
そのつど自分を発散させたほうがよい。
(追記)
同じような原稿を、この3月にも書いた。
あわせて読んでほしい。
●「抑圧」(pressure)
+++++++++++++
昨日、「抑圧」について書いた。
強烈な欲求不満がつづくと、人(子ども)は、
その欲求不満を、心の中の別室に押し込んで、
それから逃れようとする。
が、それでその欲求不満が解消されるわけではない。
10年とか、20年とか、さらには40年とか、
50年たっても、それが何らかのきっかけで、
爆発することがある。
「こんなオレにしたのは、お前だろう!」と。
++++++++++++++++++
が、こうした「抑圧」は、形こそちがえ、また
大小のちがいもあるが、だれにでもある。
あなたにもある。
私にもある。
だから、何かのことで不満を感じたら、そのつど、
外に向かって吐き出すのがよい。
けっして、心の中にためこまない。
徒然草の中にも、『もの言わぬは、腹ふくるるわざなれ』※
とある。
「言いたいことも言わないでいると、腹の中がふくれてくる」
という意味である。
が、その程度ですめばよい。
ひどいばあいには、心に別室ができてしまう。
本来なら楽しい思い出が上書きされ、不愉快な思い出は消える。
しかし別室に入っているため、上書きされるということがない。
そのまま、それこそ一生、そこに残る。
そして折につけ、爆発する。
「こんなオレにしたのは、お前だろう!」と。
そして10年前、20年前の話を持ち出して、相手を責める。
こうした抑圧された感情を解消するためには、2つの
方法がある。
ひとつは、一度、大爆発をして、すべて吐き出す。
もうひとつは、原因となった、相手が消える。
私のばあいも、親に対していろいろな抑圧があるにはあった。
しかし父は、私が30代のはじめに。
母は、昨年、他界した。
とたん、父や母へのこだわりが消えた。
同時に、私は抑圧から解放された。
親が死んだことを喜んでいるのではない。
しかしほっとしたのは、事実。
それまでに、いろいろあった。
ありすぎてここには書ききれないが、それから解放された。
母は母で、私たちに心配をかけまいとしていたのかもしれない。
しかしどんな生き方をしたところで、私たちは、それですまなかった。
「では、お母さんは、お母さんで、勝手に生きてください。
死んでください」とは、とても言えなかった。
人によっては、「朝、見に行ったら死んでいたという状態でも
しかたないのでは」と言った。
が、それは他人のことだから、そう言える。
自分の親のこととなると、そうは言えない。
いくらいろいろあったにせよ、家族は家族。
いっしょに生きてきたという(部分)まで、消すことはできない。
話が脱線したが、抑圧は、その人の心までゆがめる。
そういう例は、ゴマンとある。
大切なことは、心の別室を作るほどまで、抑圧をためこまないこと。
言いたいことも言えない、したいこともできないというのであれば、
すでにそのとき、その人との人間関係は終わっていると考えてよい』。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●思春期の子どもの心理
抑圧は、(1)内的抑圧と、(2)外的抑圧に分けて考える。
内的抑圧というのは、欲望、願望、希望などが原因で起こる、もろもろの欲求不満、不
平、不完全燃焼感などを抑圧することをいう。
外的抑圧というのは、たとえばきびしい家庭環境、威圧的、権威主義的な親の育児姿勢が
原因で起こる、もろもろの欲求不満、不平、不完全燃焼感をいう。
思春期前夜から思春期にかけては、この双方が、子どもの内部で起こりやすい。
それが結果として、子どもの心をゆがめる。
●すなおな子ども
「すなお」というより、「さわやかな」と言い換えたほうがよいかもしれない。
このことは幼児を観ると、よくわかる。
たとえば「野原と森、それに赤い屋根の白い家」を描かせてみる。
そのとき心がさわやかな子どもは、見ても、ほっとするようなやさしい絵を描く。
そうでない子どもは、どこか不気味。
もう30年前のことだが、こんなことがあった。
お父さんとお母さんの絵を描かせていたときのこと。
M君(年中児)が、お父さんの顔を描き始めるとすぐ、その顔を真っ黒に塗りつぶしてし
まった。
で、別の紙をあげ、もう一度描かせてみたが、結果は同じだった。
しばらくしてから母親に理由をたずねると、母親はこう言った。
「実はあの前の夜、夫が蒸発しまして」と。
当時は突然の家出を、「蒸発」といった。
その前後にも、似たような子どもがいた。
年長児の男児だったと思う。
その子どもは、父親の顔を描くのだが、体、とくに腕から手の部分を、鉛筆で真っ黒に塗
りつぶしてしまった。
母親に理由を聞くと、母親はこう言った。
「主人(=父親)は、子どものころ大きな事故を経験し、右手が使えません。しかし息
子がそんなことを気にしているとは、夢にも思っていませんでした」と。
●YSさんのケース
それが内的抑圧によるものなのか、それとも外的抑圧によるものなのかは、わからない。
というのも、年齢的に、思春期に入っている。
脳内で起きている変化によるものであれば、内的抑圧になる。
しかし環境的に考えると、外的抑圧になる。
どちらであるにせよ、先に書いた、欲求不満、不平、不完全燃焼感が、怒濤のごとく渦
を巻いていると考えられる。
そのはけ口があればよいが、そのはけ口もない。
YSさんの娘は、きわめて閉塞的な環境の中で、袋小路に入ってしまっている。
心理カウンセラー的な言い方をすれば、スポーツでも何でも、自分を発散させる場所を
与えろということになる。
が、実は、これと並行して、「自我の葛藤」の問題もある。
●自我の同一性
自我の同一性についても、たびたび書いてきた。
原稿をさがしてみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
Q: 最近わが子の親に対する話し方が気になります。
たとえば、私が何か「こうしなさい」と注意すると、「そんな法律がどこにあるの?」など
と言ってくるので、ついつい怒ってしまうこともしばしば……。
これは反抗期なのでしょうか?
A:思春期最大のテーマは、「同一性の確立」(エリクソン)です。
(私はこうでありたい)という理想の自己像と、(現実の私)、つまり現実自己を、一致さ
せようとします。
一致した状態を「自我の同一性」と言います。その第一歩が、おとなの優位性の打破です。
それが「思春期の反抗」と考えてください。
(悪態)もそのひとつ。「そんな法律がどこにあるの?」と。
それを許せということではありません。
それができないほどまでに、子どもを抑えてはいけないということです。カリカリするの
はしかたないとしても、「ああ、うちの子は、今、児童期から青年期へと、脱皮を始めてい
るのだ」と、一歩退いて子どもを見ます。
この時期、親意識(とくに「親に向かって何よ!」式の悪玉親意識)が強すぎると、子
どもは親の前では仮面をかぶるようになります。
自我の確立に失敗し、非行に走ったり、親子の間にキレツが入り、親子が断絶するケース
も目立ちます。
最悪のばあいには、自我の崩壊……。
ナヨナヨとした軟弱な人間になることもあります。
親には3つの役目があります。 ガイドとして子どもの前に立つ。 保護者として子ど
ものうしろに立つ。 そして3番目が重要ですが、友として子どもの横に立つ、です。
悪玉親意識を捨て、子どもの友になるつもりで、子どもの横に立ってみてください。と
たん、肩の荷が軽くなりますよ。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●言葉として発散させる
YSさんの娘が慢性的な抑圧状態にあることは、まちがいない。
が、こうした抑圧は、多かれ少なかれ、どの子どもにもある。
それがない子どもは、いない。
YSさんは、自分の子どもを「異常」と思う必要はない。
平たく言うと、「この時期の子どもによく見られる現象」ということになる。
あまりおおげさに考えないこと。
「バカなこと言ってないで、さっさと自分のことをしなさい」程度に、軽く受け流してい
く。
ただし何らかの行動をともなうようであれば、要注意。
たとえば「殺したい」と言いつつ、ナイフを買い求める。
「死にたい」と言いつつ、その種の本を買ってくる。
あるいはペットなどに、残虐な行為を繰り返す。
リストカットをする。
そういうことがあれば、「観察」の段階を超えているとみる。
学校を通して、専門医もしくは心理療法士を紹介してもらう。
「治療」を考えた指導に切り替える。
で、同時に、「子どもは家族の代表」と考え、原因は家庭にあると考え、YSさん自身が
猛省する。
「家庭は休む場所」「憩う場所」「心を休める場所」と心得、それに適した環境を娘に用意
する。
そのときコツは、娘の中で、心の別室がどのように形成されているか、静かに観察、判断
すること。
子どもの立場になり、子どもの心の中から、子どもを見る。
頭ごなしに叱ったり、注意しても意味はない。
ないばかりか、かえって症状を悪化させるので、注意する。
以上ですが、ここの書いたことを参考に、子どもを観察してみてほしい。
何が子どもを抑圧状態にしているかがわかれば、解決策も自ずと見えてくる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 抑圧 心の別室 はや
し浩司 自我の同一性 はやし浩司 残虐な言葉 思春期の子どもの心 心のゆがみ ね
ずみを殺すために家に火をつける はやし浩司 内的抑圧 外的抑圧)
Hiroshi Hayashi++++++Oct. 2011++++++はやし浩司・
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
MMMMM
m | ⌒ ⌒ |
( ̄\q ・ ・ p
\´(〃 ▽ 〃) /〜〜
\  ̄Σ▽乃 ̄\/〜〜/
\ : ξ)
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 30日号
================================
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page028.html
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【ユングのシャドウ(シャドウ)論(Shadow)】
******************
11月30日(水曜日)
浜北文化センターにて、浜松市内では
今年度最後の講演会をもちます。
開場時刻は、午後6:30。
講演は、午後7:00〜8:30です。
おいでください。
******************
+++++++++++++++++++++
次回の講演で、久しぶりに、ユングのシャドウ論に
ついて話してみたい。
(時間があればの話だが……。)
そこで私の書いた原稿を探してみる。
今では「はやし浩司 シャドウ論」で検索すれば、すぐ、
原稿が見つかる。
ネット全体が、私の書類倉庫のようなもの。
「どうしてこんなことができるのだろう?」と、よく思う。
本当に、不思議な世界だ。
++++++++++++++++++++++
●子育て
いかに子育てが恐ろしいものであるかは、私が書いた「シャドウ論」を読んでもらえば
よくわかるはず。
昔から『子は親の背を見て育つ』とはいう。
しかしそれは何も、よいことばかりではない。
親が隠している邪悪な部分まで、子どもがそっくりそのまま受け継いでしまうこともある。
それが「シャドウ論」である。
たとえば欧米では、牧師による少年、少女への性的虐待事件が後を絶たない。
「虐待」と言えば、おおかた、その種の性的虐待をいう。
こうした心理も、ユングの「シャドウ論」をあてはめてみれば、よく理解できる。
●心の別室論
その原稿、つまり以前書いた、ユングのシャドウ論を紹介する前に、「心の別室論」につ
いて書いた原稿を紹介したい。
「心の別室」という言葉は、私が考えた。
つまり抑圧された心理状態が長くつづくと、子ども(人)は、心の中に別室をつくり、そ
こへそれを押し込んでしまう。
防衛機制のひとつとされている。
わかりやすく言えば、いやなことがあったら、別の心を作り、そこへ押し込んでしまう。
が、この心の別室の怖いところは、(1)時効が働かないということ。(2)たとえその
あといろいろな楽しい思い出があったとしても、記憶が上書きされないということ。
いつまでも心の別室の中に、独立して残り、時と場合に応じて、顔を出す。
たとえばこんな例がある。
80歳を過ぎた老夫婦だが、若いころから夫婦喧嘩が絶えなかった。
が、決まってそのとき出てくる言葉が、つぎのような言葉という。
「お前は、あのとき……!」
「あんただって、あのとき……!」と。
40年とか、50年も前の話。
ときには結婚当初の話すら出てくるという。
心の別室というのは、そういうもの。
+++++++++++++++++++++
心の別室については、たびたび書いてきた。
つぎの原稿は、2009年4月に書いたもの。
+++++++++++++++++++++
●心の別室と加害意識(Another Room in the Mind and Consciousness of Guilty)
++++++++++++++++++++
カレー・ヒ素混入事件で、現在無実を争って
いる女性が、HM。
地下鉄サリン事件で、これまた無実を争って
いる男性が、OS教のMT。
現在刑事裁判が継続中なので、これらの人たちは
無実という前提で、ものを考えなければならない。
どんな被告人でも、有罪が確定するまで、推定無実。
カレーにヒ素を混入させたのは、別人物かも
しれない。
地下鉄サリン事件には、MTは関与していなかった
かもしれない。
そういう可能性が、1000に1つ、万に1つでも
あるなら、これらの人たちは、無実。
そういう前提で、ものを考えなければならない。
が、同じ無実でも、いまだに納得できないのが、
あの『ロス疑惑事件』。
Kさんの殺害現場に、一台の白いバンがやってきた。
そのバンが走り去ったとき、Kさんは、殺されていた。
Kさんのそばには、MKがいた。
白いバンは、近くのビルにいた男性たちによって
目撃されている。
MK自身が撮った写真の中にも、白いバンの
一部が写っている。
しかしMKは、「白いバンは見ていない」と。
そのMKは、ロス市警へ移送されたあと、留置場の中で
自殺している。
MKは無実だったのか?
無実だったのなら、自殺などしないで、最後の最後まで
闘ってほしかった。
どうもこの事件は、すっきりしない。
いまだにすっきりしない。
++++++++++++++++++++
●心の別室論(Another Room in the Mind)
人間には、自分にとって都合の悪いことがあると、心の中に別室を作り、
そこへ押し込めてしまうという習性がある。
心理学では、こうした心理操作を、「抑圧」という言葉を使って説明する。
「心の平穏を守るために自らを防衛する機能」という意味で、「防衛機制」のひとつ
と考えられている。
その防衛機制は、つぎの7つに大別される。
(1) 抑圧
(2) 昇華
(3) 同一化
(4) 投射
(5) 反動形成
(6) 合理化
(7) 白日夢(以上、深堀元文「心理学のすべて」)
この中でも、「不安や恐怖、罪悪感などを呼び起こすような欲求、記憶などを
無意識の中に閉じ込め、意識にのぼってこないようにする」(同書)を、「抑圧」
という。
つまり心の別室の中に、それを閉じ込め、外からカギをかけてしまう。
よく「加害者は害を与えたことを忘れやすく、被害者は害を受けたことを
いつまでも覚えている」と言われる。
(そう言っているのは、私だが……。)
この「加害者は害を与えたことを忘れやすい」という部分、つまり都合の悪いことは
忘れやすいという心理的現象は、この「抑圧」という言葉で、説明できる。
が、実際には、(忘れる)のではない。
ここにも書いたように、心の別室を作り、そこへそれを押し込んでしまう。
こうした心理的現象は、日常的によく経験する。
たとえば教育の世界では、「おとなしい子どもほど、心配」「がまん強い子どもほど、
心配」「従順な子どもほど、心配」などなど、いろいろ言われる。
さらに言えば、「ものわかりのよい、よい子ほど、心配」となる。
このタイプの子どもは、本来の自分を、心の別室に押し込んでしまう。
その上で、別の人間を演ずる。
演ずるという意識がないまま、演ずる。
が、その分だけ、心をゆがめやすい。
これはほんの一例だが、思春期にはげしい家庭内暴力を起こす子どもがいる。
ふつうの家庭内暴力ではない。
「殺してやる!」「殺される!」の大乱闘を繰り返す。
そういう子どもほど、調べていくと、乳幼児期には、おとなしく、静かで、かつ
従順だったことがわかる。
世間を騒がす、凶悪犯罪を起こす子どもも、そうである。
心の別室といっても、それほど広くはない。
ある限度(=臨界点)を超えると、爆発する。
爆発して、さまざまな問題行動を起こすようになる。
話が脱線したが、ではそういう子どもたちが、日常的にウソをついているとか、
仮面をかぶっているかというと、そうではない。
(外から見える子ども)も、(心の別室の中にいる子ども)も、子どもは子ども。
同じ子どもと考える。
このことは、抑圧を爆発させているときの自分を観察してみると、よくわかる。
よく夫婦喧嘩をしていて、(こう書くと、私のことだとわかってしまうが)、
20年前、30年前の話を、あたかもつい先日のようにして、喧嘩をする人がいる。
「あのとき、お前は!」「このとき、あなたは!」と。
心の別室に住んでいる(私)が外に出てきたときには、外に出てきた(私)が私であり、
それは仮面をかぶった(私)でもない。
どちらが本当の私で、どちらがウソの私かという判断は、しても意味はない。
両方とも、(心の別室に住んでいる私は、私の一部かもしれないが)、私である。
私「お前なんか、離婚してやるウ!」
ワ「今度こそ、本気ね!」
私「そうだ。本気だア!」
ワ「明日になって、仲直りしようなんて、言わないわね!」
私「ぜったいに言わない!」
ワ「この前、『お前とは、死ぬまで一緒』って言ったのは、ウソなのね!」
私「ああ、そうだ、あんなのウソだア!」と。
そこでよく話題になるのが、多重人格障害。
「障害者」と呼ばれるようになると、いろいろな人格が、交互に出てくる。
そのとき、どれが(主人格)なのかは、本当のところ、だれにもわからない。
「現在、外に現れているのが、主人格」ということになる。
夫婦喧嘩をしているときの(私)も、私なら、していないときの(私)も、
私ということになる。
実際、夫婦喧嘩をしている最中に、自分でもどちらの自分が本当の自分か、
わからなくなるときがある。
ともかくも、心の別室があるということは、好ましいことではない。
「抑圧」にも程度があり、簡単なことをそこに抑圧してしまうケースもあれば、
重篤なケースもある。
それこそ他人を殺害しておきながら、「私は知らない」ですませてしまうケースも
ないとは言わない。
さらに進むと、心の別室にいる自分を、まったく別の他人のように思ってしまう。
そうなれば、それこそその人は、多重人格障害者ということになってしまう。
ところで最近、私はこう考えることがある。
「日本の歴史教科書全体が、心の別室ではないか」と。
まちがったことは、書いてない。
それはわかる。
しかしすべてを書いているかというと、そうでもない。
日本にとって都合の悪いことは、書いてない。
そして「教科書」の名のもとに、都合の悪いことを、別室に閉じ込め、
カギをかけてしまっている(?)。
しかしこれは余談。
ただこういうことは言える。
だれにでも心の別室はある。
私にもあるし、あなたにもある。
大切なことは、その心の別室にいる自分を、いつも忘れないこと。
とくに何かのことで、だれかに害を加えたようなとき、心の別室を忘れないこと。
忘れたら、それこそ、その人は、お・し・ま・い!
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
心の別室 防衛機制 抑圧 はやし浩司 心の別室論 人格障害 加害意識)
++++++++++++++++++++
そこで「シャドウ論」。
以下の原稿も、2009年ごろ書いた原稿である。
この中では、北朝鮮と韓国を例にあげ、「シャドウ論」を
展開してみた。
++++++++++++++++++++
●なし崩し的既成事実化
+++++++++++++++++++++
「独島(日本名、竹島)と、K国の核兵器と
かけて、何と、説く?」。
答……「なし崩し的、既成事実化」。
共に、ものごとをなし崩し的に、既成事実化しよう
としている。
+++++++++++++++++++++
●矛盾する論理
韓国の人たちは、「オレたちは、K国とはちがう」と思っているかもしれない。
とくに、K国の核開発問題については、そうであろう。
K国は事実上、核兵器を所有し、核保有国であることを、既成事実化しようとしている。
韓国政府も、「それは認めない」とがんばっている。
が、同じように韓国は、K国と同じことをしている。
竹島(独島)への実効的支配を強化し(中央N報)、竹島は韓国領土であることを、
既成事実化しようとしている。
同じ民族。
発想が、よく似ている。
……というより、K国は、韓国のあとを、懸命に追いかけている。
今日(4月10日)の韓国・中央N報は、つぎのように伝えている。
「…… 鄭総理は日本の独島(ドクト、日本名・竹島)領有権の主張に関し、『日本がこ
の
問題を持続的に取り上げるのは、韓日間の未来の発展に決して役立たない。すでに韓国の
国民が居住しているが、独島に対する実効的支配をさらに強化していく必要がある』と強
調した」と。
つまり事実上、支配しているから、竹島は、韓国の領土だ、と。
しかしこんな論理がまかりとおるなら、K国の核兵器開発問題は、どうなる?
K国も同じ論理をふりかざして、「自分たちの国を核保有国として認めろ」と騒いでいる。
●シャドウ論
韓国とK国を並べてながめていると、ユングのシャドウ論が、頭の中を横切った。
韓国のもつシャドウを、K国が受け継いでいる。
そんな感じがした。
そんな感じがしたので、韓国とK国、それにシャドウ論をからめて考えてみたい。
うまくまとめられるかどうか自信はないが、一度、書いてみる。
シャドウ論……「シャドウ(影)」として、心の裏に閉じこめられた人間性は、その近く
にいる人に伝染しやすい。その一例として、佐木隆三の『復讐するは我にあり』がある。
昨年(09年3月)に書いた原稿を、もう一度、ここでとりあげてみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【シャドウ論】
●仮面(ペルソナ)
++++++++++++++++++++
ペルソナ(仮面)そのものを、職業にしている人たちがいる。
いわゆる「俳優」という人たちが、それである。
で、あくまでも一説だが、あの渥美清という俳優は、本当は気難し屋で、
人と会うのをあまり好まなかったという(某週刊誌)。
自宅のある場所すら、人には教えなかったという(同誌)。
が、その渥美清が、あの『寅さん』を演じていた。
寅さんを演じていた渥美清は、ペルソナ(仮面)をかぶっていたことになる。
といっても、ペルソナ(仮面)が悪いというのではない。
私たちは、例外なく、みな、仮面をかぶって生きている。
私もそうだし、あなたもそうだ。
++++++++++++++++++++
●みな、かぶっている
たとえばショッピングセンターで、深々と頭をさげる女子店員を見て、
「人間的にすばらしい人」と思う人は、まずいない。
顔には美しい笑みを浮かべている。
何か苦情を言ったりしても、おだやかな口調で、「すみません。ただ今、
お調べいたします」などと答えたりする。
彼女たちは、営業用のペルソナ(仮面)をかぶって、それをしている。
同じように、教師だって、医師だって、みな、ペルソナ(仮面)を
かぶっている。
最近では、さらにそれが進化(?)した。
インターネットの登場である。
今、あなたは、私が書いたこの文章を読んでいる。
で、あなたはそれを読みながら、「はやし浩司」のイメージを頭の中で
作りあげている。
心理学の世界では、これを「結晶」と呼んでいる。
そのあなたが作りあげているイメージは、どんなものだろうか。
私にはわからない。
それに結晶といっても、その中身は、みなちがう。
ある人は、「林って、理屈っぽい、気難しい男だな」と思うかもしれない。
また別のある人は、「わかりやすい、単純な男だな」と思うかもしれない。
文章を読む人の、そのときの気分によっても、左右される。
映画なら、まだそこに「像」を見ながら、相手のイメージを頭の中で
作りあげることができる。
しかし文章だけだと、それがさらに極端化する。
それがこわい。
●相手の見えない世界
以前にも書いたが、たとえばメールで、「お前はバカだなあ」と書いたとする。
書いた人は、半ば冗談のつもりで、つまり軽い気持ちでそう書いた。
しかし受け取る側は、そうではない。
そのときの気分で、読む。
たとえば何かのことで、その人の心が緊張状態にあったとする。
だから、それを読んで激怒する。
「何だ、バカとは!」となる。
もっとも小説家といわれる人たちは、こうした結晶を逆手に利用しながら、
読者の心を誘導する。
よい例が、スリラー小説ということになる。
恋愛小説でもよい。
たとえば「A子は、みながうらやむほどの、色白の美人であった」と書いてあったとする。
それぞれの人は、それぞれの美人を空想する。
その美人の姿は、それぞれの人によって、みなちがう。
●現実
が、ここで重要なことは、ペルソナ(仮面)は、ペルソナ(仮面)として、
(現実)とは、しっかりと切り離すこと。
たとえば学生時代、私にとっては、「ベン・ハー」イコール、
「チャールトン・ヘストン」であり、「チャールトン・ヘストン」イコール、
「ベン・ハー」であった。
私には区別がつかなかった。
しかしこうした現象は、何も私だけに起きた特殊なものではない。
映画ドラマの中の主人公を、(現実の人)と思いこんでしまう現象は、
よく見られる。
しかも若い人たちだけではない。
40歳前後の女性ですら、それが区別できなくて、韓国の俳優を追いかけたり
する。
が、相手を見るときはもちろんのこと、自分自身に対してもである。
ペルソナ(仮面)と(現実)は切り離す。
とくに、自分がかぶっているペルソナ(仮面)には、警戒したほうがよい。
この操作を誤ると、自分で自分がわからなくなってしまう。
欧米では、牧師に、そのタイプの人が多いと言われている。
みなの前で、神の言葉を語っているうちに、自分自身が(現実)から遊離してしまい、
自分のことを(神)と思いこんでしまう。
が、それだけではすまない。
●シャドウ
このとき同時に、自分の中にある(邪悪な部分)を、心の中に別室に閉じこめて
しまう。
閉じこめながら、自分を善人と思いこんでしまう。
こうした現象を、あのユングは「シャドウ(影)」という言葉を使って説明した。
このシャドウが、別のところで、別人格となって、その人を裏から操る。
大教会の神々しいほどまでの牧師が、その裏で、少年や少女を相手に、性犯罪を
繰り返していたという例は、欧米では、たいへん多い。
が、さらに恐ろしいことが起きる。
このシャドウは、ときとして、そっくりそのまま子どもに伝わることがある。
心理学の教科書に出てくる例として、あの映画『復讐するは、我にあり』がある。
それについては以前にも書いたので、このあとに、そのとき書いた原稿を添付
しておく。
こういう例は極端な例であるとしても、親子の間でも、こうした現象はよく
観察される。
●シャドウを受けつぐ子ども
ある母親は、世間では「仏様」と呼ばれていた。
しかし2人の息子は、高校時代、ともに犯罪行為を犯し、退学。
周囲の人たちは、「どうしてあんないい母親なのに、息子さんたちは……?」と
言っていた。
が、こうした現象も、シャドウ論をあてはめてみると、説明がつく。
母親は、邪悪な部分、たとえば嫉妬、ねたみ、恨み、不満などを、心の中の別室に
閉じことによって、善人を演じていただけである。
そのシャドウを、いつも近くで見ていた息子たちが、受けついでしまった。
では、どうするか。
私たちはいつもペルソナ(仮面)をかぶっている。
それはそれでしかたのないこと。
ショッピングセンターの女子店員が、客に向って、「オイ、テメエ、そこの客、
泥靴なんかで、この店に来るなよ!」と叫べば、その女子店員は、そのまま解雇。
職を失うことになる。
この私だって、そうだ。
で、大切なことは、それをペルソナ(仮面)と、はっきりと自覚すること。
そして脱ぐときは、脱ぐ。
脱いで、自分に戻る。
ありのままの自分に戻る。
それをしないでいると、それこそ人格そのものが、バラバラになってしまう。
これはたいへん危険なことと考えてよい。
+++++++++++++++++
シャドウについて書いた原稿を
添付します。
+++++++++++++++++
【シャドウ論】
++++++++++++++++
仮面をかぶっても、仮面をぬぐことも
忘れないこと。
その仮面をぬぎ忘れると、たいへんな
ことになりますよ!
++++++++++++++++
●自分の中の、もう1人の自分
もともと邪悪な人がいる。そういう人が仮面をかぶって、善人ぶって生きていたとする。
するとやがて、その人は、仮面をかぶっていることすら、忘れてしまうことがある。自分
で、自分は善人だと思いこんでしまう。
このタイプの人は、どこか言動が不自然。そのため簡単に見分けることができる。さも
私は善人……というように、相手に同情して見せたり、妙に不自然な言い方をする。全体
に演技ぽい。ウソっぽい。大げさ。
こういう話は、以前にも書いた。
そこでこのタイプの人は、長い時間をかけて、自分の中に、もう1人の自分をつくる。
それがシャドウである。ユングが説いたシャドウとは、少し意味がちがうかもしれないが、
まあ、それに近い。
このシャドウのこわいところは、シャドウそのものよりも、そのシャドウを、時に、身
近にいる人が、そっくりそのまま受けついでしまうこと。よくあるのは、子どもが、親の
醜いところをそっくりそのまま、受けついでしまうケース。
●仮面(ペルソナ)をかぶる女性
ある母親は、近所の人たちの間では、親切でやさしい女性で通っていた。言い方も、お
だやかで、だれかに何かを頼まれると、それにていねいに応じていたりした。
しかし素性は、それほど、よくなかった。嫉妬深く、計算高く、その心の奥底では、醜
い欲望が、いつもウズを巻いていた。そのため、他人の不幸話を聞くのが、何よりも、好
きだった。
こうしてその女性には、その女性のシャドウができた。その女性は、自分の醜い部分を、
そのシャドウの中に、押しこめることによって、一応は、人前では、善人ぶることができ
た。
が、問題は、やがて、その娘に現れた。……といっても、この話は、20年や30年単
位の話ではない。世代単位の話である。
その母親は、10数年前に他界。その娘も、今年、70歳を超えた。
●子に世代連鎖するシャドウ
その娘について、近所の人は、「あんな恐ろしい人はいない」と言う。一度その娘にねた
まれると、とことん、意地悪をされるという。人をだますのは、平気。親類の人たちのみ
ならず、自分の夫や、子どもまで、だますという。
その娘について、その娘の弟(現在67歳)は、こう教えてくれた。
「姉を見ていると、昔の母そっくりなので、驚きます」と。
話を聞くと、こうだ。
「私の母は、他人の前では、善人ぶっていましたが、母が善人でないことは、よく知っ
ていました。家へ帰ってくると、別人のように、大声をあげて、『あのヤロウ!』と、口汚
く、その人をののしっていたのを、よく見かけました。ほとんど、毎日が、そうではなか
ったかと思います。母には、そういう2面性がありました。私の姉は、その悪いほうの一
面を、そっくりそのまま受け継いでしまったのです」と。
この弟氏の話してくれたことは、まさに、シャドウ論で説明がつく。つまり、これがシ
ャドウのもつ、本当のおそろしさである。
●こわい仮面
そこで重要なことは、こうしたシャドウをつくらないこと。その前に、仮面をかぶらな
いこと。といっても、私たちは、いつも、その仮面をかぶって生きている。教師としての
仮面。店員としての仮面。営業マンとしての仮面。
そういう仮面をかぶるならかぶるで、かぶっていることを忘れてはいけない。家に帰っ
て家族を前にしたら、そういう仮面は、はずす。はずして、もとの自分にもどる。
仮面をとりはずすのを忘れると、自分がだれであるかがわからなくなってしまう。が、
それだけではない。こうしてできたシャドウは、そのままそっくり、あなたの子どもに受
けつがれてしまう。
(はやし浩司 仮面 ペルソナ シャドウ (はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論
幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW はやし浩司 ユング 仮面 ペルソナ
シャドウ論)
++++++++++++++++++
少し前に書いた、「シャドウ論」を、
もう一度、ここに添付しておきます。
内容を少し手なおしして、お届けします。
++++++++++++++++++
●仮面とシャドウ
だれしも、いろいろな仮面(ペルソナ)をかぶる。親としての仮面、隣人としての仮面、
夫としての仮面など。もちろん、商売には、仮面はつきもの。商売では、いくら客に怒鳴
られても、にこやかな顔をして、頭をさげる。
しかし仮面をかぶれば、かぶるほど、その向こうには、もうひとりの自分が生まれる。
これを「シャドウ(影)」という。本来の自分というよりは、邪悪な自分と考えたほうがよ
い。ねたみ、うらみ、怒り、不満、悲しみ……そういったものが、そのシャドウの部分で、
ウズを巻く。
世間をさわがすような大事件が起きる。陰湿きわまりない、殺人事件など。そういう事
件を起こす子どもの生まれ育った環境を調べてみると、それほど、劣悪な環境ではないこ
とがわかる。むしろ、ふつうの家庭よりも、よい家庭であることが多い。
●凶悪事件の裏に
夫は、大企業に勤める中堅サラリーマン。妻は、大卒のエリート。都会の立派なマンシ
ョンに住み、それなりにリッチな生活を営んでいる。知的レベルも高い。子どもの教育に
も熱心。
が、そういう家庭環境に育った子どもが、大事件を引き起こす。
実は、ここに(仮面とシャドウの問題)が隠されている。
たとえば親が、子どもに向かって、「勉強しなさい」「いい大学へ入りなさい」と言った
とする。「この世の中は、何といっても、学歴よ。学歴があれば、苦労もなく、一生、安泰
よ」と。
そのとき、親は、仮面をかぶる。いや、本心からそう思って、つまり子どものことを思
って、そう言うなら、まだ話がわかる。しかしたいていのばあい、そこには、シャドウが
つきまとう。
親のメンツ、見栄、体裁、世間体など。日ごろ、他人の価値を、その職業や学歴で判断
している人ほど、そうだ。このH市でも、その人の価値を、出身高校でみるようなところ
がある。「あの人はSS高校ですってねえ」「あの人は、CC高校しか出てないんですって
ねえ」と。
悪しき、封建時代の身分制度の亡霊が、いまだに、のさばっている。身分制度が、その
まま学歴制度になり、さらにそれが、出身高校へと結びついていった(?)。街道筋の宿場
町であったがために、余計に、そういう風潮が生まれたのかもしれない。その人を判断す
る基準が、出身高校へと結びついていった(?)。
この学歴で人を判断するという部分が、シャドウになる。
●ドロドロとした人間関係
そして子どもは、親の仮面を見破り、その向こうにあるシャドウを、そのまま引きつい
でしまう。実は、これがこわい。「親は、自分のメンツのために、オレをSS高校へ入れよ
うとしている」と。そしてそうした思いは、そのまま、ドロドロとした人間関係をつくる
基盤となってしまう。
よくシャドウ論で話題になるのが、今村昌平が監督した映画、『復讐するは我にあり』で
ある。佐木隆三の同名フィクション小説を映画化したものである。名優、緒方拳が、みご
とな演技をしている。
あの映画の主人公の榎津厳は、5人を殺し、全国を逃げ歩く。が、その榎津厳もさるこ
とながら、この小説の中には、もう1本の柱がある。それが三國連太郎が演ずる、父親、
とるけん」と言う。そんなセリフさえ出てくる。
父親の榎津鎮雄は、倍賞美津子が演ずる、榎津厳の嫁と、不倫関係に陥る。映画を見た
人なら知っていると思うが、風呂場でのあのなまめかしいシーンは、見る人に、強烈な印
象を与える。嫁は、義理の父親の背中を洗いながら、その手をもって、自分の乳房を握ら
せる。
つまり父親の榎津鎮雄は、厳格なクリスチャン。それを仮面とするなら、息子の嫁と不
倫関係になる部分が、シャドウということになる。主人公の榎津厳は、そのシャドウを、
そっくりそのまま引き継いでしまった。そしてそれが榎津厳をして、犯罪者に仕立てあげ
る原動力になった。
●いつのありのままの自分で
子育てをしていて、こわいところは、実は、ここにある。
親は仮面をかぶり、子どもをだましきったつもりでいるかもしれないが、子どもは、そ
の仮面を通して、そのうしろにあるシャドウまで見抜いてしまうということ。見抜くだけ
ならまだしも、そのシャドウをそのまま受けついでしまう。
だからどうしたらよいかということまでは、ここには書けない。しかしこれだけは言え
る。
子どもの前では、仮面をかぶらない。ついでにシャドウもつくらない。いつもありのま
まの自分を見せる。シャドウのある人間関係よりは、未熟で未完成な人間関係のほうが、
まし。もっと言えば、シャドウのある親よりは、バカで、アホで、ドジな親のほうが、子
どもにとっては、好ましいということになる。
(はやし浩司 ペルソナ 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て は
やし浩司 シャドウ 仮面 ペルソナ 結晶 はやし浩司 復讐するは我にあり シャド
ウ論 参考文献 河出書房新社「精神分析がわかる本」)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●韓国とK国
K国は韓国に対して、甘ったれている。
「好き勝手なことをしても、韓国は、何もしてこないだろう」と。
一方、韓国は日本に対して、甘ったれている。
「好き勝手なことをしても、日本は、何もしてこないだろう」と。
そしてK国は、韓国に対して、言いたい放題のことを言い、やりたい放題のことをして
いる。
韓国は、日本に対して、言いたい放題のことを言い、やりたい放題のことをしている。
ともにその根底にあるのは、被害妄想と「甘えの構造」。
たしかに韓国はK国に対して、何もしないだろう。
本音を言えば、「相手にしたくもない」。
南北統一についても、今、統一したら、それこそたいへんなことになる。
南北統一を望んでいないのは、当の韓国ということになる。
一方日本は韓国に対して、何もしないだろう。
本音を言えば、「相手にしたくもない」。
竹島の実効的支配を進めれば進めるほど、世界に向かって、「竹島は韓国の領土ではない」
と、宣言しているようなもの。
どうしてあんな島に、ヘリポートを作り、一般人を住まわせるのか?
その(無理)が、不自然!
不自然だから、無理をする!
世界の人は、だれしも、そう思う。
本当に自分の領土なら、もっと堂々としていればよい。
姑息なことをするから、かえって疑われる。
●で、シャドウ論
K国は、韓国のシャドウを受け継いでいるだけ。
わかるか?
表では正論をぶっているが、仮面の下では、姑息なことを繰り返している。
自動車にしても、「前から見れば、TOYOTA車、うしろから見れば、NISSAN車」。
そんな車を、平気で作っていた。
ほんの10年前の話である。
日本中の、それこそ津々浦々にまで産業スパイをはびこらせ、日本から奪えるものは、
何でも奪っていった。
その結果が今である。
ウソだと思うなら、韓国の現在の産業構造を見ればよい。
20〜40年前の日本の産業構造そのもの。
自動車、鉄鋼、電子産業などなど。
反対に韓国が独自に発展させた産業は、ひとつもない!
それをK国は、横から見ている。
そして韓国が生来的にもっていた(姑息さ)を、K国がそっくりそのまま引き継いでいる。
先に「K国は、韓国のあとを追いかけている」と書いたのは、そういう意味。
……と書くのは、書き過ぎ。
かなり過激。
私もそれをよくわかっている。
しかしこれだけは言える。
韓国の人よ、K国の人よ、なし崩し的に、ものごとを既成事実化するのは、やめよう。
「竹島」にしても、韓国の人よ、日本人がおとなしいからといって、それをよいことに、
言いたい放題のことを言い、やりたい放題のことをやるのは、やめよう。
いいか、韓国の人よ、K国が崩壊したら、竹島どころではなくなるぞ。
へたをすれば、38度線以北は、中国の領土となる。
「渤海国」になる。
わかっているのか。
そのとき日本に泣きついてきても、遅いぞ。
ここは冷静に!
この極東アジアで、だれが友人で、だれが友人でないか、少しは頭を冷やして考えろ。
謙虚になれ。
「自分たちの領土でない」ということを、心の奥で自覚しているからこそ、日本政府の
発言に、そのつどビクつく。
大騒ぎする。
それがいやなら、もっと正々堂々と、国際裁判所という「場」で、たがいに証拠をあげて
闘おうではないか。
どうしてそれがまずいのか?
何かまずいことでもあるのか?
以上、「竹島(独島)」問題を、シャドウ論をからめて、考えてみた。
どこか「木に竹を接ぐ」ようなエッセーになってしまったが、許してほしい。
竹島問題の記事を読んだとき、ふと「シャドウ論」が頭の中を横切った。
「K国は、韓国のシャドウを受け継いでいるだけ」と。
それでこんなエッセーになってしまった。
「?」と思われる人がいるなら、このエッセイを、「朝鮮問題」と、「シャドウ論」の2
つに、頭の中で分けて読んでほしい。
勝手な願いで、ごめん!
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 竹島問題 独島問題 シャドウ論 はやし浩司 ユング シャドウ論
実効的支配 なし崩し的支配)(以上、2009年3月記)
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●2011年11月25日
先のシャドウ論を書いた日付は、2009年3月になっている。
それから2年。
今は、2011年11月25日。
で、改めて自分の書いた原稿を読みなおす。
いろいろ考える。
「これはシャドウ論というよりは、サイコパス(性格障害)の問題ではないか」とか、「妄
想とどう区別するのか」とか。
●日韓問題
日韓問題にしても、すべてをシャドウ論で説明できるわけではない。
が、シャドウ論をあてはめてみると、韓国人のもつ精神的に二重構造性が、よく理解でき
る。
(1)「日本ごときに植民地にされた」という屈辱感。
(2)「自分たちの力で独立できなかった」という不完全燃焼感。
(3)さらに「南北に分断されたのも、もとはと言えば、日本の責任」という日本責任
論。
これら3者が混然一体となり、韓国人の心の別室の中に、押し込まれている。
それが時と場合に、表に出てくる。
よく「韓国人は政治と経済を、使い分けている」という。
政治で反日、経済では親日、と。
しかし使い分けているのではない。
民族意識はどこの民族にもある。
それが誇張されたのが、民族主義。
「我ら民族がもっともすぐれている」と。
韓国人のばあい、「日本ごときに、蹂躙(じゅうりん)された」という思いが、心の別室の
原点にある。
言い換えると、そう思いながら、実は日本人を徹底的に差別している。
(「差別」というよりは、「軽蔑」に近いが……。)
私はこれを「逆差別」と呼んでいる。
●二重構造性
それはともかくも、ユングのシャドウ論で考えると、韓国人がもつ精神の二重構造性が
よく理解できる。
と、同時に、私たちが個人がもつ二重構造性も、よく理解できる。
私たちは円滑な人間関係を保つために、常に、この二重構造的精神状態の中で生きてい
る。
冒頭にも書いたように、それが悪いというのではない。
それがあるからこそ、またそれができるからこそ、私たちは、この複雑な社会で生きるこ
とができる。
が、問題は、親子関係である。
ほとんどのばあい、子どものほうが、心の別室を作り、そこへ不平や不満をためこむ。
そしてそれが、時と場合に応じて、爆発する。
「こんなオレにしたのは、お前だア!」と。
そういう言葉が、10年たっても、20年たっても、口から出てくる。
もちろん子ども自身にはそれがわかっていない。
「抑圧」「心の別室」という言葉すら知らない。
加えて先にも書いたように、「心の別室」には、時効が働かない。
20年前、40年前の記憶がそのまま、生々しく残る。
また上書きされることもない。
楽しい思い出は、心の別室には入らない。
●よい子論
終わりに「よい子論」についても書いておきたい。
今、日本の子ども観、子育て観は、世界の標準から、かなりかけ離れつつある。
結論から先に言えば、たくましさがない。
またそうであることを、ほとんどの親たちは、「できのいい子」と誤解している。
たとえば従順で柔和で、やさしく、キバを抜かれてしまったような子どもほど、「よい子」
と位置づける。
またそういう子どもにしようと、あくせくしている。
昔風の、腕白で、自己主張が強く、たくましい子どもを、「できの悪い子」として、むし
ろ遠ざけたり、白い目で見たりする。
私の教室でも、そうである。
ときどき「うちの子には、この教室は合いません」と言って去っていく親がいる。
が、そういう親でも自分の子どもが、親の過干渉や過関心で萎縮していることに気づいて
いない。
親自身のものの考え方が権威主義的で、威圧的であることに気づいていない。
その結果として、むしろそういう子どもほど、心をゆがめやすい。
ゆがめやすいことは、ここに書いた「シャドウ論」を読んでもらえばわかるはず。
あるいはイプセンの『人形の家』を読んでみたらよい。
自らを「人形子」と呼んだ主人公が、精神の二重構造の中で、いかに苦しみもがいたか。
それがよくわかるはず。
本来、子どもは、そうであってはいけない。
++++++++++++++++++++++
しめくくりに、イプセンの『人形の家』について
書いた原稿をさがしてみる。
日付は2008年6月になっている。
(次号(明日号)につづく)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
MMMMM
m | ⌒ ⌒ |
( ̄\q ・ ・ p
\´(〃 ▽ 〃) /〜〜
\  ̄Σ▽乃 ̄\/〜〜/
\ : ξ)
┏━━┻━━━━┓
┃来月もよろしく┃
┃はやし浩司 ┃
┗━━━━━━━┛
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 28日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page027.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●11月23日(勤労感謝の日)
++++++++++++++++
朝から、あちこちへ電話をかける。
が、どこへかけても、応答なし。
それもそのはず。
今日は祭日。
会社は休み。
忘れていた!
++++++++++++++++
●仕事
ギリギリまでたまっていた仕事を、午前中に片づける。
ほっとする。
今どき「郵送?」と思う人もいるかもしれない。
しかし重要な原稿や書類類は、郵送。
あとで届いたかどうかの確認を入れる。
が、それでも郵送。
せっかく早めに仕事をすましたが、今日は郵便局も休み。
が、その分だけ、すっきりした。
午後からは、フリータイム!
●フリータイム
ということで、昼風呂。
午後12時ごろ、入浴。
そのあと昼ごはん。
ワイフがチャーハンを作ると言っていた。
私はそれを待ちながら、柿とキーウィを食べる。
柿は、もらいもの。
キーウィは、自家製。
今年は豊作。
今のところまだ野鳥の餌になっていない。
●寒い
現在、居間のヒーターは故障中。
先日修理に来てもらったが、「寿命です」と。
それで新しいヒーターを注文したが、今のところ連絡なし。
もう4日もたつ。
だから現在、居間の暖房は、こたつだけ。
寒い。
身の置き場がない。
●山荘へ
こういう祭日は、どこへ行っても、混雑している。
……ワイフはチャーハンを作ると言っていたが、その気配なし。
で、あれこれ無意味な会話がつづいたあと、午後は、山荘へ行くことにした。
その途中で何かを食べることにした。
ワイフは「ドーナツはどう?」と言った。
私は「NO!」と答えた。
しかし山荘も、寒い。
冬場だと、浜松市内より、気温もいつも、2〜3度低い。
●キャラバン隊
昨夜、浜松市内で、大きなボンネットバスを見かけた。
ボディに、大きな文字で、「福島」「キャラバン隊」と書いてあった。
あとの文字は読めなかった。
たぶん、福島県から、何かの運動のためにやってきたのだろう。
色は赤だったと思う。
大きなバスだったが、だれも乗っていなかったように思う。
で、それを見たとき、「みんな必死にがんばっているのだなあ」と思った。
はるばる福島から、浜松へ。
こんにちは!
●ホームレスの男
そう言えば、昨夜、ホームレスの男と並んで、パンを食べた。
たまたま並んだ。
私が菓子パンとミルク、ワイフがサンドイッチとコーヒーを食べていた。
そこへその男が、横に並んだ。
カウンター形式のパン屋だった。
男の横顔が、死んだ父そっくりだった。
懐かしさの混ざった親しみを覚えた。
まじまじと横顔をながめた。
が、声をかけようとしたその瞬間、その男が、何やら独り言を口にし始めた。
かなり大きな声だった。
意味はわからなかったが、別のだれかに話しかけているような言い方だった。
????
話しかけるのをやめた。
その男は小さな菓子パンを、大切そうに、時間をかけ、ゆっくりと食べていた。
●組織レス
私は若いころからホームレスのような生活をしてきた。
ホームレスというよりは、「組織レス」。
頼れる人は、だれもいなかった。
頼れる組織も、なかった。
だからというわけでもないが、ホームレスの人たちの心情がよく理解できる。
……というか、強い共感を覚える。
私たちが感ずる孤立感には、相当なものがある。
「孤独」ではない。
「孤立感」。
反対に、組織の中にどっぷりとつかりながら、安穏としている人たちを見ると、腹が立
つ。
地位だの肩書だの、そんなことで、あくせくしている人を見ると、バカに見える(失礼!)。
(反対に、彼らから見ると、私がバカに見えるにちがいない。
世に中には、地位や肩書でしか、人を判断しない人は多い。)
●勲章
これも負け惜しみか。
何もできず、社会の隅で細々と生きてきた。
しかし同時に今、地位や肩書の無意味さも、よくわかる。
言うなれば軍人の勲章のようなもの。
戦争がなければ、(もちろんないほうがよいにきまっているが)、ただの飾り。
そんなものをぶらさげ、「俺は価値のある人間」といくら声だかに叫んでも、だれも耳を貸
さない。
「あら、そう?」で終わってしまう。
が、その渦の中にいる人には、それがわからない。
ただひたすら貪欲に生きながら、それが人生と思い込んでいる。
●裸
今でも、私を笑う人は多い。
笑わなければ、自分の立場がない。
口では、「子ども相手に、いい仕事ですね」と言う。
しかしバカにしている。
以心伝心というか、それがよくわかる。
が、残念ながら、私自身は、自分をバカとは思っていない。
ラ・マンチャの男(=ドン・キ・ホーテ)とは思うことはあるが、バカとは思っていない。
価値判断の基準そのものが、ちがう。
もしそれでも私をバカと思うなら、ひとりで裸で生きてみたらよい。
社会のきびしさが、少しはわかるだろう。
その上で、私のことをバカと思えばよい。
●リチャード・マクドナルド
そう言えば、昨日も1人の中学生がこう言った。
「先生は、どうしてこんな仕事をしているの?」と。
中学生くらいになると、急速に世俗的な価値観を見つけるようになる。
よほど私のしている仕事が、バカに見えるらしい。
それがわかったから、あのマクドナルドの話をしてやった。
パソコンを開き、「はやし浩司 マクドナルド」で検索をかけてみた。
いくつかの原稿をヒットすることができた。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
マクドナルドの生き様を書いた。
それを読み聞かせてやると、その中学生は何を勘違いしたのか、こう言った。
「それも先生の自慢話?」と。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●リチャード・マクドナルド
投資に失敗し、自殺するのはバカげていると、私は書いた。
が、同時に、巨億の財産を築いたジョブズ氏を、私はうらやましいとは思わない。
世界のマスコミは、「世界の偉人」を失ったかのように書き立てている。
が、私はそうは思わない。
時流に乗っただけ。
もっとはっきり言えば、運がよかっただけ。
あの程度の苦労をしている人なら、いくらでもいる。
私もそうかもしれないし、あなたもそうかもしれない。
たとえばその一方で、こんな人がいたことを、あなたは知っているか。
リチャード・マクドナルドという人である。
13年ほど前に(1998年)、89歳でなくなったが、あのハンバーガーチェーンの「マ
クドナルド」の創始者と言えば、だれでも知っている※。
が、当のマクドナルド氏自身は、早い時期にレストランの権利を別の人物(レイ・クロッ
ク氏)に売り渡している。
それについて生前、テレビのレポーターが、「損をしたと思いませんか」と聞いたときのこ
と。
マクドナルド氏はこう答えている。
「もしあのまま会社に残っていたら、今ごろはニューヨークのオフィスで、弁護士や会計
士に囲まれてつまらない生活をしていることでしょう。
(こういう農場でのんびり暮らしている)今のほうが、ずっと幸せです」と。
(注※)リチャード・ディック・ジェイ・マクドナルド(Richard "Dick" J. McDonald、
1
909年生まれ、1998年死去)
●金権教団
要するに私たちは、意識的であるにせよ、無意識的であるにせよ、「金権」に毒されすぎ
ている。
そういうこと。
皮肉な言い方をすれば、全人類、オール「金権教団」というカルト教団の信者。
自由貿易体制(資本主義体制)の中ではしかたのないことかもしれない。
が、大切なことは、そういう世界にあっても、自分を見失わないこと。
見失ったとたん、たとえば「自殺」という道を選んでしまうかもしれない。
で、再び、ジョブズ氏の話。
たまたま彼は病気で死んだ(失礼!)。
巨億の富の蓄財にも成功した。
言うなれば、この世界では大成功者ということになる。
が、もし彼が、その事業で失敗していたとしたら、どうだろうか。
こんな仮定をするのは許されないことだということは、よく知っている。
が、もしその事業で失敗し、無一文になっていたとしたら……。
彼はどうなっていただろうか。
自殺していなかったと言えるだろうか。
現在の今、どう評価されていただろうか。
●結び
ずいぶんと回りくどい言い方をした。
が、私は最近、現在の自由貿易体制(資本主義体制)に、疑問を感じ始めている。
もちろんだからといって、共産主義がよいというのではない。
(どこかのBLOGに、「はやし浩司は共産主義者」と書いてあったが、それはウソ。
マルクス経済学など、見たことも読んだこともない。)
が、今の自由貿易体制(資本主義体制)は、個人的にみても、また国家的にみても、不公
平。
矛盾だらけ。
その人が老後を安楽に暮らせるのに、2億円の費用がかかるとする。
しかしこの世の中、60歳で貯金ゼロの人が50%もいる半面、何十億円もの蓄財に成功
した人もいる。
国にしても、そうだ。
そうたいして働きもしないアメリカ人が、世界の富をかき集めている。
何かが、おかしい。
狂っている。
私は経済学者ではないから、これ以上のことはわからない。
またどうあったらよいのかもわからない。
が、モヤモヤとしたものだけは、心の底に滞留している。
現代という世界では、ジョブズ氏のような人物を、「大成功者」と呼ぶのだが……。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●Uターン
山荘に向かったが、急にラーメンが食べたくなった。
ショッピングセンターから、Uターン。
その近くにあった、「幸楽苑」(ラーメン店)に入った。
こういう日は、熱いラーメンが恋しい。
「混んでないかしら?」とワイフが言った。
時計を見ると、午後2時50分だった。
「今なら、だいじょうぶだよ」と。
●ジョッブズ氏
先の原稿は、その前段部分と、後段部分を省略した。
だから誤解されるかもしれないので、補足しておく。
現在でいうパソコンにも、黎明期というのがあった。
1978〜80年ごろのことである。
そのころ日本も、いろいろなパソコンを世に送り出していた。
が、結果的にみると、日本は出遅れた。
当時の首相が、あの田中角栄氏。
土建部門は得意だったが、それだけの知的能力がなかった。
だからあれよあれよと思う間もなく、日本の電子産業は遅れていった。
すでにそのころから、オーストラリアでは、小学校レベルでコンピューターの授業を始め
ていた。
その結果が今であり、ジョッブズ氏ということになる。
アメリカにとっては偉人だが、どうして私たち日本人が、彼を賞賛しなければならないの
か。
私は右翼でも国粋主義者でもない。
しかし今の若い人たちをみていると、いったい何人かと言いたくなる。
……ということで、先の原稿を書いた。
その中で、リチャード・マクドナルド氏に触れた。
●昼寝
家に帰り、こたつに入ると、猛烈な睡魔に襲われた。
そのまま、居眠り。
気がつくと、1時間半も眠ってしまった。
いろいろな夢を見たが、今は、覚えていない。
何だったのか?
ワイフが言うには、私は寝言で歌を歌っていたという。
プレスリーの「♪I can't help loving you」だったという。
が、私は覚えていない。
●N先生
起きてから、N先生に電話をする。
久しぶり。
で、今度12月にネパールへ行くという。
8泊の旅行という。
今度の日曜日に会うことにした。
●世界経済
日本は今日は、休日。
しかし世界経済は、さらに大きく動き始めた。
毎日Bloombergと、ロイターNEWSに目を通す。
EUの金融危機について言えば、こうだ。
ユーロを増刷して危機を乗り切れと主張するフランス。
「そんなことをしたら、モラルハザードが起きてしまう」と反対するドイツ。
最終的には、ユーロを大増刷するしかないだろう。
もしそれがだめなら、EUの解体……というところまで進む。
どうであるにせよ、早く結論を出さないと、周辺国や新興国に被害が及ぶ。
数か月ならまだしも、こんな状態が半年とか1年もつづいたら、それこそ世界がめちゃめ
ちゃになってしまう。
社会不安から政情不安。
その先にあるのは、戦争!
●N證券
そう言えばN證券が、証券部門以外を、売却し始めたというニュースも伝わってきてい
る(11月23日、ロイターNEWS)。
20年以上つきあったN證券だが、今月(11月)のはじめ、すべての縁を切った。
その少し前のこと。
私はおそるおそる、しかしていねいに、こう聞いた。
「あのう、もし……、これはあくまでも仮定の話ですが、もしN證券が倒産ということに
でもなったら、私のもっている債権はどうなりますか?」と。
たいへん聞きにくい質問だった。
が、若い女子店員は、何を思ったか、その電話をそのまま上司の男性に回してしまった。
私もそこまで深刻に考えてはいなかった。
あくまでも「仮定」の話だった。
ところがその男性は、電話口に出るやいなや、神経質な声でこう言った。
「N證券はつぶれません。それでいいですか!」と。
その声を聞いて、「これはかなり、あぶないな!」と直感した。
それで縁を切ることにした。
●日本再生
日本政府は、当然、それを考えているにちがいない。
「それ」というのは、「大恐慌後の日本」。
しかしだいじょうぶか?
昨日は、国会議員のパソコン(サーバー)が、ウィルスに侵されていたというニュースも
伝わっている。
しかも全員。
「IDとパスワードが盗まれていた」と。
こんな状態で、国家機密が保持できるのか。
今ごろ、「それ」を考えて、いろいろな策が練られているはず。
その策が、どこかの国に筒抜けになっていた可能性が、きわめて高い。
ことの深刻さが、まるでわかっていない。
バカというか、アホというか……!
昔から日本はスパイ天国と言われている。
スパイを取り締まる法律さえない。
世界中のスパイが、日本国内で、したい放題のことをしている。
が、ここまでくると、もう言葉はない。
重要なことは、おかしな大国意識を捨て、お人好しをやめること。
みなが1人1人、緊張感をもつこと。
世界は、そんなに甘くないぞ。
今回も野田首相は、東南アジアでの何かの会議に出て、2兆円をばらまいてきた。
2兆円だぞ!
そんなお金があったら、東北の復興費用に回せ。
●11月23日夜
今日も終わった。
たいした成果もなく。
これといって、した仕事もない。
こうして1日、1日が過ぎていく。
ア〜アと思って、今日の日記はおしまい。
みなさん、明日からもがんばりましょう。
2011/11/23夜記
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●ドン・キ・ホーテ(2011年11月24日)【日本亡国論vs豆腐系人種】
++++++++++++++++
今朝は、ウォーキングから始まった。
30分間、時速6キロで歩いた。
全身にジワーッと汗をかいたところで、おしまい。
ウォーキングマシンから、降りた。
居間のヒーターは、目下故障中。
こういうときは自家発電しかない。
運動で体を温めるしかない。
称して「貧者の暖房法」。
++++++++++++++++
●ラ・マンチャの男(ドン・キ・ホーテ)
昨日、ラ・マンチャの男について少し書いた。
セルバンテスの『ラ・マンチャの男』である。
その原稿を探してみる。
2008年の1月に、BLOGにその原稿を
書いている。
++++++++++++++++++はやし浩司
●2月29日号(Magazine for Feb. 29th edition)
I will issue nr. 1011st magazine on Feb. 29th, which is this. I issued nr. 1000th
on the last Feb. 4th but it is funny that I dont feel anything special in my mind
that I have done something. Why not? I am stepping forward again to another goal of
nr. 2000th, but I shall follow my nose. I just keep writing, which is everything for
me.
+++++++++++++++++
この原稿は、2月29日号ということ
になる(2008年)。
去る2008年2月4日(月)に、電子マガジンは、
1000号になった。
だからこの2月29日号は、1011号という
ことになる。
つぎの1000号をめざして、また、
長い戦いが始まった。
しかし2000号は、目ざさない。
成り行きに任せる。
あとは行けるとこまで行く。
ただとても残念なことに、1000号
を超えたというのに、「何かをなし遂げた」という
実感は、ほとんど、ない。
どうしてだろう?
++++++++++++++++++
●雑感・あれこれ
今日は、2008年1月30日。
このところ、何かにつけて、忙しい。
たとえば、こうだ。
私のしたいことと、ワイフのしたいことが
同時にあったとする。
そういうときは、両方とも、する。
あるいは、1時間でもヒマができたら、
その1時間で、したいことをする。
けっして、あと回しにしない。
もちろん私の仕事もある。
+++++++++++++++++
●まじめに生きる
ときどき、まじめに生きるのが、バカらしくなる。
ほんとうは、そうであってはいけない。
それはわかっている。
しかしそのバカらしさと戦うのも、たいへん。
言うなれば、これは(内なる敵)との戦いということか。
ワイフも、ときどき、こう言う。
「あなたは、ラマンチャの男(=ドンキホーテ)みたい」と。
++++++++++++++++++
原稿をさがしてみた。
何と、6年前にも同じことを考えていた。
++++++++++++++++++
●私はドンキホーテ
セルバンテス(ミゲル・デーサーアベドラ・セルバンテス・1547〜1616・スペ
インの小説家)の書いた本に、『ドンキホーテ』がある。
『ラマンチャの男』とも呼ばれている。夢想家というか、妄想家というか、ドンキホーテ
という男が、自らを騎士と思いこみ、数々の冒険をするという物語である。
この物語のおもしろいところは、ひとえにドンキホーテのおめでたさにある。
自らを騎士と思いこみ、自分ひとりだけが正義の使者であり、それこそ世界をしょって立
っていると思いこんでしまう。
そして少し頭のにぶい、農夫のサンチョを従者にし、老いぼれたロバのロシナンテに乗っ
て、旅に出る……。
こうした「おめでたさ」は、ひょっとしたら、だれにでもある。
実のところ、この私にもある。
よくワイフは私にこう言う。
「あんたは、日本の教育を、すべてひとりで背負っているみたいなことを言うね」と。
最近では、「あなたは日本の外務大臣みたい」とも。
私があれこれ国際情勢を心配するからだ。
が、考えてみれば、私一人くらいが、教育論を説いたところで、また国際問題を心配し
たところで、日本や世界は、ビクともしない。
もともと、だれも私など、相手にしていない。
それはいやというほどわかっているが、しかし、私はそうではない。
「そうではない」というのは、相手にされていると誤解しているというのではない。
私は、だれにも相手にされなくても、自分の心にブレーキをかけることができない。
そういう意味で、ドンキホーテと私は、どこも違わない。
あるいはどこがどう違うのか。
よく、私塾を経営している人たちと、教育論を戦わすことがある。
私塾の経営者といっても、経営だけを考えている経営者もいるが、中には、高邁(こうま
い)な思想をもっている経営者も、少ないが、いる。
私が議論を交わすのは、後者のタイプの経営者だが、ときどき、そういう経営者と議論し
ながら、ふと、こう思う。「こんな議論をしたところで、何になるのか?」と。
私たちはよく、「日本の教育は……」と話し始める。
しかし、いくら議論しても、まったく無意味。
それはちょうど、街中の店のオヤジが、「日本の経済は……」と論じるのに、よく似ている。
あるいはそれ以下かもしれない。
論じたところで、マスターベーションにもならない。
しかしそれでも、私たちは議論をつづける。
まあ、そうなると、趣味のようなものかもしれない。
あるいは頭の体操? 自己満足? いや、やはりマスターベーションだ。
だれにも相手にされず、ただひたすら、自分で自分をなぐさめる……。
その姿が、いつか、私は、ドンキホーテに似ていることを知った。
ジプシーたちの芝居を、現実の世界と思い込んで大暴れするドンキホーテ。
風車を怪物と思い込み、ヤリで突っ込んでいくドンキホーテ。
それはまさに、「小さな教室」を、「教育」と思い込んでいる私たちの姿、そのものと言っ
てもよい。
さて私は、今、こうしてパソコンに向かい、教育論や子育て論を書いている。
「役にたっている」と言ってくれる人もいるが、しかし本当のところは、わからない。
読んでもらっているかどうかさえ、わからない。
しかしそれでも、私は書いている。
考えてみれば小さな世界だが、しかし私の頭の中にある相手は、日本であり、世界だ。
心意気だけは、日本の総理大臣より高い? 国連の事務総長より高い?
……勝手にそう思い込んでいるだけだが、それゆえに、私はこう思う。「私は、まさに、
おめでたいドンキホーテ」と。
これからも私というドンキホーテは、ものを書きつづける。
だれにも相手にされなくても、書きつづける。
おめでたい男は、いつまでもおめでたい。しかしこのおめでたさこそが、まさに私なのだ。
だから書きつづける。
(02−12−21)
● 毎日ものを書いていると、こんなことに気づく。
それは頭の回転というのは、そのときのコンディションによって違うということ。
毎日、微妙に変化する。
で、調子のよいときは、それでよいのだが、悪いときは、「ああ、私はこのままダメになっ
てしまうのでは……」という恐怖心にかられる。
そういう意味では、毎日、こうして書いていないと、回転を維持できない。
こわいのは、アルツハイマーなどの脳の病気だが、こうして毎日、ものを書いていれば、
それを予防できるのでは……という期待もある。
● ただ脳の老化は、脳のCPU(中央演算装置)そのものの老化を意味するから、仮に老
化したとしても、自分でそれに気づくことはないと思う。
「自分ではふつうだ」と思い込んでいる間に、どんどんとボケていく……。
そういう変化がわかるのは、私の文を連続して読んでくれる読者しかいないのでは。
あるいはすでに、それに気づいている読者もいるかもしれない。
「林の書いている文は、このところ駄作ばかり」と。
……実は、私自身もこのところそう思うようになってきた。ああ、どうしよう!!
●太陽が照っている間に、干草をつくれ。(セルバンテス「ドン・キホーテ」)
● 命のあるかぎり、希望はある。(セルバンテス「ドン・キホーテ」)
● 自由のためなら、名誉のためと同じように、生命を賭けることもできるし、また賭けね
ばならない。(セルバンテス「ドン・キホーテ」)
● パンさえあれば、たいていの悲しみは堪えられる。(セルバンテス「ドン・キホーテ」)
● 裸で私はこの世にきた。だから私は裸でこの世から出て行かねばならない。(セルバン
テス「ドン・キホーテ」
● 真の勇気とは、極端な臆病と、向こう見ずの中間にいる。(セルバンテス「ドン・キホ
ーテ」)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●2011年11月24日へタイムスリップ(日本亡国論)
9年前に書いた原稿を、こうして読みなおす。
ほぼ10年前。
当時の私は、認知症になるのが、何よりも恐(こわ)かった。
今も恐い。
しかし今のところ、何とかもちこたえている。
認知症だけは、頭のよしあしでは決まらない。
東大の薬学部長をしていたMZ先生だって、認知症になってしまった。
●日本の命運
この10月(2011)に始まった世界大恐慌。
今はまだ、その前哨戦に過ぎない。
あるいは「最後の悪あがき」?
今朝のニュース(Bloomberやロイター)を読むと、あのドイツまでおかしくな
ってきた。
中国も、つい先日までは「ソフト・ランディング」と言われていたが、ここにきて急に「ハ
ードランディング」という言葉が使われるようになった。
もしそうなると、日本経済に与える影響は、計り知れない。
最後に残された道は、ただひとつ。
EU中央銀行による、ユーロ(札)の大増刷(ユーロ共同債の発行)。
ユーロ(札)をばらまいて、急場をしのぐ。
ドイツのメルケル首相は、つい数日前までそれに反対していた。
が、昨日(24日)、10年物国債の入札で、応札額が募集額を35%も下回ったという。
つまり売れ残った。
わかりやすく言えば、ドイツ政府が「金を貸してくれ」と、世界に申し出た。
が、手にしたのは、そのうちの35%。
……この先、この日本は、どうなるのか?
ここまで考えて、思考停止。
日本の命運は、アメリカと中国の動向によって決まる。
●仕事がなかったら、屋台でも引け
ちょうど1か月ほど前、市内で弁当屋を経営しているFD氏(社長)と話した。
そのFD氏がこう言った。
「林さん、今に失業者が街にあふれるようになりますよ」と。
その弁当屋も現在、不況のドン底であえいでいる。
いくら値段を下げても、客の数は減っていくばかり。
「バブルのころは、1店舗だけで、1日、数百万も売り上げがあったのですがねエ」と。
が、今は、1店舗、店員を1人態勢にしても、経営が厳しいという。
……しかし『命のあるかぎり、希望はある』(セルバンテス)。
これをもじるとこうなる。
『希望がなくても、命があるかぎり、生きていくしかない』と。
私たちが考えるべきことは、「そのあとどうするか?」ということ。
大不況のあと、どう日本を立て直していくかということ。
その第一が、教育ということになるが、最近の子どもたちをみていると、絶望的と言わざ
るをえない。
草食系と言えば、まだよい。
豆腐系?
中身は、「ヤワ」。
国を支えていくという、気概すら感じられない。
「仕事がなかったら、屋台でも引け」と言いたいが、そんなことを言えば、かえって私の
方が奇人に思われる。
(私はしたぞ!
浜松に来たころ、画家の卵をしていたSJ君と2人で、SJ君の父親の描いた絵をリヤカ
ーに積み、団地で売って歩いたぞ。)
この先この日本が立ちなおるためには、あの野生臭をもう一度、取り戻すしかない。
そうでなくても、日本を一歩、外に出れば、そこは海千山千の世界。
猛獣が住む、野蛮世界。
そんな世界を相手に、これからこの日本は、どうやって戦っていくというのか。
何をするにも、資格、認可、許可、免許、登録……。
官僚制度によって、体中ががんじがらめに縛られている。
狭い世界でこぢんまりと生きていくには、よい。
しかしこんな日本を、どうして「自由な国」と言えるのか。
●曲がった信号
話を変える。
10月に、この浜松市を巨大な台風が直撃した。
それ以来、あちこちの四つ角の信号が、風で向きを変えた。
信号といっても、歩行者用の小さな信号。
ひどいところで、20〜30度、横を向いた。
そういう信号が、自宅から4キロほど離れたところにある西郵便局(このあたりの主要
郵便局)までに、3〜4か所もある。
が、すでに2か月近くもたつのに、手つかずのまま。
それに対して浜松市は、今度、補正予算を組んだ。
額は忘れたが、億単位。
名目は、「台風被害による……信号の……」とか何とか。
しかし、である。
そんな信号なら、脚立とペンチ一個で、直せるはず。
金槌で叩いても直せる。
どうして自分でそれをしないのか?
警察官でもよい。
市役所の役人でもよい。
つまりその(しないところ)が、(野生臭の欠落)ということになる。
豆腐系ということになる。
●よい子論
今、教育現場では、こんな珍事が続発している。
世の母親たちは、静かでおとなしい子どもほど、「できのいい子」と評価する。
反対に、腕白で、元気があり、自己主張のはげしい子どもを、「できの悪い子」と評価する。
そういう子どもをもつ母親は、きまってこう言う。
「みなさんに、迷惑をかけてすみません」と。
さらに私の教室でも、そういう腕白で、元気があり、自己主張のはげしい子どもがいた
りすると、母親のほうが「この教室はよくない」というレッテルを張ってしまう。
「うちの子がかえって萎縮してしまいます」などと言って、去っていく母親すらいる。
が、これはとんでもない誤解である。
もし誤解でないというのなら、では、いったい、どういう子どもを「よい子」と言うのか。
たぶんこの日本では、柔和で、やさしく、ハキがなく、おとなしく、追従的で、キバのな
い子どもを、「よい子」と言うのだろう。
しかしそんな子どもは、私のような団塊の世代から見ても、不気味。
世界の基準から見れば、さらに不気味。
映画に出てくる、平安時代の公家のようでもある。
顔中に「白粉(おしろい)」を塗りたくって、オホホホと口を押えて笑う。
女ではない。
男が、だぞ!
その結果、小学1年生で、いじめられて泣くのは男児。
いじめて泣かすのは女児。
そういう構図ができあがって、もう20年になる。
●異常な完ぺき主義
だからといって、私の生き様が正しいというのではない。
しかし今の日本人に求められているのは、まさに「ラ・マンチャの男」ではないのか。
この違和感。
この孤立感。
私がおかしいというよりは、世の中がおかしくなってしまった。
完ぺき主義も、ここまでくると異常。
繰り返すが、この日本では何をするにも、資格、認可、許可、免許、登録……!
この完ぺき主義が、やがてこの日本を滅ぼす。
官僚主義にもよい点はある。
しかしそれにも限度がある。
最後に7、8年ほど前、アメリカでタクシーに乗ったときの話を書く。
++++++++++++++++++はやし浩司
●日本は超管理型社会(2010年9月記)
最近の中学生たちは、尾崎豊をもうすでに知らない。
そこで私はこの歌(「♪卒業」)を説明したあと、中学生たちに「夢」を語ってもらった。
私が「君たちの夢は何か」と聞くと、まず1人の中学生(中2女子)がこう言った。
「ない」と。「おとなになってからしたいことはないのか」と聞くと、「それもない」と。
「どうして?」と聞くと、「どうせ実現しないから」と。
もう1人の中学生(中2男子)は、「それよりもお金がほしい」と言った。
そこで私が、「では、今ここに1億円があったとする。それが君のお金になったらどうす
る?」と聞くと、こう言った。
「毎日、机の上に置いてながめている」と。
ほかに5人の中学生がいたが、皆、ほぼ同じ意見だった。
今の子どもたちは、自分の将来について、明るい展望をもてなくなっているとみてよい。
このことは内閣府の「青少年の生活と意識に関する基本調査」(2001年)でもわかる。
15〜17歳の若者でみたとき、「日本の将来の見とおしが、よくなっている」と答えた
のが、41・8%、「悪くなっている」と答えたのが、46・6%だそうだ。
●超の上に「超」がつく管理社会
日本の社会は、アメリカと比べても、超の上に「超」がつく超管理社会。
アメリカのリトルロック(アーカンソー州の州都)という町の近くでタクシーに乗ったと
きのこと(2001年4月)。
タクシーにはメーターはついていなかった。
料金は乗る前に、運転手と話しあって決める。
しかも運転してくれたのは、いつも運転手をしている女性の夫だった。「今日は妻は、ほか
の予約で来られないから……」と。
社会は管理されればされるほど、それを管理する側にとっては便利な世界かもしれない
が、一方ですき間をつぶす。
そのすき間がなくなった分だけ、息苦しい社会になる。
息苦しいだけならまだしも、社会から生きる活力そのものを奪う。
尾崎豊の「卒業」は、そういう超管理社会に対する、若者の抗議の歌と考えてよい。(20
10年9月記)
●今日も始まった
……ということで今日も始まった。
株価は、予想通り、3・11大震災直後のそれを下回った。
今になって、東京証券取引所と大阪証券取引所を統合するという。
バカめ!
今さら、それをしてどうなる?
上場している外資企業など、10社もない。
みんなシンガポールへ逃げていってしまった。
理由は言わずとしれた、翻訳料。
資格、認可、許可、免許、登録に加えて、規則、規制。
それがふえればふえるほど、天下り先がふえる。
官僚たちは決まってこう言う。
「日本の公務員数は、欧米並みです」と。
が、文科省だけでも、天下り先機関は2000近くもある。
もしそういう機関の職員も含めたら、日本はギリシャ以上の公務員王国。
そういう現実が、まったくわかっていない!
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 日本亡国論 野生臭さ
の欠落 豆腐系人間 恐慌後の日本)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●11月24日(夜)
++++++++++++++++++++++++
今日、居間にガスストーブがついた。
工事に1時間半ほど、かかった。
そのあと試運転。
暖かい空気を手であおりながら、ワイフがうれしそうに言った。
「これで暖かいわね」と。
書斎は、私の「城」。
台所と居間は、ワイフの「城」。
……というのは、少しおおげさ。
しかし私はいつも、そう考えている。
++++++++++++++++++++++++
●薬害頭痛
「薬害頭痛」という言葉がある。
同じ頭痛薬を、慢性的に服用していると、頭痛薬そのものが頭痛を引き起こす。
それを「薬害頭痛」という。
肝臓が抗体を作るためではないか。
「薬」というのは、基本的には、毒物。
肝臓は、薬を毒物と判断する。
頭痛薬をのんで、頭痛になる。
が、こういう例は多い。
子どもの世界でよく経験するのが、ワークブック。
能力を超えたワークブック(問題集)を買ったために、勉強がそこでストップしてしまう
というようなケースは少なくない。
かえって成績がさがってしまう。
塾にしても、家庭教師にしても、そうだ。
家庭教育では、とくにこの点を注意する。
親というのは、どこの親でもそうだが、難しいワークブックを買い与えれば、それで子
どもの学力は伸びると考える。
しかも字数が多く、問題数が多ければ多いほど、「得」と考える。
が、問題集は、スーパーのバーゲン品とはちがう。
安ければ、それでよいというものではない。
大切なのは、達成感。
「やった」「できた」「やり終えた」という達成感。
その達成感が、子どもを前向きに伸ばす。
そのためワークブックは、簡単なものを選ぶ。
子どもの能力で、楽にできるものを選ぶ。
●失われた10年?
いまだに「失われた10年」という言葉を使う人がいる。
驚く。
実際には、「失われた20年」。
10年ではなく、20年。
この20年で、日本は、1980年代に戻ってしまった。
時計の針は、20年前で止まったまま。
ドイツのメルケル首相が、EU債の発行にひとり抵抗している。
「そんなことをすれば、モラル・ハザードが起きてしまう」と。
つまり安易に債務国を助ければ、そういった国々は、自らの努力をやめてしまう、と。
どこまでがんばれるかは、わからない。
しかしこういう根性のある政治家がいるドイツは、すばらしい。
少なくとも、この日本にはいない。
あちらでいい顔、こちらでいい顔……。
八方美人。
一本のスジ(筋)が通っていない。
なぜ今、この日本が韓国との間で、スワップ協定を結ばなければならないのか。
そのひとつ取りあげても、日本政府のふがいなさが、なさけない。
政府が言うように、「日本の進出企業が被害を受ける」というのであれば、その後、つまり
韓国がデフォルト(債務超過)した後、そうした企業を救済すればよい。
またそのほうが、安くつく。
どうしてそれくらいの危機意識を、日本はもたないのか。
日本よ、おかしな大国意識は、もう捨てろ!
お人好し外交は、もうやめろ!
日本は日本第一に考え、行動する。
ロイターですら「日本の凋落ぶり」をつぎのように書いている(2011/11/24)。
『……東京株式市場の値動きは、香港や上海などアジア市場の値動きにさえ振りまわされ
る従属的な状況。
もはやアジアのメイン市場との見方はされていない」(外資系投信)という』と。
++++++++++++++++++はやし浩司
●11月25日
日は替わって、今日は11月25日。
昨夜遅く、従弟(いとこ)と電話で話す。
柿を送ってくれた。
その礼の電話が、長くなった。
1時間ほど、話した。
しめくくりのエッセーを書くつもりだったが、そのまま就寝。
●仕事
EUの金融危機がどういう形で決着するにせよ、つぎは日本。
すでにこの3月、あの3・11大震災が起こる直前まで、日本の経済破綻は時間の問題と
ささやかれていた。
「可能性の問題ではない。時間の問題」と。
が、そこへあの3・11大震災。
とたん、「経済破綻」は、どこかへ消えてしまった。
が、それで問題が解決したわけではない。
今の今も、この問題はくすぶりつづけている。
あるいはいつなんどき、この日本へ飛び火してくるか、わからない。
だから従弟には、こう言った。
「どんなことがあっても、仕事を手放してはいけないよ。
一度手放したら、つぎの仕事はないよ」と。
●危機感
この浜松市を見ただけでも、危機感のなさには、これまた驚く。
あのバブル経済がはじけたあと、浜松市は「音楽の町」として、名乗り出た。
「楽器の町」が「音楽の町」になった。
豪華な楽器博物館もできた。
結構な話である。
が、そのあとがまずい。
浜松市からは、どんどんと工場が消えていった。
HONDA、SUZUKI、YAMAHA……。
名前だけは残っているが、工場はすべて、郊外の他の町へ。
そこで浜松市がつぎに打った手は、「花木の町」。
フルーツパークができた。
花博も開いた。
これまた結構な話である。
が、音楽や花木で、いくら稼げる?
外貨はいくら入ってくる?
この浜松市は、金持ちの道楽のようなことばかりしている。
で、最近は、市中心部の活性化。
が、笛吹けど、踊らず。
もしここに私が書いていることが「?」と思うなら、あのザザ・シティの中央館を見た
らよい。
エスカレーターに乗り、2〜5階を見たらよい。
西館にしても、ガラガラ。
地下にスーパーがあるが、ついでにその奥ものぞいてみたらよい。
広い空き部屋があって、中高校生たちが、テーブルを囲んでカードゲームをしている。
いったいどれだけの税金が無駄に使われたことやら!
……使われていることやら!
楽器博物館にしても、今では閑古鳥すら鳴いていない。
言うなれば楽器のガラクタ倉庫。
危機感のなさ、ここに極まれり!
書き忘れたが、建物だけは、超豪華。
どう豪華かは、皆さんの地域にある官製建物を見ればわかるはず。
エスカレーター付きの、大理石でできたラセン階段を下りたら、そこはスーパーだった!
以前は、100円ショップもあった(ザザ・シティ・西館)。
……笑うに笑えない話だが、それにしても不思議なのは、こうした失政を繰り返しなが
ら、だれも責任を追及しないこと。
だれも責任を取らないこと。
民主主義というのは、そういう意味では便利な制度だ。
民主主義を隠れ蓑に、いくらでも失敗をごまかせる。
●精神状態
……ということで、今朝の私の精神状態は、あまりよくない。
何を考えても、イラつく。
(見た目には、穏やかでやさしいが……。)
話題を変えよう。
冬になったので、庭に鳥の餌をまき始めた。
数日前からである。
ところが、である。
イヌのハナが、それを食べてしまう。
で、昨日、ハナの目を盗んで、こっそりと庭に餌をまいた。
ハナが食べにくいように、広く、まばらにまいた。
が、ふと気がつくと、ハナが右うしろに!
私が餌をまく手を、じっと見ていた。
●失敗
これはおとといの話。
中学生クラスで教えているときのこと。
ふと立ったとき、腸内ガスがブリブリと出てしまった。
本当にブリブリという音だった。
「しまった!」と思ったが、中3のS君が、それを聞いてしまった。
見ると、笑いを必死でこらえていた。
それがよくわかった。
で、私はS君にこう言った。
「何も言うな!」と。
が、その反対側にいる、Nさんも、同じように笑いを必死でこらえていた。
私がNさんの顔をのぞくと、そこで視線が合ってしまった。
私が気まずそうに顔をゆがめると、どういうわけか、Nさんも気まずそうに顔をゆがめた。
「あのなあ、君も、何も言うな!」と。
が、その直後、教室中の生徒が、どっと笑った。
前の席に座っていた生徒たちまで、こう言った。
「聞こえたよオ!」と。
……で、そのあと、私は教室の隅で、ずっと小さくなっていた。
何も言わず、黙っていた。
だれと目が合っても、その生徒は笑った。
教室が終わり、あとでワイフに聞くと、ワイフはこう言った。
「あんな大きな音だったから、みなに聞こえたにきまっているわよ。
ああいうときはね、だまって知らんぷりしているのがいちばんいいのよ」と。
それにしてもドジな話。
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 26日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page026.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【子どもの学力】(ウィキペディア百科事典より)(資料として保存)
++++++++++以下、ウィキペディア百科事典より抜粋++++++++++
●試験・調査の結果
●国際的機関による調査
●学習到達度調査 (PISA)
2007年12月に発表されたPISA2006の被験者(当時高校1年生)は、小学6年生からゆと
り教育を受けている世代として結果が注目されたが、
読解力は41か国中14位→56か国中15位へ(統計的には9〜16位グループ)、
数学的リテラシー(能力・知識)は41か国中6位→56か国中10位へ(同4〜9位)、
科学的リテラシーは41か国中2位→56か国中6位へ(同2〜5位)へ、
と全分野で順位を下げる結果となった。
また、同一問題による正答率の比較でも、前回を下回る問題の方が多かった。
PISA2003では、日本は読解力でレベル1あるいはレベル1未満の下位層の割合が増えてい
ること、及びフィンランドや韓国と比べて下位層の割合が高いことが問題視された。
さらにPISA2006では、数学でレベル5やレベル6といった上位層の割合が減っているなど、
新たな課題も判明した。
読解力の正答率の推移と比較では、2000年、2003年、2006年で共通に実施された(同一)
問題28題について、平均正答率は00年が65.2%、
03年が62.2%、06年59.5%であり、年ごとに低下していた。
正答率の比較では、06年は03年より上回った問題は6問、下回った問題は22問であった。
そのうち5ポイント以上、上回った問題が1問、下回った問題が6問だった。
科学的リテラシーの正答率の推移と比較では、2003年と2006年で共通に実施された(同一)
問題22題について、
平均正答率は03年が59.5%、
06年が60.1%であった。
正答率の比較では、06年は03年より上回った問題は13問、下回った問題は8問、変わら
ず1問であった。
そのうち5ポイント以上、上回った問題が1問、下回った問題が1問であった。
また、2000年と2006年の共通問題14題について、平均正答率は00年が65.7%であったの
に対して、06年は61.5%であり、00年に比べ約4.2%低下していた。
正答率の比較では、06年は00年より、上回った問題が9問、下回った問題が4問、変わら
ず1問だった。
そのうち5ポイント以上、上回った問題が0問、下回った問題が4問だった。
数学的リテラシーの正答率の推移と比較では、2003年と2006年で共通に実施された(同一)
問題48題について、
平均正答率は03年が56.1%、
06年が53.4%であり、約2.7%低下していた。
正答率の比較では、06年は03年より、上回った問題が8問、下回った問題が40問だった。
そのうち5ポイント以上、上回った問題が1問、下回った問題が10問だった。
国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)
2003年に国際教育到達度評価学会(IEA)が行った国際数学・理科教育動向調査
(TIMSS2003)
(TIMSS2003)
では、
小学4年生の算数の平均得点は1995年より3点低くなったが統計上の誤差を考慮すると有
意差はなかった。
小数第2位までのひき算「4.03−1.15」では、正答率が95年の87.3%から03年の72.3%へ
と15.0ポイントも下げている。
中学2年生の数学同一問題全79題の平均正答率は、1999年より4%低くなっていて、前回
より上がった問題が7問、下がった問題が72問となっている。
同時に行われた調査では、「数学の勉強が楽しい」かについて「強くそう思う」割合は9%
(前回は6%)と若干増えたものの、国際平均29%と比べると依然低いままであった。
また「そう思う」割合は30%(前回33%)、「そう思わない」「まったくそう思わない」割合
は61%(前回61%)、前々回(1995年)の54%より7%増えた。
国内機関による調査
小・中学校教育課程実施状況調査
2003年に国立教育政策研究所が行った平成15年度 小・中学校教育課程実施状況調査 (無
作為抽出により、1学年1教科1問題冊子当たり、1万6千人対象 小学校 1万6千人×4
教科×3冊子÷2(1人2教科)×1.1×2学年 中学校 1万6千人×5教科×3冊子÷3(1人
3教科)×1.1×3学年) では、多くの学年、教科で前回調査と同一の問題については、正
答率が有意に上昇した設問が、正答率が有意に下降した問題よりも多かった。
特に、小学生と中学3年生の上昇が顕著で、理科では前回より正答率が上昇した。
また、アンケートで「勉強が好き」「どちらかというと好きだ」と答えた子の割合は増加傾
向にあった。
高等学校教育課程実施状況調査
2007年4月13日に文部科学省が発表した教育課程実施状況調査 (6教科12科目。1科目
1問題冊子当たり 1万6千人対象。各教科問題冊子は二種類のうち一つ)国内においての
みの調査なので、国際比較はできない。
では、平成10年以降の指導要領で学んだ高校生はそれ以前の指導要領で学んだ高校生に比
べ、同じ内容の問題181問(総数657問中)において、145問は正答率が前回並、26問は
前回を上回り、10問は前回を下回るという結果になった。
内訳は、国語(上1、同4、下5)、
数学(上0、同11、下0)、
英語(上4、同16、下1)、
地歴公民(上10、同58、下0)、
理科(上11、同56、下4)で、前回を有意に上回る問題の多くは、地歴公民と理科に見ら
れた。
同時に学習についての意識面でも「勉強は大切」と答えた生徒の割合は増加するなど、学
力に関する肯定的な傾向もみられた。
大学入試センター試験
2006年1月に行われた大学入試センター試験では、現役受験生は中学3年生から2002年度
以降施行の学習指導要領で学んだ1期生となった。
しかし、この学習指導要領では学習内容が減っており、試験内容もそれを反映しているの
で、この成績によって以前との世代の学力の単純比較を行うことはできない。
他国との比較による議論
G8での順位比較(PISA2006)
国\科目
科学的リテラシー
読解力
数学的リテラシー
カナダ
347
ドイツ
131820
フランス
252323
イタリア
363338
日本
61510
ロシア
353934
イギリス
141724
アメリカ合衆国
29-35
このようにG8のほとんどの先進国は日本よりも順位が低いため、日本としては昔のよう
に「先進国に追いつき追い越せ」というスタイルを再現するよりも、先進国としての新し
いスタイルで子ども達に意欲をもたせるかを国民全体で考えることが重要であるとの指摘
がある。
保護者の意識
学力低下への不安から、子供を塾に通わせる意識は高くなっており、塾費用は増加してい
る。そのため、ゆとり教育の導入後、教育費を得るために母親が仕事をせざるを得なくな
り、親子の接触が減り、かえって家庭のゆとりがなくなることもある。
学力低下の要因としては、ゲームや漫画、ゆとり教育、教師の質の低下を挙げている。
『学力低下の原因(複数回答)では「ゲームやマンガなど誘惑の増加」53%がトップ。続い
て、「授業時間の削減」50%、「教師の質の低下」41%』
PISAにおける日本の成績
左側の数字は平均を500とした時の点数。()内の数字は順位。 上位10位までの結果につ
いてはOECD生徒の学習到達度調査を参照。
参加国数日本の参加学校数日本の参加生徒数数学読解力科学問題解決
PISA200032カ国135学科約5300人557(1)522(8)550(2)
PISA200341カ国・地域144学科約4700人534(6)498(14)548(1)547(4)
PISA200657カ国・地域185学科約6000人523(10)498(15)531(5)
PISA200965カ国・地域185学科約6000人529 (9)520 (8)539 (5)
●TIMSSにおける日本の成績
左側の数字は点数。()内の数字は順位。 上位10位までの結果については
国際数学・理科教育調査を参照。
小学校4年生
参加国数日本の参加学校数日本の参加生徒数算数理科
TIMSS1995597(3)574(2)
TIMSS200325カ国・地域150校4535人565(3)543(3)
TIMSS200737カ国・地域148校4487人568(4)548(4)
中学校2年生
参加国数日本の参加学校数日本の参加生徒数数学理科
TIMSS1995605(3)571(3)
TIMSS199938カ国・地域140校4745人579(5)550(4)
TIMSS200346カ国・地域146校4856人570(5)552(6)
TIMSS200750カ国・地域146校4312人570(5)554(3)
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/37/img6c2d39c7zik5zj.
jpeg" width="991" height="1388" alt="img231.jpg">
jpeg" width="991" height="1388" alt="img231.jpg">
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/38/img24e07281zikbzj.
jpeg" width="991" height="684" alt="img232.jpg">
jpeg" width="991" height="684" alt="img232.jpg">
++++++++++以上、ウィキペディア百科事典より抜粋++++++++++
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【思考回路(プロセス)と思考力】
Independent Thinker論
++++++++++++++++++++
思考回路とは何か?
ひとつの例として、私は田丸謙二先生のことを思い浮かべる。
田丸謙二先生は、50歳をすぎてから独学で中国語を学んだ。
いつも手紙で、「50歳を過ぎてからの独学はたいへんです」と書いていた。
その田丸謙二先生は、そのころよく中国へ行った。
年に数回という頻度ではなかったかと記憶している。
大の中国びいきで、そのことは田丸謙二先生のホームページを見てもわかる。
ホームページのトップには敦煌(とんこう)で撮った写真。
随所に、中国での写真が飾ってある。
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/69/img081e73a5zik3zj.
jpeg" width="593" height="398" alt="tonnkou.jpg">
jpeg" width="593" height="398" alt="tonnkou.jpg">
(田丸謙二先生撮影)
が、ここからが田丸謙二先生のすごいところ。
田丸謙二先生は、そのあと中国化学界(南京)の総会で、記念講演をしている。
もちろん中国語で。
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/68/img46c4872ezik3zj.
jpeg" width="554" height="464" alt="中国化学会.jpg">
jpeg" width="554" height="464" alt="中国化学会.jpg">
(田丸謙二先生のHPより転載)
つまりこれが思考回路である。
先生の脳の中には、そういう思考回路ができている。
「学ぶ」→「ものにする」という思考回路。
さらに詳しく書けば、「学びたい」→「どう学ぶか」という思考回路。
そうした思考回路ができている。
できているからこそ、中国科学院での記念講演ができた。
私たちにとって重要なのは、この思考回路。
情報ではなく、思考回路。
この思考回路をどう頭の中で作っていくか。
が、それは実は、乳幼児期から始まっている。
乳幼児期から形成される。
おとなになってからでは、遅い。
思考回路というのは、そういうもの。
脳科学の世界では、「思考プロセス」ともいう。
意味はややちがうが、「回路」のあるなしで、その人のものの考え方、さらには生き様は大
きく異なってくる。
田丸謙二先生を例にあげるまでもない。
++++++++++++++++++++
●愚劣な情報
先週、何かのテレビ番組を見た。
5分程度のことだったので、内容は断片的なもの。
その中で、司会者が、「歯磨きをするのは、食事のあとすぐあとがいいか、それともしばら
くしてからのほうがいいか」と、質問していた。
食後直後?
それとも食後、しばらく間をおいてから?
私も瞬間あれこれと考えたが、専門家と言われる人が説明を始めたところで、自分の書
斎に入った。
●歯磨き
歯磨きなど、いちいちそこまで考えてする人はいない。
食べたものにもよる。
昼食か、夕食かにもよる。
場所にもよる。
レストランで1〜2時間かけてディナーを楽しむときもある。
甘いものを食べれば、口の中が何となくねばっこくなる。
そういうときは、すぐ磨く。
しかし仕事中のときは、そうはいかない。
歯磨きというのは、それができるとき、その場ですればよい。
いくら早くしたくても、できないときがある。
ばあいによっては、家に帰ってからということもある。
直後がよいとか、悪いとか、そんなことを議論するほうが、ナンセンス。
●150万時間
もしこんな情報に振り回されていたら、頭の中が混乱する。
それだけが情報ではない。
磨き方。
歯ブラシの選び方、などなど。
ほかにもいろいろある。
それこそ重箱の底をほじり始めたら、きりがない。
つまりこれが、無用の情報。
……とまでは言えないにしても、テレビで全国に流さなければならないような情報ではな
い。
仮に視聴率が5%として、1億2000万人の中の、約600万人が見る。
その人たちが15分間、その番組を見たとするなら、延べ150万時間。
日本人全体で、150万時間を無駄にしたことになる。
(人間の一生を、80年とするなら、70万時間。
2人の人が、一生、同じ番組を繰り返し見たとすると、140万時間になる。)
●批判精神
幸い私は、批判精神が旺盛。
いつごろから私がそうなったかはわからないが、小学1、2年生のときには、そうなって
いた。
前にも書いたが、小学3年生のときのこと。
私の家に、10数人の人たちが集まっていた。
「M・倫理研究会」という団体に、私の父が入っていた。
その団体が、定期的に各家庭を回って、座談会のようなものを開いていた。
私もそのとき、それを聞いていた。
その中で、中央に座った男性が、「親の因果、子にたたり……」というような話をした。
で、その直後私に向かって、その男性が、こう聞いた。
「そこにいるぼく、君はどう思うかね?」と。
が、私はこう言った。
「そんなもの、ありません」と。
「たたりなどない」という意味で、そう言った。
まわりの人たちが、シーンとしたというか、ざわめいたのを脳のどこかで記憶している。
●自己実現のための思考回路
このことは、子どもたちを観察していると、よくわかる。
思考回路のできている子どもは、自分の思考回路に沿って、ものを考え、行動する。
どうすれば自分の夢を実現させることができるか、それをよく知っている。
発達心理学の世界では、それを「自己実現」という言葉を使って説明する。
自分の夢や希望を、やがて目的に昇華し、その目的に向かって努力していく。
その「力」を、「自己実現能力」という。
たとえば昔、宇宙飛行士になりたいと言っていた子どもがいた。
たまたまペットボトルのロケット実験で、市長賞を取ったこともある。
中学生のときのことだった。
で、最近その消息を聞くと、あのNASDAで、本当に宇宙ロケットを設計しているとい
う。
その子どもは自分の思考回路に従い、自分の夢を実現した。
その思考回路については、たびたび書いてきた。
原稿を探してみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【思考回路】
●夢や希望を育てる
________________________________________
たとえば子どもが、「花屋さんになりたい」と言ったとする。そのとき重要なことは、親
は、それに答えて、「そうね、花屋さんはすてきね」「明日、球根を買ってきて、育てて
みましょうか」「お花の図鑑を買ってきましょうか」と、子どもの夢や希望を、育ててや
ること。
が、たいていの親は、この段階で、子どもの夢や希望を、つぶしてしまう。
そし
てこう言う。
「花屋さんも、いいけど、ちゃんと漢字も覚えてね」と。
●子どもを伸ばす三種の神器
________________________________________
子どもを伸ばす、三種の神器が、夢、目的、希望。
しかし今、夢のない子どもがふえた。
中学生だと、ほとんどが、夢をもっていない。
また「明日は、きっといいことがある」と
思って、一日を終える子どもは、男子30%、女子35%にすぎない(「日本社会子ども
学会」、全国の小学生3226人を対象に、04年度調査)。
子どもの夢を大切に、それを伸ばすのは、親の義務と、心得る。
●役割混乱
________________________________________
子どもは、成長するにつれて、心の充実をはかる。
これを内面化というが、そのとき同時に、「自分らしさ」を形成していく。
「花屋さんになりたい」と言った子どもは、いつの間にか、自分の周囲に、それらしさを
作っていく。これを「役割形成」という。
子どもを伸ばすコツは、その役割形成を、じょうずに育てていく。
それを破壊すると、子どもは、「役割混乱」を起こし、精神的にも、情緒的にも、たいへん
不安定になり、混乱する。
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/++++++++++++++++はやし浩司
●思考プロセス(回路)
________________________________________
しかし重要なのは、「思考プロセス」。
幼いときは、「花屋さんになりたい」と思ってがんばっていた子どもが、年齢とともに、今
度は、「看護婦さんになりたい」と言うかもしれない。
しかし幼いときに、花屋さんになりたいと思ってがんばっていた道筋、あるいは思考プロ
セスは、そのまま残る。
その道筋に、花屋さんにかわって、今度は、看護婦が、そこへ入る。
中身はかわるかもしれないが、今度は、子どもは、看護婦さんになるために、がんばり始
める。
●進学校と受験勉強
________________________________________
たいへんよく誤解されるが、「いい高校」「いい大学」へ入ることは、一昔前までは、目
的になりえたが、今は、そういう時代ではない。
学歴社会を支える、権威主義社会そのものが崩壊してしまった。
親は、旧態依然の考え方で、「いい大学へ入ることが目的」と考えやすいが、子どもにとっ
ては、それは、ここでいう目的ではない。
「受験が近いから、(好きな)サッカーをやめて、受験塾へ行きなさい」と子どもを追うこ
とで、親は子どもの夢をつぶす。
「つぶしている」という意識すらないまま……。
●これからはプロの時代
________________________________________
これからはプロが生き残る時代。
オールマイティなジェネラリストより、一芸にひいでたプロのほうが、尊重される。
大手のT自動車の面接試験でも、学歴不問。
そのかわり、「君は何ができるか?」と聞かれる時代になってきている。
大切なことは、子どもが、生き生きと、自分の人生を歩んでいくこと。
そのためにも、子どもの一芸を大切にする。「これだけは、だれにも負けない」というもの
を、子どもの中につくる。
それが将来、子どもを伸ばす。
●大学生の問題
________________________________________
現在、ほとんどの高校生は、入れる大学の入れる学部という視点で、大学や学部を選ん
でいる。
もともと、勉強する目的すらもっていない。
そのため、入学すると同時に、無気力になってしまったり、遊びに夢中になってしまう大
学生が多い。
燃え尽きてしまったり、荷おろし症候群といって、いわゆる心が宙ぶらりんになってしま
う子どもも多い。
当然、誘惑にも弱くなる。
●自我の同一性と役割形成
________________________________________
子どもをまっすぐ伸ばすためには、(子どもがしたがっていること)を、(現在している
こと)に一致させていく。
そしてそれを励まし、伸ばす。親の価値観だけで、「それはつまらない仕事」「そんなこと
は意味がない」などと、言ってはいけない。
繰りかえすが、子どもが、「お花屋さんになりたい」と言ったら、すかさず、「それはすて
きね」と言ってあげる。
こういう育児姿勢が、子どもを、まっすぐ伸ばす基礎をつくる。
●結果はあとからついてくるよ!
________________________________________
大切なことは、今できることを、懸命にすることだよ。
結果は、あとからついてくる。
またその結果がたとえ悪くても、気にしてはいけないよ。
ぼくたちの目的は、失敗にめげず、前に進むことだよ。
あの「宝島」を書いたスティーブンソンは、そう言っているよ。
●子育ては工夫
________________________________________
子育ては工夫に始まって、工夫に終わる。
わかりやすく言えば、知恵比べ。
この知恵比べによって、子どもは、伸びる。
が、それだけではない。
何か問題が起きたときも、同じ。
家庭環境は千差万別。状態も状況も、みなちがう。
子どもについて言うなら、性格も性質も、みなちがう。
能力もちがう。そんなわけで、「子育ては知恵くらべ」と心得る。
この知恵比べが、前向きにできる人を、賢い親という。
●内政不干渉
________________________________________
たとえ親類でも、兄弟でも、内政については、干渉しない。
相手が相談をもちかけてきたときは別として、こちらからあれこれアドバイスしたり、口
を出したりしてはいけない。
相手を説教するなどということは、タブー中のタブー。
ばあいによっては、それだけで、人間関係は、破壊される。
それぞれの家庭には、人には言うに言われぬ事情というものがある。
その事情も知らないで、つまり自分の頭の中だけで考えてものを言うのは、たいへ
ん危険なことである。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●思考回路
よく私はこんな説明をする。
私はこうしてものを書くのが好きだから、何か問題が起きると、すぐ、文章によってそれ
を解決しようとする。
また文章でないと、落ち着かない。
そのため口約束というものを、信用しない。
が、たとえば暴力団と呼ばれる人たちはどうだろうか。
本当のところそういう人たちがどういう思考回路をもっているか、私には、わからない。
わからないが多分、何か問題が起きると、暴力によって解決しようとするかもしれない。
それが思考回路(厳密には、行動回路)ということになる。
で、この思考回路は、人によってみなちがう。
問題への対処の仕方が、みなちがう。
もちろん夢や希望をもったとき、その実現方法も、みなちがう。
人それぞれだが、ではあなたはどうか?
あなたにも、その思考回路があるはず。
●田丸謙二先生
同じ「学ぶ」といっても、私と田丸謙二先生とは、ちがう。
たとえば私は、今、外国語をマスターしたいという気持ちは、ほとんどない。
ないから、それを実現しようというエネルギーがわいてこない。
もしそれだけのエネルギーと時間があれば、もっとほかの面に向けたい。
が、田丸謙二先生は、研究者として、若い時から、そういう思考回路をもっていた。
並大抵のチャレンジ精神ではない。
未開の分野を切り開いていく。
そのことは、日本触媒学会の会長、国際触媒学会の会長という経歴をみてもわかる。
40年前の昔、「触媒」に目を向ける学者は少なかった。
が、今や、触媒なしでは、科学の世界は成り立たないほど、触媒は私たちの日常生活に溶
け込んでいる。
もう一言、付け加えるなら、田丸謙二先生のような研究者がいたからこそ、この分野では
日本は世界のトップを走っている。
それがチャレンジ精神であり、それを実現していく道筋が、思考回路ということになる。
●終わりに……
そこで私やあなたには、どんな思考回路があるか。
それを少しだけ、探ってみるとおもしろい。
あるいはあなたの子どもでもよい。
たとえば何かの夢や希望があったとする。
問題でもよい。
あなたはそれを、どのような形で実現したり、解決したりするだろうか。
が、中には不幸にして、その思考回路そのものがない人(子ども)もいる。
その時々の波にのまれ、のまれるまま、右往左往する。
子どもにたとえるなら、夢や希望にしても、とんでもないものをもったりする。
「ぼくは、ゴレンジャーになりたい」とか、など。
最後に私が心配するのは、今、その思考回路のない人(子ども)が、多いということ。
考え方や行動に、一本の筋が通っていない。
発達心理学風に表現すれば、自我の確立に失敗し、役割混乱を起こしている。
そしてそのままおとなになり、社会人になる。
だからいつもこう悩む。
「私とは何か?」と。
いつも心のどこかに不完全燃焼感をもち、その日その日を、ただ何となく過ごす……。
ここでいう(思考回路)には、そういう問題も含まれている。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教
育評論 はやし浩司 思考回路 思考プロセス 役割混乱 不完全燃焼感 はやし浩司
自我の確立 自我の同一性 はやし浩司 田丸謙二先生 Independent thinker)
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●『休息を求めて疲れる』"Men tire themselves in pursuit of rest."
Laurence Sterne(ローレンス・スターン:1713〜1768)の言葉という(「英語で読む世
界の名言サイトより)。
『イギリスの小説家。奇抜な発想とスタイルを持った作品が多い』(同サイト)とある。
が、ネットで調べてみると、Florence Nightingale(フロレンス・ナイチンゲール)の
言葉という説もある。
あのナイチンゲール(1820−1910)である。
生年月日でみるかぎり、Laurence Sterneのほうが先ということになる。
……しかし何よりも驚くのは、こうした調べが、私の小さな書斎で、しかも瞬時にでき
てしまうということ。
以前は、図書館まで出かけ、1日仕事だった。
で、私はこの言葉を、1970年に、オーストラリアで知った。
オーストラリアの友人の、いつもの口癖だった。
それで耳に残った。
が、訳は私がつけた。
『休息を求めて疲れる』。
もっともだれが訳しても、同じ訳になる。
Men tire themselves in pursuit of rest.……「直訳すれば、人は休息の追求の中で、自
らを疲れさせる」ということになる。
が、これではおかしい。
だから「休息を求めて疲れる」と。
20年ほど前に書いた本の中で、この格言を紹介した。
が、その訳で検索をかけてみると、460万件近くもヒットした。
が、何よりもすばらしいのは、こうして過去と現在が、ひとつの格言を通してつながる
こと。
「あのとき、あの人が言った言葉は、Laurence Sterneの言葉だったのだ」と。
繰り返しになるが、この格言は、愚かな生き方の代名詞のようにもなっている。
言外で、「そういう生き方をしてはいけませんよ」と。
今日はこの言葉を、肝に銘じたい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 休息を求めて疲れる
はやし浩司 休息を求めて、疲れる)
+++++++++++++++++
10年ほど前、中日新聞に書いた
コラムを紹介する。2011/11/22
+++++++++++++++++
●「休息を求めて疲れる」。
イギリスの格言である。愚かな生き方の代名詞にもなっている格言でもある。
「いつか楽になろう、なろうと思っているうちに、歳をとってしまい、結局は何もできな
くなる」という意味である。「やっと楽になったと思ったら、人生も終わっていた」と。
ところでこんな人がいる。
もうすぐ定年退職なのだが、退職をしたらひとりで、四国八八か所を巡礼をしてみたい、
と。
そういう話を聞くと、私はすぐこう思う。「ならば、なぜ今、しないのか?」と。
私はこの世界に入ってからずっと、したいことはすぐしたし、したくないことはしなかっ
た。
名誉や地位、それに肩書きとは無縁の世界だったが、そんなものにどれほどの意味がある
というのか。
私たちは生きるために稼ぐ。稼ぐために働く。これが原点だ。
だから○○部長の名前で稼いだ100万円も、幼稚園の講師で稼いだ100万円も、10
0万円は100万円。
問題は、そのお金でどう生きるか、だ。
サラリーマンの人には悪いが、どうしてそうまで会社という組織に、義理立てをしなけれ
ばならないのか。
未来のためにいつも「今」を犠牲にする。
そういう生き方をしていると、いつまでたっても自分の時間をつかめない。
たとえばそれは子どもの世界を見ればわかる。
幼稚園は小学校の入学のため、小学校は中学校や高校への進学のため、またその先の大学
は就職のため……と。社会へ出てからも、そうだ。
子どものときからそういう生活のパターンになっているから、それを途中で変えることはできな
い。
い。
いつまでたっても「今」をつかめない。つかめないまま、人生を終わる。
あえて言えば、私にもこんな経験がある。
学生時代、テスト週間になるとよくこう思った。「試験が終わったら、ひとりで映画を見に
行こう」と。
しかし実際そのテストが終わると、その気力も消えてしまった。
どこか抑圧された緊張感の中では、「あれをしたい、これをしたい」という願望が生まれるもの
だが、それから解放されたとたん、その願望も消える。
だが、それから解放されたとたん、その願望も消える。
先の「四国八八か所を巡礼してみたい」と言った人には悪いが、退職後本当にそれをした
ら、その人はよほど意思の強い人とみてよい。
私の経験では、多分、その人は四国八八か所めぐりはしないと思う。退職したとたん、そ
の気力は消えうせる……?
大切なことは、「今」をどう生きるか、だ。
「今」というときをいかに充実させるか、だ。明日という結果は明日になればやってくる。
そのためにも、「休息を求めて疲れる」ような生き方だけはしてはいけない。
(以上、中日新聞のコラムより)
++++++++++++++++++はやし浩司2011/11/22
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 23日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page025.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【BW教室より・カタカナ(年中児)の学習】
満4・5歳(4歳6か月)を境に、幼児は急に文字に興味をもち、自らそれを学ぼうとし
ます。この時期をうまくとらえ、指導もしくは種まきをしておくと、子どもは自然な形で
(=無理をしなくても)、文字を覚えてしまいます。「文字は楽しい」という印象作りを大
切に! そういう目的をもって、今日のレッスンを進めました。
(1)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/zzjE95hAvas"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/4_NMNyhB3-c"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/yMILqUmM2eo"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(4)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/c1IU0MW4KRs"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●悪魔の論理(強者の合理主義vs弱者の論理)
++++++++++++++++++++++
抑圧が長くつづくと、心は悪魔的になる。
サイコパスもそのひとつだが、それ以前の段階で、
ものの考え方がゆがんでくる。
たとえばこんな例で考えてみよう。
たとえば今、あなたは失業しているとする。
働いても、働いても、たいした収入にはならない。
子どももいる。
家計は火の車。
明日の食費すらままならない。
もしそんな状態が、1年から10年単位でつづいたとする。
こんな状態で、ものの考え方を正常に保つのは不可能。
ひがみ、ねたみ、不平、不満、怒り、不安、心配……。
これらが混然一体となって、あなたの心をゆがめる。
が、これは個人にかぎらない。
国全体が、そうなることもある。
たとえば北朝鮮。
先のワールドカップ3次予選では、日本側チーム、サポーターは、
「冷遇」(ニュース各社)されたという。
どう冷遇されたかは、すでにみなさんご存知の通り。
それに対して、北朝鮮が、猛然と反論してきた。
「冷遇したのは、日本側」と。
読めば読むほど、ガラスに爪をたて、それをかきむしるような不快感が充満してくる。
しかしこれが「悪魔の論理」である。
国も心がゆがむと、そこまでゆがむ。
MSNの記事を、そのまま紹介する。
+++++++++++++以下、MSN記事より++++++++++++++
●「まるで監獄だった」北が日本での待遇を逆非難
北朝鮮・平壌で15日に行われたサッカーワールドカップ(W杯)予選の日朝戦で、日
本代表が空港で足止めされるなど異例の対応を受けたと、日本メディアが報じたことに対
し、北朝鮮は機関紙を通じて9月に日本であったW杯予選での北朝鮮代表への待遇を挙げ、
「まるで監獄だった」と逆非難した。
ラヂオプレス(RP)によると、朝鮮労働党機関紙「労働新聞」は18日、ウェブサイ
トで、北朝鮮選手に対して日本警察がトイレまで付いてきたりしたとし、「まるで監獄に行
ってきたようだ」との選手の話を紹介した。入国時にチョコレートを没収されたとも訴え
たが、真偽は全く不明だ。
日本サポーターは日の丸などの応援グッズを没収され、観客席の一角に押し込まれる"冷
遇"を受けたが、「選手団も応援団、取材団も平壌に来て、商店をはじめ行きたいところに
自由に行った」と事実に反する主張を繰り広げている。
+++++++++++++以上、MSN記事より++++++++++++++
●相手にしない
こういう国は、相手にしないほうがよい。
言いたいように言わせておけばよい。
こちらが本気になればなるほど、相手の思うつぼ。
で、ここでは話を、もう一歩、先に進める。
●まともでない国
経済学がそのつど、かならずといってよいほど、デッドロックに乗り上げるのは、悪魔
の論理を計算に入れていないから。
つまり経済学は、(まともな論理)を基盤にし、その上に成り立っている。
が、世界には、(まともでない国)のほうが、多い。
北朝鮮もそうだが、たとえばスペインも症状は軽いが、そのひとつ。
多額の国家負債をかかえ、明日にでもデフォルト(債務不履行)を起こすかもしれない。
が、スペイン自体は、どこか居直っている?
一部の人たちは都市で、緊縮予算反対などと騒いでいるが、あくまでも一部。
たいはんの人たちは今日も裏通りで、バックギャモンに興じている。
それに対して、ドイツやフランスが、大あわて。
表向きはスペイン救済を口にしているが、実際には、自分たちの救済。
「国」ではなく、「一家」にたとえてみると、それがよくわかる。
●アンダーワールド
あなた(スペイン)は年収の何倍もの借金をかかえている。
明日の生活を維持するためには、さらに借金を重ねるしかない(=国債を発行するしかな
い)。
利息も、バカにならない。
この先、増収分よりも、利息のほうが多くなる。
つまり働いても働いても、そこはアリ地獄。
もうこうなったら、自己破産(デフォルト)するしかない。
自己破産して、借金をチャラにする。
その上で、もう一度、一家を立て直す。
が、金を貸している銀行(ドイツ銀行)は、そうでない。
もしここでチャラにされたら、元も子もなくなる。
相手が個人なら、財産の没収ということもできるが、相手が国ではそれもできない。
スペインの半分の領土を、ドイツに渡せとも言えない。
本当に、元も子もなくなる。
つまり(まともな論理)を振りかざすドイツと、(まともでない論理)を振りかざすスペ
イン。
ここで両者がたがいに、はげしく衝突する。
が、その衝突を裏で支えるグループがある。
それが23%とも言われる、失業中の若年労働者たち。
この人たちにしてみれば、もうこれ以上、失うものは何もない。
このグループが、「力」で、政治を裏で操ろうとする。
つまりここで悪魔の論理が働く。
まともな経済学の論理が通じない、いわば、アンダーワールドの世界。
このアンダーワールドの世界が、こわい。
●弱者の論理
悪魔の論理をさらに理解するためには、弱者の論理を知らなければならない。
弱者には弱者独特の論理がある。
またその上で、ものを考える。
++++++++++++++++++はやし浩司
2006年6月に書いた原稿より。
++++++++++++++++++はやし浩司
【主義の限界】
++++++++++++++++++++
なぜ、共産主義も、資本主義も、そして
民主主義も、最後の最後のところで、
行きづまってしまうのか?
わかりやすく言えば、そのどれも、
最後の、あと一歩というところで、
ほころびを生じてしまう。ボロボロに
なってしまう。
よい例が、今のイラク。民主主義は最善
とばかり、それを押し付けようとする、
アメリカ。
しかしその民主主義とやらを、イラクの
人たちは、どうやら別の目で見ている?
なぜか?
++++++++++++++++++++
●教育論の限界
教育論という「論」がある。それはそれとして、その「論」にも、限界がある。いくら
高尚な教育論を説いたとしても、そこには、一定の限界がある。
こんな例で考えてみよう。
私たちが「子ども」というときは、子ども全体をさす。1人ひとりの子どもについて書
くこともあるが、しかしそれでも、「個人」については、書かない。また書いてはならない。
私たちが「子ども」というときは、顔をもたない、子どもたちの世界、全体を意味する。
教育論は、そうした「子ども」を前提として、組み立てる。が、最後の最後のところで、
子どもをもつ親は、こう言う。
「先生、うちの子は、だいじょうぶでしょうか?」と。
つまり、「うちの子は、ちゃんと目的どおり、SS中学校へ、入学できるでしょうか」と。
これが教育論の限界である。私たちは「論」を説きながらも、そこにいつも、一定の限
界があることを知る。
●主義の限界
資本主義にも、共産主義にも、似たような限界がある。民主主義にも、ある。ある一定
のところまでは、その「主義」は、有効であり、それなりの支持を得る。が、それを越え
ると、とたんに、ほころびが生ずる。ボロが出る。矛盾が生ずる。
なぜか?
こうした限界も、教育論がもつ限界を当てはめてみると、簡単に理解できる。
「高尚な教育論も結構だが、私という親が目的とすることは、自分の子どもを、SS中
学に入れることなのです」と。
つまり今日の生活にも困っている人に向かって、資本主義や共産主義、さらには、民主
主義という「主義」を説いても意味はない。「高尚な主義も結構だが、今日の生活を、まず、
何とかしてくれ。主義の話をするのは、そのあとで、結構!」となる。
●強者の論理vs弱者の論理
こうした「限界」を、如実に表しているのが、「経済理論」である。ご存知のように、経
済理論ほ
ど、ツギハギだらけの理論はない。ツギハギにツギハギを重ねながら、何とかその場、そ
の場をしのいでいる。ごまかしている。
遠い昔には、アダム・スミスがいた。ケインズがいた。マルクスがいた。最近では、ド
ラッカー(1909〜)がいた。しかし一度とて、その理論どおりに、経済が動いたため
しがない。
理由は、簡単である。
こうした経済理論は、いわば、強者の論理でしかないからである。わかりやすく言えば、
とりあえずは、日ごろの生活には困らない、それなりのエリートたちが考えた論理だから
である。
それに対して、弱者と呼ばれる人たちは、いつも別の論理で、ものを考え、行動する。
しかも不幸なことに、そういった弱者は、「もの言わぬ民」である。自分たちの主義(?)
を、論理として、まとめることもできない。今日という現在を、生きていくだけで、精一
杯。明日の生活を心配しながら、不安な毎日を送っている。
そのためには、ときには、法もやぶる。悪いこともする。そうでもしないと、生きてい
かれない。そういう人たちが、時として、主流となり、エリートたちが説く「主義」を、
ことごとく否定していく……。
●教育の世界でも……
高尚な教育論など、受験塾の玄関をくぐれば、そのままどこかへ吹き飛んでしまう。そ
こでは、教育そのものが、個人の欲得の追求の場になっている。
「1人でも多く、他人を蹴落とせ」
「点数こそ、すべて」
「人間の勝ちも、それで決まる」と。
しかしだれが、そういう受験塾を否定することができるだろうか。彼らは、みな、決ま
ってこう言う。
「私の目的は、SS中学校の入試に、合格すること」と。
わかりやすく言えば、歴然とした社会的格差をそのままにしておいて、いくら、高尚な
教育論を説いても意味はない。親や子どもたちは、日々の生活を通して、否応なしに、そ
の格差を、肌で感じ取っている。
「来月はどうやって生きていこうか」と悩んでいる人もいれば、数千万円の年収を稼ぎ、
外車を何台も乗り回している人もいる。
その入り口に、「教育」がある。つまり彼らにとっての「教育」とは、そういう教育をい
う。そして私たちが説く教育論とは、まったく異質のものである。
●民主主義の限界
民主主義といっても、いかにいいかげんなものであるかは、すでに、みさなん、ご存知
のとおり。国政選挙があるたびに、だれしも心のどこかで、何かしらの疑問を感じている。
「こんなことで、本当に政治が変わるのだろうか」と。
このH市でも、中央から天下り官僚がやってきて、選挙に出馬する。当選する。そして
また中央へと戻っていく。それが明治の昔から、慣例になっている。
で、選挙が終わっても、生活は、何も変わらない。相変わらず、今日という「今」を生
きていくだけで、精一杯。
もっとも、これは「個人」の話だが、これが、「国家」の話になることもある。
欧米先進国が、いくら高尚な民主主義を説いたところで、国によっては、今日という「今」
を生きていくだけで精一杯という国もある。
そういう国へ行けば、「何が民主主義だ!」となる。つまりこれが、民主主義の限界とい
うことになる。
●弱者の論理
こうした「限界」を乗り越えるためには、弱者の論理でものを考え、そのレベルで主義
を作らねばならない。が、しかしそうした主義は、今度は、強者の利害と、まっこうから
対立する。
これも教育の場で考えてみると、それがよくわかる。
「とにかく、この日本では、学歴のあるものが勝ち」
「勝てば、官軍」
「1点でも、点数をあげろ。すべては偏差値で決まる」と。
講演などでも、「日本の教育の未来」という演題では、人は、集まらない。しかし「こう
すれば、あなたの子どもを、目的の大学へ入学させることができます」と言えば、人は、
集まる。
現実の世界は、そこにある。
しかし教育論を説く人が、そんな話をするわけには、いかない。先にも書いたが、「子ど
も」といっても、子ども、そのものが、ちがう。こんな私にしても、ものを書きながら、
その限界を、毎日のように感じている。
●主義の限界
つまりは主義には、限界があるということ。それがつまりは、共産主義にせよ、民主主
義にせよ、資本主義の限界ということにもなる。
もちろん限界があることが、悪いというのではない。またそれがあるからといって、そ
れぞれを否定するのも、おかしい。
大切なことは、いくら主義をもっても、それは強者の論理でしかないということ。弱者
は弱者で、別の論理で動く。たとえば宗教、さらにはカルト、迷信、占い、まじないにし
ても、それを「おかしい」と思うのは、その人の勝手だが、だからといって、そういうも
のに身を寄せている人を、「まちがっている」と言ってはいけない。
そういうものに身を寄せることで、懸命に自分を支えている人だっている。
それを忘れると、いくらすばらしい主義を唱えても、やがて矛盾を露呈し、ここに書い
たように、ボロボロになってしまう。
なぜあのイラクで、ブッシュ大統領が説く民主主義が定着しないかという理由も、こん
なところにあるのではないか。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
主義 はやし浩司 弱者の論理 貧者の論理 主義の限界 民主主義 経済学の限界)
Hiroshi Hayashi++++++++++July 06+++++++++++はやし浩司
●弱者の論理vs依存性
+++++++++++++++++
弱者が必ずしも正しいというわけではない。
弱者の論理が、同じように、正しいというわけではない。
弱者の論理の根底を流れるのが、「依存性」。
弱者の論理を、依存性の観点から、考えてみた。
それがつぎの原稿。
日付は2009年の2月(BLOG)になっている。
+++++++++++++++++
●依存性(Dependence)
++++++++++++++++++++++++++++
依存性には中毒性がある。
依存される側を、「主者」とする。
依存する側を、「従者」とする。
一度、二者の間で依存関係ができると、主者はいつも主者となり、
従者は従者となる。
途中で、立場が入れ替わるということはない。
これについては、前にも何度か書いた。
そこでここでは、もう一歩、話を進める。
++++++++++++++++++++++++++++
●親子の依存性
実は、親子関係においても、この依存性が生まれることがある。
親が主者となり、子が従者となるケースが多い。
が、反対に、親が従者となり、子が主者となるケースもある。
一般的に、精神的欠陥、情緒的未熟性があると、従者になりやすい。
親側にそれがあれば、親が従者になる。
で、こうした依存性を、自分の中に感じたら、できるだけ早い時期に、
依存性と決別したほうがよい。
自分の親や、自分の子どもに感じたときも、そうである。
主者はますます主者になり、従者はますます従者になる。
従者は、「助けてもらうのが当たり前」という考え方をする。
そのためお金やモノの流れが、一方的になる。
で、親子のばあいは別として、(親子でもそうなるケースは多いが)、
従者が主者にそれだけ感謝しているかというと、それはない。
立場が逆転したとき、その分だけ、今度は従者が、主者を助けてくれるかというと、
それはない。
こんな例がある。
●麻痺する感覚
A氏(50歳)は、実母の実家ということで、長い間、伯父を財政的に援助してきた。
伯父は実家を守っていたが、定職はなかった。
そこで「小遣い」と称して、実母はそのつど、伯父に渡していた。
もとはと言えば、A氏が実母に渡したお金である。
ハンパな額ではない。
合計すると、年間、数百万円にはなった。
それを10年近く、つづけてきた。
が、A氏が50歳になったとき、A氏の事業が行き詰った。
一時的に多額の借金を負った。
そこでA氏はそれとなく伯父に打診してみたのだが、伯父は、だんまりを決め込んだ。
A氏はこう言った。
「私の窮状を知りつつ、音なしの構え。そればかりか、それとなく『うちは貧乏』と、
そればかりを口にするようになりました。
それもズルイ言い方をするのですね。『この3年間、旅行などしたことがない』とか、
『家の改築費に、600万円かかった。ローンの返済で、たいへん』とかなど。
実際には、町に空き地を買い上げてもらっていたのですが……」と。
だからA氏はこう言う。
「依存関係ができたら、その人を援助しても無意味です。感謝されるのは、最初だけ。
しばらくすると、それが当たり前になり、さらにしばらくすると、援助しないでいると、
逆に請求されるようになります。
それに応じないと、かえって恨まれることもあります」と。
なぜか。
●弱者の立場で
従者の心理を理解するためには、一度、弱者の立場に自分を置いてみる必要がある。
弱者には、弱者の論理がある。
こんな例で考えてみよう。
あなたの隣に、金持ちが住んでいる。
大型の外車に乗り、大きな家に住んでいる。
毎日、ごちそうを食べている。
が、あなたは貧乏。
その日の食費さえ、満足にない。
子どもの学費もままならい。
そんなある日、隣人が、金銭的な援助をしてくれた。
あなたは涙を出して、それを喜んだ。
が、あなたは一時的には感謝するかもしれないが、その気持ちは、いつまでも
つづかない。
あなたはそれまでにも、そしてそのときにも、別の心で、隣人をねたみ、そういった
不公平があることについて、大きな不満を感じていた。
だから「隣人が自分を助けてくれるのは当然」とまでは考えないにしても、
助けてくれたからといって、それまでのねたみや不満が消えるわけではない。
そのねたみや不満が、それまでにもていった慢性的な(怒り)が、
感謝の念を消してしまう。
むしろ助けてもらったことによって、ねたみや不満を増大させてしまうこともある。
●日本政府の援助
よい例が、日本政府が外国に対してする、政府間援助。
日本は毎年、東南アジアを中心に、70〜80億ドル規模の、援助をしている
(政府開発援助・06)。
しかしそういう国々が、日本に対して感謝しているかといえば、それはない。
中国にせよ、韓国にせよ、東南アジアの国々やアフリカ諸国の国々にせよ、
いまだかって、日本に感謝したという例は、ひとつもない。
「援助をやめる」と言っただけで、逆に抗議される。
あのK国にいたっては、核兵器で脅して、日本から援助をとりつけようとしている!
だから冒頭の話に戻る。
依存性には、中毒性がある、と。
が、それでもだれかを助けたくなったら、どうするか?
そういうときは、無私、無欲、自分とは関係のない人に対してしたらよい。
人間関係を破壊したくなかったら、そうする。
そうそうもうひとつ。
援助するならするで、相手をよく見極めてからするのがよい。
「逆の立場だったら、この人は、私を助けてくれるか」と。
そういう目で、相手を見ながら援助するのがよい。
●依存性の内容について
依存性にも、(1)攻撃型と、(2)同情型、(3)服従型がある。
ある親に向って、自分の努力なさを棚にあげて、「こんなオレにしたのは、お前だろ!」と
叫んだ男性がいた。
「だから、オレの責任を取れ」と。
これを攻撃型依存性という。
一方、弱々しい自分を演じながら、相手に依存する人もいる。
相手が援助しなければならないように、相手を追い込んでいく。
ある男性は、「あなたが助けてくれなければ、一家心中です」と言って、相手に
援助させていた。
これを同情型依存性という。
さらに相手に、「あなたにすべてを任せます」といった様子を売りこんで依存する
ケースもあります。
ある女性は、実弟が生活費を渡すたびに、こう言った。
「大切に使わせてもらいます」と。
つまり(もらう)のが当然という考え方をする。
これを服従型依存性という。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
依存性 攻撃型依存性 服従型依存性 同情型依存性)
++++++++++++++++++はやし浩司
●弱者の論理
+++++++++++++
最後に、私が好きな私の原稿。
この原稿を読むたびに、ジンと
胸が熱くなる。
(中日新聞発表済み)
+++++++++++++
●尾崎豊の「♪卒業」論
学校以外に学校はなく、学校を離れて道はない。
そんな息苦しさを、尾崎豊は、『卒業』の中でこう歌った。
「♪……チャイムが鳴り、教室のいつもの席に座り、何に従い、従うべきか考えていた」
と。
「人間は自由だ」と叫んでも、それは「♪しくまれた自由」にすぎない。
現実にはコースがあり、そのコースに逆らえば逆らったで、負け犬のレッテルを張られて
しまう。
尾崎はそれを、「♪幻とリアルな気持ち」と表現した。
宇宙飛行士のM氏は、勝ち誇ったようにこう言った。
「子どもたちよ、夢をもて」と。
しかし夢をもてばもったで、苦しむのは、子どもたち自身ではないのか。つまずくことす
ら許されない。
ほんの一部の、M氏のような人間選別をうまくくぐり抜けた人だけが、そこそこの夢をか
なえることができる。
大半の子どもはその過程で、あがき、もがき、挫折する。
尾崎はこう続ける。
「♪放課後街ふらつき、俺たちは風の中。孤独、瞳に浮かべ、寂しく歩いた」と。
日本人は弱者の立場でものを考えるのが苦手。
目が上ばかり向いている。
たとえば茶パツ、腰パン姿の学生を、「落ちこぼれ」と決めてかかる。
しかし彼らとて精一杯、自己主張しているだけだ。
それがだめだというなら、彼らにはほかに、どんな方法があるというのか。
そういう弱者に向かって、服装を正せと言っても、無理。尾崎もこう歌う。
「♪行儀よくまじめなんてできやしなかった」と。
彼にしてみれば、それは「♪信じられぬおとなとの争い」でもあった。
実際この世の中、偽善が満ちあふれている。
年俸が二億円もあるようなニュースキャスターが、「不況で生活がたいへんです」と顔をし
かめて見せる。
いつもは豪華な衣装を身につけているテレビタレントが、別のところで、涙ながらに難
民への寄金を訴える。
こういうのを見せつけられると、この私だってまじめに生きるのがバカらしくなる。
そこで尾崎はそのホコ先を、学校に向ける。
「♪夜の校舎、窓ガラス壊して回った……」と。
もちろん窓ガラスを壊すという行為は、許されるべき行為ではない。が、それ以外に方
法が思いつかなかったのだろう。いや、その前にこういう若者の行為を、誰が「石もて、
打てる」のか。
この「卒業」は、空前のヒット曲になった
。CDとシングル盤だけで、二〇〇万枚を超えた(CBSソニー広報部、現在のソニーM
E)。「カセットになったのや、アルバムの中に収録されたものも含めると、さらに多くな
ります」とのこと。
この数字こそが、現代の教育に対する、若者たちの、まさに声なき抗議とみるべきでは
ないのか。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 尾崎豊 卒業)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●合理との対立関係
人の心もゆがむときには、ゆがむ。
が、問題は、どうゆがむかではなく、なぜゆがむかということ。
そこにメスを入れないかぎり、この世の中は、ますますゆがんでいく。
わかりやすく言えば、人間が原罪的にもつ(欲望)。
その欲望をどうコントロールしていくか。
そのあたりまで掘り下げないと、この問題、つまり弱者の論理(貧者の論理)は、解決し
ない。
いつまでたっても、合理と対立関係を維持したまま、私たちの住む世界を、ゆがめていく。
2011/11/21
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●寒い! (はやし浩司 2011−11−22)
+++++++++++++++++
時計は見なかった。
午前4時半ごろだった。
顔に肌を刺すような冷気を感じ、そのまままたふとんの中へ。
昨夜遅く、30分ほど、自転車で走った。
そのときも寒かった。
が、今朝は一段と冷えていた。
(現在時刻は5:53AM。
デスクの上の気温は、11・9度。)
枕元にあったパソコンをネットにつなぐ。
欧米の経済動向を探る。
そのままふとんの中で30分ほど、過ごす。
++++++++++++++++++
●無私無欲
昨日は2つのテーマについて考えた。
ひとつは、「貪欲」について。
もうひとつは、「弱者の論理(貧者の論理)」について。
楽しかった。
書いている間、オーストラリアの友人からメールが入った。
「時には休息も必要だから、休息をとれ」と。
「休息は、土への肥料のようなもの」とも。
オーストラリア人らしい言い方である。
つまり休息をとることによって、それが心の肥料になる、と。
が、どうか誤解しないでほしい。
私はこうしてものを考えているときが、いちばん楽しい。
無私、無欲で書いているから、なお楽しい。
苦しいときもあるが、それを乗り越えたとき、その苦しみが大きな喜びに変わる。
つまり休息のとり方は、人それぞれ。
問題は、そのあと。
その休息を、そのあと何のために使うか。
●……だから、それがどうしたの?
イギリスの格言に、『休息を求めて、疲れる』というのがある。
愚かな生き方の代名詞のようにもなっている格言である。
つまり「いつか楽になろう、楽になろうとがんばってきた。
で、やっと楽になったと思ったら、疲れてしまって、何もできない」と。
が、この格言を反対から読むと、こうなる。
『楽にはなった。しかし気がついてみたら、何もやることがない』と。
これも愚かな生き方ということになる。
だから私はいつも自分にこう問いかける。
「……だから、それがどうしたの?」と。
たとえば休暇になった。
気分を休めた。
羽を伸ばした。
……だから、それがどうしたの?、と。
ただ休息のための休息であるなら、意味はない。
時間の無駄という。
●誤解
オーストラリアの友人は、もうひとつ誤解していることがある。
ものを書くというのは、運動技術に似ている。
たとえば1週間でも、ものを書かないでいると、そのあと調子を戻すのに苦労する。
もしそれが1か月にでもなったら、さらにそうで、考えそのものが、まとまらなくなる。
毎日書いているから、ものを書くことができる。
……と書くと、「何を偉そうに!」と思う人がいるかもしれない。
「いっぱしの作家気取りで、何を言うか!」と。
もちろん私は作家ではない。
無名。
ベストセラーとなった本は、1冊しかない。
あとはよくて2、3刷で絶版。
ほとんどの本は、初版だけで、絶版。
皮肉なことに、若いころゴーストライターとして書いた本のほうが、今でもよく売れてい
る。
が、支持者がいないわけではない。
HPやBLOGへのアクセス数は、月間、50万件以上を記録している。
もちろんみながみな、好意的というわけではない。
それはわかっているが、しかしその「数」こそが、私を支えていてくれる。
私はそうした人たちの期待を裏切ることができない。
●実験
さらに一言。
私はときどき、こう思う。
「私は今、おもしろい実験をしている」と。
実験というのは、こうしてものを書くことが、どういう意味をもつのか、それを知るこ
とをいう。
まったく意味のないことをしているのか。
そいれとも意味のあることをしているのか。
ネットに乗せた原稿だけでも、すでに20万枚を超えている。
(40字x36行を、1枚とする。)
あるいはそれ以上かもしれない。
こうして書いた原稿は、10年後にはどうなっているか。
20年後にはどうなっているか。
今年は2011年だから、もし興味のある人は、10年後でもよい。
20年後でもよい。
そのころ気がついた人がいたら、はやし浩司の原稿がどうなっているか、一度、チェック
してみてほしい。
それが今、私がしている実験の結果ということになる。
●田丸謙二先生から
同じころ、田丸謙二先生からメールが届いた。
先週の月曜日、体の調子を悪くし、先週の土曜日、退院したとか。
田丸謙二先生は、すでに歴史上の人物になっている。
この先、何十万、何百万の人たちが、田丸謙二先生の名を口にすることになる。
●悲観的な見方
話は変わる。
こういう時期だから、どうしても経済の話になる。
で、いろいろな見方があるだろう。
悲観論、楽観論……。
しかし現在のEUは、ソ連崩壊のあのときの状況に似ている。
かなり悲観的な見方だが、大きな流れは、まっすぐその方向に向かって進んでいる。
で、現在、民主党主導による「仕分け作業」がつづいている。
しかし今は、そんなばあいではない。
そんなことをしているばあいではない。
このまま進めば、日本という国家すら危うくなる。
破産するかもしれない。
たとえて言うなら、原子力発電所が爆発するかもしれないときに、節電を呼びかけてい
るようなもの。
日本が今すべきことは、そこにある巨大な危機を、どう回避するかということ。
そのあと日本をどう再生させるかということ。
「仕分け」などという手ぬるい手法では意味がない。
一刀両断に国家予算を緊縮する。
まず手をつけるべきは、公務員の人件費の削減。
不要な箱物行政の縮減。
そういうこともさておいて、何が年金制度の改革だ!
消費税の税率アップだ!
「危機」を先取りしながら、その準備をする。
今の日本人に欠けるのは、その危機意識。
今、世界で何が起こりつつあるか。
永田町の政治家たちには、それが見えないらしい。
●基軸通貨
結局は、アメリカのひとり勝ちになるのか。
すでにユーロからドルへ、再び基軸通貨の動きが、加速し始めている。
つまり再び、ドルが世界の基軸通貨になるということ。
(今でもそうだが……。)
何だかんだといっても、アメリカは強い。
強大な軍事力を擁している。
資源もある。
農産物もある。
EU危機を巧みに利用しながら、「肉を切らせ、相手の骨を切る」という戦術に出ている。
したたかなアメリカ。
『ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドのストラテジスト、ブライアン・キム氏(コ
ネティカット州スタンフォード在勤)は、「米国の格付けが再び引き下げられるのかどうか、
市場は見極めようとしている」と指摘。
「リスクを回避し、ドルを選好する傾向になっている」と述べた』(Bloomberg)と。
●ドジのドジ、大ドジのバカ
ドジといえば、この事件。
『……衆参両院のコンピューターシステムがサイバー攻撃を受けた問題で、参議院は21
日、一部のサーバーがウイルスに感染し、すべての国会議員のIDやパスワードが流出し
た可能性があると発表しました』(TBSーi・11/22)と。
開いた口が塞がらないというか、バカげているというか……?
「すべての国会議員のIDやパスワードが流出した」という部分が恐ろしい。
その深刻さが、国会議員たちには、わかっているのだろうか。
日本の国家機密が、そのままどこかの国へ、筒抜けになっていた。
無知な議員が、どこかのファイルを開いてしまったのだろう。
改めて国会議員の知的レベルの低さに驚く。
●11月22日
……ということで、今日も激動の1日になりそう。
私の予想では、今日も300円前後、株価(日経平均)は下がるはず。
証券株と銀行株を注視!
++++++++++++++++++はやし浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 21日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page024.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●「浜名湖弁天リゾート・ジ・オーシャン」にて
++++++++++++++++++++++
弁当を買う。
DVDショップで、DVDを借りる。
雑誌「Sapio誌」(小学館)を1冊仕入れる。
「中国・大崩壊」という特集が気に入った。
そのあと一度、家に戻り、そのままジ・オーシャンに。
先ほど電話を入れたら、「今日は、けっこう混んでいます」と。
で、和室で頼んだら、太平洋側ではなく、裏弁天側という。
「裏弁天側なら、和室が空いています」と。
この際、ぜいたくは言わない。
温泉に入れるだけでも、ありがたい。
+++++++++++++++++++++
●雨
今朝から、土砂降り。
昼ごろになって雨脚(あまあし)が、やや弱くなった。
庭に出てみると、生暖かい南の風。
私とワイフは、弁当屋に向かった。
600円の弁当でも、ホテルで食べると、おいしい。
言い忘れたが、今回は、1泊朝食。
夕食なし。
料金は6200円+消費税+入湯料とか。
通いなれたホテルだけに、気分も落ち着く。
●無理
が、いつもそうだが、迷わなかったわけではない。
せっかくの土曜日だから、一日、家の中でのんびりしていたいという気持ちもないわけで
はない。
それに土曜日は、どこへ行っても、混雑している。
ホテルにしても、料金は割高。
が、そこは思い切って、アクセルを踏む。
この「踏む」という部分で、かなり無理をする。
年を取れば取るほどなおさらで、その(無理)がないと、「一日中、家の中で……」となる。
しかしこれは、まずい。
気力がますます弱くなる。
刺激を求めなくなる。
廊下の入り口に立つと、そうなる。
●老人性無気力症
老人になると、何ごとにつけ、無気力になる。
フロイトが説いた「性的エネルギー」は、そのままユングの説いた「生的エネルギー」に
一致する。
性的エネルギーの衰退は、当然、生的エネルギーの衰退と考えてよい。
その生的エネルギーが衰退する。
だから「アクセルを踏む」となる。
しかしこれは努力の問題というよりは、習慣の問題。
その習慣があればよし。
そうでなければ、そうでない。
それは(運動)に似ている。
運動することよりも、「運動をする」という習慣が大切。
その習慣をどう作るか。
老後に向け、どう作っていくか。
その習慣作りに失敗すると、あとは死の待合室にまっしぐら!
●中国大崩壊
中国がおかしい。
……ということは、みな、感じている。
不動産(マンション)価格が、今年に入ってから、暴落に近い値下がりをつづけている。
日本でもそういう事件はあった。
先にマンションを買った住人たちが、価格を下げた業者に対して、暴動を起こしたという。
そんなニュースも伝わってきている。
そのためマンションの売買取引は、「(昼間はあぶないので)、夜になされている」(上海)
とか。
しかしこれはおかしい。
いくら値下がりしたとはいえ、そのときはそのときで、納得して買ったはず。
あとになって価格がさがったからといって、つまり高いでマンションを買わされたからと
いって、怒るほうがどうかしている。
私が住んでいるこの団地にしても、買ったときは坪11万5000円だった。
が、あのバブル時代には、坪50万円近くまで、はねあがった。
現在は坪30万円前後で落ち着いている。
つまり中国政府は、ここにきて突然、急ブレーキを踏んだ。
(まだSapio誌を読んでいないが、たぶんそのあたりを切り口にしているはず。)
●R631(28D)、TOSHIBA・ウルトラブック
今日のお供は、R631。
たいへん気に入っている。
指紋認証が、こんなに便利なものとは、知らなかった。
それに光るキーボードというのも、よい。
スイッチONから、デスクトップ画面が現れ、スタンバイになるまで、10秒前後。
軽くて、持ち運びやすい。
世界イチ、軽くて薄いとか。
まるでふつうのノートのよう。
今、そのパソコンを、車の中で使っている。
楽しい。
気持ちよい。
指が慣れてきたせいか、キーボードの感触がよい。
今夜はだれにもじゃまされず、思う存分、文章を叩ける。
●大雨注意報
3時に家を出た。
こういう日は、駐車場の確保に苦労する。
夕方になると、温泉が混雑してくる。
だから3時。
早めのチェックイン。
バイパスから国道1号線へ抜けるとき、東海道線の線路をまたぐ大橋を渡る。
そのときのこと、車が風で、左右に大きく揺れた。
ワイフは、「台風みたい……」と、2、3度、言った。
見ると、どこかの倉庫を包むビニール・シートが、風に大きくはためいていた。
国道1号線に出てからも、みな、速度を落として走っている。
そういえば現在、大雨注意報、発令中。
もうすぐ弁天島に到着。
●中国とEU
風呂から出て、先ほどまで居間のほうでSapio誌を読んでいる。
中国では、不動産価格が、今年に入って20%下落したとある。
「高値づかみした住民が暴動を起こした」という記事も載っていた。
ハイパーインフレも目下、進行中。
おおかたの見方は、予想範囲というか、常識的。
(偉そうなことを書いて、ごめん。このところ私も、経済にかなり明るくなってきた。)
ただ知らなかったのは、中国がEU経済に深く、関わりこんでいるということ。
Sapio誌によれば、「ギリシャ国債やポルトガル国債、スペイン国債など、危機に直面
するEU各国の国債を、数10億ユーロ単位で大量に保有している」(P8)とか。
具体的な数字は書いてなかったが、「日本の対EU貿易は全体の1割にすぎず、デフォルト
が懸念される欧州国債を保有する金融機関もわずか」(P6)だ、そうだ。
道理で中国は、「助ける」「助ける」を連呼している。
助けなければ、自分があぶない。
悪魔のシナリオを考えるなら、EUが破産し、中国と韓国が破産し、日本だけ何とか生
き延びる。
……というのは、どうやら無理のようだ。
崩壊度にもよるが、中国が中程度以上の崩壊をすれば、日本経済もそのまま崩壊する。
●世界の荒波
要するに、今、世界中の銀行が、札を印刷機をフル回転で増刷した。
世界中が、通貨安競争を繰り返した。
その結果が、今。
この際いつまでも優等生ぶらないで、日本も印刷機をフル回転させたらよい……というの
は、暴論だが、このままでは本当に1ドル=50円になってしまう。
ハイパーインフレ、やむなし!
またそれによって、日本の借金も、(仮に物価が2倍になれば)、半分に減る。
……つまりそこまで腹を決めないと、この激流は、乗り切れない。
とはいっても、やがてそうせざるをえなくなる。
たとえるなら、日本は小さな防波堤で囲まれた一軒家。
世界の荒波は、そのすぐそこまで押し寄せてきている。
●ジ・オーシャン
ホテルは、2間つづきの広い和室を用意してくれた。
寝室と居間が分かれている。
このホテルの中でも、スィートルーム。
こういう心遣いがうれしい。
夕食は、もちろん弁当。
ほかに家からもってきた、柿とみかん。
景色がいつもとはちがうので、部屋に入った瞬間、かなりとまどった。
今回は裏弁天側。
いつもはそこにあるはずの太平洋が、今日は見えない。
……浜松に来たころには、この裏弁天にあった友人の別荘に寝泊まりしていた。
冬場は、だれも使っていないということだった。
それでその別荘の一部屋を貸してもらった。
そのこともあって、浜松市内に居を構えてからも、夏になると毎週のようにこの裏弁天へ
遊びに来ていた。
東海道線のガードをくぐると、西山貸し船店というボート屋がある。
私と同年齢の主人が、その店を経営していた。
今も、その主人が経営しているという。
2、3年前だったか、その西山氏が、何かのことで新聞に紹介されていた。
なつかしいというより、うれしかった。
そのボート屋でボートを借り、浜名湖へ出た。
ジ・オーシャン……大理石に覆われたピカピカのホテルではない。
古い旅館をていねいに改装したホテルである。
それだけに居心地がよい。
従業員の人たちも、やる気満点。
随所に本気度が満ち溢れている。
今回は夕食抜きで泊まったが、いつも一流ホテルの客のように、私たちを扱ってくれる。
満足度で評価するなら、文句なしの5つ星の、★★★★★。
今ならキャンペーン中ということで、1泊2食付で、7500円前後で泊まれる。
正確には、1室4名……6510円(1泊2食付)
1室3名……7035円
1室2名……7560円
詳しくは……053−592−1155まで
●年賀状
今年も年賀状の季節になった。
ときどき文面を考える。
が、年々、簡素なものになってきた。
今日もこのホテルへ来るまで、遠くの景色を見ながら考えた。
「どうしようか?」と。
そういえば、すでに喪中の知らせが、何通か届いている。
が、そのたびに、私はこう思う。
「なぜ日本人は、こうまで年賀状にこだわるのか」と。
5、6年前、私は年賀状廃止宣言をした。
が、そののち、少しずつ復活。
昨年も、X百枚かの年賀状を出した。
もちろん今年、世話になった人には、令状として年賀状を出す。
親しい知人や友人にも出す。
毎年欠かさず年賀状をくれる人にも出す。
しかしそこまで。
虚礼で出す年賀状ほど、意味のないものはない。
そういう相手からだと、年賀状をもらっても、かえって不愉快になるだけ。
その年賀状だが、2年ほど前までは減少傾向にあったという。
が、今年になって発行枚数の減少が止まったとか。
しかしその今年。
あの3・11大震災が日本を襲った。
「明けましておめでとうございます」という気分には、どうしてもなれない。
放射線による被害が出てくるのは、これから。
チェルノブイリ事故のばあい、2〜5年後から被害が現れ始め、10年後にピークを迎え
たという。
ともあれ、そういうことも考えながら、文面を考える。
2008年……40億2000万枚
2009年……39億5000万枚
2010年……38億2000万枚
2011年……38億2000万枚(財経新聞)
●午後5時2分
ワイフがこう言った。
「5時で、真っ暗よ」と。
時計を見ると、5時02分。
日が沈むのが、早くなった。
隣の部屋には、ダブルのベッドが2つ、ゆったりと並べてある。
1つだけでも、自宅のダブルベッドより広い。
……先ほどワイフが「少し頭が痛い」と言った。
私も少し痛い。
若いころは偏頭痛に苦しんだ。
が、ワイフはちがう。
若いころから、頭痛とは無縁だった。
が、このところ急に、体力が衰えてきた。
そんな感じがする。
……たった今、ワイフが「寒いわね」と言った。
見るとエアコンが切ってあった。
スイッチを入れ、24度に設定した。
●私流の尺度
私にとって経済学というのは、もっと直接的なもの。
つまり肌で感ずるもの。
たとえば今回の一連のEU金融危機についても、30分ごとに入れ替わるニュースを読
んでいても、実感がわかない。
それよりもむしろ株価の動きを見ていたほうがよくわかる。
グラフで示される。
たとえば野村ホールディングズ(野村証券)の株価。
私は野村ホールディングズの株価を見ながら、EUの動向を探っている。
株価が上がれば、EU経済は快方に向かっている。
下がれば、EU経済は悪化している。
私のような素人があれこれ判断するより、無数のプロたちが集合して出す結論のほうが正
しい。
(ただし私は野村株は、一度ももったことはない。
株は、3・11大震災の1週間前に、すべて売り払った。)
同じように中国経済をみるときは、100円ショップを見ればよい。
今では大きなゴミ箱まで、100円で買える。
が、もし品数が減ってくれば、中国の中小企業が傾き始めたことを示す。
品質が悪くなり、小物ばかりになってきたら、元高に向かっていることを示す。
(それほど単純でないことは、よくわかっているが……。)
言うまでもなく、あの100円ショップの商品は、そのほとんどが中国から入ってきて
いる。
私はいつも、「どうしてこんなものが、100円でできるのだろう」と思いながら、買い物
をしている。
それもやがて限界にくる。
そのとき中国は崩壊する。
ほかにたとえばガソリン価格。
ガソリンの価格が上がれば、資源の価格が上昇している。
下がれば、下降している、などなど。
おおまかに言えば、原油価格と貴金属価格は連動している。
たとえばガソリン価格が上昇していて、貴金属価格が上昇していないときは、「貴金属は買
い」と判断できる。
●Sapio誌
Sapio誌は、「中国崩壊」について、つぎのような記事を並べている。
(1)倒産→夜逃げラッシュ、不動産価格の一斉下落で、中国経済崩壊はもはや秒読み。
(2)日経平均株価5000円、冷凍食品が消滅、日本経済&生活は、こう変わる。
(3)来年1月総選挙が分岐点…追い詰められた中国は、台湾併合で覇権の歩を進める
(4)中国は焦っている! TPP日本参加の本質は、日米同盟強化と中国封じ込め
(5)「2歳女児ひき逃げは見殺し」は、氷山の一角! 「冷漠社会」よりこわい「誘拐
(6)多発地帯」
(7)極貧生活者3億人、大卒失業者800万人…世界最悪の格差社会と反格差デモ。
(8)中国GDPを押し上げてきた「金持ち愛人」たちの逆襲。
(9)胡錦濤「共青団」と習近平「太子党」が暗闘中、ほか。
どれもギョーギョーしい記事ばかり。
この雑誌は、何かにつけ、ギョーギョーしい。
信頼性は、あまりない。
●資本主義
資本主義は、今、大きな曲がり角に来ているのではないか。
またそういう視点で考えると、世界の動きが、より正確に理解できる。
たとえば(資本=マネー)そのものが、ゲーム化している。
神聖な……とまでは言えないが、労働力の対価としてのお金(マネー)が、ばくち(バク
チ)の対象になっている。
1日中働いて、数ドルしか稼げない人もいれば、一昼夜で、数億ドルも稼ぐ人もいる。
ドル、ユーロ、元、円は強いが、そうでない通貨は、そのつどジャンク(ゴミ)になって
しまう。
強い通貨をもった国は繁栄し、弱い通貨をもった国は、ますます貧乏になっていく。
こんなバカげたことをつづけていたら、世界は本当におしまい。
やがて世界は、メチャメチャになってしまう。
精神的な部分から、破壊されてしまう。
●11月20日
日本の若者たちで、何がいちばん欠けているかといえば、(たくましさ)。
数日前、高校生と大学生の就職率が発表された。
それを見ても、かなり悪い。
が、仕事がないわけではない。
(きれいな仕事)がないだけで、その気になれば、何だってできるはず。
タイの若者たちは、先般の大洪水のとき、土嚢の上で屋台を開いていた。
16歳の少女だが、自分でボートを借り、ソーセージを焼いて売っていた。
そういう(たくましさ)が、この日本から消えてしまった。
かわりに、あのトレンディ・ドラマ。
就職したら、マンション住まい。
車もあり、冷蔵庫も、エアコンもあり……。
そのつど「給料があがったら、金を返す」と言っては、親から金をせびる。
最初からこんな生活をしようと思うから、「就職先がない」となる。
が、日本国内ではそれでよいとしても、日本を一歩外に出れば、そこは猛獣が行き交う
野獣の世界。
そんな連中を相手に、この先、どうやって日本人は生きていくというのか。
日本の若者たちよ、仕事先ではなく、仕事をさがせ!
●二日酔い
今朝は4時30分に目が覚めた。
毎度のこと。
エアコンのサワサワとした乾いた風が、どうも肌に合わない。
温度を23度に設定したが、寒い。
……ということで、午前4時30分、起き。
頭が痛いのは、昨夜、寝る前に飲んだチューハイのせい。
いつもより多く、飲んだ。
つまり二日酔い。
●仕事
先に「仕事先ではなく、仕事をさがせ」と書いた。
それについて、追記。
これはその年齢の若者たちだけの問題ではない。
子どもたちの問題でもある。
さらに言えば、(依存性)の問題でもある。
子どもたちにしても、仕事、つまり家事をまったくといってよいほど、しない。
親自身がさせない。
「家事をさせなさい」などと言うと、「させることがありません」と。
掃除は掃除機で、ものの10分足らずですんでしまう。
料理にしても、レトルト食品。
電子レンジに入れて、ポンで終わってしまう。
洗濯は、もちろん全自動。
だから最近の子どもたちは、(してもらうこと)を、当然と考えている。
が、(すべきこと)がないわけではない。
アメリカ人の友人が、こんな話をしてくれた。
その友人は、浜松市内で英語を教えていたとき、ときどき生徒を自宅へホームスティとし
て招いていた。
そのときのこと。
そのアメリカ人は、こう言った。
「ヒロシ、日本の子どもたちは、みなスポイルされているよ」と。
「スポイルされている」というのは、簡単に言えば、「ドラ息子・ドラ娘」という意味。
そこで私が、「君は、どんなところを見て、そう言うのか」と聞いてみた。
するとその友人は、こう話してくれた。
「何もしない。ぼくが料理をしているときも、遊び回っている。
食べた食器は、いつもそのまま。
シャワーを使っても、泡を流さない。
朝起きても、ベッドをなおさない。
何もしない」と。
そういう子どもが勉強だけして、やがて就職先をさがすようになる。
が、この不況。
おいそれと仕事先が見つかるわけではない。
だからある女子大生は、中日新聞の投書欄にこう書いた。
「就職先を(私たちのために)用意するのは、社会の役目」と。
私はその投書を読んで、こう思った。
「こんな女子大生が公務員にでもなったら、日本はおしまい」と。
●経営者は1人
私の教室は、経営者は、私1人だけ。
ワイフが手伝ってくれるから、従業員は1人ということになるが、実際には、家族経営。
だから、それがよくわかる。
「1人」の意味がよくわかる。
つまり1人の人間が生きていくだけで、精一杯。
もしアルバイトの人を雇ったら、私の教室など、あっという間に閉鎖。
それだけの余力は、どこにもない。
……というようなことを、先日も、道路清掃をしている人たちを見たときに考えた。
道路の落ち葉を片づけていた。
清掃車の前後に、旗振りの男女が1人ずつ。
清掃する人、落ち葉を清掃車に詰め込む人、それが4人。
合計で、6人!
私はそれを見ながら、「6人の人を食べさせていくのは、不可能」と思った。
半ば公的な仕事で、国からそれなりの補助金でも出ればまだ、できる。
しかしそれもなかったら、不可能。
だいたい落ち葉など、その近所の人たちが清掃すれば、すむはず。
それを6人がかりで、清掃する。
税金の無駄というより、馬鹿げている。
つまり(仕事)に対する感覚が、完全にズレている。
それがわからなければ、一人(独りでもよい)で生きてみること。
何ができて、何ができないか、すぐわかるはず。
(仕事)の原点は、いつもそこにある。
●雨上がり
20日になって、雨が上がった。
同じ雨雲だが、空が高い。
車はゆっくりと自宅に向かっている。
頭痛が残っているため、最適のコンディションとは言えない。
文章を書いていても、どうしても暗くなる。
……今日の予定。
アメリカに住む孫に、「石」を送ること。
何でも「石」に興味があるとか。
私の家に来たときも、庭のあちこちを掘っていた。
……実は私もちょうどその年齢のころ、石に興味があった。
何かの本の付録についてきた石である。
最近までその石の名前を覚えていたが、忘れた。
黒く、コーヒーの結晶のような石だった。
私は毎日、その石を磨いて遊んでいた。
あとは昼寝をしてから考える。
やろうと思えば、いくらでもやることはある。
しかしどうも気が進まない。
今日一日は、おとなしくしていよう。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教
育評論 はやし浩司 はやし浩司 ジ・オーシャンズ はやし浩司 2011−11−2
0 浜名湖弁天リゾート・ジ・オーシャン)
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●老人心理と貪欲さについて(はやし浩司 2011−11−20)
(John Milton's "On Time")
++++++++++++++++++++++
今夜の夕食は、私がインスタント焼きそばと白いご飯。
ワイフが、レトルトの牛丼。
息子が、インスタント・ラーメン。
まことにもって、質素な夕食。……でした。
++++++++++++++++++++++
●運動2単位
先ほど、ウォーキングマシンの上で30分、歩いた。
時速は6キロ(MAX)。
ダラーと汗をかいたところで、終了。
これで1単位。
(1単位=約30〜40分。全身に汗をかく程度を1単位とする。)
●竹やぶ
自宅の横に、大きな竹やぶがある。
その竹やぶの竹を、草払機で100本ほど、切り倒した。
放っておけば、自宅のほうまで伸びてくる。
壁をこする。
また枯れた竹や葉が、かなり積もっている。
だれかがタバコの吸い殻でも捨てたら、そのまま火事になる。
……ということで、毎年、今の時期になると、竹やぶの竹を切る。
夏場は、ハチの巣があるので、それはできない。
切るなら、今ごろ。
毎年、それが恒例行事になっている。
で、今日はそのあと、庭の芝生も刈った。
その運動が、ちょうど1単位。
だから今日は、計2単位。
運動の量としては、まずまず。
●半眠状態
脳みその健康のためには、運動は欠かせない。
とくに私のような低血圧気味の人間には、欠かせない。
運動をする前と、運動したあととでは、脳みその働きはまったくちがう。
ものを書いていると、それがよくわかる。
が、今は、どこかぼんやりとしている。
集中力というより、(怒り)がわいてこない。
食後ということもあって、脳みそは半眠状態。
平和。
穏やか。
さて本論。
++++++++++++++++++はやし浩司
イギリスの詩人、ミルトンはこう書いている。
『老人が落ち込む、その病気は、貪欲である』と。
私は英語の原文を知らない。
「貪欲」というのは、「greedy」のことか。
卑しい意味で、「greedy」という。
「あなたはgreedyだ」と言われ、それを喜ぶ人はいない。
日本語で言うと、「むさぼる」という意味になる。
++++++++++++++++++はやし浩司
●老人のこだわり
ある老人が、自宅で倒れた。
たまたま隣人が医師だった。
それでその老人は隣人の家まで、這うようにしてやってきた。
が、ここからが常人には、理解できないところ。
その医師が「救急車を呼びましょう」と声をかけると、「それだけはやめてくれ」と。
理由を聞くと、「近所に恥ずかしいから」と。
●見栄?
こうした老人特有の(こだわり)は、あちこちでよく耳にする。
たとえばA氏、82歳。
A氏の妻も、同じく、82歳。
A氏は自宅に住んでいる。
A氏の妻は、有料老人ホームに住んでいる。
ところが最近、A氏の体調が悪くなってきた。
10年ほど前に、前立腺がんの手術を受けている。
それが再発。
大腸がんを併発した。
が、A氏は、どんなことがあっても、自宅の雨戸を閉めたまま、あるいは開けたままに
しない。
A氏が自宅にいないときは、A氏の妻が有料老人ホームからタクシーでやってきて、その
時刻になると、雨戸を開けたり、閉めたりしている。
見栄なのか?
それとも虚栄なのか?
これらの老人に共通しているのは、自分の弱みを人に知られることを、極度に警戒して
いるということ。
私の母にしても、そうだ。
兄と自転車店を経営していたが、60歳を過ぎてからは、めったに外泊すらしなかった。
店を閉める……ということを、極端にいやがっていた。
たとえば兄が胃潰瘍で入院したときも、医師とかけあって、1週間程度で病院から連れ出
してしまった。
●恥?
こういう老人特有の心理を、どう理解したらよいのか。
ふつうの常識のある人なら、ケース・バイ・ケースでものを考える。
若い人なら、なおさらであろう。
救急車を呼ぶことを、恥と考える。
自宅や店を閉めることを、恥と考える。
他人の目の中で生きてきた人ほどそうかもしれない。
が、それだけでは、理解できない。
もうひとつ考えられるのは、そうした老人たちは、そういう目で他人を判断してきたとい
うこと。
たとえば近所の人が救急車で運ばれたりすると、それを喜んだり、笑ったりする。
店を閉めた人についても、そうだ。
あれこれとその家の事情を詮索し、それを世間話にして花を咲かせる。
低俗な人たちだが、そういう人は、たしかにいる。
●他人の不幸をのぞく人
義姉の母親が倒れた。
義姉の義母、つまり夫の母親だった。
その母親は2年間ほど、義姉の家にいた。
義姉が介護した。
そのときのこと。
ある日突然、夫の従姉と従兄の2人が見舞いに来たという。
いろいろ事情があった。
その事情について書くのは、ここでの目的ではない。
簡単に言えば、「来るはずもない2人が来た」(義姉)と。
義姉はこう言った。
「好奇心というか、物見見物といった感じです。義母が倒れたのが、よほどうれしかった
のでしょうね。それを自分の目で確認するために来たのです」と。
私にも似たような経験がある。
あるので、そのときの義姉の気持ちがよく理解できた。
世の中には、本当に残念なことだが、他人の不幸を酒の肴(さかな)にして、喜ぶ人がい
る。
●人生の総決算
老齢期になると、それまで奥に隠し持っていた醜悪な人間性が、そのまま表に出てきて
しまう。
隠そうという意欲そのものが、薄れてくる。
(反対に若いときは、気力で、それをごまかすことができる。)
言うなれば、持病のようなもの。
それがどっと表に出てくる。
老齢期というのは、そういう意味で、人生の総決算期。
老齢期の人間性を見れば、その人がどういう人生観をもっていたかが、おおよそわかる。
もちろんそれがよいものであれば、よし。
しかしそうでなければ、そうでない。
みなにあきられ、嫌われる。
●では、どうするか
釈迦は、「精進」という言葉を使った。
「日々に鍛練あるのみ」と。
この鍛練にみによって、自分の人生観を変えることができる。
しかもその時期は、早ければ早いほど、よい。
30歳や40歳を過ぎてからでは、遅い。
50歳では手遅れ。
60歳では、先に隠された人間性のほうが表に出てきてしまう。
つまり一度できた人間性は、簡単には改まらない。
ゆがんだ心となると、さらにそうだ。
ばあいによっては、(ほとんどがそうだが)、死ぬまでそのまま。
●縁を切る
あなたの周囲にも、ずる賢い人はいくらでもいる。
小細工に小細工を重ね、善人ぶっている人はいくらでもいる。
ウソをつき、インチキを繰り返す。
大きな悪事こそできないが、平気で人をだます。
実のところ、私のまわりにもそんな人がいた。
が、50歳を過ぎるころから、私は心に決めた。
「縁を切ろう」と。
そういう人たちとつきあっていても、得るものは何もない。
ないばかりか、しばらくつきあっていると、そういう人たちがもつ、あの独特の毒気に染
まってしまう。
そういう人たちは、そういう人たち同士が集まり、独特の社会を形成している。
そういう社会に取り込まれると、それこそ私やあなたは、酒の肴にされてしまう。
が、それが本当の被害ではない。
本当の被害は、時間を無駄にすること。
時間を無駄にすること以上の、「損」はない。
●総決算
「救急車を呼ぶな」と言った老人。
毎日、雨戸をきちんと開けたり閉めたりする老人。
それがその老人たちがもつ人生観の、総決算ということになる。
……この話は以前にも書いた。
原稿をさがしてみる。
++++++++++++++++++++
「救急車を呼ぶな」と言った老人。
日付を見ると、2002年となっている。
今から9年前。
その前後に書いた原稿と併せて、再掲載する。
++++++++++++++++++++
●ある退職者
退職してからも、現役時代の肩書きや地位を引きずって生きている人は多い。とくに「エ
リート」と呼ばれた人ほど、そうだ。そういう人にしてみれば、自分が歩んだ出世コース
そのものが、自分の人生そのものということになる。Y氏(六七歳)もその一人。
私に会うと、Y氏はこう言った。「君は、学生時代、学生運動か何かをしていたのかね?
それでまともな仕事につけなかったのかね?」と。
彼は数年前まで、大手の都市銀行で、部長をしていた。この浜松へは、生まれ故郷とい
うことで、定年と同時に、移り住んできた。彼の父親の残した土地が、あちこちにあった。
そこで私が、「本も書いています」と言うと、「いやあ、こういう時代だから、本を書いて
もダメでしょ。本は売れないでしょ」と。たしかにそうだが、しかしそういうことを面と
向かって言われると、さすがの私でもムッとくる。
問題は、なぜY氏のような人間が生まれるか、だ。仕事第一主義などという、生やさし
いものではない。彼にしてみれば、人間の価値まで、その仕事で決まるらしい。いや、そ
れ以上に、なぜ、人は、そこまで鼻もちならないエリート意識をもつことができるのか。
自尊心という言葉があるが、その自尊心とも違う。肩書きや地位にしがみつくのは、自尊
心ではない。自尊心というのは、生きる誇りをいう。肩書きや地位とは、関係ない。彼の
ような人間は、戦後の狂った経済社会が生みだした、あわれなゾンビでしかない。
もっとも彼にしてみれば、過去の肩書きや地位を否定するということは、自分の人生そ
のものを否定することになる。最後は部長になったが、その部長をめざして、どれほど身
を粉にして働いたことか。家庭を犠牲にし、自分を犠牲にしたことか。それはわかるが、「で
は、Y氏は何か?」という部分になると、実のところ何もない。何も浮かんでこない。少
なくとも私には、ただの定年退職者(失礼!)。
別れぎわ、「今度、また自治会の仕事をよろしくお願いします」と言ったら、こう言った。
「ああ、県や市でできることがあれば、私に一度、連絡してください。私のほうから口を
きいてあげます」と。そうそう、こうも言った。「林君は、カウンセリングもできるのです
か。だったら、国のほうでも、そういう仕事があるはずですから、今度、私のほうで、話
おめでたい人というのは、Y氏のような人をいう。が、私は心の中で、Y氏とは、完全
につながりを切った。「何かの仕事の話になっても、(そういうことはありえないが)、断ろ
う」と心に決めた。
(02−12−2)
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●老後
おととい、Pペイントという、日本でも一、二を争うペンキ会社で、会長をしていたとい
うT氏が、久しぶりに我が家へ寄ってくれた。一五年ぶり? 玄関で会ったとき、「お元気
ですか」と言いかけたが、思わず、その言葉がのどの奥に引っ込んでしまった。T氏は、
すっかり老人ぽくなってしまっていた。
居間でしばらく話していると、やがて年齢の話になった。私が「五五歳になりました」
と言うと、「いいですねえ、これからですよ」と。私が驚いていると、こうつづけた。「ち
ょうどバブルのころということもありましてね。私が本当に自分の仕事ができたと思うの
は、五六歳から六三歳までのときでした。頭も体も、すこぶる快調で、気持ちよく仕事が
できました」と。
実のところ、私は、自分でも実感できるほど、体の調子がよい。昨日も講演先の小学校
で、階段を三段とびにのぼっていたら、あとから追いかけてきた校長が、「足がじょうぶで
すね」とほめてくれた。「はあ、自転車で鍛えていますから」と答えたが、そのおかげとい
うか、健康には、これといって、不安なところはない。ダイエットしたおかげで、どこか
頭の中もスッキリしている。
私は年配の人が、私に向かって、「若くていいですね」と言うときは、いつもそれを疑っ
てしまう。「本当にそうかな?」「なぐさめてくれているのかな?」「お世辞かな?」と。五
五歳になった私の印象としては、「先が読めない」という不安感のほうが強い。「これから
はガンになる確率がぐんと高くなる」とか、「これからはすべてが先細りになる」とか、そ
んなことばかり考える。よくワイフは、「あなたは、見かけは若々しいけど、中身は老人ぽ
い」と言うが、本当にその通りだと思う。
ルソー(フランスの思想家、一七一二〜七八)が、『エミール』の中でこう疑問を投げか
けている。多分、これを書いたとき、彼も今の私と同じ、五〇歳代だったのだろう。
「一〇歳では菓子に、二〇歳では恋人に、三〇歳では快楽に、四〇歳では野心に、五〇
歳では貪欲に動かされる。人間はいつになったら、英知のみを追うようになるだろうか」
と。
あのルソーですら、「貪欲に動かされる」と。いわんや私をや……と、居なおるわけでは
ないが、五五歳というのは、ちょうど、「そうであってはいけない」「しかしそういう自分
も捨てきれない」と、そのハザマで悩む年齢かもしれない。まだ野心の燃えカスのような
ものも、心のどこかに残っている?
T氏はさかんに、「まだまだ、これからですよ」と言ってくれたが、「これから先、何が
できるのだろうか」という思いも、また強い。またそういう思いとも戦わねばならない。「貪
欲さ」がよくないとはわかっているが、しかしそれがなくなったら、生活の基盤そのもの
が、あやうくなる。働いて、仕事をして、稼ぎを得て、それで生きていかねばならない。
私のばあい、悠々自適(ゆうゆうじてき)の年金生活というわけにはいかない。いわんや
「英知のみを追う」などというのは、夢のまた夢。
そうそうT氏は別れぎわ、こうも言った。「林さんは、いいねえ。道楽が多くて……。私
なんぞ、人間関係のウズの中で、自分を支えるだけで精一杯でした」と。しかしこれは、
T氏一流の、私への「なぐさめ」と理解した。
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●アンビリーバブル
世の中には、信じがたい人たちというのは、たしかにいる。ふつうの常識では、考えら
れない人たちである。実は、先日も、こんなことがあった。
その男性は、現在、八五歳。子どもはいない。大手の自動車会社の研究所で、研究員を
長年したあと、筑波(つくば)の国立研究所で、一〇年ほど研究員をした。そのあと、し
ばらく私立大学の教壇に立ったあと、今は、退職し、年金生活を送っている。が、そのあ
といろいろないきさつがあって、このH市に住んでいる。
ここまではよくある話だが、実は、その男性は、がんを患っている。もう余命はそれほ
ど、ない。手術も考えたが、年齢が年齢だからという理由で、抗がん剤だけで治療してい
る。が、私が「信じがたい」というのは、そのことではない。その男性は、莫大な資産家
でもある。市内だけでも、大きなビルを、三か所もっている。それに大地主。市の中心部
と郊外に、一〇〇〇坪単位の土地をいくつかもっている。ハンパな金持ちではない。
が、だ。その男性、今、別の男性(五二歳)と、わずか一〇坪の土地について、民事調
停をしている。本来なら、話しあいでどうにかなった問題だが、関係が、こじれてそうな
った。先日も、その土地をはさんで、二人が道路で、大声で怒鳴りあう喧嘩(けんか)を
していたという。
私はこの話を聞いて、「へえエ〜」と言ったきり、言葉が出なかった。
もし私ががんを宣告されたら、それだけで意気消沈してしまうだろう。何もできなくな
るだろう。しかも八五歳といえば、私より三〇歳も年上ということになる。そういう人生
の大先輩が、その上、大金持ちが、わずか一〇坪の土地のことで、言い争っている? 人
間の「生」への執着心というか、はっきり言えば、愚かさというか、それが私には信じら
れなかった。あるいは何がそうまで、その男性を、駆り立てるのか?
ここまで考えて、私はしばらく、あちこちの本を読みなおしてみた。で、最初に目につ
いたのが、ミルトン(一六〇八〜七四、イギリスの詩人)の『わめく女』。その中でミルト
ンは、こう書いている。「老人が落ち込む、その病気は、貪欲である」と。これだけを根拠
にするわけではないが、どうも年をとればとるほど、人間的な円熟味がましてくるという
のは、ウソのようだ。中には、退化する人もいる? そういえば、ギリシャのソフォクレ
スも、「老人は再び子ども」という有名な言葉を残している。
私はこの男性の話を聞いたとき、「老年とは何か」、それを考えてしまった。あるいはこ
ういう人たちは、その年齢になっても、まだ人生は永遠につづくとでも、思っているのだ
ろうか。仮にあの世があるとしても、あの世まで、財産をもっていくことができるとでも
思っているのだろうか。さらに「死」を目前にして、我欲にとりつかれることの虚しさを
覚えないのだろうか。さらにあるいは、老年には老年の、私たちが知る由もない、特別の
心理状態があるのだろうか。
これは近所の男性(八〇歳)のことだが、こんな話もある。ある夜、隣の家の人に、そ
の男性が「助けにきてほしい」と電話をしてきたという。そこでその隣の人が、その男性
の家にかけつけてみると、その男性は玄関先で倒れていたという。隣の人がそれを見て、「救
急車を呼びましょうか?」と声をかけると、その男性は、こう言ったという。「恥ずかしい
から、それだけはやめてくれ」と。
この話を聞いたときも、私はわが耳を疑った。その男性は、だれに対して、何を恥ずか
しいと思ったのだろうか。
さてさて、人はだれしも、老いる。それは避けることのできない未来である。末路と言
ってもよい。そういうとき、どういう心理状態になり、どういう人生観をもつか。私は私
なりに、その準備というわけでもないが、それを知りたいと思っている。で、こういう人
たちが一つの手がかりになるはずのだが、しかし、残念ながら、私には、まったく理解で
きない。冒頭に書いたように、どれだけ、また何回、頭の中で反芻(はんすう)しても、
理解できない。信じられない。つまりアンビリーバブルな話ということになる。この問題
は、ひょっとしたら、私自身がもう少し年をとらねば、わからない問題なのかもしれない。
ただここで言えることは、老人のなり方をまちがえると、かえってヘンな人間になって
しまうということ。偏屈でがんこになるのならまだしも、邪悪な人間になることもある。
そういう意味では、人間は、死ぬまで、前向きに生きなければならない。うしろを向いた
ときから、その人間は、退化する。釈迦も、「精進(しょうじん)」という言葉を使って、
それを説明した。「死ぬまで精進せよ(前向きに生きろ)」と。
(02−12−4)
●老人が、人生の大家であるというのは、まったくの幻想である。何と醜い老人が多いこ
とか。またこの世の中に、のさばっていることか。……と書いて、私たちはそうであって
はいけない。またそういう老人になってはいけない。一方的に老人を礼さんする人という
のは、その人自身がすでに、その老人の仲間になっているか、前向きに生きるのをやめた
ということを意味する。本当にすばらしい老人というのは、自らが醜いことを知っている
老人である。安易な老人美化論には、注意しよう!
●私の観察では、人間は、早い人で、もう二〇歳くらいから進歩することをやめてしまう。
あるいは三〇歳くらいから、それまでの人生を繰り返すようになる。毎年、毎月、毎日、
同じことを繰り返すことで、そのときどきを、無難に生きようとする。あるいは考えるこ
とをやめてしまう。が、なおさらに、タチが悪いことに、自らを退化させてしまう人もい
る。そういう意味で、人間にとっては、「停滞」は、「退化」を意味する。それはちょうど、
川の流れのようなものではないか。よどんだ水は、腐る。
●自らを輝かせて生きるためには、いつも前向きに生きていかねばならない。恩師は、一
つの方法として、「新しい情報をいつも手に入れることだ」と教えてくれた。また別の恩師
は、「いつもトップクラスの人とつきあうことだ。新しい世界にチャレンジすれば、自然と、
自分が磨かれる」と教えてくれた。方法はいろいろある。山に登るにも、道は必ずしも一
つではない。
●そこで考えてみよう。あなたのまわりには、老人と呼ばれる人がたくさんいる。あなた
自身も、すでにその老人の仲間になっているかもしれない。そういう老人や、あなたは、
今、輝いているか、と。実は、これは私自身の問題でもある。私は今、満五五歳。このと
ころとみに気力が衰えてきたのがわかる。何かわずらわしいことが起きると、それが若い
ころの何倍も気になるようになった。チャレンジ精神も薄れてきたように思う。できるな
らひとり、のんびりと暮らしたいと思うことも多い。つまり私自身、輝きをなくしつつあ
るように思う。
●そこで、考える。どうすればいいのか、と。逃げるわけではないが、この問題は、これ
から先、私にとっては、大きな問題になるような気がする。今は、ここまでしか書けない
が、この問題は、近々、決着をつけなければならないと思っている。
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●ルソーとミルトン
ルソーもミルトンも、同じ言葉を使っている。
「貪欲」という言葉である。
(1)まず、ルソー。
ルソー(フランスの思想家、一七一二〜七八)が、『エミール』の中でこう疑問を投げか
けている。
多分、これを書いたとき、五〇歳代だったのだろう。
「一〇歳では菓子に、二〇歳では恋人に、三〇歳では快楽に、四〇歳では野心に、五〇
歳では貪欲に動かされる。
人間はいつになったら、英知のみを追うようになるだろうか」と。
(2)ミルトン(一六〇八〜七四、イギリスの詩人)は、『わめく女』の中で、こう書いて
いる。
「老人が落ち込む、その病気は、貪欲である」と。
ただしミルトンは、敬虔なキリスト教徒の立場で、「貪欲」という言葉を使っている。
そのことは、ここにあげる「On Time」という詩を読んでもわかる。
ともあれ年を取れば取るほど、貪欲になっていく老人は多い。
少なくとも、加齢とともに、人は賢くなっていくわけではない。
多くは世俗に巻き込まれ、自分を見失い、強欲になっていく。
それを避けるために、私たちは何をすべきか。
何を準備すべきか。
結局は『精進』という言葉に行き着く。
それがそのまま、このエッセーの結論ということになる。
●補記(John Miltonの詩より・「On Time」)
ON TIME(予定どおりに)
FLY, envious Time, till thou run out thy race;ねたましい時よ、燃え尽きるまで過ぎ
ろ
Call on the lazy leaden-stepping hours,怠惰で、鉛にように重い時を訪ねよ
Whose speed is but the heavy plummet's pace;その速さは、恐ろしく遅い
And glut thyself with what thy womb devours,子宮がむさぼるもので、汝の食欲を満た
せ
Which is no more then what is false and vain,それは失敗でも無駄でもない
And merely mortal dross;ただの死すべき無価値なもの
So little is our loss,失うものは、ほとんどない
So little is thy gain.得るものも、ほとんどない。
For when, as each thing bad thou hast entomb'dなぜなら悪しきものはすべて墓に葬ら
れ
And last of all thy greedy self consumed,汝の貪欲さは、すべて消耗されるから
Then long Eternity shall greet our bliss,そのとき長い永遠が、祝福で私たちを迎える
With an individual kiss;それぞれの接吻で
And Joy shall overtake us, as a flood,喜びが洪水のように、私たちを包み、
When every thing that is sincerely good,誠実でよきものすべてが
And perfectly divine,完ぺきに神々しいものとなる
With truth, and peace, and love, shall ever shine,真実と平和と愛が、永遠に輝く
About the supreme throne神の最高位の王位の上に
Of Him, to whose happy-making sight, alone,そこに見えるのは、幸福な光景のみ
When once our heavenly-guided soul shall climb,ひとたび魂が天に導かれ昇るなら
Then all this earthly grossness quit,地上の世俗は、消え失せる
Attired with stars, we shall for ever sit,星々で飾られ、私たちは永遠にそこに座る
Triumphing over Death, and Chance, and thee, O Time死と運命と汝を乗り越えて。
(注:訳は私が直感的につけたので、かなり不正確。
ミルトンの基本的なものの考え方を知るにはよい。
ミルトンは、こう言っている。
『貪欲にやりたいことを、とことんやってみろ。
自分を燃やし尽くしてみろ。
それは失敗でも、無駄でもない。
やがてそれが無価値であったことがわかれば、
あなたも神の座に座ることができる』と。)
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教
育評論 はやし浩司 「救急車を呼ぶな」 老人の見栄と体裁 貪欲 人格の暴露 人間
性 邪悪な人間性)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 19日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page023.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●今日の目標
今日は、「八卦とDNA」について、もう一度、その謎解きに挑戦してみたい。
もし八卦と、DNA言語が一致していたら……。
これは世界の科学の常識をひっくり返すほどの大発見となる。
では、このつづきは、またあとで……。
2011/11/15朝記
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●謎の八卦(易経)
+++++++++++++++++++++++++
今日は1日、八卦(易経)とDNAの関係について考えてみた。
何度も図表を見ながら、その向こうに隠された関係を
考えてみた。
(……関係があれば……という条件つきだが。)
が、意外と簡単に、謎解きの糸口をつかむことができた。
それを今日は、わかりやすく説明してみたい。
+++++++++++++++++++++++++
<img src="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/64/img866cb8ffzik9zj.jpeg"
width="721" height="777" alt="img221.jpg">
width="721" height="777" alt="img221.jpg">
【表は、学研『ニビルの謎』より】
●はじめに
これは言うなれば、知的道楽のようなもの。
私自身、易経というものをほとんど知らない。
「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という程度にしか、「八卦」のことを知らない。
そんな私が現在、八卦に興味をもっているのは、それがDNAと関係があるのではないか
という点に着目したから。
改めて、その謎解きに挑戦してみる。
ちょうど1年ぶりの再開である。
●2進数
私たちは日常生活の中では、10進数を使っている。
これは人間の指が10本であることに、大きく関係しているという。
これに対してたとえばコンピューターの世界などでは、2進数を使用する。
2進数というは、(0)と(1)だけの世界をいう。
(―)と(+)でもよい。
便宜上、10進数の(1)と(2)を使用する。
その2進数では、たとえばつぎのように数える。
(かっこ)内は、10進数による数え方をいう。【表1】
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/85/img0144c68ezik0zj.
jpeg" width="587" height="718" alt="img228.jpg">
jpeg" width="587" height="718" alt="img228.jpg">
0(0)
1(1)
10(2)
11(3)
100(4)
101(5)
・
・
・
これでは数が大きくなるについて、段がついてしまうので、頭に(0)をつけ、わかり
やすくする。
つぎの表がそれである。
便宜上、6桁にしたが、それには理由がある。
その理由は、あとで述べる。
000000(0)
000001(1)
000010(2)
000011(3)
000100(4)
000101(5)
000110(6)
000111(7)
001000(8)
001001(9)
001010(10)
001011(11)
001100(12)
・
・
・
これですっきりした。
●八卦との関係
八卦では、一本の長い棒(−)と、二本の短い棒(・・)で、数を表す。
たとえば……、
(・・は、短い二本の棒、ーは、長い棒を表す。)【表2】
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/87/imgbec9b955zikdzj.
jpeg" width="771" height="1094" alt="img229.jpg">
jpeg" width="771" height="1094" alt="img229.jpg">
000000(0)⇒・・
・・
・・
000001(1)⇒―
・・
・・
000010(2)⇒・・
―
・・
000011(3)⇒―
―
・・
●長い棒と二本の短い棒
まずここで理解してほしいことは、八卦は、2進数で書かれた数字であるということ。
俗説によれば、伏義※という伝説上の賢者によって、発明されたという。
その当時の中国には、もちろん、数字の(0)(1)は、存在しなかった。
(中国語でいう漢字には、(0)の概念はない。)
だから(長い棒)と(二本の短い棒)で、「数」を表したとしても、何もおかしくない。
……というような回りくどい説明は、ここでは省略する。
八卦で使う(棒)は、二進数を表す。
たとえば10進数の(50)は、2進数では「110010」となる。
それを2種類の棒で書き表すと、【表3】のようになる。
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/88/img854d9d6ezik0zj.
jpeg" width="771" height="841" alt="img226.jpg">
jpeg" width="771" height="841" alt="img226.jpg">
●DNA
同じようにDNAについての説明も省略する。
そのDNAは、4つの塩基(AGCT)から、3つの組み合わせで、構成される。
Aは「アデニン」、Gは「グァニン」、Cは「シトシン」、Tは「チミン」を表す。
その4つの中から、たとえばATCと3つが結合し、それが螺旋階段のように並び、DN
Aを構成する。
それを1個とするなら、人間のDNAは、約30億個あるとされる。
それはいわばコンピューターでいうプログラムのようなもの。
「設計図」と表現する人もいる。
この設計図に応じて、人間の「形」ができる。
●必要条件
そのDNAと八卦との不思議な関係については、すでに多くの研究家が本に書いている。
しかしDNAはDNA。
八卦は八卦。
それもそのはず、DNAは、戦後、発見された。
歴史は浅い。
八卦は、俗説に従えば、5500年前からあったという。
3000年前でも、2000年前でもよい。
この際、年代はどうでもよい。
少なくとも、DNAの発見は、ごく最近のもの。
八卦は、それよりもずっと昔からあった。
だからもし八卦がDNAの配列をうまく説明したとしても、それだけでは必要十分条件
を満たしたことにはならない。
偶然の一致ということも、ありえる。
が、ともかくも、その「必要条件」だけでも、ここで考えてみたい。
本当に、何らかの関係があるのか。
それともないのか。
(十分条件を満たすためには、その論理で、ほかの未知のDNAの構造まで説明しなけれ
ばならない。)
はたして八卦とDNAの間には、何かの関連性があるのだろうか。
●64卦
八卦では、64卦ともいうように、8x8=64の卦(け)を基本にものを考える。
そこで10進数でいう(0)を2進数で、(0000000)(6桁)とする。
(63)は、(111111)(6桁)となる。
最近のコンピューターは、64ビットマシンが主流。
そのことも記憶のどこかにとどめておいてほしい。
この6桁の数字を、(長い棒)と(短い2本の棒)で表したのが、八卦ということにな
る。
【64卦の方位図】
●DNA
先にも書いたように、DNAは、4つの塩基のうち、3つの塩基の組み合わせで、最小
単位を構成する。
「3文字言語」という言葉も、そこから生まれた。
そこでここでは、6桁の(棒)を、3組に分けてみる。
当然のことながら、2本ずつの3組になる。
(八卦をDNAに、無理にこじつけようとしている感じがしないでもないが、そこは許し
てほしい。)
が、ここでたいへん興味深い事実に気がつく。
(長い棒)と(短い2本の棒)の組み合わせは、4通り。
この4通りという数は、4つの塩基の数と、奇妙なことに一致する。
が、ここでは、まだ、偶然の一致ということにしておく。
つまりだからといって、八卦とDNAとの間に、何らかの関連性があるとは言えない。
ともかくも、4つの組み合わせ、つまりパターンができる。
それをここでは、パターン(1)(2)(3)(4)としておく。【図4】
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/89/img67623bfazikfzj.
jpeg" width="752" height="877" alt="img225.jpg">
jpeg" width="752" height="877" alt="img225.jpg">
パターン(1)― ―
― ―
パターン(2)―――
― ―
パターン(3)― ―
―――
パターン(4)―――
―――【図4−2】
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/90/imgbf4d386azik3zj.
jpeg" width="773" height="663" alt="img224.jpg">
jpeg" width="773" height="663" alt="img224.jpg">
●10進数の(50)は、(110010)
こうして6桁の八卦を、3つに分解し、それぞれのパターンに、(1)(2)(3)(4)
と番号をふってみる。
たとえば10進数の(50)は、2進数では(110010)となる。
これを3つの組に分けると、(11)(00)(10)となる。
が、八卦をよく見てもらうとわかるが、数字の並び方が逆になっている。
(50)は、(010011)となっている。
だから3つの組に分けると、(01)(00)(11)となる。
これを先にあげた、4つのパターンに当てはめてみる。
すると(50)は、(3)(1)(4)となる。
同じように、(51)は、(4)(1)(4)。
(52)は、(1)(2)(4)となる。【表5】
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/91/img55c85ba7zik6zj.
jpeg" width="775" height="1109" alt="img223.jpg">
jpeg" width="775" height="1109" alt="img223.jpg">
●AGCTの相性
ここで最初の難関は、DNAでいう4つの塩基と、ここでいう4つのパターンの間には、
何か関係があるのだろうか。
あるとすれば、DNAの4つの塩基、(AGCT)は、それぞれ4つのパターンのうち、
どれと同じと考えたらよいだろうか。
その関連性を解く鍵がひとつある。
それはDNAにおいては、4つの塩基の中から3つの塩基で最小単位を構成するが、それ
ぞれに相性というのがあるそうだ。
たとえば、「AはTとのみ結合し、GはCとのみ結合する」(「ニビルの謎」)とある。
(DNAについての勉強は、今始めたばかりなので、不正確で申し訳ない。)
●プラスとマイナス
そこでさらに仮定を飛躍させる。
今まで(長い棒)と(二本の短い棒)と書いてきた部分を、(+)と(−)に置き換えて
みる。
すると、ここで磁力的な説明がつくのがわかる。
(短い棒を、マイナス、長い棒を、プラスとした。
もちろんその反対でもよい。)【図4−2】
パターン(1)は、(−)
(−)
パターン(2)は、(+)
(−)
パターン(3)は、(−)
(+)
パターン(4)は、(+)
(+)となる。
ここで電磁的にものを考えると、……どれとどれが結合すると考えてよいのか?
(+)と(−)は結合する。
(−)と(−)は結合しない。
つまりパターン(1)は、パターン(2)と(4)と結合する。
同じようにパターン(4)は、パターン(1)と(3)と結合する。
(+とーは、結合する。)
反対に考えると、パターン(2)は、パターン(4)のみとしか結合しない。
パターン(3)は、パターン(1)のみとしか結合しない。
つまり、パターン(2)は、Aもしくは、G。
パターン(3)は、Aもしくは、G、ということになる。
ここでパターン(2)をAと仮定すると、パターン(4)がTということになる。
すると、パターン(3)は、Gということになる。
残ったパターン(1)は、C!
もう一度、整理してみる。
パターン(2)をAと仮定すると、
パターン(1)=C
パターン(2)=A
パターン(3)=G
パターン(4)=T、ということになる。……仮定(1)
同じように、今度はパターン(2)をGと仮定すると、
パターン(1)=T
パターン(2)=G
パターン(3)=A
パターン(4)=C、ということになる。……仮定(2)
2つのケースが考えられる。
仮定(1)と仮定(2)はどちらが正しいのだろうか。
あとは実際のDNAの配列に当てはめて考えてみるしかない。
矛盾なく、合理的に説明できるほうが正しいということになる。
●塩基(3文字言語)
「ニビルの謎」に紹介されている、DNAの3文字言語を並べてみる。
「CGTAGAATTCT……」(P142)。
この並び方を合理的に説明するのは、(仮定1)のほうなのか。
それとも、(仮定2)のほうなのか。
?????
●DNA言語
では具体的に、10進数の(0)から(63)までを、DNAの3文字言語で置き換え
てみる。
ここでは前述(仮定1)に従って、並べてみる。
0……CCC
1……ACC
2……GCC
3……TCC
4……CAC
5……AAC、となる。
同じように、今度は前述(仮定2)に従って、並べてみる。
0……TTT
1……GTT
2……ATT
3……CTT
4……TGT
5……GGT、となる。
どちらが正しいのだろう?
頭の中を整理するため、10進数の(50)(51)(52)を、64卦で表し、さらに
それを3つのパターンに分けてみる。【図5】
八卦とDNAの間には、何か、関係があるのだろうか。
そこでもう一つのヒント。
DNA言語では、「TAA」は、「停止」を意味するという。
これはコンピューターでプログラムを組んだことがある人なら、みな知っていることだが、
プログラムの始めと終わりには、特殊な命令を入れる。
私はベーシック言語しか知らないが、ベーシックでは、「END」を書く。
その「END」に当たる言葉が、DNA言語では、「TAA」という。
この「TAA」を、(仮定1)で翻訳すると、「TAA」は、2進数で「11・10・1
0」となる。
10進数になおすと、「23」。
漢字では、「訟」。
数字を反対に並び替えると、「01・01・11」とすると、「58」。
漢字では、「需」。
今度は「TAA」を、(仮定2)で翻訳すると、「TAA」は、2進数で、「00・0
1・01」となる。
10進数になおすと、「40」。
漢字では、「明夷」。
数字を反対に並び替え、「10・10・00」とすると、「5」。
漢字では、「晋」。
整理してみる。
28……訟
58……需
40……明夷
5……晋
これら4つの漢字の中で、「END」を表すものがあれば、ビンゴー!
しかし残念ながら、「ニビルの謎」によれば、「END(停止)」を表すのは、「9」、
「ごん(「良」の上の点を取った文字)」だそうだ。
●今日はここまで
何か関係がありそうで、ない?
なさそうで、ある?
今日は、しかし、ここまで。
Time Up!
このつづきは、またの機会に書いてみたい。
が、これだけは覚えておいてほしい。
年代を特定するのはむずかしいが、古代中国では、何かとてつもない不思議なことが起き
ていた。
周囲文化とはかけ離れた、突出した科学が存在していた。
文中に書いた、「伏義(「義」の文字は現代漢字を使った)」にしても、調べれば調べる
ほど、不思議な人物(?)である。
興味のある人は、自分で調べてみてほしい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 DNA 八卦 易経
八卦の謎 謎の八卦 伏義 はやし浩司)
2011/11/16追記
【東洋医学(黄帝内経・素問)の謎】
こうした「八卦とDNAの関係」に興味をもったのには、理由がある。
私が書いた本の一部を、ここに紹介する。
(出典は、はやし浩司著『目で見る漢方診断』。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●黄帝内経・地動説
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569491793/" title="img368 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2103/2569491793_
e053d4e7e7_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img368" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2103/2569491793_
e053d4e7e7_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img368" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569491933/" title="img369 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3261/2569491933_
c876f6dd30_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img369" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3261/2569491933_
c876f6dd30_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img369" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569492031/" title="img370 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3171/2569492031_
632e812c56_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img370" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3171/2569492031_
632e812c56_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img370" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569492205/" title="img371 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3091/2569492205_
3e73c2031f_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img371" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3091/2569492205_
3e73c2031f_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img371" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569492373/" title="img372 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3042/2569492373_
b55b00f8ba_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img372" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3042/2569492373_
b55b00f8ba_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img372" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2570317708/" title="img373 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3149/2570317708_
0b8e893718_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img373" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3149/2570317708_
0b8e893718_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img373" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569492725/" title="img374 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3025/2569492725_
787b6aca41_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img374" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3025/2569492725_
787b6aca41_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img374" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569492907/" title="img375 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3064/2569492907_
e798b24dfd_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img375" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3064/2569492907_
e798b24dfd_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img375" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2570318190/" title="img376 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3281/2570318190_
83f4d4229d_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img376" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3281/2570318190_
83f4d4229d_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img376" /></a>
●黄帝は実在したか?
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2570318350/" title="img377 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3109/2570318350_
f01470acb9_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img377" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3109/2570318350_
f01470acb9_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img377" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569493345/" title="img378 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3005/2569493345_
2b80e586d5_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img378" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3005/2569493345_
2b80e586d5_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img378" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2569493501/" title="img379 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3027/2569493501_
9e83a92f70_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img379" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3027/2569493501_
9e83a92f70_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img379" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2570318812/" title="img380 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3107/2570318812_
cd7c1d6745_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img380" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3107/2570318812_
cd7c1d6745_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img380" /></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/2570318946/" title="img381 by
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3067/2570318946_
9f6a04fc0f_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img381" /></a>
bwhayashibw, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3067/2570318946_
9f6a04fc0f_o.jpg" width="729" height="1068" alt="img381" /></a>
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【DNA情報は、64ビット言語で書かれたプログラム】byはやし浩司2011/11/16夜記
+++++++++++++++++++++++++++++
昨日(2011年11月15日)から、DNAについて考えている。
今日で2日目。
ド素人の、そのまたド素人の私が、DNAに興味をもっている。
きっかけは、八卦。
あの八卦は、実はDNA配列を説明したものという説に、興味をもった。
自分なりに検証してみようという気になった。
言うなれば、知的道楽。
で、今朝(2011/11/16)、つぎのような原稿を書いた。
前もって断っておくが、DNAを2進数で表そうとしているのは、世界でも私が最初だと
思う。
あちこちのサイトをのぞいてみたが、DNAを2進数で表した論文は、私が知るかぎりな
い。
だから、おもしろい。
……ということで、昨日、そして今朝につづいて、原稿のつづきを書いてみる。
+++++++++++++++++++++++++++++
●4つの塩基を、2進数で表してみる
昨日、4つの塩基を(ー)と(+)に置き換え、さらに2進数に置き換えるところまで
考えた。
この世界は、現在恐ろしく進歩していて、私がここに書いていることは、英語で言えば、
アルファベットのようなもの。
プロの人が読んだら、私のことを「アホ」と思うだろう。
が、だからといって、遠慮することはない。
私は私。
私の発想で、ものを考えてみる。
で、今朝、4つの塩基について、(−)(+)の置き換え方は2通りあると書いた。
(1)パターン(2)を「A」と仮定するばあい。
(2)パターン(2)を「G」と仮定するばあい。
それについて書いた部分を抜粋してみる。
『パターン(2)をAと仮定すると、
パターン(1)=C
パターン(2)=A
パターン(3)=G
パターン(4)=T、ということになる。……仮定(1)
同じように、今度はパターン(2)をGと仮定すると、
パターン(1)=T
パターン(2)=G
パターン(3)=A
パターン(4)=C、ということになる。……仮定(2)
2つのケースが考えられる。』と。
●遺伝子情報を、2進数で書き換えてみる
ここでいう「パターン」というのは、つぎの4つの組み合わせをいう。
パターン(1)は……(−)(−)
パターン(2)は……(+)(−)
パターン(3)は……(ー)(+)
パターン(4)は……(+)(+)。
ここでは(仮定1)に従って、
パターン(1)=C
パターン(2)=A
パターン(3)=G
パターン(4)=T、としてみる。
すると(C)(A)(G)(T)は、それぞれ、2進数で、つぎのように表せる。
C=(00)
A=(10)
G=(01)
T=(11)
この規則に従って、大腸菌の遺伝子を、2進数で表してみる。
どんなことになるだろうか。
●例題塩基配列:大腸菌由来 RNase HI 遺伝子
大腸菌の遺伝子配列(一部、4501〜5041)は、つぎのようになっている。
4501 taaaaacaag ccacgaattc gccaggcggt tggagccacc cggcaatgtc gtaaaccaca
4561 ggcttaaact tcaacttggt agcctgtatc ttccagtgtg ggattcatcg ccgcggcacg
4621 agccagttca tcacagcgtt cgttttccgg gtgtccggca tggcctttaa cccattccca
4681 tttgatttga tgctgcccca atgcagcatc aagacgttgc cagagatcga cattttttac
4741 tggttttttg tctgcggttt tccagccacg ttttttccag ttatggatcc actgggtgat
4801 accctggcgg acatactggc tgtcggtact caaaatgact tcgcaatgtt cttttaacgc
4861 ctccagcgcg acaatagcgg ccatcaactc catacggttg ttggtggtgc gggtgtagcc
4921 agcgctaaag gttttctcgc gtccgcgata gcgtaaaata gcgccgtaac ccccaggtcc
4981 tggattgccc agacacgaac catcggtgaa aatttctacc tgtttaagca tctctggtag
5041 acttcctgta attgaatcga actgtaaaac gacaagtctg acataaatga ccgctatgag
以上の中の(4501)と(4561)だけを、2進数で置き換えてみる。
(何しろ数が膨大なので……。)
以下が、その結果である。
4501 (11)(10)(10)(10)(10)(10)(00)(10)(10)(01)
(00)(00)(10)(00)(01)(10)(10)(11)(11)(00)
(01)(00)(00)(10)(01)(01)(00)(01)(01)(11)
(11)(01)(01)(10)(01)(00)(00)(10)(00)(00)
(00)(01)(01)(00)(10)(10)(11)(01)(11)(00)
(01)(11)(10)(10)(10)(00)(00)(10)(00)(10)
4561 (01)(01)(00)(11)(11)(10)(10)(10)(00)(11)
(11)(00)(10)(10)(00)(11)(11)(01)(01)(11)
(10)(01)(00)(00)(11)(01)(11)(10)(11)(00)
(11)(11)(00)(00)(10)(01)(11)(01)(11)(01)
(01)(01)(10)(11)(11)(00)(10)(11)(00)(01)
(00)(00)(01)(00)(01)(01)(00)(10)(00)(01)
数字の羅列だけで、まったく意味がわからない。
そこで最初から、3組ずつ、まとめてみる。
全部はできないので、最初から3x10個だけにする。
(11)(10)(10)
(10)(10)(10)
(00)(10)(10)
(01)(00)(00)
(10)(00)(01)
(10)(10)(11)
(11)(00)(01)
(00)(00)(10)
(01)(01)(00)
(01)(01)(11)
これから(かっこ)を取り外してみる。
(111010)
(101010)
(001010)
(010000)
(100001)
(101011)
(110001)
(000010)
(010100)
(010111)
これらの数字を、今度は、10進法で書き改めてみる。
(111010)……58
(101010)……42
(001010)……10
(010000)……16
(100001)……33
(101011)……43
(110001)……49
(000010)…… 2
(010100)……20
(010111)……23
つぎに今度は、これらの10進法の数字に、八卦でいうところの漢字をあてはめてみる。
(111010)……58(需)
(101010)……42(既済)
(001010)……10(蹇)
(010000)……16(師)
(100001)……33(?)
(101011)……43(家人)
(110001)……49(損)
(000010)…… 2(比)
(010100)……20(解)
(010111)……23(訟)
その「END」に当たる言葉が、DNA言語では、「TAA」という。
この遺伝子配列の中では、冒頭にそれがあるのがわかる。
「TAA」は、2進法配列では、(111010)。
10進法に改めると、58、つまり漢字では、「需」。
この「需」というのは、どういう意味なのだろう。
『漢字牧場サイト』では、つぎのように説明する。
『……「需」の復習ですが、巫祝が雨乞いをすることを「需」といいます。そして、その
雨乞いをする巫祝のことを「儒」というのです』(「漢字牧場」より)と。
念のため八卦の表現方法にするため、「(111010)……58(需)」の数字を、逆に
並びかえてみる。
(111010)は、(010111)となる。
これを10進法に改めると、23(訟)となる。
Goo辞書には、「訟……裁判で是非を争う。訴える」(Goo辞書)とある。
「需」も「訟」も、意味の上においては、DNAの3言語の意味とはつながらない?
もしここで「スタート」を表す漢字とつながれば、私は飛び上がって喜んだだろう。
八卦は、DNA言語の意味と一致した!、と。
しかしそういうことは、なさそうだ。
(ガッカリ……。)
が、ここでへこたれてはいけない。
この世界は、先にも書いたように、底なしに深い。
とにかく今夜はここまで。
おもしろかった。
楽しかった。
明日からもまた、DNAについて考えてみたい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 DNA言語と二進数 2進
数 DNA 2進数論 八卦とDNA 3文字言語 DNA言語 2進数 易経 八卦)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 16日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page022.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【英語教育、ひとつの提言】
●小学校での英語教育が今、デッドロックに乗り上げている。
どう乗り上げているかは、みなさんすでにご存知の通り。
そこで私はそれを打開するため、ひとつの方法を提案する。
「英会話」ではなく、「言葉として英語を教える」。
その具体的な方法を、今週は年長児、年中児のみなさんで試してみた。
「英語の前に日本語」とか、「論語を教えろ」という暴論もある。
この方法なら、そういう人たちも、反対をしないはず。
(1)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/i0dpwJH_rLY?hl=ja
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/4M6VA0Yd5Z4?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/yZ-sidBT9DI?hl=ja
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(4)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/cKjOvQ0X3z0?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●八卦とDNA(古代中国の科学と謎)
+++++++++++++++++
昨夜、ワイフが、こう聞いた。
「中国では2進数を使っていたの?」と。
それで私が「そうだよ。が、それだけではない。
あの八卦(はっけ)が、DNA言語と一致
しているという説もある」と説明すると、
心底、驚いた様子をしてみせた。
昨年書いた原稿を、さがしてみる。
+++++++++++++++++
まず、つぎの2表をよくみてほしい。
その上で、以下の文章を読んでくれれば、
ここでいう「八卦とDNAの関係」が、
よくわかるはず。
出典は、『ニビルの謎』(学研)。
+++++++++++++++++
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/64/img866cb8ffzik9zj.
jpeg" width="721" height="777" alt="img221.jpg">
jpeg" width="721" height="777" alt="img221.jpg">
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/65/imga0558262zik8zj.
jpeg" width="699" height="1211" alt="img222.jpg">
jpeg" width="699" height="1211" alt="img222.jpg">
+++++++++++++++++
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
(以下、2010年10月8日Eマガに書いた原稿より)
●中国の二進数(古代中国の大ロマン)
+++++++++++++++++
今、端緒をつかんだばかり。
今までの不勉強が悔やまれる。
まだ不確実な段階だが、5000年以上も
さかのぼる太古の昔、中国に、何と
二進数があったらしい。
(こんなことも知らなかったのか、と
笑われそうだが……。)
もしこれが事実とするなら、私は、今までの
古代観を根底から、作りなおさなければ
ならない。
+++++++++++++++++
●二進数
二進数では、(0)と(1)だけの
数字を使って数を表す。
だからたとえば、0、1、2、3、4、5、6……は、二進数では、
0、1、10、11、100、101、110……となる。
コンピューター言語の基本にもなっている。
それを古代中国では、つぎのように表す。
ワード文書を使って表記するので、たいへんぎこちない書き方になるが、許してほしい。
+++++++++++++
0……
+++++++++++++
1……
+++++++++++++
2……
+++++++++++++
3……
+++++++++++++
4……
+++++++++++++
5……
+++++++++++++
6……
+++++++++++++
つまり横線2本は、(0)を表す。
横線1本は、(1)を表す。
これを冒頭に書いた、二進数と見比べてみてほしい。
念のため、数字をその横に並べて、もう一度、ここに書いてみる。
+++++++++++++
0……
000
+++++++++++++
1……
001
+++++++++++++
2……
010
+++++++++++++
3……
011
+++++++++++++
4……
100
+++++++++++++
5……
101
+++++++++++++
6……
110
+++++++++++++
十進数の「5」は、二進数の「101」になるが、それを横にすれば、
ここに書いたようになる。
こうして6段の線を使えば、何と、0から63までの64個の数を、二進数で
表すことができる。
コンピューターの世界でいう、まさに64ビット!
●易(えき)
漢字には(0)の概念がない。
たとえば、「120」は、「百二十」と表記する。
そういう中国で、どうしてこうした「0」の概念が生まれたか。
しかも二進数。
それだけでも不思議だが、それを知ったのは、つまり中国の二進数を知ったのは、
「易(えき)」。
昔から日本では、『当たるも八卦、当たらぬも八卦』という。
あの「易」。
「易占い」の「易」。
EX-Word(シャープ)には、つぎのようにある。
「周易で、陰陽の(こう)を組み合わせた8つの形象。
自然界、人事界百般の現象を象徴する」(広辞苑)と。
さらにマイペディアには、つぎのようにある。
「(はっか)とも読む。易(えき)による占いの基本となる図形。
乾(けん)、坤(こん)、震(しん)、巽(そん)、(かん・土へんに「欠」)、離、
(ごん)、兌(だ)の8種をいう。
これを組み合わせたのが64卦。
この形を得るために、算木を用意する。
八卦は伏義(ふくぎ)の創案と伝えられる。
易占の基本として、易占と同義にも用いられる」と。
その易の起源については、「易経」の注釈には、つぎのようにある。
「……伏義が天下を支配していたとき、天と見、地を見、鳥獣を見、身近を見、
こうしてその中から伏義は八卦を考案した……」と。
●64ビット
ここでひとつの疑問が生まれる。
「易」は、「占い」なのかという疑問である。
くどいようだが、もう一度、2つの八卦、つまり8x8=64(64卦)を、
今度は、点と線で表してみる。
(左上が、十進数で「0」、3段目、右端が、「14」。)
・・ ーー ・・ ーー ・・
・・ ・・ ーー ーー ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ーー
・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・
ーー ・・ ーー ・・ ーー
・・ ーー ーー ・・ ・・
ーー ーー ーー ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ーー ーー
・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ーー ・・ ーー ・・
ーー ーー ・・ ・・ ーー
・・ ・・ ーー ーー ーー
ーー ーー ーー ーー ーー
・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・
以下、こうして二進数で表現すると、
「63」は、
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
となる。
コンピューターの64ビット言語と同じ!
プラス、驚き!
●黄帝内経(こうていだいけい)
もっともこんなことは、八卦の世界では常識。
もちろん私が発見したことではない。
そこでさらに調べてみると、この64卦は、「4つの塩基から3つを選び出した
DNA言語の単語と一致する」(「ニビルの謎」北周一郎・学研)とか。
ますますおもしろくなってきた。
私も若いこと、黄帝内経(こうていだいけい)という書物にたいへん興味をもった。
3冊も本を書いた。
うち1冊(「東洋医学・基礎編」学研)は、今でも全国の医学部や鍼灸学校で教科書
として使ってもらっている。
あの黄帝内経は、歴史の中で書き換えられるうち、いつの間にか「医学書」として
の体裁を整えてしまった。
が、私はもともとは、天気の運行に関する科学書ではなかったかと考えている。
わかりやすく言えば、天文学に関する書物。
その片鱗は、黄帝内経(素問)の随所に残っている。
『五運行大論篇』もそのひとつ。
それについてはたびたび書いてきたので、興味のある人は、そちらを読んでみて
ほしい。
http://shizuoka.cool.ne.jp/bwhayashi/page055.html
●大ロマン
過去の歴史の中には、何やらとてつもない謎が隠されているらしい。
つまり(現在)は(過去)の上に積み重ねられてできたのではなく、遠い過去に、
すでに(現代)以上の(現代)があったことになる。
ロマンといっても、これ以上のロマンがあるだろうか。
デニケンやシッチンの説に従えば、遠い昔、人類をはるかに超越した知的生物体
が、この地球にやってきた。
そして人類を見つけ、その中に自分たちにDNAを組み込んだ!
それをのちのちの人間に教え伝えるために、「易」を教えた。
……という説は、一見、荒唐無稽に思えるが、しかしありえない話ではない。
ないことは、この「易」をみてもわかる。
この問題については、もう少し情報を集め、理解を深めてから書いてみたい。
2010/09/15
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 八卦 易 伏義 古代中国の二進数 2進数 64卦)
Hiroshi Hayashi+++++++Sep. 2010++++++はやし浩司
【易経と64卦】
●易経の二進数(古代中国の大ロマン)
+++++++++++++++++
今、端緒をつかんだばかり。
今までの不勉強が悔やまれる。
まだ不確実な段階だが、5000年以上も
さかのぼる太古の昔、中国に、何と
二進数があったらしい。
(こんなことも知らなかったのか、と
笑われそうだが……。)
しかもその配列の仕方は、(漢字との意味の符合性において)、
DNAの配列と同じという。
もしこれが事実とするなら、私は、今までの
古代観を根底から、作りなおさなければ
ならない。
もちろんこの説を鵜呑みにするわけにはいかない。
それが正しいかどうか、自分で検証してみる
必要がある。
「根底から作りなおす」というからには、
それなりの確信が必要である。
本当に、「易」は、「DNA」の配列と関係が
あるのか?
+++++++++++++++++
●二進数(PART2)
二進数では、(0)と(1)だけの
数字を使って数を表す。
だからたとえば、0、1、2、3、4、5、6……は、二進数では、
0、1、10、11、100、101、110……となる。
コンピューター言語の基本にもなっている。
それを古代中国では、つぎのように表す。
http://www.flickr.com/photos/86343436@N00/4996382953/
<src="http://farm5.static.flickr.com/4104/4996382953_f02920464f.jpg" width="353"
height="500" alt="img058" />
●まずはじめに……(国立がんセンターのHPより引用)
『……遺伝子が設計図だとすると、どのような言葉(言語)で書かれているのでしょう
か。遺伝子は、物質としてはDNAと呼ばれる分子からできていますが、この DNAは「A、
G、C、T」という4つの「塩基」の並びでできています。
言語というのは英語であればアルファベット26文字、日本語であれば平仮名50音の組み
合わせでつくられますが、遺伝子の場合には、この4つの文字からなる遺伝子の言語で書
かれているということになります。人間ではこのA、G、C、T という文字が30億個並ん
で遺伝子全体をつくっています。
比喩的にいうと、4つの文字の配列によりつくられた、意味のあるひとつひとつの「文章」
がひとつひとつの「遺伝子」に相当し、ヒトの場合、そのような遺伝子が40,000個ぐらい
あるといわれています。
ある生物がもつすべての遺伝子、人間なら人間のすべての遺伝子を全部ひっくるめて「ゲ
ノム」といいます。遺伝子を句点「。」で区切られたひとつの文章だとすれば、文章が集ま
った一冊の本がゲノムであるといえます。遺伝子が一本の木だとすると、その木が集まっ
た森がゲノムにあたります』(以上、国立がんセンターHPより)。
●「易経」の二進数
●赤ワク
この中で赤ワクで囲んだのは、上下3本ずつが、同じ配列になったものである。
そこでさらに、これら64のパターンを、8つのグループに分けてみる。
(0)と(1)の組み合わせは、8種類ある。
こういうグループ分けに、とくに意味はない。
(A)上部3本が、(000)のグループ
(B)上部3本が、(001)のグループ
(C)上部3本が、(010)のグループ
(D)上部3本が、(011)のグループ
(E)上部3本が、(100)のグループ
(F)上部3本が、(101)のグループ
(G)上部3本が、(110)のグループ
(H)上部3本が、(111)のグループ
8つのグループに、それぞれ8つの組み合わせがある。
合計すると、8x8で、64種類ということになる。
●DNA言語も64語
ところでDNA言語は、A(アデニン)、G(グアニン)、C(シトシン)、
T(チミン)という4種類の塩基が基本になっている。
これらの塩基が鎖状に連なって、遺伝子情報を伝える。
一見無秩序に見える塩基情報だが、実際には、A、G、C、Tの4つの塩基から、
3つを取り出し、その組み合わせによって、64種類の言葉が生まれることがわかって
いる。
AAA、AAG、AAC、AAT、AGA、AGG,AGC,AGT……TTT、と。
『易経の謎』(光文社)、『ニビルの謎』(学研)によれば、こうした遺伝子言語は、
そのままDNA言語と一致するという。
並び方だけではない。
意味まで、一致するという(『ニビルの謎』)。
たとえば「DNA言語の(ATG)は、「開始」を意味するが、これに対応する
八卦は、「かん(土偏に欠)」で、これも「開始」を表す。
DNA言語の(TAA)は、「停止」を意味するが、これに対応する八卦は、「ごん」で、
これも「停止」を表す」(『ニビルの謎』)と。
上述、「易経の二進数」のうち、(18)(010010)が、「かん」、
(9)(001001)が、「ごん」にあたるという。
しかし自分で改めて検証してみると、つじつまが合わなくなる。
(1)と(0)の組み合わせは、
(00)(01)(10)(11)の4つである。
この4つを、どう「A」「G」「C]「T]と結びつければよいのか?
たとえば、
10……「A」
01……「G」
11……「C」
00……「T」とすると、
「ATG」は、「10・00・01」となる。
並び方を反対にすると、つまり「GTA」にすると、「01・00・10」となり、
たしかに「かん」となる。
が、同じように「TAA」は、「AAT」にすると、「10・10・00」となり、
「ごん」にならない。
「ごん」は、二進数では、「00・10・01」である。
(「00・10・10」なら、つじつまが合うのだが……。)
私の解釈の仕方がまちがっているのだろうか。
あるいはどこかまちがっているのだろうか。
これら2冊の本だけではよくわからない。
●4つの組み合わせx4通り
わかりやすく言えば、「A」「G」「C」「T」と、(00)(01)(10)(11)を、
どう結びつけるかということ。
これがうまく結びつけば、中国の二進数は、まさにDNA言語そのものを表している
ことになる。
(00)は、「A」なのか。
「G」なのか。
「C」なのか。
それとも「T」なのか。……(1)
(01)は、「A」なのか。
「G」なのか。
「C」なのか。
それとも「T」なのか。……(2)
(10)は、「A」なのか。
「G」なのか。
「C」なのか。
それとも「T」なのか。……(3)
(11)は、「A」なのか。
「G」なのか。
「C」なのか。
それとも「T」なのか。……(4)
そこでヒントとなるのが、DNAが複製されるときの性質、つまり「A」は「T]と
のみ結合し、「G」は「C」とのみ結合するという性質。
これを二進数と組み合わせてみると、興味深い事実が浮かびあがってくる。
(00)と(11)の関係。
(01)と(10)の関係。
これらは、数字の上では補完関係にあることがわかる。
仮に(00)を「A」とすると、(11)は「T」ということになる。
同じように(01)を「G」とすると、(10)は「C」ということになる。
この仮定の上で、もう一度、表を作り直してみる。
それがつぎの表ということになる。
00……「A」
01……「G」
10……「T」
11……「C」
仮にこの配列で、中国の二進数を並べ直してみると、つぎのようになる。
00……AAA(00・00・00だから、AAAとなる。)
01……AAG
02……AAT
03……AAC
04……ATA
05……AGG
06……AGT
07……AGC
08……ATA
09……ATG(00・10・01だから、ATGとなる。TAAにならない)(ごん)
10……ATT
11……ATC
12……ACA
13……ACG
14……ACT
15……ACC
16……GAA
17……GAG
18……GAT(01・00・10だから、GATとなる。ATGとならない)(かん)
????
別の組み合わせを考えてみる。
というより、上記(1)(2)(3)(4)の4つの組み合わせを、総当たり的に
確かめてみる。
「9」の「ごん」で、「TAA」に、「18」の「かん」で、「ATG]になればよい。
そういう組み合わせは、あるのか?
●矛盾
もう一度、数字を並べてみる。
「9」(ごん)……(00・10・01)……「TAA」
「18」(かん)…(01・00・10)……「ATG」
これらの数字(二進数)に、「A」「G」「C」「T」を当てはめてみる。
いわば暗号解きのパズルのようなものだが、一見して共通性がないのがわかる。
(01)が「A」で、(00)が「T」ということまでは、わかる。
が、そのほかは、矛盾する。
で、ここに先にあげた、補完関係を応用してみる。
(「補完関係」といっても、私が勝手に仮説として考えたものにすぎないが……。)
(01)が「A」とすると、(10)が「T」ということになってしまう。
つまりまたまた矛盾してしまう。
(01)が「A」とすると、「T」は、(10)でなければならない。
アアアア!
●謎への再挑戦
もう一度、『ニビルの謎』を読んでみる。
繰り返しになるが、許してほしい。
この壁を乗り越えないと、謎を解くことができない。
「……DNA言語の(ATG)は、「開始」を意味するが、これに対応する
八卦は、「かん(土偏に欠)」で、これも「開始」を表す。
DNA言語の(TAA)は、「停止」を意味するが、これに対応する八卦は、「ごん」で、
これも「停止」を表す」(『ニビルの謎』)と。
そこにはたしかに(ATG)は、(かん)、(TAA)は(ごん)と書いてある。
(かん)は、二進数で、(01・00・10)。
(ごん)は、二進数で、(00・10・01)。
この2つを並べてみると、(00)は、「T」ということになる。
両者が共通にもっている(10)、あるいは(01)は、「A」ということになる。
残ったのは、この両者にない、(11)。
この(11)は、「C」ということになるのか?
となると、「G」は、(10)と(01)のどちらなのか?
「A」が(10)なら、「G」は、(01)、
「A」が(01)なら、「G」は、(10)ということになる。
一応、ここまでを、一覧表にしてみる。
10、あるいは01……「A」
01、あるいは10……「G」
11……「C」
00……「T」
ほかに手がかりはないのか?
ということで、今、あちこちをネットでサーフィンしながら、調べてみた。
が、私が調べたところ、それに関する情報は手に入らなかった。
「A」は、(10)なのか、(01)なのか?
それさえ決まれば、易経の二進数と、DNAの関係が、少しだけだが浮かびあがって
くる。
……が、ここでタイプアップ!
仕事の準備をする時間になった。
このつづきは、またの機会にしたい。
(2010年9月17日、午前10時)
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 易経の謎 中国の二進数 2進数 DNAの謎 DNAと易経 ニビ
ルの謎)
【注】今回『ニビルの謎』(学研)という本を参考にさせてもらったが、私自身は、
「ニビル」なる惑星については、まだ半信半疑。
真夏の夜のロマンのひとつにしか考えていない。
興味をもったのは、その中に書かれていた「二進数」、つまり易経でいう「64卦」。
そこに「64卦は、DNA言語と関係がある」と書いてあったので、興味をもった。
どうか誤解のないように!
Hiroshi Hayashi+++++++Sep. 2010++++++はやし浩司
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●11月15日(2011)
今日は、友人にメールを書くことから始まった。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
Good morning, D!
It is a bit cold morning but I don't need a heater yet.
The temperature is now 17 C degrees now.
It is 5:16 AM in the morning.
I woke up this morning earlier than usual.
Akiko and I are well and there seems to be no problems so far for us.
But we have many as a matter of fact.
The best way to live happily is just to forget them and to go my own way.
How are you?
お早よう、D君!
少し寒いが、まだヒーターは必要ない。
今、気温は17度。
午前5時16分。
今朝はいつもより早く起きた。
晃子と私は元気で、ぼくたちにとって、何も問題がないように見える。
が、実際には、たくさんの問題をかかえている。
幸福に過ごすための最善の方法は、それらをただ忘れ、自分の道を行くことだ。
元気か?
I had a small trouble with a doctor yesterday
and it made me feel very bad.
But now I am recovering from it.
昨日、ある医師とトラブルがあった。
それが気分を悪くした。
が、今は、回復しつつある。
Whatever I am I have no choice but to go my own way.
Since this is the life of mine and I have no other way to go.
This is why I woke up this morning earlier and started my job.
I miss those days with you and Bob in Melbourne this March.
自分が何であれ、ぼくは自分の道を行くしかない。
これがぼくの人生だし、ほかに進むべき道もないから。
これが今朝、早く起き、仕事を始めた理由。
3月に、君とB君にメルボルンで会った日々が、なつかしい。
Hiroshi
浩司
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●スペイン危機
++++++++++++++++
ギリシャ、イタリアにつづいて、
スペインの金融危機が表面化してきた。
今朝のBloombergは、つぎのように伝える。
『……イタリアの銀行最大手、ウニクレディトは6.2%の値下がり。
同行は最大75億ユーロ相当の新株発行計画を明らかにした。
スペインも借り入れコストが上昇し、ビルバオ・ビスカヤ・
アルヘンタリア銀行(BBVA)を中心に銀行株が下げた。
ドイツの建設会社ホッホティーフも大幅安。
空港運営事業の売却の遅れが売り材料となった』
『スペイン10年債と独10年債のスプレッドは、
36bp広がり432bpとなった。
スペイン30年債利回りは6.74%に達し、
ブルームバーグがデータ収集を開始した1998年以来の最高となった。
CMAによれば、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)で、
スペイン国債の保証コストは21bp上昇し、441bpと、
過去最高を記録した』(以上、Bloomberg 2011・11・15)と。
注意深く読むと、スペインの金融危機の本質がよくわかる。
つぎの1点に注目してほしい。
(1)ドイツの建設会社ホッホティーフも大幅安
どうしてスペインの金融危機なのに、ドイツの建設会社の株が大幅安になったか。
理由は言わずと知れた、乱開発と過剰融資。
スペインは、低金利のユーロをドイツから借り、スペインの地中海沿岸で、リゾート開発
を推し進めた。
ドイツ人のための、ドイツ人によるリゾート開発。
それを後押ししたのが、言うまでもなく、ドイツ。
ドイツ銀行。
ドイツは自国の経済が好調なことをよいことに、スペインにユーロを貸しつづけた。
言うなれば、ドイツはスペインで、バブル経済を発生させた。
その結果が、これ。
平たく言えば、自業自得。
が、ドイツはそれではおもしろくない……ということで、現在、メンケル首相が慌てふ
ためいている。
(肝心のスペインは、のんきなもの。
もともとドイツは、EU内部では、嫌われ者。
いつも大きな顔をしている。)
ギリシャ問題は解決した……と考えている人は多い。
しかし実際には、何も解決していない。
借金に借金を重ねる、自転車操業。
イタリアにしても同じ。
しかし本当の問題はスペインにある。
借金の規模がちがう。
ギリシャが倒れれば、フランスは肺炎。
スペインが倒れれば、ドイツは肺がん。
そこでドイツとフランスは、この日本にあれこれ、言い寄ってきている。
最後のババは、日本に引かせよう、と。
「ドイツの建設会社ホッホティーフも大幅安」という一文の中には、そういう現実が隠さ
れている。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●はやし浩司の独り言
日本に残された道……結局は大増税しかないんだろうね。
歳出カットといっても、人件費の削減は無理。
役人の力が強すぎる。
結局は、行政サービスの低下。
今回のEUの金融危機について、アメリカが音無しの構えを見せているのは不気味。
が、考えてみればそれもそのはず。
EUは、もともと、アメリカの一局支配に対抗して生まれた。
ユーロが強くなればなるほど、相対的にドルが弱くなる。
が、ユーロが弱くなれば、再びドルの時代が戻ってくる。
中国がギリシャを助け、スペインを助けた。
なぜ中国なのか……という理由も、これでわかるはず。
そのアメリカも神経質な動きを見せている。
たった0・1%、失業率が下がっただけで、株価は大上昇。
『向こうの2年間の経済成長率予想が下方修正され、失業率見通しも悪化した』(ロイタ
ー・11・14)というニュースが流れただけで、今度は大暴落。
世界はたった1日で変わるわけではないのに、1日ごとに乱高下。
もうめちゃめちゃ。
日本はどうなるんだろう……と考えたところで、思考停止。
これだけ借金が多いと、身動きが取れない。
打つ手もない。
世界の激流の中で、流されるまま、あたふたとするしかない。
つまりもうなるようにしか、ならないということ。
が、これだけは忘れてはいけない。
結局は、最後の最後にババを引くのは、私たち一般庶民ということ。
「どう生きるか」ではなく、「どう貧困に耐えるか」。
今から、それを覚悟するしかない。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 14日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page021.html
●まぐまぐプレミアの購読料は、月額300円です。よろしかったら、お願いします。
********安全は確認しています。どうか安心して、お読みください*****
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●11月18日(じっと我慢するしかない)
+++++++++++++++++++++
規則正しい生活は、健康の要(かなめ)という。
しかし不規則という規則もあるのでは?
万事、自然体。
そのことは、犬のハナを見ていると、よくわかる。
ハナは、いつも庭で放し飼いになっている。
しつけらしいしつけは、いっさい、していない。
そのハナ……すでに老齢ということもあるが、
毎日、好き勝手なことをしている。
朝も、昼も、夕方も、起きたいときに起き、
眠りたいときに眠っている。
基本的には、天気任せ。
昨日のように、小春日和(びより)の日は、
芝生の上で、ずっと横になっている。
暑くなったら、そのまま小屋へ。
人間の年齢に換算すると、100歳を超えている。
もう22歳を超えた。
だから……というわけでもないが、私たち夫婦は、
若いときから、不規則であることを、とくに
気にしたことはない。
昨日は8時、起き。
今朝は5時、起き。
起床時刻ですら、めちゃめちゃ。
++++++++++++++++++++++
●EUの金融危機
私は、言うなれば河原の小石のような人間。
そんな人間が、横を流れる川の心配をしても、どうしようもない。
どうにもならない。
が、だからこそ、おかしなことに、川の流れがよくわかる。
どちらの方向に向かって、どのように流れているか、それがよくわかる。
恐らく川に呑み込まれてしまった人には、それがわからないだろう。
川の中で溺れるまま、右往左往している。
現在のEUの金融危機を、一言で説明すれば、そういうことになる。
●貸し手と借り手
お金(マネー)の力は、恐ろしく弱い。
人間と人間をつなぐ力(パワー)は、ほとんどない。
貸したほうは、「相手は感謝しているはず」と考える。
が、借りたほうは、一時的。
しばらくすると、それが当たり前になってしまう。
さらにしばらくすると、今度は、貸した方が逆恨みされるようになる。
「オレたちが貧しいのは、お前たちのせい」と。
これには友人、知人もない。
親類、親、兄弟もない。
もちろん国もない。
現在のドイツとスペインの関係は、まさに、それ。
ひとり勝ちのドイツ。
借金漬けのスペイン。
強い経済力を背景に、ドイツはスペイン国内でしたい放題。
豪勢なリゾート開発に、豪勢な生活。
肝心のスペイン人は、それを指をくわえて見ているだけ。
●慌てまくるドイツとフランス
貸し手と借り手。
その借り手が金融危機に陥った。
こういうケースのばあい、慌てまくるのは、貸し手側。
借り手側ではない。
借り手側のほうは、むしろ、のんびりとしたもの。
「破産、結構」と。
むしろ破産したほうが、借金が帳消しになって、気が楽になる。
現在のギリシャ、イタリアが、その立場。
食べ物とワインと、明るく輝く太陽があれば、それでよい。
そこはまさしく、「オーソレミオ」の世界。
あとはバックギャモンでもして、一日を過ごす。
が、ドイツとフランスは、事情がちがう。
つまり貸し手側。
●ドイツvsフランス
フランスは、ユーロ(札)の大増刷で、難局を乗り切ろうとまたまた言い出した。
が、ドイツは、「ナイン(NO)!」。
そんなことをすれば、ユーロの価値が暴落してしまう。
ユーロを大量にもつドイツとしては、それに納得するはずがない。
かたやフランスはといえば、ギリシャ→イタリアとつづいて、自分の足下(もと)が燃
えだした。
このまま行けば、貸し金の回収どころか、自分まで破産してしまう。
だからドイツに向かって、なりふり構わず、こう言い出した。
「ユーロを大増刷しよう」と。
●アメリカも……
傍観、静観、無視……。
アメリカはかねてより、EU経済をよく思っていなかった。
ユーロが台頭すればするほど、ドルの価値がさがる。
自分たちの立場が、相対的に弱くなる。
だから今まで、傍観、静観、無視を決め込んでいた。
が、ここにきて、火の粉が大西洋を越えて、自分たちにも襲いかかってきた。
放っておけば、自分たちまで燃えてしまう。
それもあって、数日前から、オバマ大統領の発言が、目立って多くなった。
「お前たちで、何とかしろ!」と。
で、こういうとき「ファイア・ウォール(防火壁)」という言葉を使うらしい。
私はずっと、これをパソコン用語と思っていた。
が、経済用語にもなっていた。
つまりオバマ大統領は、「防火壁を作れ」と。
アメリカの株価は、ささいなことに一喜一憂し、大冒頭、大暴落を繰り返している。
つまり大揺れ!
●大国意識
日本よ、大国意識は、捨てろ。
お人好しは、やめろ。
この場に及んで、フランス国債やドイツ国債を買い込んで、どうする。
どうなる。
……どうにもならない。
一時的に日本の金融機関を救済することができても、それは救済というより「避難」。
世界の動き……つまり川の流れは、すでに激流に変わりつつある。
濁流でもよい。
今や、それが大洪水となって、日本をも、巻き込もうとしている。
どうしてこんな簡単なことがわからないのか。
アメリカにペコペコしていれば、それですむという時期は、とっくの昔に過ぎた。
●狂騒曲
お金(マネー)が、ゲームの対象になっている。
称して「マネー・ゲーム」。
汗水流し、働いて稼ぐお金もマネーなら、ゲームで稼ぐお金もマネー。
が、桁がちがう。
2桁も、3桁も、ばあいによっては、4桁もちがう。
そこらの若造が、パソコンの画面を見つめながら、億単位のマネーを買ったり売ったり
している。
その異常性。
つまり、狂っている。
狂ったまま、世界を騒がせている。
まさに「狂騒曲」!
いくら資本主義社会とはいえ、こんなアホなことが、野放しになっていて、よいのか。
「ヘッジファンド」と言えば、聞こえはまだよい。
しかし中身は、博徒。
バクチ屋。
今、そのバクチ屋に、世界が振り回されている。
●大洪水
長引けば長引くほど……すでに8月3日から4か月になろうとしているが、その波紋は
周辺国に及ぶ。
……及び始めた。
ハンガリーなどの周辺国はもちろん、新興国から、中東へ。
そしてこのアジアまで……。
へたにあがくから、みなが、迷惑する。
傷口が深くなる。
さっさとEUを一度、解体し、あぶない国は破産させる。
またそのときが来たら、EUを再興させればよい。
一瞬の激流なら、まだ何とかなる。
しかし大洪水となると、そうはいかない。
日々に世界は、疲弊する。
その疲弊がこわい。
●円高
円売り介入をつづける日本政府と日銀。
しかしそれ以上の円が、買われている。
その差額が、昨日(11・17)あたりで、1兆円とも言われている。
(1兆ドルだったかもしれない。記憶があいまいで、ごめん!)
狂ったバクチ屋どもが、さらなる円高を見越して、円を買いつづけている。
が、それよりも恐ろしいのは、そのあと、つまり円が行き着くところまで行ったあと、
今度はその揺り戻しが始まること。
円が逆流し、日本中が、円でダブダブになる。
猛烈な円安に、日本は見舞われる。
これは可能性の問題ではない。
確実に起こる、つぎの事実。
が、そのとき、日本の命運が決まる。
1000兆円以上とも言われる国の借金が、日本経済の息の根を止める。
それがいやなら、今すぐ、超緊縮予算を組み、大増税をするしかない。
役人の数を3分の1に減らし、給料も50%カットする。
消費税を20%にする。
が、現実的には、それは不可能?
だったら、私たち(小石族)は、自ら覚悟するしかない。
大洪水の中で、身を寄せ合って、じっと洪水が収まるのを待つ。
川のいちばん底で、静かにしていれば、流されることもない。
大恐慌は大恐慌だが、2〜3年もすれば、またその先に光が見えてくる。
それまでじっとがまんするしかない。
さあ、今すぐ、その準備を始めよう!
(1)預金の現金化(失業しても、2〜3年は生きられるようにしておく。)
(2)そのうちの半分は、金、プラチナなどへの、現物資産化。(貴金属は現物でもつ。)
(3)こういうとき、いっぱしの投資家気取りで、株や外債に手を出すと、大やけどをす
る。
(この(1)〜(3)は、あくまでも参考的意見。あとの判断は、(つまりリスク負担は)、
自己責任で!)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【通俗性とどう闘うか】(金権教に毒されると……)
++++++++++++++++++
コンディションは、よくない。
朝からイライラする。
イライラというより、「ピリピリ」。
Ca不足かもしれない。
天候のせいかもしれない。
忙しいこともある。
昨夜も、遅くまで、講演会用のレジュメづくりをした。
++++++++++++++++++
●不快な男
そういえば、少し前、ある男から電話がかかってきた。
通俗を「地」で這うような男である。
私より、5、6歳、年下。
私が、「毎晩仕事が終わるのは、9時半です」と話すと、こう言った。
「林さん、そんなに稼がなくてもいいんじゃない」と。
私はその言葉を聞いた瞬間、返答に困ってしまった。
「はあ〜」と言っただけで、黙ってしまった。
何もその男を責めているのではない。
その男は、一見、正当なことを言いながら、実は、自分の心の中を吐露した。
つまりその男は、(仕事)を、瞬間、(金)に結びつけた。
それだけ(金)に執着しているからに、ほかならない。
それがわからなければ、逆の立場で考えてみればよい。
もしあなたなら、こういうケースのばあい、何と答えるだろうか。
久しぶりに、割と仲がよい知人に電話をした。
が、留守だった。
で、夜遅く、電話した。
9時ごろになって、やっと連絡が取れた。
その相手が、こう言った。
「やっと今、仕事が終わったところで……」と。
いろいろな返事の仕方がある。
(1)「お疲れ様」と相手をねぎらう
(2)「体をこわすないでよ」と相手の健康を心配する。
(3)「がんばれよ」とエールを送る。
返事の言い方はさまざまある。
そのつど、こちら側の心と反応する。
自分が睡眠不足であったりすると、「眠くないか?」などと言うかもしれない。
しかし「そんなに稼がなくてもいいんじゃない」は、ない?
つまりその男はそう言いながら、自分の内部に潜む下劣性をさらけ出していた。
●他山の石
こういう例は多い。
ひとつには、自分の心の中を、思わず吐露してしまうケース。
もうひとつは、醜い自分を、思わぬところで、さらけ出してしまうケース。
先に書いた「通俗」というのは、それをいう。
では、どうするか。
こういう不快感をどこかで味わったら、即、反面教師にする。
他山の石でもよい。
他山の石というのは、『他山の石以て玉を攻(おさ)むべし』という意味。
見本といっても、悪い見本。
が、私にも、こんな失敗がある。
30代のころのことだったと思う。
ある日、オーストラリアの友人にこう聞いたことがある。
「君の給料はいくらだ」と。
ご存知の人も多いかと思う。
オーストラリア人やアメリカ人に、給料を聞くのはタブー中のタブー。
当時の私は、金権教の信者(=亡者)。
反対に私の方が、叱られてしまった。
●金権教
通俗と、どう闘っていくか。
自分の中の(通俗)である。
通俗であることが悪いというのではない。
しかし通俗とは、心のどこかで一線を引く。
そうでないと、その人の人間性は、一気に下劣化する。
その一例というわけではないが、私が嫌いな番組に、『なんでも鑑定団』というのがある。
当初は「おもしろい」と思って見ていたが、やがて自分の心の中に、別の見方が育ってい
るのを知った。
芸術の価値すら、金銭的価値で置き換えてみる見方である。
「この絵は、100万円の価値があるから、すばらしい絵」と。
それについては、以前にも書いたことがある。
原稿をさがしてみる。
++++++++++++++++++はやし浩司
●【金権教】(2009年6月に書いた原稿より)
●ぜいたくな悩み
+++++++++++++++++++++
悩みといっても、本来、悩むような問題ではないかもしれない。
ぜいたくな悩みということは、よくわかっている。
この地球上では、約3分の1の人たちが、飢餓状態に
あると言われている。
食べるのもなくて、困っている。
が、そういう中、私は今、ときどきこんな選択に迫られる。
「食べたら損なのか?」「食べなければ損なのか?」と。
+++++++++++++++++++++
●レストランで……
昨日、ワイフの誕生日祝いということで、郊外のホテルで昼食をとった。
フルコースの半分の、ハーフコースというのを注文した。
肉料理を省略したコースをいう。
そのコースのあと、最後にデザートが出た。
最近はやりの、バイキング・デザートというのである。
10種類くらいのケーキから、好きなのを選んで、いくらでも食べられる。
私はイチゴ系のケーキ、ワイフはオレンジ系のケーキを選んだ。
1個というよりは、ひとかけらと言ったほうがよい。
小さなケーキだった。
で、それを食べ終わるころ、ボーイが、「ほかに、どれになさいますか?」と
聞いてきた。
そのときのこと。
またあの選択が頭の中を横切った。
「食べたら損なのか?」「食べなければ損なのか?」と。
私は現在、ダイエット中。
昨日の朝、体重計に乗ってみたら、目標にしていた63キロ台!
この1か月半で、約5キロの減量に成功した。
「何としても、今の体重を維持しよう」と、心に決めていた、その矢先のことである。
私はググーッとわいてくる食欲を懸命に抑えながら、「もう結構です」と答えた。
「食べたら損」のほうを、選択した。
●ムダ肉
脂肪細胞というのは、わかりやすく言えば、エネルギーの貯蔵庫のようなもの。
ノートパソコンにたとえるなら、バッテリーのようなもの。
たとえば数日おきくらいにしか食べ物にありつけないような環境なら、脂肪細胞も
必要。
脂肪細胞にエネルギーを貯蔵しておく必要がある。
しかし現在の日本のように、1日3食、もしくは2食、食べるのが当たり前になって
いるような国では、脂肪細胞にエネルギーを貯蔵しても、意味はない。
その必要もない。
必要なエネルギーは、そのつど摂(と)ればよい。
それに体は軽ければ軽いほどよい。
運動量もふえるから、筋肉も鍛えられる。
それが良循環となって、肉体は健康になる。
ポテポテとした肉体を引きずっていて、よいことは、何もない。
が、どうしてか、「食べなければ損」という意識が、いつも働く。
どうしてだろう?
つまりこんなところでも、マネーの論理が働く。
「同じ値段なのだから、たくさん食べなければ損」と。
言い換えると、その人の健康観まで、マネーに毒されている(?)。
これは忌々(ゆゆ)しき問題と考えてよい。
●金銭的感覚
が、「損とは何か?」「得とは何か?」、それを考えていくと、
その先が、灰色のモヤに包まれてしまう。
何をもって、人は、得といい、何をもって、人は、損というのか?
いちばんわかりやすい例でいえば、金銭的な損と得がある。
数字が大きくなることを、「儲けた」といい、数字が小さくなることを、
「損した」という。
しかしそれにも限界がある。
金(マネー)に毒されすぎると、何が大切で、何がそうでないか、
わからなくなってしまう。
ときに人の命まで、金銭的感覚で、判断してしまう。
自分の人生まで、金銭的感覚で、判断してしまう。
●○○鑑定団
私の大嫌いなテレビ番組に、『○○鑑定団』というのがある。
いろいろな人が、いろいろなものをもちよって、その値段を
「鑑定」するという、あの番組である。
しばらくああいう番組を見つづけていると、ものの価値まで、金銭的感覚で、
判断してしまうようになる。
(……なってしまった。)
「この絵は、200万円の価値があるから、すばらしい絵だ」
「あの絵は、10万円の価値しかないから、つまらない絵だ」とか、など。
その絵にしても、有名人(?)の描いたものほど、値段が高い。
が、もし、ものの価値のみならず、美術的価値まで、金銭的感覚で判断する
ようになってしまったら、「美術とはいったい、何か?」ということに
なってしまう。
モノならまだしも、自分の健康となると、そうはいかない。
またそうであってはいけない。
●社会のCPU(中央演算装置)
話は少し脱線する。
世の中には、「カルト」と呼ばれる、宗教団体がある。
正確には、「狂信的宗教団体」と言うべきか。
で、そういう団体に属する信者の人たちと話していて、いつも不思議に思うことがある。
10年前に、世間を騒がせた、あの宗教団体の信者の人たちにしても、そうだ。
会って、個人的に話をしている間は、ごくふつうの、どこにでもいるような人。
そういう狂信的な団体に属しているから、どこかおかしいのでは(?)と思って観察して
みるのだが、そういうことはない。
どこもおかしくない。
冗談も通ずる。
ふつうの常識も、もっている。
が、全体として、つまりその団体を全体としてみると、やはりおかしい(?)。
集団となったとき、反社会的な行為を繰り返す。
団体の教義を批判したり、否定したりすると、彼らは猛烈にそれに対して反発する。
あるいはそのまま私たちを、ワクの外にはじき飛ばしてしまう。
……これは「カルト」と呼ばれるカルト教団の話である。
が、実は、私たちも全体として、同じような宗教を信仰しているのではないか。
「マネー教」というカルト教である。
その信者でいながら、全体がそうであるから、それに気がつかない。
そういうことは、じゅうぶん考えられる。
つまり社会のCPU(中央演算装置)そのものが狂っているから、その(狂い)すら、
自分で気がつくことができない。
●私の子ども時代
このことは、私の子ども時代と比較してみてもわかる。
当時の特徴を2つに分けるとこうなる。
(1) 戦時中の軍国主義的な色彩が、まだ残っていた。
(2) その時代につづく金権主義の色彩は、まだ薄かった。
軍国主義的な色彩というのは、たとえば教育の世界にも強く残っていた。
(学校の先生)にしても、戦時中のままの教え方をする人もいた。
反対に民主主義的な(?)教え方をする人もいた。
それがおもしろいほど、両極端に分かれていた。
一方当時は、まだ牧歌的な温もりが残っていた。
私の父にしても、将棋をさしながら、仕事をしていた。
将棋に熱中してくると、客を待たせて将棋をさしていたこともある。
客が、その将棋に加わることもあった。
そういう時代と比べてみると、たしかに(現代)はおかしい。
狂っている。
が、みな狂っているから、それが見えない。
わからない。
●飽食の時代の中で
アメリカ(USA)では、肥満をテーマにしたエッセーを書くのは、タブーだそうだ。
それだけで、「差別」ととらえられるらしい。
しかしご存知のように、アメリカ人の肥満には、ものすごいものがある。
どうすごいかは、見たとおり。
あの国では、肥満でない人をさがすほうが、むずかしい。
で、最近、私は日本もそうなりつつあるのを、感ずる。
アメリカ人型の肥満がふえているように思う。
飽食のせいというよりは、アメリカ型食生活の影響ではないか。
ともかくも、そういった人たちは、よく食べる。
このことは以前にも書いたが、浜松市の郊外に、バイキング料理の店がある。
ランチタイム時は、1人、1200円で、食べ放題。
そういうところで食事をしている人を見ると、まさに「食べなければ損」といった感じ。
デザートのケーキでも、一個を一口で食べている。
パク、パク、パク……の3回で、3個!
食事を楽しんでいるというよりは、食欲の奴隷。
「食べる」というよりは、「食べさせられている」。
そんな印象すら、もつ。
もちろんそういう人たちは、例外なく、太っている。
歩くのも苦しそう。
しかしそういう人ほど、「食べたら、損」なはず。
食べれば食べるほど、健康を害する。
が、そういう人たちほど、よく食べる。
●散歩の途中で
私たちの日常生活は、マネーにあまりにも毒されすぎている。
それに気づかないまま、毒されすぎている。
芸術も文化も、マネー、マネー、マネー。
ついでに健康までも、マネー、マネー、マネー。
その一例として、「食べなければ損」について考えてみた。
しかしどうして「食べなければ損」なのか。
たまたま今日、ワイフと散歩しながら、途中でラーメン屋に寄った。
今度から「ランチ・メニュー」が始まった。
ラーメン+ギョーザ+ミニ・チャーハンの3点セットで、580円。
安い!
私は、チャーシュー丼を注文した。
ワイフは、ランチセットを注文した。
が、とても2人で食べられるような量ではない。
ランチセットを2人で分けても、まだ量が多すぎる。
しかし1人分の料理を、2人で分けてたべるというのも、気が引ける。
で、2人分、頼んだ。
が、そこでもあの選択。
「食べたら損」なのか、「食べなければ損」なのか?
私はチャーシュー丼には、ほとんど口をつけなかった。
そのかわり、ワイフが注文したランチセットを、2人で分けて食べた。
が、それでもラーメンの麺は、40%近く、食べないで、残した。
大切なことは、「ラーメンの味を楽しんだ」という事実。
味を楽しめばじゅうぶん。
目的は達した。
「もったいないから、食べてしまおう」と思ったとたん、マネー教の虜(とりこ)
になってしまう。
●マネー教からの脱出
お金がなければ不幸になる。
しかしお金では、幸福は買えない。
心の満足感も買えない。
お金の力には、限界がある。
が、その一方で、人間の欲望には、際限がない。
その(際限なさ)が、ときとして、心をゆがめる。
ゆがめるだけではない。
大切なものを、大切でないと思い込ませたり、大切でないものを、大切と
思い込ませたりする。
子どもの世界でそれを考えると、よくわかる。
10年ほど前のこと。
1人の女の子(小学生)が、(たまごっち)というゲームで遊んでいた。
私はそれを借りて、あちこちをいじった。
とたん、あの(たまごっち)が死んでしまった。
その女の子は、「たまごっちが死んでしまったア!」と、大声で泣き出した。
私たちはそういう女の子を見ると笑う。
しかし本当のところ、私たちはその女の子と変わらないことを、日常的に
繰り返している。
繰り返しながら、それに気づかないでいる。
●ではどうするか?
私たちはカルト教団の信者を見て、笑う。
「私たちは、あんなバカではない」と。
しかし同じようなバカなことをしながら、そういう自分に気づくことはない。
自分を知るというのは、それくらい難しい。
つまり自分自身を、そうしたカルト教団の信者に置き換えてみればよい。
あなたならそういう信者を、どのようにして説得し、教団から抜けださせることが
できるだろうか。
いきなり頭から「あなたは、まちがっている!」と言ってはいけない。
梯子(はしご)をはずすのは簡単なこと。
大切なことは、同時に、その人に別の救いの道を提示すること。
それをしないで、一方的に、「あなたはまちがっている」と言ってはいけない。
同じように、自分に対して、「私はまちがっている」と思ってはいけない。
大切なことは、自分の中で、別の価値観を創りあげること。
方法は、簡単。
常に、何が大切で、何が大切でないか、それを問い続ければよい。
何があっても、それを問い続ける。
あとは、時間が、あなたを導いてくれる。
やがてその向こうに、その(大切なもの)が、見えてくるようになる。
(見えてくのもの)は、それぞれみなちがうだろう。
しかし見えてくる。
その価値観が優勢になったとき、マネー教はあなたの中から、姿を消す。
●食べたら損
で、結論は、「食べたら損」ということになる。
いっときの欲望を満足させることはできるが、かえって健康を損(そこ)ねる。
同じように、いくらそのチャンスがあったとしても、人をだましたら、損。
ずるいことをしたら、損。
自分を偽ったら、損。
その分だけ、心の健康を損なう。
「損(そん)」とは、もともと「損(そこ)なうこと」をいう。
失うことを、「損」というのではない。
が、今では、金銭的な損を、「損」という。
またそういうふうに考える人は多い。
「食べたら損」なのか、「食べなければ損」なのか。
そういうふうに迷うときがあったら、あなたも勇気を出して、「食べたら損」を
選択してみたらどうだろうか。
たったそれだけのことだが、あなたの心に、何らかの変化をもたらすはず。
ついでに言うなら、マネーが日本で、一般社会に流通するようになったのは、
江戸時代の中期ごろから。
このことについては、以前、私がかなり詳しく調べたから、まちがいない。
つまりそれまでは、日本人は、マネーとは無縁の生活をしていた。
私が子どものころでさえ、「マネー」を、おおっぴらに口にすることは、
卑しいこととされていた。
それが今は、一変した。
何でも、マネー、マネー、マネーとなった。
マネー教の信者になりながら、信者であることにさえ気がつかなくなってしまった。
その結果が、「今」ということになる。
(付記)
「食べ物を残すことはもったいない」という意見に、一言。
レストランへ行くと、「お子様ランチ」というのがある。
同じように、「シルバー・ランチ」、もしくは「シルバー・メニュー」のようなものを、
もっと用意してほしい。
最近の傾向として、レストランでの料理の量が、多くなってきたように感ずる。
全国規模で展開しているレストランほど、そうで、たいてい食べ残してしまう。
しかしこれは食料資源という面で、「もったいない」。
私も、そう思う。
だから高齢者向けに、高齢者用のメニューをふやしてほしい。
「カロリー少なめ、塩分少なめ、糖分控え目、ハーフサイズ」とか。
もちろん値段も、その分、安くしてほしい
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て
Hiroshi Hayashi 林浩司 BW BW教室 マネー教 金権教 金権教団
はやし浩司 なんでも鑑定団 お宝鑑定団 金権教 マネー教)
++++++++++++++++++はやし浩司
●欲望性
こうして考えてみると、「通俗」というのは、「マネー」にいかに毒されているかで決ま
るということになる。
わかりやすく言えば、そのさらに向こうにある(欲望)と結びついている。
欲望性が強ければ強いほど、人は通俗になる。
わかりやすく言えば、欲望に溺れるまま生きている人は、通俗的になる。
異論もあるだろうが、それほど的をはずしていない(?)。
が、マネーと権力。
この2つには恐ろしいほどの魔力がある。
それでもって、相手の価値を判断したり、自分の価値を判断したりする。
こちら側が積極的に闘う姿勢を見せないかぎり、あっという間に、その毒牙にかかってし
まう。
金権を手中に収め、おごり高ぶることも、毒牙。
反対に、金権といえるようなものもなく、自分を過小評価するのも、これまた毒牙。
冒頭で、私はある男の話を書いた。
「林さん、そんなに稼がなくてもいいんじゃない」と言った、あの男の話である。
考えてみれば、なぜ私がああまで不愉快に思ったかといえば、私自身の中に潜む金権教
を、その言葉がえぐり出したからとも考えられなくはない。
「痛いところを突かれた」……そうも考えられなくはない。
しかしその人の文化性の高さは、いかに通俗的でないかによって、決まる。
最後に私がオーストラリアで経験した話を載せる。
これも古い原稿である。
もともとは「意識」について書いた原稿である。
ここでいう「通俗性」の理解に役立てば、うれしい。
++++++++++++++++++はやし浩司
【意識論】
++++++++++++++
自分がもっている(意識)ほど、
アテにならないものはない。
「私は私」と思っていても、
そのほとんどは、(作られたもの)。
本当の「私」など、どこにもない?
++++++++++++++
●日本の商社マンは、軽蔑されている?
今から、40年も前のこと。日本には、まだ綿棒もなかった。バンドエイドもなかった。
乾燥機もなかった。ほとんどの家では、まだボットン便所を使っていた。
そんなとき、私は、オーストラリアのメルボルン市へと渡った。人口300万人(当時)
のメルボルン市ですら、日本人の留学生は、私1人だけだった。そんなある日のこと。あ
る友人(顔は覚えているが、名前をどうしても思い出せない)が、私にこう言った。
「ヒロシ、日本の商社マン(ビジネスマン)は、オーストラリアでは、軽蔑されている」
と。「軽蔑(despise)」という言葉を、はっきりと使った。
その少し前にも、仲のよかったD君もそう言った。それで気になって、その友人に、私
はこう聞いた。
「いったい、君は、日本の商社マンのどこを見て、そう思うのか?」と。すると、その
友人は、こう話してくれた。
その友人の父親も何かのビジネスをしていたらしい。そしてあるとき、日本の商社マン
と知りあいになった。その商社マンを、食事に招待した。向こうの人たちは、少し親しく
なると、自宅へ食事に招待する習慣がある。
で、いっしょに食事をしているときのこと。日本の商社マンは、家の中をあちこち見ま
わしながら、目ざとく日本製を見つけ、「これは日本製」「あれも日本製」と言いだした。
日本の商社マンにしてみれば、親近感をもってもらいために、そう言ったのかもしれない。
が、オーストラリア人であるその父親にしてみれば、不愉快だった。
しかしそれで終わったわけではない。食事がすむと日本の商社マンは、大きなバッグか
ら、何かの繊維見本を見せて、「これを買わないか?」ともちかけたという。その父親は、
取り扱い分野がちがうからという理由で、それを断った。するとすかさず、今度は、何か
別の商品を取り出し、「これはどうだ?」と迫ったという。
……つまり、そういう経験から、その友人の父親は、日本の商社マンを軽蔑するように
なったという。それでその友人は、そう言った。
●しかし……
しかし当時の私は、その話を聞いて、日本の商社マンのそうした行為が、どうして「軽
蔑」につながるのか、それが理解できなかった。私自身も、日本の商社への入社が内定し
ていたこともある。その上、当時の日本の経済は、高度成長期へと突入しつつあった。日
本中が、「マネー」「マネー」の大合唱に揺れていた。
それに羽田―シドニー間の航空運賃(往復)だけでも、42、3万円の時代である。大
卒の初任給が、やっと5万円を超えた時代である。しかもオーストラリアドルは、1ドル
が、400円に固定されていた。
オーストラリアでの生活費は、日本での生活費の、10倍、もしくはそれ以上だった。
オーストラリアへやってきた商社マンたちも、それゆえ、必死だった。
今でこそ、日本は豊かになった。しかし当時の日本人のだれが、日本がここまで豊かに
なると予想しただろうか。私はあるとき日記に、こう書いたのを覚えている。「日本が、オ
ーストラリアに追いつくためには、50年かかる。あるいは、100年でも不可能かもし
れない」と。
ほとんどの学生は、車をもっていた。学生の親たちは、別荘をもっていた。農場を経営
していたT君(南オーストラリア州)の父親の年収は、1400〜1500万円(当時)
もあった。ごくふつうの、平均的な農場主である。
「1400〜1500万円」と聞くと驚く人もいるかもしれないが、1ドルを400円
で計算すると、そうなった。とくにリッチな生活をしていたわけではないのだが……。
●作られる意識
一方、私たちはどうかというと、みな、就職といえば、迷わず、銀行、証券会社、商社
の道を選んだ。またそれが学生が進むべき道として、正しい方向と信じていた。
私も三井物産という会社と、伊藤忠商事という会社の2社の入社試験に合格した。しかし「大
きいほうがいい」ということで、三井物産という会社にした。
きいほうがいい」ということで、三井物産という会社にした。
日本でいえば「商社マン」だが、オーストラリアでは、「ビジネスマン」。その商社マン
が、軽蔑されていると知って、心底、驚いた。私は、商社マンは尊敬されることはあって
も、軽蔑される存在などとは、考えたこともなかった。
が、こうした意識も、同じように外国からやってきた留学生たちの意識とくらべてみる
と、作られたものだということがわかった。たとえばフィリッピンからやってきた留学生
は、こう言った。
「ヒロシ、君は、どうして日本の軍隊に入らないのか?」と。
当時のフィリッピンは、マルコス政権下。軍人になること、イコール、出世コースとい
うことになっていた。(今も、基本的にはそうだが……。)彼らがもっていた、軍事として
のエリート意識には、相当なものがあった。
一方、私は私で、ほかに自慢できるものがなかったこともあり、ことあるごとに、私は、
「日本へ帰ったら、ミツイ&カンパニーの商社マンになる」と、言っていた。が、先の友
人は、こう言った。
「ヒロシ、そんなことを言うのは、もうよせ。君は知らないかもしれないが、日本の商
社マンは、ここオーストラリアでは、軽蔑されている」と。
●それから40年
それから40年。私ももうすぐ60歳になる。三井物産という会社は、どうにもこうに
も肌に合わなくて、入社後半年を待たずして、やめた。
理由はいろいろある。が、その前に、私の意識そのものが変わってしまった。その話は
ともかくも、今度は、反対の立場で、似たような経験をすることになった。
いきさつはともかくも、ある女性から、ある日、電話がかかってきた。「どうしても会い
たいので、会ってほしい」「お伝えしたいことがある」と。
二男が高校生のとき世話になった友人の母親からのものである。私はその申し出をてい
ねいに受けた。そして食事に招待することにした。
私はその母親と会うことについて、かなり緊張した。そのとき二男はすでにアメリカに
渡っていた。内心では、二男が何かトラブルでも起こしたのではないかと心配していた。
が、食事は始終、よい雰囲気のままだった。私はほっとした。が、そのあとのこと。私
がおもむろに、「で、大切な話というのは何ですか?」と切り出した。
とたんその母親の表情が、さらに緩(ゆる)んだ。その母親は、こう言った。
「林さん、こういう健康食品がありますが、興味ありません?」と。
その母親は、ズラズラと、テーブルの上に健康食品を並べた。とたん、私はむっとする
ような不快感を覚えた。「私に会いたいというから会ったが、こんな話で会いたかったの
か!」と。
利用されたという不快感。金儲けに利用されたという不快感。そういう商品を売りつけ
られるという不快感。そうした不快感は、その女性が、「漢方」という名前を出したときに、
頂点に達した。
漢方(東洋医学)の「カ」の字も知らない女性が、私に漢方の説明をし始めた。そして
こうも言った。
「林さんは、お顔も広いようですから、ほかに買ってくださる方を紹介してくださった
ら、1個につき、xx%のマージンをさしあげます」と。
私は、そのときは、はっきりとこう言った。その少し前にも同じような経験をしたこと
もあった。「お帰りください。あなたが話があると言ったから、こういう場を用意しました。
しかしモノを売りつけるために、こんな場を利用するなんて、失敬でしょ!」と。
私は、その瞬間、40年前の、あのオーストラリアの友人の言った言葉を思い出した。
●意識
私たちがもっている(意識)ほど、アテにならないものはない。40年前のその少しあ
と、私は、三井物産という会社をやめ、そのあとしばらくして、幼稚園の講師になった。
それについても、当時の私を知る人たちは、みな、こう言った。
「あの林は、頭がおかしくなった」と。
たしかに私の頭はおかしい。今も、おかしい。それはわかる。しかしそうした私を支え
てくれたのは、実は、オーストラリアの友人たちだった。私が幼稚園で働いていると手紙
に書くと、みな、こう言った。
「ヒロシ、すばらしい選択だ」と。
今でこそ、私のような生き方をする人がふえてきた。だから商社マンをやめて、幼稚園
の講師になった人がいたとしても、それほど目立たない。しかし当時は、ちがった。私の
母ですら、電話口の向こうで泣き崩れてしまった。「浩ちゃん、あんたは道を誤ったア!」
と。
けっして母を責めているのではない。母は、母で、当時の常識をもとにして、そう言っ
た。「常識」というよりは、「意識」と言ったほうがよいかもしれない。
で、この話の結論。
私たちは、無数の意識をもっている。しかしその意識にも、2種類ある。意識的に意識
する意識と、無意識のまま意識しない意識である。
脳みその活動をもとにすると、私たちが意識できる(意識)というのは、脳みそ全体の
数10万分の1にもならないという。あるいは、もっと少ないかもしれない。
つまり人間の脳みその中には、無意識のまま意識しない意識のほうが、絶対的に多いと
いうこと。ほとんどがそうであるとみてよい。
この無意識のまま意識しない意識が、実は、私たちの意識を、ウラから操る。が、その
操られる私たちは、それに気づかない。操られていると知ることもなく、操られている。
実は、ここに、(意識)のおもしろさというか、恐ろしさがある。
……ということで、この話は、おしまい。今までに「意識」について書いた原稿を、こ
こに添付する。
+++++++++++++
●指で鼻をさす(教育のダークサイド)
子どもたち(小学生)は、「自分」を表すとき、指で鼻先を押さえる。欧米では、親指で
自分の胸を押さえる。そこで私はいつごろから、子どもたちが自分の鼻を押さえるように
なるかを調べてみた。「調べた」というのもおおげさだが、授業の途中で、子どもたちにど
うするかを聞いてみた。
結果、年長児ではほぼ全員。年中児でも、ほぼ全員。年少児になると、何割かは鼻先を押
さえるが、ウロウロと迷う子どもが多いということがわかった。そんなことで、こういう
習慣は、四歳から五歳ぐらいにかけてできるということがわかった。つまりこの時期、子
どもたちは誰に教えてもらうわけでもなく、いつの間にか、そういう習慣に染まっていく。
私は何も、ここでジェスチャについて書くつもりはない。私が言いたいのは、教育には、
常に「教えずして教える」という、ダークサイドの部分があるということだ。これはジェ
スチャという、どうでもいいようなことだが、ものの考え方や道筋、思考回路などといっ
たものも、実はこのダークサイドの部分でできる。
しかもその影響は、当然のことながら、幼児期ほど、大きい。この時期に論理的なものの
考え方を見つけた子どもは、ずっと論理的なものの考え方ができるいようになるし、そう
でない子どもは、そうでない。そればかりではない。
この時期に、人生観や価値観の基本までできる。異性観や夫婦像といったものまで、この
時期に完成される。少なくとも、それ以後、大きく変化するということはない。そのこと
はあなた自身を静かに観察してみれば、わかる。
たとえば私は、今、いろいろなことを考え、こうして文を書いているが、基本的なもの
の考え方が、幼児期以後、変わったという記憶がない。途中で大きく変化したということ
は、ないのだ。今の私は、幼児期の私であり、その幼児期の私が、今の私になっている。
それはちょうど金太郎飴のようなもので、私の人生は、どこで切っても、「私」にほかなら
ない。幼児期に桃太郎だった私が、途中で金太郎になるなどということは、ありえない。
もうわかっていただけると思うが、幼児教育の重要性は、実はここにある。この時期に
作られる「私」は、一生、「私」の基本になる。あるはその時期にできた方向性に従うだけ
である。中には幼児教育イコール、幼稚教育と考えている人がいるが、それはとんでもな
い誤解である。
……と書いたところで、今、ふと、別のことが頭の中を横切った。実は今、ある男の子
(小二)のことが気になっている。彼は男の子なのだが、言い方、ものごしが、女の子っ
ぽいというより、その女の子を通り越して、同性愛者ぽい。まちがいを指摘したりすると、
「イヤーン」と甘ったるい声を出したりする。いくら注意してもなおらない。
で、私が悩んでいることは、このことではなく、それを親に言うべきかどうかということ
だ。もうこの傾向は、ここ1年以上続いている。
なおそうとしてもなおるものではないし、さりとて放置しておくわけにもいかない。放置
しておけば、彼はひょっとしたら、一生、そのままになるだろう。近く、結論を出すつも
りでいる。(以上、01年記「子育て雑談」)
(付記)
教えずして教えてしまうこと。実は、これがこわい。ユングも、「シャドウ」という言葉
を使って、それを説明した。
たとえばあなたが、本当は邪悪な人間であったとする。その邪悪さをおおいかくして、
善人ぶっていたとする。そのときその邪悪さが、その人のシャドウとなる。子どもは、あ
なたの近くにいるため、そのシャドウをそのまま引き継いでしまう。
要するに、ウソやインチキ、ごまかしや仮面で、いくら善人ぶっても、子どもはだませ
ないということ。子どもは、あなたのすべてを見ている。
そういう意味で、子育ては怖いぞ〜オ!
++++++++++++++
内容が少しダブりますが、
こんな原稿を書いたこともあり
ます。
(中日新聞、掲載済み)
++++++++++++++
●国によって違う職業観
職業観というのは、国によって違う。もう30年も前のことだが、私がメルボルン大学
に留学していたときのこと。当時、あの人口300万人と言われたメルボルン市でさえ、
正規の日本人留学生は私1人だけ。(もう1人、Mという女子学生がいたが、彼女は、もと
もとメルボルンに住んでいた日本人。)そのときのこと。
私が友人の部屋でお茶を飲んでいると、1通の手紙を見つけた。許可をもらって読むと、
「君を外交官にしたいから、面接に来るように」と。
私が喜んで、「外交官ではないか! おめでとう」と言うと、その友人は何を思ったか、そ
の手紙を丸めてポイと捨てた。「アメリカやイギリスなら行きたいが、99%の国は、行き
たくない」と。考えてみればオーストラリアは移民国家。「外国へ出る」という意識が、日
本人のそれとはまったく違っていた。
さらにある日。フィリッピンからの留学生と話していると、彼はこう言った。「君は日本
へ帰ったら、ジャパニーズ・アーミィ(軍隊)に入るのか」と。私が「いや、今、日本で
は軍隊はあまり人気がない」と答えると、「イソロク(山本五十六)の伝統ある軍隊になぜ
入らないのか」と、やんやの非難。
当時のフィリッピンは、マルコス政権下。軍人になることイコール、そのまま出世コース
ということになっていた。で、私の番。
私はほかに自慢できるものがなかったこともあり、最初のころは、会う人ごとに、「ぼく
は日本へ帰ったら、M物産という会社に入る。日本ではナンバーワンの商社だ」と言って
いた。が、ある日、1番仲のよかったデニス君が、こう言った。「ヒロシ、もうそんなこと
を言うのはよせ。日本のビジネスマンは、ここでは軽蔑されている」と。彼は「ディスパ
イズ(軽蔑する)」という言葉を使った。
当時の日本は高度成長期のまっただ中。ほとんどの学生は何も迷わず、銀行マン、商社
マンの道を歩もうとしていた。外交官になるというのは、エリート中のエリートでしかな
かった。この友人の一言で、私の職業観が大きく変わったことは言うまでもない。
さて今、あなたはどのような職業観をもっているだろうか。あなたというより、あなた
の夫はどのような職業観をもっているだろうか。それがどんなものであるにせよ、ただこ
れだけは言える。
こうした職業観、つまり常識というのは、決して絶対的なものではないということ。時代
によって、それぞれの国によって、そのときどきの「教育」によってつくられるというこ
と。大切なことは、そういうものを通り越した、その先で子どもの将来を考える必要があ
るということ。
私の母は、私が幼稚園教師になると電話で話したとき、電話口の向こうで、オイオイと泣
き崩れてしまった。「浩ちャーン、あんたは道を誤ったア〜」と。母は母の時代の常識にそ
ってそう言っただけだが、その一言が私をどん底に叩き落したことは言うまでもない。
しかしあなたとあなたの子どもの間では、こういうことはあってはならない。これからは、
もうそういう時代ではない。あってはならない。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 通俗性 はやし浩司
金権教 はやし浩司 ディスパイズ despise 軽蔑という言葉を使った)2011/11/19記
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●「地元に張りつく」?(日本人の島国根性と、都会的優越感)
++++++++++++++++++はやし浩司
産経ニュースは、つぎのように伝える(11・17)。
『……民主党の小沢一郎元代表は16日夜、東京・赤坂のレストランで同党所属の衆院当
選1回の若手議員5人と会食し、「年が開ければ、翌年(平成25年)が任期満了で選挙の
空気が強まる。みんな、地元に張り付いてどぶ板でがんばれ」と語った』(産経ニュース)
と。
++++++++++++++++++はやし浩司
●「上」からの視点
2006年に、こんな原稿を書いた。
私たち浜松に住む人間は、「田舎者」だそうだ。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●田舎者はイチコロよ!
+++++++++++++++++++++++
片山さつき氏は、私の選挙区から選出された、
国会議員である。
ふつうは、こうしたエッセーでは、実名を伏せる
ことにしているが、ここでは、あえて、実名で
書かせてもらう。
雑誌「諸君」の中に、こんな記事があった。
「私が土下座なんてしたら、この辺の田舎者は、
イチコロよ」(片山さつき談)と!
++++++++++++++++++++++
06年の8月。先の衆議院議員選挙(05年8月)が終わって、ちょうど1年になる。
同じ自民党の城内実氏を僅差で破って、衆議院議員になった。それが片山さつき氏である。
城内実氏は、郵政民営化に反対して、K首相の反感をくらった。
つまり片山さつき氏は、城内実氏をたたき落とすために、中央から送り込まれた、刺客
ということになる。片山さつき氏は、財務省主計局主計官(防衛担当)を退官し、静岡県
7区から立候補した。
私が住む、この選挙区で、である。
その片山さつき氏について、倉田真由美氏(マンガ家)が、こんな気になる記事を書い
ている。
『……片山さつきさんの地元代議士への土下座は、毒々しさすら漂っていた。謝罪では
ない、媚(こび)の土下座は見苦しいし、世間からズレている。未だに「ミス東大→財務
省キャリア」という自意識に浸(つ)かり、「謙虚」のケの字もわからないまま、「私が土
下座なんてしたら、この辺の田舎者は、イチコロよ」と高を括(くく)る。
そうしたバランス感覚の欠如も、いくら揶揄(やゆ)されても変えない髪型や化粧も、
自分が客観視できない、強すぎる主観の表れだ。
「私いいオンナだから、これでいいの」という思い込みに対して、周りの人間も、もは
やお手上げなのだろう』(以上、原文のまま。雑誌「諸君」・05年11月号・P87)と。
この記事の中で、とくに気になったのは、「私が土下座なんてしたら、この辺の田舎者は、
イチコロよ」という部分である。本当にそう言ったかどうかは、この記事を書いた、倉田
真由美氏に責任を取ってもらうことにして、これほど、頭にカチンときた記事はない。
片山さつき氏が、どこかの席で、土下座をして、「当選させてほしい」と頼んだという話
は、当時、私も耳にしたことがある。しかしそのあと、東京に戻って、「私が土下座なんて
したら、この辺の田舎者は、イチコロよ」と話した部分については、私は知らなかった。
何が、「田舎者」だ! 「イチコロ」とは何だ! しかしこれほど、選挙民をバカにした
発言はない。民主主義そのものを否定した発言はない。そういうタイプの女性ではないか
とは疑っていたが、片山さつき氏は、まさにその通りの女性だった。
私たちが、田舎者? ならば聞くが、いまだにあちこちに張ってある、あのポスターは
何か? あれが都会人の顔か? あれが元ミス東大の顔か? 笑わせるな!
もしこれらの発言が事実とするなら、私は片山さつき氏を許さない。片山さつき氏は、
まさに選挙のために地元へやってきて、私たち選挙民を利用しただけ。しかも利用するだ
け利用しておきながら、その私たちを、「田舎者」とは!
そして先の選挙からちょうど1年になるが、片山さつき氏が、この1年間、この地元に
帰ってきて、何かをしたという話を、私は、まったく知らない。念のためワイフにも聞い
てみたが、ワイフも、「知らない」と言った。ワイフの知人も、「知らない」と言った。
つまり、片山さつき氏は、選挙のために、私たちを利用しただけ。もっとはっきり言え
ば、自己の名聞名利のために、私たちを利用しただけ。
しかしこれがはたして、民主主義と言えるのか? こんな民主主義が、この日本で、ま
かり通ってよいのか?
ある日、突然、中央から、天下り官僚がやってくる。それまで名前のナの字も知らない。
もちろん地元のために、何かをしてきた人でもない。そういう人が、うまく選挙だけをく
ぐりぬけて、国会議員になり、また中央へ戻っていく! どうしてそういう人が、地元の
代表なのか?
そののち片山さつき氏は、派手なパフォーマンスを繰りかえし、政界ではさまざまな話
題をふりまいている。しかしそれらは、あくまでも、自分のため。私たちの住むこの地元
の利益につながったという話は、まったく聞いていない。少なくとも、私は、まったく知
らない。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●「私が土下座なんてしたら、この辺の田舎者は、イチコロよ」
先の原稿は、2006年に書いたもの。
あの国会議員のパフォーマンスには、どこか不自然なものを感じていた。
そんなとき、雑誌「諸君」は、先の記事をあげた。
「田舎者」と。
片山さつき氏の選挙区(つまり私の選挙区)は、浜松市の西に位置する。
半分程度は、浜松市内に隣接しているが、「田舎」といえば「田舎」。
しかしそれにしても、「私が土下座なんてしたら、この辺の田舎者は、イチコロよ」(片山
さつき氏談)とは!
……この種の発言は、ときどき中央からこの地方まで、漏れてくる。
冒頭にあげた、「張りつけ発言」(小沢一郎氏談)も、そのひとつ。
中央集権意識がかなり強くなければ、こういう言葉は出てこない。
つまり「主体」は、東京にあり、地方はただの「借り家」?
視点が「上」にある。
地方を上から見ている。
だから下にある地元に、「張りつけ」?
一方、地方に住む私たちは、そういう考え方をしない。
国会議員というのは、あくまでも私たちの住む地方を代表する議員。
「国会でがんばってきてほしい」とは言うが、「張りついてほしい」とは言わない。
言葉の切れ端を問題にするつもりはない。
しかし全体としてみると、小沢一郎氏というのは、そういう人物だろうなということが、
よくわかる。
失言というより、「しっぽ」。
まさに氷山の一角。
私にはこう聞こえた。
「土下座でも何でもして、また東京へ戻って来い」と。
●中央集権意識
中央集権意識というのが、どういうものか。
それはアメリカやオーストラリアへ行ってみると、よくわかる。
とくにオーストラリア。
もともとは州ごとに独立していた。
列車の線路の幅もちがっていた(1970年当時)。
だから首都をどこにするかで、もめた。
結果、シドニーとメルボルンの間にあるキャンベラに首都が置かれた。
で、こんなことがある。
「♪ウォルチング・マチルダ」と言えば、だれもが知っているオーストラリアのブッシュ・
ソングである。
しかし南オーストラリア州の人たちは、それを歌わない。
「浩司、あれはニュー・サウス・ウェールズ州(NSW)の歌だよ」と。
「東京から来た」というだけで、何でもかんでもありがたがる田舎根性。
アホでもバカでもよい。
インチキでもよい。
それを知りたければ、年末恒例のディナーショーをみればよい。
少し大きなホテルになると、東京からタレントを呼んできて、ディナーショーを開く。
一方、中央(東京)に住む連中は、みな、こう言っている。
「東京で有名になって、地方で稼げ」と。
私は若いころ、NETのアフターヌーショー(川崎敬三)や、11PM(水曜)の脚本を
書いていた。
そのあたりの事情をよく知っている。
その集約されたものが、「政治」ということになる。
●都会的優越感
都会的優越感が、いかに幻惑であるかは、都会の中を走る電車に乗ってみればわかる。
私のいちばん記憶に残っているのは、京急久里浜線(神奈川県)に乗ったときのこと。
たしか三崎口(始発)というところから、横浜まで乗った。
乗ったときは、ガラガラ。
まわりにはまだ田園風景も見られた。
が、4〜5駅も過ぎると、ラッシュアワー時ということもあって、急に混み始めた。
ふつうの混み方ではない。
私はそれを見ながら、こう思った。
「このあたりの人たちは、毎日1時間も、こんな環境の中で過ごしているのか」と。
とたん、都会がもつ「幻惑」が、ガラガラと音をたてて崩れていくのを感じた。
私たち地方人のほうが、はるかに人間らしい生活をしている。
が、都会に住んでいる人たちには、それがわからない。
「自分たちは地方に住んでいる人間より、(偉い)」と思い込んでいる。
馬鹿げた優越感だが、都会に住んでいる人にはわからない。
その理由のひとつが、「田舎根性」。
つまり田舎に住む私たち自身にも、責任がある。
●慇懃無礼
現在、東京には友人は1人もいない。
親類もいない。
少し前までは、何人かいたが、仕事上のつきあいだった。
だからあえて、書く。……書ける。
東京から来る人は、それなりに電話などで連絡をしてくる。
「それなり」というのは、「慇懃無礼(いんぎんぶれい)」という意味。
が、決まってこう言う。
「○○時○○分に、浜松駅へ着くから」と。
その言葉の向こうで、「当然、浜松駅まで、迎えに来い」と。
いまだかって、「あなたの自宅へ、何時ごろ着く」と言った人は、1人もいない。
JR浜松駅から、私の自宅まで、タクシーで約25分。
料金は2000円とちょっと(2011年現在)。
この浜松市を、地図上の「点」としか考えていない。
帰るときもそうだ。
いまだかって、「タクシーを呼んでください」と言った人は、これまた1人もいない。
が、その一方で、礼儀正しいのは、むしろオーストラリア人。
どう礼儀正しいかは、今さらここに書くまでもない。
●「地元に張りつく」
恐らく東京に住んでいる人には、理解できないだろう。
「地元に張りつく」という言葉を聞いても、それを当然と思うかもしれない。
それ以前に、疑問にも思わないだろう。
が、私はちがう。
この浜松市に住んで40年。
50歳になるころまで、浜松と東京の間を行き来しながら、仕事をしてきた。
だから東京に住む都会人がどのように考え、一方地方に住む「田舎人」がどのように考え
るか、それがよくわかる。
さいごに今朝の中日新聞に載った、放射線拡散の様子をシミュレーションした図を紹介
する(気象研究所発表)。
3・11大震災のあと、3月19日と3月20日の拡散様子図である。
ここで見てほしいのは、放射線の拡散した様子ではない。
いかにこの日本が小さいかということ。
こんな小さな国で、中央だの、地方だの言っていること自体、馬鹿げている。
それがわかってほしかったから、あえて紹介する。
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/37/img35ea577fzik4zj.
jpeg" width="413" height="492" alt="img230.jpg">
jpeg" width="413" height="492" alt="img230.jpg">
……改めて、日本が島国であることを知る。
本当に日本は、小さな国。
この図をじっとながめていると、それがよくわかる。
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●映画『インモータルズ』
+++++++++++++++++++
今夜、映画『インモータルズ』を観てきた。
が、驚いたのは、観客。
観客は、私たち2人だけ。
(あの広い劇場で、私たち2人だけだぞ!)
3D映画で、アメリカでは大好評だったとか。
しかし私はあの手の映画は、見飽きた。
いつもパターンは同じ。
で、ほしはきびしいく、2つの★★。
で、再び、観客の話。
私たちだけということで、おしゃべり自由。
それが楽しかった。
++++++++++++++++++++
●浜松駅前
駅前は活気を取り戻しつつある。
それは私にもわかる。
が、その一方で、駅(JR浜松駅)から歩いて数分も離れると、とたんに人影はまばらに
なる。
5分も歩けば、ザザ・シティというショッピング・センターにやってくる。
現在、中央館と西館が営業している。
しかし大理石のらせん階段をおりると、そこはスーパー。
たこ焼き屋に、いくつかの飲食店。
占いのコーナーもある。
少し前まで、100円ショップもあった。
無残なのは、中央館。
1階ですら、人影はまばら。
2〜4階は、まばらどころか、空き部屋だらけ。
エスカレーターで上がってくる人も、ほとんどいない。
駅前にEデパートがオープンしてから、人足がさらに遠のいた。
●失敗の連続
私が浜松に住むようになってしばらくしてからのこと。
そのザザ・シティのあったところに、西武デパートができた。
当初はたいへんなにぎわいようだった。
が、駅前に、イトーヨーカー堂ができた。
その前にJR浜松駅が大改修を行い、メイワンというデパートもできた。
とたん、西武デパートから人が去った。
が、決定的だったのは、昔からあった松菱デパートの倒産。
駅とザザ・シティの中間あたりに位置していた。
その数か月前、つまり松菱デパートが倒産する数か月前、ザザ・シティと松菱デパートを
つなぐ空中歩道を市が建設した。
空中歩道は、まったくの無駄づかいになった。
もちろん税金の無駄づかいである。
●ザザ・シティの不振
今日も映画の帰りに、ザザ・シティの中を歩いてみた。
(映画館はそのザザ・シティの西館にある。)
が、今夜も、人影はほとんどなかった。
あやしげな雰囲気の男子高校生、女子高校生が、あちこちに数人ずつのかたまりをつくっ
ていた。
それだけ。
1階には店が並んでいるが、客のいる店はなかった。
ザザ・シティは、今、沈没しかかっている。
●行政不信
考えてみれば、浜松市はおかしなことばかりしている。
たとえば駅前に巨大なビルを建てた。
アクトタワーというビルである。
が、フタをあけてみると、新規に外からやってきて事務所を開いた会社はゼロ(当時)。
みな、市内から、横滑りで入居していった。
その結果、市内の貸しビルは、空き室だらけになってしまった。
不動産業を営んでいた友人(学生時代の同級生)は、こう言った。
「3分の2が空き室だ」(当時)と。
それからもう12、3年になる。
その状況は、今も変わっていない。
で、今回の駅前開発。
駅前に力を注げば注ぐほど、その直近にある外側のデパートや商店街から客足が遠のく。
市内へやってくる客の数は、ほとんど変わらない。
たとえば駅から歩いて1〜2分のところにある、「べんがら横丁」は、今、3分の1ほどが
店を閉めている。
で、今度は、ザザ・シティ。
笛吹けど、(客は)、踊らず。
そのつど、いったいいくらの税金が無駄になっていることやら。
●発想の転換
何度も書くが、「駅前は浜松市の顔」という発想を捨てる。
よくても、悪くても、浜松市の工業にはほとんど影響はない。
無理に活性化させようとしても、うまくいくはずがない。
それが世界の常識。
郊外に大型店があれば、なおさら。
外国へ行っても、駅前はどこもガランとしている。
倉庫街の真ん中にあるところもある。
どうして日本人だけが、(浜松だけが)、駅前に、こうもこだわるのか。
そんな化粧をしても、見る人が見れば、わかる。
そういうのを「化けの皮」という。
●映画『源氏物語』
まだ予告編しか観ていない。
映画『源氏物語』。
その予告編の中で、男女が接吻(=口と口の接吻)するシーンが出てくる。
まことにもって、生々しいシーンだが、ちょっと待った!
平安時代の昔、日本人は、接吻などしただろうか?
私が子どものころですらなかった。
日本人が接吻をするようになったのは、戦後のこと。
アメリカ映画の影響とされる。
(つまり映画のもつ影響力には、ものすごいものがある。)
ときのGHQは、日本映画界に対して、1回はかならず接吻シーンを入れろという命令を
出したとか。
昔、そんな風説を耳にしたことがある。
そこであちこちを調べてみた。
この分野の研究は、みなが関心をもっているだけに、かなり進んでいる。
その中でも、「教えて、GOO」の中に、こんな記述があった。
そのまま一部を紹介させてもらう。
『……文献にも、平安初期の「土佐日記」に
「ただ押鮎の口をのみぞ吸ふ。この吸ふ人々の口を押鮎もし思ふやうあらむや」
船旅の途中、正月に祝い膳もなく、口吸いたい恋人もいないから、押し鮎を(彼女に見立
てて)吸ってみたりしたよ。鮎も、口吸ってる相手(=人)の事を、愛しいと思ってくれ
るかなぁ〜(笑)(私訳)
と言う記述があります』と。
「ああ、日本にもあったんだ!」というところで、この話はおしまい。
しかし、だ。
日本人がこうまで接吻をするようになったのは、最近のことだぞ!
2011/11/17朝記
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 12日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page020.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【自己主張する幼児】(年長5〜6歳児)
●自己主張
まずつぎのYOUTUBEを観てほしい。
前半は、ややかったるいレッスンがつづくが、やがて子どもたち(年長児)が造反し始め
る。
ワイワイと私に抵抗をし始める。
このYOUTUBEを観ていただければ、子どもの自己主張というものがどういうもか、
よくわかってもらえる。
ただ残念なことに、この日本では、子どもを判断する基準が昔と違ってきた。
国際的にも、かなり違う。
こうして自己主張を繰り返す子どもを、この日本ではむしろできの悪い子どもと位置づけ
る。
が、それは世界の常識ではない。
とくにアメリカでは、「シャイな子ども」を、問題児と位置づけている。
小児うつ病の診断基準のひとつにもなっている。
それもあってアメリカでは、はげしく自己主張する子どもほど、できのよい子どもと考え
る。
またそういう子どもにするために、教育をする。
「教え育てワクに入れる」のではなく、「子どもの能力をエデュース(educe=引き出す)す
る」ために、教育をする。
この違いは大きい。
その結果、日本人は、成人になるころには、キバを抜かれてしまう。
ハキのない、草食系人間になってしまう。
日本国内ではそれでよいとしても、このタイプの人間は、世界では通用しない。
日本を一歩外に出れば、そこは海千山千の世界。
盗賊と海賊が、食うか食われるか、血みどろの戦いをしている。
ともあれ、子どもの自己主張がどういうものであるか、一度、このYOUTUBEを観
てほしい。
年長児(5〜6歳児)の子どもたちである。
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/t4nhhyi-R-c"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 幼児の自己主張 幼児期後
期の子どもたち 幼児期後期 自立期の子ども 2011/11/13記)
期の子どもたち 幼児期後期 自立期の子ども 2011/11/13記)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●スカートの下(提言:スカートをやめ、ズボンにせよ!)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
またまた、ある男性がスカートの中を盗撮していて
逮捕された。
今度はテレビTというテレビ局の社員。
ヤフー・NEWSは、つぎのように伝える。
++++++++++++++++++++
女子高校生のスカート内を携帯電話で撮影しようとしたとして、
警視庁練馬署が13日までに、テレビT東京報道局社員、
KK容疑者(34)を都迷惑防止条例違反容疑で、
現行犯逮捕していたことが分かった。
逮捕容疑は12日午前11時10分ごろ、
同区豊玉北の都営地下鉄大江戸線練馬駅構内の、
上りエスカレーターで、女子高校生(18)の
スカート内に携帯電話を差し入れたとしている。
同署によると、KK容疑者は偶然近くにいた
非番の警察官に取り押さえられた。
容疑を認めているという(以上、ヤフーNEWSより)。
+++++++++++++++++++++
●性癖は理性では理解できない
男の私でも、そう思う。
男の性癖は、理性では理解できない。
人、それぞれ。
みなちがう。
またその性癖には、ものすごいパワーがある。
ひとたび発情すると、本人の理性の力では、どうにもならない。
(だからといって、その男性の行為を擁護しているわけではない。)
●スカートの下
まともな男性なら、(女性でもよいが)、「どうして?」と思ったまま、思考停止になって
しまうだろう。
私も、その1人。
細かいことを言えば、私にもいろいろな性癖はある。
が、「スカートの下」にはない。
興味がないわけではないが、手鏡やカメラを使ってまで見たいとは思わない。
見たところで、汚れた下着。
●男も女も同じ
基本的には男も女も同じ。
ホルモンの作用によって、それが外へ飛び出したのが「男」。
そのままの状態で中に残ったのが、「女」。
さらにホルモンの作用によって、思春期前夜から性差は大きくなるが、それでも基本的に
は男も女も、同じ。
私も子どものころ、クレヨンしんちゃんと同じように、ソーセージを(おまた)にはさ
んで、女のまねをしたことがある。
そのまねをすれば、男と女は区別できない。
……できるはずもない。
●神秘
が、「スカートの下」を、なぜか男たちはのぞきたがる。
なぜか?
理由は簡単。
そうした性癖がある男性は、それが神秘であるからではなく、条件反射的に脳の一部に操
られるからである。
しかもそうした性癖は、成長過程のどこかで作られる。
その結果、それを見たいと思う男性もいれば、そうでない男性もいる。
●のぞき
私は子どものころ、近くに、のぞきが趣味という友だちをもっていた。
最初に誘われたのが、小学3〜4年生のころのことではなかったか。
学校の帰りなどに、「林君、行こう、行こう」と盛んに誘われた。
それぞれの家が、先を競って、家の中に内風呂を作り始めていたころのことである。
が、私は行かなかった。
興味がなかったというより、それだけのエネルギーがわいてこなかった。
が、つぎに記憶しているのは、おとなになってからのこと。
久しぶりに会うと、その友だちは、温泉の話ばかり。
郷里のG県には、まだ、混浴温泉というのが、あちこちに残っていた。
その友だちは、混浴温泉に入るのが何よりの楽しみと言った。
すでに奥さんも、子どももいたのだが……。
●友だち
が、その友だちが、実は「スカートの下」に異常な興味と関心をもっていたのではない
かと知ったのは、10年ほど前のこと。
3階建てのビルを建設した。
1階は、自宅用。
2階と3階を貸し店舗にした。
2階がブティック、3階が金融会社になっていた。
私はその家を見て、何となく「?」とは思ったが、そこまで。
が、ワイフがこう言ったときに、気がついた。
「私なら、あんな店(ブティック)には、行かないわ」と。
●格子の階段
2階と3階へ行くためには、一度ビルの内側に入らなければならない。
そこから格子でできた、ゆるくカーブした階段を上らねばならない。
そのとき、1階の住居から、その階段を上っていく人がよく見えた。
もちろん「スカートの下」も!
もちろんこれは私の邪推かもしれない。
しかし私は子どものころから、その友だちの性癖をよく知っていた。
だから私はこう思った。
「あいつなら、やりそうだな」と。
●性的エネルギー(フロイト)
ふつうの人なら、こう思う。
「そこまでやるか?」と。
が、そこまでやるのが、「性的エネルギー」(フロイト)。
こうした事件が繰り返し起こるたびに、強くそう思う。
言い換えると、このエッセーを読んでいる人の中にも、そういう人は多いはず。
(あるいはあなたが女性なら、あなたの夫の中にも、多いはず。)
が、実態調査はむずかしい。
こうした性癖は、本人自身も隠す。
そうした性癖が強ければ強いほど、そうだ。
●性欲からの解放
何度も書くが、私は50代のはじめ、「男の更年期」というのを経験した。
本当にそういう更年期があるのかどうかは、知らない。
が、ワイフがそう言った。
私はその時期、「女」にほとんど興味を失ってしまった。
その種の写真を見ても何も感じなくなってしまったばかりか、時に、ブタの脂身のよう
に感じてしまったこともある(失礼!)。
が、それはきわめてさわやかな世界でもあった。
体中を取り巻いていた無数のクサリが、飛び散ったような感じだった。
私はそれを勝手に、「性欲からの解放」と呼んだ。
……と、同時に、私はそれまでの「私」が、いかに性欲の奴隷であったかを知った!
●民族性
これには民族性の問題もからんでいると思う。
たとえば私が学生時代を過ごしたオーストラリアでは、当時、女子学生たちは平気で下着
を見せていた。
中には下着をつけないまま、あぐらを組んで座る女子学生もいた。
私は日本人とオーストラリア人は、羞恥心そのものがちがうと考えていた。
だから私が知るかぎり、オーストラリアの友人と話していても、そういうことが話題にな
ったことがない。
「近くのヌーディスト村へ行っている」とか、そういう話はする。
しかし「スカートの下」はない。
(最近のオーストラリアの女性は、ほとんどがジーパンをはいているということもある?)
●ではどうするか?
日本人は「下着」を意識しすぎるのではないか?
男性も女性も、である。
逆に、水着と下着は、どこがどうちがうのか、それを説明できる人はいるだろうか。
水着は見られてもよいが、下着はだめというのは、あまりにも合理性に欠ける。
極端な言い方をすれば、「そんなもの見られたからといって、ガタガタするな」ということ
になる。
……というのは書きすぎ。
それはよくわかっているが、しかしそれが「男」と「女」ということになる。
男は自分の意思で、そういう行動をしていると思い込んでいる。
しかし実際には、「女」に操られている。
その「女」も、実は本能に操られている。
本能に操られているから、「男」を挑発しているという意識はない。
短いスカートをはき、無意識のうちにも、男を挑発している。
だったら、どうするか?
方法は簡単。
女子学生も、みな、ズボン(パンツ)にすればよい。
学校の制服も、そうすればよい。
どうして今、この時代に、スカートなのか?
一方、見られても構わないという女性は、(見られるのを前提に)、スカートをはけばよい。
男性もそうだ。
自分に露出狂のケがあるなら、下着をはかないで、スカートをはけばよい。
どうして男は、スカートをはかないのか?
●終わりに……
この種の事件は、これからもずっとつづく。
実態はわからないが、数%〜数10%の男性には、そのケがあるのでは?
その中でも、とくに強い性癖をもった人たちがいる。
そういう人たちが、こうした事件を引き起こす。
わかりやすく言えば、防ぎようがない。
これは理性の問題ではない。
本能の問題である。
(繰り返すが、だからといって、そういうことをする男性を擁護しているのではない。
どうかくれぐれも、誤解のないように。)
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●明日からの1週間(11月13日夜記)
++++++++++++++++++++
明日からの1週間を予測するのは、楽しい。
予言者にでもなったかのような気分になれる。
もちろん私には、そういう能力はない。
想像できなくはないが、しかしあくまでも想像の範囲。
そう言えば、近く、あの霊能力者がこの浜松市へ
やってくるそうだ。
ディナーショー形式で、対談会を開くそうだ。
会場は、某ホテル。
夕食付きで、1名、1万5000円前後とか。
++++++++++++++++++++
●EUの金融危機
マクロな見方をすれば、EUの金融危機は拡大することはあっても、収束することはあ
りえない。
EUという先進国が、無理に無理を重ねてきた。
金融を操りながら、ごまかしてきた。
収入は減り、国家経済は火の車。
にもかかわらず、生活水準はそのまま。
あとはお決まりの、借金漬け。
今はイタリアに目が向いている。
しかしどこからどのような伏兵が出てくるか、わからない。
スペインやポルトガルではなく、今はまったく名の出ていない国が、突然金融危機に陥る
ことも考えられる。
たとえばベルギー?
ハンガリー?
しかし誤解してはいけないことが、ひとつ、ある。
仮にイタリア(本当はスペインのほうが、あぶないが……)が金融危機に陥ったとする。
そのとき本当に困るのは、イタリアではなく、イタリアに金を貸している(=イタリアの
国債を大量に抱えこんでいる)ドイツやフランス、それにイギリスということ。
こういうのを経済学の世界では、「Counter Party Risk(カウンター・パーティ・リスク)」
と呼んでいる。
だからドイツやフランスが、今、慌てふためいている。
11月14日からの1週間は、さらに激動の1週間になるはず。
●野田政権
政治の動きが、よくわからない。
野田首相は、トラブルを起こすのを何よりも恐れているようにも見える。
慎重すぎるというより、長期政権をねらっている(?)。
「自分のしたいことをするのは、その後」と。
このまま可もなく不可もなく……という状態がつづく。
今は実績作り。
そのため日本の政治は眠ったような状態。
それに野田首相は、顔の脂肪が厚く、感情がどうも読み取れない。
何を考えているのか、それがよくわからない。
●霊能力
霊(スピリチュアル)能力というのは、私は信じない。
信じないというより、最初から、そういう思考回路が私の脳の中には、ない。
まったく、ない。
ないから論評のしようがない。
しかしそれを否定してしまうと、町の祭もなくなってしまう。
寺も神社もなくなってしまう。
だからほどほどに……ということになるが、世の中には悪党も多い。
そういう(力)があると人に信じ込ませ、金儲けにつなげる人もいる。
そういう人は許せない。
私の母も、晩年、ある宗教団体の女性から、白い壺を買わされた。
値段を聞くと、10万円だったという。
どうしてそんなものを買ったのかと叱ると、母はこう言った。
「若くて、親切な女の子だったから」と。
母は毎晩、その壺を磨いていた。
が、御利益はあったのか。
それともなかったのか。
母は死んでしまったので、私にはわからない。
●しめくくり
今日もこうして終わった。
先ほどあちこちのニュースサイトをながめてみた。
できるだけ、私の頭を刺激しないよう、コントロールしながらそうした。
今夜は、このまま静かに眠りたい。
運動は1単位だけ。
今日はだれにも会わなかった。
従姉から電話があったが、それだけ。
静かで、穏やかな1日だった。
では、みなさん、おやすみなさい。
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●11月14日
今朝は、ぐっすり眠った。
1、2度、目を覚ましたが寒かったので、そのまままた目を閉じた。
起きて時計を見ると、午前8時!
運動をさぼって、そのまま書斎に。
Eメールに目を通し、ニュースをいくつか読んだら、それだけでもう30分。
で、そこに名古屋にいるM君から電話。
今度、浜松市内にフード・バンクを設立するとか。
11月xx日に、浜松市内で会うことにした。
あと「月曜日の電話」。
月曜日の朝というのは、あちこちに電話をしなければならない。
私はそれを「月曜日の電話」と呼んでいる。
つまりこうして私の1週間が始まる。
●R631
話題はやはり、R631。
TOSHIBAの新型パソコン。
「買ってよかった」というか、たいへん気に入っている。
11月11日の発売日に購入して、今日で4日目。
R631のおかげで、ほかのパソコンが使えなくなってしまった。
つまりこのパソコンは、次世代のパソコンのあり方を示唆している。
(1)薄型、軽量は、時代の流れ。
(2)バッテリー9時間は、必需。
(3)光るキーボードは、便利。
(4)SSDは、常識、と。
スイッチ・ONから、10秒前後で、スタンバイ状態になる。
指紋認証というのもついていて、めんどうなパスワード入力も、簡単にできる。
サーッと指でこするだけ。
すでに裏面には、こまかい傷がつき始めた。
こうしてパソコンは年をとっていく。
傷まるけになったとき、パソコンは私の脳の一部になる。
●英訳(英文の抄訳)(日本語→グーグル翻訳→訂正→友人の推敲)
私の書いた原稿に、英文の抄訳をつけてほしいという。
ある出版社からの依頼である。
そこでまず、和文の抄訳を書く。
「子どもを知ることによって、私たち自身を知ることができる。あのワーズワースは、『子
どもは人の父』といった。私たち自身にも子ども時代があり、その時代に私という人間が
作られていった。子どもの心の形成過程を、乳幼児期から思春期まで、段階的に追いかけ
てみた。自分発見の手がかりになればうれしい。」
まずグーグルの翻訳サービスを使って、おおまかな翻訳をしてみる。
つぎのが、それ。
By knowing your child, we can know ourselves. That Wordsworth, the "father of the
children," and. There is also our own childhood, that I were a human being made in
that period. Formation process of the mind of a child, from infancy to adolescence,
I pursued in stages. Once your happy to discover clues.……(1)
つぎにこの英文に手を加える。
By knowing children, we can know ourselves better. W. Wordsworth once wrote, "A Child
is Father of the Man". We all were once that children and our mind was formed through
these ages. Here in the article I write about the process of how the minds of children
are formed from the age of infancy to adolescence. I hope this article would be some
of your help to know yourselves better.……(2)
ここでワーズワースの言葉を取りあげたが、原文を知らなければならない。
本当に「A Child is Father of the Man」のままでよいのか。
私の書いた原稿のどこかに、それが書いてあるはず。
それも「はやし浩司 子どもは人の父」で検索をかければ、すぐわかった。
原文では、つぎのようになっている。
●The Child is Father of the Man
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky :
So was it when my life began,
So is it now I am a man,
So be it when I shall grow old
Or let me die !
The Child is Father of the Man :
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.
●子どもは、人の父
イギリスの詩人ワーズワース(1770〜1850)は、次のように歌っている。
空に虹を見るとき、私の心ははずむ。
私が子どものころも、そうだった。
人となった今も、そうだ。
願わくは、私は歳をとって、死ぬときもそうでありたい。
子どもは人の父。
自然の恵みを受けて、それぞれの日々が、
そうであることを、私は願う。
正しくは、この原文からもわかるように、「The Child is Father of the Man」である。
そこで(2)の英文を、書き改める。
By knowing children, we can know ourselves better. W. Wordsworth once wrote, "The
Child is Father of the Man". We all were once that children and our minds were formed
through these ages. Here in the article I write about the process of how the minds
of children are formed in stages from the age of infancy to adolescence. I hope this
article would be some of your help to know yourselves better.
また、名前はW.Wordsworthでよいのか。
ウィキペディア百科事典で調べると、「William Wordsworth」となっていた。
つまり、これでOK。
で、この英文を、オーストラリアのモナーシュ大学にいる友人に送る。
いつも私の英文を添削してくれる。
その結果は、またあとで……。
(追記)
30分後、オーストラリアの友人から、添削が届いた。
英語の勉強になった。
By knowing children, we can know ourselves better.
William Wordsworth once wrote, "The Child is Father of the Man".
Once we were all children and our minds were formed during this age of childhood.
In this article I have written about the process of how the minds of children are
formed in stages from the age of infancy to adolescence.
I hope this article will be of some help to you in getting to know yourselves better.
「さすが!」と驚くのもどうかと思うが、これで完ぺきになった。
英語の勉強に役立てばうれしい。
●環太平洋連携協定(TPP)問題
環太平洋連携協定(TPP)問題。
参加に賛成する工業団体。
反対する農業団体。
ともに利権(=既得権)がからんでいるため、たがいに一歩も譲らない。
しかし大切なことは、一度、こういう形でもよいから、日本の農業の実態を明確にする
こと。
もう少し端的に言えば、メスを入れること。
日本の農業は、あまりにもわかりにくい。
闇に包まれている。
つまり補助金行政の中で、「補助金漬け」になっている。
その上で不必要な補助金は廃止し、もう一度日本の農業を、基本的な部分から再検討す
る。
既得権にあぐらをかいている農家の人たちにとっては、きびしい協定になるかもしれない。
しかし同じ農業を経営しながらも、「このままではよくない」と考えている人も多いはず。
私はそういう人たちの良識を信じたい。
何がなんでも反対!、というのは、あまりにも時代の流れに逆行している。
●株価
11月14日、日本の株価は高値で始まった。
午前10時30分……125円高。
しかしこの乱高下がこわい。
EUの金融危機は、何も解決していない。
しかも本当にあぶないのは、ギリシャでもイタリアでもない。
スペイン。
スペインがあぶない。
が、肝心のスペインは、のんきなもの。
それもそのはず。
スペインがデフォルトして困るのはドイツ。
そのドイツが慌てまくっている。
こういうケースのばあい、金を貸しているほうが、慌てる。
またそういう視点で見ると、EUの金融危機がどういったものであるか、それがよくわか
る。
では、今朝はここまで。
みなさん、おはようございます。
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●韓国・中央日報のウソ記事(?? ?? ??? ??? ??)
++++++++++++++++++++
?? ??? ??? ??? ?? ??.
?? ?? (11.14) ???? ?????.
"?? ?? ?? ?? ???? TPP ??? ??"??.
?? ???? ??? ?? ??? "?? ?? ??"?? ?? ?????
? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ??
?????.
?? ?? ????.
?? ?? BLOG? ??? ?????.
++++++++++++++++++++
中央日報のウソ記事には、うんざりする。
今朝(11・14)の記事には、こうある。
『日本首相、韓国・中国牽制のためTPP参加を決定』と。
いつ、どこで日本の野田首相が、「韓国牽制のため」という言葉を使ったか?
つまり中央日報はこうした記事を韓国国内で報道することによって、
韓国国内の反日感情をあおりたてている。
いつもの常套手段である。
韓国の国内のBLOGに、このまま投稿する。
2011/11/14
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
**********************
【講演会のお知らせ】
11月30日(水曜日)
午後6時30分開場
午後7:00〜8:30
場所:浜北文化センターにて
主催:浜北区健全育成会
入場は自由(無料)
『こうすれば、伸びる3つの話し』
**********************
【11月14日】(落ち込み)
浜北区での講演会に向けて……(浜松市内では今年度最後の講演会)
●時の流れ
「時」は流れに沿って、すべてを変えていく。
つい先日までそこにいた人が、今は、いない。
反対につい先日までそこにいなかった人が、今は大きな顔をして、そこにいる。
モノにしても、そうだ。
つい先日までカタログでながめていたパソコンが、今は、目の前にある。
●64歳
大切なことは、時の流れを感じたら、それに逆らわないこと。
やって来る人もいれば、去って行く人もいる。
モノにしても、いつまでもそこに「形」があるわけではない。
私自身にしてもそうだ。
いつの間にか、64歳。
50代の記憶は、あるにはあるが、どれも断片的。
40代の記憶は、さらに断片的。
シワだらけの自分の手や顔を見る。
64歳であることを実感する。
しかしそんな「数字」に、どれほどの意味があるというのか。
●人来たりて、また去る
フランスの詩人、ジャン・ダルジーはかつてこう歌った。
『……人来たりて、また去る
人来たりて、また去る
かくして、私の、あなたの、彼の、彼女の、彼らの人生が流れる
あたかも何ごともなかったかのように……』と。
詩の内容は、記憶によるものなので、不正確。
しかし私はこの詩の意味が、歳を経るごとに、よくわかるようになった。
「まさにそうだ……」というよりは、人生の悲哀感が、この詩の中に深くこめられている。
その悲哀感に、共鳴するようになった。
●失敗組
率直に言えば、私は失敗組。
自分でもよくわかっている。
地位にも肩書にも、一生、縁がなかった。
いろいろやってはきたが、いろいろやってきたというだけ。
今の今だって、そうだ。
虚勢こそ張らないが、……というか、張れるようなものは何もないが、私を飾るものは、
何もない。
見たまま。
裸のまま。
●負け戦
が、体質というのは、恐ろしい。
そうでありながら、まだどこかに、出世主義が残っている。
ときどきそれが顔を出す。
出して、こう言う。
「お前の人生も、たいしたことなかったな」、
「若いときは、あんなに偉そうなことを言っていたのに」と。
この無念さは、いったい、どこから来るのか。
劣等感に近い。
それとも不完全燃焼感?
考えてみれば、いつも負け戦。
その連続だった。
●原因
今夜の私は、落ち込んでいる。
理由がある。
浜松市のX区に、SN医院という医院がある。
かなり前から、別の同級生から、その医院の院長は、金沢大学出身と聞いていた。
学年も同じだった。
一度は、私はそれを確かめたかった。
同じ合唱団に、SNという名前の仲間がいた。
もしそうなら、ふつう以上に親しい間がらだった。
合唱団での練習が終わると、よく香林坊の盛り場を飲み歩いた。
で、今夜いろいろあって、その医院に電話をしてみた。
夜、6時を過ぎていた。
自分なりに失礼でない時刻を選んだつもりだった。
が、電話口に出た、SN医師は、きわめて傲慢だった。
傲慢というより、強圧的。
威張っていた。
私の話をほとんど聞かないうちから、「どこのだれだ!」「何の用だ!」「用件を早く言
え!」と。
私のほうがたじろいでしまった。
説明したくても、それができなかった。
SN医師は、私を何かのセールスマンと誤解したようだ。
ワイフはあとで、そう言った。
SN医師は、一方的に電話を、そのままガチャンと切った。
私もこういう性格だから、かなり頭に来た。
そこらのヤワな男とは、ちがう。
しかし自分を抑えた。
抑えて、怒りを鎮めた。
●無念さ
怒りはしばらくすると、収まった。
が、それと反比例する形で、無念さが、胸の中に充満してきた。
「どうしてあんなバカな電話をしたのだろう?」と。
と、同時に、自分がかぎりなく小さくなっていくのを感じた。
自分のしていることが、かぎりなくつまらなく思えてきた。
●SK君
金沢市にSK君というのがいる。
同じ法科出身。
合唱団でもいっしょだった。
そのSK君だったら、SN君のことを知っているはず。
私はそのあとしばらくしてから、電話をした。
私「SN君というのがいたよな?」
S「ああ、彼なら金沢市で開業しているよ」
私「金沢でか?」
S「そうだよ」
私「ナーンダ」と。
しばらく話していると、話が混乱してきた。
S「林君ねえ、君ねえ、SN君とNT君をまちがえているんじゃないか」
私「……ああ、そうだ、NT君だ。今、思い出した……」
S「君が言っているのは、NT君だよ。ほら、NT君」
私「そうだ、あいつだ。同じ名前だったから、それでまちがえた」
S「あのNT君も、金沢にいるよ。今は、金沢大学の付属病院で、院長をしているよ」
私「院長か?」
S「そうだ。ほら、あのNT君は、MBさんと結婚したよ。合唱団のMBさんだよ」
私「ああ、その話なら覚えている。MBさんが好きだという話は、NT君から直接、聞い
ていた」
S「そのあと、結婚したんだよ」と。
それを知って、少しだけだが、胸がスカッとした。
SK君はある都市銀行の取締役まで務めた。
今は定年退職し、金沢大学で教壇に立っている。
●しょせん……
……とは、書きつつ、しょせん、私も、この程度。
今夜は、それがよくわかる。
わかりすぎるほど、よくわかる。
わかるから、落ち込んでいる。
朝までの元気は、どこへ消えたのか。
……ということで、これからサイクリングに行ってくる。
時刻は午後9時。
一汗もかけば、気分も収まるだろう。
●サイクリング
今夜は、思いっきり全力で道路を走った。
薄着だったが、寒さは感じなかった。
途中、何人かの人を、追い抜いた。
が、足を休めなかった。
近く大きな講演がある。
その講演に向け、体力をつける。
整える。
浜松市内では、今年最後の講演。
真剣勝負で臨みたい。
2011/11/14夜記
**********************
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 9日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page019.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●「宇宙人の存在」(はやし浩司がつかんだ、ささやかな証拠)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MSN・ニュースサイトに、こんな興味深い記事が載っている。
ノーベル科学賞を受賞した、ポール・クルーグマン氏が、11月10日、自身が担当す
る米ニューヨークタイムズ紙のレギュラーコラムで、先日ホワイトハウスが宇宙人との接
触を否定した発表について、厳しく批判したというのだ。
「Fools」「Fools」と冒頭から冗談か真剣からともかく激しい批判の口調で書
き始めている「Space:The Final Stimulus」と題して論を展開して
いる。
「宇宙人の存在こそが、次の経済の希望になるということをわかっていないのか」と政
府を批判したという(以上、MSNニュース・サイトより)。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●宇宙人の存在
私は気がつかなかったが、この記事によれば、ホワイトハウスが、宇宙人との接触を否
定したらしい。
それについて、ノーベル科学賞を受賞した、ポール・クルーグマン氏が、「バカ、バカ!」
と一蹴。
その上で、「宇宙人の存在こそが、次の経済の希望になるということをわかっていないのか」
と政府を批判した、というのだ。
●希望
宇宙人の存在は、たしかに大きな希望である。
恐ろしい宇宙人もいるそうだが、逆説的に考えるなら、そういう宇宙人は少数派。
もし宇宙人がいて、その宇宙人が邪悪で、攻撃的であったとするなら、その宇宙人はとっ
くの昔に自滅していたはず。
破滅的な兵器も、同時にもっているはず。
その兵器で、自滅していたはず。
宇宙を自由に行き来できるような科学力をもっている宇宙人がいるとするなら、その宇
宙人は、同時に、穏やかで平和的。
そうでなければ、……たとえば人間のように半世紀ごとに大きな戦争を繰り返すような宇
宙人なら、この宇宙では生きてはいかれない。
とっくの昔に自滅していたはず。
もしそこに宇宙人がいるとするなら、穏やかで平和的。
そういう宇宙人に接触することは、希望以外の何ものでない。
●宇宙人がいるという証拠
それにしても不思議なのは、なぜこの場に及んでも、アメリカ政府やNASAは、宇宙
人の存在を否定するかということ。
もうここまでわかっているのだから、いいかげんに事実を認めたらよい。
繰り返しになるが、私がつかんだ、「ささやかな証拠」をここに再掲載する。
なおここに紹介する「火星上空を飛ぶUFO」について、知人の1人は、「カメラのレン
ズについたゴミ」と評している。
が、カメラをいじったことのある人なら、みな知っている。
レンズについたゴミは、こんなふうには、写らない。
さらにおかしなことに、その後発表された写真には、このUFOは写っていない。
消されている。
NASAはなぜ、そんな小細工ばかり、繰り返すのか?
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●宇宙人はいる!(2011年5月に書いた原稿より)
++++++++++++++++++++
「はやし浩司」という1人の、小さな人間が住む、
そのまた小さな世界。
その中で、はやし浩司ははやし浩司なりに、
宇宙人の存在を確信した。
それは私の人生の中でも、特筆すべきできごと
といってもよい。
「他人を介していない」という意味において、
また私自身が確信できるという意味において、
特筆すべきことできごとといってもよい。
小さな、そのまた小さな証明だが、しかし
それ以上の証明が、この私にできるだろうか。
組織力も、調査力もない。
どこまでも小さな私である。
あなたと同じ、小さな人間である。
何はさておき、ここに新聞のコピー(1)と、
火星で撮影された写真(2)を、並べて掲載する。
(1)の記事は、私が2000年11月25日(土)に、
中日新聞に寄稿したエッセーである。
「2000年」という年号に注意しておいてほしい。
(2)の写真は、2003年6月10日に打ち上げられた、
アメリカの火星探査機「スピリット」が、地球に
送ってきた写真である。
スピリットは、2004年1月3日に火星に到達している。
つまりこの写真は、どんなに早くて、2004年1月
3日以後に撮影されたものということになる。
この「2004年」という年号に注意しておいてほしい。
その上で、私自身が描いた新聞上のイラストと、
スピリットが送ってきた写真を見比べてみてほしい。
もし逆、つまり私が描いたイラストがスピリットが
送ってきた写真よりあとということなら、私が
スピリットの送ってきた写真を模してイラストを
描いたと疑われてもしかたない。
しかし私のほうが、先に書いている。
2000年の11月である。
スピリットがこの写真を送ってきたのは、少なくとも
2004年1月以後である。
私がスピリットの送ってきた写真を模してイラストを
描いたということは、ありえない!
つまりこれが、私という小さな人間の、ささやかな、
実にささやかな「証拠」ということになる。
「宇宙人は存在する」という、ささやかな証拠
ということになる。
+++++++++++++++
(1)
<img src="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/84/imge35bb262zik5zj.jpeg
" width="652" height="846" alt="2000年月1125日発表の原稿">
" width="652" height="846" alt="2000年月1125日発表の原稿">
★2000年、私が発表したコラム
★原稿より(上、写真版の読みづらい人は、どうか下をお読みください。)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●見たぞ、UFO!(中日新聞記事より)(2000年11月)
見たものは見た。巨大なUFO、だ。
ハバが一、二キロはあった。しかも私と女房の二人で、それを見た。
見たことにはまちがいないのだが、何しろ二十五年近くも前のことで「ひょっとしたら…」
という迷いはある。が、その後、何回となく女房と確かめあったが、いつも結論は同じ。「ま
ちがいなく、あれはUFOだった」。
その夜、私たちは、いつものようにアパートの近くを散歩していた。時刻は真夜中の一
二時を過ぎていた。そのときだ。何の気なしに空を見あげると、淡いだいだい色の丸いも
のが、並んで飛んでいるのがわかった。私は最初、それをヨタカか何かの鳥が並んで飛ん
でいるのだと思った。
そう思って、その数をゆっくりと数えはじめた。
あとで聞くと女房も同じことをしていたという。が、それを五、六個まで数えたとき、私
は背筋が凍りつくのを覚えた。
その丸いものを囲むように、夜空よりさらに黒い「く」の字型の物体がそこに現われたか
らだ。
私がヨタカだと思ったのは、その物体の窓らしきものだった。
「ああ」と声を出すと、その物体は突然速度をあげ、反対の方向に、音もなく飛び去って
いった。
翌朝一番に浜松の航空自衛隊に電話をした。
その物体が基地のほうから飛んできたからだ。が、どの部署に電話をかけても「そういう
報告はありません」と。
もちろん私もそれがUFOとは思っていなかった。
私の知っていたUFOは、いわゆるアダムスキー型のもので、UFOに、まさかそれほど
までに巨大なものがあるとは思ってもみなかった。
が、このことを矢追純一氏(UFO研究家)に話すと、矢追氏は袋いっぱいのUFOの写
真を届けてくれた。
当時私はアルバイトで、日本テレビの「11PM」という番組の企画を手伝っていた。
矢追氏はその番組のディレクターをしていた。
あのユリ・ゲラーを日本へ連れてきた人でもある。
私と女房はその中の一枚の写真に釘づけになった。私たちが見たのと、まったく同じ形の
UFOがあったからだ。
宇宙人がいるかいないかということになれば、私はいると思う。
人間だけが宇宙の生物と考えるのは、人間だけが地球上の生物と考えるくらい、おかしな
ことだ。
そしてその宇宙人(多分、そうなのだろうが…)が、UFOに乗って地球へやってきても
おかしくはない。
もしあの夜見たものが、目の錯覚だとか、飛行機の見まちがいだとか言う人がいたら、私
はその人と闘う。
闘っても意味がないが、闘う。私はウソを書いてまで、このコラム欄を汚したくないし、
第一ウソということになれば、私は女房の信頼を失うことになる。
……とまあ、教育コラムの中で、とんでもないことを書いてしまった。
この話をすると、「君は教育評論家を名乗っているのだから、そういう話はしないほうがよ
い。君の資質が疑われる」と言う人もいる。
しかし私はそういうふうにワクで判断されるのが、好きではない。文を書くといっても、
教育評論だけではない。
小説もエッセイも実用書も書く。ノンフィクションも得意な分野だ。東洋医学に関する本
も三冊書いたし、宗教論に関する本も五冊書いた。うち四冊は中国語にも翻訳されている。
そんなわけで私は、いつも「教育」というカベを超えた教育論を考えている。
たとえばこの世界では、UFOについて語るのはタブーになっている。だからこそあえて、
私はそれについて書いてみた。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
<img src="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/85/imgecf17303zik8zj.jpeg
" width="682" height="653" alt="イラスト拡大図(2000年11月の記事より)">
" width="682" height="653" alt="イラスト拡大図(2000年11月の記事より)">
★コラムの中のイラストの拡大図
<img src="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/66/img61c597d8zik2zj.jpeg
" width="1023" height="1023" alt="d88cbd81.jpg">
" width="1023" height="1023" alt="d88cbd81.jpg">
★火星探査機「スピリット」が送ってきた、火星上空を浮遊するUFO(2004年)
<img src="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/65/img62d89929zikczj.jpeg
" width="480" height="640" alt="●火星上のUFO.jpg">
" width="480" height="640" alt="●火星上のUFO.jpg">
★(UFOの拡大写真)
<img src="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/86/img4e55c54czikbzj.jpeg
" width="874" height="980" alt="2004年に火星探査機「スピリット」によって撮影された火星
上空のUFO">
" width="874" height="980" alt="2004年に火星探査機「スピリット」によって撮影された火星
上空のUFO">
★別の本に紹介された、火星上空のUFO(「世界のUFO現象」(学研))
●宇宙人は、確かにいる!
私はあの夜のことを忘れない。
あの夜、私とワイフは、UFOを見た。
が、当初、私は、それをUFOとは思わなかった。
私が聞いていたUFOは、円盤形のものをいう。
「く」の字型(ブーメラン型)のUFOなど、知るよしもなかった。
しかも、巨大だった。
天空をぐいと横切るほど、巨大だった。
新聞記事の中では、1、2キロと書いたが、実際のところ、よくわからない。
それよりも大きかったかもしれない。
あるいは小さかったかもしれない。
が、飛行機とは比較にならないほど、巨大だった。
あの夜見たものを、もう一度、整理しておきたい。
(1)窓
私もワイフも窓らしきものを目撃している。
大きな丸い窓(?)で、よく見ないとわからないほど、淡い橙色のものだった。
私はそれはジグザグに並んでいたように思うが、ワイフは、一直線だったと言っている。
(2)黒いシルエット
私は黒いシルエット(輪郭)を見ているが、ワイフはよく覚えていないという。
最初はそのシルエットは見えなかった。
少しずつ黒くなって、真上にきたとき、黒いシルエットとなった。
黒いシルエットが、その背景の夜空よりも黒く、夜空に浮かびあがった。
月は出ていなかったように記憶している。
私が記憶しているシルエットは、中日新聞紙上で発表したとおりである。
私はその形を忘れないように、当時、何かにメモした記憶がある。
(3)消え方
私が見たそのUFOは、西の方角からゆっくりやってきて、真上に来たとき、突然
スピードをあげ、東の方角へ飛んでいった。
スーッという感じだった。
そのときのこと。
そのUFOは、遠ざかって消えるというよりは、空に溶け込むようにして
消えていった。
大きさは遠ざかるにつれて小さくなったように感じたが、そのまま透明になり、
消えていった。
その先に白い小さな筋雲がいくつかあったように記憶している。
そのUFOは、雲の中に消えたのではない。
(4)自衛隊に電話
その直後、私は電話帳で自衛隊基地の番号を知り、電話をかけた。
何度もかけたように記憶している。
その夜は、ほとんど一睡もせず、朝を待った。
電話がやっとつながったのは、午前8時30分だったように記憶している。
つながった先は、たしか「管制室」だったと思う。
電話口の向こうの男性は、「そういう報告はあがっていません」とだけ、何度も
繰り返した。
私は「そんなはずはない!」と、何度も押し問答を繰り返した。
「あんな大きなものが上空を通過したのに、レーダーに映っていないはずがないだろ!」
と言った記憶がある。
(参考)(豊田ひろし氏のHPより抜粋)
『……火星の表面を移動し、水が存在した証拠を探る米航空宇宙局(NASA)の無人探
査車「スピリット」が米太平洋時間3日[2004年1月]午後8時35分(日本時間4日午後1
時35分)、火星に着陸、周囲の写真撮影に成功しました。
スピリットは、火星の大気圏に時速1万9000キロ以上の高速で突入。パラシュートとロ
ケット噴射で減速するとともに、24個のエアバッグを膨らませて本体を包み、着陸後バウ
ンドを繰り返した末に無事停止しました。専門家が「地獄のようなもの」と呼ぶ、1400度
を超す高温と接地時の激しい衝撃に耐え、探査車は生き残りました。
スピリットは2003年6月10日MER-A 1号機によって打ち上げられ,約7ヶ月弱で火星
に到着しました。
スピリットは今後約1週間かけて観測機器の機能を確認。その後約3カ月間、周囲を走り
回り、カメラや試料採取装置などを使って岩石や土壌の組成を分析、水の痕跡を探ること
で、生命の有無を確かめます。いままでは,すべてモノクロ写真の地上撮影でしたが,今回
は地上のカラー写真もはじめて撮影しました』(豊田ひろし氏のHPより)。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●希望論(2000年ごろ書いた原稿より)
希望にせよ、その反対側にある絶望にせよ、おおかたのものは、虚妄である。
『希望とは、めざめている夢なり』(「断片」)と言った、アリストテレス。
『絶望の虚妄なることは、まさに希望と相同じ』(「野草」)と言った、魯迅などがいる。
さらに端的に、『希望は、つねに私たちを欺く、ペテン師である。
『私のばあい、希望をなくしたとき、はじめて幸福がおとずれた』(「格言と反省」)と言っ
た、シャンフォールがいる。
このことは、子どもたちの世界を見ているとわかる。
もう一〇年にもなるだろうか。
「たまごっち」というわけのわからないゲームが、子どもたちの世界で流行した。
その前後に、あのポケモンブームがあり、それが最近では、遊戯王、マジギャザというカ
ードゲームに移り変わってきている。
そういう世界で、子どもたちは、昔も今も、流行に流されるまま、一喜一憂している。
一度私が操作をまちがえて、あの(たまごっち)を殺して(?)しまったことがある。
そのときその女の子(小一)は、狂ったように泣いた。「先生が、殺してしまったア!」と。
つまりその女の子は、(たまごっち)が死んだとき、絶望のどん底に落とされたことになる。
同じように、その反対側に、希望がある。
ある受験塾のパンフレットにはこうある。
「努力は必ず、報われる。希望の星を、君自身の手でつかめ。○×進学塾」と。
こうした世界を総じてながめていると、おとなの世界も、それほど違わないことが、よ
くわかる。
希望にせよ、絶望にせよ、それはまさに虚妄の世界。
それにまつわる人間たちが、勝手につくりだした虚妄にすぎない。その虚妄にハマり、と
きに希望をもったり、ときに絶望したりする。
……となると、希望とは何か。絶望とは何か。
もう一度、考えなおしてみる必要がある。
キリスト教には、こんな説話がある。あのノアが、大洪水に際して、神にこうたずねる。「神
よ、こうして邪悪な人々を滅ぼすくらいなら、どうして最初から、完全な人間をつくらな
かったのか」と。
それに対して、神は、こう答える。「人間に希望を与えるため」と。
少し話はそれるが、以前、こんなエッセー(中日新聞掲載済み)を書いたので、ここに
転載する。
++++++++++++++++++++
子どもに善と悪を教えるとき
●四割の善と四割の悪
社会に四割の善があり、四割の悪があるなら、子どもの世界にも、四割の善があり、四
割の悪がある。
子どもの世界は、まさにおとなの世界の縮図。
おとなの世界をなおさないで、子どもの世界だけをよくしようとしても、無理。子どもが
はじめて読んだカタカナが、「ホテル」であったり、「ソープ」であったりする(「クレヨン
しんちゃん」V1)。
つまり子どもの世界をよくしたいと思ったら、社会そのものと闘う。
時として教育をする者は、子どもにはきびしく、社会には甘くなりやすい。
あるいはそういうワナにハマりやすい。
ある中学校の教師は、部活の試合で自分の生徒が負けたりすると、冬でもその生徒を、プ
ールの中に放り投げていた。
その教師はその教師の信念をもってそうしていたのだろうが、では自分自身に対してはど
うなのか。自分に対しては、そこまできびしいのか。
社会に対しては、そこまできびしいのか。
親だってそうだ。子どもに「勉強しろ」と言う親は多い。しかし自分で勉強している親は、
少ない。
________________________________________
●善悪のハバから生まれる人間のドラマ
話がそれたが、悪があることが悪いと言っているのではない。
人間の世界が、ほかの動物たちのように、特別によい人もいないが、特別に悪い人もいな
いというような世界になってしまったら、何とつまらないことか。
言いかえると、この善悪のハバこそが、人間の世界を豊かでおもしろいものにしている。
無数のドラマも、そこから生まれる。旧約聖書についても、こんな説話が残っている。
ノアが、「どうして人間のような(不完全な)生き物をつくったのか。
(洪水で滅ぼすくらいなら、最初から、完全な生き物にすればよかったはずだ)」と、神に
聞いたときのこと。
神はこう答えている。
「希望を与えるため」と。
もし人間がすべて天使のようになってしまったら、人間はよりよい人間になるという希望
をなくしてしまう。
つまり人間は悪いこともするが、努力によってよい人間にもなれる。
神のような人間になることもできる。旧約聖書の中の神は、「それが希望だ」と。
________________________________________
●子どもの世界だけの問題ではない
子どもの世界に何か問題を見つけたら、それは子どもの世界だけの問題ではない。
それがわかるかわからないかは、その人の問題意識の深さにもよるが、少なくとも子ども
の世界だけをどうこうしようとしても意味がない。
たとえば少し前、援助交際が話題になったが、それが問題ではない。
問題は、そういう環境を見て見ぬふりをしているあなた自身にある。
そうでないというのなら、あなたの仲間や、近隣の人が、そういうところで遊んでいるこ
とについて、あなたはどれほどそれと闘っているだろうか。
私の知人の中には五〇歳にもなるというのに、テレクラ通いをしている男がいる。
高校生の娘もいる。
そこで私はある日、その男にこう聞いた。「君の娘が中年の男と援助交際をしていたら、君
は許せるか」と。するとその男は笑いながら、こう言った。
「うちの娘は、そういうことはしないよ。うちの娘はまともだからね」と。
私は「相手の男を許せるか」という意味で聞いたのに、その知人は、「援助交際をする女性
が悪い」と。
こういうおめでたさが積もり積もって、社会をゆがめる。子どもの世界をゆがめる。
それが問題なのだ。
________________________________________
●悪と戦って、はじめて善人
よいことをするから善人になるのではない。
悪いことをしないから、善人というわけでもない。
悪と戦ってはじめて、人は善人になる。
そういう視点をもったとき、あなたの社会を見る目は、大きく変わる。子どもの世界も変
わる。(中日新聞投稿済み)
++++++++++++++++++++++
このエッセーの中で、私は「善悪論」について考えた。
その中に、「希望論」を織りまぜた。それはともかくも、旧約聖書の中の神は、「もし人間
がすべて天使のようになってしまったら、人間はよりよい人間になるという希望をなくし
てしまう。
つまり人間は悪いこともするが、努力によってよい人間にもなれる。
神のような人間になることもできる。それが希望だ」と教えている。
となると、絶望とは、その反対の状態ということになる。キリスト教では、「堕落(だら
く)」という言葉を使って、それを説明する。
もちろんこれはキリスト教の立場にそった、希望論であり、絶望論ということになる。
だからほかの世界では、また違った考え方をする。
冒頭に書いた、アリストテレスにせよ、魯迅にせよ、彼らは彼らの立場で、希望論や絶望
論を説いた。
が、私は今のところ、どういうわけか、このキリスト教で教える説話にひかれる。
「人間は、努力によって、神のような人間にもなれる。それが希望だ」と。
もちろん私は神を知らないし、神のような人間も知らない。
だからいきなり、「そういう人間になるのが希望だ」と言われても困る。
しかし何となく、この説話は正しいような気がする。
言いかえると、キリスト教でいう希望論や絶望論に立つと、ちまたの世界の希望論や絶望
論は、たしかに「虚妄」に思えてくる。
つい先日も、私は生徒たち(小四)にこう言った。授業の前に、遊戯王のカードについて、
ワイワイと騒いでいた。
「(遊戯王の)カードなど、何枚集めても、意味ないよ。
強いカードをもっていると、心はハッピーになるかもしれないけど、それは幻想だよ。
幻想にだまされてはいけないよ。
ゲームはゲームだから、それを楽しむのは悪いことではないけど、どこかでしっかりと線
を引かないと、時間をムダにすることになるよ。
カードなんかより、自分の時間のほうが、はるかに大切ものだよ。
それだけは、忘れてはいけないよ」と。
まあ、言うだけのことは言ってみた。しかしだからといって、子どもたちの趣味まで否
定するのは、正しくない。
もちろん私たちおとなにしても、一方でムダなことをしながら、心を休めたり、癒(いや)
したりする。
が、それはあくまでも「趣味」。決して希望ではない。
またそれがかなわないからといって、絶望する必要もない。
大切なことは、どこかで一線を引くこと。
でないと、自分を見失うことになる。時間をムダにすることになる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●ポール・クルーグマン氏(ノーベル科学賞受賞者)
ポール・クルーグマン氏について、ウィキペディア百科事典には、つぎのようにある。
『ポール・クルーグマン(Paul Robin Krugman、1953年2月28日)は、アメリカの
経済学者、コラムニスト。
現在、プリンストン大学教授、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授を兼任。
1991年にジョン・ベーツ・クラーク賞、2004年にアストゥリアス皇太子賞社会科学部門、
2008年にはノーベル経済学賞を受賞した。
専門の国際経済学の分野以外でも積極的に発言しており、反ジョージ・W・ブッシュの旗
手としても知られる。
また、2008年の民主党大統領候補指名のキャンペーンでヒラリー・クリントン候補のメデ
ィケア政策を擁護し、一時的にバラク・オバマ陣営から批判が出たものの、結果的にはメ
ディケアに対してオバマ陣営が当初表明していた共和党寄りの方針を撤回させ、民主党の
本流の政策に転換させることに成功している。
ただし、この論争がしこりとなりクルーグマンは民主党の要職から外れることになった』
(以上、ウィキペディア百科事典より)と。
ポール・クルーグマン氏については、そういう人であるということがわかった。
MSNニュースにあるように、「ノーベル科学賞」ではなく、「ノーベル経済学賞」。
そう言えば、「ノーベル科学賞」というのは、聞いたことがない。
正しくは「ノーベル経済学賞」。
ともかくも、そういう人の発言であるだけに、たいへん興味深い。
●宇宙人はいる!
宇宙人論では、私はかなり叩かれた。
事実、教育の世界で宇宙人を口にすると、即、変人扱いを受ける。
(ただし私は教室で、子どもたちに宇宙人の話をしたことはない。念のため。)
「君は教育者を名乗るのだから、そういうことは口にしないほうがいい」と忠告してく
れた人もいる。
(私自身は、「教育者」を名乗ったことは、一度もないのだが……。)
が、ここに書いたコラムのように、「見たものは、見た!」。
たったそれだけのことだが、この日本では、それすら、自由に言ったり書いたりすること
ができない。
……つまり、こうして一歩、一歩、アメリカ政府やNASAを追いつめていく。
彼らは、何かを隠している。
つまり何かを知っている。
それを知るのは、人類全体の「希望」でもある。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 ノア 人間を滅ぼすく
らいなら ポール・クルーグマン はやし浩司 火星上空のUFO ブーメラン型UFO)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●時間という砂時計
++++++++++++++++++++
ワイフの老眼鏡が、合わなくなった。
老眼の度が進んでいるという。
眼科医で調べてもらうと、ドクターがそう言ったという。
そこで近くのメガネ屋へ。
大通りに出て右に曲がると、やがて橋を越える。
橋全体が高くなっていて、一瞬だが、見晴らしがよくなる。
川幅は50メートル前後はあるだろうか。
近くの佐鳴湖から浜名湖へ流れる、人工の用水である。
時は晩秋。
明るい日差しを浴びて、川面が光っていた。
が、見ると、ちょうど釣り人が、ルアーを川に投げ込むところだった。
カラフルな服を着ていた。
++++++++++++++++++++++
●人それぞれ……
生き様は人、それぞれ。
私は私、あなたはあなた。
人は人。
しかしそれを見た瞬間、私はこう思った。
「ぼくには、できないな」と。
……こう書くからといって、魚釣りが、どうこう言うのではない。
また釣り人が、どうこう言うのではない。
先にも書いたように、人、それぞれ。
が、私にはできない。
そうでなくても、時間が足りない。
「忙しい」というのではない。
「時間が足りない」。
●レジュメ
午前中は、今度浜北区の文化センターで講演をすることになった。
その資料をまとめた。
浜松市内では、今年度最後の講演会である。
総まとめ。
その日に向け、テンションを高めていく。
昨日から少しずつだが、運動量もふやした。
そのため、つまり資料の整理のために、1〜2時間ほどつぶした。
で、そのあと、もう一度、自動車G会の原稿に目を通す。
英文で要約説明文も、書かねばならない。
巻頭言で6ページ。
全世界で発行されるという。
それぞれの国の言語に翻訳されるという。
いろいろな原稿を書いてきたが、これほどまでの依頼は、はじめて。
気合いが入る。
●田丸謙二先生
田丸謙二先生が、いかに偉大な人物であるかは、いまさらここに書くまでもない。
肩書(経歴)を並べたら、とても1枚の紙には収まらない。
その田丸謙二先生が、先日、ドイツで行われた「ハーバー記念講演会」に講師として招か
れた。
全世界から1000人近い、科学者が集まったという。
ノーベル賞受賞者も多数、いたという。
が、何よりも驚くのは、今年、田丸謙二先生が、88歳であるということ。
常識的に見れば、ヨボヨボの老人ということになる。
その田丸先生に、自動車G会の原稿を送った。
●裸で勝負
「田丸謙二先生へ、
今度自動車G会のために書いた原稿を送ります。
年1回発行され、全世界で配布されます。
先生にお会いしたのが、1970年。
そのとき私は心に誓いました。
『この先生と、裸で勝負してやる』と。
先生は東大で、30代で教授になったとか。
東大でも最年少で教授になったと、先生は自慢していました。
で、以来、42年。
先生から見れば、ヒヨコみたいかもしれませんが、いっさいの組織に属することもなく、
いっさいの肩書もなく、ここまでがんばってきました。
ぼくも、88歳までがんばってみます」と。
●魚釣り
先にも書いたように、「とにかく時間がない」。
今の私は、その一言に尽きる。
知りたいことは、山のようにある。
知らないことも、これまた山のようにある。
1冊の週刊誌を読んだだけでも、頭の中でバチバチと火花が飛ぶ。
だからといって、私の生き様が正しいとか、また人もそうであるべきとか、そんなふうに
考えているわけではない。
私は私。
人は人。
が、今の私には、仮に100歩譲っても、魚釣りはできない。
食べ物に困って、その食材にということであるなら、話は別。
しかしすぐ、こう考えてしまう。
「……だから、それがどうしたの?」と。
つまり「魚を釣ったからといって、それがどうしたの?」と。
私に当てはめてみると、その答が返ってこない。
どうしても返ってこない。
●健康余命まで、あと4年
命は砂時計のようなもの。
「……ようなもの」ではなく、「命は砂時計」と断言してもよい。
刻一刻と、命は短くなっていく。
その心境は大病で、死を宣告された患者と同じ。
「あなたはがんです。余命はあと半年です」と宣告されれば、だれだって慌てる。
が、「あなたの寿命は、あと14年です」と言われても、慌てる人はいない。
が、どうして?
たったの14年だぞ!
私は現在、64歳。
日本人の平均余命(男性)は、79歳前後。
もっともそれまで元気なら、まだよいほう。
その前、平均して10年間ほど、病魔と闘わねばならない。
(平均余命)から10年を引いた年齢。
これを「健康余命」という。
つまり健康でこうしてがんばれるのも、あと4年。
たったの4年だぞ!
それを思ったら、とても魚を釣って時間をつぶす余裕などない。
少なくとも、私にはない。
●だからそれがどうしたの?
私はよく自分に問いかける。
「だから、それがどうしたの?」と。
そのときズシリとした答が返ってくるときもあれば、そうでないときもある。
その答がないとき、私は深い悔恨の念にとらわれる。
「時間を無駄にした」と。
先に『命は砂時計』と書いた。
命は、砂時計の砂のように、刻一刻と、下へ落ちていく。
「砂」といっても、ただの砂ではない。
それがわからなければ、「金」に置き換えてもよい。
若い人にしても、そうだ。
時間給はそれぞれちがうだろう。
しかし同時に、命は、1時間ごとに減っていく。
金銭で置き換えることはできない。
しかしまさに「金(ゴールド)」。
あるいは、はるかにそれ以上。
●定年退職者?
のどかな風景。
どこにでも見られる風景。
このところ、プラス気になるのは、私の年代層の人たちが、急にふえてきたということ。
見た感じでは、定年退職者?
本当に魚釣りを楽しんでいるというよりは、暇つぶし?
こう書くとたいへん失礼ということは、よくわかっている。
あるいは本当は、そういう人たちでも、こう叫びたいのかもしれない。
「もっと仕事をしたい」「もっと意味のあることをしたい」と。
書き忘れたが、用水といっても、全国でも汚染度ナンバー5前後を争っている。
そんな湖から流れ出てくる用水の魚を釣って、食べる人はいない。
だとするなら、なおさら、「……だから、それがどうしたの?」となる。
●老後は孫の世話?
が、たぶん、若い人たちはこう考えるにちがいない。
「人生も終わったのだから、ゆっくり休んだらどう?」と。
私も若いころは、老人たちを見て、そう考えていた。
「老後は、庭いじりと孫の世話」と。
しかし私のその年齢になった。
なってみて、こんなことがわかった。
青い空は、やはり青い空。
白い雲は、やはり白い雲。
老人組に入ったからといって、色があせてくるわけではない。
自分の髪の毛の白さにしても、顔のシワにしても、自分では見えない。
つまり心は、若いときと、何も変わっていない。
若い人たちが、「庭いじりと孫の世話はできない」と思うのと同じように、私たちだって、
本音を言えば、それだけで時間をつぶすことはできない。
が、それよりも恐ろしいことが起きるようになる。
●底に穴のあいたバケツ
これは推測でも何でもない。
医学的に証明された事実でもない。
しかし実感として、老人組に入ると、それがよくわかる。
つまり脳みその底に穴があいたような状態になる。
それがよくわかる。
その穴から、知識や経験、技術や能力が、どんどんと外へこぼれ出ていく。
ほんの数か月前まで知っていたことが、消えてしまったり、ほんの数週間前までできた
ことができなくなったりする。
そんなことが連続して起きるようになる。
ど忘れなど、日常茶飯事。
それは恐怖以外の何物でもない。
が、闘う方法がないわけではない。
先に書いた田丸謙二先生は、50歳を過ぎて中国語を独学し、60歳のころ、中国の科学
院(もっとも権威のある学会)で、記念講演をしている。
もちろん中国語、で!
そういう先生を鏡にすると、一瞬一秒、無駄にできる時間はない。
が、もしここで今、現在の状態の上にアグラをかいてしまったら……。
それこそ死の待合室にまっしぐら。
たわいもない世間話か、兄弟親類のゴシップ話。
そんな話に花を咲かせるようになる。
しかも繰り返し、繰り返し、同じ話をするようになる。
●終わりに
だからといって、繰り返すが、魚釣りがどうのとか、それを楽しんでいる人がどうのと
か、そんなことを書いているのではない。
私は私。
あなたはあなた。
人は人。
それぞれの人が、それぞれの人生を歩む。
大切なことは、それぞれの人がそれぞれの人の人生を認めあうこと。
わかっている!
このエッセーを読んで、こう思っている人もいるにちがいない。
「はやし浩司もかわいそうな男だ」と。
「人生を楽しむことも知らない、あわれな男だ」と。
しかし誤解しないでほしい。
今の私には、今の私が楽しい。
こうして日々に新しい発見をしていくことが、私には楽しい。
……こうして私に好き勝手なことをさせてくれるワイフに感謝しながら……。
(はやし浩司 2011―11―13日記)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 7日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page018.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【幼児に、言葉としての英語をどう教えるか】(実践教育)
●会話ではなく、言葉。言葉としての英語を、幼児にどう教えるか。それが今回のレッス
ンの目的です。もちろん相手は幼児ですから、「文法」を教えても意味はありませんね。…
…ということで、今回のレッスンを考えてみました。結果はまずまずでした。
(1)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/E-83SzwvgWk?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/L8F9JW9oGZ8?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/VM30locA55I?hl=ja
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(4)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/t4nhhyi-R-c?hl=ja
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 言葉としての英語をど
う教えるか 英語教育 幼児の英語教育 はやし浩司 言葉教育 幼児教育 英語の文法
言葉)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●秋の夕暮れ時
夕方になって、やっと少し時間ができた。
……というか、現在、TOSHIBAのR631の初期設定を進めている。
アンチ・ウィルス・ソフトは、「Microsoft Security Essentials」(無料版)を使うことに
した。
それと現在は、WINDOWのUPDATE中。
この2つだけで、すでに1時間ほど時間を無駄にした。
外はすっかり夕暮れモード。
庭のクルミの木の葉が、冷たい冬の風の中で、ヒラヒラと揺れている。
今にも落ちそうな、枯れた葉。
私は子どものころから、こういう景色が苦手。
気分まで落ち込んでしまう。
●パソコン作法
パソコンをネットにつなげるためには、この先、無線LANの設定をしたあと、メールの
初期設定をしなければならない。
作業そのものは、たいしたことない。
しかし今は、それがもどかしい。
言い換えると、こういう作業がつづくから、パソコンはただの電気製品ではない。
この段階で、パソコンを投げ出してしまう人も多い。
では、だれかに接続してもらえば、それでよいかというと、そうでもない。
パソコンを使いこなすには、それなりの知識と経験、それに失敗が必要。
冷や汗をかきながら、人は、パソコンの使い方を学習する。
「ウィルスが入った」と平気な顔をしておられる人は、まったくの素人か、それなりの経
験者。
そのどちらか。
重要なファイルは、いつも二重、三重に保存しておく。
それはパソコンを使うときの、大鉄則。
●遠鉄デパート
JR浜松の駅前に、今度、遠鉄デパートが、新しいオープンした。
南側に旧館。
北側に新館。
「冥土のみやげに」ということで、今夜、ワイフと行ってみた。
私の印象としては、電車の乗客を、どこまで取り込めるかで、成否が決まるのでは?
車でやってくる人もいるが、それだけでは各フロアを客で満たすことはできない。
やはり電車の乗客。
が、それ以上に驚いたのは、人通りの多いこと。
土曜日の夜ということもあって、通りにはゾロゾロと人が歩いていた。
浜松市は、町(=駅前)の活性化ということで、毎年、億単位の予算を組んでいる。
その効果はあるのか、ないのか。
たとえば遠鉄電車のガード下を利用した、「べんがら横丁(ラーメン横丁)」は、5、6年
を経た今、閑古鳥が鳴いている。
半数は、店をたたんでいる。
正確には、13店舗中、5店舗が厚いボードで店を包んでいる。
遠鉄デパートから、歩いて1分もない。
理由は、本気度の欠落。
店の作りからして、お粗末。
で、成否を決めるのは、本気度。
遠鉄デパートでは、その本気度を感じた。
……というか、今、全国、どこへ行っても駅前は元気がない。
みじめなのは、郷里の岐阜市。
岐阜駅の前。
シャッター街がずらりと並んでいる。
最近、駅前の2つのデパートですら、閉店したと聞いている。
だから浜松くらいは……というふうに、最近は考えるようになった。
で、その遠鉄デパート。
私が見たところ、高級品店をねらっているよう。
どの階でもワイフがこう言った。
「高いわねえ」と。
松菱デパートの失敗もある。
現在のバブル経済がはじけ、この先、大不況の荒波が押し寄せたとき、果たして遠鉄デパ
ートは、生き残ることができるのか?
がんばれ、浜松!
がんばれ、遠鉄!
……と書いてみたが、私自身は、リピーターになることは、まずないだろう。
モノを買うこともない。
あれほどの高級店は、私には縁がない。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●映画『1911』
帰りに、劇場で、映画『1911』を観てきた。
断言はできないが、台湾製の映画と思う。
それとも香港製?
孫文をこの上なく、称えている。
イマイチ、主題がどこにあるのか、よくわからなかった。
編集が甘いというか、的をしぼりきれていない?
孫文の映画なのか、ジャッキーチェンの映画なのか、それとも戦争映画なのか?
恋愛映画のようでもあり、政治的プロパガンダ映画のようでもあった。
映像そのものは、『赤壁』に優るとも劣らない映画であっただけに、残念。
……というか、「台湾映画、恐るべし!」という印象をもった。
星は、3つの、★★★。
楽しんで観る映画というよりは、歴史の重みをズシリと感ずる映画だった。
(注)ネットで調べてみたら、「製作国、中国」となっていた。
漢字が簡略体になっていたので、「?」と思っていたが……。
中国映画、恐るべし!
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【R631】【映画「1911】【優越感vs劣等感】
●秋の夕暮れ時
夕方になって、やっと少し時間ができた。
……できたというか、今現在、TOSHIBAのR631の初期設定を進めている。
その第一。
アンチ・ウィルス・ソフトのインストール。
そのアンチ・ウィルス・ソフトには、「Microsoft Security Essentials」(無料版)を使う
ことにした。
無料ながら、ほかの有料ソフトにひけをとらない(Mr. PC誌)。
Microsoft社製ということからもわかるように、安心して使える。
が、さらにすごいことができる。
エクスプローラーで調べたいファイルを選び、そこで右クリックをすると、そのファイル
だけをチェックしてくれる。
それと目下、WINDOWのUPDATE中。
この2つだけで、すでに1時間ほど時間を無駄にした。
外はすっかり夕暮れ時。
庭のクルミの木の葉が、冷たい冬の風の中で、ヒラヒラと揺れている。
今にも落ちそうな、ボロボロの枯葉。
私は子どものころから、こういう景色が苦手。
気分まで落ち込む。
●パソコン作法
パソコンをネットにつなげるためには、この先、無線LANの設定をしたあと、メールの
初期設定をしなければならない。
作業そのものは、たいしたことない。
10〜20分前後ですむはず。
しかし今は、それがもどかしい。
言い換えると、こういう作業がつづくから、パソコンはただの電気製品ではない。
この段階で、パソコンを投げ出してしまう人も多い。
では、だれかに設定を手伝ってもらえば、それでよいかというと、そうでもない。
パソコンを使いこなすには、それなりの知識と経験、それに失敗が必要。
冷や汗をかきながら、人は、パソコンの使い方を学習する。
「ウィルスが入った」と平気な顔をしていられる人は、まったくの素人か、それなりのプ
ロ。
そのどちらか。
そういうこともあるから、重要なファイルは、いつも二重、三重に保存しておく。
それはパソコンを相手にするときの、大鉄則。
●遠鉄デパート
JR浜松の駅前に、今度、遠鉄デパートが、新しいオープンした。
南側に旧館。
北側に新館。
「冥土のみやげに」ということでもないが、今夕、ワイフと行ってみた。
私の印象としては、電車の乗客を、どこまで取り込めるかで、成否が決まるのでは?
車でやってくる人もいるが、それだけでは各フロアを客で満たすことはできない。
やはり電車の乗客。
が、それ以上に驚いたのは、人通りの多いこと。
土曜日の夜ということもあって、人がゾロゾロと歩いていた。
浜松市は、町(=駅前)の活性化ということで、毎年、億単位の予算を組んでいる。
その効果はあるのか、ないのか。
たとえば遠鉄電車のガード下に、「べんがら横丁(ラーメン横丁)」というのがある。
が、5、6年を経た今は、閑古鳥が鳴いている。
半数は、店をたたんでいる。
正確には13店舗中、5店舗が厚いボードで覆われている。
遠鉄デパートから、歩いて1分もない。
そんなところでも、このあり様。
理由は、本気度の欠落。
店の作りからして、お粗末。
で、成否を決めるのは、本気度。
遠鉄デパートでは、その本気度を感じた。
……というか、今、全国、どこへ行っても駅前は元気がない。
みじめなのは、郷里の岐阜市。
JR岐阜駅の前。
シャッター街がずらりと並んでいる。
最近、駅前の2つのデパートですら、閉店したと聞いている。
だから浜松くらいは……というふうに、最近は考えるようになった。
「浜松くらいは、がんばってほしい」と。
で、その遠鉄デパート。
私が見たところ、高級店をねらっているよう。
どの階でもワイフがこう言った。
「高いわねえ」と。
つまり値段が高い、と。
松菱デパートの失敗もある。
浜松の松坂屋をねらったが、数年で倒産した。
現在のバブル経済がはじけ、この先、大不況の荒波が押し寄せたとき、果たして遠鉄デ
パートは、生き残ることができるのか?
がんばれ、浜松!
がんばれ、遠鉄!
……と書いてみたが、私自身は、リピーターになることは、まずない。
モノを買うこともない。
あれほどの高級店は、私には縁がない。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●映画『1911』
街へ行った帰りに、劇場で、映画『1911』を観てきた。
断言はできないが、台湾製の映画かと思う。
それとも香港製?
孫文をこの上なく、称えている。
が、イマイチ、主題がどこにあるのか、よくわからない映画だった。
編集が甘いというか、的をしぼりきれていなかった。
孫文の歴史映画なのか、ジャッキー・チェンの映画なのか、それとも革命映画なのか?
恋愛映画のようでもあり、政治的プロパガンダ映画のようでもあった。
映像そのものは、『赤壁』に優るとも劣らない映画であっただけに、残念。
……というか、「台湾映画、恐るべし!」という印象をもった。
星は、3つの、★★★。
ジャッキー・チェンの演技がすばらしかったので、おまけに(+)の★★★+。
楽しんで観る映画というよりは、歴史の重みをズシリと感ずる映画だった。
(注)ネットで調べてみたら、「製作国、中国」となっていた。
漢字が簡略体になっていたので、「?」と思っていたが、中国映画だった。
中国もすごい映画を作るようになった。
中国映画、恐るべし!
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●SSDパソコン
R631には、ハードディスクは搭載されていない。
SDメモリーのみ。
そのため、起動がめちゃめちゃ速い。
スイッチONから、デスクトップ画面まで、10秒もかからない。
「速い」「速い」と喜んでいたら、こんな弊害も現れた。
私はほかにも、TOSHIBAのダイナブックを4台使っている。
が、そのどれもが、使い物にならなくなってしまった。
遅いのなんのといったら、これでは勝負にならない。
モタモタというより、モッタリ、モッタリ……という感じ。
この先、パソコンは、SSDが主流になる。
一度、SSDパソコンを使ったら、ほかのパソコンが使えなくなる。
まちがいなく、そうなる。
●人生は一度でたくさん
人は先へ行ってはじめて、うしろが見える。
自分が利口になってはじめて、それまでの自分がバカだったと知る。
R631を使ってみて、改めて、それを確認した。
つまりより性能のよいパソコンを使ってはじめて、それまでのパソコンがいかに性能の悪
いものだったかがわかる。
映画『1911』の中に、こんな気になるシーンがあった。
若い男性が、ジャッキー・チェンに向かって、こんなようなことを言う。
「あなたはもう老人だから、未来はない」(記憶)と。
しかし本当に、そうか?
自分が老人組だからというわけではないが、私たちには過去があり、その分だけ、若い人
たちの未来がよく見える。
が、若い人たちには、それが見えない。
私たち老人組は、みな、バカと思っている。
しかし私たち老人組からみると、若い人たちは、みな、バカに見える(失礼!)。
私たちがしてきたのと同じ過去を繰り返しながら、自分では自分の人生を歩んでいるつも
りでいる。
つまり老人には未来がないのではない。
若い人たちが言う「未来」は、すでに経験済み。
その上で、私たち老人組は、自分の人生を生きている。
少し回りくどい言い方をしたが、平たく言えば、こう。
「私たちには未来がある。老人には未来がない」と、優越感に浸(ひた)ってはいけな
い。
明日のことはわからない。
あなたは老人になる前に、命を終えるかもしれない。
事故や病気は、運と確率の問題。
さらに言えば、「命」は、「生き様」の問題。
無益にダラダラと時間を無駄にするかもしれない。
年齢という数字の問題ではない。
優越感に浸れば浸るほど、いつか、逆の立場になったとき、あなたが今度は追われる立
場になる。
これは何も、(年齢)にかぎった話ではない。
だから私自身は、こう思う。
神様か何かが現れて私にこう言ったとする。
「君を、40年、若くしてあげようか」と。
もし今のままの知識と経験をもったまま、40年、若くしてくれるならよい。
しかし脳みそも一度、リセットされるというのであれば、私は断る。
人生は一度で、たくさん。
こりごり。
またすべてをイチから始めろと言われても、私には、できない。
だから断る。
相手の命の短さを理由に、優越感に浸ってはいけない。
浸れば浸るほど、今度はその人生観で、いつか自分が苦しむことになる。
●人間の価値
もし優越感があるとするなら、(その反対に劣等感でもよいが)、こんなとき。
たとえばだれにもまねできないような、偉業をなしたとき。
あるいは反対に、だれにもまねできないような偉業をなした人に出会ったとき。
一度、ワールドカップ・日本代表だった選手と、2時間ほど、話したことがある。
私の教室の生徒の親だった。
そのときのこと。
対峙して座ったとたん、身がひきしまるような緊張感を覚えた。
同時に、別の心でこんなことを考えた。
「私は20代の男性を前に、大きな劣等感を覚えている」と。
「私は彼の年齢のとき、何をしていたのだ」とも。
そういう過ごし方をした人なら、反対に私に対して優越感をもったとしても、おかしく
ない。
しかしそういう人にかぎって、おおらかで、穏やか。
人を包み込むようなやさしさを、併せもっている。
つまりその人の価値は、(何をした人か)(何をしている人か)で決まる。
肩書や経歴など、腸から出るガス程度の意味もない。
もちろん(年齢)ではない。
……こう書くからといって、私はけっして自己弁護しているわけではない。
私は先日、64歳になった。
若い人たちからみれば老人組だが、私自身は、自分が老人と思っていない。
まだまだ若い……という意味で、「ヤング・オールド・マン(Young Old Man)」と位置づけ
ている。
仕事も健康も、快調。
「仕事がない」と言って、そこらでショボくれている若い人たちよりは、ずっと意気軒昂
(けんこう)。
そういう私だから、年配の人にも、年齢に関係なく、敬意を払っている。
どんな老人を見ても、「この人には未来がない」などと思ったことはない。
●優越感
要するに優越感にせよ、劣等感にせよ、そういったものには、意味はない。
ナンセンス!
そう言い切ってもよい。
……というようなことを、映画『1911』の1シーンを観ながら、考えた。
本物をベースにした映画だけに、迫力もあった。
次回は、ブラッド・ピット主演の『マネー・ボール』。
あるいは『インモータルズ』。
楽しみ。
●11月12日夜
こうして2011年11月12日も終わる。
家に帰り、寝支度がすんだのが、午後11時40分。
明日の午前中は、とくに予定がない。
早起きして、思う存分、R631を叩いてみたい。
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●就寝
先のところまで書いて、今まで、数時間。
とくに何かをしたわけではないが、時間だけ、過ぎてしまった。
時計を見ると、午後11時30分。
もうそんな時刻!
ふとんの中で半分体を起こし、今、この文章を書いている。
光るキーボードが美しい。
・・・ふと見ると、ワイフがすでにイビキをかいている。
ほんの5分前まで、まだ起きていた。
私も眠い。
しかしいつまでもこうして、文章を書いていたい。
本当のことを言えば、こうしてキーボードに触れていたい。
超薄型パソコンということで、ストローク(キーの深さ)は浅いが、じゅうぶんなクリッ
ク感はある。
パチパチというより、ひざの上で、トントン、パタパタと鳴る。
(「パタパタ」というのは、ENTER・KEYを叩いたときの音。)
それが心地よい。
・・・とはいえ、もう私も眠らなくてはいけない。
●午前5時(2011ー11ー12)
今朝は午前5時に目が覚めた。
トイレに行き、そのまま居間へ。
軽い偏頭痛があったので、Z剤を半分に割ってのむ。
熟睡していても痛いのが、偏頭痛。
その偏頭痛のせいで、寝起きに、いやな夢を見た。
どうしてだろう?
つまりどうして偏頭痛なのだろう。
このところ精神状態は、悪くない。
日々が楽しく、それなりに満足している。
ワイフとも仲がよい。
神経を使うということもない。
●原稿依頼
自動車技術会(公益社団法人)から、原稿依頼をもらった。
その機関誌に、6P(ページ)の原稿を書かせてもらうことになった。
年に1度の機関誌という。
前もって打診はあったが、依頼書を見て仰天。
20P近い企画案内と、原稿の体裁についての注意書きがあった。
ワイフにそれを見せると、「すごい企画書ね」と。
日本の自動車会社が共同して発行する機関誌という。
私もこうして原稿を書くようになって40年。
しかしここまで「すごい!」企画書は、見たことがない。
たいていは、「○○字x○○行」ですんでしまう。
原稿は完成しているので、再度推敲し、来週中には相手方へ届けたい。
●レッツノート
今日は土曜日。
とくに予定はない。
会う人もいない。
・・・こうしてR631を叩いていると、12年ほど前に使っていた、TOSHIBA
のダイナブックSSと、PANASONICのレッツノートを思い出す。
ダイナブックSSは当時としては、超薄型のパソコンだった。
23万円ほどもした。
ボロボロになるまで使い倒した。
(本当にボロボロになった。)
レッツノートも薄型だったが、キーボードが平たく、ツルツルしていた。
その感触が、このR631と同じ。
どちらも愛用のパソコンだったが、両方とも、1〜2か月で故障。
とくにレッツノートは、それ以後、4、5回も修理に出した。
CDドライブが着脱式になっていて、本体との相性がたいへん悪かった。
当時は、一度修理に出すと、戻ってくるまで、1か月以上もかかった。
そんなこともあり、レッツノートは、それ以後、一度も買っていない。
●狂乱状態
今朝はまだニュースに目を通していない。
見たいが、心のどこかでブレーキが働いている。
目まぐるしいというより、狂乱状態。
先にも書いたように、ギリシャがあぶないと思っていたら、今度はイタリア。
その前にキプロスがおかしくなった。
同時に、ベルギー、オーストリア、フランスまで……。
今度は、ハンガリー?
なぜか?
少し、視野を広げてみると、それがよくわかる。
・・・つまり地中海の上(北)と下(南)。
距離はそれほど離れていないが、生活レベルがあまりにも、ちがいすぎる。
同じ人間が、同じように働いている。
しかし「上」の人たちは、それほど働いてもいないのに、優雅な生活を楽しんでいる。
一方、「下」の人たちは、働けど働けど、極貧状態。
「南北格差」という言葉がある。
しかしこれほどまでにひどい「格差」のある地域は、ほかにない。
ヨーロッパだけ。
今、その格差が縮み始めている。
そう考えると、EUの狂乱状態が、よく理解できる。
必死でユーロの「力」を守ろうとする、EU。
それをよしとしない、新興勢力。
激震に激震を重ねながら、ユーロも、やがて、ごくふつうの通貨になっていく。
ついでにアメリカのドルも、日本の円も・・・。
●破壊主義
が、だからといって、そのまま享楽主義に走ることは、正しくない。
もしそれぞれの人が享楽主義、つまり自分だけがその場を楽しめばよいと考えるようにな
ったら、それこそ、世界はおしまい。
欲望だけが、むき出しになってしまう。
人間は頭がよい分だけ、教育の仕方をまちがえると、たいへん。
欲望がぶつかりあうと、破壊主義が生まれる。
破壊主義は、そのまま戦争につながってしまう。
何としても、それだけは避けなければならない。
●人間の価値
とは言っても、そこには「現実」がある。
生きていかねばならない。
そのためには、ある程度の収入を確保しなければならない。
・・・これについては、がんばるしかない。
それぞれの個人が、それぞれの立場で、がんばるしかない。
どこまでがんばれるか、本当のところ自信はないが、がんばるしかない。
ただひとつ気になっているのは、「命」の価値が、年々、たいへん軽くなりつつあること。
私にしても、(そしてこの文章を読んでいるあなたにしても)、死ねば、骨から灰になり、
そのまま消えてなくなってしまう。
数年もすれば、身内の人にすらも、忘れられてしまうだろう。
人と人のつながりが、家族の中においても、希薄になってきている。
つまり(つながり)イコール、(人間の価値)と考えてよい。
その価値が低下し始めている。
今では隣人が亡くなっても、「ああ、そう」で終わってしまう。
その人が老齢であれば、なおさら。
●仕事
私はまだラッキーなほう。
仕事がある。
が、老後を考えると、暗たんたる気持ちになる。
年金というと、国民年金だけ。
「何もないよりはマシ」という金額だが、この先、猛烈なインフレが待ち構えている。
「タクシーの初乗りが、1万円」と。
そんな時代に、6万5000円前後の年金をもらって、どうする?
どうなる?
貯金ゼロの家庭が、全体の30%以上もあるという。
60歳の定年退職時においてですら、約50〜60%。
気がついてみたら、子どもの学費で使い果たしてしまったという人も多い。
だから死ぬまで働くしかない。
が、それを「不幸」と、とらえてはいけない。
少なくとも、私は不幸とは思っていない。
●講演活動
たとえば講演にしても、それがあるからこそ、生活の中に緊張感が生まれる。
1週間ほど前から、体調を整える。
運動量をふやす。
食事に気をつける。
ここ4〜5年は、講演旅行をかねて、ワイフとその先で、できるだけ一泊するようにし
ている。
それがまた楽しい。
雑誌「President」の最新号の中にも、こう書いてあった。
『心の豊かさは収入の額ではない。お金の使い方で決まる』(記憶)と。
映画を観て、帰りに回転寿司を食べる。
それだけでハッピーになれる人は、いくらでもいる。
●アンチ・ウィルスソフト
偏頭痛は収まったが、何かした頭がフア〜ッと浮いたような状態。
薬の副作用と思われる。
要するに、偏頭痛薬というのは、基本的には血管収縮剤。
緩んだ血管を、収縮させる。
今が、その状態?
・・・しかし今、EUは、どういう状況なのだろう。
気にはなる。
が、このR631は、まだネットにはつながっていない。
アンチ・ウィルスソフトをどうしようか、まだ結論が出ていない。
市販(有料)のものもあるが、雑誌などによれば、マイクロソフト社から、無料のアンチ・
ウィルスソフトが配布されているという。
「Microsoft Security Essentials」というのが、それ。
有料版に近い、ウィルス検出能力があるという。
ほかにも、「AVG Anti-Virus Free Edition 2012」というのもある。
どうしようか?
この世界では、無料イコール、無責任。
アンチ・ウィルスソフトだけは、しっかりとしたものをインストールしたい。
ネットに接続するのは、そのあと。
●天高く……
今、雨戸を開け、今日、はじめて空を見た。
「天高く・・・」というのは、こういう空のことを言うらしい。
昨夜までの雨模様は収まり、そこには水色のさわやかな空が広がっていた。
こういう朝は、筋雲が美しい。
それが幾重にも連なり、まるで長い髪の女性が、髪を風になびかせているかのようにも見
える。
先ほど雨戸を開けたとき、サーッと冷気を含んだ風が部屋の中に入ってきた。
さわやかな朝。
GOOD MORNING!
しばし空の美しさに、見とれる。
●ニュース
もう一台のノートパソコンで、いくつかのニュース・サイトを開いてみた。
今では新聞よりも先に、(もちろんテレビよりも先に)、ニュースはネットで読む。
新聞は、その確認用。
一方、まったく意味のないのが、テレビのニュース。
ウソこそ言わないが、本当のことも言わない。
これだけ情報が氾濫してくると、私たちはその向こうにある、隠された意図というものま
で読み取ることができるようになる。
テレビは、たしかに私たちの心を、巧みに操っている。
それがわかるようになる。
●ニュース
NYダウは、259ドル高。
EU市場も、落ち着いているよう。
Bloombergによれば、「EUに楽観論、広がる」とある。
が、「よかった!」とは、私は思わない。
明日のことは、わからない。
こんなことで一喜一憂していたら、それこそ気がヘンになる。
取り越し苦労に、ヌカ喜び。
むしろ気になったのは、アメリカ・サンフランシスコ連銀のウィリアムズ総裁が、つぎの
ように発言したこと(Bloomberg)。
「新たな資産バブルが形成される、著しいリスクがある」と。
それもそのはず。
これだけ市中に、お金(マネー)をばらまけば、そのあと世界はどうなるか。
そんなことは、私のような者でも、よくわかる。
ウィリアムズ総裁は、「それが暴走したときが、こわい」と。
●朝風呂
今朝は朝風呂になりそう。
朝風呂といっても、昨夜、風呂に入るのをサボった。
それで朝風呂になりそう。
ワイフがタブに湯を入れ始めた。
・・・こうしてR631の処女航海は、無事すんだ。
使い勝手は、たいへんよい。
当初、キーの縦幅がやや狭いのが気になった。
が、打ち始めてみると、それはすぐ解消した。
巨大なENTERキーにも、すぐ慣れた。
叩くたびに、パタパタという音がするのは、許容範囲。
愛嬌。
今までの周辺機器が、そのまま使えるのもよい。
(他社のUltra bookは、接続コネクターが必要。)
ただ色が、あまりよくない。
「色はシルバー」とあるが、実際には、ダーク・シルバー。
イメージが暗い。
悪い。
これはTOSHIBA製のパソコンすべてに共通している点だが、どこか事務機器ぽい。
オシャレ感に乏しい。
が、パソコンは事務機器ではない。
愛用品。
心の通う愛用品。
もっていて楽しい・・・というパソコンにしてほしい。
しかしこれで現役のTOSHIBA・ダイナブックは、計5台になった。
(はやし浩司 2011−11−12朝記)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 12月 5日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page017.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【小学1&2年生に、割り算を教えてみました】
(1)小学1年生クラス
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nyLT4l4wYbg?hl=ja
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)小学1年生クラス
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/SmVkawhwCyI?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)小学1年生クラス
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/rHWr-4WXuAo?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
(1)小学1&2年生クラス(Active Children)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/WZ8o9V5I8AQ?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)小学1&2年生クラス(Active Children)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/19cerFdKphY?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)小学1&2年生クラス(Active Children)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/L46BUArgYcA?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 割り算 割り算レッス
ン 日本の小学1年生 Active Learning 愉快な子どもたち 活発に学ぶ子どもたち わ
り算練習)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●7・206
現在(08:15)、イタリア(10年国債)の利回りは、7・206。
午前7:15分時と、変化なし。
はげしい動乱のあと、EUも、やっと眠りについたらしい。
で、今度は、この日本。
株価はどう動くか。
大和、野村の株価は、どう動くか。
目が離せない!
……ということで、今日も始まった。
田丸謙二先生、みなさん、おはようございます。
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【教育とエデュケーション】
●2011年11月11日(金曜日)(はやし浩司 2011−11−11)
++++++++++++++++++
今朝は、雨。
冷たい雨。
肌寒いが、身がひきしまる。
一、二度、くしゃみを繰り返す。
そう言えば、昨日から鼻水が出る。
どこか花粉症ぽい?
今日は、インフルエンザの予防注射を受けてくる。
ワイフは、2週間ほど前にすませた。
+++++++++++++++++
●雑感
曇天より、雨のほうがよい。
降るなら降る。
はっきりしてほしい。
私はそのほうが、好き。
ところで、こんな話。
教育観は、教師によって、みなちがう。
180度ちがうときもある。
たとえば私は、いつも、(そこにいる子ども)を原点にし、子どもを考える。
さまざまな問題があっても、それはそれ。
仮に何かの障害(?)をもっていても、不問。
IQなど、話題にしたこともない。
すべてが、そこからスタートする。
一方、テストにテストを重ね、「ここに問題がある」「あそこに問題がある」と子どもの
問題を指摘しながら、指導する教師もいる。
もちろんIQテストも頻繁に繰り返す。
子どもの問題や能力を、数値化する。
指導の結果も、数値化する。
どこか教育の視点が、無機質化している。
が、この方法は、私のやり方ではない。
AD・HD児を例にあげて、考えてみたい。
●「教育」と「エデュケーション」
「教育」と「エデュケーション」は、基本的に方向性が、逆。
反対向き。
「教育」とは、「教え育てる」ことをいう。
寺の本山教育を思い起こせばよい。
わかりやすく言えば、「教え育てることによって、子どもを一定のワクに閉じこめようよす
る」。
一方、エデュケーションは、「educe」が語源になっている。
もともとは「引き出す」という意味である。
それぞれの子どもには、すでに自ら伸びる能力が宿っている。
その能力を引き出すのが、「educe」。
が、その能力は、みな、ちがう。
個性をもっている。
わかりやすく言えば、「子どもがもつそれぞれの能力を、じょうずに引き出してやる」。
それが「エデュケーション」ということになる。
●AD・HD児
……という話は、何度も書いてきた。
田丸謙二先生は、いつもそう言っている。
が、この(ちがい)には、もうひとつ、重要な意味が隠されている。
たとえばこんな例で考えてみよう。
AD・HD児と呼ばれる子どもがいる。
昔は、多動児とか、多動性児とか、あるいは活発型遅進児(まったく遅れてなどいないが)
とか、呼ばれた。
このタイプの子どもでも、小学3〜4年生を境に、急速に症状が落ち着いてくる。
自己認識能力(=自分を客観的に評価する能力)と、自己管理能力(=自分を自らコント
ロールする力)が、身についてくるからである。
が、幼児期や児童期においては、そうでない。
どう(そうでない)かは、すでに、みな、よくご存知の通り。
「問題児」とか、「指導困難児」とか呼ばれている。
●私の経験
AD・HD児という言葉がさかんに使われるようになったのは、2000年前後から。
そのころ、日本にはまだ診断基準もなかった。
時の厚生省が研究班を組織し、特定の大学に診断基準の作成を依頼したのも、そのころの
こと。
が、ADHD児と呼ばれる子どもは、すでに40年前にもいた。
(当然のことだが・・・。)
私は一度、このタイプの子どもに、自分の研究授業をメチャメチャにされたのをきっか
けに、たいへん興味をもつようになった。
強く叱っても、効果は一時的。
10〜15秒も効果はつづかなかった。
で、勤めていた幼稚園の園長に相談し、このタイプの子どもだけを数人、教えさせても
らうことにした。
数人が限度だった。
が、教えるというよりは、毎日、プロレスごっこ。
20代の私でも、1時間、接しただけで、ヘトヘトになるほどだった。
●診断名
西洋医学の世界では、体に不調が起きると、まず診断名をつける。
診断名をつけたあと、診断名に応じて、攻撃的な治療にとりかかる。
これが西洋医学的なものの考え方であり、治療法である。
つまり診断基準を設けるということは、すでにその時点において、西洋医学的な視点で
子どもを見ているということになる。
「この子どもは、ADHD児である」と。
一見科学的(?)だが、しかし重要な視点を見落としている。
「相手は、人間である」。
しかし40年前の当時には、そんな診断名すら、なかった。
またなくても、困らなかった。
私はやがて、・・・といっても、それを知るまでに、10年以上もかかったが、こう考えるよ
うになった。
「時を待てば、自然に解決する」と。
脳の器質的障害(=機質的障害)は別として、AD・HDのような機能的障害については、
子ども自身に自己治癒能力が備わっている。
年齢とともに、脳の機能が、自らを正常化していく。
その結果というわけではないが、それ以後の研究によれば、あのモーツアルトも、エジ
ソンも、そしてチャーチルも、AD・HD児だったと言われている。
さらに最近では、あのアインシュタインも、そうであったと、言われ始めている。
もちまえのバイタリィテイが、ある年齢以上になると、よい方向に作用し始める。
●複雑化
が、2000年以後、診断基準が確立されると、「リタリン」という薬がこの日本でも使
用されるようになった。
私は、即、その薬についての文献を、アメリカでさがした。
が、驚いたことにすでにそのとき(2000年ごろ)、リタリンの副作用や弊害が指摘され
ていた。
そのことは、私のHPにそのまま翻訳し、収録した。
(現在でも、その当時の文献は、そのままHPに残っている。)
が、それから数年の間、リタリンは、ADHD児の特効薬として、ごくふつうに、学校内
部でも使用された。
昼休みの時間などに、保険の教師が、子どもに投与しているのを、私は何度も見かけたこ
とがある。
が、子どものばあい、とくに幼児のばあい、脳の機能(=脳間伝達物質)をいじる薬物
治療については、慎重であったほうがよい。
脳には、フィードバック機能というのがある。
ある特定の脳間伝達物質を服用すると、脳自体が本来もつ機能を停止してしまう。
これがかえって症状を、悪化させてしまう。
それが理由だと思うが、現在、リタリンの使用は、AD・HD児に関しては、使用がき
びしく制限されている。
●幼児性
つまり私はADHD児という言葉がポピュラーになる前、すでに30年近い経験を積ん
でいたことになる。
(こんなことを自慢しても、何にもならないが・・・。)
そこへ降ってわいたように、AD・HD児という言葉が出てきた。
治療法(?)も、出てきた。
学校によっては、診断基準に応じて、特別学級が用意されるようになった。
たしかにAD・HD児は、「指導困難児」である。
それは事実。
教育の場である「教室の秩序」を、容赦なく破壊してしまう。
が、幼児期から児童期にかけ、症状さえこじらさなければ、先にも書いたように、症状は
やがて落ち着いてくる。
が、こじらせば、話は別。
薬物療法を受けた子どもや、はげしい指導(強圧的、威圧的な指導)を受けた子どもは、
AD・HDの症状のほか、複合的な症状をあわせもつようになる。
当然のことながら、その分だけ、「立ち直り」が遅れる。
顕著な症状としては、人格の核(コア)形成の遅れがあげられる。
その年齢(学年)なのに、その年齢(学年)に比して、著しく幼い印象を与える。
小学6年生なのに、小学3〜4年生のように見えるなど。
だから指導のポイントは、つぎのようになる。
「症状をこじらせないよう、あとは時期を待つ」。
●自然治癒力
話を戻す。
そこにAD・HD児がいたとしても、それはそれ。
まずその子どもが、そういう子どもであることを認める。
診断名がついていたとしても、教育の場では、不問。
わかっていても、知らぬフリをし、指導を開始する。
指導が「困難」といっても、「不可能」ではない。
それにワクに入らないからといって、「問題児」と決めつけてはいけない。
(日本人は、古来より、「型」を重要視する。
ワクからはみ出る子どもを、嫌う。
しかしこれこそ、悪しき「本山教育」の弊害。)
ポイントは、先にも書いたように、症状をこじらせることがないよう、時期を待つ。
つまりここで「引き出す」という言葉が生きてくる。
仮にAD・HD児であっても、子ども自身がもつ、自然治癒力や自然平衡能力、そういっ
た力が自然に機能するまで、待つ。
平たく言えば、脳の機能も、年齢とともに成長する。
●終わりに
要するに(引き出す)ということ。
つまりこと教育に関して言うなら、(診断)→(治療)という、西洋医学的な視点は、参考
にはなっても、本題であってはならない。
なぜなら、どんな子どもでも、1人の人間であり、現にそこにいるからである。
相手がどんな子どもであっても、そこにいる子どもを認め、その上で、指導を組み立てて
いく。
教育者の考えるワクに入らないからといって、その子どもを問題視するほうが、まちが
っている。
いわんや「型」に押し込めようとするのは、まちがっている。
もし教師がやるべきことがあるとするなら、その子どもがもつ、自然治癒力を引き出すと
いうことになる。
……という意味で、今一度、「educe(引き出す)」の意味を考えてみた。
その一例として、AD・HD児について、考えてみた。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 教育とエデュケーショ
ン 引き出す教育 ADHD児 AD・HD児 多動性児 多動児 はやし浩司 教育に
おける診断と治療)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●雑感(なぜ男性便器の周辺は、汚れるのか?)
ときとして、(……というより、いつもそうなのだが……)、無駄なことを考えて遊んで
いる。
たとえば先日来より気になっているのが、男子トイレの汚れ。
不潔さ。
女性は知らないかもしれないが、どこの男子トイレへ行っても、便器のまわりは汚れてい
る。
それを見て、だれしもこう考える。
「ちゃんと便器の中へすれば、そんなに汚れないのに……」と。
私もそう考えていた。……考えている。
「どうして汚れるのか」「汚れないようにするためには、どうすればいいのか」と。
いろいろ理由があることがわかってきた。
そのひとつは、小便というのは、本体の小便のほか、周囲を霧状になって散る小便がある。
これは明るい太陽を横にし、立ち小便をしてみるとよくわかる。(大発見!)
チリも積もれば……ということで、それが便器の周辺に飛び散る。
便器の周辺を汚す。……(1)
が、それだけではない。
男性のばあい、(女性のことは知らないが)、それが終了するとき、そのまま途切れるの
ではなく、一部が、ソーセージに沿って、下内側へ逆行する。
表面張力という力が働いて、逆行する。
……と考えていたが、よくよく観察すると、どうもそれだけではなさそうだ。
実は……ということで、前から知ってはいたが、改めて発見した。
小便の出口は、管状になっているのではない。
細い縦糸状になっている。
男性というのは、いつも上からソーセージを見ているので、知っていても、直接それを
見ることは、めったにない。
イメージとしては、管状。
しかし実際には、縦糸状。
つまり出口が縦糸状になっているから、それが終わるとき、しずくが縦に流れる。
それが先に書いた表面張力の力で、ソーセージの下から逆方向に落ちる。(大発見!)
だから便器の中へではなく、そのまま便器の外へ落ちる。
便器の周辺を汚す。……(2)
●では、どうすればよいか?
(1)による汚れをなくすためには、小便をできるだけ低い位置からすればよい。
立ってするから、霧状の小便が、周囲に飛び散る。
(2)による汚れをなくすためには、ソーセージより後方に、便器を広げる。
しかし実際には、足がじゃまになるので、それができない。
そこでもう少し深く、考えてみる。
なぜ出口が縦糸状なのか、と。
理由はすぐわかった。
もともと人間は、四つ足で歩いたり、走ったりしていた。
犬が小便する様を思い浮かべてみればよい。
その姿勢では、ソーセージは、真下に向かってたれさがっている。
が、人間は二足歩行をするようになった。
そのため人間は、ソーセージを真横に向けて、小便をするようになった。
そもそも、……こう結論づけるのは危険かもしれないが、横に向かって小便をすることに
は、無理がある。
無理だから、小便の一部が逆行してしまう。
では、どうするか?
もうおわかりかと思うが、ソーセージを真下に向けて小便をする。
ズボンのチャックを横にではなく、真下にあける。
真下にあけて、そこから手を突っ込んで、ソーセージを引き出す。
そして真下に向かって、シャーッ(ジャーッでもよい)と、小便を出す。
が、実際問題として、手を下から入れて、ソーセージを出すのは不可能。
だったら、男性もスカートをはけばいい?
が、そうすると、これまたいろいろな問題が出てくる。
下着はどうするか?
●結論
よく純和風の旅館に泊まったりすると、便器が、筒状の傘立てのようになっているとこ
ろがある。
あれならよい。
男性はその筒状の便器の真上に、それをまたいで立ち、ソーセージをまっすぐ下に向け、
小便をする。
そうれば、(1)と(2)の問題を、同時に解決することができる。
便器のまわりを汚さないですむ。(大発見!)
要するに、現在の便器には、欠陥がある。
その欠陥故に、便器のまわりが汚れる。
ふとどきな連中が、便器のまわりを汚すのではない。
ソーセージそのものが、汚すようにできている。
そこで結論。
便器は傘立てのように筒状にする。
小便はその上でまたいでする。
そのときソーセージをしっかりと下に向けてする。
ソーセージと便器の高低差はできるだけ小さくする。
そうすれば、便器の周辺を汚さないですむ。……はず。
以上、男子トイレについて、考察を加えてみた。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 男性便器 便器 どう
して男性のトイレは不潔なのか 汚れるのかはやし浩司 男子トイレ 男子トイレ考察)
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●ULTRABOOK TOSHIBA R631/28D
+++++++++++++++++++++++
ACER社とSUSAS社、それにTOSHIBA社。
これら3社から、ULTRABOOKが、出そろった。
3社3様。
が、私は、カタログで、私はTOSHIBAのR631に、決めていた。
そのR631が、11月11日(本日)、発売になった。
駅前のB店に行くと、それが並んでいた。
他の2社と比較すると、やや値段が高いかなと感じた。
「Office/Home & Business2010」が、付属しているということもある。
が、私は日本人。
迷ったら、日本製。
それにノートパソコンは、TOSHIBA製と決めている。
ただ発売当日に購入というのも、どうかと思った。
1〜2か月もすると、値段が、数万円程度は安くなる。
が、それまで待ちきれない。
・・・ということで、購入。
今、そのR631で、この文章を打っている。
+++++++++++++++++++++++
●R631
一度自分のモノになったら、批評はしない。
批評すれば、自分がさみしくなる。
よくても悪くても、この先、いっしょにつきあうしかない。
私のほうが、パソコンに慣れる。
自分に「これはよいパソコン」と、繰り返し言って聞かせる。
それしかない。
そのR631。
よいパソコンだ。
ENTERキーが大きいのが、二重丸。
バッテリーのもちも、9時間(実測でも7時間程度)。
それだけあれば、ほぼ一日中、使える。
が、何よりもすばらしいのは、起動が速いこと。
電源を入れて、10秒ほどで、デスクトップ画面が現れる。
SSD(ハードディスクの代わりにSDを使ったパソコン)のすごさを、改めて実感する。
●欲望
で、その欲望。
欲望をすべて「悪」と決めつけてはいけない。
欲望そのものは、生きるエネルギーと直結している。
そのことは、生きる力をなくした老人を見れば、よくわかる。
私の母がそうだった。
元気なころは、ちぎり絵に没頭していた。
一日中、部屋にこもって、作品と取り組んでいた。
が、晩年の母は、ちぎり絵にまったく関心を示さなくなっていた。
私が材料や道具を用意して置いてみたが、手も触れようとしなかった。
生きる意欲そのものを失っていた。
もう1人、こんな人がいた。
車が好きで、元気なころは、つぎつぎと新型の車に乗り換えていた。
が、あるときから、パタンと、・・・本当にパタンと、車に興味を示さなくなってしまった。
何かの大病を患ったときのことだった。
その人はそのあと、しばらくして、亡くなってしまった。
だから・・・。
たとえば、(ものが欲しい)という欲求が生まれたら、(あくまでも60歳以上の人につい
ての話だが)、それを消さないようにする。
しばらく放っておくと、その欲望そのものが消えてしまう。
どうでもよくなってしまう。
●自己投資
が、こうなると、時間との勝負。
私が早くくたばるか、欲望が早くくたばるか・・・?
平均余命まで、あと15年。
何とかそれまでは、元気で過ごしたい。
そのためにも、欲望を大切にしたい。
ずいぶんと身勝手な、かつ手前味噌的な意見だが、今の私は、そう思う。
だから家に、ノートパソコンがいくらゴロゴロしていても、新しいパソコンを買う。
もう少し専門的な表現を借りるなら、自己投資。
脳みその健康のためには、自己投資を怠らない。
命はお金では買えない。
が、お金で命を延ばすことはできる。
だから、自己投資!
●条件反射
物欲そのものは、線条体に、受容体を作りやすい。
つまり条件反射が起きやすくなる。
ニコチン中毒やアルコール中毒と同じ。
新製品のカタログを見ているだけで、ググーッとそのモノがほしくなる。
これはまさしく条件反射。
若い男性が、女性のヌードを見たときのようなもの。
性欲本能は、(本能)で、ここでいう(条件反射)とは異質のものかもしれない。
しかし性欲も、扱い方によっては、受容体を形成しやすい。
たとえば女性の下着を見ただけで、(それも汚れた下着のほうがよいそうだ)、ググーッ
と性欲を覚えるなど。
だから欲望といっても、善玉と悪玉とに分ける必要がある。
どこでどうこの両者を区別するかについては、むずかしい。
しかし基本的には、欲望イコール、(生きる原動力)と考えてよい。
もちろん犯罪性をともなう、反社会的行為は別である。
●甘い陶酔感
・・・今のところ、R631が、たいへん気に入っている。
キーボードが打ちやすい。
画面も13・3インチ(ワイド)ある。
それに軽い!
驚くほど、軽い!
部屋の中を持ち歩いても、苦にならない。
それにもうひとつ、大発見。
欲望をじょうずに満たすと、脳の中に、モルヒネ様のホルモンが分泌される。
それが脳内を、甘い陶酔感(=満足感)で満たす。
その結果、買うまでは軽い頭痛があったが、それが消えた。
反対に欲望を抑え込むと、ストレスが増大する。
それが脳内ストレスを引き起こす。
サイトカインという悪玉ホルモンを分泌する。
このサイトカインには注意したほうがよい。
最悪のばあいには、体の免疫機能に作用して、免疫力そのものを弱めてしまう。
●結果論
これは結果論。
冒頭に書いたように、私は3つパソコンの中から、どれにするか、それに迷った。
が、もっとも値段が高く、性能もよいTOSHIBA製のパソコンを選んだ。
しばらく使ってみると、それが心地よい喜びとなって返ってきた。
「いちばん気に入ったパソコンを手にした」という喜びである。
こういうときは、いちばんよい機種を手にするのがよい。
二番手、三番手をもつと、かならず飽きる。
後悔する。
飽きて、結局は一番手が、またほしくなる。
ミニパソコンが出始めたころ、私はそれで失敗した。
つぎつぎと新製品が出たこともある。
気がついたときには、5〜6台のパソコンがテーブルの上に並んでいた。
もっとも当時は、それをもらい受けてくれる息子たちが近くにいたからよかった。
が、そういう失敗は、二度と繰り返したくない。
多少、値段は高くても、一番手、つまり本命をねらう。
だから昔の人は、こう言った。
『安物買いの、銭(ぜに)失い』と。
ただし一言。
パソコンだけは、いくら使わなくなっても、自分で処分する。
リカバリーしてから渡すという方法もないわけではない。
しかしめんどう。
削除したファイルでも、プロの手にかかると、簡単に生き返ってしまうそうだ。
●ワイフとの仕事
さて、そろそろ今年1年間を振り返るときが、やってきた。
早いもので、もう11月の中旬。
あっという間の1年だった。
で、この1年間を振り返ってみて、ひとつよいことがあった。
ワイフのこと。
ワイフが私の仕事を手伝ってくれるようになって、もう4〜5年になる。
当初は、ためらっていたが、今は、自分のほうから手伝ってくれるようになった。
親や子どもたち(=生徒たち)とのつながりができたこともある。
それがワイフなりの(生き甲斐)になってきた。
が、それだけではない。
私の仕事は、孤独との闘いだった。
その孤独を、ワイフが共有してくれるようになった。
たとえば若いころ、大切に思っていた生徒が退会したとする。
私はつらくて、それをワイフに話すことができなかった。
1〜2か月もして、「実は・・・」と。
が、今は、ワイフはそれを目の前で見ている。
私が思うのと同じくらい、それをつらく思ってくれる。
それだけでも、私の心は軽くなる。
・・・若いころは、ワイフにはそれが理解できなかったらしい。
私がそのつらさを、八つ当たりという形でワイフにぶつけたりした。
すると、ワイフはいつもこう言った。
「あなたは仕事のことしか考えていない!」と。
それが私を、さらに孤独のドン底へと、叩き落とした。
●すごい国!
もちろん、あの3・11大震災もあった。
あの震災が、日本という国を、根底からひっくり返した。
今も、その状態がつづいている。
電話でだれと話しても、みな不安そうにこう言う。
「この先、この日本はどうなるんでしょう?」と。
どうにもならない。
なるようにしか、ならない。
ただこう思うときもある。
「日本って、すごい国なんだなあ」と。
こんな状況になっても、見た目には、びくともしない。
円高をどうこう言う人もいるが、こんな大災難の中にあっても、円高!?
アメリカをはじめ、世界中が、通貨安競争を繰り広げた。
日本だけは、しなかった。
自制した。
(本当は、アメリカの圧力で、できなかったのだが・・・。)
その結果が今。
この先のことはわからないが、世界中が大恐慌に見舞われている中、日本だけは何とか持
ちこたえている。
(・・・と言っても、経済の動きは、そんな単純なものではない。
日本が円高なのは、ヘッジファンドが、この先日本経済が崩壊するのを先読みしているか
らにすぎない。
そう説く経済学者もいる。)
●緊張感
経済の話は、もうやめよう。
憂うつになるだけ。
こうした金融危機は、いつなんどき、自分たちの身に降りかかってくるか、わかったもの
ではない。
とんでもないところから、突然、始まる。
ギリシャ、ギリシャと騒いでいたら、今度はキプロス、イタリア。
イタリア、イタリアと騒いでいたら、今度はオーストリア、ベルギー。
さらに今度は、フランス、それにベルギー・・・。
それらがそのまま、さらなる恐慌へとつながっていく。
それにしても、このピンと張りつめたようなこの緊張感。
息が抜けない。
これはどうしたものか。
が、人間は、こうした緊張感に弱い。
それほど長く、もたない。
そのときが、こわい。
●バツをつけると怒る子ども
数日前、こんなことがあった。
小学高学年の子ども(生徒)だった。
その子どものテストを採点しているとき、当然のことだが、まちがえたところに赤ペンで
正しい答を書いてやった。
それを見て、その子どもはパニック状態になってしまった。
体中を緊張させ、恐ろしいほどの形相で、私をにらみ返した。
大声で泣きたいのを、必死でがまんしているといったふうだった。
それをワイフがうしろで見ていて、あとでこう言った。
「きっと悔しかったのね」と。
が、その子どもは悔しくて、そうなったのではない。
簡単に言えば、かんしゃく発作を起こした。
それ以前の問題として、軽いアスペルガー症候群、あるいは自己愛者的な症状も見られる。
心が閉じているから、そうなる。
つまりその分だけ、心に余裕がない。
その場で、ハハハと笑ってすますことができない。
そういう性質を私もよく知っていたから、ていねいな言い方で、採点をした。
それでもそうなった。
●儀式
新しいパソコンを買うと、最初の数晩は、枕元に置いて寝る。
またその前後には、指をキーボードに慣れさせる。
キーボードを指でこする。
これが私の儀式。
新しいパソコンを買ったときの、儀式。
指先の神経は、脳細胞のどこかに直結している。
指先の神経を刺激していると、やがて甘ったるい陶酔感が脳に満ちてくる。
モルヒネ様のホルモン(エンケファリンやエンドロフィン)が分泌されるためと言われて
いる。
また古来より中国では、モノをいじることによって、ボケを防止しているそうだ。
そういう効果もあるらしい。
ともかくも、指がキーボードに慣れるまで、少し時間がかかる。
やがてキーの表面が、指でこすれてピカピカになるころには、ブラインド・タッチができ
るようになる。
大のおとな(ジー様)が、パソコンを枕元に置いて寝るというのも、おかしな話に聞こ
えるかもしれない。
しかしこの習慣だけは、私が子どものころから変わっていない。
何か欲しいものを手に入れたときは、枕元に置いて寝た。
おそらく、死ぬまで変わらないだろう。
●光るキーボード
今回買ったパソコンは、キーボードが光る。
闇の中でも、文章を書くことができる。
いつか映画『トロン』の中で見たようなパソコンである。
横でそれを見たワイフがこう言った。
「不思議なパソコンね」と。
これがなかなか重宝。
車の中でもパソコンを使える。
枕元の電気を消したあとでも、パソコンを使える。
が、こんなに便利なものとは、知らなかった。
一度使ったら、後戻りできない。
光るキーボードは、そういう機能と考えてよい。
つぎにまたパソコンを買うときは、光るキーボード付のパソコン・・・ということになり
そう。
●柿
家に帰ると、従姉から柿が届いていた。
岐阜の柿である。
大きくて、色があざやかに輝いていた。
すぐ礼の電話を入れた。
私より1歳、年上の従姉だが、元気そうだった。
●浜北文化センターでの講演
今度、11月30日(水曜日)に、浜松市浜北区にある、文化センターで講演をするこ
とになった。
浜松市内では、今年最後の講演会である。
主催者の先生に電話を入れて確かめると、「一般参加もOK」とのこと。
もしこの文章を読み、時間がある人は、どうか聞きにきてほしい。
自信はないが・・・というのも、いつも失敗ばかりしているので・・・今度こそ、最高の
講演をしてみたい。
真剣勝負。
開場は、午後6時30分。
講演時間は7:00〜8:30ということになっている。
演題は『思春期前夜から思春期の子どもの心と発達』『こうすれば伸びる3つの方法』。
*********************
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 11年12月 3日号臨時
================================
2011年月8日1日現在……1552号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page016.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
********安全は確認しています。どうか安心して、お読みください*****
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●田丸謙二先生の講演旅行記より
Fritz Haber Institut の創立百年祭に招待されて
1911年にKaiser Wilhelm Institut として Berlinに創立された研究所が途中で Fritz
Haber Institut (FHI) と名前を変えて、今年の10月26日〜28日に創立百年のお祝いをし
た。
4年前にノーベル化学賞をとった前所長の Ertl 教授の75 歳の誕生日のお祝いも兼ねて、
世界中から一流の学者を招いての盛大な講演会でもあった。
参加した人たちは物理、化学は言うまでもなく化学史の専門家まで含み、千人近くの集ま
りであった。
私は百年の歴史の中での「Haber と日本」と題して、原稿も見ずに、この百年の間での田
丸家と Fritz Haber Institut との関連について講演をした。
内容的には亡父が1908年2月に Karlsruhe の Haber 研究室に留学し、「死ぬほど働
いて」アンモニア合成の成功に関与し、Haber が新設されたBerlin の Kaiser Wilhelm
Institut の所長になった折に直ちに亡父を所員に招き、第一次世界大戦が始まって日独が
敵対関係になるまで合計6年間 Haber と共に研究をして来た。
今回においてその当時亡父が撮った百年前の写真を何枚も出して見せたのは現在見せられ
た聴衆にとっては大変に印象的であったようであったし、FHI としても非常に貴重なもの
であった。
その後1918年に Haber はノーベル化学賞を受け、1924年に星一さんの招待に応じて夫妻
で来日をした。
在日中は各地で講演をし「国を発展させるには科学の振興が必要である]という、彼がド
イツで英仏をしのいで国を振興させた実績に基づいた講演をし、亡父がそれを翻訳し、自
分なりの科学振興の必要性も加えて、一冊の本として岩波から出版したのである。
(事実その頃の我が国から欧州への自然科学の留学の75%はドイツに行ったものである)
その影響もあってわが国では昭和一桁の非常な経済不況の中にありながら、Kaiser Wilhelm
協会をモデルにして日本学術振興会を作り、大学や研究所に研究費を増額分配し、ベルリ
ン工科大学をモデル化して東京工大を新設もした。
(尤もこの両方の学術振興の実積は亡父の尽力なしでは実現しなかったものである)Haber
がドイツの学術振興だけでなく結果的にはわが国でも科学振興の実績を積んだことは、ド
イツ人たちにとっても初耳であったし,大変に印象的でもあったらしい。(わが国でもほと
んど知られていない)
次世代として私が、世界で初めて触媒反応中に固体触媒表面の挙動を直接観察して、
それまで反応機構は推論に基づいていただけだったのを飛躍的に発展させて、触媒科学が
科学として生まれたことを触れて、それをErtl が例えば Photoemission electron
microscope を用いて見事な発展をもたらしてノーベル賞に至ったことに触れ、さらに婿の
大山茂生(現東京大学教授)がフンボルト賞を三年前にうけて Hajo Freund と共に半年間
FHI に滞在したことを告げて、結局田丸家は過去百年の間三代にわたり FHIと深い関係を
持って来たことを紹介し、これまで一世紀の間世界をリードして来たFHI が更なる新しい
世紀も世界をリードすることを願う、と言って話を閉じた。
話の途中に亡父が残した百年前の写真の中にある亡父が着ていたモーニングがベルリ
ン製であり、百年の間無事に保たれ、興味あることに私の娘の大山秀子にピッタリのサイ
ズであることを言って、秀子がその服を着て現れた時は拍手大喝采であったし、ハ―バー
夫妻が鎌倉の我が家を訪問した折の写真の中に、私が母の腕の中にいた赤ん坊であって、
ハーバーと直接会っている証拠でもあると言った時も拍手が湧いた。
話が終わってからの皆の態度はそれまでとはガラリと変わり、何十人もの人が入れ替
わりに、素晴らしい話だった、wonderful だけでも十何人か、, beautiful, elegant, moving
(感動的), gem (宝石)(招待に与った Friedrich さんの表現)、highlight (今回の
Centenary の議長を務めた FTI のdirector のGerard Meijer 教授も使った表現),
excellent (Ertl さんの表現)と各人なりの言葉を使って私に対してベタ褒めであった。
英語も解りやすく、素晴らしかったし、とにかく88歳の人があんな素晴らしい presentation をす
るなんて考えられない、という大変な評判であった。
るなんて考えられない、という大変な評判であった。
そうしてあの話はとても内容が素晴らしくて、話を聞いておくだけではもったいないし、
是非テレビで放送させ、その資料をドイツ化学会やFHIに永久に保存すべき話であるから、
面倒でももう一度同じ話をして貰いたいということになり、今度は聴衆は十何人か位のま
までもう一度 presentation をさせられた。
ビデオにまとまったら送ってくれるという。
とにかくこの上ない大変な好評であった。
ビジネスクラスの旅費まで出してくれてのご招待であったので、それに充分以上に報いる
ことが出来て本当によかったと思った。
中には鎌倉まで人を派遣して古い資料を見せてくれないか、とまで言われた。
FHI の図書室に「田丸古文書」の枠を作ることも議論されているとのことであった。
昔は従来英語で苦労をすることがなかったが、今回は耳が遠くなり、英語が聞き難く、
秀子が大分助けてくれた。
老化現象も耳の遠くなる不便さはどうにかしなければ、もっと優れた補聴器にするか、と
いうのが正直の感じであった。
幸い婿が全てを手配してくれたし、私は日本円を彼らにまとめて手渡しただけで、ドイツ
のお金は一文も使わずに、済ますことが出来た。
ベルリンでは日本に比べて非常な寒さであって、往復途中もよく眠れず、時差もあって肉
体的に大変な苦労であったし、風邪をこじらせながらようやく無事に帰国できた。(会議が
終わってから秀子たちと Romance Road を回って来た)
秀子が科学史の専門家に我が家には亡父が百年前に購入した Lavoisier ヤ Liebig
などの手書きの手紙があると伝えたら大変に興味を示していたという。
亡父が購入したままに置いてあっただけに、多分世界で唯一の本物の手書きの手紙だけに、
科学史の資料としても大変に貴重なものであるからである。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●ハーバー博士
ハーバーのおかげで、今、私やあなたは、ここにいる。
そう言っても何ら、過言ではない。
ハーバーは、空気中の窒素の固定化に成功した。
当時は、『空気からパンを作った』と、絶賛された。
私たち人類が受けた恩恵には、計り知れないものがある。
その私といえば……おととい、伊東市で講演をし、帰りに御殿場のホテルに泊まってき
た。
何とも書くのもみじめなほど、スケールが小さい。
情けない。
田丸謙二先生という方は、42年前から、いつもそうだった。
言うなれば、私にとっては、北極星。
Unreachable Star! (ラ・マンチャの男より)
いつも私の数十歩先を歩き、その先で、私のようなヒヨコがヨチヨチ歩いてついてくるの
を、笑って見ていた。
ともかくも先生、無事のご帰国、お喜び申し上げます。
いただいた原稿は、さっそく、先生のHPにUPしておきます。
で、私が言えることは、ただ一言。
「私も88歳まで、がんばります!」と。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●YOUTUBE
(注※)「こんにちは、はじめまして。
今日の講演会でお話を聞かせていただきました。
質問したかったのですが手をあげれなかったのでコメントしました。
お話の中の「責任論」につながるんでしょうか、
躾というか、家でのルールがあるのですが、場所が変わると通せなくなり、うやむやにな
ったりします。
例えば、食事中に立ち上がったら食事は終わり、が、家では出来るのですが、実家などで
は難しくなります。
周りに厳しい、可愛そうみたいにされてしまうと、私が間違いみたいな状態になってしま
うのではないかと思ったりもします。
場所が変わっていることを子供が分かっているので、ルールがリセットされる事はないの
ですが複雑です。
教えていただけたら嬉しいです。」(以上、ココログへのコメントより)
●11月8日
現在、時刻は、午後10時45分。
もうすぐ今日も、終わる。
私とワイフは、テーブルに相向かって座り、それぞれ勝手なことをしている。
私はパソコンを叩き、ワイフは、雑誌を読んでいる。
ときどき話しかけてくる。
適当に、私はそれに答える。
PRESIDENT誌(11・14日号)に、おもしろいことが書いてある。
●幸せなお金持ちの共通点(PRESIDENT誌より)
(1)人と自分を比べない。
(2)がんばらない。
(3)競争しない。
(4)ギラギラしない。
(5)ジタバタしない。
(6)苦労しない。
(7)自己投資している。
(8)大きく発想する。
(9)大きい挫折の経験がある。
(10)好きなことで成功している。
(11)人のためを考えている。
(12)さわやかな図々しさがある。
(13)夫婦仲がよい。(以上P43)
つまり金持ちかどうかは、収入の額によって決まるのではなく、生き様の問題というこ
とらしい。
本文の中に、こうある。
『夫婦仲がよくないと、お金は残りません。
夫婦間にストレスがあって、それを手っ取り早く解消する方法は、お金を使うことだから
です。
反対に、夫婦仲がいい家庭は、お金を使わない傾向がありますね。
家でパスタでもつくって、映画でも観ていれば、それだけでハッピーなんです』(同誌)
と。
(1)〜(13)項目の中で、「さわやかな図々しさがある」というのは、どういう意
味か。
それをワイフに聞くと、こう教えてくれた。
「図々しいけど、イヤミのない人ね」と。
ウ〜ン、ナルホド?
わかったような、それでいてわからない説明だが、へんに納得。
●福島県の人
先ほど、フロントの女性に聞いた。
何でもこのロッジには、福島県からの避難してきた人たちが住んでいるという。
フロントの女性は、「女の子たち」と言った。
その言葉通りとするなら、集団で、女の子たちだけが、避難しているということになる。
ここへ着いたとき見かけた女子中学生風の子どもたちは、彼女たちだったかもしれない。
浜松市にも、福島県からの避難者が来ているという。
私は直接的には知らないが、子ども(生徒)たちから、そういう話を聞いている。
「福島から転校生が来たよ」と。
●カナダ風ロッジ
このロッジは、カナダ風という(宿の案内書)。
カナダ規格で建てられたロッジにちがいない。
廊下も幅が広く、ドアの高さも高い。
キッチンも高い。
全体に大ざっぱだが、がっしりとしている。
どこか外国のモーテルに泊まっているよう。
だんだんと、そういう気分になってきた。
つまり気に入ってきた。
●自己投資
幸せなお金持ちの共通点(PRESIDENT誌より)の(7)に「自己投資」という
言葉が出てくる。
自己投資……たいへん重要なこと。
とくに60歳を過ぎたら、重要。
努めて、自己投資する。
というのも、60歳を過ぎると、どうしてもケチになる。
金銭的にケチになるというよりは、自分の保守的な部分が削られるのを、恐れる。
守銭奴ならぬ、守「我」奴になる。
自己投資ということは、つまりは新しい「我」を、どんどんと注入すること。
そうでなくても、知恵や知識は、容赦なく、こぼれ出て行く。
努めて補充していかないと、要するに、バカになる。
保守的になる。
その「努めて」という部分が、「自己投資」ということになる。
具体的には、「しっかりと金を使え」ということか。
●自己投資
私「なあ、自己投資しろとあるよ」
ワ「どうせまた、パソコンが欲しいと言うのでしょ」
私「ビンゴー(当たり)」
ワ「自分の都合のいいように解釈しないほうがいいわよ」
私「そうかなあ……」と。
パソコンという機器は、いくら高性能でも、数年たてばただのパソコン。
たとえば数年前、私は当時では最先端を行くデスクトップ・パソコンを買った。
が、今では、ノートパソコンでも、同等の性能をもっている。
言い換えると、パソコンという機器は、使い倒してこそ、価値がある。
飾ってしまっておくようなものではない。
●富士山
先ほど露天風呂の鍵をFRONTへ返しに行ってきた。
そのときFRONTの男性に、「富士山はどちらですか?」と聞くと、指をさしながら、
「そこ!」と言った。
「目の前です」と。
ついでに天気も調べてくれた。
「明日は快晴ですね」と。
これまたラッキー。
最近、旅行に恵まれている。
どこへ行っても、「ラッキー」がつづく。
●ロッジ
昼間見たら、さびれたロッジだった。
が、夜のロッジには、独特の風情がある。
都会のホテルのよな冷たさが、ない。
反対に人間的な温もりすら覚える。
私「あのなあ、老人ホームってさあ、こうでなくちゃあ」
ワ「そうねえ。オーストラリアで見たオールドマン・ビレッジ(老人村)によく似ているわね」
私「ぼくも、そう思っていた。二階部分を取り払ったら、まさにオールドマン・ビレッジ
だ」と。
またまたケチをつけて、恐縮だが、日本の老人ホームは、お金のかけ過ぎ。
どこも一流ホテル以上。
お金をかければ、それでよいというものではない。
それがわからなければ、日本の役人も、一度、オーストラリアのオールドマン・ビレッジ
を見学してくることだ。
一戸一戸、それぞれが別棟になっていて、庭もある。
その横には、幼稚園が併設されている。
●就寝
FRONTでもらった日本酒。
それをワイフが飲み始めた。
私が泊まった、「貸し切り風呂付きコース」には、こうしたサービスがついている。
「これ発泡酒よ」と言って、今、テーブルに置いてくれた。
「フ〜ン」と言って、私はそれを横目で見る。
今日も、これでおしまい。
忙しかったが、それだけ。
成果、なし。
明日は、午前9時25分にここを離れ、三島駅で10時過ぎの新幹線に乗る。
昼までには、家に帰れるだろう。
途中、義兄に、みやげを届けるつもり。
……では、このつづきは、また明日!
Have a good Nite!
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●11月9日
朝、7時にモーニングコール。
部屋というより、ロッジ中に響き渡るような大音響だった。
ジリジリジリ……、と。
目覚ましにはなったが、そのあとすぐ、また夢を見た。
ほんの数分のことではなかったか。
どこかの体育館のようなところにいた。
いろいろな人がいた。
何でもない夢だった。
起き上がって、「目覚ましが鳴ったあと、夢を見た」と告げると、ワイフは怪訝(けげ
ん)そうな顔をしてみせた。
●朝食
朝食は近くの朝食センターでとった。
窓の外には、サッカー場が見えた。
どこかの女子チームが、三角のポールを並べているところだった。
私は和食。
ワイフは洋食。
「9時25分のバスで帰ろうか?」と聞くと、「あわてなくてもいいんじゃない?」と。
朝食のあとのコーヒータイム。
ゆるやかに時間が流れる。
頭の中はまだぼんやりとしている。
まだ夢の中。
●散歩
朝食のあと、あちこちを散歩した。
お薦めは、『茶目湯殿』。
風情のある建物で、もし時之栖(ときのすみか)に泊まるようなことがあれば、ぜひ行っ
てみたらよい。
ほかにもいろいろな催し物が用意されている。
スケート場もある。
私自身は寒いのが苦手。
だから冬場に来ることはない。
来るとしても、春。
今度は来年の春にでも、もう一度、来てみたい。
●批評
時之栖(ときのすみか)について、ほめてばかりいては、いけない。
全体としてみると、随所に(やる気なさ)が感じられる。
看板は立て放題。
美的感覚も乏しい。
路上の三角ポールに張りつけた紙も、風に舞ってパラパラしている。
建物の形、色づかいにも統一性がない。
あと数歩崩れると、全体として町中の小さな公園風、もしくはさびれた遊園地風になる。
要するに、手当たり次第というか、その場、その場で、とってつけたような建物が無造作
に並んでいる。
この不況下。
何かとたいへんだろうとは思うが、唯一の救いは、料金が安いこと。
ときにこれからの冬場は楽しそう。
●鼻水
帰りのバス。
軽い鼻水が出る。
風呂から出たあと、風邪をひいたらしい。
今のところ、症状は鼻水だけ。
●新幹線の中で
今ごろになって、眠気が襲ってきた。
横では、ワイフが「サンデー毎日」を読んでいる。
「雅子さまの高まるストレス」というタイトルの記事を読んでいる。
女性というのは、皇室でのできごとが気になるものらしい。
よく知っている。
昨日も、「雅子さんは〜〜だけれども、紀子さんは〜〜」と、詳しく説明してくれた。
まるで知人か友人でもあるかのように、性格分析までしてくれた。
私は「どうしてそんなことを知っているのだろう?」と思いながら、聞いた。
が、私自身は、ほとんど興味がない。
大切なことは、そっと静かにしておいてやること。
どんな家庭にも、問題がある。
問題のない家庭など、ない。
それにしても、眠い。
「家に帰ってから寝よう」と言うと、「うん」とワイフは言った。
●新富士
列車は新富士に着いた。
FRONTの男性は「明日は(=今日は)、快晴」と言った。
ところが起きてみると、どんよりとした雲が、低く垂れ下がっていた。
新幹線の中からも、そうだろう。
向かって太平洋側の席に座ったこともある。
私は見上げることもなく、パソコンを開いたまま、まどろみ始めた。
……こんな話をした。
「もし、敦賀原発(福井県)が事故を起こしたら、岐阜県は全滅する。
少し間をおいて、静岡県も全滅する。
そのときは、逃げるしかないね」と。
浜岡原発(静岡県御前崎町)については、すでに行動計画は立ててある。
間髪を入れず、即、避難。
風向きにもよるが、浜松市は一夜にして、高汚染地帯に入る。
政府の避難勧奨など、まったくアテにならない。
アテにならないことは、一連のフクシマで証明された。
が、どこへ避難するか?
……放射線を浴びても、症状が現れるのは2〜5年後(チェルノブイリ)。
だったら、寿命のほうが先にくる。
そんな意見もある。
しかし放射線のような得体の知れないもので、寿命を縮めることはない。
そこらのチンピラにからまれ、怪我をするようなもの。
死ぬときになって、「原因は、あの原子力発電所の事故によるでは?」と疑うことくらい、
無念なものはない。
はっきりと因果関係がわかっていれば、まだ救われる。
恨んで死ぬことができる。
が、それもあいまいなままだと、恨んで死ぬこともできない。
つまり生殺し!
土俵際に立たされたような私だが、まだまだふんばってやる!
●静岡
新幹線は、静岡駅を離れた。
窓の下には、大井川が見える。
今回の講演旅行も、終わりに近づいてきた。
ところでボケには、転地療法がよいという。
もちろん予防にもなる。
称して「転地予防」。
部屋の様子が変わるだけでも、脳みそへの刺激になる。
ワイフもそう言った。
これからも機会を見つけ、もちろん懐(ふところ)とも相談しながら、転地予防をつづ
けたい。
肉体の老化もこわいが、脳みその老化は、もっと、こわい。
私が私でなくなってしまう。
そう言えば、先ほどバスの中で、うしろに座った老夫婦が、こんな話をしていた。
何でもその老夫婦の知人が、認知症になってしまったという。
そこで家族がその老人を、施設に入れた。
が、入れたとたん、その老人が盲目になってしまったという。
恐らく緑内障か何かになったのだろう。
一時的でも、強力なストレスが加わると、それまでボヤボヤとしていた持病が一気に悪化
する。
そういうことは多い。
いくら認知症になっても、まだ「心」は残っていた。
私はその老夫婦の話を、そのように理解した。
窓の外には、寒々とした冬の景色が広がっている。
こういうときは、気分まで暗くなる。
ア〜ア、暖かい布団に入って、昼寝をしたい!
列車は、掛川駅に止まった。
つぎは、浜松駅。
(伊豆、御殿場、講演旅行記、おしまい!)
はやし浩司 2011−11−09
Hiroshi Hayashi+++++++NOV. 2010++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●11月10日朝記(はやし浩司 2011ー11−10)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
昨夜、友人宅から帰ったのが、午後11時。
4時間近くも、話し込んでしまった。
そのときのこと。
何かを説明するために自分のパソコンを開いた。
ついでに……ということで、EUの経済動向を見て、驚いた。
イタリアの10年国債の利回りが、7・14%になっていた(午後19:00)。
朝方は、たしか、6%前後だったはず。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●イタリアの金融危機
家に帰ったのが、午後11時ごろ。
それから軽い夜食。
お茶漬けを食べた。
そのあとイタリアの金融危機が気になった。
今では、リアルタイムで、その国の国債の利回りを知ることができる(Bloomber
g)。
で、「寝る前に……」とパソコンを開く。
23:30……7・213%
24:00……7・282%
00:10……7・299%
00:26……7・251%
7%を超えたとき、アイルランドもギリシアも、金融危機に陥った。
Bloombergは、つぎのように伝える。
『……ロンドン時間午後5時3分現在、イタリア5年債利回りは前日比70ベーシスポイ
ント(bp、1bp=0.01%)上昇し7.57%。
同国債(表面利率4.75%、2016年9月償還)価格は2.54下げ89.265』と。
この報道によれば、日本時間で、今朝(11月10日)午前4時3分ごろ、7・57%
まで達したことになる。
で、現在(日本時間:午前7時15分)は、やや落ち着いて、
07:15……7・206%
今度はイタリア!、ということか。
しかし不思議なのは、……というか、私には理解できないのは、「では、ギリシアはどうな
ったのか?」という疑問。
ギリシアの金融危機問題にしても、何も解決していない。
が、EU関連のニュースのどこを見ても、ギリシアの名前が出てこない。
イタリアの陰に隠れてしまった。
言い換えると、イタリアの金融危機問題は、それほどまでに大きいということ。
●フランスの金融危機
イタリアの最大債権国は、フランス。
ドイツは2番目。
そのフランスの国債(10年もの)の利回りも、ジワジワと上昇している。
00:00……3・147
00:10……3・184
00:26……3・168
07:15……3・179
不気味なことに、フランスが今度は、イタリアのあとを追いかけ始めた。
中村清次日銀審議委員は9日、「イタリアに債権を沢山抱えるフランスについてもいろいろ
なうわさが出ている」と問題の深化・複雑化に懸念を示したという(ロイター)。
同時に、ニューヨーク・ダウ・工業株30種も、大暴落。
389ドルの下げを記録している(11月09日、終値)。
TBS−iは、つぎのように伝える。
『……9日からは、EUヨーロッパ連合がイタリアの財政監視を開始しましたが、ギリシ
ャの5倍という巨額の国債発行残高のあるイタリアが、財政再建に失敗すれば、世界的な
影響は計り知れません(10日03:50)』と。
何やら恐ろしいことが起こり始めている……というところまでは私にもわかる。
わかるが、そこで思考停止。
世界経済は、一度、行き着くところまで、行き着く。
●証券会社の格下げ
同じくTBS−iニュースは、こんな記事を配信している。
『……金融市場の混乱が証券業界を直撃しています。
アメリカの格付け会社・ムーディーズは、国内証券2位の大和証券グループの格付けを1
段階引き下げるとともに、国内最大手の野村ホールディングスの格付けも引き下げる方向
で見直すと発表しました』と。
が、私には、この「ムーディーズ」(信用格付け)というのが、よくわからない。
経営の健全性を示す指標になっているということらしい。
たとえば日本経済新聞は、『……ムーディーズ・インベスターズ・サービスは9日、野村ホ
ールディングス(HD)の格付けを現在の「Baa2」から引き下げ方向で見直すと発表
した』と報道している。
「Baa2」とは何か。
そこでおさらい。
●格付け(ムーディズのばあい)
+++++++++++++++++
信用リスクが低い Aaa
Aa
A
中程度の水準 Baa
Ba
B
Caa
Ca
信用リスクが高い C
債務不履行に陥っているD
++++++++++++++++
大和証券、野村證券(ホールディングズ)は、上述「Baa」のレベルにあるというこ
とらしい。
しかし信用を第一とする銀行や証券会社にとって、この格付けはそのまま営業に直結する。
事実、この発表を受け、野村證券は、即、反応した。
「我が社の経営は、堅固である」と。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●田丸謙二先生(11月10日)
昨夜(11月09日)、田丸謙二先生から、メールが届いていた。
ドイツでの講演が無事終わったらしい。
「前回のメールでは、命が心配です」とあった。
よかった。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 11年12月 2日号定期
================================
2011年月8日1日現在……1552号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page016.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
********安全は確認しています。どうか安心して、お読みください*****
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【伊豆から、御殿場へ】(はやし浩司 2011−11−08)
●伊東市で講演+時之栖(ときのすみか)に一泊
●新幹線の中
静岡までひかりで行き、静岡駅で、こだまに乗り換える。
乗り換え、熱海まで。
熱海から、伊東まで。
予定では、8時20分前後に、伊東へ着くはず。
●世界経済
JR浜松駅では、週刊誌(「週刊現代」)と、タブロイド紙の「日刊ゲンダイ」を買う。
いつもならパソコン雑誌を買う。
気分を和らげるなら、パソコン雑誌がいちばんよい。
私(的)には……。
が、今は緊迫の度をます、世界経済。
それが気になる。
●株
昨日、X証券とは、完全に縁を切った。
口座に残った金額は、ゼロ。
いつもの社員に電話をかけたが、「接客中です」の繰り返し。
何も怒っているわけではないが、私を避けている雰囲気が、アリアリ。
(そう言えば、どうもこのところX証券の動きが、おかしい?)
すでに3月のはじめの段階で、日本経済の先行きに暗雲が漂い始めていた。
そのとき私は手持ちの株をすべて売り払った。
その直後に、あの3・11大震災。
ギリギリのセーフだった。
(売り損ねた人も多いと思うが、ゴメン!)
●投資信託
金融商品には、大きく分けて、3種類ある。
株投資を中心にしたもの。
債権投資を中心にしたもの。
それに外貨(FX)取り引きを中心にしたものもある。
それらの混合型も、もちろん、ある。
今回、大きく被害を受けた人は、株投資型の金融商品に手を出した人。
が、そこへきて、今度は、債券投資もあぶなくなってきた。
個人だけではない。
たとえば先ほど買った「日刊ゲンダイ」紙によれば、三菱UFJファイナンシャルだけで
も、イタリア国債を、2600億円分も保有しているという。
第一生命保険は、イタリアとスペイン国債を、3000億円分も保有しているという。
日本全体で、1兆円(同紙)というが、実態は不明。
●イタリアの金融危機
そのイタリア。
今朝、出かける前に確かめると、国債の金利が、6・6%を超えていた(11・8朝)。
昨日までは、6・5%だった。
7%を超えると、実質的にデフォルト状態という。
ペイオフ制度で、銀行のばい、預金は1000万円まで保証される。
しかし外貨預金は、その対象外。
(対象外ということは、1円も戻ってこないということ。)
証券会社は、繰り返し、「分別保管していますから、安全です」と言う。
しかしそんな言葉を信ずる客は、いない。
先に倒産したアメリカのE銀行のばあい、巨額の顧客資金が行方不明になっている。
仮に保証されても、顧客は、どこでどのようにして、自分の債権の取り立てをすればよい
のか。
とくに私のようにネットで取り引きしている者は、その証拠となる「書類」そのものがな
い。
セゾン投信代表取締役社長の中野晴啓氏自身ですら、「投信は今すぐ、手放せ」と論じて
いる(「週刊現代」11・19日号P39)。
●大恐慌のあと……
で、私はいつも、その先を考える。
大恐慌は避けられないもの。
からなず、やって来る。
すでにその真っただ中にある。
で、問題は、その先。
日本も大被害を受けるが、日本は、どう立ち直っていくか。
とくに教育の分野において、どう立ち直っていくか。
が、私はそれについては、あまり悲観していない。
●頭脳と組織
たとえばタイへ進出した企業がある。
中国でもよい。
現地でモノを作ることはできても、研究開発はできない。
結局、研究開発は、日本国内で……となる。
日本は、その「日本国内で……」という部分で生き残る。
加えて日本人がもつ勤勉性。
日本に住んでいるとそれがわからないかもしれない。
しかしあのオーストラリアにしても、なぜ大企業が育たないかといえば、その勤勉性がな
いから。
もう少し正確には、「組織的勤勉性」。
それがない。
その一言に尽きる。
独立精神が旺盛なのはよいが、それがかえって災いし、「組織」が育たない。
組織が育たないから、組織的な研究や開発ができない。
この2つ、つまり「頭脳」と「組織」が、大恐慌のあと、この日本を再生させる。
●教育
が、後発組の国とて、手をこまねいているわけではない。
アジア各国は、日本に追いつけ、追い越せを合言葉にしている。
すでに国民1人当たりの所得では、日本はシンガポールに抜かれている。
経済大国、世界第二位の地位は、中国に明け渡した。
そこで日本は日本として、独自の教育を組み立てる必要がある。
「世界と同じことをしていて、世界に勝てるわけがない」。
●数学
わかりやすい例で考えてみよう。
たとえば小学1年生では、(数)→(足し算)→(引き算)→(繰り上がりのある足し算)
→(繰り下がりのある引き算)→……と、学習を進めていく。
しかしこんなカリキュラムでは、子どもを算数嫌いにするだけ。
おもしろくない。
つまらない。
そこで発想を変える。
1〜10までの数の範囲でも、方程式を教えることができる。
分数だって、少数だって教えることができる。
鶴亀算はもちろん、正負の数、棒グラフ、折れ線グラフだって、教えることができる。
そういう発想に切り替える。
どうできるかは、またそれにはどうしたらよいかは、私の「BW公開教室」を見てほしい。
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
繰り返す。
今のような「形」にこだわった教育では、これからの日本を支えることはできない。
つまりそういう子どもを育てることは、できない。
●三島
時間が飛ぶ。
2時間ほど前に、伊東市での講演を終えた。
そのあと電車を乗り継いで、ここ三島へやってきた。
たった今、昼食を終えたところ。
このあとシャトルバスに乗って、「時之栖(ときのすみか)」というホテルに向かう。
三島駅から40分ほどの距離という。
今、そのバスをまっている。
伊東市では、佐々木教育長※と、1時間ほど話をする機会があった。
いろいろな話をした。
久々に有意義な時間を過ごした。
同じ団塊の世代。
意見がことごとく一致した。
同志を得たような、喜びを感じた。
うれしかった。
●たくましさ
現代の子どもたちに欠けるものと言えば、「たくましさ」。
その一言に尽きる。
小学1年生でも、いじめられ、泣くのは男児。
いじめ、泣かせるのは女児。
が、本当のたくましさは、生活力で決まる。
数日前、あのタイの大洪水のニュース記事を読んだ。
その中に、こんな記述があった。
何でも洪水をせき止める土のうの上で、屋台を開いている人がいるという。
職を失った若い女性が、舟を借り、ソーセージを焼いて売っているという。
私が言う「たくましさ」というのは、それをいう。
私が20代のころは、この日本にも、そうしたたくましさが残っていた。
私自身も、そういう生き方をしてきた。
が、今、そのさくましさが消えた。
その結果が、今!
この先、この日本人は、海千山千の、それこそ海賊や山賊のような外国人を相手に、ど
うやって戦っていくというのか。
佐々木教育長も、それを心配していた。
(※佐々木教育長……伊東市教育長 佐々木誠氏)
●損得論
昨夜、損得論について書いた。
何をもって「得」といい、何をもって「損」というか。
その判断は、人によってみなちがう。
つまり人、それぞれ。
しかし大切なことは、2つある。
それがどんなものであれ、損得論ほど、個人的な幻想に包まれたものはないということ。
私がもっている損得論が正しいというわけではない。
同じように、あなたがもっている損得論が正しいというわけではない。
人々は、それぞれの損得論をもち、その範囲で、「得をした」「損をした」と右往左往する。
数年前に亡くなった、アメリカ人の友人は、いつもこう言っていた。
「ヒロシ、友だちの数こそが、財産だよ」と。
そういう損得論もある。
●金権教
金権教については、たびたび書いてきた。
自分自身への戒めの意味もある。
私たち日本人は、戦後、それまでの神国日本教を捨て、金権教に走った。
「国のため」が、「会社のため」となり、さらに「金(マネー)のため」となった。
金銭的な得を、「得」といい、損を、「損」と、言うようになった。
またそういった基準で、仕事を考え、生き様を考えた。
が、そこはまさにゲームの世界。
お金がなければ、人はたしかに不幸になる。
しかしお金では、幸福は買えない。
●バスの中で
「私たち、今までこうして無事で来られてよかった」と。
その意味が、今になって、つくづくとよくわかる。
もしそれを「得」と考えるなら、私たちは本当に得をしたことになる。
が、それを声に出して言うことはできない。
そこにだれか相手がいるなら、なおさら。
この世の中、そうでない人も多い。
病気や事故で苦しんでいる人も多い。
金銭的なトラブルや人間関係で苦しんでいる人も多い。
そうした人もいるから、「得をした」という思いは、しっかりと心の中に封印する。
それに、今はそうであっても、この先のことはわからない。
明日、その「無事」が、どこかへ飛んで消えるかもしれない。
だからよけいに口が重くなる。
●時之栖(ときのすみか)
選択をまちがえたかな……?
ホテルといっても、ロッジ。
ブルーベリーロッジ、スローハウスヴィラ。
部屋に入って外を見ていると、女子中学生らしい一群が、ロッジの中へ消えていった。
部屋は4部屋ある。
和室、ベッドルーム、洗面所+風呂+トイレ、それにこの居間+台所。
広さはそれぞれ8畳ほど。
ホテルや旅館とは、まったく趣を異にする。
どこかのマンションを借りて入ったよう。
あるいはどこかの有料老人ホームに入ったよう。
よく言えば、外国の大学の家族寮のようでもある。
あまり楽しくない。
生活臭が強すぎて、旅館に泊まったというな実感がない。
ついでに言えば、旅行で来たというような実感もない。
好き好きもあるだろうし、何とも言えないが、星は2つ?
(あとで、星は4つに上昇。その理由は、あとで……。)
造りはカナダ風(ロッジの説明書)とある。
「そうだろうな……」と思いつつ、あちこちを部屋の中を探索する。
●林檎の湯(りんごのゆ)
風呂は、「林檎の湯」だそうだ。
歩いて数分のところらしいが、今夜はこのまま冷えそう。
風呂へ行くためには、一度、部屋を出て、外気の中を歩かねばならない。
だいじょうぶかな?
また低い雲に隠れて見えないが、目の前には富士山がそびえ立っているはず。
この御殿場は、同じ静岡県の中でも、毎年、初雪が、もっとも早く降る。
入浴は4時から〜とある。
時刻は現在、3時42分。
ほかにも2つの温泉施設がある。
一眠りしてから行こうか、それとも夕食後に行こうか……。
目下、思案中。
●入浴
林檎の湯は、よかった。
客は私、1人だけ。
途中からもう1人、客が入ってきたが、フレンドリーな人だった。
「結構、寒いですね」と声をかけると、ハハハと笑ったあと、「そうですね」と。
そのあと、いろいろ、話がはずんだ。
浴室で体を洗ったあと、露天風呂に飛び込んだ。
湯加減もよく、気持ちよかった。
●部屋
今日は「朝食のみ、貸し切り風呂」の料金ということで、1人1泊7500円(ジャラ
ン)。
何かの目的があれば別だが、わざわざこうしたロッジに泊まりに来る客はいない。
フロントで聞くと、スポーツ選手やその団体が、よく泊まりに来るという。
隣には、サッカー場もある。
私は、居間+台所が気に入った。
ごくふつうの家の台所といった感じ。
ここでなら、思う存分、文章が書ける。
●本
何冊か、本をもってきた。
ほかに週刊誌や新聞など。
これだけ情報が氾濫しているにもかかわらず、どうも落ち着かない。
「もっと知りたい」というより、知れば知るほど、底が抜けていくように感ずる。
底が抜けていくから、結論が出せない。
ネットであちこちのニュースサイトを読みあさる。
とくに経済ニュース。
特筆すべきは、オリンパス工業の株価、大暴落。
つづいて野村證券の株価、暴落。
野村證券は、オリンパス工業の「主幹」証券会社になっているという。
(主幹という意味が、よくわからない。
風説によれば、野村證券の元社員が、オリンパス工業の株価大暴落の裏で、インサイダー
取り引きを指南していたという。
野村證券側は、即座に否定会見を行ったが、時、すでに遅し。
40%と言われる外国人を中心にした投資家が逃げた(Bloomberg)。
今日の終値は、240円前後。
43円安(15%安)。
一時は、2500円前後(2000年ごろ)もあった。
そのときと比べると、10分の1以下。
「すでに200円割れも視野に入っている」とか。)
しかし……。
オリンパス工業は、損失を先送りしながら、投資家をだましたということになる。
こうした手法を使ったのは、本当にオリンパス工業だけなのか。
ほかにもあるのではないのか。
それが証明されないかぎり、私たちはますます株式市場を信用しなくなる。
仮に天下の野村證券がそういうインチキに加担していたとするなら、これはとんでもない
話。
詐欺以上の、詐欺。
●ラッキー!
夕方、時之栖の中を散策してみた。
とたん、目に飛び込んできたのが、イルミネーションのアーチ!
それが数百メートルにわたって、つづいていた。
私とワイフは、まっすぐそのアーチの中に飛び込んだ。
うわさには聞いていたが、これほどまでのものとは想像もしていなかった。
ワイフは何度も「天国みたい」と言った。
私はなんども「夢の中みたい」と言った。
本格的な展示は、11月10日からという。
(今日は11月8日。)
最後の仕上げ作業ということで、試運転を始めていた。
途中、作業員の男性に、「今夜は何時までですか?」と聞くと、「6時までだよ」と。
時計を見ると、まだ5時少し前。
私とワイフは、天国と夢の中を歩いた。
●訂正
時之栖は、旅行で来るようなところではないと、先に書いた。
しかしそれはまちがいだった。
帰る途中、時之栖美術館とBOOKS&CAFEに寄った。
BOOKS&CAFEでは、軽い夕食をとった。
温泉も3か所、ある。
気楽坊、茶目湯殿、それに林檎の湯。
ホテルもあり、もちろんホテルの中にもあるという。
もちろん目の前には、富士山。
時之栖だけを目的に来ても、じゅうぶん楽しめる。
「先に星は2つ」と書いたが、星は4つにUPの、★★★★。
ホテルに泊まって、東海地方イチという、イルミネーションのアーチをくぐるのもよい。
小さいが、3-D劇場というのもある。
手づくり工房というのもある。
地元のみやげ物を売っている。
家族で来ても、じゅうぶん、楽しめる。
●リラックス
講演のできは、最悪だった。
あれも話そう、これも話そうと、話を広げすぎてしまった。
そのため途中で、あせってしまった。
その分、早口になったが、舌のほうが、それについてこなかった。
で、こういうときは、あまり気分がよくない。
ワイフは、「よかったわ」と慰めてくれたが、それを聞くのも、つらい。
講演のあと、今にいたるまで、その話題は、避けている。
●仮眠
6時ごろ、仮眠をとった。
2時間ほど、眠った。
深夜の貸し切り風呂になるまで、あと数時間。
フロントの女性は、「(午後)11時半からです」と言った。
ローソクの灯で、日本酒つきの貸し切り風呂へ入れるという。
●相談
今日、講演に来てくれた人から、早速、相談が届いていた※。
いわく、「家庭で、いくらしつけをしても、実家などへ帰ったとき、それが破られてしま
う。
あまりうるさく言うのもどうかと思い、黙っているが、そういうときは、どう考えたらよ
いか」と。
答……何ごとも完ぺき主義は、よくない。
とくに子育てでは、そうで、子どもはファジー(あいまいな部分)で息抜きをする。
またその部分で、伸びる。
言うべきことはいいながらも、あとは子どもに任す。
というのも、(しつけ)の中身が問題。
日本で(しつけ)というと、(細かい作法やマナー)が多い。
「ウソをつかない」とか、「約束を守る」というのは、世界共通、普遍的な(しつけ)と
いうことになる。
一方、「食事の間は席を離れない」(相談者)などというのは、つまりは作法。
それが破られたからといって、子どもの人格に影響を与えるということはない。
私など、食事中に、いつも席を離れている。
問題とすべきは、子どもの(しつけ)ではなく、その相談者の完ぺき主義。
程度の問題もあるが、度を越すと、育児ノイローゼになる。
詳しくは、YOUTUBEで。
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/jl9VnNzWGSg?hl=
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ja&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 11年12月 1日号臨時
================================
2011年月8日1日現在……1552号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page016.html
★メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
★2009年、2010年、連続、カテゴリー部門・人気NO.1に選ばれました。
********安全は確認しています。どうか安心して、お読みください*****
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●老人心理(前向きに生きるvs後ろ向きに生きる)
+++++++++++++++++
老人は、老人独特のものの考え方をする。
先の見えない死生観が、ものの考え方に
大きな影響を与える。
が、その考え方を大きく、2つに分けると、
つぎのようになる。
(1)開放型(前向き型)
(2)閉塞型(後ろ向き型)
+++++++++++++++++
●年金で家?
少し前、ある老人(男性)が死んだ。
2年近い、苦しい闘病生活のあとに、死んだ。
何かの難病だったと記憶している。
その様子を、あるテレビ局が取材した。
レポーターが話しかけると、老人の妻が、こう言った。
「2年もがんばってくれたおかげで、娘の家が建ちました」(某テレビ局)と。
つまり2年間生き延びてくれた。
その分の年金で、娘のために家を建てることができた、と。
この話は以前にも書いた。
私のBLOGに、その話を書いた(2009年9月)。
その記事をそのまま紹介する。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【損得論】
●損と得
++++++++++++++++++
60歳をすぎて、「損と得」についての考え方が、大きく変わってきた。
「損とは何か」「得とは何か」と。
それをしみじみと(?)、心の中で思いやりながら、
「老人になるというのは、こういうことなのか」と思う。
「老人」といっても、使い古された、老いぼれた人のことではない。
少し照れくさいが、「円熟した人」をいう。
++++++++++++++++++
●何が損か
この世の中で、「損かどうか」を考えること自体、バカげている。
どんなにあがいても、「死」というもので、私たちは、すべてを失う。
この宇宙もろとも、すべてを失う。
「死」を考えたら、それほどまでの「大きな損」はない。
たとえばあなたが地球上の、ありとあらゆる土地を自分のものにしたとする。
北極から南極まで。
一坪残らず、だ。
が、死んだとたん、すべてを失う。
つまり「死」にまさる(?)、損はない。
これには、自分の死も、相手の死もない。
そのため「死」をそこに感ずるようになると、日常的に
経験する損など、何でもない。
損とは感じなくなる。
●「金で命は買えん」
たとえば私の友人の中には、数か月で、数億円も稼いだ人がいた。
その友人は、数年前、死んだ。
莫大な財産を残したが、死んだとたん、「彼の人生は何だったのか?」
となってしまった。
私の母ですら、死ぬ直前、こう言っていた。
「金(=マネー)で命は、買えん」と。
あれほどまで、お金に執着していた母ですら、そう言った。
●得
一方、「得」と思うことも多くなった。
昨日も、秋の空を見たときも、そう思った。
澄んだ水色の空で、白い筋雲が、幾重にも重なって流れていた。
それを見て、「ああ、生きていてよかった」と思った。
ただ「損」とちがって、「得」という感覚は、実感しにくい。
大きな青い空を見たからといって、大きく得をしたとは思わない。
反対に、小さな花を見たからといって、大きな青い空を見たときに感ずるそれに、
劣るということはない。
もちろん私も、金権教にかなり毒されている面もあるから、お金は嫌いではない。
たいていのばあい、金銭的な価値に置き換えて、ものの損得を考える。
たとえば予定外の収入があったりすると、「得した」と思う。
しかし同時に、そこにある種の虚しさを覚えるようになったのも事実。
「だから、それがどうしたの?」と。
●長生き
では、長生きはどうか?
長生きをすればするほど、得なのか、と。
が、これについても、最近は、こう考える。
「それが無駄な生き方なら、長生きしても、意味はない」と。
「生きることが無駄」と言っているのではない。
「どうせ生きるなら、最後の最後まで、意味のある生き方をしたい」と
いう意味で、そう言う。
もちろん、できれば、長生きしたい。
たった一度しかない人生だから、それは当然のこと。
問題は、どうしたら、意味のある人生にすることができるか、ということ。
●今のままで、よいのか
未来は現在の延長線上にある。
とするなら、今の生き方が、未来の生き方になる。
となると、「今のままでいいのか」となる。
今、意味のある人生を送っていない私が、この先、意味のある人生を
送れるようになるということは、ありえない。
言い換えると、今の生き方そのものが、大切ということになる。
「今日」という「今」ではなく、「この瞬間」における「今」ということになる。
「私は、この瞬間において、意味のある生き方をしているのか」と。
●命の換算
この話は前にも書いたので恐縮だが、テレビでこんな人を紹介していた。
ある男性だが、何かの病気で、2年近い闘病生活のあと亡くなった。
その男性について、妻である女性が、こう言った。
「がんばって生きてくれたおかげで、娘の家が建ちました」と。
つまり夫であるその男性が、死の病床にありながらも、がんばって生きて
くれたので、その年金で、娘のための家を建てることができた、と。
私はその話を聞いたとき、「夫の命まで、金銭的な価値に置き換えて
考える人もいるのだなあ」と、驚いた。
まあ、本音を言えば、だれだってそう考えるときがある。
私もあるとき、ふと、こう思ったことがある。
「1年、長生きをして、1年、仕事がつづけられたら、○○○万円、
得をすることになる」と。
しかしこの考え方は、まちがっている。
もしこんな考え方が正しいというなら、私は自分の命すら、金銭的な
価値に置き換えてしまっていることになる。
仕事ができること自体が、喜びなのだ。
収入があるとすれば、それはあとからついてくるもの。
生きる目的として、収入があるわけではない。
●奇跡
さらに言えば、アインシュタインも言っているように、「この世に生まれた
ことだけでも、奇跡」ということになる。
(あなた)という人間が生まれるについても、そのとき1億個以上の精子が1個の
卵子にたどりつけず、死んでいる。
もしそのとき、隣の1個の精子が、あなたにかわって卵子にたどりついていたら、
あなたという人間は、この世には存在しない。
そのことは、二卵性双生児(一卵性双生児でもよいが)を見れば、わかる。
外の世界から見れば、(あなた)かもしれないが、それはけっして、(あなた)
ではない。
他人が見れば、(あなた)そっくりの(あなた)かもしれないが、けっして、
(あなた)ではない。
つまり私たちは、この世にいるということだけ、この大宇宙を手にしたのと
同じくらい、大きな得をしたことになる。
●統合性の確立
若いときは、生きること自体に、ある種の義務感を覚えた。
子育ての最中は、とくにそうだった。
働くことによって収入を得る。
その収入で、家族を支える。
しかし今は、それがない。
どこか気が抜けたビールのようになってしまった。
生きる目的というか、心の緊張感が、なくなってしまった。
「がんばって生きる」とは言っても、何のためにがんばればよいのか。
そこで登場するのが、「統合性」ということになる。
(自分がすべきこと)と、(現実のしていること)を一致させていく。
それを「統合性の確立」というが、この確立に失敗すると、老後も、みじめで
あわれなものになる。
くだらない世間話にうつつを抜かし、自分を見失ってしまう。
そんなオジチャン、オバチャンなら、いくらでもいる。
あるいは明日も今日と同じという人生を繰り返しながら、時間そのものを無駄に
してしまう。
が、その統合性の確立には、ひとつの条件がある。
無私、無欲でなければならない。
功利、打算が入ったとたん、統合性は霧散する。
こんな話を、ある小学校の校長から聞いた。
●植物観察会
ある男性(80歳くらい)は、長い間、高校で理科の教師をしていた。
その男性が、今は、毎月、植物観察会を開いている。
もちろん無料。
で、雨の日でも集合場所にやってきて、だれかが来るのを待っているという。
そしてだれも来ないとわかると、そのまま、また家に帰っていくという。
その男性にとっては、植物観察会が生きがいになっている。
参加者が多くても、またゼロでも構わない。
大切なことは、その(生きがい)を絶やさないこと。
が、もしその男性が、有料で植物観察会をしていたら、どうだろうか。
月謝を計算し、収入をあてにしていたら、どうだろうか。
生徒数がふえることばかり考えていたら、どうだろうか。
同じ植物観察会も、内容のちがったものになっているにちがいない。
つまり、無私、無欲でしているから、その男性の行動には意味がある。
「統合性の確立」というのは、それをいう。
●変化
損か、得か?
それを考えるとき、これだけは忘れてはいけない。
今、ここに生きていること自体、たいへんな得をしているということ。
それを基本に考えれば、日常生活で起こるさまざまな損など、損の中に入らない。
そして損ということになれば、「死」ほど、大きな損はない。
それを基本に考えれば、日常生活で起こるさまざまな損など、損の中に入らない。
つまり生まれたこと自体、大きな得。
死ぬこと自体、大きな損。
私たちは、その得と損の間の世界で、ささいな損得に惑わされながら生きている・
・・・というようなふうに、このところ考えることが多くなった。
私自身が「死」に近づいたせいなのか。
それとも「生」の意味が少しはわかるようになったせいなのか。
どうであるにせよ、「損と得」について、私の考え方が大きく変わってきた。
この先のことはわからないが、人は老人になると、みな、そう考えるようになるのか。
それとも、私だけのことなのか。
どうであるにせよ、今は、自分の中で起こりつつある変化を、静かに見守りたい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林
浩司 BW はやし浩司 老後 損得論 損か得か 自己の統合性 統合性の確
浩司 BW はやし浩司 老後 損得論 損か得か 自己の統合性 統合性の確
立 2年の闘病生活 おかげで 娘の家 建った)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●「1円も渡したくない」
冒頭にあげた老人の話は、原稿の内容からして、2009年の9月より、さらに以前の
話ということになる。
それはともかくも、その妻の言葉は、老人心理をうまく表現していて、たいへん興味深い。
というのも、このタイプの老人は、たいへん多い。
たとえば、ある老人は、1か月でも長生きをすれば得と考えている。
その分だけ、年金が余計に入るからという。
また別の老人は、反対にそれまでもっていた土地(実家の跡地)を、市に寄付してしま
った。
その土地は、現在、「記念公園」になっている。
理由を聞くと、「息子や娘には、1円も渡したくないから」と。
一見、正反対の老人のようにみえるが、中身は同じ。
ものの考え方が、後ろ向き。
つまり閉塞型。
が、こんな話は、どうだろう。
●失う
ある老人(75歳くらい)は、マラソンが趣味。
若いころは、いろいろな大会に出ては、賞を取っていた。
そのこともあって、今でも、毎朝、1〜2時間ほど、走っている。
で、こういう話を聞くと、みなこう思う。
「健康のために走っている」「すばらしい老人」と。
しかしその老人のばあいは、中身が、かなりちがう。
その老人は、失うことを恐れて走っている。
つまり「走れなくなること」を恐れて、走っている。
わかるかな?
その中身は、金持ちが金(マネー)を失うのを恐れる心理と、同じ。
……と書いても、一般の人には、なかなか理解できないかもしれない。
●優越感
その老人にとっては、「走れる」ということが、ステータスになっていた。
ちょうど金持ちが、貧しい人を見下すように、それでもって、いつも不健康な人を見下し
ていた。
そしてその分だけ、優越感に浸(ひた)っていた。
「あいつは、もう歩けなくなった」とか、「あいつはもう車いすに乗っている」とか。
その優越感を守るために、毎朝、走っていた。
●老人心理
もちろん、みながみな、そうであるというわけではない。
またそうした損得感や優越感を、「悪」と決めつけて考えるのも、正しくない。
年金を1か月でも長くもらうために長生きするのも、人生。
優越感を保つために、毎朝走るのも、これまた人生。
人は、それぞれの人生を、それぞれの思いをもって生きる。
が、先にも書いたように、老人の心理というのは、若い人たちが考えているより、はる
かに複雑。
年季が入っている分だけ、複雑。
一筋縄では理解できない。
……というようなことを、年々、より強く感ずるようになった。
●開放型
では、開放型の老人は、どうか?
それについては、ワイフが今夜、散歩の途中で、私に聞いた。
「どこで見分けるの?」と。
私「簡単だよ」
ワ「どこ?」
私「そのあとに、……だからそれがどうしたの?、という言葉をつなげてみるとわかる」
ワ「どういうこと?」
私「いいか、たとえば毎朝ランニングしている老人がいたとする。そういう老人に、『だか
ら、それがどうしたの?』という疑問を、そのままぶつけてみればいい。前向きに生きて
いる老人のばあい、答が直接、はね返ってくる。そうでなければそうでない」と。
話が、入り組んできたので、話題を少し変える。
●Nothing(虚無)!
イラクのフセイン大統領は死刑になった。
エジプトのムバラク大統領は、失脚した。
もっとも悲劇的だったのは、リビアのカダフィ大佐。
最後は下水管の中で発見され、射殺された。
『すべてをもつ者は、すべてを恐れる』という。
あるいは『すべてをもつものは、失うことを恐れる』でもよい。
へたに余計なものをもっているから、失うことを恐れる。
何も独裁者だけの話ではない。
ある女性(70歳)の口癖は、いつも同じ。
「そんなことすれば、貯金が減る」と。
貯金に異常なこだわりをみせている。
つまり人生も、(もの)と考える。
(もの)と考え、失うことを恐れる。
(反対に、長生きすることを得と考える。)
そういう人は、万事において、生き方が後ろ向き。
表面的な様子にだまされてはいけない。
一方、数は少ないが、「命」を別の人たちに還元しながら生きている人もいる。
そういう人たちは、(失うこと)を恐れない。
自分の命すらも、他人に捧げてしまう。
そういう人を、ここでいう「開放型の人」という。
(ネーミングがあまりよくないかもしれないが、ほかによい言葉を思いつかなかったので、
「開放型」とした。)
それを知るために、私は「……だから、それがどうしたの?」という言葉を思いついた。
カダフィ大佐が、すべての権力を手に入れた……だから、それがどうしたの?、と。
そう問いかけてみると、カダフィ大佐のばあい、そのあとに、何も残らないのがわかる。
つまり、Nothing(虚無)!
●「……だからそれがどうしたの?」
わかりやすく言えば、生きる意味を、常に他人と結びつけていくのを、開放型という。
反対に自己満足のためだけに生きている人を、閉塞型という。
どちらがよいかといえば、開放型がよいに決まっている。
が、自分を開放型にするのは、並大抵の努力では、できない。
つまりそこらの、(私も含めての話だが)、凡人には無理。
ほとんどの人は、その一歩も二歩も手前で、その先に進むことをあきらめてしまう。
が、そうであってはいけない。
そこでひとつのヒント。
何かを言ったり、したりしたら、すかさず、「だからそれがどうしたの?」と自問してみれ
ばよい。
前向きに生きているときには、そのとたん、ズシリとした答が返ってくる。
が、そうでないときは、そうでない。
スーッとそのまま答がどこかへ消えてしまう。
たとえば……。
新しい車を買った……だからそれがどうしたの?
今夜はおいしいものを食べた……だからそれがどうしたの?
息子がよい大学へ入った……だからそれがどうしたの?、と。
……しかしこれについては、以前にも書いたことがある。
原稿をさがしてみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
書いた日付はわからないが、No.600となっているから、
10年ほど前(2000年ごろ)に書いた原稿ということになる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
最前線の子育て論byはやし浩司(600)
●「xxxx」を読んで……
どういうわけか、ポロッと、古い本が、出てきた。「アレッ」と思って表紙を見ると、2
0年ほど前に買った、単行本(新書版)だった。
タイトルは、「xxxx」。
そのときは、1ページごとに、頭をハンマーでたたかれるような衝撃を受けた。
著者は、ST。
今まで気づかなかったが、M大学の元学長だったそうだ。
奥付を読みながら、ふと、「今でも生きているのだろうか?」と思った。
ほぼ20年ぶりに、その本を読みなおす。「感動よ、再び……」と思って、読みなおす。
が、読めば読むほど、「そうかなあ?」と思ってみたり、「私なら、こう書くのに……」と
思ってみたりする。
奥付から計算すると、ST氏が、60歳くらいのときに、書いた本ということになる。
当時は、週刊誌にも連載記事を書くなど、よく知られた評論家だった。
そのST氏の書いたことに、「?」をもつようになったのは、それだけ私に、「私」ができ
たためか。
それとも、私に、「クセ」ができたためか。
本の内容より、そうした自分自身の変化のほうを知ることが楽しい。
その本は、いわば、私の心のカガミのようなもの。
20年ほど前の私の心を、その中に、映(うつ)し出してくれる。
このところ、ヒマさえあれば、その本ばかり、読んでいる。
(追記)ST氏のことを、ヤフーで検索してみたが、同姓同名が多くて、消息を知ること
ができなかった。
多分、もう亡くなってしまったのかもしれない。
++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司
●目的
目的のない人生は、地図の上で、右往左往するようなもの。
へたをすれば、同じ場所を、ぐるぐると回るだけ、ということになりかねない。
そこで、目的ということになる。
この目的が、その人を、前にひっぱっていく。進むべき、方向を決める。
が、ここで注意しなければ、ならないことがある。
つまり「だからそれがどうしたの?」という部分がないまま、我欲を追求する。
それは、ここでいう「目的」ではない。
たとえば、おいしい料理を食べる。
たとえば、すばらしい高級車に乗る。
たとえば、きれいな服を着る。
そのとき、ほんの一言でよいから、自分に問うてみる。
「だから、それがどうしたの?」と。
ほとんどの人は、その時点で、がく然とするはず。
それもそのはず、ほとんどの人は、ほとんどの時間を、目的など考えないで、過ごしてい
る。
「ただそうしたいから、そうしているだけ」「ただ、そうできるから、そうしているだけ」
と。
それが悪いというわけではない。
「生きる」ということは、そうした日常生活の積み重ねの上に、成りたっている。
が、それでは、満足できない。
そこで私たちは、その中から、自分の目的をさがし始める。もう少し、順を追って、説明
してみよう。
たとえばA氏は、車に、関心があった。
そしていつか、ドイツのBxx車を買いたいと願っていた。
そこでA氏は、いつもより懸命に働き、そしてお金をためた。
ためて、念願のBxx車を手に入れた。
つまりA氏は、Bxxを買うことを目的とした。
それで働いて、その車を手に入れた。A氏にすれば、A氏の目的を達成したことになる。
その車は、A氏のものになった。
が、この段階で、もしA氏が、自分に、「だからどうしたの?」と、問うてみたとしたら、
どうなるだろうか。
毎日、ワックスをかけて、ピカピカにみがくのが楽しい。
毎日、近くの行楽地を走ってみるのが、楽しい。
毎日、知人や友人を助手席に座らせて、ドライブするのが、楽しい。
それはわかる。しかし、それがどうしたの?
昨日、子ども(生徒、小3)たちと、こんな会話をした。
私「おとなになったら、何になりたい?」
A「野球の選手」
私「野球の選手になって、どうする?」
A「有名になって、お金を稼ぐ」
私「お金を稼いで、どうする?」
A[ほしいものを買う]
私「ほしいものを買って、どうする?」
A「(ほしいものが、手に入れば)、うれしい」と。
しかしそれで心の満足は得られるのだろうか。
……と考えたが、それは言わなかった。
私「がんばって、野球の選手になれよ。応援するよ」と。
つまり、こうした我欲の追求は、「目的」ではない。
たとえば織田信長。
今でも、織田信長を信奉する政治家や、実業家は多い。
それはわかる。信長自身は、毛利遠征の途上に逗留した本能寺(京都市)で、家臣の明智
光秀に襲われ、自害した。
そのため彼がめざした、天下統一が、何であったのかは、今では、知ることができない。
私の印象では、ただがむしゃらに、殺戮(さつりく)、平定を繰りかえしただけの人物で
はなかったかと思う。
信長が、商工業者に、楽市、楽座の朱印状を与え、経済を活性化させたとか、関所を廃止
して、流通を自由にしたとかいうのは、あくまでも、自分の野望を完成させるためにした、
その結果でしかない。
信長が、日本人全体の、安寧(あんねい)と、幸福を考えて、天下統一をめざしたかと
いうと、そういうことは、ありえない。
いくら歴史書を読んでも、そういう意図が、浮かびあがってこない。
つまり信長も、結局は、明智光秀に自害を迫られるまで、「だからそれがどうなの?」と
いう部分のないまま、生きたことになる。
そこで再び、目的論ということになる。
つまり私たちが「目的」としていることは、実は、目的ではなく、手段にすぎないとい
うこと。
そこに気づけば、これらの問題は、解決する。
「Bxxの車を買う」「野球の選手になる」「天下を自分のものにする」というのは、実
は、目的にたどりつくための手段にすぎない。
では、目的は何かということになる。
たとえばあのアンネ・フランクは、当時、ただの少女でありながら、こう、看破(かん
ぱ)している。
We all live with the objective of being happy; our lives are all different and yet
the same.
(私たちは、みな、幸福になるという目的をもって、生きるのよ。みんなの生活は、み
な、ちがうけど、目的は、同じよ、と。
つまり、「幸福になるのが、目的」と。
今朝は、ここまでしか書けないが、ギリシャの劇作家のソフォクレスは、こう書き残し
ている。
知恵のみが、幸福の最高の部分である。(Wisdom is the supreme part of happiness. )
と。
モノや金ではない。知恵である、と。
私は、このソフォクレスの言葉を、信じたい。
この原稿のしめくくりとして、そしてあえて(?)、自分をなぐさめるために。
++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司
●真・善・美
教育に目標があるとするなら、未来に向かって、真・善・美を後退させないこと。
その基盤と方向性を、子どもたちの世界に、残しておくこと。
今すぐは、無理である。無理であることは、自分の過去を知れば、わかる。
若い人たちは、真・善・美を、そこらにころがる小石か、さもなければ、空気のように思
っている。
その価値がわからないどころか、その価値すら、否定する。
しかしやがて、その、真・善・美に、気がつくときが、かならずやってくる。
そしてその価値にひれ伏し、それまでの自分の過去にわびるときがやってくる。
そのとき、その子ども(子どもというよりは、人)が、その基盤と方向性をもっていれ
ばよし。そうでなければ、その子どもは、まさに路頭に迷うことになる。
「私は何のために生きてきたのか?」と。
そしてやがて、その人は、真・善・美を、自ら、追求し始める。
そのときを予想しながら、子どもの中に、その基盤と方向性を残しておくこと。
それが教育の目標。
+++++++++++++++++++++++++++
【補記】
真・善・美の追求について、私は、それに気づくのが、あまりにも遅すぎた。
ものを書き始めたのが、40歳前後。
それまでは実用的な本ばかりを書いてきたが、「私」を書くようになったのは、そのあとで
ある。
現在、私は57歳だが、本当に、遅すぎた。
どうしてもっと早く、自分の愚かさに気づかなかったのか。
どうしてもっと早く、真・善・美の追求を始めなかったのか。
今となっては、ただただ悔やまれる。
本当に悔やまれる。
もっと早くスタートしていれば、頭の働きだって、まだよかったはず。
どこかボケかけたような状態で、そしてこれから先、ますますボケていくような状態で、
私に何が発見できるというのか。
これは決して、おおげさに言っているのではない。
本心から、そう思っている。
だからもし、この文章を読んでいる人の中で、若い人がいるなら、どうかどうか、真・
善・美の追求を、今から始めてほしい。
30代でも、20代でも、早すぎるということはない。
今となっては、出てくるのは、ため息ばかり。
どんな本に目を通しても、出てくるのは、ため息ばかり。
「こんなにも、私の知らないことがあったのか」とである。
と、同時に、「後悔」のもつ恐ろしさを、私は、今、いやと言うほど、思い知らされている。
★読者のみなさんへ、
つまらないことや、くだらないことで、時間をムダにしてはいけませんよ。
時間や健康、それに脳ミソの働きには、かぎりがあります。
余計なお節介かもしれませんが……。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●これからの老人像
もう答は出たようなもの。
老人はけっして老人臭くなってはいけない。
後ろ向きになってはいけない。
そういう意味で、老人心理を知るひとつのヒントとして、ここで老人論を考えてみた。
あくまでも私自身の努力目標のひとつとして。
明日こそは、その目標に、少しでも近づいてみよう……ということで、今夜はここまで。
ワイフが横へ来て、「寝よう」「寝よう」と言っている。
高貴な哲学者にでもなったような気分だったが、それが消えた。
私のワイフは、どうしてこうまで俗っぽいのか?
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【LibreOfficeとMSのWordの互換性について】
(1)Wordで作成した文書を、(W)とする。
LibreOfficeで作成した文書を、(L)とする。
(L)で、(O)の文書を開くことについては、問題ない。
が、そのあと、こんな問題が起きた。
(O)で編集し、保存をかける。
いつもの作業である。
そのとき、(元の書式で保存するか)(O)の書式で保存するかをたずねてくる。
そこで(元の書式)を選択し、保存をかける。
(2)つぎに一旦、LibreOfficeを終了し、今度は、Wordを立ち上げる。
先ほど編集した文書を開こうとすると、ほかの文書まですべて、LibreOffice
形式で保存されていることがわかった。
ゾーッ!
その状態で、先ほどの文書を開いてみると、たとえば文書の色(私は目を疲れさせないよ
う、背景の色を、薄いブルーかグリーンに設定している)が、その色が消えている。
つまり白地になってしまっている。
ページ番号が消えている。
ほかに、ネットから引用した文書の文字間がバラバラになってしまっている。
以上の不都合が、あれこれと起きているのがわかった。
つまりいくら互換性があるからといっても、完ぺきではない。
(W)にするか、(L)にするか。
やはりどちらか一方に、統一したほうがよい。
で、「今はやはり、ワードを使おう」ということで、ワードにしたいが、先ほども書いた
ように、ワードで開くと、文字間がばらばらになってしまったりする。
(今のところ、ワード上では、元に戻すことができないでいる。)
背景の色を変えることができない。
(何か、方法があるのかもしれないが、今のところ、どうしたらよいかわからない。
……たった今、いろいろ試してみたら、(書式)→(ページ)→(背景)で、背景色を変え
ることができることがわかった。
ただし文字部だけで、白い枠が外側にできてしまう。
こうなると、明暗度が際だってしまい、かえって目が疲れるのではないか。)
しばらく試行錯誤がつづきそう。
パソコンが1〜2台の人ならまだよい。
私のように、常時5〜6台使っている人や、1〜2年ごとにパソコンを買い換えている人
にとっては、そのつど2万円前後のソフトを購入しなければならないというのは、つらい。
やはり少しずつ、LibreOfficeに乗り換えていくのが賢明なのかもしれない。
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
|
