| はやし浩司メインHP | マガジン過去版INDEX |
| 2012年 1月号 |
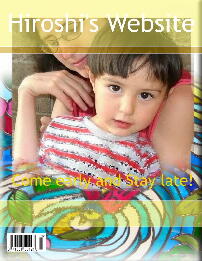 |
 |
| |
|
●2012年01月号
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm 発行人 はやし浩司(ひろし)
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 31日臨時号
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page015.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】2012年01月31日臨時号□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●寒い朝(12月27日)
++++++++++++++++++++
昨日、最後の歳暮の品を、発送した。
「最後」というのは、私はそれぞれの人に、
それぞれの歳暮の品を、送っている。
親類の人たちには、正月に口にしてもらえるのが、
いちばんよい。
そう考え、親類の人たちには、
いつもぎりぎりの年末に送っている。
今日は、12月27日。
火曜日。
昨日、日本列島は、今年いちばんの寒気に見舞われたとか。
この浜松市でもわずかだが、雪が降った。
寒いというより、冷たかった。
夕方、ワイフと市内のレストランへ行ったが、
肌が切れるような冷気を感じた。
そのころ気温は、2~3度ではなかったか。
++++++++++++++++++++
【リビドーvsサナトス】(創造vs破壊、生と死のはざまで……)
●心理学で考える、善と悪
●隕石
昨日、子ども(中学生)たちと、隕石の話になった。
1人が、「2012年に、巨大な隕石が落下し、人類が滅亡するかもしれない」と言った。
それに答えて、ほかの子どもたちが、「おもしろい」とか、「○○国に落ちればいい」とか言っ
た。
た。
「この日本に落ちるかもしれないよ」と私が言っても、本気にしない。
むしろ楽しみにしているような雰囲気さえある。
ことに深刻さが、まるでわかっていない。
が、こうした心理を、どう理解したらよいのか。
つまり危機的状況を、子どもたちは明らかに楽しんでいる。
こうした心理を、どう理解したらよいのか。
●死へのあこがれ(サナトス)
フロイトは、「生への欲求」を、「リビドー」と定義した。
その「リビドー」に対して、人間には、「死への欲求」もあると説いた。
「死への欲求」を、「サナトス」という。
ここでいう「サナトス」とは、自己に向かう破滅的な力を、総称していう。
必ずしも「死」もしくは、「自殺」を意味するのではない。
当然のことである。
この2つの相反した欲求が、人間の中で、同時に起こる。
「生」と「破滅」。
このことは、年をそれなりに取ると、実感として理解できるようになる。
生命力(=リビドー)そのものが弱くなり、その陰から破滅的なエネルギーが顔を出してくる。
つまり(リビドー)を、生産的な生命力とするなら、(サナトス)は、破滅的な破壊力ということにな
る。
る。
●創造vs破壊
誤解してはいけないのは、(サナトス)自体が、エネルギーであるということ。
虚無的になり、逃避し、その結果として「死にたい」というのとは、中身がちがう。
ちがうことは、子どもたちの世界をのぞいてみると、わかる。
たとえば子どもたちと、ドミノ倒しをしたとする。
ドミノを順に並べ、あとでそれを倒す。
(積み木遊びでも、何でもよい。)
すると子どもたちの心理が、(リビドー)と(サナトス)の間で、はげしく揺れ動いているのがわ
かる。
かる。
「長く並べたい」という思いは、創造性によるものと考えられる。
「早く倒してみたい」という思いは、破壊性によるものと考えられる。
この両者が、交互に顔を出し、子どもたちの行動を裏から操る。
●フロイト
フロイトの理論でたいへん興味深いのは、つぎの点である。
フロイトは、ひとつの心理状態があるとすると、他方に、それと相反する心理状態があると考え
る。
る。
こうした相反する心理状態を、フロイトは、「アンビバレンツ」と名づけた。
このことは、交感神経と副交感神経に結びつけて考えてみると、わかりやすい。
人間の脳の命令は、つねに(プラス)と(マイナス)が、同時に働く。
「動け」という命令に対して、「止まれ」という命令。
どちらか一方が強すぎると、行動はちぐはぐなものとなる。
つまりこの両者が、バランスよく働いたとき、人間の行動はスムーズなものとなる。
人間の心理にも、同じように考えることができる。
●プラス型vsマイナス型
幼児に接していると、常に(プラス型)と(マイナス型)があるのがわかる。
たとえば同じ赤ちゃん返りという現象にしても、下の子ども(弟、妹)に対して攻撃的になるケー
スがある。
スがある。
嫉妬がからんでいる分だけ、執拗かつ陰湿になりやすい。
反対に、ネチネチと甘ったるい言い方をし、赤ちゃんぽく演ずることによって、親の関心をひこ
うとするケースもある。
うとするケースもある。
5、6歳児になって、とつぜん、おもらしをしたりするなど。
(この両者の混在型もあるが……。)
フロイトも、たぶん、同じような現象をどこかで見たにちがいない。
「生きたい」という欲求があるなら、当然、「死にたい」という欲求もあるはず。
フロイトがそう考えたところで、何もおかしくない。
●バランス
要はバランスの問題ということになる。
そのバランスをうまくコントロールしながら、良好な人間関係を保つ。
そのコントロールする力が、「理性」ということになる。
またそれができる人のことを、人格の完成度の高い人という。
ピーター・サロベイのIQ論を引き合いに出すまでもない。
最初の話に戻る。
子ども(中学生)たちは、隕石の話をしながら、「そうであってはいけない」という思いと、「そう
あってほしい」という思いの中で、揺れ動く。
あってほしい」という思いの中で、揺れ動く。
が、子どもたちであっても、そこに理性の力が働く。
「そうであってほしい」という思いは、冗談として、脳の中で処理される。
もっとわかりやすい例としては、銀行強盗がある。
私もよく夢想する。
「どうすれば、うまく強盗ができるか」と。
そのときも、「やってみたい」という気持ちと、「やってはだめだ」という気持ちが、同時に働く。
しかし実際に、行動に移すことはない。
脳の中で、強いブレーキが働く。
それが「理性の力」ということになる。
●距離感
こう考えていくと、では「理性の力」とは、何かということになる。
もちろん程度の差がある。
力の強い人もいれば、そうでない人もいる。
そこでその程度を決めるのが、「距離感」ということになる。
先に銀行強盗の例をあげた。
わかりやすいから、銀行強盗にした。
その銀行強盗。
「一度、危険を犯せば、一生、楽な生活ができる」というのは、たしかに魅力的に聞こえる。
あとは遊んで暮らせる。
(もちろん失敗すれば、一生、刑務所の中で過ごすことになるが……。)
だれかが、「おい、林、一度してみないか?」と言ったとする。
そのとき、私は、それをどう思うだろうか。
……そこでこう考える。
銀行強盗をするにも、銀行強盗から遠い距離にいる人がいる。
頭の中で空想することはあっても、「実行」ということは、まったく考えない。
が、ひょっとしたら、何かのきっかけさえあれば、「実行」を考える人もいるかもしれない。
このタイプの人は、それだけ銀行強盗に近い距離にいるということになる。
つまりこの「距離感」をつくる力こそが、「理性の力」ということになる。
(私は映画が好きだから、よく映画のシナリオを自分で考える。
そのひとつとして、銀行強盗を頭の中で夢想する。
どうか誤解のないように!)
●サナトス
さらに踏み込んで考えてみよう。
フロイトの理論に従えば、リビドーの強い人は、当然、サナトスも強いということになる。
反対にリビドーの弱い人は、当然、サナトスも弱いということになる。
「生きよう」という力の強い人であれば、お金に困れば、銀行強盗を、より強く考えるかもしれな
い。
い。
反対に、もとから「生きよう」とする力の弱い人であれば、銀行強盗を考える力も弱いということ
になる。
になる。
つまり「銀行強盗を考えない」からといって、理性の力が強いということにはならない。
もとから生きる力の弱い人は、銀行強盗をしようという気力も弱い。
●善人論vs悪人論
このことはそのまま、善人論、悪人論に結びつく。
よいことをするから、善人というわけではない。
(善人の仮面をかぶり、悪いことをしている人はいくらでもいるぞ!)
悪いことをしないから、善人というわけでもない。
(小さな世界で、小さく生きている人は、いくらでもいるぞ!)
善人が善人であるためには、そこにある「悪」と積極に闘わねばならない。
その積極性のある人を、「善人」という。
つまり「生きる力(リビドー)」の強い人は、「死にたいという力(このばあいは、破滅的な力)」
も、同時に強いとことになる。
も、同時に強いとことになる。
言い換えると、その分だけ、「理性の力」も、強くなければならない。
もし生きる力だけが強く、理性の力が伴わなければ、その力は破滅的な方向に向かってしま
う。
う。
生きる力が強い人は、それだけ悪に手を染めやすいということにもなる。
●バランス感覚
そこで重要なのが、バランス感覚。
私たちは、(生きたいという力)と、(死にたいという力)、
(創造したいという願望)と、(破壊したいという願望)、
さらに言えば、(善)と(悪)。
その相反するエネルギーの中で、絶妙なバランスを保ちながら生きている。
このバランスが崩れたとき、悪人は悪人になる。
行動が破滅的になり、それがときとして自分に向かう。
さて、本論。
●老人論
私は先に、こう書いた。
「年をそれなりに取ると、実感として理解できるようになる」と。
その理由は、年を取ると、生きる力が弱くなる。
そのためそれまで姿を隠していた、サナトスが、姿を現すようになる。
現在の「私」についてではなく、過去の「私」について、である。
その点、子ども(中学生)たちは、正直に自分を表現する。
自分を隠さない。
しかし同時に、それは私自身の過去の姿でもある。
私も心のどこかで、こう思ったことがある。
「隕石か何か落ちてきて、地球なんか、木っ端微塵に壊れてしまえばいい」と。
実のところ、最近でもときどきそう思う。
そういう自分が、よく見えるようになる。
●善人vs悪人
……こうして考えていくと、結論はただひとつ。
善人も悪人も、違いは、紙一重。
ついでに言えば、成功者も失敗者も、違いは、紙一重。
見た目には大きな違いに見えても、紙一重、と。
被災地で被災者のために懸命に働く人を、私たちは善人と言う。
隕石の落下を望むような人を、私たちは悪人と言う。
が、そのちがいは何かと言えば、その間には、何もない。
ちょっとしたきっかけで、善人は悪人になる。
悪人は善人になる。
善人の裏には悪がある。
悪人の裏には善がある。
善だけの善人はいない。
悪だけの悪人はいない。
ではそのちがいは何かと言えば、「理性の力」ということになる。
そのきっかけを、どう作っていくかが、結局は「教育」ということになる。
先に書いた「距離感」を作っていくのが、「教育」ということになる。
今朝は、善と悪について、心理学の立場で考えてみた。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 リビドー サナトス 善人論 悪人
論 善と悪 距離感 はやし浩司 心理学 善と悪)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 リビドー サナトス 善人論 悪人
論 善と悪 距離感 はやし浩司 心理学 善と悪)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
以下、2006年にBLOGで発表した原稿です。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【善と悪】(2006-04-28記)
●昆虫のような脳みそ
+++++++++++++++++
「昆虫のような脳みそ」と書いたことに
ついて、コメントの書きこみがあった。
「お前は、いったい、何様のつもり?」と。
+++++++++++++++++
「昆虫のような脳みそ」という言葉を使ったことに対して、コメントの書きこみがあった。「お前
は、いったい、何様のつもり?」と。
は、いったい、何様のつもり?」と。
たしかに辛(しん)らつな言葉である。私も最初聞いたとき、そう思った。恩師のT教授が、い
つも口ぐせのように使っている言葉である。いつの間にか、私も、そのまま使うようになってしま
った。しかし、私にも、言い分がある。
つも口ぐせのように使っている言葉である。いつの間にか、私も、そのまま使うようになってしま
った。しかし、私にも、言い分がある。
いつだったか、私は、善と悪は、平等ではないと書いた。西欧社会では、『善は神の左手、悪
は神の右手』と説く。しかし平等ではない。
は神の右手』と説く。しかし平等ではない。
善人になるのは、意外と簡単なことである。約束を守る、ウソをつかない。この2つさえ守れ
ば、どんな人でも、やがて善人になれる。
ば、どんな人でも、やがて善人になれる。
しかし自分の中に潜む悪を、自分から追い出すことは、容易なことではない。とくに乳幼児期
までに心にしみついた悪を追い出すことは、容易なことではない。生涯にわたって、その人の
心の奥底に潜む。
までに心にしみついた悪を追い出すことは、容易なことではない。生涯にわたって、その人の
心の奥底に潜む。
それについては、以前に書いたので、ここでは、そのつぎを考えてみたい。
仮にここに10人の人がいたとする。が、そのうちの9人が善人でも、1人が悪人だったとす
る。数の上では善人のほうが、多いということになる。が、やがてその9人は、1人の悪人に、
翻弄(ほんろう)されるようになる。最悪のばあいには、9人の善人たちは、たった1人の悪人
の支配下に置かれるようになるかもしれない。
る。数の上では善人のほうが、多いということになる。が、やがてその9人は、1人の悪人に、
翻弄(ほんろう)されるようになる。最悪のばあいには、9人の善人たちは、たった1人の悪人
の支配下に置かれるようになるかもしれない。
悪のもつパワーには、ものすごいものがある。一方、善の力は、弱い。善人たちが集まって
考えた、社会のルールやマナーが、少人数の悪人によって、こなごなに破壊されるということ
も、珍しくない。
考えた、社会のルールやマナーが、少人数の悪人によって、こなごなに破壊されるということ
も、珍しくない。
この点でも、善と悪は、平等ではない。
恩師のT教授が、「昆虫のような脳みそ」という言葉を使う背景には、もつろん軽蔑の念もあ
る。しかしそれ以上に、いつも私は、そこに怒りの念がこめられているのを感ずる。「せっかく
知的な世界を作ろうとしているのに、昆虫のような脳みそをもった連中が、それを容赦なくこわ
してしまう」と。
る。しかしそれ以上に、いつも私は、そこに怒りの念がこめられているのを感ずる。「せっかく
知的な世界を作ろうとしているのに、昆虫のような脳みそをもった連中が、それを容赦なくこわ
してしまう」と。
T教授は、あの東大紛争(1970)を経験している。T教授の理学部研究室は、その東大紛争
の拠点となった安田講堂の向かってすぐ右側裏手にあった。そのため、T教授の研究室は、爆
弾でも落とされたかのように、破壊されてしまった。うらみは大きい。日ごろは穏やかな恩師だ
が、こと学生運動については、手きびしい。「昆虫のような脳みそ」という言葉は、そういうところ
から生まれた(?)。
の拠点となった安田講堂の向かってすぐ右側裏手にあった。そのため、T教授の研究室は、爆
弾でも落とされたかのように、破壊されてしまった。うらみは大きい。日ごろは穏やかな恩師だ
が、こと学生運動については、手きびしい。「昆虫のような脳みそ」という言葉は、そういうところ
から生まれた(?)。
「私は善人である」と、自分を悪人の世界から分けて考えることは、簡単なこと。悪いことをし
ないから、善人というわけでもない。よいことをするから、善人というわけでもない。悪と戦って
はじめて、人は、善人になれる。
ないから、善人というわけでもない。よいことをするから、善人というわけでもない。悪と戦って
はじめて、人は、善人になれる。
その(戦う)という部分に、この言葉がある。「昆虫のような脳みそ」と。「サルのような脳みそ」
という言葉もある。そういえば数年前にベストセラーになった本に、「ケータイをもったサル」とい
うタイトルのもあった。
という言葉もある。そういえば数年前にベストセラーになった本に、「ケータイをもったサル」とい
うタイトルのもあった。
あえて言うなら、「昆虫のような脳みそ」というのは、「バカの脳みそ」ということになる。しかし
誤解しないでほしい。「バカなことをする人を、バカ」(「フォレスト・ガンプ」)という。知的な能力
をさして言うのではない。恩師のT教授が、「昆虫のような脳みそ」と言うときは、「せっかくすば
らしい能力をもちながらも、その能力を、悪のために使ってしまう人」を意味する。
誤解しないでほしい。「バカなことをする人を、バカ」(「フォレスト・ガンプ」)という。知的な能力
をさして言うのではない。恩師のT教授が、「昆虫のような脳みそ」と言うときは、「せっかくすば
らしい能力をもちながらも、その能力を、悪のために使ってしまう人」を意味する。
だから何も遠慮することはない。この言葉は、堂々と使えばよい。昆虫のような脳みそをもっ
た人たちを見たら、そう言えばよい。何も善人が、遠慮して生きる必要はない。遠慮したとた
ん、私たちは、その悪人の餌食(えじき)になる。
た人たちを見たら、そう言えばよい。何も善人が、遠慮して生きる必要はない。遠慮したとた
ん、私たちは、その悪人の餌食(えじき)になる。
このエッセーが、そのコメントを書いてきた人への、反論ということになる。(コメントそのもの
は、即、削除してしまったが……。)
は、即、削除してしまったが……。)
で、私が何様のつもりかって? ハハハ、見たとおりの、ただのドンキホーテ。セルバンテス
の男。ハハハ。
の男。ハハハ。
++++++++++++++++++
4年前に書いた原稿を、ここに添付します。
++++++++++++++++++
●善と悪
●神の右手と左手
昔から、だれが言い出したのかは知らないが、善と悪は、神の右手と左手であるという。善が
あるから悪がある。悪があるから善がある。どちらか一方だけでは、存在しえないということら
しい。
あるから悪がある。悪があるから善がある。どちらか一方だけでは、存在しえないということら
しい。
そこで善と悪について調べてみると、これまた昔から、多くの人がそれについて書いているの
がわかる。よく知られているのが、ニーチェの、つぎの言葉である。
がわかる。よく知られているのが、ニーチェの、つぎの言葉である。
『善とは、意思を高揚するすべてのもの。悪とは、弱さから生ずるすべてのもの』(「反キリス
ト」)
ト」)
要するに、自分を高めようとするものすべてが、善であり、自分の弱さから生ずるものすべて
が、悪であるというわけである。
が、悪であるというわけである。
●悪と戦う
私などは、もともと精神的にボロボロの人間だから、いつ悪人になってもおかしくない。それを
必死でこらえ、自分自身を抑えこんでいる。
必死でこらえ、自分自身を抑えこんでいる。
トルストイが、「善をなすには、努力が必要。しかし悪を抑制するには、さらにいっそうの努力が
必要」(『読書の輪』)と書いた理由が、よくわかる。もっと言えば、善人のフリをするのは簡単だ
が、しかし悪人であることをやめようとするのは、至難のワザということになる。もともと善と悪
は、対等ではない。しかしこのことは、子どもの道徳を考える上で、たいへん重要な意味をも
つ。
必要」(『読書の輪』)と書いた理由が、よくわかる。もっと言えば、善人のフリをするのは簡単だ
が、しかし悪人であることをやめようとするのは、至難のワザということになる。もともと善と悪
は、対等ではない。しかしこのことは、子どもの道徳を考える上で、たいへん重要な意味をも
つ。
子どもに、「~~しなさい」と、よい行いを教えるのは簡単だ。「道路のゴミを拾いなさい」「クツ
を並べなさい」「あいさつをしなさい」と。しかしそれは本来の道徳ではない。人が見ていると
か、見ていないとかということには関係なく、その人個人が、いかにして自分の中の邪悪さと戦
うか。その「力」となる自己規範を、道徳という。
を並べなさい」「あいさつをしなさい」と。しかしそれは本来の道徳ではない。人が見ていると
か、見ていないとかということには関係なく、その人個人が、いかにして自分の中の邪悪さと戦
うか。その「力」となる自己規範を、道徳という。
たとえばどこか会館の通路に、1000円札が落ちていたとする。そのとき、まわりにはだれも
いない。拾って、自分のものにしてしまおうと思えば、それもできる。そういうとき、自分の中の
邪悪さと、どうやって戦うか。それが問題なのだ。またその戦う力こそが道徳なのだ。
いない。拾って、自分のものにしてしまおうと思えば、それもできる。そういうとき、自分の中の
邪悪さと、どうやって戦うか。それが問題なのだ。またその戦う力こそが道徳なのだ。
●近づかない、相手にしない、無視する
が、私には、その力がない。ないことはないが、弱い。だから私のばあい、つぎのように自分
の行動パターンを決めている。
の行動パターンを決めている。
たとえば日常的なささいなことについては、「考えるだけムダ」とか、「時間のムダ」と思い、でき
るだけ神経を使わないようにしている。社会には、無数のルールがある。そういったルールに
は、ほとんど神経を使わない。すなおにそれに従う。駐車場では、駐車場所に車をとめる。駐
車場所があいてないときは、あくまで待つ。交差点へきたら、信号を守る。黄色になったら、止
まり、青になったら、動き出す。何でもないことかもしれないが、そういうとき、いちいち、あれこ
れ神経を使わない。もともと考えなければならないような問題ではない。
るだけ神経を使わないようにしている。社会には、無数のルールがある。そういったルールに
は、ほとんど神経を使わない。すなおにそれに従う。駐車場では、駐車場所に車をとめる。駐
車場所があいてないときは、あくまで待つ。交差点へきたら、信号を守る。黄色になったら、止
まり、青になったら、動き出す。何でもないことかもしれないが、そういうとき、いちいち、あれこ
れ神経を使わない。もともと考えなければならないような問題ではない。
あるいは、身の回りに潜む、邪悪さについては、近づかない。相手にしない。無視する。とき
として、こちらが望まなくても、相手がからんでくるときがある。そういうときでも、結局は、近づ
かない。相手にしない。無視するという方法で、対処する。それは自分の時間を大切にすると
いう意味で、重要なことである。考えるエネルギーにしても、決して無限にあるわけではない。
かぎりがある。そこでどうせそのエネルギーを使うなら、もっと前向きなことで使いたい。だか
ら、近づかない。相手にしない。無視する。
として、こちらが望まなくても、相手がからんでくるときがある。そういうときでも、結局は、近づ
かない。相手にしない。無視するという方法で、対処する。それは自分の時間を大切にすると
いう意味で、重要なことである。考えるエネルギーにしても、決して無限にあるわけではない。
かぎりがある。そこでどうせそのエネルギーを使うなら、もっと前向きなことで使いたい。だか
ら、近づかない。相手にしない。無視する。
こうした方法をとるからといって、しかし、私が「(自分の)意思を高揚させた」(ニーチェ)こと
にはならない。これはいわば、「逃げ」の手法。つまり私は自分の弱さを知り、それから逃げて
いるだけにすぎない。本来の弱点が克服されたのでも、また自分が強くなったのでもない。そこ
で改めて考えてみる。はたして私には、邪悪と戦う「力」はあるのか。あるいはまたその「力」を
得るには、どうすればよいのか。子どもたちの世界に、その謎(なぞ)を解くカギがあるように思
う。
にはならない。これはいわば、「逃げ」の手法。つまり私は自分の弱さを知り、それから逃げて
いるだけにすぎない。本来の弱点が克服されたのでも、また自分が強くなったのでもない。そこ
で改めて考えてみる。はたして私には、邪悪と戦う「力」はあるのか。あるいはまたその「力」を
得るには、どうすればよいのか。子どもたちの世界に、その謎(なぞ)を解くカギがあるように思
う。
●子どもの世界
子どもによって、自己規範がしっかりしている子どもと、そうでない子どもがいる。ここに書い
たが、よいことをするからよい子ども(善人)というわけではない。たとえば子どものばあい、悪
への誘惑を、におわしてみると、それがわかる。印象に残っている女の子(小三)に、こんな子
どもがいた。
たが、よいことをするからよい子ども(善人)というわけではない。たとえば子どものばあい、悪
への誘惑を、におわしてみると、それがわかる。印象に残っている女の子(小三)に、こんな子
どもがいた。
ある日、バス停でバスを待っていると、その子どもがいた。私の教え子である。そこで私が、
「缶ジュースを買ってあげようか」と声をかけると、その子どもはこう言った。「いいです。私、こ
れから家に帰って夕食を食べますから」と。「ジュースを飲んだら、夕食が食べられない」とも言
った。
「缶ジュースを買ってあげようか」と声をかけると、その子どもはこう言った。「いいです。私、こ
れから家に帰って夕食を食べますから」と。「ジュースを飲んだら、夕食が食べられない」とも言
った。
この女の子のばあい、何が、その子どもの自己規範となったかである。生まれつきのものだ
ろうか。ノー! 教育だろうか。ノー! しつけだろうか。ノー! それとも頭がかたいからだろう
か。ノー! では、何か?
ろうか。ノー! 教育だろうか。ノー! しつけだろうか。ノー! それとも頭がかたいからだろう
か。ノー! では、何か?
●考える力
そこで登場するのが、「自ら考える力」である。その女の子は、私が「缶ジュースを買ってあげ
ようか」と声をかけたとき、自分であれこれ考えた。考えて、それらを総合的に判断して、「飲ん
ではだめ」という結論を出した。それは「意思の力」と考えるかもしれないが、こうしたケースで
は、意思の力だけでは、説明がつかない。「飲みたい」という意思ならわかるが、「飲みたくな
い」とか、「飲んだらだめ」という意思は、そのときはなかったはずである。あるとすれば、自分
の判断に従って行動しようとする意思ということになる。
ようか」と声をかけたとき、自分であれこれ考えた。考えて、それらを総合的に判断して、「飲ん
ではだめ」という結論を出した。それは「意思の力」と考えるかもしれないが、こうしたケースで
は、意思の力だけでは、説明がつかない。「飲みたい」という意思ならわかるが、「飲みたくな
い」とか、「飲んだらだめ」という意思は、そのときはなかったはずである。あるとすれば、自分
の判断に従って行動しようとする意思ということになる。
となると、邪悪と戦う「力」というのは、「自ら考える力」ということになる。この「自ら考える力」
こそが、人間を善なる方向に導く力ということになる。釈迦も『精進』という言葉を使って、それ
を説明した。言いかえると、自ら考える力のな人は、そもそも善人にはなりえない。よく誤解さ
れるが、よいことをするから善人というわけではない。悪いことをしないから善人というわけでも
ない。人は、自分の中に潜む邪悪と戦ってこそはじめて、善人になれる。
こそが、人間を善なる方向に導く力ということになる。釈迦も『精進』という言葉を使って、それ
を説明した。言いかえると、自ら考える力のな人は、そもそも善人にはなりえない。よく誤解さ
れるが、よいことをするから善人というわけではない。悪いことをしないから善人というわけでも
ない。人は、自分の中に潜む邪悪と戦ってこそはじめて、善人になれる。
が、ここで「考える力」といっても、二つに分かれることがわかる。
一つは、「考え」そのものを、だれかに注入してもらう方法。それが宗教であり、倫理ということ
になる。子どものばあい、しつけも、それに含まれる。
になる。子どものばあい、しつけも、それに含まれる。
もう一つは、自分で考えるという方法。前者は、いわば、手っ取り早く、考える人間になる方
法。一方、後者は、それなりにいつも苦痛がともなう方法、ということになる。どちらを選ぶか
は、その人自身の問題ということになるが、実は、ここに「生きる」という問題がからんでくる。そ
れについては、また別のところで書くとして、こうして考えていくと、人間が人間であるのは、そ
の「考える力」があるからということになる。
法。一方、後者は、それなりにいつも苦痛がともなう方法、ということになる。どちらを選ぶか
は、その人自身の問題ということになるが、実は、ここに「生きる」という問題がからんでくる。そ
れについては、また別のところで書くとして、こうして考えていくと、人間が人間であるのは、そ
の「考える力」があるからということになる。
とくに私のように、もともとボロボロの人間は、いつも考えるしかない。それで正しく行動できる
というわけではないが、もし考えなかったら、無軌道のまま暴走し、自分でも収拾できなくなって
しまうだろう。もっと言えば、私がたまたま悪人にならなかったのは、その考える力、あるいは
考えるという習慣があったからにほかならない。つまり「考える力」こそが、善と悪を分ける、
「神の力」ということになる。
というわけではないが、もし考えなかったら、無軌道のまま暴走し、自分でも収拾できなくなって
しまうだろう。もっと言えば、私がたまたま悪人にならなかったのは、その考える力、あるいは
考えるという習慣があったからにほかならない。つまり「考える力」こそが、善と悪を分ける、
「神の力」ということになる。
(02-10-25)※
++++++++++++++++++++
●補足
善人論は、むずかしい。古今東西の哲学者が繰り返し論じている。これはあくまでも個人的
な意見だが、私はこう考える。
な意見だが、私はこう考える。
今、ここに、平凡で、何ごともなく暮らしている人がいる。おだやかで、だれとも争わず、ただ
ひたすらまじめに生きている。人に迷惑をかけることもないが、それ以上のことも、何もしない。
小さな世界にとじこもって、自分のことだけしかしない。日本ではこういう人を善人というが、本
当にそういう人は、善人なのか。善人といえるのか。
ひたすらまじめに生きている。人に迷惑をかけることもないが、それ以上のことも、何もしない。
小さな世界にとじこもって、自分のことだけしかしない。日本ではこういう人を善人というが、本
当にそういう人は、善人なのか。善人といえるのか。
私は収賄罪で逮捕される政治家を見ると、ときどきこう考えるときがある。その政治家は悪い
人だと言うのは簡単なことだ。しかし、では自分が同じ立場に置かれたら、どうなのか、と。目
の前に大金を積まれたら、はたしてそれを断る勇気があるのか、と。刑法上の罪に問われると
か、問われないとかいうことではない。自分で自分をそこまで律する力があるのか、と。
人だと言うのは簡単なことだ。しかし、では自分が同じ立場に置かれたら、どうなのか、と。目
の前に大金を積まれたら、はたしてそれを断る勇気があるのか、と。刑法上の罪に問われると
か、問われないとかいうことではない。自分で自分をそこまで律する力があるのか、と。
本当の善人というのは、そのつど、いろいろな場面で、自分の中の邪悪な部分と戦う人をい
う。つまりその戦う場面をもたない人は、もともと善人ではありえない。小さな世界で、そこそこ
に小さく生きることなら、ひょっとしたら、だれにだってできる(失礼!)。しかしその人は、ただ
「生きているだけ」(失礼!)。が、それでは善人ということにはならない。繰り返すが、人は、自
分の中の邪悪さと戦ってこそ、はじめて善人になる。
う。つまりその戦う場面をもたない人は、もともと善人ではありえない。小さな世界で、そこそこ
に小さく生きることなら、ひょっとしたら、だれにだってできる(失礼!)。しかしその人は、ただ
「生きているだけ」(失礼!)。が、それでは善人ということにはならない。繰り返すが、人は、自
分の中の邪悪さと戦ってこそ、はじめて善人になる。
いつかこの問題については、改めて考えてみたい。以前書いた原稿(中日新聞掲載済み)を
ここに転載する。
ここに転載する。
++++++++++++++++++++
●四割の善と、四割の悪
(以前、掲載したのと同じ原稿です。お許しください。)
子どもに善と悪を教えるとき
●四割の善と四割の悪
社会に四割の善があり、四割の悪があるなら、子どもの世界にも、四割の善があり、四割の悪
がある。子どもの世界は、まさにおとなの世界の縮図。おとなの世界をなおさないで、子どもの
世界だけをよくしようとしても、無理。子どもがはじめて読んだカタカナが、「ホテル」であった
り、「ソープ」であったりする(「クレヨンしんちゃん」V1)。
がある。子どもの世界は、まさにおとなの世界の縮図。おとなの世界をなおさないで、子どもの
世界だけをよくしようとしても、無理。子どもがはじめて読んだカタカナが、「ホテル」であった
り、「ソープ」であったりする(「クレヨンしんちゃん」V1)。
つまり子どもの世界をよくしたいと思ったら、社会そのものと闘う。時として教育をする者は、子
どもにはきびしく、社会には甘くなりやすい。あるいはそういうワナにハマりやすい。ある中学校
の教師は、部活の試合で自分の生徒が負けたりすると、冬でもその生徒を、プールの中に放
り投げていた。
どもにはきびしく、社会には甘くなりやすい。あるいはそういうワナにハマりやすい。ある中学校
の教師は、部活の試合で自分の生徒が負けたりすると、冬でもその生徒を、プールの中に放
り投げていた。
その教師はその教師の信念をもってそうしていたのだろうが、では自分自身に対してはどうな
のか。自分に対しては、そこまできびしいのか。社会に対しては、そこまできびしいのか。親だ
ってそうだ。子どもに「勉強しろ」と言う親は多い。しかし自分で勉強している親は、少ない。
のか。自分に対しては、そこまできびしいのか。社会に対しては、そこまできびしいのか。親だ
ってそうだ。子どもに「勉強しろ」と言う親は多い。しかし自分で勉強している親は、少ない。
●善悪のハバから生まれる人間のドラマ
話がそれたが、悪があることが悪いと言っているのではない。人間の世界が、ほかの動物た
ちのように、特別によい人もいないが、特別に悪い人もいないというような世界になってしまっ
たら、何とつまらないことか。言いかえると、この善悪のハバこそが、人間の世界を豊かでおも
しろいものにしている。無数のドラマも、そこから生まれる。旧約聖書についても、こんな説話
が残っている。
ちのように、特別によい人もいないが、特別に悪い人もいないというような世界になってしまっ
たら、何とつまらないことか。言いかえると、この善悪のハバこそが、人間の世界を豊かでおも
しろいものにしている。無数のドラマも、そこから生まれる。旧約聖書についても、こんな説話
が残っている。
ノアが、「どうして人間のような(不完全な)生き物をつくったのか。(洪水で滅ぼすくらいなら、
最初から、完全な生き物にすればよかったはずだ)」と、神に聞いたときのこと。神はこう答え
ている。「希望を与えるため」と。もし人間がすべて天使のようになってしまったら、人間はより
よい人間になるという希望をなくしてしまう。つまり人間は悪いこともするが、努力によってよい
人間にもなれる。神のような人間になることもできる。旧約聖書の中の神は、「それが希望だ」
と。
最初から、完全な生き物にすればよかったはずだ)」と、神に聞いたときのこと。神はこう答え
ている。「希望を与えるため」と。もし人間がすべて天使のようになってしまったら、人間はより
よい人間になるという希望をなくしてしまう。つまり人間は悪いこともするが、努力によってよい
人間にもなれる。神のような人間になることもできる。旧約聖書の中の神は、「それが希望だ」
と。
●子どもの世界だけの問題ではない
子どもの世界に何か問題を見つけたら、それは子どもの世界だけの問題ではない。それが
わかるかわからないかは、その人の問題意識の深さにもよるが、少なくとも子どもの世界だけ
をどうこうしようとしても意味がない。たとえば少し前、援助交際が話題になったが、それが問
題ではない。
わかるかわからないかは、その人の問題意識の深さにもよるが、少なくとも子どもの世界だけ
をどうこうしようとしても意味がない。たとえば少し前、援助交際が話題になったが、それが問
題ではない。
問題は、そういう環境を見て見ぬふりをしているあなた自身にある。そうでないというのなら、あ
なたの仲間や、近隣の人が、そういうところで遊んでいることについて、あなたはどれほどそれ
と闘っているだろうか。
なたの仲間や、近隣の人が、そういうところで遊んでいることについて、あなたはどれほどそれ
と闘っているだろうか。
私の知人の中には50歳にもなるというのに、テレクラ通いをしている男がいる。高校生の娘も
いる。そこで私はある日、その男にこう聞いた。「君の娘が中年の男と援助交際をしていたら、
君は許せるか」と。するとその男は笑いながら、こう言った。
いる。そこで私はある日、その男にこう聞いた。「君の娘が中年の男と援助交際をしていたら、
君は許せるか」と。するとその男は笑いながら、こう言った。
「うちの娘は、そういうことはしないよ。うちの娘はまともだからね」と。私は「相手の男を許せる
か」という意味で聞いたのに、その知人は、「援助交際をする女性が悪い」と。こういうおめでた
さが積もり積もって、社会をゆがめる。子どもの世界をゆがめる。それが問題なのだ。
か」という意味で聞いたのに、その知人は、「援助交際をする女性が悪い」と。こういうおめでた
さが積もり積もって、社会をゆがめる。子どもの世界をゆがめる。それが問題なのだ。
●悪と戦って、はじめて善人
よいことをするから善人になるのではない。悪いことをしないから、善人というわけでもない。
悪と戦ってはじめて、人は善人になる。そういう視点をもったとき、あなたの社会を見る目は、
大きく変わる。子どもの世界も変わる。
悪と戦ってはじめて、人は善人になる。そういう視点をもったとき、あなたの社会を見る目は、
大きく変わる。子どもの世界も変わる。
(参考)
子どもたちへ
魚は陸にあがらないよね。
鳥は水の中に入らないよね。
そんなことをすれば死んでしまうこと、
みんな、知っているからね。
そういうのを常識って言うんだよね。
みんなもね、自分の心に
静かに耳を傾けてみてごらん。
きっとその常識の声が聞こえてくるよ。
してはいけないこと、
しなければならないこと、
それを教えてくれるよ。
ほかの人へのやさしさや思いやりは、
ここちよい響きがするだろ。
ほかの人を裏切ったり、
いじめたりすることは、
いやな響きがするだろ。
みんなの心は、もうそれを知っているんだよ。
あとはその常識に従えばいい。
だってね、人間はね、
その常識のおかげで、
何一〇万年もの間、生きてきたんだもの。
これからもその常識に従えばね、
みんな仲よく、生きられるよ。
わかったかな。
そういう自分自身の常識を、
もっともっとみがいて、
そしてそれを、大切にしようね。
(詩集「子どもたちへ」より)
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
●数遊び
今日のテーマは、数遊び。
年中児(4~5歳児)のみなさんです。
数をテーマに、子どもの脳をいろいろな角度から、刺激してみました。
(1)
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/puqcKCSlVzs"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mmH0Y3inSdg"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DRpuVY366l8"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(4)
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/d2X1w7NvQTY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
【2011年の終わりに】□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今日が仕事納め】(明日から、冬休み!)
●サイゼリアで夕食(12月27日)
夜のクラスまでに、1時間半の空きができた。
ワイフと2人で、サイゼリア(レストラン)へ行った。
夕食をとり、1時間ほど、そこで過ごした。
教室の外へ出ると、身を切るような冷気を感じた。
寒かった。
●正月の予定
正月の予定は、とくになし。
温泉地も、この時期はどこも満員。
料金も高い。
だから例年、私たちは静かにしている。
たぶん、今年も、そうなるだろう。
初詣なるものは、この数年、していない。
が、初詣の先取りというのは、している。
12月の終わりに、近くの神社へ行く。
人ごみが平気な人もいる。
そうでない人もいる。
が、私は基本的には、人ごみが苦手。
落ち着かない。
だから先取り。
「今年もよろしく」ではなく、「来年もよろしく」と。
いつもそう祈念する。
●年賀状
「年賀状はどうするの?」とワイフ。
「明日、書くよ」と私。
昔は手書きで、1週間仕事だった。
今は、プリンターを操作するだけ。
片手間で、できる。
楽になった。
が、同時に、ありがたみが消えた。
それもあって、数年前、年賀状廃止宣言なるものをした。
が、それでも(人とのつながり)は、残る。
この1、2年、逆戻り。
出す枚数が、ふえてきた。
ここは自然体で考えるしかない。
なりゆきに任せる。
それが(人生の流れ)。
●保安院
今日のニュース。
保安院が、東京電力に対して、厳重注意をしたという。
東京電力の(いいかげんさ)を、問題にしたらしい。
が、そんなことは、当初から、わかっていたこと。
3・11大震災から、すでに9か月もたっている。
どうして、今ごろ?
私たち一般庶民の目から見ると、保安院も東京電力も同じ。
同じ穴のムジナ。
当初はその両方が、肩を並べて、記者会見に臨んでいた。
●計画停電→料金値上げ→国有化
3・11大震災直後、東京電力は「計画停電」なるものを、実施した。
「私たちをいじめると、停電しますよ」と。
が、そのあと、電力が不足したという事実は、まったくない。
そこであの手、この手を使って、「国」から金(マネー)を出させようとした。
が、それがうまくいかないとわかると、今度は、「料金の値上げ」という言葉を使うようになった。
「私たちをいじめると、料金を値上げしますよ」と。
幼稚な心理。
幼稚な発想。
幼稚な脅迫。
そこで政府は、伝家の宝刀を抜いた。
「国有化するぞ」と。
逆に東京電力を脅した。
が、その前に、責任問題を明確にしてほしい。
これだけの被害を出しながら、責任者がいないでは、すまされない。
東京電力はすでに、こう言って、防波堤を立てている。
「私たちは国の基準に従い、許可を得てやっている(つまり責任はない)」
「私たちは国の指示通りに、行動している(つまり責任はない)」と。
どこまでも狡猾(こうかつ)な東京電力。
●北朝鮮と天皇制
だれもが、そこまでわかっている。
知っている。
しかしそれを口に出して言うことは、この日本では、タブー。
北朝鮮の新しい指導者は、金正恩。
その金正恩……。
独裁制がおかしい?
世襲制がおかしい?
偶像化がおかしい?
権威化がおかしい?
が、私たち日本人は、それを声に出して言うことができない。
言えば、日本という国自体が、自己矛盾の世界に落ち込んでしまう。
北朝鮮という国は、皮肉なことに、戦前、戦時中の日本とそっくり。
日本以上に、日本的?
私が子どものときでさえ、(戦後、10年近くもたってのことだったが)、「天皇」と呼び捨てにし
ただけで、父に殴られた。
ただけで、父に殴られた。
「陛下と言え!」と。
「日本と北朝鮮は違う」と主張する人も多い。
しかしどこがどう違うのか?
それをきちんと説明できる人はいるのだろうか。
日本に言論の自由があるというのは、ウソ。
言論の自由度にしても、日本は、178か国中、11位(国境なき記者団2010)。
順だけをみれば、まずまず。
が、皇室問題に関しては、どうか?
男系男子?
賛成、反対?
男はよい?
女はダメ?
今どき、こんなアホなことを議論している国は、そうはない。
……おっと、口がすべった。
日本の言論の自由も、ここまで。
この程度。
●北朝鮮を支持?
中国が北朝鮮支持の姿勢を、鮮明にし始めた。
が、こんなことは、最初からわかっていたこと。
6か国協議が始まったときから、私はこう書いてきた。
「茶番劇」と。
「泥棒に、泥棒の管理を任せるようなもの」とも。
その結果が、今。
が、いつか必ず、現在の歴史を振り返るときがやってくる。
そのとき、恥をかくのは、中国。
現在の今の今も、政治犯収容所には、約20万人もの人が収容されているという。
「10年もたたずして、みな死んでいく」(脱北者証言)とも。
単純に計算すれば、1年で、2万人。
50年で、100万人。
あるいはそれ以上。
現在の悲惨な状況は、やがて明るみになる。
そのとき中国は、現在の中国を、どう弁解するつもりなのか。
●「窮乏者の年末」
数日前、どこかの新聞社が、こんな社説を載せていた。
題して「窮乏者の年末」(仮称)。
記事は読まなかった。
読むまでもなかった。
現在、「どうやって年越しをしたらいいのか」と、困っている人は多い。
お金がなくて、途方に暮れている人は多い。
そういう人たちへの、励ましの記事。
表題だけで、中身がわかった。
が、ここでパラドックス。
そういう人たちは、新聞代を払うお金もない。
つまり新聞を読まない。
読まない人に向かって、「がんばれ」と励ましても、意味がない。
貧乏の恐ろしさは、それを体験したものでないと、わからない。
まさに精神の拷問。
長くつづくと、心そのものが腐る。
●リビドーvsサナトス
昨日、善悪論を、心理学の世界で考えてみた。
15枚ほど原稿を書いた。
が、どうもうまく、まとめることができなかった。
そのことを、夕食をとりながら、ワイフに話した。
要するに、生命力が強い人ほど、同時に、破壊力も強いということ。
フロイトは、生命力を「リビドー」、破壊力を「サナトス」と呼んだ。
人は、この2つの力を、同時にもっている。
つまり飛躍した意見に聞こえるかもしれないが、こういうこと。
善への志向性が強い人ほど、悪への志向性が強いということ。
で、それをコントロールする力が、「理性」ということになる。
が、この理性ほどアテにならないものはない。
そこで釈迦は、「精進」という言葉を使った。
正しくは「正精進」。
つまり「中正かつ公正な精進」。
この場合の「正」は、「ごくふつうの」という意味。
わかりやすく言えば、「人が総じてもっている常識的な」という意味。
その常識を日々に、研さんし、磨く。
それが正精進。
それがないと、人は偏(かたよ)ったものの考え方をするようになる。
これが理性のコントロールを狂わせる。
●最後の一仕事
今年も、残すところ、あと1クラス。
それが終われば、冬休み。
帰りにワイフと打ち上げ会。
毎年、そうしている。
……今年も、いろいろあった。
本当に、いろいろあった。
その「いろいろ」という言葉の中に、ぎっしりと思い出が詰まっている。
が、こうして無事、年を越せることに感謝する。
大きな病気は、しなかった。
みな、健康だった。
来年(2012年)も、現状維持。
それを目標に、がんばる。
がんばるしかない。
さあ、これから教室に戻り、一仕事。
(以上、市内、サイゼリアにて、はやし浩司 2011-12-27夕方記)
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
Hiroshi Hayashi+++++++Jan. 2012++++++はやし浩司・林浩司
では、2月もよろしく!
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm 発行人 はやし浩司(ひろし)
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 30日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page015.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●無事、64歳!
2011年を振り返る。
あれこれ振り返る。
いろいろあった。
あったが、私は無事、64歳になった。
昭和22年(1947年)生まれ。
団塊の世代、第1号。
先週、10年ぶりに、1人の男が我が家を訪ねてくれた。
突然の訪問だった。
話を聞くと、今は大学を卒業し、浜松の貿易会社に勤務しているという。
OBである。
年中児(幼稚園)から、中学3年まで、私の教室に通ってくれた。
「まだ高校3年生くらいかなと思っていたよ」と告げると、「そんなはずないですよ」「もう10年に
なりますよ」と言って笑った。
なりますよ」と言って笑った。
10年!
あっという間の10年だった。
と、同時に、こう思った。
「よくもまあ、この10年間、無事だったなあ」と。
その男のことではない。
この私が、無事だったなあ、と。
●2012年
来年のことは、わからない。
何やら大変な年に、なりそう。
悪い予感がする。
いちばん心配なのが、日本経済。
EU、中国、アメリカ……。
どのひとつが経済破綻しても、そのまま日本も破綻する。
あるいは日本のほうが、先に破綻するかもしれない。
(私が心配したところで、どうにもならないが……。)
経済の世界には、「イベント・リスク」という言葉がある。
不測の事態(=イベント)による、危険因子(=リスク)をいう。
今回の3・11大震災も、そのひとつ。
今、日本の経済は、薄氷の上を、恐る恐る歩いている。
何か起きたら、おしまい。
そのまま奈落の底へ……。
私について言えば、今までは無事だった。
しかし2012年のことは、私にもわからない。
無事、来年、65歳を迎えることができるだろうか。
●老人段階論
退職後の友人たちをみていると、一定のパターンがあるのがわかる。
称して「老人段階論」。
(1)準備期……老後に向けて、何かの運動(体力づくり)を始める。
(2)活動期……「何かをしなければ」と言いながら、行動を開始する。
(3)限界期……突然の病気になったり、仕事が行き詰ったりする。
(4)葛藤期……老人になることに抵抗し、心理的にはげしく葛藤する。
(5)受諾期……老人であることを認め、心の整理を始める。
ほとんどの人が、判を押したように、運動を始めるのは興味深い。
ウォーキング、ランニング、サイクリング、ゴルフ、テニスなどなど。
それまでに下地のできている人は別として、たいていは、長続きしない。
ちょっとした病気や怪我がきっかけで、そのまま休んでしまう。
このとき自分に、「限界」を覚える。
また自分が老人であることを認めるのは、平均して75歳だそうだ。
それまでは抵抗する。
「私はまだ若い!」と。
●どちらが現実なのか?
再び、この1年を振り返ってみる。
あれこれ思い出してみる。
……あの3・11大震災は、あまりにも現実離れしていた。
この世のできごととは、思えなかった。
同時に、今の今ですら、こうして無事でいられることが、不思議でならない。
どうして3万人近い人たちが、あっという間に、津波に飲み込まれたのか。
どうして今、私がこうしてここに生きているのか。
どちらが現実なのか。
それを考えていると、心の中がバラバラになってしまう。
だから9か月たった今でも、こう思う。
「あの3・11大震災さえなければ……」「あの原発事故さえなければ……」と。
●2012年
ともあれ、とにかく生きていくしかない。
あれこれ悩んだところで、どうにもならない。
2012年は2012年。
今日できることは、今日、する。
がんばってする。
その結果として、明日はやってくる。
2012年は、やってくる。
が、2012年は、先にも書いたように、たいへんな年になりそう。
ロイターは、つぎのように報道している(12月23日)。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
……2012年は米国とロシアとフランスで大統領選が行われ、中国ではポスト胡錦濤体制が
始動する。欧州はソブリン危機の不透明感が晴れず、民主化の波を受けた中東は政治的動
揺が続き、経済の悪化は世界各地でデモなどの混乱を引き起こす可能性がある。足元では、
ユーロをめぐる不安が根強く、核開発を続けるイランをイスラエルが軍事攻撃するとの懸念も
残ったままだ。
始動する。欧州はソブリン危機の不透明感が晴れず、民主化の波を受けた中東は政治的動
揺が続き、経済の悪化は世界各地でデモなどの混乱を引き起こす可能性がある。足元では、
ユーロをめぐる不安が根強く、核開発を続けるイランをイスラエルが軍事攻撃するとの懸念も
残ったままだ。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
もう少しこの記事を、整理してみる。
(1)2012年は米国とロシアとフランスで大統領選が行われ、
(2)中国ではポスト胡錦濤体制が始動する。
(3)欧州はソブリン危機の不透明感が晴れず、
(4)民主化の波を受けた中東は政治的動揺が続き、
(5)経済の悪化は世界各地でデモなどの混乱を引き起こす可能性がある。
(6)足元では、ユーロをめぐる不安が根強く、
(7)核開発を続けるイランをイスラエルが軍事攻撃するとの懸念も残ったままだ。
が、本当に困るのは、以上のことではない。
こうした不安定な状況がつづくと、発展途上国のもならず、先進国においても政情が不安定に
なること。
なること。
ロイターは、つぎのよう結んでいる。
『……中東の紛争やユーロ圏の崩壊といった事態が避けられたとしても、専門家の間では、経
済成長の鈍化と失業率の上昇に伴い、先進国でも発展途上国でも社会不安のリスクが増大
し、世界中で政治情勢は難しさを増すと指摘する声は多い』と。
済成長の鈍化と失業率の上昇に伴い、先進国でも発展途上国でも社会不安のリスクが増大
し、世界中で政治情勢は難しさを増すと指摘する声は多い』と。
この先、北朝鮮がどう出てくるか。
それもこの日本にとっては、心配の種。
●現状維持
2012年も、「現状維持」。
それだけで精一杯。
それができれば、御の字。
健康イコール、運動。
ボケ防止イコール、仕事。
何も望まない。
何も期待しない。
ただひたすら、懸命に、かつまじめにその日を生きる。
抱負?
そんなもの、あるわけない。
とにかく現状維持。
結果は、あとからついてくる。
2011/12/24
メリークリスマス!
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
【年賀状】(2012年・新年)
今年の年賀状は、東洋医学(黄帝内経・素問)の一節で飾った。
「毎年、ちがった年賀状を出す」が、私のモットーになっている。
(中には、10年、20年と、まったく文面の人もいるが……。)
『八風(自然)の理によく順応し、世俗の習慣にみずからの趣向を無理なく適応させ、恨
み怒りの気持ちはさらにない。
行動や服飾もすべて俗世間の人と異なることなく、みずからの崇高性を表面にあらわすことも
ない。
ない。
身体的には働きすぎず、過労に陥ることもなく、精神的にも悩みはなく、平静楽観を旨とし、自
足を事とする』(上古天真論篇)と。
足を事とする』(上古天真論篇)と。
が、これだけでは、何ともおもしろくない。
そこでムーディーズなどの評価法を借り、現状を分析してみた。
『2011年の成績
ボケ度…Aa (ムーディーズ)
離婚騒動…6回くらい(前年度比-20%)
一泊旅行…50泊くらい(前年度比+10%)
仕事…弱含み (日銀短観)
体力…Bbb (ムーディーズ)(運動量前年度比ー15%)
精力…Ca 沈没寸前 (ムーディーズ)
ピンコロ可能性…5年以内に50%(前年度比+10%)
劇場映画鑑賞…48回(前年度比+10%)』と。
こうしてできあがったのが、つぎの年賀状。
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/85/imgd929afdfzik5zj.
jpeg" width="696" height="873" alt="img237.jpg">
jpeg" width="696" height="873" alt="img237.jpg">
多くの方に、年賀のあいさつを失礼している。
こんな年賀状だが、そういう人たちの目にとまれば、うれしい。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●映画『山本五十六』、『世にも不思議な留学記』
●12月25日(風邪?)
++++++++++++++++++++
昨夜、寒い中、がまんしたのがよくなかった。
11時ごろまで、書斎で、あれこれ作業をしていた。
というか、このところ気温センサーが鈍くなったよう(?)。
寒いはずなのに、それほど寒く感じない。
足腰が金属のように冷たくなって、はじめて寒さを感ずる。
昨夜が、そうだった。
「寒い」というより、冷え冷えとした感覚が足の先から腰までやってきて、はじめて外気の冷たさ
がわかった。
がわかった。
それがわかって、あわてて暖かいはずの布団の中に入った。
が、足の先だけは、なかなか温まらなかった。
足を布団の中でこすりつけたりした。
30分ほど、もがいた。
……ということで、今朝は、起きたときからゾクゾクする。
腰が痛い。
のども痛い。
どうやら風邪をひいたらしい。
が、負けてはおられない。
10分のウォーキングのあと、熱い風呂へ飛び込む。
まだ風邪薬はのんでいないが、あとで葛根湯をのむつもり。
風邪(かぜ)のひき始めは、葛根湯(かこんとう)。
風邪(ふうじゃ)が、体の内部に入り、悪寒がするようになったら、麻黄湯(まおうとう)。
インフエンザのばあいは、張仲景の『傷寒論』(『傷寒雑病論』ともいう)が、参考になる。
後漢時代の医家である。
(注:ただし、張仲景が言う「傷寒・雑病」というのは、チフスやコレラのような伝染病をさすとい
う説もある。
う説もある。
「傷寒」というのは、文字通り、「寒邪に敗れる」を意味する。
それもあって、私は「インフルエンザ説」を唱える。)
ともあれ、今日は、とくに予定はなし。
家で静かにしている。
ゾクゾク……。
症状が麻黄湯に近くなってきたような感じがする。
++++++++++++++++++++++
●「はやし浩司 目で見る漢方診断」
たった今、ヤフーの検索機能を使って、「はやし浩司 目で見る漢方診断」を検索してみた。
2340件、ヒットした。
そのトップに、「AMAZON COM JP」があった。
それをクリック。
私の本が、AMAZONで、6339円で売られているのを知った。
紹介には、こうあった。
「……状態の悪い本です、カバーがなく、ページに水ぬれ跡がずっとついています。書き込み
や線引き、ページの欠落はありませんが、読めればよい方向けです」(わだ古書店)と。
や線引き、ページの欠落はありませんが、読めればよい方向けです」(わだ古書店)と。
うれしかった。
ボロボロの中古本が、6339円!
少し状態のよい本になると、7000~9000円で取り引きされている。
現在、その「目で見る漢方診断」は、HPのほうで無料で公開している。
興味のある人は、どうか、そちらを見てほしい。
http://bwtachiyomi.ninja-web.net/page051.html
(私が生きている間の、早いもの勝ち! ……つまり死んだら、HPは、閉鎖になり、公開も終
わるという意味。
わるという意味。
無料で読むなら、今のうち!)
おかしなもので、最近は、自分の書いた本を参考にし、ものを書くことがときどきある。
『目で見る漢方診断』にしても、100%、私が書いた本である。
にもかかわらず、同時に2000年前(黄帝の時代になると、5500年前)に、他人によって書か
れた本のような感じもする。
れた本のような感じもする。
自分の本であって、自分の本でない?
その本を書いたころでさえ、遠い遠い昔のような気がする。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 目で見る漢方診断 東洋医学
はやし浩司 東洋医学基礎編 基礎篇 東洋医学基礎篇 黄帝内経 素問)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 目で見る漢方診断 東洋医学
はやし浩司 東洋医学基礎編 基礎篇 東洋医学基礎篇 黄帝内経 素問)
●映画『山本五十六』
昨日の午後、映画『山本五十六』を観てきた。
久々に観る、邦画である。
CGの稚拙さは随所に見られたが、星は3つの、★★★。
よかった。
途中、何度か涙がこぼれた。
ただし悪役の新聞記者の演技が、大げさ。
露骨。
俳優そのものの、脳みそが薄っぺらい。
だから演技に、深みが出てこない。
知的な俳優が、ああいう役をこなせば、すばらしい俳優ということになる。
が、そうでない俳優が、無理に悪役を演ずるから、かえって底が見えてしまう。
現実に、ああまで感情をむき出しにする人がいたら、私たちはその人を「バカ」という。
もし『山本五十六』を観る機会があったら、新聞記者の演技に注目してほしい。
私がここで言っている意味が、わかってもらえるはず。
で、その山本五十六について、こんな原稿を書いたことがある。
中日新聞に発表させてもらった原稿である。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●国によって違う職業観
職業観というのは、国によって違う。もう30年も前のことだが、私がメルボルン大学
に留学していたときのこと。当時、あの人口300万人と言われたメルボルン市でさえ、
正規の日本人留学生は私1人だけ。(もう1人、Mという女子学生がいたが、彼女は、もと
もとメルボルンに住んでいた日本人。)そのときのこと。
私が友人の部屋でお茶を飲んでいると、1通の手紙を見つけた。許可をもらって読むと、
「君を外交官にしたいから、面接に来るように」と。
私が喜んで、「外交官ではないか! おめでとう」と言うと、その友人は何を思ったか、そ
の手紙を丸めてポイと捨てた。「アメリカやイギリスなら行きたいが、99%の国は、行き
たくない」と。考えてみればオーストラリアは移民国家。「外国へ出る」という意識が、日
本人のそれとはまったく違っていた。
さらにある日。フィリッピンからの留学生と話していると、彼はこう言った。「君は日本
へ帰ったら、ジャパニーズ・アーミィ(軍隊)に入るのか」と。私が「いや、今、日本で
は軍隊はあまり人気がない」と答えると、「イソロク(山本五十六)の伝統ある軍隊になぜ
入らないのか」と、やんやの非難。
当時のフィリッピンは、マルコス政権下。軍人になることイコール、そのまま出世コース
ということになっていた。で、私の番。
私はほかに自慢できるものがなかったこともあり、最初のころは、会う人ごとに、「ぼく
は日本へ帰ったら、M物産という会社に入る。日本ではナンバーワンの商社だ」と言って
いた。が、ある日、1番仲のよかったデニス君が、こう言った。「ヒロシ、もうそんなこと
を言うのはよせ。日本のビジネスマンは、ここでは軽蔑されている」と。彼は「ディスパ
イズ(軽蔑する)」という言葉を使った。
当時の日本は高度成長期のまっただ中。ほとんどの学生は何も迷わず、銀行マン、商社
マンの道を歩もうとしていた。外交官になるというのは、エリート中のエリートでしかな
かった。この友人の一言で、私の職業観が大きく変わったことは言うまでもない。
さて今、あなたはどのような職業観をもっているだろうか。あなたというより、あなた
の夫はどのような職業観をもっているだろうか。それがどんなものであるにせよ、ただこ
れだけは言える。
こうした職業観、つまり常識というのは、決して絶対的なものではないということ。時代
によって、それぞれの国によって、そのときどきの「教育」によってつくられるというこ
と。大切なことは、そういうものを通り越した、その先で子どもの将来を考える必要があ
るということ。
私の母は、私が幼稚園教師になると電話で話したとき、電話口の向こうで、オイオイと泣
き崩れてしまった。「浩ちャーン、あんたは道を誤ったア~」と。母は母の時代の常識にそ
ってそう言っただけだが、その一言が私をどん底に叩き落したことは言うまでもない。
しかしあなたとあなたの子どもの間では、こういうことはあってはならない。これからは、
もうそういう時代ではない。あってはならない。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 通俗性 はやし浩司
金権教 はやし浩司 ディスパイズ despise 軽蔑という言葉を使った はやし浩司 山本五
十六)
十六)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
もう1作。
これも中日新聞で発表済み。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
イソロクはアジアの英雄だった【2】
●自由とは「自らに由る」こと
オーストラリアには本物の自由があった。自由とは、「自らに由(よ)る」という意味だ。こんな
ことがあった。
ことがあった。
夏の暑い日のことだった。ハウスの連中が水合戦をしようということになった。で、一人、二、
三ドルずつ集めた。消防用の水栓をあけると、二〇ドルの罰金ということになっていた。で、私
たちがそのお金を、ハウスの受け付けへもっていくと、窓口の女性は、笑いながら、黙ってそれ
を受け取ってくれた。
三ドルずつ集めた。消防用の水栓をあけると、二〇ドルの罰金ということになっていた。で、私
たちがそのお金を、ハウスの受け付けへもっていくと、窓口の女性は、笑いながら、黙ってそれ
を受け取ってくれた。
消防用の水の水圧は、水道の比ではない。まともにくらうと学生でも、体が数メートルは吹っ
飛ぶ。私たちはその水合戦を、消防自動車が飛んで来るまで楽しんだ。またこんなこともあっ
た。
飛ぶ。私たちはその水合戦を、消防自動車が飛んで来るまで楽しんだ。またこんなこともあっ
た。
一応ハウスは、女性禁制だった。が、誰もそんなことなど守らない。友人のロスもその朝、ガ
ールフレンドと一緒だった。そこで私たちは、窓とドアから一斉に彼の部屋に飛び込み、ベッド
ールフレンドと一緒だった。そこで私たちは、窓とドアから一斉に彼の部屋に飛び込み、ベッド
ごと二人を運び出した。運びだして、ハウスの裏にある公園のまん中まで運んだ。公園といっ
ても、地平線がはるかかなたに見えるほど、広い。
ても、地平線がはるかかなたに見えるほど、広い。
ロスたちはベッドの上でワーワー叫んでいたが、私たちは無視した。あとで振りかえると、二
人は互いの体をシーツでくるんで、公園を走っていた。それを見て、私たちは笑った。公園にい
た人たちも笑った。そしてロスたちも笑った。風に舞うシーツが、やたらと白かった。
人は互いの体をシーツでくるんで、公園を走っていた。それを見て、私たちは笑った。公園にい
た人たちも笑った。そしてロスたちも笑った。風に舞うシーツが、やたらと白かった。
●「外交官はブタの仕事」
そしてある日。友人の部屋でお茶を飲んでいると、私は外務省からの手紙をみつけた。許可
をもらって読むと、「君を外交官にしたいから、面接に来るように」と。そこで私が「おめでとう」と
言うと、彼はその手紙をそのままごみ箱へポイと捨ててしまった。「ブタの仕事だ。アメリカやイ
ギリスなら行きたいが、九九%の国へは行きたくない」と。彼は「ブタ」という言葉を使った。
をもらって読むと、「君を外交官にしたいから、面接に来るように」と。そこで私が「おめでとう」と
言うと、彼はその手紙をそのままごみ箱へポイと捨ててしまった。「ブタの仕事だ。アメリカやイ
ギリスなら行きたいが、九九%の国へは行きたくない」と。彼は「ブタ」という言葉を使った。
あの国はもともと移民国家。「外国へ出る」という意識そのものが、日本人のそれとはまったく
ちがっていた。同じ公務の仕事というなら、オーストラリア国内のほうがよい、と考えていたよう
だ。また別の日。
ちがっていた。同じ公務の仕事というなら、オーストラリア国内のほうがよい、と考えていたよう
だ。また別の日。
フィリッピンからの留学生が来て、こう言った。「君は日本へ帰ったら、軍隊に入るのか」と。
「今、日本では軍隊はあまり人気がない」と答えると、「イソロク(山本五十六)の、伝統ある軍
隊になぜ入らない」と、やんやの非難。当時のフィリッピンは、マルコス政権下。軍人になること
イコール、出世を意味していた。
「今、日本では軍隊はあまり人気がない」と答えると、「イソロク(山本五十六)の、伝統ある軍
隊になぜ入らない」と、やんやの非難。当時のフィリッピンは、マルコス政権下。軍人になること
イコール、出世を意味していた。
マニラ郊外にマカティと呼ばれる特別居住区があった。軍人の場合、下から二階級昇進する
だけで、そのマカティに、家つき、運転手つきの車があてがわれた。またイソロクは、「白人と対
等に戦った最初のアジア人」ということで、アジアの学生の間では英雄だった。これには驚いた
が、事実は事実だ。日本以外のアジアの国々は、欧米各国の植民地になったという暗い歴史
がある。
だけで、そのマカティに、家つき、運転手つきの車があてがわれた。またイソロクは、「白人と対
等に戦った最初のアジア人」ということで、アジアの学生の間では英雄だった。これには驚いた
が、事実は事実だ。日本以外のアジアの国々は、欧米各国の植民地になったという暗い歴史
がある。
そして私の番。ある日、一番仲のよかった友だちが、私にこう言った。「ヒロシ、もうそんなこと
言うのはよせ。ここでは、日本人の商社マンは軽蔑されている」と。私はことあるごとに、日本
へ帰ったら、M物産という会社に入社することになっていると、言っていた。ほかに自慢するも
のがなかった。が、国変われば、当然、価値観もちがう。
言うのはよせ。ここでは、日本人の商社マンは軽蔑されている」と。私はことあるごとに、日本
へ帰ったら、M物産という会社に入社することになっていると、言っていた。ほかに自慢するも
のがなかった。が、国変われば、当然、価値観もちがう。
私たち戦後生まれの団塊の世代は、就職といえば、迷わず、商社マンや銀行マンの道を選
んだ。それが学生として、最良の道だと信じていた。しかしそういう価値観とて、国策の中でつく
られたものだった。私は、それを思い知らされた。
んだ。それが学生として、最良の道だと信じていた。しかしそういう価値観とて、国策の中でつく
られたものだった。私は、それを思い知らされた。
時、まさしく日本は、高度成長へのまっただ中へと、ばく進していた。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●山本五十六
私がいたカレッジには、世界中から学生たちが集まっていた。
アジアからの学生も、70~80人、いた。
が、それらの学生たちは、山本五十六だけは、尊敬していた。
先の原稿の中で書いたことは、事実である。
東条英機は嫌われていたが、山本五十六は、尊敬されていた。
今でも、「白人と対等に戦った最初のアジア人」と言った相手の名前と顔をよく覚えている。
タン・アー・チュウアン君である。
マレーシアから来ていた留学生だった。
そのタン君について書いた原稿もある。
それを掲載する。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●処刑になったタン君【12】
●日本人にまちがえられたタン君
私の一番仲のよかった友人に、タン君というのがいた。マレ-シアン中国人で、経済学部に
籍をおいていた。
籍をおいていた。
最初、彼は私とはまったく口をきこうとしなかった。ずっとあとになって理由を聞くと、「ぼくの
祖父は、日本兵に殺されたからだ」と教えてくれた。そのタン君。ある日私にこう言った。
祖父は、日本兵に殺されたからだ」と教えてくれた。そのタン君。ある日私にこう言った。
「日本は中国の属国だ」と。そこで私が猛烈に反発すると、「じゃ、お前の名前を、日本語で
書いてみろ」と。私が「林浩司」と漢字で書くと、「それ見ろ、中国語じゃないか」と笑った。
書いてみろ」と。私が「林浩司」と漢字で書くと、「それ見ろ、中国語じゃないか」と笑った。
そう、彼はマレーシア国籍をもっていたが、自分では決してマレーシア人とは言わなかった。
「ぼくは中国人だ」といつも言っていた。マレー語もほとんど話さなかった。話さないばかりか、
マレー人そのものを、どこかで軽蔑していた。
マレー人そのものを、どこかで軽蔑していた。
日本人が中国人にまちがえられると、たいていの日本人は怒る。しかし中国人が日本人にま
ちがえられると、もっと怒る。タン君は、自分が日本人にまちがえられるのを、何よりも嫌った。
街を歩いているときもそうだった。「お前も日本人か」と聞かれたとき、タン君は、地面を足で蹴
飛ばしながら、「ノー(違う)!」と叫んでいた。
ちがえられると、もっと怒る。タン君は、自分が日本人にまちがえられるのを、何よりも嫌った。
街を歩いているときもそうだった。「お前も日本人か」と聞かれたとき、タン君は、地面を足で蹴
飛ばしながら、「ノー(違う)!」と叫んでいた。
そのタン君には一人のガ-ルフレンドがいた。しかし彼は決して、彼女を私に紹介しようとし
なかった。一度ベッドの中で一緒にいるところを見かけたが、すぐ毛布で顔を隠してしまった。
が、やがて卒業式が近づいてきた。
なかった。一度ベッドの中で一緒にいるところを見かけたが、すぐ毛布で顔を隠してしまった。
が、やがて卒業式が近づいてきた。
タン君は成績上位者に与えられる、名誉学士号(オナー・ディグリー)を取得していた。そのタ
ン君が、ある日、中華街のレストランで、こう話してくれた。「ヒロシ、ぼくのジェニ-は……」と。
喉の奥から絞り出すような声だった。「ジェニ-は四二歳だ。人妻だ。しかも子どもがいる。
今、夫から訴えられている」と。
ン君が、ある日、中華街のレストランで、こう話してくれた。「ヒロシ、ぼくのジェニ-は……」と。
喉の奥から絞り出すような声だった。「ジェニ-は四二歳だ。人妻だ。しかも子どもがいる。
今、夫から訴えられている」と。
そう言い終わったとき、彼は緊張のあまり、手をブルブルと震わした。
●赤軍に、そして処刑
そのタン君と私は、たまたま東大から来ていた田丸謙二教授の部屋で、よく徹夜した。教授
の部屋は広く、それにいつも食べ物が豊富にあった。
の部屋は広く、それにいつも食べ物が豊富にあった。
田丸教授は、『東大闘争』で疲れたとかで、休暇をもらってメルボルン大学へ来ていた。教授
はその後、東大の総長特別補佐、つまり副総長になられたが、タン君がマレ-シアで処刑され
たと聞いたときには、ユネスコの国内委員会の委員もしていた。
はその後、東大の総長特別補佐、つまり副総長になられたが、タン君がマレ-シアで処刑され
たと聞いたときには、ユネスコの国内委員会の委員もしていた。
この話は確認がとれていないので、もし世界のどこかでタン君が生きているとしたら、それは
それですばらしいことだと思う。しかし私に届いた情報にまちがいがなければ、タン君は、マレ
-シアで、一九八〇年ごろ処刑されている。タン君は大学を卒業すると同時に、ジェニ-とクア
ラルンプ-ルへ駆け落ちし、そこで兄を手伝ってビジネスを始めた。
それですばらしいことだと思う。しかし私に届いた情報にまちがいがなければ、タン君は、マレ
-シアで、一九八〇年ごろ処刑されている。タン君は大学を卒業すると同時に、ジェニ-とクア
ラルンプ-ルへ駆け落ちし、そこで兄を手伝ってビジネスを始めた。
しばらくは音信があったが、あるときからプツリと途絶えてしまった。何度か電話をしてみた
が、いつも別の人が出て、英語そのものが通じなかった。で、これから先は、偶然、見つけた
新聞記事によるものだ。
が、いつも別の人が出て、英語そのものが通じなかった。で、これから先は、偶然、見つけた
新聞記事によるものだ。
その後、タン君は、マレ-シアでは非合法組織である赤軍に身を投じ、逮捕、投獄され、そし
て処刑されてしまった。遺骨は今、兄の手でシンガポ-ルの墓地に埋葬されているという。
て処刑されてしまった。遺骨は今、兄の手でシンガポ-ルの墓地に埋葬されているという。
田丸教授にその話をすると、教授は、「私なら(ユネスコを通して)何とかできたのに……」と、
さかんにくやしがっておられた。そうそう私は彼にで会ってからというもの、「私は日本人だ」と
言うのをやめた。「私はアジア人だ」と言うようになった。その心は今も私の心の中で生きてい
る。
さかんにくやしがっておられた。そうそう私は彼にで会ってからというもの、「私は日本人だ」と
言うのをやめた。「私はアジア人だ」と言うようになった。その心は今も私の心の中で生きてい
る。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 タン君 タン・アー・チュアン マレ
ーシア 田丸謙二 はやし浩司 世にも不思議な留学記)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 タン君 タン・アー・チュアン マレ
ーシア 田丸謙二 はやし浩司 世にも不思議な留学記)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
これらの原稿は、以下のところで紹介している。
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page195.html
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●では、今日は、ここまで
やはりこれから葛根湯をのんでくる。
そのあとのことはわからないが、しばらく布団の中で横になるつもり。
ワイフは、現在、美容院へ行っている。
ワイフが帰ってくるまで、無事、生きていたい。
2011/12/25朝記
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
●1日遅れのクリスマス
12月25日。
1日遅れのクリスマス。
ワイフは「老人組はクリスマスなど、しないわ」と居直っている。
「……しかしねエ~」と、私。
それで1日遅れのクリスマス。
25日になって、クリスマスをすることになった。
夕食の材料を買いに行ったついでに、ケーキを一個。
「売れ残りのケーキはありますか?」と聞くと、店員はあっさりとこう言った。
「今日が本番です」と。
ホント?
知らなかった……!
我が家では12月24日の夜に、ずっとクリスマスを祝っていた。
「シャンパーンが1本、あるわ」とワイフ。
●寒い
日昼でも、気温は6度前後。
寒いというより、冷たい。
午後1時ごろ、雹(ひょう)が降った。
が、私はそのころ、昼寝中。
ちょうど1時間40分。
1レム分、ぐっすりと眠った。
今夜は山荘で1泊するつもり。
●岐阜は大雪
従兄が餅を送ってくれた。
「郡上のやきもち」という餅だった。
故郷の温もりが、プ~ンと香った。
礼の電話をした。
あれこれ話をした。
岐阜(関市板取村)では、昨夜から雪が降り始めたという。
「30センチは積もった」という。
「いいなア」と思う気持ち半分。
「たいへんだなア」と思う気持ち半分。
●不景気
従兄は何度も「不景気」という言葉を使った。
「浜松もひどいもんですよ」と言うと、「がんばるしかないねエ」と。
そう、がんばるしかない。
生きるのもたいへん。
死ぬのもたいへん。
簡単には死ねない。
だからがんばるしかない。
●乾杯!
……ということで、今夜、1日遅れのクリスマス・パーティを開いた。
ケーキとシャンパーンだけ。
プレゼント交換もない。
食事の終わりに、「メリークリスマス」。
それに乾杯。
それだけ。
棚の上のクリスマスカードも、どこかさみしそう。
「R君から、クリスマスカードは来た?」とワイフに聞くと、「ほら」とそこを指さした。
見ると、棚の上に並んでいた。
「会いたいなア」と私。
「3月に、またオーストラリアへ行こうか?」とワイフ。
「クリスチャンでもないぼくたちが、クリスマスだなんて、おかしいよ」と。
そう言って、自分を慰める。
さみしいクリスマス。
言い訳をする。
●形相
近所に、そのあたりでも評判の意地悪ジー様がいる。
何かにつけ、意地悪。
利己主義というか、自分の家の前にだれかが車を止めただけで、パトカーを呼ぶ。
30分も止めておくと、写真を撮る。
撮った写真を警察へ送る。
私も一度、やられた。
一事が万事。
万事が一事。
……というジー様。
で、そのシー様、今年、80歳くらいになった。
久しぶりにその顔を見た。
散歩の途中だった。
ワイフも横にいた。
が、その顔を見て、ゾッとした。
ワイフも、そうだったとあとで言った。
なぜ、ゾッとしたか……。
……つまり、そういう顔。
ゆがんでいた。
恐ろしい形相をしていた。
「心がゆがむと、顔もゆがむね」と。
そんな話をワイフと2人で、しあった。
●老人心理
老人には老人独特の心理がある。
独特の死生観と言うべきか。
ワイフの父親は、生前、いつもこう言っていた。
「申し訳ない、申し訳ない」と。
「自分だけ生き残り、日本へ帰ってきて、申し訳ない」と。
行きは3000人。
帰ってきたのは、たったの300人。
ワイフの父親は、戦時中、ラバウルへ出兵していた。
その一方で、知りあいが死ぬたびに、「あいつが死んだ」「こいつが死んだ」と喜ぶ人もいる。
表では悲しんでいるフリをするが、それは演技。
仮面。
常人には理解できない心理だが、そういう老人もたしかに、いる。
世間体を気にし、見栄や体裁ばかりを気にする。
だからそういう死生観になるのか。
あるいはそういう死生観をもっているから、そういう人生観になるのか。
ワイフの父親のような老人もいれば、心のゆがんだ老人もいる。
そのちがいは、日々の積み重ねによって決まる。
老人になってから、決まるのではない。
若いころからの生き様によって、決まる。
●小雨
山荘へ向かう途中、小雨が降り始めた。
午後6時だった。
が、外は真っ暗。
路面が鏡のように、街の明かりを照り返していた。
寒々とした景色だった。
よく見ると、雨ではなく雪だった。
●『2012年・マヤ予言の謎』
買い癖。
コンビニへ行くたびに、この種の本を買う。
今夜は『2012年、マヤ予言の謎』(Gakken)。
「予言など当たるわけがない」と思いつつ、ついつい買ってしまう。
よい例が「ノストラダムスの大予言」。
結果は、ハズレ!
あれほどまでに騒いでおきながら、ハズレもハズレ、大ハズレ!
1999年の終わりにあったのは、「2000年問題」だけ。
全世界のコンピューターが狂うと言われた。
が、それも、結局は何ごともなく、終わった。
今夜は、私は、これを読む。
暇つぶしには、この種の本がいちばん。
読んでいるうちに、たいてい眠くなる。
●イスラエルによるイラン攻撃
新年早々というか、ひょっとしたら明日かも知れない。
イスラエルによるイラン攻撃が心配される。
可能性の問題ではない。
時間の問題。
運転しながらワイフがこう言った。
「いつかしら?」と。
私「だれもが、そうでないと思っているときさ」
ワ「じゃあ、いつ?」
私「ぼくはクリスマスの夜と思っていた。が、何ごともなかった。つぎは新年だろうね」と。
こうした奇襲攻撃は、相手がいちばん油断しているときをねらう。
相手が構えていたら、奇襲攻撃にならない。
が、それをきっかけに原油価格の高騰。
とたん、世界経済は、さらにおかしくなる。
●人類滅亡7つの可能性
『2012年、マヤ予言の謎』によれば、人類滅亡には、7つの可能性があるという。
そのまま書き出してみる。
(1)バイオハザード
(2)小惑星NEOの衝突
(3)スーパー・ソーラーストーム
(4)超新星ベテルギウスの爆発
(5)エイリアンの侵略
(6)氷河期の到来
(7)闇の集団による世界統一
マヤが以上のことを予言しているわけではない。
2012年に起こるかもしれないということで、7つの可能性があげられている。
で、私なりに、その可能性を採点してみる。
(1)バイオハザード……いつ起きてもおかしくないが、2012年とはかぎらない。
(2)小惑星NEOの衝突……直径が10メートル前後のものは、ありうる。
(3)スーパー・ソーラーストーム……ほぼ確実視されている。規模は不明。
(4)超新星ベテルギウスの爆発……どうかな?
(5)エイリアンの侵略……地球など侵略しても、意味はない。
(6)氷河期の到来……海流の流れが変わると、局地的に極寒期に入ることもありえる。
(7)闇の集団による世界統一……何を今さら! すでに無数の集団が誕生している。
●山荘にて
山荘では、ワイフはいつものようにビデオを見始めた。
私は、TOSHIBAのR631を叩き始めた。
ウルトラ・パソコン。
R631は、週刊アスキー誌で、今年のベスト・バイ賞を受賞した。
この賞に異議はない。
たしかに完成度が高い。
使えば使うほど、愛着がわいてくる。
●騎士道
ワイフの見ているDVDの中に、こんなセリフがあった。
『デビル・クエスト』というDVDである。
主演は、ニコラス・ケイジ。
そのニコラス・ケイジ演ずる騎士が、1人の若者に騎士(ナイト)の称号を与える。
「身が灰塵となるまで……神に忠誠を誓うべし……」(記憶)と。
西洋の騎士道の原点である。
スケールが大きい。
相手は「神」。
「日本の武士道とは、ずいぶんと違うなア」と、私。
日本的に考えるなら、『仏に忠誠を誓うべし』となるのか?
しかし『仏に忠誠』というのも、おかしい。
●死に際の美学
そう言えば、昨日観た映画、『山本五十六』の中にも、武士道を思わせるセリフがいくつか出
てきた。
てきた。
たとえばこんなセリフ。
役所公司演ずる山本五十六が、こう言う。
「武士は、夜討ち(=暗殺)をしかけるときも、相手の枕を一度蹴る。
蹴って相手が起きあがったところで、相手を殺す」(記憶)と。
つまり武士たるもの、宣戦布告もしないで、真珠湾を攻撃するような卑怯なことはしない、と。
これも死に際の美学ということになる。
正確には、「殺しの美学」?
そのときは「うまいこと言うなア」と、感心した。
●卑怯
では、イスラエルはどうか?
一度、宣戦布告をしてから、イランを攻撃するだろうか。
それには前例がある。
一度、イランの核施設を攻撃したことがある。
が、イスラエルはそういう布告をした例(ためし)がない。
いつも奇襲攻撃。
日本流に考えれば、武士道の精神から完全にはずれている。
だいたい西洋の騎士道には、「卑怯」という言葉そのものが、ない。
あえて言えば、「ずるい(sneaky)」という言葉がある。
が、殺し合いに、ずるいも何もない。
●映画『聯合艦隊司令長官・山本五十六』
映画『聯合艦隊司令長官・山本五十六』は、よい映画だった。
直後の評価では、星を3つ、つけた。
しかし1日たった今、少しずつだが、評価が崩れてきた。
私が映画『トラ・トラ・トラ』を観たのは、1970年。
オーストラリアにいたころ。
その『トラ・トラ・トラ』と比べたら、……というか、『山本五十六』は、比較にならない。
つまりお粗末。
「空前のスケールで描く、一大巨編」(公式サイトおよび広告)と言うほど、すごくはなかった。
そのあと発表された映画『パールハーバー』と比べても、そうだ。
比較にならない。
……たしか最後のところで、こんなナレーションもあったように記憶している。
「戦後70年もたち……」「私たちは……を忘れている」(記憶)と。
日本映画の悪いところ。
必ず、こうした説教がましい説明が入る。
説教がましい説明が、映画そのものを台無しにしてしまう。
●卑怯(2)
Weblio辞書には、こうある。
「卑怯を英語に訳すと(おくびょう)、 cowardice(卑劣)。
【形式ばった表現】 meanness卑怯な(おくびょうな) cowardly;
《口語》 chicken(卑劣な)
【形式ばった表現】 mean(不正な)」と。
卑怯イコール、臆病(おくびょう)ということになる。
私は武士道でいう「卑怯」は、「ずるい」のほうに近いと思う。
これは解釈の違いによるものか。
少し気になったので、Weblio辞書を使って、「卑怯」の英訳を調べてみた。
●正月休み
正月休み。
10日も、ある。
どうしようか。
ワイフは「あちこちへ旅行しよう」と言う。
私も、そう思う。
しかし今年は、まだ計画を立てていない。
とくに行きたいところは、ない。
行くとしたら、「ひおき」(民宿)。
岐阜県板取村にある、「ひおき」。
明日にでも電話をしてみよう。
●おでん
時刻は午後9時。
先ほど、ワイフがこう言った。
「9時以後は、何も食べてはだめよ」「太るから」と。
その9時が、近づいてきた。
家からもってきた、おでんが食べたい。
うらめしい。
が、ここはがまん。
現在、体重は66キロ。
適正体重より、2キロもオーバー。
●死生観
ところでこのところ、おかしな死生観が漂うようになった。
たとえばこんなふうに、考える。
何かの大病になったとする。
そのとき私は、どうするか、と。
大病と闘う人もいる。
闘っている人もいる。
しかし私のばあい、闘っても、意味はない。
だからこう思う。
「息子たちにはもちろん、ワイフにも知らせないでおこう」と。
つまり静かに、その時を迎えよう、と。
手遅れなら、手遅れでもよい。
私はもう、じゅうぶんすぎるほど、長く生きた。
無理に生きて、みなに迷惑をかけるくらいなら、さっさと死んだほうがよい。
たぶん、ワイフも同じ考えだろう。
ああいう性格の女性だから、大病になっても、私には知らせないだろう。
静かに死ぬことだけを望むだろう。
命を天に預ける。
共に命を天に預ける。
ジタバタしない。
……そんな死生観。
●「ああ、これで死ねるのか」
だからといって、誤解しないでほしい。
「死にたい」と書いているのではない。
生きたい。
どこまでも生きたい。
しかし同時に、「死」が、それほど怖い存在ではなくなってきた。
この正月(2011年)に廊下で倒れたときも、こう思った。
「ああ、これで死ねるのか」と。
不思議なほど、穏やかな気持ちだった。
本当に不思議なほど、穏やかな気持ちだった。
あれほどまでに死を恐れていた私が、穏やかな気持ちだった。
そのほうが、私にとっては不思議だった。
この世に未練はない。
はじめから期待していない。
期待していないから、未練はない。
●孫たち
孫(誠司と芽衣)のビデオ(YOUTUBE)が届いた。
http://youtu.be/1PAtjz0jPsA
送ったプレゼントは無事、届いたようだ。
誠司は「石」に関心をもっている。
芽衣は「料理」に関心をもっている。
この時期、子どもたちは自分の方向性(思考回路)を決定する。
与えるものには、慎重でありたい。
●就寝
今日の総括。
今日は、どうだったか。
一言で表せば、寒い1日だった。
それ以外、印象の薄い1日だった。
とくに成果なし。
平凡な1日。
不完全燃焼感を心の底で押しつぶしながら……、
みなさん、おやすみなさい!
……私たち夫婦は、冬場はいつも、布団乾燥機で布団を暖めながら寝る。
その音が寝室のほうから聞こえてくる……。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教育
評論 はやし浩司 孫 誠司 芽衣 Sage Mae Soichi727 林 宗市 Soichi Hayashi はや
し浩司 2011-12-25)
評論 はやし浩司 孫 誠司 芽衣 Sage Mae Soichi727 林 宗市 Soichi Hayashi はや
し浩司 2011-12-25)
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 27日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page014.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【性欲の奴隷たち】
●クリ○○ス
昨日の中学3年生のK君が、こう聞いた。
「先生、この○の中の字は、何?」と。
見ると、そこに、「クリ○○ス」と書いてあった。
即座に、「(ス)(マ)」と答えると、何やら意味ありげな笑みを浮かべた。
それでピンときた。
この時期の子どもは、24時間のうち、23時間、「SXX」のことを考えている。
(残りの1時間は、眠っている。)
私もそうだったし、あなたもそうだった。
それが悪いというのではない。
それがあるからこそ、私たちは子孫を後世に残すことができる。
しかしその子どもは、自分が性欲の奴隷になっていることには、気づいていない。
●性欲の奴隷
性欲の奴隷なら、奴隷でもよい。
それに気づいているなら、それでよい。
しかし中学生にかぎらず、おとなの私たちにしても、それに気づいている人は少ない。
「私は私」と思い込みながら、奴隷になっている。
奴隷になりながら、それを「私」と思い込んでいる。
意識というのはそういうもの。
自分で築きあげた意識というのもあるには、ある。
0・01%。
1万分の1もない。
99・99%は、作られた意識。
たとえて言うなら、「私」というのは、タマネギのようなもの。
作られた意識で覆われた、タマネギのようなもの。
そこで「私」と思っている部分(皮)をどんどんとめくっていく。
「これでもか」「これでもか」とめくっていく。
が、どこまでめくっても、「私」にたどりつくことはない。
「私」というのは、それほどまでに小さく、頼りない。
●「性的エネルギー」(Ribido)
「性的エネルギー」という言葉を考えたフロイトは、すばらしい。
後にフロイトの弟子のユングは、それを「生的エネルギー」という言葉に置き換える。
どちらであるにせよ、それが生きる原点になっている。
で、最近の脳科学によれば、そうした原点的な信号が、脳下垂体の下部あたりから発せられ
ていることがわかってきた。
ていることがわかってきた。
コンピューターのパルス信号のようなものではないかと、私は勝手に想像している。
その信号が、たとえばドーパミン(欲望と快楽を司るホルモン)の分泌を促したりする。
それが生きる原動力となって働く。
さらに今では、私たちが「感情」と称しているものにしても、ホルモン説、つまり脳内ホルモンに
よって引き起こされるという説は、常識である。
よって引き起こされるという説は、常識である。
つまり脳内ホルモンを軽く考えてはいけない。
この脳内ホルモンこそが、人間を裏から操る。
●「私」
私は鼻先で、「フン」と笑って、その場を去った。
が、それが青春。
この時期の子どもに、「君は性欲の奴隷になっているよ」と諭しても意味はない。
理解することさえ、不可能。
ぜったいに不可能。
その子どもは子どもなりに、それが「私」と思い込んでいる。
思い込みながら、つぎつぎと行動を発展させていく。
恋愛もあるだろう。
結婚もあるだろう。
育児もあるだろう。
その過程で名誉を求めたり、肩書きを求めたりする。
欲望には際限がない。
富や権力を求め、それなりに苦労もするだろう。
そして最後に、こう思う。
「どうだい、私はすばらしいだろう!」と。
●メタ認知能力
だからといって、「性的エネルギー」にせよ、「生的エネルギー」を否定してはいけない。
それがあるからこそ、人生も、これまた楽しい。
男が女を求め、女が男を求める。
そこから無数のドラマが生まれる。
そのドラマが、楽しい。
あえて言うなら、できればその間に一線を引く。
(タマネギの皮)と、(タマネギの芯の私)の間に、一線を引く。
一線を引き、自分を客観的に見る。
これを「メタ認知能力」と言ってよいかどうかは知らない。
しかしこれこそが、まさに「高次(メタ)な認知能力」ということになる。
大切なことは、性欲の奴隷であるにせよ、その奴隷のまま性欲に溺れてはいけないというこ
と。
と。
常に自分を客観的に、醒(さ)めた目で見る。
そういう自分を見失ってはいけない。
私は鼻で「フン」と笑ったとき、そう考えた。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●「精神のメルトダウン」
昨日、「精神のメルトダウン」という言葉を知った。
外国の社会学者が、何かの評論の中で使っていた。
「日本人は、精神的にもメルトダウンしている」と。
ナルホド!
私に欠けるのは、こうした自由な発想。
造語能力。
実にうまい。
的確。
精神的メルトダウン!
たしかに日本人は、精神的にメルトダウンしてしまっている。
日本語的に表現すれば、「もの言わぬ従順な民」に、なりさがってしまっている。
自分で考えない。
自分で行動しない。
自分で責任を取らない。
その前に、そこにある不正、腐敗、矛盾、不公平、不平等に対しても、声をあげようともしな
い。
い。
「だれかが何とかしてくれるだろう」
「何とかなるだろう」と。
そしてその返す刀で、「自分だけ、そこそこによければ、それでいい」と、そこにある問題から
逃げてしまう。
逃げてしまう。
まさに精神のメルトダウン。
実にうまい表現。
昨日、その言葉に感心した。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●静かな早朝
人間はいつものを考えるか。
今朝は布団の中で、そんなこと考えた。
時計を見ると、午前6時。
運動するのも、30分。
そのまま横になっているのも、30分。
今朝の私は、怠け者の30分を選んだ。
周囲はまだ暗かった。
気温は10度前後。
かすかに掛け時計が時を刻む音が聞こえた。
が、それだけ。
静かな朝だった。
2011/12/23朝記
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司※
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●12月21日(TSUTAYAにて)
++++++++++++++++++++++
今夜は久しぶりに、TSUTAYAにやってきた。
車で自宅から、5分ほどの距離。
奥の、左の一角に読書コーナーがある。
400円前後で、コーヒーやココアを飲むこともできる。
そこへ読みたい本を持ち込み、つまり「立ち読み」ならぬ、「座り読み」が、できる。
書籍(雑誌、週刊誌を含む)というのは、そういう商品。
書店は売れなければ、そのまま返本(=返品)できる。
汚れても、折り曲がっても、どうということはない。
出版社へ返本すればよい。
書店にしてみれば、痛くもかゆくもない。
だからこういうサービスができる。
客の私たちにとっては、ありがたいサービス。
新刊書でも何でも、読み放題。
が、その分だけ、心のどこかで何かしらの罪悪感を覚える。
週刊誌2冊で、350+400=750円。
だからこうして、飲みたくもないミルクやコーヒーを買う。
++++++++++++++++++++++
●二日酔い
とりあえず……ということでもってきたのが、週刊誌4冊。
(あとで知ったが、「持ち込みは2冊まで」だ、そうだ。
「週刊文春」と「週刊ポスト」を、おおかた読み終える。
あちこちで、カチンときたが、今夜は、あまりそれについては書きたくない。
今日は朝から二日酔い。
昨夜寝る前に、チューハイ(発泡酒)を一杯飲んだのが、悪かった。
アルコールを飲めない私が、酒を飲む……。
このところ、そんなバカなことばかりしている。
そのツケが、今朝、どっと出た。
今は、できるだけ、精神を安定させたい。
●正面の男
私とワイフは、喫茶コーナーの一番奥に陣取った。
右横は、黄土色の壁。
背中側は、茶色の壁。
左横に、どこかのネームカードをぶらさげた女性が2人、座っている。
学生なのか、たがいに何やら教えあっている。
左前にも、似たような女性が2人、座っている。
ノートを見ると、大腸の絵が、ミミズのように描いてあった。
看護学校の学生か、何かのだろう。
得体のわらからないのが、正面、つまりワイフの背中側に座っている男。
作業帽子を深くかぶり、深いえりのついたジャンパーを着ている。
えりは鼻の下まで届き、顔はほとんど見えない。
芸能雑誌を熱心に読んでいる……というより、ときどき、周囲の動きに目を配っている。
腕時計をしている。
ジーパン。
ジャンパーは、農作業の人が着るような、作業服。
服装とは不似合な、明らかに安物とわかる派手な靴を書いている。
白地に薄い水色の線が、3本。
「何をしている男だろう……?」と。
テーブルの上に、i-podを、これみよがしに置いている。
年齢は、……今、顔をあげたが、30歳くらい。
40歳くらいに見えたが、30歳くらい。
●正面の男(2)
いや、もう1人、いた。
左奥に、小さく体を丸めて、1人の女性がノートに何かを懸命に書き込んでいる。
左前の2人の女性の陰に隠れて、今まで気がつかなかった。
その女性は、本当に勉強しているといったふう。
ただひたすら、ノートに何かを書き込んでいる。
あとの女性は、勉強というより、おしゃべり。
小声だが、それでも雀がさえずるように、ペチャペチャ、クチャクチャ……。
加えてBGMは、すっかりクリスマス・ムード。
ジャス風のクリスマス・ソングが、ずっと流れている。
前の男が席を立った。
うしろ姿を見た。
首から頭にかけ、すっかり禿げあがっているのがわかった。
帽子を深くかぶっている理由が、それでわかった。
手にした雑誌を見ると、それには『flick』と書いてあった。
『flick』?
私の知らない雑誌である。
男は、私の住んでいる世界とは、別の世界に住んでいる。
そう思った。
●DVD
2階が、DVDショップになっている。
私「何か、新しいのを借りたの?」
ワ「メリル・ストリープのと、それに新作を1本、ね」
私「フ~~ン」と。
……その男を見ながら、30年前に亡くなった、今井 修氏(実名)のことを思い出した。
そのとき32、3歳だった。
焼酎とタバコを片手に、いつも原稿を書いていた。
最後に会ったのは、ショッピングセンターの中だった。
一角に小さな椅子が置いてあり、今井 修氏はそこに座っていた。
話しかけても、何も言わなかった。
うつろなまなざしで、宙をぼんやりとながめていた。
あとでわかったことだが、そのとき、今井 修氏は、ホスピスにいた。
そこを抜け出し、そのショッピングセンターへ来ていた。
今井 修氏が食道がんで亡くなったと知ったのは、それから1か月もたたないときのことだっ
た。
た。
私は、今井 修氏ががんだったということも、またホスピスにいたということも知らなかった。
だからそのときは、今井 修氏の態度に少なからず、ショックを受けた。
冷ややかな態度だった。
「どうして怒っているのだろう?」と。
●死に行く人
今までに死に行く人を、何人か見かけてきた。
数年前に亡くなった、大学の同窓生のIK君も、そうだった。
亡くなる、ちょうど2か月前ほどに、街中で偶然、会った。
話しかけたが、やはり私を避けた。
やや強引に、私は近くの時計店に誘ったが、迷惑そうだった。
そのときワイフも横にいた。
ワイフも同じように感じたらしい。
「IKさん、おかしいわね」と。
IK君は、そのあとしばらくして、病院で亡くなった。
直接の死因は肺炎ということだったが、あとで聞くとそのとき、前立腺がんが大腸に転移してい
たという。
たという。
前の席に座った男が、どうこうのと書いているのではない。
その男のもつ、どこか暗い雰囲気が、気になった。
●8時半
ワイフが、こう言った。
「8時半よ……」と。
私「山(=山荘)へ行く?」
ワ「そうね……。頭(=頭痛)治ったの?」
私「うん、まあね……。山でビデオを観るの?」
ワ「時間があればね……」と。
●資料
週刊ポスト誌(2011年12月23日号・P46)には、こうある。
「職業別官民格差」として、一覧表が載っている。
(かっこ)内は、民間平均。
バス運転手 ……526万円(344万円)
自動車運転手……541万円(234万円)
清掃職員 ……604万円(210万円)
守衛 ……548万円(293万円)
福祉施設職員……574万円(289万円)
幼稚園教諭 ……598万円(330万円)
看護師 ……521万円(427万円)
用務員 ……534万円(274万円)
定年退職金……2452万円(2075万円)
(以上、筆者のほうで、1000の位で四捨五入。)
(注:公務員は「地方公務員給与実態調査結果」(総務省・平成22年)、
民間は、「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省・平成22年)による。
「自動車運転手は、公務員は公用車、民間はタクシー。
民間の「清掃職員」は、ビル清掃員をいう。)
週刊ポスト誌は、こう伝える。
「役人という肩書をもつだけで、2倍近い給料を受け取っている」(P47)と。
ほかにも驚くべき事実が、官僚の発言として紹介されていた。
「……知的水準の低い一般国民から、保険料をまきあげる……」
「官僚の出世の条件は……国民からカネを巻き上げて、省益を拡大させること」(以上、ポスト
誌、覆面座談会の席で)と。
誌、覆面座談会の席で)と。
公務員の給料が民間の2倍近くもあるのは、「優秀な人材の確保のため」だそうだ。
また国家公務員と地方公務員の給与格差がほとんどないのは、地方公務員の不満を抑制す
るためだそうだ(ポスト誌)。
るためだそうだ(ポスト誌)。
先にあげた官民格差表でいう「公務員」は、地方公務員の給与をいう。
……こんな日本が、どうして北朝鮮の悪政を笑うことができるだろうか。
●相談
たった今、メールを開くと、こんな相談が届いていた。
【韓国在住のKUさん(母親)より、はやし浩司へ】(一部、文字化け)
【 お子さんの年齢(現在の満年齢) 】:満4歳
【 お子さんの性別(男・女) 】:男
【 家族構成・具体的に…… 】:
父母、姉(10歳。精神遅滞)、祖父、祖母
【 お問い合せ内容】
韓国在住の来月満4歳になる男の子の母子分離不安について相談します。
母子分離不安について検索していると、はやしさんのサイトに行き着き、母子分離不安につい
ての解答を拝見させていただきました。
ての解答を拝見させていただきました。
家の事情もあり、もう少し具体的どうしたらいいか知りたく、メールしています。
上の子は10歳ですが、重度の精神遅滞があり、まだ一人で歩けず、話せません。
1歳前後の状態で、オムツをしています。
激しく泣いたり、物をなめたりかんだり、泣いてもなぜ泣いているのかわからなかったり、一緒
にいてほしかったり、眠いのに眠れなくて、ないていたり、手がかかります。
にいてほしかったり、眠いのに眠れなくて、ないていたり、手がかかります。
下の子が生まれてからも、上のこの障害児保育園(家から遠い)や物理治療などに通うのに私
が連れて行って、その間下の子はおじいちゃんかおばあちゃんと一緒にいました。
が連れて行って、その間下の子はおじいちゃんかおばあちゃんと一緒にいました。
下の子が2歳になった時、上の子が小学校に就学させたのですが、(韓国では親の判断で入
学を遅らせることができる)、小学校の送り迎えや、お昼の食事介助などで手がかかるので、
下の子を保育園に入れました。
学を遅らせることができる)、小学校の送り迎えや、お昼の食事介助などで手がかかるので、
下の子を保育園に入れました。
送るのはおじいちゃんおばあちゃんがしてくれたのですが、あまりにも泣いくので3日ほどで泣く
のが耐えられないとやめさせてしまいました。
のが耐えられないとやめさせてしまいました。
次の年、満3歳になった時再び送ったのですが、やはりおじいちゃんとおばあちゃんがやめさ
せてしまいました。
せてしまいました。
それでも、私があまりにも大変なので、その5月から再び送りました。
今度は時間をやりくりして、私が送りました。
相変わらず泣いていくのですが、保育園の先生の言うとおりがんばって送りました。
2週間ぐらいはお昼ぐらいに帰ってきていました。
しかし、私が顔面神経麻痺にかかってしまい、その後5時まで送っていました。
朝は相変わらず激しく泣いて行き、帰ってくると元気がない、1ヶ月ほど様子を見ていたのです
が、「このこまでおかしくなったらどうする?
が、「このこまでおかしくなったらどうする?
嫌がる子を保育園に送っていって、後で精神科に通っている子もいっぱいいる」など、周りに言
われ心配になり、やめさせました。
われ心配になり、やめさせました。
先生いわく、おじいちゃんおばあちゃんにとってもかわいがられ、甘やかされて育っているので
忍耐力がまだない、とのこと。
忍耐力がまだない、とのこと。
園でも「たいくつだ」と先生に言ってばかりで、友達が寄ってきても遊ぼうとしない、お昼寝もしな
い、そうです。
い、そうです。
姉の事もあって、お母さんをお姉ちゃんに取られるという心配もあるのかも、とも。
3ヶ月まえから・u梛:・・ぢ回の美術の習い事を始めたのですが(美術というより友達を作るた
め)、本来部屋で子供2,3人と先生とでするのですが、子供が離れようとせず、私が部屋の中
の隅で座ってみていないといけません(先生の提案で)。
め)、本来部屋で子供2,3人と先生とでするのですが、子供が離れようとせず、私が部屋の中
の隅で座ってみていないといけません(先生の提案で)。
少しずつ、しばらくしたら部屋の外に出て行けるようにはなったのですが、「窓からずっとみてい
て」とか途中で「お母さんどこ?」と出てきたりします。
て」とか途中で「お母さんどこ?」と出てきたりします。
友達と遊びたい気持ちがあって、同じ教室の女の子のお世話?をしたり、ゆずってあげたり。
お母さんが一緒で子供と遊ぶ機会があればいいのですが。
最近の韓国は、1歳過ぎから保育園に通う子が多く、公園にいっても遊ぶ子がいなく、習い事な
ども夕方の時間しかなく(昼間は子もがいないので)、このまま保育園にいかずうちで過ごすの
もどうなのか悩んでいます。
ども夕方の時間しかなく(昼間は子もがいないので)、このまま保育園にいかずうちで過ごすの
もどうなのか悩んでいます。
月数の少ない48ヶ月までの文化センターなどのクラス(お母さんと一緒にする)はある事はある
ので、同い年ではない、小さい子達と混ざってでも、したらいいのかなぁとも考えています(来年
は保育園に送らないで)。
ので、同い年ではない、小さい子達と混ざってでも、したらいいのかなぁとも考えています(来年
は保育園に送らないで)。
家では、「遊ぼう、遊ぼう」と人形遊びやブロックなど私とやりたがります。
一人ではほとんど遊べません。
私もずっととなると疲れて、いやになります。
休日など公園に行っても、別の人がいると遊ばず、「いなくなるまで待ってる」とただ見ていま
す。
す。
うちに来る私の友達などは割りと問題なくいられるのですが、外で会う知らない人やたまにあう
人には警戒心丸出しで、「嫌いだ、いやだ、あっち行け」などと言います。
人には警戒心丸出しで、「嫌いだ、いやだ、あっち行け」などと言います。
美術の先生にも、です。
朝は上の子を学校に送りに行く時はおじいちゃんかおばあちゃんに見てもらうのですが、おじ
いちゃんがいるとき(一日おきの仕事をしている)は「お母さん、いってらっしゃい」と送ってくw)?
「譴襪里任垢・△、个△舛磴鵑了・蓮◆岼貊錣帽圓・繊廚筏磴い特紊い突茲泙后・發β腓④・
覆辰燭里念貊錣僕茲討發いい里任垢・△、个△舛磴鵑・蹐覆い・蕕醗貊錣帽圓・擦泙擦鵝・・
w)現状をだらだら書いてしまいましたが、サイトに書いてあるように、対人恐怖症というのもあ
ると思います。
いちゃんがいるとき(一日おきの仕事をしている)は「お母さん、いってらっしゃい」と送ってくw)?
「譴襪里任垢・△、个△舛磴鵑了・蓮◆岼貊錣帽圓・繊廚筏磴い特紊い突茲泙后・發β腓④・
覆辰燭里念貊錣僕茲討發いい里任垢・△、个△舛磴鵑・蹐覆い・蕕醗貊錣帽圓・擦泙擦鵝・・
w)現状をだらだら書いてしまいましたが、サイトに書いてあるように、対人恐怖症というのもあ
ると思います。
又、スキンシップも「抱っこ、抱っこ」とせがむ時はしてあげているし、十分にしていると思ってい
るのですが、思っている以上に足りないのでしょうか?
るのですが、思っている以上に足りないのでしょうか?
上の子も家ではけっこう泣くので、この子もみんながストレスを抱えているようです。
八方塞のように感じて、アドバイスいただけるとうれしいです。
(以上、相談より。)
【はやし浩司より、韓国のKUさんへ】
KU様へ
こんばんは!
現在、出先なので、
あとでゆっくりと返事を書きます。
大切なことは、(現実)と闘うことではなく、(現実)を受け入れることです。
「私は私」と居直ることです。
こと子育てについて言えば、闘っても意味はありません。
居直れば、おのずと、道が前に見えてきます。
あとは静かに、その道(流れ)に身を任せてください。
温かい愛情と、生きていく勇気を見失わずに、ね。
あなたの子どもは、今、あなたに何か尊いことを教えるために、そこにいます。
子どもに教えを乞うてください。
あなたはすばらしい人になれますよ。
どうか、自信をもって、前に進んでください。
またあとで返事を書きます。
はやし浩司
●幼稚園教諭 ……598万円(330万円)
さきほどあげた「官民格差」で気になったのが、幼稚園教諭の給料。
公立幼稚園の教諭が、598万円。
私立幼稚園の教諭が、330万円。
本当かな?、と思った。
公立幼稚園の教諭についてではない。
私立幼稚園の教諭についてである。
私が知る範囲では、私立幼稚園の教諭は、330万円も、もらっていない。
月額に換算すると、(12か月で割ると)、27~8万円。
退職金にしても、定年退職時まで勤める教諭は、ほとんどいない。
だから2000万円以上の退職金など、こと私立幼稚園の教諭に関して言えば、ありえない。
どこの幼稚園(私立)でも、人件費は、削るだけ削っている。
まず未婚の若い教諭を、インターン(見習い)の形で雇う。
結婚と同時に退職……というのが、暗黙の了解事項になっている。
相場では、そういう若いインターンは、月額10数万円程度。
(手取りで、月額14~5万円と聞いている。)
ボーナスを入れても、330万円ということは、ありえない。
どこからこんな数字が出てきたのだろう?
公立幼稚園のばあい、ありとあらゆる労働者の権利が認められている。
産休で3年間休職したとしても、職場を失うことはない。
さらにたいていの教諭は、最終的には園長に昇格したあと、退職する。
「幼稚園の先生になるなら、公立の幼稚園」というのは、この世界では常識。
役人の言葉を借りるなら、「知的水準の高い教諭は、公立幼稚園。知的水準の低い教諭は、
私立幼稚園」(「週刊ポスト」誌)ということか。
私立幼稚園」(「週刊ポスト」誌)ということか。
……グググーッと怒りがわいてきたが、今夜はここまで。
もちろん一人一人の役人に責任があるわけではない。
責任を感じてほしいと書いているのでもない。
が、このままでは、日本は本当に沈没してしまう。
怒りというより、私は強い危機感を覚える。
●知的水準?
知的水準とは何か?
あの片山さつき氏は、私の地元で国会議員に当選したあと、東京に戻り、こう言ったという。
「(浜松の)田舎者は、私が土下座すれば、イチコロよ」(雑誌「諸君」)と。
が、こうした差別意識は、何も片山さつき氏だけのものではない。
ある男は、私にこう言った。
某大銀行の部長職をしていた。
「退職したら、君の故郷のM市にでも行き、市長でもしようかな」と。
なぜ、人は、こんな愚かなことを言うようになるのか。
そのルーツをずっとたどっていくと、そこにあの「受験競争」が、見え隠れする。
そういう意味では、意識というのは、恐ろしい。
中学生でも、高校生でも、受験競争に勝った(?)とたん、おかしなエリート意識をもち始める。
「勉強ができる人ほど、優秀」と。
返す刀で、「勉強ができないヤツは、劣等」と。
が、それは待ってほしい。
私はこの40年間、受験生と言われる子どもを指導し、側面から観察してきた。
もちろん中には「優秀な子ども」もいる。
しかしそういう子どもほど、最後の最後まで謙虚さを失わない。
推薦で、一流大学の一流学部へと進学していく。
(学校の先生にも、それがわかるから、推薦される。)
が、すでに小学生のときから、鼻持ちならぬエリート意識をもつ子どもも少なくない。
勉強ができることを鼻にかける。
どうしようもないほどのドラ息子、ドラ娘。
で、ある日私はそんな1人の母親に、こう告げた。
「あのオ~……」と。
すかさずその母親は、私にこう言った。
「あんたは、黙って息子の勉強だけをみてくれればいい。(余計なこと、言うな!)」と。
これは本当にあった話である。
親は、浜松市内でいくつかのパチンコ店を経営していた。
そういうことを経験しているから、「知的水準」という言葉を聞くと、バチバチと頭の中で火花
が飛び散る。
が飛び散る。
いろいろ書きたいことは、山のようにある。
あるが、今夜はここまで。
要は、人も謙虚さを見失ったら、おしまい。……ということ。
●もう1人の男
TSUTAYAで、もう1人、気になった男がいた。
60歳くらいの男だった。
私とワイフがTSUTAYAへ入ったときも、そこにいた。
雑誌を取りに行ったときも、そこにいた。
そのあたりを、ブラブラしていた。
今も、そのあたりにいる。
本を読む気配もなかった。
手に取って読む雰囲気もなかった。
が、私にはすぐわかった。
その男は、ホームレスの男だった。
最近、このタイプの大型店で、このタイプのホームレスの男を、よく見かけるようになった。
今日のように、寒い夜は、さらにそうだ。
●KUさんへ(母子分離不安)
KUさんの子どもを考える。
KUさんは、母子分離不安を心配している。
症状としては、母子分離不安そのもの。
母親がそばにいないと、極度の不安状態になる。
このとき子どもは、2つのタイプに分かれる。
ワーッと攻撃的に泣き叫んで、母親の後を追うタイプ。
オドオドとしてしまい、混乱状態になるタイプ。
症状から私は、前者を「プラス型」、後者を「マイナス型」と呼んでいる。
どちらであるにせよ、子どもの側からみて、「捨てられるのでは?」という恐怖心が、母子分離
不安による症状へと結びついていく。
不安による症状へと結びついていく。
理性ではなく、本能的な部分からの恐怖心であるため、叱ったり説教したりしても意味はない。
子どもの心というのは、環境の変化に対しては、たいへんタフ。
しかし愛情の変化には、たいへんもろい。
母親が数日、入院しただけで、母子分離不安になってしまったケースがある。
遊園地で一度、迷子になっただけで、母子分離不安になってしまったケースがある。
KUさんのように、……というか、通常のケースとは逆なのだが、下の子が生まれたことによっ
て、上の子が母子分離不安になるケースもある。
て、上の子が母子分離不安になるケースもある。
が、KUさんのケースは、もう少し根が深いように考える。
●ユングのシャドウ(影)論
ユングのシャドウ(影)論をもちだすまでもない。
子どもというのは、親の心をそのまま引き継いでしまう。
たとえば親が、Aさんを内心で嫌っていたりすると、その子どももAさんを嫌うようになる。
Bさんを内心でよい人と思っていたりすると、その子どももBさんのことをよい人と思うようにな
る。
る。
こんなことがあった。
もう10年近くも前に書いた原稿に、こんなのがある。
親の心を、そっくりそのまま再現してしまう子どもの話である。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
2000年ごろ、中日新聞出に発表させてもらった原稿である。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●親の心は子どもの心
一人の母親がきて、私にこう言った。「うちの娘(年長児)が、私が思っていることを、そのま
ま口にします。こわくてなりません」と。
ま口にします。こわくてなりません」と。
話を聞くと、こうだ。
お母さんが内心で、同居している義母のことを、「汚い」と思ったとする。
するとその娘が、義母に向かって、「汚いから、あっちへ行っていてよ」と言う。
またお母さんが内心で、突然やってきた客を、「迷惑だ」と思ったとする。
するとその娘が、客に向かって、「こんなとき来るなんて、迷惑でしょ」と言う、など。
昔から日本でも以心伝心という。心でもって心を伝えるという意味だが、濃密な親子関係にあ
るときは、それを望むと望まざるとにかかわらず、心は子どもに伝わってしまう。
るときは、それを望むと望まざるとにかかわらず、心は子どもに伝わってしまう。
子どもは子どもで、親の思いや考えを、そっくりそのまま受け継いでしまう。
こんな簡単なテスト法がある。
まず二枚の紙と鉛筆を用意する。そして親子が、別々の場所で、「山、川、家」を描いてみる。
そしてそれが終わったら、親子の絵を見比べてみる。
そしてそれが終わったら、親子の絵を見比べてみる。
できれば他人の絵とも見比べてみるとよい。
濃密な関係にある親子ほど、実によく似た絵を描く。
二〇~三〇組に一組は、まったく同じ絵を描く。親子というのは、そういうものだ。
こういう例はほかにもある。
たとえば父親が、「女なんて、奴隷のようなものだ」と思っていたとする。するといつしか息子
も、そう思うようになる。
も、そう思うようになる。
あるいは母親が、「この世の中で一番大切なものは、お金だ」と思っていたとする。
すると、子どももそう思うようになる。
つまり子どもの「心」を作るのは親だ、ということ。親の責任は大きい。
かく言う私も、岐阜県の田舎町で育ったためか、人一倍、男尊女卑思想が強い。
……強かった。
「女より風呂はあとに入るな」「女は男の仕事に口出しするな」などなど。
いつも「男は……」「女は……」というものの考え方をしていた。
その後、岐阜を離れ、金沢で学生生活を送り、外国へ出て……、という経験の中で、自分を変
えることはできたが、自分の中に根づいた「心」を変えるのは、容易なことではなかった。
えることはできたが、自分の中に根づいた「心」を変えるのは、容易なことではなかった。
今でも心のどこかにその亡霊のようなものが残っていて、私を苦しめる。
油断していると、つい口に出てしまう。
かたい話になってしまったが、こんなこともあった。
先日、新幹線に乗っていたときのこと。
うしろに座った母と娘がこんな会話を始めた。
「Aさんはいいけど、あの人は三〇歳でドクターになった人よ」
「そうね、Bさんは私大卒だから、出世は見込めないわ」
「やっぱりCさんがいいわ。あの人はK大の医学部で講師をしていた人だから」と。
どうやらどこかの大病院の院長を夫にもつ妻とその娘が、結婚相手を物色していたようだが、
話の内容はともかくも、私は「いい親子だなあ」と思ってしまった。
話の内容はともかくも、私は「いい親子だなあ」と思ってしまった。
呼吸がピタリと合っている。
だから冒頭の母親に対しても、私はこう言った。
「あなたと娘さんは、すばらしい親子関係にありますね。
せっかくそういう関係にあるのですから、あなたはそれを利用して、娘さんの心づくりを考えたら
いい。
いい。
あなたのもつ道徳心や、やさしさ、善良さもすべて、あなたの娘さんに、そっくりそのまま伝える
ことができますよ」と。
ことができますよ」と。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●親の不安
KUさんのケースでは、KUさんが日常的に感じている不安感が、そっくりそのまま子どもに伝
わってしまっている。
わってしまっている。
私はKUさんからのメールを読んだとき、それを最初に感じた。
同時に、もしKUさんの近くに、祖父母がいなかったら、KUさんの子育ては壊れてしまっていた
かもしれない。
かもしれない。
KUさんの必死さを感ずるが故に、近くに祖父母がいて、KUさんの子育てを支援していること
を、私は「よかった」と思った。
を、私は「よかった」と思った。
もちろんKUさんは、そうしているだろうが、こうしたケースでは、けっして祖父母と対立しては
いけない。
いけない。
逆に言うと、祖父母と対立するのではなく、協力しあいながら、KUさんが日常的に感じている
であろう不安感、心配、孤立感と闘う。
であろう不安感、心配、孤立感と闘う。
子どもと闘うのではない。
自分と闘う。
……と書くのは簡単なこと。
私はKUさんからのメールを読んだとき、私自身も、ズシンと心が重くなってしまった。
「顔面神経麻痺」「八方ふさがり」という言葉が、今のKUさんの心情を、そのまま象徴してい
る。
る。
●許して忘れる
昨夜、ワイフは、DVDを観ていた。
メル・ギブソン主演の『復讐捜査線』というタイトルのDVDだった。
娘が暗殺された。
刑事役のメル・ギブソンが、その犯人を追いつめていくというストーリーの映画だった。
その中で、こんなことをだれかが言う。
「子どもがいる悲しみと、子どもがいないさみしさ。あなたはどちらを選ぶか」と。
それに答えて、メル・ギブソンがこう答える。
「子どもがいる悲しみ」と。
記憶によるものなので、まちがっているかもしれない。
が、それには条件がある。
「良好な親子関係」という条件である。
それがなければ、……というより、多くの親たちは、子どもをもったことを後悔する。
「子どもなんか、産まなければよかった」と。
というのも、親というのは、良好な親子関係がある間は、子どもを「許して忘れる」ことができ
る。
る。
そうでなければ、そうでない。
親ばかである自分を恥じ、自分を責める。
子どもを「許して忘れる」ことはできる。
しかし自分を「許して忘れる」ことはできない。
親子関係、つまり子育ての結論は、この一点に集中する。
「良好な親子関係」と。
メル・ギブソンと娘は、良好な親子関係で結ばれていた。
だからこう答えた。
「子どもがいる悲しみのほうがいい」と。
●親ばか
「親ばか」という言葉を使った。
親というのは、子どもを許すことはできても、自分を許すことはできない。
親ばかだった自分を恥じる。
責める。
ついでに口を閉じる。
子どものでき・ふできが問題ではない。
人間性の問題。
世の中には、子どもをだます親は、いくらでもいる。
同時に、親をだます子どもも、また同じほど、いる。
男性や女性をだますのと同じくらい、平気で親をだます。
自分の欲望の追求のために、親を利用する。
そういう子どもをもった親は、子どもを責める前に、自分を責める。
●明日は、かならずやってくる。
KUさんのケースでいえば、八方ふさがりでも、何でもない。
袋小路には入ってはいるが、八方ふさがりではない。
大切なことは、自分の子どもだけを見つめ、その「流れ」の中に身を置くこと。
身を置けば、おのずとその先に、道が見えてくる。
いや、見えてこなくても、今日、そして今、この瞬間できることだけを、懸命にする。
明日は、今日の結果として、かならずやってくる。
世の中、けっして悪い人たちばかりではない。
KUさんが明るく、さわやかに生きていけば、みなもそれに勇気づけられる。
その勇気が希望を生む。
生きる希望を共有することができる。
けっして卑屈になってはいけない。
取り越し苦労や、ヌカ喜びを繰り返してはいけない。
KUさんはKUさんで、ただひたすら前だけを見て、生きていく。
その心が伝わったとき、子どもの心の中からも、不安症状が消える。
●子どもから学ぶ
どんな家庭も、外から見ると、平和で幸福に見える。
が、問題のない子どもはいない。
問題のない家庭も、これまた、ない。
それぞれがみな、重い十字架を背負い、あえぎながら生きている。
KUさんがそうというわけではない。
しかし子どもに何か問題が起きると、みな親はこう思う。
「どうして私だけが……」とか、「どうしてうちの子だけが……」と。
そこで発想を転換してみる。
「子育てというのは、そういうもの」と。
苦労や悲しみは、つきもの。
あって、当たり前。
とたん、気が晴れる。
大切なことは、子どもから学ぶという姿勢。
子どもが泣いているときも、そうだ。
泣くのを「悪」と決めつけてはいけない。
子どもには子どもなりの理由がある。
「あなたも悲しいのね。お母さんも悲しいのよ」と。
すなおに負けを認め、子どもの立場で、いっしょにものを考える。
●帰る
TSUTAYAを出た。
車にエンジンをかけると、猛烈な勢いで、窓ガラスから温風が吹き上げてきた。
自動的にフロントガラスの曇りを消す装置が、働いた。
外気は、9度と表示されている。
寒いというより、冷たい。
私たちは一度、家に戻った。
そのまま山荘へ向かう準備を始めた。
●山荘へ
私「KUさんのこと、どう思う?」
ワ「近くに、祖父母がいて、よかったわね」
私「うん、ぼくもそう思う。KUさんひとりでは、たいへんだ」
ワ「夫は、どうしているのかしら?」
私「ぼくも気になっている。でも、夫については、何も書いてない」
ワ「韓国の人かしら?」
私「たぶんね。韓国では、夫婦別称が、当たり前だし……」と。
「KU」というのは、日本名である。
●コンビニ
途中、コンビニで、遅い夕食を買った。
私は、菓子パン。
ワイフは、日本ソバ。
あと、せんべいなどの菓子類。
……それと近く、修善寺(静岡県伊豆半島の温泉地)で、講演をすることになっている。
その講演が終わったら、修善寺温泉に一泊する。
その宿探しを、雑誌でした。
20冊近い、旅行雑誌が出口のところに並んでいた。
コンビニを出るとき、店員にこう聞いた。
「だめだと思いますが、このページをそこのコピー機で、コピーしてもいいですか」と。
すると店員は、半ばあきれ顔で、「だめです」と。
私「ハハハ、そう言われるとわかっていました。わかっていましたから、聞いてみただけです。
ハハハ」と。
ハハハ」と。
だめに決まっている。
しかしその雑誌だって、売れなければ、返本するだけ。
●母子分離不安
KUさんが今、いちばん先にすべきことは、(すでにしているかもしれないが)、同じ障害をもつ
親同士のネットワークに参加すること。
親同士のネットワークに参加すること。
けっして孤立しないこと。
けっして「私だけが……」と思わないこと。
どういった障害なのかは、メールだけでは、よくわからない。
が、そういった専門のネットワークもあるはず。
今ではネットを使えば、簡単に検索できる。
韓国のことは知らないが、この日本では、そうした子どもへのケアも、かなり充実してきてい
る。
る。
子どもが進むべき道は、けっして一本ではない。
幸福になる道も、けっして一本ではない。
あとは前だけを見て、先にも書いたように、明るく、さわやかに生きていく。
結果として、母子分離不安の問題など、吹き飛んでしまう。
子どもが泣きながら後を追いかけてきたら、KUさんは、やさしく抱いてあげればよい。
あれこれ考えないで、子どもの心になって、子どもと悲しさやさみしさを共有してあげればよい。
それと「甘やかす」ということとは、別。
つまりそうしてあげたからといって、甘やかしたことにはならない。
「甘やかす」というのは、規律のない生活の中で、欲望に溺れさせることをいう。
甘やかしたから、母子分離不安になるというわけではない。
きびしくしたからといって、母子分離不安が治るわけでもない。
●寝支度
昼寝をしたこともある。
時計を見ると、時刻は、午前0時を越えていた。
ワイフは寝支度を始めた。
外はかなり寒いはず。
「明日は、凍っていないだろうか……」と。
水が氷れば、山荘は使い物にならなくなる。
最後に、KUさんへの返事を書くことにした。
【はやし浩司より、KUさんへ】
お気づきのように、これは母子分離不安の問題ではありません。
またそんな問題は、何でもありません。
10人の子どものうち、2~3人が経験する、ありふれた問題です。
だからあまり深刻に考えないこと。
自然体で、子どもに接したらよいでしょう。
それよりも重要なことは、あなたが今、もっているであろう閉塞感、それに基づく、不安や心
配を、どうするかということです。
配を、どうするかということです。
お子さんたちは、それをそっくりそのまま受け継いでいまっています。
『子どもの心は、親の心の鏡』と考えてください。
……と、こんなことを書くと、KUさんは、自分で自分を追い込んでしまうかもしれませんね。
そこでこう考えてみてください。
親になることは、子どもをもつことで、だれでもなれます。
しかし「真の親」となると、そうはいかない。
何度も何度も、絶望のどん底へ叩き落とされながら、親はやがて「真の親」へとなっていきま
す。
す。
私たち夫婦にしても、そうです。
何度も何度も、子育てで行き詰まり、そのつど近くの山に車を走らせ、そこで泣きました。
今でもときどき、泣きます。
運命がどうのこうのと考える前に、人生も残り少なくなってきました。
だったら、もう運命を受け入れるしかない。
最近は、そう考えるようになりました。
「なるようになれ」というよりは、ありのままをさらけ出して、生きる。
どうもがいたところで、これが私の人生。
完璧な人生、完璧な人間関係、完璧な親子関係など、もとから望むべくもない。
孤独死、無縁死、何でも結構。
人に嫌われようが、悪く思われようが、それも構わない。
生まれが生まれですから……。
あとは勇気をもち、足を前に一歩、踏み出す、です。
そこにある問題から逃げるのではなく、2人のすばらしいお子さんといっしょに、前を向き、いっ
しょに歩く。
しょに歩く。
なおどうしても母子分離不安が気になるようでしたら、こうします。
(1)求めてきたときが与えどき……子どもが何かのアクションを求めてきたら、「与えどき」と思
い、すかさず、(すかさず、です。1~2秒も間をおかない)、抱いてあげます。
い、すかさず、(すかさず、です。1~2秒も間をおかない)、抱いてあげます。
力いっぱい抱くのがコツです。
たいてい数秒~10秒前後で、子どもは安心し、満足します。
(2)温かい無視
愛情だけは忘れず、そっと距離を置くようにします。
あなたとあなたのお子さんだけのことを考えます。
他人がどうこう言っても気にしないこと。
先にも書きましたが、そうしたところで、「甘やかす」ということにはなりません。
お子さんは、心底、つらいから泣くのです。
わがままとか、そういうふうに考えてはいけません。
「さみしかったのね?」とお子さんをねぎらいながら、愛情を表現してあげてください。
添い寝、抱っこ、いっしょの入浴など、濃密にしてあげてください。
その年齢がくれば、自然と収まってきます。
少なくとも児童期へ入るころには、症状は消えます。
●就寝
山荘ではいつも、枕元で、香を焚くことにしている。
お気に入りは、「オウピアム」。
名前が恐ろしい。
日本語で、「大麻」!
市販の香で、どこの店でも売っている。
どうか、どうか、誤解のないように。
が、気にはなった。
そこで一度、近くの交番にもっていったことがある。
「こんなのが市販されていますが、だいじょうぶですか?」と。
が、交番の警官は、オウピアムの意味すら、知らなかった。
「調べておきます」と言ったきり、そのままになっている。
それから2年近くになる。
……どうして「オウピアム」という名前がついているのだろう。
本物の大麻のにおいなど、知る由もない。
常識的に考えれば、においだけ似せて作った、偽物ということになる。
だからときどき「大麻って、こんなにおいなのかなあ」と思う。
(本物だったら、事件になるぞ!)
そうそう、その反対のこともある。
欧米人がみな、驚く。
「日本では、覚せい剤を堂々と売っている!」と。
英語で「アシド・ミルク(乳酸飲料)」と言えば、「覚せい剤」を意味する。
車の側面などに、「Acid Milk(乳酸飲料)」と書いてある。
それをみて、欧米人は、みな驚く。
(枕元でオウピアムの香を焚いているからといって、どうか誤解しないでほしい。)
では、今夜は、これでおやすみ。
韓国のKUさん、おやすみなさい。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教育評
論 はやし浩司 母子分離不安 よく泣く子ども 子どもの心は、親の心の鏡)
論 はやし浩司 母子分離不安 よく泣く子ども 子どもの心は、親の心の鏡)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 25日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page013.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【岐阜→関市、ぶらり旅】(はやし浩司 2011-12-18)
<IMG SRC="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000004091/75/img0b273e14zik8zj.
jpeg" width="640" height="480" alt="DSC00105.JPG">
jpeg" width="640" height="480" alt="DSC00105.JPG">
(岐阜市「一兆家」)
●映画『ミッション・インポッシブル』(はやし浩司 2011-12-17)
++++++++++++++++++
今日の午後、映画『ミッション・インポッシブル』を観てきた。
土曜日の午後ということもあり、劇場の後半座席は、ほぼ満員。
トム・クルーズの映画は、いつもそう。
いつも、ほぼ満員。
私も、『トップ・ガン』以来、彼の大ファン。
が、映画そのものは、かなりがっかり。
トム・クルーズの大ファンということで、大甘に採点しても、星は3つの、★★★。
道具仕立ても、チャチ。
随所に無理が見られた。
「?」と思うことも、しばしば。
加えて乱闘シーンが、多すぎた。
昔の「スパイ大作戦(IMF…Impossible Mission Force)」は、もっと知的な仕掛けが多かったよう
に記憶している。
に記憶している。
それがおもしろかった。
が、今回は、ハラハラドキドキ……の連続。
……というか、そういう製作意図が見え見え。
だからがっかり。
高所恐怖症の私でも、ほとんどハラハラしなかった?
直近の前作は、(名前は忘れた)、あまりにも複雑すぎた。
だれがだれなのかさえ、よくわからなかった。
が、今回は、わかりやすかった。
が、内容的には、IMFというよりは、007風?
主役がジェームズ・ボンドであっても、何もおかしくない。
そんな映画だった。
そうそうトム・クルーズも年を取った。
ときどき肌が大写しになった。
そのつど、そう思った。
+++++++++++++++++++++
●自転車の免許制には反対
オーストラリアの話をしよう。
オーストラリアのメルボルン。
大きな道路には、例外なく、自転車道が用意されている。
広い歩道を、歩道と自転車道に分けている。
狭い歩道になると、道路側に線を引き、そこを自転車道にしている。
自動車が(主)か、自転車が(主)か、と聞かれれば、自動車が(主)。
それはそうだが、しかし自転車の存在感も大きい。
道路の随所には、「貸自転車」の看板が立っている。
その横には自転車が5~10台、並べてある。
観光客などは、自由にその自転車を利用し、街中を回る。
きびしいと言えば、規則。
どんな田舎町でも、ヘルメットの着用、前部のライトと、後部の赤いテールランプがないと、自
転車を乗ることができない。
転車を乗ることができない。
つまりそういうことなら、私も納得する。
が、現在のように、自転車の走る道路もない状態で、免許とは?
免許がどうのこうのというより、私たち日本人は、そこまで管理されてよいのか。
管理を許してよいのか。
そういう問題もある。
今ではこの日本は、どこへ行っても、何をしようとしても、許可、認可、資格、免許……。
息苦しいほどまでに、生活そのものが、がんじがらめになっている。
そこで、今度は、自転車の免許?
この話を聞いて思い出すのが、自転車の鑑札制度。
自転車の登録制のことを言ったが、当時は「カンサツ」と呼んでいた。
今から50年ほど前のことだった。
自転車にも、車と同じナンバーが取りつけられた。
そのカンサツのついていない自転車は、強制的に、自転車屋でカンサツを取りつけるように
指導された。
指導された。
大きさは、ハガキの半分くらい。
それを後部の泥除けの上に、特殊な器具を使い、取りつけられた。
当時私は、自転車屋の息子だったが、そんな私にさえ、それがバカげて見えた。
そのバカげたことを、また、政府(官僚)は始めようとしている?
そんな制度を作れば作るほど、天下り先がふえるだけ。
その分だけ、税金がふえるだけ。
「もう、いいかげんにしろ!」と。
私は声を大にして、そう叫びたい。
(付記)
私が小学生のとき、学校で「自転車の乗り方教室」のようなものがあった。
それに参加すると、学校単位の私製の免許証のようなものがもらえた。
●マナーの問題
要するに、マナーの問題。
法律の問題ではない。
そのマナーまで、規則で縛ってはいけない。
そうでなくても、この日本は息苦しい。
官僚国家というのは、そういうもの。
日本がもつ異常性は、外国の人と話してみると、それがよくわかる。
オーストラリアでは、役人が政治家にたてつけば、即、クビ。
アメリカでは、公務員の解雇は日常茶飯事。
給料も「コンビニの店員より低い」(アメリカの友人)。
それに比べて、イギリスでは、官僚制度が進んでいる。
が、日本とはくらべものにならない。
むしろ逆。
規制緩和こそが、日本の社会に活性化をもたらす。
前にも書いたが、あのタイの大洪水のときのこと(2011年)。
何と積み上げられた土嚢の上で、屋台を開いていた人がいたという。
また職を失った16歳の少女は、舟を借り、その舟の上でソーセージを焼いて売っていたという
(報道記事)。
(報道記事)。
今の日本人に欠けるのは、そういう(たくましさ)。
少なくともこの先、日本が外国で生きていくためには、そういう(たくましさ)が必要。
また日本を一歩外に出れば、そういう(たくましい)連中ばかり。
そういう連中を相手に、日本はこの先、どう戦っていくというのか。
多少の不完全さは、享受しようではないか。
不完全さは、私自身で補完していこうではないか。
今では、道路に落ちた街路樹の葉ですら、市の外郭団体(=天下り先)の人たちがやってき
て、清掃している。
て、清掃している。
「日本の公務員数は、欧米並み」というのは、真っ赤なウソ!
文科省だけで、天下り先となっている外郭団体が、2000近くもある。
そういう外郭団体の職員は、もちろん公務員としてカウントされていない。
こうした清掃員のような、準公務員を数に入れたら、さらに多くなる。
道路の落ち葉くらいは、その近所の人たちが清掃すればよい。
●12月18日(岐阜まで、ぶらり旅)
明けて日曜日。
昼を過ぎて、突然、「どこかへ行こうか?」という話になった。
寒いが、空は青い。
白い雲が美しい。
「岐阜へ行こうか」と声をかけると、「うん」とワイフ。
……若いときから、私たちはいつもそうだった。
夜中でも、よくドライブに出かけた。
一泊旅行もよくした。
私たちはそれを、「ぶらり旅」と呼んでいた。
で、岐阜駅の前にある、岐阜キャッスル・インに予約を入れる。
旅支度(じたく)を整える。
ハナ(犬)の餌を、多めに用意する。
いくつかの事務をすませ、いざ出発!
●豊橋へ
浜松から岐阜まで行くには、2つの方法がある。
浜松から豊橋までJRで行き、豊橋から岐阜までは名鉄電車で行く。
もうひとつは岐阜まで、JRで行く。
私はいつも豊橋で名鉄電車に乗り換えている。
シートも快適。
今回も、豊橋から名鉄電車に乗り換える。
その電車の中。
たった今、鷲津駅を通過したところ。
ワイフは家からもってきた新聞に目を通している。
このあたりの紅葉は、今が見ごろ。
遠くの山々が、傾きかけた夕日を浴び、美しく輝いて見える。
●豊橋
豊橋駅のキオスクで、「週刊アスキー」誌と、「徹底予測2012」(日経BP社)を買う。
その「徹底予測2012」を、先ほどまで読む。
こうした旅の楽しみのひとつが、読書。
電車の規則正しい振動を感じながら、読書する。
私にとっては、至極の時。
……ということで、窓の外は、すっかり夕方景色。
橙色の夕日が、真横から注ぎ込んでくる。
家々の壁も橙色。
こうして今日も一日、終わりに近づいてきた。
名鉄電車は、今、名古屋駅を出て、「こうのみや」という駅に向かっている。
車内にそんなアナウンスが流れた。
どんな字だったかな?
電車の前部の表示板に、「次は、国府宮」と出た。
「国府宮」と書いて、「こうのみや」と読む。
岐阜へ来るのは、1年ぶり。
今年のはじめ、伯父が他界した。
たった今、右側に、「稲沢総合文化センター」が見えた。
10年ほど前、そこで講演をさせてもらった。
「ほら!」とワイフに声をかけたときには、すでにうしろへと消えていた。
……で、岐阜から、その先、どこへ行くか。
大垣、関、板取……。
大垣は近すぎる。
板取は遠すぎる。
関には、刃物会館というのがある。
岐阜からはバスで、30分ほど(?)。
午後4時37分に、新岐阜駅に着く。
すぐバスに乗れたとしても、関に着くとしても、午後5時過ぎ。
刃物会館は、もう閉まっているかもしれない。
どうしよう?
腹も減ってきた。
どこかで何かを食べながら、考えよう。
●岐阜
岐阜県は私の生まれ故郷。
郷愁感は、あまりない。
とくに母と兄が他界するまでの20年間は、私にとっては苦痛の20年間だった。
今、やっとその苦痛から解放された。
何も考えず、こうして電車に乗っていられる。
むしろ、そちらのほうが不思議。
仏教の四苦八苦のひとつに、「怨憎会苦(おんぞうえく)」というのがある。
その怨憎会苦を、身をもって体験した。
理由は、今日は書きたくない。
今日は、こうして気楽に岐阜へ行けること。
そのことを、素直に喜びたい。
●関市へ
ホテルでチェックインをすますと、そのまま岐阜バスの乗り場に向かった。
ワイフが、「岐阜の名物は何?」と聞いた。
歩きながら、何だろうと考えた。
昔からアユ料理とか、そういうのは知っているが、岐阜名物というのは知らない。
「味噌かつとか、そんなものかなあ……?」と。
しかしどうして、今、関市に向かっているのか、その理由がわからない。
100%、気まぐれ。
思いつき。
ぶらり旅。
●岐阜から関市へ
バスに乗ると、雨が降り出した。
私「関には、何か名物があるかもしれない」
ワ「うどんとか、ソバ?」
私「う~ん、そういうものしか思いつかないなあ」
ワ「……」
私「計画性がないというのは、よくないね。時間があれば、板取へ向かったのにね」と。
バスは学生時代通いなれた道を、ブォーブォーと大きな音をたてながら走っていた。
あたりの様子は、そのころとほとんど変わっていない。
岐阜市は今、不景気のどん底で、もがいている。
この15年、その状態は、そのまま。
それ以前は、既製服の町として栄えた。
が、今は、見る影もない。
……先ほど案内所で、関までの時間を聞いたら、50分と教えてくれた。
50分!
切符を買ってから、それを知った。
「大垣にすればよかった……」と。
●関の町
関の町には思い出が多い。
子どものころは、何かにつけ、関まで足を運んだ。
今はシャッター街になってしまったというが、そのころは、私には巨大な都市に見えた。
おもちゃ屋にしても、郷里の美濃町のそれの、何倍も大きかった。
その関市には、善光寺という天台宗の寺がある。
その善光寺の地下には、「戒壇巡り」という、地下迷路がある。
全国でも地価迷路があるのは、この寺だけと聞いている。
子どものころ、母とその地価迷路に入ったことがある。
壁を手探りで歩きながら先に進む。
そのとき覚えた恐怖感は、今でも忘れない。
私は、それ以前から、閉所恐怖症だった。
●ぶらり旅
いつか「外出する勇気論」について、書いた。
私の年齢になると、外出すること自体、おっくうになる。
が、それではいけない。
ワイフはいつもこう言う。
「家にいるのも好き。でも、外出するのも、好き」と。
私は「外出するのはおっくう。できれば家の中にいたい。しかし外出するたびに、楽しい」と思
う。
う。
だから「勇気」。
「外出する勇気論」について、書いた。
外出するときはいつも、それなりの勇気が必要。
その勇気を失ったら、死の待合室にまっしぐら!
こうして外出するのも、私にとっては、必死。
一方、ワイフは若いときから、行動派。
こうした(ぶらり旅)を、趣味にしている。
●関の町
それにしても、今回のぶらり旅ほど、目的があいまいなものはない。
それをワイフに話すと、こう言った。
「いいかげんな旅ね」と。
その関の町。
真っ暗だった。
うわさには聞いていたが、シャッター街は、まさにゴーストタウン。
驚いた。
と、同時に、身が詰まるような、さみしさを覚えた。
脳に刻まれた思い出の一部が、欠け落ちたようなさみしさだった。
私とワイフは、その通りを歩いたあと、またバス乗り場へ戻った。
戻って、そこから川沿いに、北のほうに向かった。
小学校と高校の恩師が、そのあたりに住んでいた。
小学校のときは、6年生のときの担任。
その先生が、高校生のとき、家庭科の教師として赴任してきた。
言い忘れたが、女性の先生だった。
温厚で、どこまでもやさしかった。
小学校のときは、市原麗子という名前だった。
高校のときは、結婚して、森 麗子という名前だった。
その先生が結婚したとき、みなで先生の家に遊びに行ったのを覚えている。
が、家は見つからなかった。
暗い夜道で、人通りもなかった。
私とワイフは、そのままもと来た道を通って、バス停まで戻った。
●商店街
私も商店街で、生まれ育った。
だからというわけでもないが、私は「商売」という仕事そのものが、嫌いだった。
プライドなどというものは、どこにもない。
いつも客にペコペコ、ヘラヘラ。
ペコペコ、頭をさげる。
ヘラヘラ、へつらう。
「商売」というのは、基本的には、だましあい。
売る側と買う側の、だましあい。
私はいつもそういう印象をもっていた。
だから、嫌いだった。
……が、そのシャッター街を歩いているとき、そこで店を開いていた人たちの悲鳴が、私には
聞こえた。
聞こえた。
明日は、今日より悪くなる。
来年は、今年より悪くなる。
それを繰り返しながら、一軒、また一軒と、店はシャッターをおろしていく。
それはたとえて言うなら、真綿で首をしめられるようなもの。
ジワジワ、ジワジワ……、と。
私の実家もそうだった。
が、客には、そんな姿は見せられない。
精一杯、虚勢を張り、明るい声で、こう叫ぶ。
「いらっしゃいませ!」と。
以前、こんな原稿を書いた。
この中の『父のうしろ姿』は、中日新聞に載せてもらった。
たいへんな反響があった。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
2000年ごろ書いた原稿より。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●貧乏
私が高校生になるころには、私の家は、まさに火の車。家業は自転車屋だったが、月に、4
~5台も売れればよいほう。ときには、数台ということもあった。
~5台も売れればよいほう。ときには、数台ということもあった。
あとはパンク修理で、何とか、その日を食いつないでいた。が、そのパンク修理とて、毎日あ
ったわけではない。一日の大半は、祖父も、父も、兄も、することもなく、店先と奥を行ったりき
たりしながら、過ごしていた。
ったわけではない。一日の大半は、祖父も、父も、兄も、することもなく、店先と奥を行ったりき
たりしながら、過ごしていた。
祖父は、すでに病気がちで、現役から引退していた。祖母は、二階にあった物干し台ですべ
って腰を打ってからといもの、そのときすでに、寝たきりの状態だった。
って腰を打ってからといもの、そのときすでに、寝たきりの状態だった。
父は、酒を飲みすぎて、すでに肝臓を悪くしていた。兄は、子どものころから、今でいう自閉
症で、そのため、母は、兄を、家の中に閉じこめたままにしていた。
症で、そのため、母は、兄を、家の中に閉じこめたままにしていた。
私にとっても、人生の中で、一番、つらい時期だった。
言い忘れたが、私には、もう1人、姉がいた。5歳年上の姉で、そのときは、G市にある洋裁
学校を卒業し、家の中で、縫製の仕事をしていた。稼ぎは、それほど、多くはなかった。
学校を卒業し、家の中で、縫製の仕事をしていた。稼ぎは、それほど、多くはなかった。
●父の酒乱
貧乏というのは、慢性疾患に似ている。痛みをともなった慢性疾患である。いつ止(や)むとも
なしにつづく。が、それだけではない。よどんだ空気、重苦しい空気、それが口をふさぐ。おま
けにあの独特の臭い。木にしみこんだ、腐った油の臭い。
なしにつづく。が、それだけではない。よどんだ空気、重苦しい空気、それが口をふさぐ。おま
けにあの独特の臭い。木にしみこんだ、腐った油の臭い。
その私は、自転車屋の仕事を、まったく手伝わなかった。手伝おうという気持ちも、起きなか
った。すでにそのとき、私の目から見ても、自転車屋という私の家の商売は、もうどうしようもな
いところまで行ってしまっていた。
った。すでにそのとき、私の目から見ても、自転車屋という私の家の商売は、もうどうしようもな
いところまで行ってしまっていた。
それまでの長いいきさつも、ある。おまけに父は、今でいうアルコール依存症だった。酒を飲
まない日には、借りてきた猫の子のように、静かで、おとなしかったが、酒が口に入ると、様子
が一変した。
まない日には、借りてきた猫の子のように、静かで、おとなしかったが、酒が口に入ると、様子
が一変した。
肝臓を悪くするまで、つまり私が中学3年生くらいまでは、2、3日に一度は、酒を飲み、家の
中で暴れた。
中で暴れた。
ふつうの暴れ方ではない。食卓のテーブルをひっくり返し、障子やガラス戸を、容赦なくこわし
た。父が発する大声や、ものをこわす音は、おそらく近所中に聞こえていただろう。が、私は、
気にしなかった。
た。父が発する大声や、ものをこわす音は、おそらく近所中に聞こえていただろう。が、私は、
気にしなかった。
私の家には、「恥」という言葉すら、もう、なかった。
●大学生に……
私はいつも母に、こうおどされた。「勉強しなければ、自転車屋を継げ」と。しかしその言葉ほ
ど、私にとっては、恐ろしい言葉はなかった。
ど、私にとっては、恐ろしい言葉はなかった。
私はいつしか、あの郷里のM町から逃れ出ることだけを考えていた。「ふるさと」という思い
は、とっくの昔に消えていた。
は、とっくの昔に消えていた。
さらに大学入試が近づくと、母は、こう言い出した。「大学は、国立でないと、行くな。お金がな
い」と。
い」と。
それについては、何も母に言われなくても、よくわかっていた。母は、私が、外に出て行くの
を、何よりも恐れていた。「地元に残って、私のめんどうをみろ」というようなことまでは言わなか
ったが、言われなくも、それが私には、よくわかった。
を、何よりも恐れていた。「地元に残って、私のめんどうをみろ」というようなことまでは言わなか
ったが、言われなくも、それが私には、よくわかった。
具体的には、「産んでやった」「育ててやった」「親の恩を忘れるな」と言った。耳にタコができ
るほど、よく言った。
るほど、よく言った。
その私が、倍率、8・6倍のK大学に合格した。今では考えられないような倍率だが、当時
は、どこの国立大学も、同じようなものだった。私たちの世代は、団塊の世代と呼ばれている。
中学校でのクラス数も、1学年上が、5、6クラス。私たちの学年からは、11クラスもあった。し
かも1クラス、55人前後。まさに寿司詰め!
は、どこの国立大学も、同じようなものだった。私たちの世代は、団塊の世代と呼ばれている。
中学校でのクラス数も、1学年上が、5、6クラス。私たちの学年からは、11クラスもあった。し
かも1クラス、55人前後。まさに寿司詰め!
●仕送りは、1万円だけ
当時、下宿代が、8~9000円前後だったと思う。4年生のときには、1万2000円になって
いた。
いた。
が、実家からの仕送りは、4年間を通して、月に1万円だけ。学費と、足りない分は、アルバ
イトで稼ぐしかなかった。が、試験期間中になると、そのアルバイトもできなかった。私は、朝と
夕に出される下宿の食事だけで、生き延びたこともある。
イトで稼ぐしかなかった。が、試験期間中になると、そのアルバイトもできなかった。私は、朝と
夕に出される下宿の食事だけで、生き延びたこともある。
その1万円も、母は、「頼母子講(たのもしこう)」と呼ばれた、相互金融救済制度をつかっ
て、工面していた。1万円といっても、当時の大卒の初任給が、4~5万円の時代だった。それ
なりの高額であったことには、まちがいない。
て、工面していた。1万円といっても、当時の大卒の初任給が、4~5万円の時代だった。それ
なりの高額であったことには、まちがいない。
こうして私は、大学を卒業するまで、貧乏が当たり前の生活をした。今になってみると、それ
がよかったのか、悪かったのか……。中には、「若いころに、貧乏を経験しておくといい」と言う
人もいるが、その貧乏にも、程度というものがある。それに期間というものがある。
がよかったのか、悪かったのか……。中には、「若いころに、貧乏を経験しておくといい」と言う
人もいるが、その貧乏にも、程度というものがある。それに期間というものがある。
私のばあい、中学生になるころには、「ジリ貧」を感じていた。ジリジリジリと、家が貧乏になっ
ていくのが、私にも、よくわかった。
ていくのが、私にも、よくわかった。
が、父も兄も、なすすべもなく、それに耐えるだけ。祖父は、道楽でオートバイをいじっている
だけ。母は母で、おかしな迷信ばかり信じて、そのときすでに私とは、まったく会話がかみあわ
なかった。今でも家の中には、仏壇のほか、4~5種類の神棚が祭ってある。
だけ。母は母で、おかしな迷信ばかり信じて、そのときすでに私とは、まったく会話がかみあわ
なかった。今でも家の中には、仏壇のほか、4~5種類の神棚が祭ってある。
私のばあい、その期間が長すぎた。多情多感なあの思春期という時代にしてみれば、それは
「一生」と言えるほど、長すぎた。
「一生」と言えるほど、長すぎた。
●実家への仕送り
プライド? そんなものは、どこにもなかった。店は、M町という田舎町だったが、その町の中
心部にあった。その町の中心部で、父は、先にも書いたように、酒を飲み、大声をあげて、暴
れた。
心部にあった。その町の中心部で、父は、先にも書いたように、酒を飲み、大声をあげて、暴
れた。
だれの目にも、私の家が、そういう家であることは、よくわかった。私ができることといえば、
居直って生きるだけ。「今だけだ」と、自分を慰めて、生きるだけ。
居直って生きるだけ。「今だけだ」と、自分を慰めて、生きるだけ。
私は、そんなわけで、あのM町については、今も、「ふるさと」という思いは、まったく、ない。
帰りたいと、思ったこともない。
帰りたいと、思ったこともない。
ただ私が、ワイフと結婚する前から、収入の約半分を、実家へ仕送りをしていたのは、それ
をするのが、私の義務と感じていたからにほかならない。「ふるさとを捨てた」という自責の念が
あったためかもしれない。
をするのが、私の義務と感じていたからにほかならない。「ふるさとを捨てた」という自責の念が
あったためかもしれない。
何も、好きこのんで、そうしていたわけではない。
そういう思いの中で書いたエッセーが、つぎのエッセーである。これは中日新聞に発表した記
事だが、ほかの記事とちがって、大きな反響があった。それを紹介する。
事だが、ほかの記事とちがって、大きな反響があった。それを紹介する。
++++++++++++++++
●父のうしろ姿
私の実家は、昔からの自転車屋とはいえ、私が中学生になるころには、斜陽の一途。私の
父は、ふだんは静かな人だったが、酒を飲むと人が変わった。2、3日おきに近所の酒屋で酒
を飲み、そして暴れた。大声をあげて、ものを投げつけた。
父は、ふだんは静かな人だったが、酒を飲むと人が変わった。2、3日おきに近所の酒屋で酒
を飲み、そして暴れた。大声をあげて、ものを投げつけた。
そんなわけで私には、つらい毎日だった。プライドはズタズタにされた。友人と一緒に学校から
帰ってくるときも、家が近づくと、あれこれと口実を作っては、その友人と別れた。父はよく酒を
飲んでフラフラと通りを歩いていた。それを友人に見せることは、私にはできなかった。
帰ってくるときも、家が近づくと、あれこれと口実を作っては、その友人と別れた。父はよく酒を
飲んでフラフラと通りを歩いていた。それを友人に見せることは、私にはできなかった。
その私も52歳。1人、2人と息子を送り出し、今は三男が、高校3年生になった。のんきな子
どもだ。受験も押し迫っているというのに、友だちを20人も呼んで、パーティを開くという。「が
んばろう会だ」という。
どもだ。受験も押し迫っているというのに、友だちを20人も呼んで、パーティを開くという。「が
んばろう会だ」という。
土曜日の午後で、私と女房は、三男のために台所を片づけた。片づけながら、ふと三男にこう
聞いた。「お前は、このうちに友だちを呼んでも、恥ずかしくないか」と。
聞いた。「お前は、このうちに友だちを呼んでも、恥ずかしくないか」と。
すると三男は、「どうして?」と聞いた。理由など言っても、三男には理解できないだろう。私に
は私なりのわだかまりがある。私は高校生のとき、そういうことをしたくても、できなかった。友
だちの家に行っても、いつも肩身の狭い思いをしていた。
は私なりのわだかまりがある。私は高校生のとき、そういうことをしたくても、できなかった。友
だちの家に行っても、いつも肩身の狭い思いをしていた。
「今度、はやしの家で集まろう」と言われたら、私は何と答えればよいのだ。父が壊した障子の
さんや、ふすまの戸を、どうやって隠せばよいのだ。
さんや、ふすまの戸を、どうやって隠せばよいのだ。
私は父をうらんだ。父は私が30歳になる少し前に死んだが、涙は出なかった。母ですら、ど
こか生き生きとして見えた。ただ姉だけは、さめざめと泣いていた。私にはそれが奇異な感じ
がした。が、その思いは、私の年齢とともに変わってきた。
こか生き生きとして見えた。ただ姉だけは、さめざめと泣いていた。私にはそれが奇異な感じ
がした。が、その思いは、私の年齢とともに変わってきた。
40歳を過ぎるころになると、その当時の父の悲しみや苦しみが、理解できるようになった。商
売べたの父。いや、父だって必死だった。近くに大型スーパーができたときも、父は「Jストアよ
りも安いものもあります」と、どこかしら的はずれな広告を、店先のガラス戸に張りつけていた。
売べたの父。いや、父だって必死だった。近くに大型スーパーができたときも、父は「Jストアよ
りも安いものもあります」と、どこかしら的はずれな広告を、店先のガラス戸に張りつけていた。
「よそで買った自転車でも、パンクの修理をさせていただきます」という広告を張りつけたことも
ある。しかもそのJストアに自転車を並べていたのが、父の実弟、つまり私の叔父だった。
ある。しかもそのJストアに自転車を並べていたのが、父の実弟、つまり私の叔父だった。
叔父は父とは違って、商売がうまかった。父は口にこそ出さなかったが、よほどくやしかったの
だろう。戦争の後遺症もあった。父はますます酒に溺れていった。
だろう。戦争の後遺症もあった。父はますます酒に溺れていった。
同じ親でありながら、父親は孤独な存在だ。前を向いて走ることだけを求められる。だからう
しろが見えない。見えないから、子どもたちの心がわからない。ある日気がついてみたら、うし
ろには誰もいない。そんなことも多い。
しろが見えない。見えないから、子どもたちの心がわからない。ある日気がついてみたら、うし
ろには誰もいない。そんなことも多い。
ただ私のばあい、孤独の耐え方を知っている。父がそれを教えてくれた。客がいない日は、い
つも父は丸い火鉢に身をかがめて、暖をとっていた。あるいは油で汚れた作業台に向かって、
黙々と何かを書いていた。そのときの父の気持ちを思いやると、今、私が感じている孤独な
ど、何でもない。
つも父は丸い火鉢に身をかがめて、暖をとっていた。あるいは油で汚れた作業台に向かって、
黙々と何かを書いていた。そのときの父の気持ちを思いやると、今、私が感じている孤独な
ど、何でもない。
私と女房は、その夜は家を離れることにした。私たちがいないほうが、三男も気が楽だろう。
いそいそと身じたくを整えていると、三男がうしろから、ふとこう言った。
いそいそと身じたくを整えていると、三男がうしろから、ふとこう言った。
「パパ、ありがとう」と。
そのとき私はどこかで、死んだ父が、ニコッと笑ったような気がした。
+++++++++++++++++
この中で、「叔父が……」という話を書いた。これについて、その叔父の息子、つまり従兄弟
(いとこ)から、「Jストアに店を出したのは、父ではない。このぼくだ。(だから父のことを悪く書
かないでほしい)」という、抗議の電話をもらった。
(いとこ)から、「Jストアに店を出したのは、父ではない。このぼくだ。(だから父のことを悪く書
かないでほしい)」という、抗議の電話をもらった。
それについては、私は知らなかった。叔父といっても、私にとっては、父親のような存在だっ
たから、悪口を書いたという思いは、私にはなかった。
たから、悪口を書いたという思いは、私にはなかった。
それに私は子どものころから、商売というのは、そういうものだと、わかっていた。勝った、負
けたは当たり前。負けたからといって、どうと思うこともないし、私は、何とも思わなかった。つま
り叔父をうらんだことは、一度も、ない。
けたは当たり前。負けたからといって、どうと思うこともないし、私は、何とも思わなかった。つま
り叔父をうらんだことは、一度も、ない。
それに勝ったと思ったところで、そんな思いは、長くても、1世代もつづかない。今度は、自分
が、だれかに追われる立場になる。あとは、その繰りかえし。
が、だれかに追われる立場になる。あとは、その繰りかえし。
●貧乏という心のキズ
そんなわけで、私の心には、無数のキズがついている。貧乏という、キズである。そのキズ
が、具体的に形となって現れているのが、今の私の不安神経症ではないか? いつも何かに
追われているという強迫観念、それが、心のどこかにある。
が、具体的に形となって現れているのが、今の私の不安神経症ではないか? いつも何かに
追われているという強迫観念、それが、心のどこかにある。
悪夢も、よく見る。
たいていはどこかの旅先にいて、そこでバスや電車に乗り遅れるという夢である。あるいはホ
テルで荷物の整理をしているうちに、刻々と時間だけが過ぎていく。そんな夢である。
テルで荷物の整理をしているうちに、刻々と時間だけが過ぎていく。そんな夢である。
で、おそらく私は、死ぬまで、そういう夢から解放されることはないだろう。だからといって、そ
ういう自分の過去を、うらんでいるというわけではない。そののち、いろいろな人と会った。知り
あった。
ういう自分の過去を、うらんでいるというわけではない。そののち、いろいろな人と会った。知り
あった。
そういう経験を通してみると、ほとんどの人が、形や内容こそちがえ、みな、何らかの心のキ
ズをもっている。心のキズをもっていない人はいない。そしてそれぞれの人が、そのキズを背
負いながら、懸命に生きている。それがわかった。
ズをもっている。心のキズをもっていない人はいない。そしてそれぞれの人が、そのキズを背
負いながら、懸命に生きている。それがわかった。
こうした私の過去は、決して私だけのものではない。むしろ、私など、まだ幸福なほうだった
かもしれない。
かもしれない。
そのあと、今のワイフに恵まれた。3人の健康な息子たちにも恵まれた。結婚してからは、そ
れほどぜいたくな生活はできなかったが、ほどほどに、自分の人生を楽しむことができた。今
も、こうして自分の人生を、思う存分、楽しんでいる。
れほどぜいたくな生活はできなかったが、ほどほどに、自分の人生を楽しむことができた。今
も、こうして自分の人生を、思う存分、楽しんでいる。
が、ひとつだけ言えることは、私がしたような経験は、私、ひとりでたくさん。息子たちには、そ
ういう思いだけは、させたくないということ。今も、そのつもりで、がんばっている。
ういう思いだけは、させたくないということ。今も、そのつもりで、がんばっている。
そういう私を知ってか知らずか、息子の1人は、よくこう言う。「パパは、何でも、お金で解決し
ようとする」と。
ようとする」と。
私は、そう言われたとき、ふとこう思う。「何を、生意気なことを! 私の気持ちを話したところ
で、お前たちに、理解できるものか!」と。
で、お前たちに、理解できるものか!」と。
しかしその(思い)を伝えたくて、今朝、このエッセーを書いた。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司 私の
過去 過去 貧乏論 岐阜県関市 関の町 はやし浩司 岐阜県 関 シャッター街 シャッタ
ー通り 父のうしろ姿 Jストア Jストアより安い 関市本町通り はやし浩司 森 麗子先生
市原麗子先生)
過去 過去 貧乏論 岐阜県関市 関の町 はやし浩司 岐阜県 関 シャッター街 シャッタ
ー通り 父のうしろ姿 Jストア Jストアより安い 関市本町通り はやし浩司 森 麗子先生
市原麗子先生)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●再び岐阜の町へ
関市では、30分ほど、過ごした。
で、そのまま再び、岐阜の町へ。
「お城が見える」とワイフ。
見ると、山の上に城が見えた。
とたんうしろから、岐阜弁が飛び込んできた。
「やっとかめやなア~、~~しちょったんやけどオ~」と。
「やっとかめやなア~」というのは、「お久しぶりですね」という意味。
「~~しちょったんやけどオ~」というのは、「~~していたのですが」という意味。
若いころは、岐阜弁にあこがれた。
私の郷里の美濃町の方言とは比較にならないほど、都会的に聞こえた。
が、今はその岐阜弁も、地方の田舎の言葉に聞こえる。
だからといって遠州弁が都会的というのではない。
東京の人たちが聞くと、かなり田舎の言葉に聞こえるらしい。
いつか、ワイフがそう言っていた。
ワイフは、一時期、東京で仕事をしていたことがある。
●一兆家
岐阜駅へ着くと、夕食屋をさがした。
ホテルのフロントで聞くと、「郵便局の前の~~家がおいしいですよ」と。
それでそこへ行くと、「本日は休業」の看板。
しかたないので、ぐるりと駅前(名鉄新岐阜駅)のほうに回った。
そこで見つけたのが、「一兆家」というラーメン店。
「ゆず塩らーめん」と書いた看板が、大きく目にとまった。
温もりのあるレタリングが気に入った。
で、私はその「ゆず塩らーめん」とネギ丼、ワイフはギョーザとチャーシュー丼を注文。
が、これがおいしかった!
星は文句なしの、5つ星、★★★★★。
私はラーメンの最後の一滴まで、飲み干した。
場所は、名鉄新岐阜駅から郵便局の方面へ向かった、北側の角。
1号店と2号店が並んで営業している。
私たちが入ったのは、1号店のほうだが、本気度、満点。
店は狭いが、その狭さが、たまらなくノスタルジック。
代金を払うとき、「おいしかったです」と一声かけると、若い店員は、うれしそうに笑った。
一兆家、ゆず塩らーめん、ぜひ、一度、ご賞味あれ!
チャーシュー丼も、これまたお勧め。
●岐阜キャッスルイン・ホテル
実は、以前、このホテルに泊まろうとしたことがある。
若いころで、懐(ふところ)に余裕がなかった。
それでこのホテルに泊まるのを、断念。
そんな思いが、心のどこかに残っていた。
つまり断念したという無念さが、どこかに残っていた。
が、今夜、その仇討(あだうち)をした。……というほど大げさなものではない。
ないが、このところ、そういうものの考え方をすることが多くなった。
人生も残り少ない。
やり残したことを、つぎつぎと実行していく。
それが最近の私の生き様にもなっている。
岐阜キャッスルイン・ホテル。
清潔でモダン。
ビジネスホテルとしては、上級クラス。
満足度、Aaa(ムーディーズ評価法)。
とくに布団、シーツが清潔。
布団は羽根布団。
枕は低反発。
サラサラとした肌触りで、気持ちよい。
今夜は、よく眠られそう。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教育評
論 はやし浩司 一兆家 ゆず塩らーめん 岐阜駅 新岐阜駅)
論 はやし浩司 一兆家 ゆず塩らーめん 岐阜駅 新岐阜駅)
●団塊の世代
今日、電車の中で、ワイフとこんな会話をした。
団塊の世代……バイキングでは、いつも食べすぎる。
団塊の世代……拾ったサイフは、自分のもの。(一般論)
団塊の世代……料理屋ではいつも、座席を2人分取る。
団塊の世代……温泉では、1泊する間に、3回、入浴する。
団塊の世代……蟹とエビに、目がない。
団塊の世代……ぜいたくをすることに、罪悪感を覚える。
団塊の世代……負けず嫌いでがんばり屋。
ほかにもいろいろある。
一言で表現すれば、団塊の世代は、たくましい。
●就寝
ぶらり旅は、よい運動になる。
今日も、時間にすれば、2~3時間は歩いた。
距離にすれば、10キロ前後か。
このホテルには、大浴場はない。
残念!
ということで、先ほど、内風呂でゆっくり、体を休めた。
ほどよい睡魔。
ほどよい疲労感。
それにほどよいワインの酔い。
そろそろ就寝タイム。
ワイフは、洗面所で寝支度をしている。
私は今日最後の、メールチェック。
明日は、朝一で、帰宅。
午前7時にホテルを出れば、9時には、自宅へ戻れるはず。
ではみなさん、おやすみなさい。
●午前3時起き
が、午前3時に目が覚めてしまった。
軽い頭痛。
久々の二日酔い(?)。
夕食後に飲んだ、ワイン。
あれがよくなかった。
しばらくそのままでいると、ワイフが大きく寝返りを打った。
「頭が痛い……」と漏らすと、「私も……」と。
小瓶で500円前後だった。
「安物のワインは、よくないね」と、私。
部屋はエアコンで乾燥していた。
のどもガラガラだった。
ワイフは加湿器を取り出し、それに水を入れ、電源をつないだ。
●ラッシュアワー
しばらく起きていよう……ということで、今、この文章を書いている。
こういうときは、自然体。
自然体がいちばん。
私「明日は、始発で帰ろうか」
ワ「そうねエ」と。
さっそくネットで時刻表を検索。
始発で帰れば、9時前には、自宅へ戻れる。
それがわかった。
私「5時53分の特急がある」
ワ「まだ暗いうちね……」と。
名鉄電車は、ラッシュアワーに重なると、たいへん。
東京の山手線程度に、混む。
それを避けなければならない。
その前に帰るか、そのあとに帰るか。
私たちはその前に帰ることにした。
●GDPで、20位以下
日本が経済大国という話は、遠い昔の話。
現在、1人当たりのGDPでは、世界で17位(2010年)。
2011年(今年)は、20位以下にさがっているという。
全体としては、世界第3位をかろうじてキープしているが、1人当たりでは20位!
今はまだ円高だからいようなもの。
円安に向かえば、さらに順位はさがる。
わかりやすく言えば、日本という国が、それだけ貧乏になっているということ。
給料はあがらず、(……実際には、さがっている)、経済も活力を失った。
未来も、お先真っ暗。
国の債務(債務負担)も、1000兆円を超えた。
地方の債務も含めると、さらに多くなる。
EUの金融危機が収束したあとは、この日本。
日本が金融危機に、陥る。
●『徹底予測2012』(日経ビジネス)
『徹底予測2012』(日経ビジネス)に、こんな興味深い一文が載っていた。
いわく「世界経済の勢力図は、産業革命前に戻る」と。
つづいて、こうある。
「18世紀の産業革命以前、世界のGDPの過半を占めていたのは、中国とインドだった。その
後、世界の覇権はイギリス、アメリカへと移ったが、中国とインドが急成長中。2050年には、
産業革命前の姿に戻る」(P11)と。
後、世界の覇権はイギリス、アメリカへと移ったが、中国とインドが急成長中。2050年には、
産業革命前の姿に戻る」(P11)と。
今、世界はその流れに沿って、動き始めている。
アメリカは別として、イギリス、つまりEUは、この先どうもがいても、衰退する。
とても残念なことだが、この日本は、その前に消えてなくなる。
同誌10Pには、こうある。
「日本は少子高齢化の最先端を行く」と。
つまりあと10年もすれば、団塊の世代が後期高齢者になる。
そうなれば、1・2人の実労働者が、1人の後期高齢者を支えることになる。
が、そんなことは常識で考えても、不可能。
現在ですらも貧弱な老人福祉だが、それがさらにひどくなる。
……というか、壊滅状態になる。
(データ:2020年には、全世帯の34・4%が、1人暮らしになる。
2025年には、人口の30%超が、65歳以上になる。……以上、『徹底予測2012年』より。)
●老人福祉の不公平
それにしても最近、目に余るのが、老人福祉の不公平。
福祉を受けられる人は、徹底的に手厚い福祉(=保護)を受けられる。
そうでない人は、そうでない。
たとえば知人(近所)の隣人は、夫婦2人。
ともに80歳前後だそうだが、ふだんは介護など必要がないほど、元気。
近くの有料老人ホームにも、入居している。
ところがどこでどう介護度をごまかしたのかは知らないが、週2~3回の訪問介護を受けてい
る。
る。
で、その訪問介護のある日だけ、自宅に戻る。
動けないフリをしている(?)。
午前10時ごろ訪問介護士がやってくる。
掃除、洗濯、料理をすます。
午後3時ごろ、訪問介護士は帰る。
そのころ、その夫婦は外へ出て、庭いじり。
それが終わると、夜は有料老人ホームへ。
近所の知人は、こう言う。
「ああいう老人がいるのを知ると、矛盾を感じます」と。
つまりその知人の隣人は、訪問介護士を、自宅管理に利用している……ということになる。
今、こうした不公平が、あちこちで起きている。
●なすすべもなく……
そこにヒタヒタと押し寄せてくる、大洪水の兆候。
しかし私たちはその現実を、見て見ぬフリをしながら、それをやり過ごそうとしている。
「何とかなるだろう」「どうにかなるだろう」と。
その前に、どうにもならない。
心配したところで、どうにもならない。
この虚脱感、プラス不安感。
それを救うのが「教育」ということになるが、教育というのは、常に20年後をみて組み立てる。
その視点すら、この日本には、ない。
相も変わらず、従順でおとなしい子どもほど、「いい子」となっている。
相も変わらず、50年前の教育を繰り返している。
それがわからなければ、どうか私のYOUTUBEをのぞいてみてほしい。
(http://bwopenclass.ninja-web.net/page018.html)
小学1年生だって、方程式だって、負の数だって、分数だって、理解できる。
小数だって、対象図形だって、グラフだって、理解できる。
教えられる。
さらに皮肉なことがある。
私はこうした教育をYOUTUBEで公開しているが、日本人によるアクセス数と同じくらい最近
ふえてきたのが、韓国、台湾からのアクセス。
ふえてきたのが、韓国、台湾からのアクセス。
本当は日本人にもっと見てほしい。
が、肝心の日本人は、安穏の上に、あぐらをかいている。
こんな時代になっても、「英語教育は不要」「コンピューター教育は不要」と。
そういう意見ばかりが、ハバをきかせ、大通りをかっ歩している!
愚痴になるが、(実際、愚痴だが……)、1980年には、日本は電子立国をめざすべきだっ
た。
た。
あのころ先陣を切っていたら、今ごろ日本は、コンピューターの分野で、世界の覇者として君臨
していたはず。
していたはず。
が、田中角栄には、その知力はなかった。
列島改造論を唱え、土建業に邁進した。
その結果が今。
ほとんど車が走らないような林道さえも、オーストラリアのハイウェイ並みに整備されている。
「公」の名をもつ会館は、どこも、超の上に超がつくほど、立派。
豪華。
アメリカのカーネギーホール(ニューヨークにあるMusic Hall)より、豪華。
カーネギーホールは、古ぼけた4~5階建の建物。
作るのは簡単。
建てるのは簡単。
今、地方自治体は、その維持費で苦しんでいる。
なすすべもなく……。
●さて、帰り支度
今、時刻は、5時17分。
5時53分の始発まで、あと30分と少し。
帰り支度を始める。
2011年12月19日、朝。
みなさん、おはようございます。
●名鉄電車の中で
1号車(指定席)の客は、私たち夫婦だけ。
貸し切り電車。
もうすぐ名古屋だが、窓の外は真っ暗。
今日は雨。
これは予想していなかった。
●ぶらり旅
今回のぶらり旅で印象的だったのは、やはり関市、「関の町」。
うわさには聞いていたが、シャッター街が、これほどまでに凄まじいものとは、知らなかった。
同時に、関市へ入る街道筋の変化。
大型店舗が、ズラリと並んでいた。
浜松で見る、ファースト・フードの店も、すべて並んでいた。
「ガスト」「吉野家」「マック」などの馴染み店のほか、「ジョイフル」「はま寿司」「かつや」「かっぱ
寿司」などなど。
寿司」などなど。
関市としては、苦渋の選択だったかもしれない。
市内の旧商店街を犠牲にし、郊外に大型店を誘致した。
そこに大型店が並べば、周辺の市町村の客も呼び込める。
全体としてみれば、税収はふえる。
しかしこんな状況も、長くはつづかない。
この先、大型店どうしの競争は、さらに熾烈さをます。
全国規模のファースト・フード・チェーン店も、低価格競争で、そのうち何割かが消えるだろうと
言われている。
言われている。
鍵は、いかにサロン風にし、女性客を呼び込めるかという点にあるそうだ(「徹底予測201
2」)。
2」)。
浜松だけに住んでいると、その変化はわからない。
子どものころよく知っていた町へ行くと、その変化がよくわかる。
今回のぶらり旅の成果は、それを肌で感ずることができたこと。
●名古屋
電車は今、名古屋駅の構内へと進んでいる。
速度を落とし、信号待ちをしているよう。
並行して走る新幹線は、動きを止めている。
たぶん名古屋始発の新幹線なのだろう。
横のワイフは、目を閉じ、静かに休んでいる。
先ほどまで、「日本が5位に転落?」と驚いていた。
日本の自動車産業は、世界5位(生産台数)に転落する。
それを読んで、驚いていた。
今にして思うと、1970年代がなつかしい。
あのころは、日本中が輝いていた。
何をやっても、押せ押せムード。
私たち団塊の世代が、その先陣を切った。
が、ここで日本が終わるわけではない。
終わらせてはいけない。
「では、どうするか?」と。
今回のEUの金融危機の最中にあっても、スウェーデンやフィンランドは、きわめて安定的な
経済運営をしている。
経済運営をしている。
もし日本がモデルにする国があるとすれば、(官僚や役人はいやがるだろうが)、スェーデンや
フィンランドということになる。
フィンランドということになる。
●行政改革
現在のように、日本が稼ぐ外貨のほとんどが、公務員と準公務員の人件費に消えていくという
のは、どう考えても尋常ではない。
のは、どう考えても尋常ではない。
もちろんひとりひとりの公務員の人たちに、責任があるというのではない。
しかし行政改革(=官僚制度の是正)は、もう待ったなし。
この先、日本人の平均余命は、2020年以後、毎年1年ずつ上昇していく。
公務員だけが豊かな年金を死ぬまでもらえるというのは、どう考えてもおかしい。
そのおかしさを正さないかぎり、日本に未来はない。
さらに言えば、「教育」。
「人材」。
人材教育をどうするか。
●ハーバード大学
先日、私の教え子(女性)が、ハーバード大学へ入ったことを知った。
現在は2つの博士号をものにし、同大学の医学部で、医局をもっているという。
東大や京大では驚かなくなった私だが、「ハーバード」という名前には驚いた。
母親はこう言った。
「あの子は、子どものころから負けん気が強くて……」と。
そう、その「負けん気」を育てるのが、幼児教育ということになる。
(多分に手前味噌的で、申し訳ないが……。)
そのあたりから、日本の教育を見なしていく。
先に書いたことの繰り返しになるが、総じてみても、日本の子どもたちは、キバを抜かれたよ
うな子どもたちばかり。
うな子どもたちばかり。
むしろこの日本では、キバのある子どもを、「できの悪い子」と位置づけてしまう。
こんなこともあった。
もう10年ほど前になるだろうか。
私が「日本ではシャイな子どもほど、いい子となっている」と言ったら、相手のアメリカ人の女性
(小学校の校長)は、心底、驚いていた。
(小学校の校長)は、心底、驚いていた。
「シャイな子ども」は、アメリカでは、AD・HD児や、LD児と並んで、問題児に位置づけられてい
る、と。
る、と。
小児うつ病の診断基準のひとつにもなっている。
●もうすぐ豊橋
名残惜しいが、もうすぐ豊橋。
今回の(ぶらり旅)も、これでおしまい。
窓の外は、美しい朝焼け。
茜色のちぎれた雲の間から、黄金色の太陽が輝いている。
はやし浩司 2011-12-19朝記。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教育
評論 はやし浩司 ぶらり旅 はやし浩司 行政改革 平均余命 日本の凋落)
評論 はやし浩司 ぶらり旅 はやし浩司 行政改革 平均余命 日本の凋落)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2011年 1月 23日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page012.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今週から、数の勉強】(年長児)「1~100までの数」
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/07BdcShDEVo"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/_Qezw3GDbOA"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/_PL2yeaHOko"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hiroshi Hayashi+++++Dec.2011+++++はやし浩司
●宇宙人との接近遭遇(冬の夜のロマン、2011年版)
+++++++++++++++++++++
先日、義兄と会ったときのこと。
義兄が、おもしろいことを言った。
「もしね、浩司君、ぼくがね、宇宙人に会ったら、
宇宙船(UFO)を一機、もらえないかと頼んでみるよ。
でね、もらえたら、その宇宙船の構造を徹底的に分析し、
同じものを作るよ。
その技術を、いろいろなものに応用する。
でもね、その技術は、ぜったいに外国には渡さない。
日本だけのものにするよ」と。
++++++++++++++++++++
●「猿の惑星」
「猿の惑星」という映画があった。
あの映画の中の猿は、人間と同等か、それ以上に知恵もあり、賢い。
が、それでも私は、猿の惑星には住みたくない。
「王様にしてやるから、どうか?」と誘われても、断る。
あんな猿たちの上に、最高権力者として君臨したからといって、それがどうだというのか。
何が、楽しいのか。
●野生の猿
もう少し現実的な話をしよう。
私の山荘の近くに、野性の猿が出没するようになって、もう10年になる。
奥のほうで第二東名の建設が進んでいる。
そこから逃げてきた猿たちである。
20~30匹が1つの群れをつくり、その群れが、数組ある。
ときどき群れどうしが、はげしく対立することもある。
あの猿。
山荘のすぐ下の道にまで来る。
が、私たちの姿を見ても、逃げようともしない。
ふてぶてしいというか、堂々としているというか……。
で、あの猿を見ていると、ときどき猿が人間に見えてくるときがある。
しぐさも、表情も、人間そっくり。
反対に人間のほうが、猿に似ていると感ずることもある。
で、そんなとき、ときどき同じことを考える。
猿がある日私のところへやってきて、こう言ったとする。
「林さん、どうか私たちのリーダーになってくれ」と。
……私は、その申し出を、即座に断るだろう。
●猿の世界
猿の世界にも、序列があるらしい。
私にはよくわからないが、研究者の話によれば、ボス猿がいて、一群を率いているという。
で、そのボス猿。
猿の世界でも、威張っているらしい。
たとえばミカンの木を独占するとか……。
メス猿をすべて自分の妻にするとか……。
人間の私から見れば、バカげた世界だが、猿どうしは、そんなふうには考えていない。
逆に、人間の世界をながめてみれば、それがよくわかる。
●権力者
権力者と呼ばれる人がいる。
独裁国家の「長」を思い浮かべれば、よい。
そういう人は、その国のありとあらゆる富を独占する。
で、そういう権力者は権力者で、結構、得意になっているのかもしれない。
「オレが一番、偉いんだ」と。
私にはそういう感覚は理解できない。
が、国家の最高権力者にでもなると、自分が神になったような気分になるらしい。
事実、神のように振る舞う最高権力もいる。
●宇宙人→人間→猿
そこで宇宙人。
宇宙人に登場してもらう。
上下関係で考えるなら、(宇宙人)が(人間)の上。
(猿)が(人間)の下。
並べると、(宇宙人)→(人間)→(猿)ということになる。
つまり宇宙人にすれば、私たち人間を見る目は、ちょうど私たち人間が猿を見る目と同じで
はないかということ。
はないかということ。
で、たとえば宇宙人にこう頼んでみる。
「人間という生物は争いばかりしています。
どうか人間のリーダーになって、人間を指導してください」と。
人間がそう頼んだら、宇宙人は何と答えるだろうか。
恐らくこう答えるだろう。
「断ります」と。
●UFO
ところで少し前、YOUTUBEで、UFOの映像を見た。
この世界も、奥が深い。
長い間、いろいろなUFOの映像を見ていると、偽物か本物か、だいたい区別がつくようにな
る。
る。
その(だいたい)という部分を、さらにきびしく切り落としていくと、中には、「これは本物」というよ
うなものに出会うときがある。
うなものに出会うときがある。
ポイントは、飛び方というより、その消え方。
私とワイフが見たUFOは、夜空に溶け込むようにして、消えていった。
独特の消え方というよりは、この世のものとは思えないような消え方をしていった。
それが私の脳裏に焼きついている。
私はUFOの映像が本物かどうかを判断するとき、いつもその消え方を見る。
……話は脱線したが、UFOがもつ技術力は、人間がもつ技術力を、はるかに超えている。
恐らく猿が、自動車を見るようなものではないか。
やっと木片を叩くことを覚えた猿に、自動車を作れと言っても、無理。
●願う
で、私はときどきこう思う。
UFOでもよいが、死ぬまでに一度は乗ってみたい、と。
UFOを一機くれなどというような、ぜいたくなことは願わない。
しかし一度だけでよいから、乗ってみたい。
で、そのことをワイフに言うと、ワイフはこう言った。
「それくらいなら、宇宙人も、あなたの言うことを聞いてくれるかもしれないわよ」と。
が、つぎの言葉は、ショックだった。
ワイフはこう言った。
「そう言えば、昔、動物園などでは、子どもが乗る電車を、猿が運転していたわよ」と。
……!
●「差」
宇宙人と人間の差は、どれくらいあるのだろうか。
一説によると、宇宙人は自分たちのDNAを、猿人に移植し、私たち人間を創造したという。
「改造」でもよい。
また宇宙人に会ったと証言する人もいる。
信ぴょう性は低いとしても、そういう人たちの話によれば、姿、形は、私たち人間に似ていると
いう。
いう。
目撃例の多い「グレイ」と呼ばれる宇宙人にしても、基本的には人間の姿、形に似ている。
が、知的能力は、どうだろうか。
それについては、私はそれほどないのでは……と思っている。
少なくとも、人間と猿ほどの差はない。
おとなと幼児程度の差ではないか。
●宇宙人の住む世界
逆に考えてみよう。
あなたは月の奥深くに住む、宇宙人である。
月の中心部は、広い空洞になっていて、その中心部には、怪しげな光を放つプラズマ太陽が、
輝いている。
輝いている。
人口は、それほど多くない。
せいぜい数十万人程度。
宇宙人たちは、月の内部の内側にへばりつくようにして、生活している。
もちろん住宅もあれば、工場もある。
水もあれば、植物もある。
一説によれば、宇宙人の寿命は、3000年ほどと言われている。
グレイのような宇宙人は、宇宙人の中でも、人造ロボットに近いそうだ。
つまり宇宙人の手下となって働く、奴隷。
ここでいう宇宙人というのは、もっと上位にいる、高度な宇宙人をいう。
そういう宇宙人であるあなたは、はたして地球へやってきて、人間のリーダーになりたいと思
うだろうか。
うだろうか。
その答は、あなたが猿たちに、「リーダーになってくれ」と頼まれたばあいを想像してみればよ
い。
い。
答は、「NO!」。
宇宙人にしてみれば、人間など相手にしても、どうしようもない。
●男と女
で、問題は、なぜそうなのか、ということ。
私たち人間は、こう考える。
猿の世界なんかでリーダーになっても、ゼンゼン、楽しくない。
おもしろくない。
なぜだろう?
……その理由のひとつに、男と女の関係がある。
ずいぶんと飛躍した考えに聞こえるかもしれない。
それを説明してみよう。
●AKB48
現在、子どもたちの世界では、AKB48が、たいへん人気がある。
私から見れば、まるで子ども。
またそのAKB48を見て騒いでいるのも、これまた、まるで子ども。
その子どもたちが私のところへやってきて、私にこう頼んだとする。
「私たちのリーダーになってくれ」と。
が、私ならやはり、さっさとその申し出を断るだろう。
またリーダーになっても、意味はない。
それは幼児や小学生に、「先生のこと、好き」と言われるのと同じ。
35歳前後の女性にそう言われたら、私はうれしい。
しかし相手が幼児や小学生では、どうしようもない。
つまり、ここにヒントがある。
「35歳前後の女性」である。
宇宙人や猿には、それがない。
つまりロマンがない。
もっと言えば、種族としての未来がない。
相手が宇宙人や猿では、子孫を残すことができない。
「残すことができない」という部分で、ロマンがスーッと萎えてしまう。
35歳前後の女性が作る、「女の惑星」があれば、私は喜んで、リーダーになるかもしれな
い。
い。
……なってもよい。
つまり私自身の判断を決めるのは、ここでも「性的エネルギー」(フロイト)ということになる。
先に「男と女の関係」と書いたのは、そういう意味。
●義兄の話
冒頭に書いた義兄の話に戻る。
私が宇宙人なら、自分たちのもつ技術を、人間には与えない。
与えたら、たいへんなことになる。
そうでなくても、人間は強欲で、喧嘩ばかりしている。
そんな人間に、宇宙人がもつ技術を分け与えたら、それこそ地球そのものを破壊してしまうか
もしれない。
もしれない。
平和利用というのは、こと人間に関して言えば、絵に描いたボタモチ。
100人の善人がいても、1人の悪人がいたら、それで地球は、おしまい。
だから私は義兄にこう言った。
「もしそんな技術を兄さんが手にしたら、兄さんはあっという間に、国によって抹殺されてしまう
でしょうね」と。
でしょうね」と。
●資格
……ということで、結論は出た。
私たち人間は、宇宙人から、高度な技術をもらってはいけない。
たとえ「あげる」と言われても、もらってはいけない。
またそんな程度のことなら、宇宙人も知っているはず。
「人間に高度な技術を与えたら、自分たち(=宇宙人)だって、あぶないぞ」と。
言うなれば、猿に機関銃を渡すようなもの。
つまり私たち人間には、その資格はない。
たしかに人間は、産業革命以来、科学、技術面では、飛躍的な進歩を遂げた。
しかし「心」は、昔のまま。
原始時代のままとまでは言わないが、その時代から、ほとんど進歩していない。
事実、人間の中には、原始人そっくりなのが、いくらでもいる。
携帯電話を片手に、高級車を乗り回しているが、原始人。
こんな状態で、人間がさらに高度な科学や技術をもったら、どうなるか。
それこそこの地球は、おしまいの、そのまた、おしまいになってしまう。
●冬のロマン
毎年秋になると、「秋のロマン」を書く。
が、今年は「冬」?
……実はこのあたりでは、今ごろが秋、まっさかり!
山荘周辺の紅葉も、今が見ごろ。
「冬のロマン」と書きながら、中身は「秋のロマン」。
浜名湖周辺は、照葉樹林帯とも呼ばれ、一年中緑の木々が生い茂っている。
木の種類も、日本一と言われている。
で、このままこの地方は本格的な冬を迎えることもなく、春になっていく。
今朝も寒かったが、それでも気温は9度前後。
書斎には、暖房器具は、いっさい、なし。
脳みその活動には、そのほうがよい。
今朝(2011/12/11)は、『第4種(宇宙人との)接近遭遇』※について、考えてみた。
(注※)(ウィキペディア百科事典より)
●接近遭遇
接近遭遇には、大きく分けて4段階ある。
o第一種接近遭遇は空飛ぶ円盤を、至近距離から目撃すること。
o第二種接近遭遇は空飛ぶ円盤が、周囲に何かしらの影響を与えること。
o第三種接近遭遇は空飛ぶ円盤の搭乗員と、接触すること。
o第四種接近遭遇は空飛ぶ円盤の搭乗員に誘拐されたり、インプラントを埋め込まれたりする
こと。また、空飛ぶ円盤の搭乗員を捕獲、拘束すること。
こと。また、空飛ぶ円盤の搭乗員を捕獲、拘束すること。
(以上、ウィキペディア百科事典より)
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 第4趣接近遭遇 秋の夜のロマ
ン 2011 冬の夜のロマン)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 第4趣接近遭遇 秋の夜のロマ
ン 2011 冬の夜のロマン)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●情報と思考(物知りと賢い子)
数日前、テレビを見ながら、ワイフが何かを言った。
言った内容は忘れた。
テレビの内容も忘れた。
何かを言ったのは、覚えている。
そのとき、つぎのように言った。
「情報というのは、頭の中で反芻(はんすう)し、加工しなければ意味がないよ」と。
つまり情報の一方的な受け入れは、意味がない。
●野球中継
このことは野球中継を見ているとわかる。
たとえば10年前の野球中継を、音声を切った状態でながめてみる。
サッカーの試合でもよい。
(実際に、そういう実験をしたわけではないが……。)
そのときその中継を、10年前のものだとわかる人は、まずいない……と思う。
よほどの野球通でも、わからないだろう。
いわんや、野球中継をたまにしか見ていない人には、ぜったいにわからない。
端的に言えば、10年前の野球中継も、5年前の野球中継も、そして今見る野球中継も、同
じ。
じ。
情報というのは、そういうもの。
つまり覚えては忘れる。
その繰り返し。
●反芻(はんすう)と加工
手に入れた情報は、一度脳の中で、反芻する。
一方的に受け入れてしまうのは、危険なことでもある。
情報を提供する側に、よいように操られてしまう。
野球中継にしてもそうだ。
興業側の餌にされながら、自分が餌になっていることに、気がつかない。
……思い出した。
ワイフが見ていた番組は、太極拳についてのものだった。
1人の女性が中国本場の太極拳を取材していた。
女優だったかもしれない。
「C式太極拳」の取材だったと思う。
その番組を見ながら、その女性が日本人離れしている体型であることに気づいた。
日本人というより、欧米人。
背が高く、細い体をしていた。
足も長かった。
●スタイル
たまたまその日、別のニュースサイトで、日本の中高校生たちが、細くなっているという記事
を読んだ。
を読んだ。
「スタイルを気にする若者がふえた」と。
私はその記事のことが頭に残っていたので、その女性を見ながら、こう思った。
「最近の若い人は、こういう体型にあこがれているのだ」と。
その女性は、周囲の中国人とは、明らかにちがう体型をしていた。
が、私が気になったのは、「胸」。
ほかの女性たちは、太極拳をしながら、ユラユラと胸を揺らしていた。
その女性の胸は、大きさは周囲の中国人の女性と、それほどちがわなかった。
しかしまったく、揺れなかった。
……なぜか……ということについては、私にはわからない。
しかしそういう体型が、健康的な体型かというと、私は、そうは思わない。
アジア人にはアジア人の体型がある。
それを無視し、体型を欧米人のそれに近づけようと、無理をすればするほど、健康を害する。
もちろんその女性が、そうというのではない。
が、気にはなった。
●太極拳
さらに言えば、こんな心配もある。
太極拳については知らないが、こうした健康法は、得てしてカルトと結びつきやすい。
オウム真理教を例にあげるまでもない。
オウム真理教は、ヨガと教義を巧みに混ぜ合わせながら、信者を獲得していった。
番組の中でも、指導(?)を始める前に、「老師」と字幕の出た指導者が、(中国語では「老師」
というのは、年齢に関係なく、「先生」という意味なのだが)、先祖の墓に参るシーンが出てき
た。
というのは、年齢に関係なく、「先生」という意味なのだが)、先祖の墓に参るシーンが出てき
た。
「先祖にあいさつしてから、指導する」と。
まさに宗教的行為!
さらに気になったのは、その老師の家での食事。
「日本から来た客(?)」ということで、もてなしをしたのだろう。
テーブルの上には、所狭しと、料理が並んでいた。
しかしよくよく考えてみると、へん(?)。
どうしてその老師は、まったくの素人に近いその女性を、そんなにも歓待するのか。
ふつうなら、そんな歓待はしない。
なぜか?
テレビカメラを背負った人が、そばにいたからなのか。
テレビカメラを背負った人は、どこへでもズカズカと入り込んでいく。
よい例が、NHKの「昼時~~」何とかいう番組。
平気で民家へあがりこみ、ときには、そこに並べてあった昼食までいっしょに食べていく。
が、どうもそれだけではないようだ。
老師は、こう言った。
「日本へも、たびたび(指導に)行っています」と。
それでピンと来た。
宣伝に利用している!
……であるなら、なおさら、疑ってみる必要がある。
こうした健康指導団体は、組織化しやすい。
「法輪功」と呼ばれる教団も、そのひとつ。
組織化が悪いというのではない。
が、どうして組織化するのか。
健康指導団体が、どうして組織化するのか?
(そのC式太極拳がそうであるというのではない。誤解のないように!)
●ウソと本当
こうして番組を見ながら、自分の頭で考え、判断をくだす。
これが「反芻と思考」ということになる。
が、それをしないで、一方的に、「すばらしい」「私もやってみよう」などと、短絡的に行動しては
いけない。
いけない。
中には「天下のBSで紹介されていたから、安全」と考える人もいるかもしれない。
が、NHKがアテにならないことは、今回の3・11大震災で証明された。
「ウソは言わないが、本当のことも言わない」。
●情報に操られる
私たちは知らず知らずのうちに、情報に操られる。
子どもの世界も、また同じ。
1年前のこと。
PSP(ソニーのゲーム機)のソフトで、「モンスター・ハンター・サード(3rd)」が発売になった。
そのソフトについて、予約で買った子どもが、私の生徒の中にも何人かいた。
「中身を確かめてから買ったのか?」と聞くと、「そんな必要はない」と。
「どうして?」と聞くと、「おもしろいに決まっている」と。
子どもたちの世界では、いかに他人より1歩抜きんでるかが、重大事。
1日でも早く先へ進むのが、ステータスにもなっている。
が、そんな子どもたちは、(もちろんそれだけの知恵も経験もないから、しかたないが)、自分た
ちが情報に操られていることに、気づいていない。
ちが情報に操られていることに、気づいていない。
もっと辛辣な言い方をすれば、おとなたちの金儲けの餌になっているだけ。
●では、どうするか
情報を得たら、反芻し、その情報をもとに、自分の思想を組み立てる。
方法はいろいろある。
近くの人と議論するのもよし。
日記風に書きとめるだけでもよい。
さらに言えば、それについて、自分なりの意見をまとめてみる。
こわいのは、情報の渦に、のみ込まれてしまうこと。
それを無批判なまま、脳の中に格納してはいけない。
もし「反芻する時間がない」というのであれば、むしろそういう情報には接しないほうがよい。
そうでなくても、現代社会は、情報にあふれている。
10分、ネットサーフィンしただけで、頭の中が満杯になる。
が、さらにこわいことがある。
情報には、中毒性がある。
●情報中毒
「情報中毒」について、以前、こんな原稿を書いたことがある。
日付は、2007年10月になっている。
●情報、過剰社会(2007年10月に書いた原稿より)
++++++++++++++
いつも音を聞いていないと、
落ち着かない……とまあ、
そんな人は多いですね。
何かの雑誌に書いてあったので
すが、日本では、エレベーターの
中、バス停でも、音声ガイダンス
が流れますね。それについて、ある
外人が驚いていたそうです。
日本人には、静かな環境で、静かにものを
考えるという習慣そのものがない?
あるいは、日本人は、静かに
ものを考えるという習慣そのものを
放棄してしまったのかもしれません。
情報、また情報。
情報の洪水の中で、情報が途切れたとたん、
不安になってしまう?
よい例が、バスガイドのガイドです。
聞いてもすぐ忘れるような情報を、
つぎからつぎへと流す。
またそれをもって、サービス?、と
誤解している。
どこかおかしいですね。
++++++++++++++
●情報の洪水
先日、パソコンで、メモリー診断をしようと思いついた。VISTAには、メモリー自己診断ツール
が標準でついている。以前には、何度か使ったことがある。
が標準でついている。以前には、何度か使ったことがある。
が、である。その何度か使ったはずのツールがどこにあるかわからない。あちこちをさがして
みたが、結局は、見つからなかった。その説明をしてある雑誌をさがしてみたが、その雑紙も
どこかへ、なくしてしまった。
みたが、結局は、見つからなかった。その説明をしてある雑誌をさがしてみたが、その雑紙も
どこかへ、なくしてしまった。
たった数か月前にできたことが、できない? 私は改めて、脳みその底にできた(穴)に驚い
た。私たちは情報の洪水の中で生きている。それはわかる。が、一方で、その情報は、容赦な
く、脳みその底にできた(穴)から、外へ流れ出てしまう。
た。私たちは情報の洪水の中で生きている。それはわかる。が、一方で、その情報は、容赦な
く、脳みその底にできた(穴)から、外へ流れ出てしまう。
情報の洪水は、つぎつぎとやってきて、またどこかへ消えていく。脳みその中に残る情報とい
うのは、ほんとうに少ない。その少ない情報も、時間とともに、どこかへ消えていく……。
うのは、ほんとうに少ない。その少ない情報も、時間とともに、どこかへ消えていく……。
●情報中毒
いつも情報にさらされていないと落ち着かないという人は、多い。情報の流入が途切れたとた
ん、不安になるらしい。少し前まで、私の母がそうだった。
ん、不安になるらしい。少し前まで、私の母がそうだった。
実家に行くたびに、テレビはガンガンとかけっぱなしだった。私がそれを止めようとすると、母
は、がんこに抵抗した。「見ていないのだからいいだろ?」と言っても、母は納得しなかった。母
は、テレビの音が聞こえていないと、落ち着かなかったのだ。
は、がんこに抵抗した。「見ていないのだからいいだろ?」と言っても、母は納得しなかった。母
は、テレビの音が聞こえていないと、落ち着かなかったのだ。
こういうのを、「情報中毒」という。意味のある情報とか、ない情報とか、そういうことは、考え
ない。選択することもない。料理番組、健康番組、ニュース……まさに、何でもござれ。そういう
情報を、つぎつぎと脳みその中に入れ、また出していく。
ない。選択することもない。料理番組、健康番組、ニュース……まさに、何でもござれ。そういう
情報を、つぎつぎと脳みその中に入れ、また出していく。
何かの雑紙に書いてあったが、日本へ来た外人が、こんなことに驚いていた。日本では、エ
レベーターの中、バス停にすら、音声ガイダンスがある、と。その記事を最初に読んだときに
は、「どうして?」と私は、思った。「どうして、そんな程度のことで、驚いたのか?」と。
レベーターの中、バス停にすら、音声ガイダンスがある、と。その記事を最初に読んだときに
は、「どうして?」と私は、思った。「どうして、そんな程度のことで、驚いたのか?」と。
少し前、観光バスで、オーストラリアの友人夫妻を長野県のほうへ連れていってやったのだ
が、そのときも、そうだった。オーストラリアの友人夫妻は、情報の洪水に驚いていた。バスガ
イドが、間断なくしゃべりつづけていたからだ。それにどこの観光地へ行っても、ガイド、ガイド、
またガイド。「右に見えますのが~~山、左に見えますのが、~~湖」と。
が、そのときも、そうだった。オーストラリアの友人夫妻は、情報の洪水に驚いていた。バスガ
イドが、間断なくしゃべりつづけていたからだ。それにどこの観光地へ行っても、ガイド、ガイド、
またガイド。「右に見えますのが~~山、左に見えますのが、~~湖」と。
一度、情報中毒にかかると、情報なしでは、落ち着かない。つまり音が聞こえていないと落ち
着かない。
着かない。
●情報と思考
何度も書くが、(情報)と(思考)は、まったく別のもの。情報量が多いからといって、その人に
思考力があるとはかぎらない。たとえていうなら、幼稚園児が、かけ算の九九を暗記して口に
するようなもの。それができたからといって、「算数ができる子ども」ということにはならない。
思考力があるとはかぎらない。たとえていうなら、幼稚園児が、かけ算の九九を暗記して口に
するようなもの。それができたからといって、「算数ができる子ども」ということにはならない。
しかしほとんどの人は、幼児が、かけ算の九九を口にしただけで、「算数のできる子ども」と
思い込んでしまう。しかしそれは誤解。まったくの誤解。
思い込んでしまう。しかしそれは誤解。まったくの誤解。
同じように、バスガイドが、観光地にまつわる歴史的な話をしても、だれも、そのガイドが、歴
史のプロだとは思わない。(思う人もいるかもしれないが……。)どうせどこかのガイドブックに
出ていたような内容を、丸暗記しているだけ(失礼!)。
史のプロだとは思わない。(思う人もいるかもしれないが……。)どうせどこかのガイドブックに
出ていたような内容を、丸暗記しているだけ(失礼!)。
先日も、紀伊半島のほうへ行ったときも、織田信長ゆかりの地を、あちこち回った。そのつ
ど、ガイドは、もの知り顔に、あれこれ説明してくれた。が、どれも、まちがいだらけ。しかしそう
いう話を聞いて、質問する人は、いない。かけ算の九九を暗記している幼児に向かって、その
意味を問いただしても意味はない。それと同じ。
ど、ガイドは、もの知り顔に、あれこれ説明してくれた。が、どれも、まちがいだらけ。しかしそう
いう話を聞いて、質問する人は、いない。かけ算の九九を暗記している幼児に向かって、その
意味を問いただしても意味はない。それと同じ。
●考えるという習慣
考えるという習慣のない人に、(考える)ことの重要性を説いても意味はない。(考える)という
意味すら、理解できない。できないばかりか、情報の量をもって、つまりもの知りであることをも
って、「私は頭がいい」と思いこんでいる。
意味すら、理解できない。できないばかりか、情報の量をもって、つまりもの知りであることをも
って、「私は頭がいい」と思いこんでいる。
しかし重要なのは、(考えること)。さらに言えば、(考えるという習慣)。
たとえば健康を維持するため、毎朝、ジョギングしている人がいる。毎日の運動が、健康にと
っていかに大切であるかを、そういう人たちは知っている。運動をした日と、しない日とでは、体
の調子はまるでちがう。運動したあとには、体の細胞のひとつひとつが、ピチピチとはじける音
すら、感ずる。
っていかに大切であるかを、そういう人たちは知っている。運動をした日と、しない日とでは、体
の調子はまるでちがう。運動したあとには、体の細胞のひとつひとつが、ピチピチとはじける音
すら、感ずる。
しかしそういう習慣のない人に、運動の大切さを説いても意味はない。ないばかりか、たとえ
ばテレビの健康番組に流されるまま、「酢がいい」と聞けば、酢を買い、「ニンニクの焼酎漬け
がいい」と聞けば、自分でそれを作ってみたりする。無駄とは思わないが、そのつど情報に振り
回されているだけ。
ばテレビの健康番組に流されるまま、「酢がいい」と聞けば、酢を買い、「ニンニクの焼酎漬け
がいい」と聞けば、自分でそれを作ってみたりする。無駄とは思わないが、そのつど情報に振り
回されているだけ。
同じように、重要なのは、(情報)ではなく、(それを選択し、加工するという習慣)である。
●考えさせない社会
日本の社会は、騒々しい。ほんとうに騒々しい。どこへ行っても、騒音、また騒音。情報の洪
水、また洪水。
水、また洪水。
また観光バスの話にもどるが、うるさいのはガイドだけではない。静かな人も多いるが、その
一方で、おしゃべりな人も多い。バスに乗っている間中、となりの人と、ペチャペチャと間断なく
しゃべっている。概してみれば、女性に多いが、男性にもいる。
一方で、おしゃべりな人も多い。バスに乗っている間中、となりの人と、ペチャペチャと間断なく
しゃべっている。概してみれば、女性に多いが、男性にもいる。
話している内容といえば、たわいもない世間話。あるいはその繰りかえし。私はそういう人た
ちを見ながら、「こういう人たちは、どこでものを考えているのだろう」と思う。「あるいは、どこで
そういう時間をもっているのだろう」とも。
ちを見ながら、「こういう人たちは、どこでものを考えているのだろう」と思う。「あるいは、どこで
そういう時間をもっているのだろう」とも。
もっと言えば、日本の社会構造そのものが、そうなっている。つまり、人が静かにものを考え
るという社会構造になっていない。さらにもっと言えば、教育の段階で、ものを考える子どもを
育てていない。
るという社会構造になっていない。さらにもっと言えば、教育の段階で、ものを考える子どもを
育てていない。
●情報の選択
だからといって、情報が無駄であると言っているのではない。良質で、適確な情報は、思考の
基盤となる。その情報に上に、私たちは自分の思考を組み立てることができる。
基盤となる。その情報に上に、私たちは自分の思考を組み立てることができる。
そこで私たちがすべきことは、情報の選択。洪水なら洪水でもよい。しかしその中から、情報
を選択していく。たとえて言うなら、無数の絵画の中から、名画と、そうでないものを選ぶのに
似ている。これはそれほどむずかしいことではない。ほんの少し訓練すれば、だれにでもでき
るようになる。
を選択していく。たとえて言うなら、無数の絵画の中から、名画と、そうでないものを選ぶのに
似ている。これはそれほどむずかしいことではない。ほんの少し訓練すれば、だれにでもでき
るようになる。
私自身は、つぎのようにして選択している。
(1) その人自身の言葉であるか、どうか。
(2) その人自身が、どういう思想的背景をもっているか。
(3) その人自身が、どういう経験をしているか。
(4) その人自身が、どういう経緯で、その情報を手に入れたか。
(5) 普遍性はあるのか。視野の広さはどうか、公正であるか、など。
つまりその人自身の言葉でないと、意味がないということ。その人自身を見て、判断するとい
うこと。
うこと。
当然のことながら、苦労に苦労を重ねた人の言葉は、重い。意味がある。そうでない人の言
葉は、そうでない。人生も永遠なものであれば、無駄な情報も、それなりに生きることを楽しくし
てくれるかもしれない。しかし今は、もうそうではない。今さらパチンコの攻略本を読んで、それ
を応用してみようなどという気持ちには、とてもなれない。
葉は、そうでない。人生も永遠なものであれば、無駄な情報も、それなりに生きることを楽しくし
てくれるかもしれない。しかし今は、もうそうではない。今さらパチンコの攻略本を読んで、それ
を応用してみようなどという気持ちには、とてもなれない。
●生きるということは、考えること
人は、考えるから、人である。考えない人は、人というより、サル。だからといって、サルが人
より劣っているというのではない。サルのほうが、ひょっとしたら、人間より考えているかもしれ
ない。幼児だって、そうだ。
より劣っているというのではない。サルのほうが、ひょっとしたら、人間より考えているかもしれ
ない。幼児だって、そうだ。
私たちは、幼児イコール、幼稚と考えやすいが、これはとんでもない誤解。幼児は幼児なり
に、懸命に考えている。そういう幼児に出会うと、心底、感動を覚える。ずいぶんと前のことだ
が、こんなことがあった。
に、懸命に考えている。そういう幼児に出会うと、心底、感動を覚える。ずいぶんと前のことだ
が、こんなことがあった。
ある日、幼稚園へ行くと、1人の子ども(年長男児)が、地面を掘っていた。「何をしている
の?」と聞くと、その子どもは、こう言った。「石の赤ちゃんをさがしている」と。
の?」と聞くと、その子どもは、こう言った。「石の赤ちゃんをさがしている」と。
その子どもは、石は、土の中で生まれるものと思っていた。だから地面を掘れば、石の赤ち
ゃんがそこにあると思っていた。その幼児は、その幼児なりに、懸命にそう考えて、穴を掘って
いた。
ゃんがそこにあると思っていた。その幼児は、その幼児なりに、懸命にそう考えて、穴を掘って
いた。
レベルの問題ではない。たしかに私たちおとなから見れば、幼稚(?)な行動かもしれない
が、そこに、私は、生きる価値を見た。もしそれを否定するとなると、つまり私たち自身も、否定
されることになる。
が、そこに、私は、生きる価値を見た。もしそれを否定するとなると、つまり私たち自身も、否定
されることになる。
人間にしても、まだ進化の過程にある。1000年後、あるいは1万年後の人たちが、現在の
私たちを見て、幼稚だと思うかもしれない。しかしだからといって、それを批評することは、許さ
れない。それを許すということは、とりもなおさず、私たちが、私たち自身を否定することにな
る。
私たちを見て、幼稚だと思うかもしれない。しかしだからといって、それを批評することは、許さ
れない。それを許すということは、とりもなおさず、私たちが、私たち自身を否定することにな
る。
私たちは私たちで、懸命に生きている。考えている。内容は幼稚かもしれないが、そこに人が
生きる価値がある。それがわからなければ、ここに書いた幼児を頭の中で、もう一度、想像し
てみてほしい。
生きる価値がある。それがわからなければ、ここに書いた幼児を頭の中で、もう一度、想像し
てみてほしい。
●考えることのすばらしさ
ところで考えることは、宝さがしに似ている。ひとり荒野の中を歩いている。そこで小さな宝石
を見つけるのに似ている。小さな宝石かもしれないが、キラリと輝く。それを見つけたときは、う
れしい。ほんとうに、うれしい。
を見つけるのに似ている。小さな宝石かもしれないが、キラリと輝く。それを見つけたときは、う
れしい。ほんとうに、うれしい。
が、考えることは、けっして、楽な作業ではない。難解な数学の問題を前にして、その問題を
解くようなもの。考えることには、苦痛や苦労がともなう。しかもその問題は、必ずしも、解ける
とはかぎらない。解答用紙もない。
解くようなもの。考えることには、苦痛や苦労がともなう。しかもその問題は、必ずしも、解ける
とはかぎらない。解答用紙もない。
だからできるなら、考えないですませたいと思う。もっとも手っ取り早い方法は、宗教なら宗教
に身を寄せること。思想をだれかに注入してもらうこと。しかしそれは同時に、その人の「死」を
意味する。
に身を寄せること。思想をだれかに注入してもらうこと。しかしそれは同時に、その人の「死」を
意味する。
パスカルの言葉を借りるまでもなく、たとえか弱く、細いアシであっても、人は、自らの足で立
ち上がる。そこに人が生きる意味があるし、気高さも、そこから生まれる。しかし、その価値は
ある。
ち上がる。そこに人が生きる意味があるし、気高さも、そこから生まれる。しかし、その価値は
ある。
考える人からは、考えない人がどういうものか、よくわかる。反対に考えない人からは、考え
る人がどういうものか、わからないだろう。だからいって、私がその考える人というわけではな
い。つまりは相対的な立場でしかない。
る人がどういうものか、わからないだろう。だからいって、私がその考える人というわけではな
い。つまりは相対的な立場でしかない。
私よりものをよく考える人は、いくらでもいる。そういう人たちから見れば、私など、何も考えな
い部類の人間でしかない。しかし一度、考える習慣を身につけると、それまで見ていた世界が
一変する。
い部類の人間でしかない。しかし一度、考える習慣を身につけると、それまで見ていた世界が
一変する。
それは山登りに似ている。下から見ると低く見える山でも、登ってみると、意外と視野が広い
のには驚く。そのすばらしさは、山に登ったことがある人でないとわからない。
のには驚く。そのすばらしさは、山に登ったことがある人でないとわからない。
同じように、考えることによって、だれでも、思考の山に登ることができる。そしてその視野の
広さに驚くことができる。
広さに驚くことができる。
さあ、あなたも勇気を出して、考えてみよう。あなたも、きっとそのすばらしさを、実感するは
ず。……という結論で、この話は、おしまい。
ず。……という結論で、この話は、おしまい。
(以上、2007年10月記)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●再び、2011年12月(現在へ)
2007年に書いた原稿を、今、こうして読み直してみる。
内容的には、それ以前に、あちこちで書いたものを寄せ集めただけの原稿である。
で、ここが重要だが、そういう原稿を4年前に書きながら、ではその私は、この4年間で、4年
分の進歩をしたかということ。
分の進歩をしたかということ。
答は、「NO」に近い。
ただ情報を一方的に受け入れることだけは、2007年の当時も、今もしていない。
繰り返しになるが、あの3・11大震災を契機に、私は情報のもつ恐ろしさというか、洗脳される
ことの恐ろしさを、いやというほど、思い知らされた。
ことの恐ろしさを、いやというほど、思い知らされた。
政府にせよ、NHKにせよ、「ウソは言わないが、本当のことも言わない」。
その(本当のことも言わない部分)で、私たちは日々に少しずつ、洗脳されていく。
すでに今ですら、「原発事故は片づいた」と考えている人は多い。
少し前だが、中学3年生のOさんですら、そう言った。
学年でもトップクラスの成績を収めている子どもである。
私「何も片づいていないよ」
O「ウッソー!」
私「あのね、被害が出てくるのは、これからだよ。チェルノブイリでも被害が出始めたのは、2
年後から5年後。10年後にピークを迎えた。現在の今でも、チェルノブイリでは被害がつづい
ているよ」
年後から5年後。10年後にピークを迎えた。現在の今でも、チェルノブイリでは被害がつづい
ているよ」
O「今でも……?」
私「今でも、だ。そのとき汚染された子どもが母親になり、その母親が子ども産む。その子ども
に症状が現れている」と。
に症状が現れている」と。
不必要に心配することはない。
しかし必要以上に安心するのも、よくない。
今、「もう片づいた」と考えている子どもがいること自体、私たちが情報に操作されていることを
示す。
示す。
もろもろのどうでもよい情報の洪水の中で、思考力そのものを失っている。
つまり、それが、コ・ワ・イ。
●最後に
ここに書いたことを参考に、(物知りな子ども)と、(賢い子ども)について考えてみてほしい。
遠回しな言い方をしたが、このエッセーで書きたかったことは、この1点に尽きる。
情報が多いことイコール、思考力があるということではない。
情報と思考は、まったく別のもの。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教育
評論 はやし浩司 情報と思想 情報中毒 思考力 反芻と思考 はやし浩司 物知り もの
知り 賢い子ども 考える子ども はやし浩司 情報の反芻 はやし浩司 思想と情報 はやし
浩司 情報論)
評論 はやし浩司 情報と思想 情報中毒 思考力 反芻と思考 はやし浩司 物知り もの
知り 賢い子ども 考える子ども はやし浩司 情報の反芻 はやし浩司 思想と情報 はやし
浩司 情報論)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●はやし浩司 2011-12-10夜記(映画・リアル・スティール、ほか)
++++++++++++++++++
今夜は、映画『Real Steel(リアル・スティール)』を観てきた。
土曜日ということで、劇場内は、かなり混んでいた。
内容は、ロボットどうしの闘い。
結構、おもしろかった。
どこか『ロッキー・ザ・ファイナル』を思い起こさせるような映画だった。
最後のシーンでは、かなり涙が出た。
星は4つの、★★★★。
(最近は、映画の採点が甘くなったような記がする。
イコール、何かにつけ、涙もろくなった。)
++++++++++++++++++
●クリスマス・プレゼント
アメリカに住む孫たちに、クリスマス・プレゼントを送った。
合計で、5個になった。
最初の2個は、孫たちがほしがりそうなもの。
つづく3個は、使わなくなったパソコンとか、ゲーム機、それにカメラなど。
2年ほど前に買ってやったゲーム機を、まだ大切に使っている様子。
それを聞いて、ジー様の私としては、胸にジンときた。
それで今年は、5個も送った。
あとはクリスマス前に届くことを、願うばかり。
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
●善と悪
++++++++++++++++++++
「この世の中には、4割の善と4割の悪がある」。
すべてが善ではない。
すべてが悪でもない。
が、悪もある。
その割合は、それぞれが4割前後ではないか?
……ということで、私は以前、「4割の善と4割の悪」という
エッセーを書いた。
中日新聞に載せてもらった。
が、この「4割」という数字は、けっして出任せではない。
こんな話を聞いた。
+++++++++++++++++++
●300円
よく道路沿いで、野菜や果物などを売っている。
無人の販売所で、それを買う人は、100円とか200円を貯金箱のような箱に入れて買う。
私もよく利用させてもらう。
このあたりだと、秋になると、ミカンを売るところが多い。
そういう販売所を出している人に、Kさんという人がいた。
昨年亡くなったが、山荘の造成では、たいへん世話になった。
自宅の周辺に、ミカン園ももっていた。
そんなKさんに、ある日、こう聞いた。
もう20年前近くも、前のことである。
「たとえば1000円分の果物を並べておくと、実際にはいくら、みな払っていきますか」と。
するとそのKさんは、すかさずこう言った。
「700円くらいだよ」と。
つまり料金をごまかしていく人が、(300円分)いる、と。
私が驚いていると、「車の通りの少ないところでは、600円くらいかな」とも。
それで私は「4割」という数字をはじき出した。
30~40%が、料金をごまかしていく!
●善悪論
もっとも何を善といい、何を悪というか。
その判断は、むずかしい。
きわめて観念的な概念で、定義づけることは、不可能。
あえて言うなら、みなが常識と思っていることの中に、善はある。
みなが非常識と思っていることの中に、悪がある。
が、だからといって、その常識が正しいとはかぎらない。
非常識がまちがっているとはかぎらない。
12年ほど前に書いた原稿を探してみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【四割の善と、四割の悪】
子どもに善と悪を教えるとき
●四割の善と四割の悪
社会に四割の善があり、四割の悪があるなら、子どもの世界にも、四割の善があり、四割の悪
がある。子どもの世界は、まさにおとなの世界の縮図。おとなの世界をなおさないで、子どもの
世界だけをよくしようとしても、無理。子どもがはじめて読んだカタカナが、「ホテル」であった
り、「ソープ」であったりする(「クレヨンしんちゃん」V1)。
がある。子どもの世界は、まさにおとなの世界の縮図。おとなの世界をなおさないで、子どもの
世界だけをよくしようとしても、無理。子どもがはじめて読んだカタカナが、「ホテル」であった
り、「ソープ」であったりする(「クレヨンしんちゃん」V1)。
つまり子どもの世界をよくしたいと思ったら、社会そのものと闘う。時として教育をする者は、子
どもにはきびしく、社会には甘くなりやすい。あるいはそういうワナにハマりやすい。ある中学校
の教師は、部活の試合で自分の生徒が負けたりすると、冬でもその生徒を、プールの中に放
り投げていた。
どもにはきびしく、社会には甘くなりやすい。あるいはそういうワナにハマりやすい。ある中学校
の教師は、部活の試合で自分の生徒が負けたりすると、冬でもその生徒を、プールの中に放
り投げていた。
その教師はその教師の信念をもってそうしていたのだろうが、では自分自身に対してはどう
なのか。自分に対しては、そこまできびしいのか。社会に対しては、そこまできびしいのか。親
だってそうだ。子どもに「勉強しろ」と言う親は多い。しかし自分で勉強している親は、少ない。
なのか。自分に対しては、そこまできびしいのか。社会に対しては、そこまできびしいのか。親
だってそうだ。子どもに「勉強しろ」と言う親は多い。しかし自分で勉強している親は、少ない。
●善悪のハバから生まれる人間のドラマ
話がそれたが、悪があることが悪いと言っているのではない。人間の世界が、ほかの動物た
ちのように、特別によい人もいないが、特別に悪い人もいないというような世界になってしまっ
たら、何とつまらないことか。言いかえると、この善悪のハバこそが、人間の世界を豊かでおも
しろいものにしている。無数のドラマも、そこから生まれる。旧約聖書についても、こんな説話
が残っている。
ちのように、特別によい人もいないが、特別に悪い人もいないというような世界になってしまっ
たら、何とつまらないことか。言いかえると、この善悪のハバこそが、人間の世界を豊かでおも
しろいものにしている。無数のドラマも、そこから生まれる。旧約聖書についても、こんな説話
が残っている。
ノアが、「どうして人間のような(不完全な)生き物をつくったのか。(洪水で滅ぼすくらいなら、
最初から、完全な生き物にすればよかったはずだ)」と、神に聞いたときのこと。神はこう答え
ている。「希望を与えるため」と。もし人間がすべて天使のようになってしまったら、人間はより
よい人間になるという希望をなくしてしまう。つまり人間は悪いこともするが、努力によってよい
人間にもなれる。神のような人間になることもできる。旧約聖書の中の神は、「それが希望だ」
と。
最初から、完全な生き物にすればよかったはずだ)」と、神に聞いたときのこと。神はこう答え
ている。「希望を与えるため」と。もし人間がすべて天使のようになってしまったら、人間はより
よい人間になるという希望をなくしてしまう。つまり人間は悪いこともするが、努力によってよい
人間にもなれる。神のような人間になることもできる。旧約聖書の中の神は、「それが希望だ」
と。
●子どもの世界だけの問題ではない
子どもの世界に何か問題を見つけたら、それは子どもの世界だけの問題ではない。それが
わかるかわからないかは、その人の問題意識の深さにもよるが、少なくとも子どもの世界だけ
をどうこうしようとしても意味がない。たとえば少し前、援助交際が話題になったが、それが問
題ではない。
わかるかわからないかは、その人の問題意識の深さにもよるが、少なくとも子どもの世界だけ
をどうこうしようとしても意味がない。たとえば少し前、援助交際が話題になったが、それが問
題ではない。
問題は、そういう環境を見て見ぬふりをしているあなた自身にある。そうでないというのなら、
あなたの仲間や、近隣の人が、そういうところで遊んでいることについて、あなたはどれほどそ
れと闘っているだろうか。
あなたの仲間や、近隣の人が、そういうところで遊んでいることについて、あなたはどれほどそ
れと闘っているだろうか。
私の知人の中には50歳にもなるというのに、テレクラ通いをしている男がいる。高校生の娘
もいる。そこで私はある日、その男にこう聞いた。「君の娘が中年の男と援助交際をしていた
ら、君は許せるか」と。するとその男は笑いながら、こう言った。
もいる。そこで私はある日、その男にこう聞いた。「君の娘が中年の男と援助交際をしていた
ら、君は許せるか」と。するとその男は笑いながら、こう言った。
「うちの娘は、そういうことはしないよ。うちの娘はまともだからね」と。私は「相手の男を許せ
るか」という意味で聞いたのに、その知人は、「援助交際をする女性が悪い」と。こういうおめで
たさが積もり積もって、社会をゆがめる。子どもの世界をゆがめる。それが問題なのだ。
るか」という意味で聞いたのに、その知人は、「援助交際をする女性が悪い」と。こういうおめで
たさが積もり積もって、社会をゆがめる。子どもの世界をゆがめる。それが問題なのだ。
●悪と戦って、はじめて善人
よいことをするから善人になるのではない。悪いことをしないから、善人というわけでもない。
悪と戦ってはじめて、人は善人になる。そういう視点をもったとき、あなたの社会を見る目は、
大きく変わる。子どもの世界も変わる。
悪と戦ってはじめて、人は善人になる。そういう視点をもったとき、あなたの社会を見る目は、
大きく変わる。子どもの世界も変わる。
(参考)
子どもたちへ
魚は陸にあがらないよね。
鳥は水の中に入らないよね。
そんなことをすれば死んでしまうこと、
みんな、知っているからね。
そういうのを常識って言うんだよね。
みんなもね、自分の心に
静かに耳を傾けてみてごらん。
きっとその常識の声が聞こえてくるよ。
してはいけないこと、
しなければならないこと、
それを教えてくれるよ。
ほかの人へのやさしさや思いやりは、
ここちよい響きがするだろ。
ほかの人を裏切ったり、
いじめたりすることは、
いやな響きがするだろ。
みんなの心は、もうそれを知っているんだよ。
あとはその常識に従えばいい。
だってね、人間はね、
その常識のおかげで、
何一〇万年もの間、生きてきたんだもの。
これからもその常識に従えばね、
みんな仲よく、生きられるよ。
わかったかな。
そういう自分自身の常識を、
もっともっとみがいて、
そしてそれを、大切にしようね。
(詩集「子どもたちへ」より)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●善と悪
要するに、善と悪と、2つに区別することのほうが、まちがっている。
とくに善人と悪人を区別することのほうが、まちがっている。
善も悪も、紙一重。
善人も悪人も、紙一重。
同じ善(善人)でも、見る人がちがえば、悪(悪人)に見えることがある。
同じ悪(悪人)でも、見る人がちがえば、善(善人)に見えることがある。
だから私たちはそのつど常識をみがき、その常識に従って生きていくしかない。
それを決定づけるのが、(思考)(思索)ということになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 善と悪 善悪論)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 善と悪 善悪論)
Hiroshi Hayashi+++++Dec.2011+++++はやし浩司
●経済ニュース
またまた素人の経済論。
1週間ほど前、オーストラリアの友人からメールが届いた。
「金(ゴールド)は、買うべきか、どうか」と。
私は「今は、時期が悪い。2、3か月待て」と返事を書いた。
が、けっして憶測でそう書いたのではない。
長い間、貴金属の動向をながめていると、その動きがおおかた予想できるようになる。
理由の第一。
高騰のし過ぎ。
いくらリスクオフ資産とはいえ、現在の価格はメチャメチャ。
金(ゴールド)のほうが、プラチナよりも高い。
あんな延べ棒1キロ分だけで、TOYOTAのプリウスが1・5台も買える!
理由の第二。
資産の現金化が始まっている。
現金(キャッシュ)が、市場で回らなくなっている。
その分だけ、投資家は金(ゴールド)を売って、現金(キャッシュ)を手に入れようとする。
ふつう、経済が不安定になると、金(ゴールド)のような現物資産に、お金(マネー)が集まる。
が、今は、その逆。
みなが一斉に金(ゴールド)を売り始めた。
資産を現金化し始めた。
つまり金(ゴールド)の価格が急降下し始めた。
年末まで、この状態はつづく。
ともあれ、毎日ハラハラするようであれば、その金融資産は手放したほうがよい。
健康にもよくない。
●オーストラリア経済
ついで「株はどうか?」と。
その友人は、どこかのレアメタル採掘会社の株をもっているという。
株価は今まで上昇してきた。
現在も、安定している。
だから「どうしたらいいか?」と。
が、私はオーストラリア経済については、ほとんど知らない。
知らないが、私の経済論は、単純。
たとえば自動販売機で売っているペットボトルの値段を見て、それを知る。
つまり為替相場を知る。
現在、オーストラリアでは、日本で120円前後で売られているペットボトルが、3ドル50セント
前後。
前後。
量は、日本のそれの約1・5倍。
それで計算すると、実勢レートは、120x1・5=180円=3・5ドル。
つまり1豪ドル=51円。
51円が、実勢レート。
(180÷3・5ドルで計算。)
現実には、1豪ドル=78円(12月16日現在)で取り引きされている。
51円の価値しかないものを、78円で取り引きされている。
つまり豪ドルは、まださがる。
加えて、オーストラリアの10年もの国債の利回りは、現在、3・786%。
この利率は、ニュージーランドの3・783%よりも、悪い。
フランスの3・036%よりも、悪い。
もう少していねいにみると、こうなる。
『……オーストラリアの輸出は、2010年後半は前年比で30%を超える高い伸びとなってい
た。
た。
が、2011年以降は豪州の洪水被害による石炭の輸出減や、3・11大震災による対日輸出な
どが減少し、2011年6 月には前年比+1・6%まで急減速した。
どが減少し、2011年6 月には前年比+1・6%まで急減速した。
直近9月はそういった供給サイドの要因が剥落してきたことから、前年比+17・2%まで伸び
が拡大している。
が拡大している。
ただ、今後は9月から11月にかけて鉄鉱石の中国向けスポット価格が、3割程度急落してお
り、そういった影響が顕在化していくとみられる。
り、そういった影響が顕在化していくとみられる。
中国が12月に入って預金準備率の引き下げなど金融緩和に動いているものの、中国や欧米
など世界景気の減速が2012年前半にかけて続くことから、輸出は当面、軟調な展開が想定
される』(以上、MIZUHOリサーチ・要約)と。
など世界景気の減速が2012年前半にかけて続くことから、輸出は当面、軟調な展開が想定
される』(以上、MIZUHOリサーチ・要約)と。
こうした事実から、現在、オーストラリア政府は、豪ドルを何とか強く見せようと無理をしてい
るのが、わかる。
るのが、わかる。
わかりやすく言えば、化粧で、元気ぽく見せかけている。
が、長くはつづかない。
つまり豪ドルは、やがてドスンとさがる。
そのとき株価も、ドスンとさがる。
だから友人にはこう書いた。
「今、利益が出ているなら、現金に換えたほうがいい。株価がさがったとき、また買い戻せばい
い」と。
い」と。
どうであるにせよ、こういうときは、素人は株や債権には手を出さない方がよい。
素人が手を出せば、(私も含めてだが)、やけどを負うに決まっている。
すでにこの日本では、95%の一般投資家が、損をしているという(某経済誌)。
95%だぞ!
で、この「95%」という数字をどう読むか。
読み方にもいろいろある。
が、こうも読める。
「金融資産の95%を失った人もいる」と。
事実、私はそういう人を、何人か知っている。
なお株や債権がさがりはじめると、たいていの投資家は、「塩漬け」を決め込む。
が、これがますます墓穴を深くする。
気がついたときには、10分の1、あるいは20分の1になっている。
だからプロの投資家はこう教える。
「10%の損失を出したら、損切りをしろ」(某経済誌)と。
この鉄則は、私が商社マンだったころの40年前と、何も変わっていない。
それに一言。
株や債権で損をしても、だれも同情してくれないぞ。
助けてくれないぞ。
ただ笑われるだけ。
私ごとで失礼。
私は3・11の大震災直前に、株はすべて売り逃げた。
8月はじめのアメリカの債務上限問題直前に、債権はすべて売り逃げた。
債務上限問題のときは、おおかたの予想では、「追いつめられたアメリカは、結局は債務上限
を棚上げにせざるをえない」「そのあと同時に株価は上昇するだろう」となっていた。
を棚上げにせざるをえない」「そのあと同時に株価は上昇するだろう」となっていた。
債務上限は棚上げにされたが、しかし直後、逆に全世界の株価は大暴落した。
EUの金融危機問題が発生した。
●貪欲
総じてみれば、今の世の中、狂っている。
みな、必要以上に貪欲になるから、こういうことになる。
みなが、みな、あるところで一線を引き、「これ以上は不要です」と言えば、こういうことにはなら
ない。
ない。
が、現実は、そうではない。
「もっと欲しい」「さらに欲しい」と。
貪欲の追求こそが善であると、思い込んでいる。
それが世の中を狂わせる。
わかりやすく言えば、「だからそれがどうしたの?」という部分がないまま、人間はみな、今、暴
走状態にある。
走状態にある。
高級ワインを飲んだ……だからそれがどうしたの?……コンビニの120円チューハイでいいじ
ゃないの?
ゃないの?
高級な衣服で身を飾った……だからそれがどうしたの?……本当の美しさは健康から生まれ
るんじゃないの?
るんじゃないの?
高級な車で買い物に行った……だからそれがどうしたの?……歩いて行ったほうが、体のた
めにもいいんじゃないの?
めにもいいんじゃないの?
今、私たち人間に必要なのは、ほどほどのところで満足するという哲学。
欲望をコントロールする理性。
それを支える思考力。
それがないから、富や権力の偏在が起こる。
それが弱者をたたきのめす。
社会を不安定にする。
今朝は、経済問題を取りあげながら、別の心でそんなことを考えた。
これからもう一度、布団の中にもぐりこむ。
あの臭気が消えていることを願いながら……
2011/12/17朝記
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
心の別室論については、たびたび書いてきた。
原稿を探してみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●心の別室と加害意識
(Another Room in the Mind and Consciousness of Guilty)
2009年4月に発表した原稿より。
++++++++++++++++++++
カレー・ヒ素混入事件で、現在無実を争って
いる女性が、HM。
地下鉄サリン事件で、これまた無実を争って
いる男性が、OS教のMT。
現在刑事裁判が継続中なので、これらの人たちは
無実という前提で、ものを考えなければならない。
どんな被告人でも、有罪が確定するまで、推定無実。
カレーにヒ素を混入させたのは、別人物かも
しれない。
地下鉄サリン事件には、MTは関与していなかった
かもしれない。
そういう可能性が、1000に1つ、万に1つでも
あるなら、これらの人たちは、無実。
そういう前提で、ものを考えなければならない。
が、同じ無実でも、いまだに納得できないのが、
あの『ロス疑惑事件』。
Kさんの殺害現場に、一台の白いバンがやってきた。
そのバンが走り去ったとき、Kさんは、殺されていた。
Kさんのそばには、MKがいた。
白いバンは、近くのビルにいた男性たちによって
目撃されている。
MK自身が撮った写真の中にも、白いバンの
一部が写っている。
しかしMKは、「白いバンは見ていない」と。
そのMKは、ロス市警へ移送されたあと、留置場の中で
自殺している。
MKは無実だったのか?
無実だったのなら、自殺などしないで、最後の最後まで
闘ってほしかった。
どうもこの事件は、すっきりしない。
どう考えても、すっきりしない。
++++++++++++++++++++
●心の別室論(Another Room in the Mind)
人間には、自分にとって都合の悪いことがあると、心の中に別室を作り、
そこへ押し込めてしまうという習性がある。
心理学では、こうした心理操作を、「抑圧」という言葉を使って説明する。
「心の平穏を守るために自らを防衛する機能」という意味で、「防衛機制」のひとつ
と考えられている。
その防衛機制は、つぎの7つに大別される。
(1) 抑圧
(2) 昇華
(3) 同一化
(4) 投射
(5) 反動形成
(6) 合理化
(7) 白日夢(以上、深堀元文「心理学のすべて」)
この中でも、「不安や恐怖、罪悪感などを呼び起こすような欲求、記憶などを
無意識の中に閉じ込め、意識にのぼってこないようにする」(同書)を、「抑圧」
という。
つまり心の別室の中に、それを閉じ込め、外からカギをかけてしまう。
よく「加害者は害を与えたことを忘れやすく、被害者は害を受けたことを
いつまでも覚えている」と言われる。
(そう言っているのは、私だが……。)
この「加害者は害を与えたことを忘れやすい」という部分、つまり都合の悪いことは
忘れやすいという心理的現象は、この「抑圧」という言葉で、説明できる。
が、実際には、(忘れる)のではない。
ここにも書いたように、心の別室を作り、そこへそれを押し込んでしまう。
こうした心理的現象は、日常的によく経験する。
たとえば教育の世界では、「おとなしい子どもほど、心配」「がまん強い子どもほど、
心配」「従順な子どもほど、心配」などなど、いろいろ言われている。
さらに言えば、「ものわかりのよい、よい子ほど、心配」となる。
このタイプの子どもは、本来の自分を、心の別室に押し込んでしまう。
その上で、別の人間を演ずる。
演ずるという意識がないまま、演ずる。
が、その分だけ、心をゆがめやすい。
これはほんの一例だが、思春期にはげしい家庭内暴力を起こす子どもがいる。
ふつうの家庭内暴力ではない。
「殺してやる!」「殺される!」の大乱闘を繰り返す。
そういう子どもほど、調べていくと、乳幼児期には、おとなしく、静かで、かつ
従順だったことがわかる。
世間を騒がす、凶悪犯罪を起こす子どもも、そうである。
心の別室といっても、それほど広くはない。
ある限度(=臨界点)を超えると、爆発する。
爆発して、さまざまな問題行動を起こすようになる。
話が脱線したが、ではそういう子どもたちが、日常的にウソをついているとか、
仮面をかぶっているかというと、そうではない。
(外から見える子ども)も、(心の別室の中にいる子ども)も、子どもは子ども。
同じ子どもと考える。
このことは、抑圧を爆発させているときの自分を観察してみると、よくわかる。
よく夫婦喧嘩をしていて、(こう書くと、私のことだとわかってしまうが)、
20年前、30年前の話を、あたかもつい先日のようにして、喧嘩をする人がいる。
「あのとき、お前は!」「このとき、あなたは!」と。
心の別室に住んでいる(私)が外に出てきたときには、外に出てきた(私)が私であり、
それは仮面をかぶった(私)でもない。
どちらが本当の私で、どちらがウソの私かという判断は、しても意味はない。
両方とも、(心の別室に住んでいる私は、私の一部かもしれないが)、私である。
私「お前なんか、離婚してやるウ!」
ワ「今度こそ、本気ね!」
私「そうだ。本気だア!」
ワ「明日になって、仲直りしようなんて、言わないわね!」
私「ぜったいに言わない!」
ワ「この前、『お前とは、死ぬまで一緒』って言ったのは、ウソなのね!」
私「ああ、そうだ、あんなのウソだア!」と。
そこでよく話題になるのが、多重人格障害。
「障害者」と呼ばれるようになると、いろいろな人格が、交互に出てくる。
そのとき、どれが(主人格)なのかは、本当のところ、だれにもわからない。
「現在、外に現れているのが、主人格」ということになる。
夫婦喧嘩をしているときの(私)も、私なら、していないときの(私)も、
私ということになる。
実際、夫婦喧嘩をしている最中に、自分でもどちらの自分が本当の自分か、
わからなくなるときがある。
ともかくも、心の別室があるということは、好ましいことではない。
「抑圧」にも程度があり、簡単なことをそこに抑圧してしまうケースもあれば、
重篤なケースもある。
それこそ他人を殺害しておきながら、「私は知らない」ですませてしまうケースも
ないとは言わない。
さらに進むと、心の別室にいる自分を、まったく別の他人のように思ってしまう。
そうなれば、それこそその人は、多重人格障害者ということになってしまう。
ところで最近、私はこう考えることがある。
「日本の歴史教科書全体が、心の別室ではないか」と。
まちがったことは、書いてない。
それはわかる。
しかしすべてを書いているかというと、そうでもない。
日本にとって都合の悪いことは、書いてない。
そして「教科書」の名のもとに、都合の悪いことを、別室に閉じ込め、
カギをかけてしまっている(?)。
しかしこれは余談。
ただこういうことは言える。
だれにでも心の別室はある。
私にもあるし、あなたにもある。
大切なことは、その心の別室にいる自分を、いつも忘れないこと。
とくに何かのことで、だれかに害を加えたようなとき、心の別室を忘れないこと。
忘れたら、それこそ、その人は、お・し・ま・い!
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
心の別室 防衛機制 抑圧 はやし浩司 心の別室論 人格障害 加害意識)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 20日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page011.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●情報と思考(物知りと賢い子)
数日前、テレビを見ながら、ワイフが何かを言った。
言った内容は忘れた。
テレビの内容も忘れた。
何かを言ったのは、覚えている。
そのとき、つぎのように言った。
「情報というのは、頭の中で反芻(はんすう)し、加工しなければ意味がないよ」と。
つまり情報の一方的な受け入れは、意味がない。
●野球中継
このことは野球中継を見ているとわかる。
たとえば10年前の野球中継を、音声を切った状態でながめてみる。
サッカーの試合でもよい。
(実際に、そういう実験をしたわけではないが……。)
そのときその中継を、10年前のものだとわかる人は、まずいない……と思う。
よほどの野球通でも、わからないだろう。
いわんや、野球中継をたまにしか見ていない人には、ぜったいにわからない。
端的に言えば、10年前の野球中継も、5年前の野球中継も、そして今見る野球中継も、同
じ。
じ。
情報というのは、そういうもの。
つまり覚えては忘れる。
その繰り返し。
●反芻(はんすう)と加工
手に入れた情報は、一度脳の中で、反芻する。
一方的に受け入れてしまうのは、危険なことでもある。
情報を提供する側に、よいように操られてしまう。
野球中継にしてもそうだ。
興業側の餌にされながら、自分が餌になっていることに、気がつかない。
……思い出した。
ワイフが見ていた番組は、太極拳についてのものだった。
1人の女性が中国本場の太極拳を取材していた。
女優だったかもしれない。
「C式太極拳」の取材だったと思う。
その番組を見ながら、その女性が日本人離れしている体型であることに気づいた。
日本人というより、欧米人。
背が高く、細い体をしていた。
足も長かった。
●スタイル
たまたまその日、別のニュースサイトで、日本の中高校生たちが、細くなっているという記事
を読んだ。
を読んだ。
「スタイルを気にする若者がふえた」と。
私はその記事のことが頭に残っていたので、その女性を見ながら、こう思った。
「最近の若い人は、こういう体型にあこがれているのだ」と。
その女性は、周囲の中国人とは、明らかにちがう体型をしていた。
が、私が気になったのは、「胸」。
ほかの女性たちは、太極拳をしながら、ユラユラと胸を揺らしていた。
その女性の胸は、大きさは周囲の中国人の女性と、それほどちがわなかった。
しかしまったく、揺れなかった。
……なぜか……ということについては、私にはわからない。
しかしそういう体型が、健康的な体型かというと、私は、そうは思わない。
アジア人にはアジア人の体型がある。
それを無視し、体型を欧米人のそれに近づけようと、無理をすればするほど、健康を害する。
もちろんその女性が、そうというのではない。
が、気にはなった。
●太極拳
さらに言えば、こんな心配もある。
太極拳については知らないが、こうした健康法は、得てしてカルトと結びつきやすい。
オウム真理教を例にあげるまでもない。
オウム真理教は、ヨガと教義を巧みに混ぜ合わせながら、信者を獲得していった。
番組の中でも、指導(?)を始める前に、「老師」と字幕の出た指導者が、(中国語では「老師」
というのは、年齢に関係なく、「先生」という意味なのだが)、先祖の墓に参るシーンが出てき
た。
というのは、年齢に関係なく、「先生」という意味なのだが)、先祖の墓に参るシーンが出てき
た。
「先祖にあいさつしてから、指導する」と。
まさに宗教的行為!
さらに気になったのは、その老師の家での食事。
「日本から来た客(?)」ということで、もてなしをしたのだろう。
テーブルの上には、所狭しと、料理が並んでいた。
しかしよくよく考えてみると、へん(?)。
どうしてその老師は、まったくの素人に近いその女性を、そんなにも歓待するのか。
ふつうなら、そんな歓待はしない。
なぜか?
テレビカメラを背負った人が、そばにいたからなのか。
テレビカメラを背負った人は、どこへでもズカズカと入り込んでいく。
よい例が、NHKの「昼時~~」何とかいう番組。
平気で民家へあがりこみ、ときには、そこに並べてあった昼食までいっしょに食べていく。
が、どうもそれだけではないようだ。
老師は、こう言った。
「日本へも、たびたび(指導に)行っています」と。
それでピンと来た。
宣伝に利用している!
……であるなら、なおさら、疑ってみる必要がある。
こうした健康指導団体は、組織化しやすい。
「法輪功」と呼ばれる教団も、そのひとつ。
組織化が悪いというのではない。
が、どうして組織化するのか。
健康指導団体が、どうして組織化するのか?
(そのC式太極拳がそうであるというのではない。誤解のないように!)
●ウソと本当
こうして番組を見ながら、自分の頭で考え、判断をくだす。
これが「反芻と思考」ということになる。
が、それをしないで、一方的に、「すばらしい」「私もやってみよう」などと、短絡的に行動しては
いけない。
いけない。
中には「天下のBSで紹介されていたから、安全」と考える人もいるかもしれない。
が、NHKがアテにならないことは、今回の3・11大震災で証明された。
「ウソは言わないが、本当のことも言わない」。
●情報に操られる
私たちは知らず知らずのうちに、情報に操られる。
子どもの世界も、また同じ。
1年前のこと。
PSP(ソニーのゲーム機)のソフトで、「モンスター・ハンター・サード(3rd)」が発売になった。
そのソフトについて、予約で買った子どもが、私の生徒の中にも何人かいた。
「中身を確かめてから買ったのか?」と聞くと、「そんな必要はない」と。
「どうして?」と聞くと、「おもしろいに決まっている」と。
子どもたちの世界では、いかに他人より1歩抜きんでるかが、重大事。
1日でも早く先へ進むのが、ステータスにもなっている。
が、そんな子どもたちは、(もちろんそれだけの知恵も経験もないから、しかたないが)、自分た
ちが情報に操られていることに、気づいていない。
ちが情報に操られていることに、気づいていない。
もっと辛辣な言い方をすれば、おとなたちの金儲けの餌になっているだけ。
●では、どうするか
情報を得たら、反芻し、その情報をもとに、自分の思想を組み立てる。
方法はいろいろある。
近くの人と議論するのもよし。
日記風に書きとめるだけでもよい。
さらに言えば、それについて、自分なりの意見をまとめてみる。
こわいのは、情報の渦に、のみ込まれてしまうこと。
それを無批判なまま、脳の中に格納してはいけない。
もし「反芻する時間がない」というのであれば、むしろそういう情報には接しないほうがよい。
そうでなくても、現代社会は、情報にあふれている。
10分、ネットサーフィンしただけで、頭の中が満杯になる。
が、さらにこわいことがある。
情報には、中毒性がある。
●情報中毒
「情報中毒」について、以前、こんな原稿を書いたことがある。
日付は、2007年10月になっている。
●情報、過剰社会(2007年10月に書いた原稿より)
++++++++++++++
いつも音を聞いていないと、
落ち着かない……とまあ、
そんな人は多いですね。
何かの雑誌に書いてあったので
すが、日本では、エレベーターの
中、バス停でも、音声ガイダンス
が流れますね。それについて、ある
外人が驚いていたそうです。
日本人には、静かな環境で、静かにものを
考えるという習慣そのものがない?
あるいは、日本人は、静かに
ものを考えるという習慣そのものを
放棄してしまったのかもしれません。
情報、また情報。
情報の洪水の中で、情報が途切れたとたん、
不安になってしまう?
よい例が、バスガイドのガイドです。
聞いてもすぐ忘れるような情報を、
つぎからつぎへと流す。
またそれをもって、サービス?、と
誤解している。
どこかおかしいですね。
++++++++++++++
●情報の洪水
先日、パソコンで、メモリー診断をしようと思いついた。VISTAには、メモリー自己診断ツール
が標準でついている。以前には、何度か使ったことがある。
が標準でついている。以前には、何度か使ったことがある。
が、である。その何度か使ったはずのツールがどこにあるかわからない。あちこちをさがして
みたが、結局は、見つからなかった。その説明をしてある雑誌をさがしてみたが、その雑紙も
どこかへ、なくしてしまった。
みたが、結局は、見つからなかった。その説明をしてある雑誌をさがしてみたが、その雑紙も
どこかへ、なくしてしまった。
たった数か月前にできたことが、できない? 私は改めて、脳みその底にできた(穴)に驚い
た。私たちは情報の洪水の中で生きている。それはわかる。が、一方で、その情報は、容赦な
く、脳みその底にできた(穴)から、外へ流れ出てしまう。
た。私たちは情報の洪水の中で生きている。それはわかる。が、一方で、その情報は、容赦な
く、脳みその底にできた(穴)から、外へ流れ出てしまう。
情報の洪水は、つぎつぎとやってきて、またどこかへ消えていく。脳みその中に残る情報とい
うのは、ほんとうに少ない。その少ない情報も、時間とともに、どこかへ消えていく……。
うのは、ほんとうに少ない。その少ない情報も、時間とともに、どこかへ消えていく……。
●情報中毒
いつも情報にさらされていないと落ち着かないという人は、多い。情報の流入が途切れたとた
ん、不安になるらしい。少し前まで、私の母がそうだった。
ん、不安になるらしい。少し前まで、私の母がそうだった。
実家に行くたびに、テレビはガンガンとかけっぱなしだった。私がそれを止めようとすると、母
は、がんこに抵抗した。「見ていないのだからいいだろ?」と言っても、母は納得しなかった。母
は、テレビの音が聞こえていないと、落ち着かなかったのだ。
は、がんこに抵抗した。「見ていないのだからいいだろ?」と言っても、母は納得しなかった。母
は、テレビの音が聞こえていないと、落ち着かなかったのだ。
こういうのを、「情報中毒」という。意味のある情報とか、ない情報とか、そういうことは、考え
ない。選択することもない。料理番組、健康番組、ニュース……まさに、何でもござれ。そういう
情報を、つぎつぎと脳みその中に入れ、また出していく。
ない。選択することもない。料理番組、健康番組、ニュース……まさに、何でもござれ。そういう
情報を、つぎつぎと脳みその中に入れ、また出していく。
何かの雑紙に書いてあったが、日本へ来た外人が、こんなことに驚いていた。日本では、エ
レベーターの中、バス停にすら、音声ガイダンスがある、と。その記事を最初に読んだときに
は、「どうして?」と私は、思った。「どうして、そんな程度のことで、驚いたのか?」と。
レベーターの中、バス停にすら、音声ガイダンスがある、と。その記事を最初に読んだときに
は、「どうして?」と私は、思った。「どうして、そんな程度のことで、驚いたのか?」と。
少し前、観光バスで、オーストラリアの友人夫妻を長野県のほうへ連れていってやったのだ
が、そのときも、そうだった。オーストラリアの友人夫妻は、情報の洪水に驚いていた。バスガ
イドが、間断なくしゃべりつづけていたからだ。それにどこの観光地へ行っても、ガイド、ガイド、
またガイド。「右に見えますのが~~山、左に見えますのが、~~湖」と。
が、そのときも、そうだった。オーストラリアの友人夫妻は、情報の洪水に驚いていた。バスガ
イドが、間断なくしゃべりつづけていたからだ。それにどこの観光地へ行っても、ガイド、ガイド、
またガイド。「右に見えますのが~~山、左に見えますのが、~~湖」と。
一度、情報中毒にかかると、情報なしでは、落ち着かない。つまり音が聞こえていないと落ち
着かない。
着かない。
●情報と思考
何度も書くが、(情報)と(思考)は、まったく別のもの。情報量が多いからといって、その人に
思考力があるとはかぎらない。たとえていうなら、幼稚園児が、かけ算の九九を暗記して口に
するようなもの。それができたからといって、「算数ができる子ども」ということにはならない。
思考力があるとはかぎらない。たとえていうなら、幼稚園児が、かけ算の九九を暗記して口に
するようなもの。それができたからといって、「算数ができる子ども」ということにはならない。
しかしほとんどの人は、幼児が、かけ算の九九を口にしただけで、「算数のできる子ども」と
思い込んでしまう。しかしそれは誤解。まったくの誤解。
思い込んでしまう。しかしそれは誤解。まったくの誤解。
同じように、バスガイドが、観光地にまつわる歴史的な話をしても、だれも、そのガイドが、歴
史のプロだとは思わない。(思う人もいるかもしれないが……。)どうせどこかのガイドブックに
出ていたような内容を、丸暗記しているだけ(失礼!)。
史のプロだとは思わない。(思う人もいるかもしれないが……。)どうせどこかのガイドブックに
出ていたような内容を、丸暗記しているだけ(失礼!)。
先日も、紀伊半島のほうへ行ったときも、織田信長ゆかりの地を、あちこち回った。そのつ
ど、ガイドは、もの知り顔に、あれこれ説明してくれた。が、どれも、まちがいだらけ。しかしそう
いう話を聞いて、質問する人は、いない。かけ算の九九を暗記している幼児に向かって、その
意味を問いただしても意味はない。それと同じ。
ど、ガイドは、もの知り顔に、あれこれ説明してくれた。が、どれも、まちがいだらけ。しかしそう
いう話を聞いて、質問する人は、いない。かけ算の九九を暗記している幼児に向かって、その
意味を問いただしても意味はない。それと同じ。
●考えるという習慣
考えるという習慣のない人に、(考える)ことの重要性を説いても意味はない。(考える)という
意味すら、理解できない。できないばかりか、情報の量をもって、つまりもの知りであることをも
って、「私は頭がいい」と思いこんでいる。
意味すら、理解できない。できないばかりか、情報の量をもって、つまりもの知りであることをも
って、「私は頭がいい」と思いこんでいる。
しかし重要なのは、(考えること)。さらに言えば、(考えるという習慣)。
たとえば健康を維持するため、毎朝、ジョギングしている人がいる。毎日の運動が、健康にと
っていかに大切であるかを、そういう人たちは知っている。運動をした日と、しない日とでは、体
の調子はまるでちがう。運動したあとには、体の細胞のひとつひとつが、ピチピチとはじける音
すら、感ずる。
っていかに大切であるかを、そういう人たちは知っている。運動をした日と、しない日とでは、体
の調子はまるでちがう。運動したあとには、体の細胞のひとつひとつが、ピチピチとはじける音
すら、感ずる。
しかしそういう習慣のない人に、運動の大切さを説いても意味はない。ないばかりか、たとえ
ばテレビの健康番組に流されるまま、「酢がいい」と聞けば、酢を買い、「ニンニクの焼酎漬け
がいい」と聞けば、自分でそれを作ってみたりする。無駄とは思わないが、そのつど情報に振り
回されているだけ。
ばテレビの健康番組に流されるまま、「酢がいい」と聞けば、酢を買い、「ニンニクの焼酎漬け
がいい」と聞けば、自分でそれを作ってみたりする。無駄とは思わないが、そのつど情報に振り
回されているだけ。
同じように、重要なのは、(情報)ではなく、(それを選択し、加工するという習慣)である。
●考えさせない社会
日本の社会は、騒々しい。ほんとうに騒々しい。どこへ行っても、騒音、また騒音。情報の洪
水、また洪水。
水、また洪水。
また観光バスの話にもどるが、うるさいのはガイドだけではない。静かな人も多いるが、その
一方で、おしゃべりな人も多い。バスに乗っている間中、となりの人と、ペチャペチャと間断なく
しゃべっている。概してみれば、女性に多いが、男性にもいる。
一方で、おしゃべりな人も多い。バスに乗っている間中、となりの人と、ペチャペチャと間断なく
しゃべっている。概してみれば、女性に多いが、男性にもいる。
話している内容といえば、たわいもない世間話。あるいはその繰りかえし。私はそういう人た
ちを見ながら、「こういう人たちは、どこでものを考えているのだろう」と思う。「あるいは、どこで
そういう時間をもっているのだろう」とも。
ちを見ながら、「こういう人たちは、どこでものを考えているのだろう」と思う。「あるいは、どこで
そういう時間をもっているのだろう」とも。
もっと言えば、日本の社会構造そのものが、そうなっている。つまり、人が静かにものを考え
るという社会構造になっていない。さらにもっと言えば、教育の段階で、ものを考える子どもを
育てていない。
るという社会構造になっていない。さらにもっと言えば、教育の段階で、ものを考える子どもを
育てていない。
●情報の選択
だからといって、情報が無駄であると言っているのではない。良質で、適確な情報は、思考の
基盤となる。その情報に上に、私たちは自分の思考を組み立てることができる。
基盤となる。その情報に上に、私たちは自分の思考を組み立てることができる。
そこで私たちがすべきことは、情報の選択。洪水なら洪水でもよい。しかしその中から、情報
を選択していく。たとえて言うなら、無数の絵画の中から、名画と、そうでないものを選ぶのに
似ている。これはそれほどむずかしいことではない。ほんの少し訓練すれば、だれにでもでき
るようになる。
を選択していく。たとえて言うなら、無数の絵画の中から、名画と、そうでないものを選ぶのに
似ている。これはそれほどむずかしいことではない。ほんの少し訓練すれば、だれにでもでき
るようになる。
私自身は、つぎのようにして選択している。
(1) その人自身の言葉であるか、どうか。
(2) その人自身が、どういう思想的背景をもっているか。
(3) その人自身が、どういう経験をしているか。
(4) その人自身が、どういう経緯で、その情報を手に入れたか。
(5) 普遍性はあるのか。視野の広さはどうか、公正であるか、など。
つまりその人自身の言葉でないと、意味がないということ。その人自身を見て、判断するとい
うこと。
うこと。
当然のことながら、苦労に苦労を重ねた人の言葉は、重い。意味がある。そうでない人の言
葉は、そうでない。人生も永遠なものであれば、無駄な情報も、それなりに生きることを楽しくし
てくれるかもしれない。しかし今は、もうそうではない。今さらパチンコの攻略本を読んで、それ
を応用してみようなどという気持ちには、とてもなれない。
葉は、そうでない。人生も永遠なものであれば、無駄な情報も、それなりに生きることを楽しくし
てくれるかもしれない。しかし今は、もうそうではない。今さらパチンコの攻略本を読んで、それ
を応用してみようなどという気持ちには、とてもなれない。
●生きるということは、考えること
人は、考えるから、人である。考えない人は、人というより、サル。だからといって、サルが人
より劣っているというのではない。サルのほうが、ひょっとしたら、人間より考えているかもしれ
ない。幼児だって、そうだ。
より劣っているというのではない。サルのほうが、ひょっとしたら、人間より考えているかもしれ
ない。幼児だって、そうだ。
私たちは、幼児イコール、幼稚と考えやすいが、これはとんでもない誤解。幼児は幼児なり
に、懸命に考えている。そういう幼児に出会うと、心底、感動を覚える。ずいぶんと前のことだ
が、こんなことがあった。
に、懸命に考えている。そういう幼児に出会うと、心底、感動を覚える。ずいぶんと前のことだ
が、こんなことがあった。
ある日、幼稚園へ行くと、1人の子ども(年長男児)が、地面を掘っていた。「何をしている
の?」と聞くと、その子どもは、こう言った。「石の赤ちゃんをさがしている」と。
の?」と聞くと、その子どもは、こう言った。「石の赤ちゃんをさがしている」と。
その子どもは、石は、土の中で生まれるものと思っていた。だから地面を掘れば、石の赤ち
ゃんがそこにあると思っていた。その幼児は、その幼児なりに、懸命にそう考えて、穴を掘って
いた。
ゃんがそこにあると思っていた。その幼児は、その幼児なりに、懸命にそう考えて、穴を掘って
いた。
レベルの問題ではない。たしかに私たちおとなから見れば、幼稚(?)な行動かもしれない
が、そこに、私は、生きる価値を見た。もしそれを否定するとなると、つまり私たち自身も、否定
されることになる。
が、そこに、私は、生きる価値を見た。もしそれを否定するとなると、つまり私たち自身も、否定
されることになる。
人間にしても、まだ進化の過程にある。1000年後、あるいは1万年後の人たちが、現在の
私たちを見て、幼稚だと思うかもしれない。しかしだからといって、それを批評することは、許さ
れない。それを許すということは、とりもなおさず、私たちが、私たち自身を否定することにな
る。
私たちを見て、幼稚だと思うかもしれない。しかしだからといって、それを批評することは、許さ
れない。それを許すということは、とりもなおさず、私たちが、私たち自身を否定することにな
る。
私たちは私たちで、懸命に生きている。考えている。内容は幼稚かもしれないが、そこに人が
生きる価値がある。それがわからなければ、ここに書いた幼児を頭の中で、もう一度、想像し
てみてほしい。
生きる価値がある。それがわからなければ、ここに書いた幼児を頭の中で、もう一度、想像し
てみてほしい。
●考えることのすばらしさ
ところで考えることは、宝さがしに似ている。ひとり荒野の中を歩いている。そこで小さな宝石
を見つけるのに似ている。小さな宝石かもしれないが、キラリと輝く。それを見つけたときは、う
れしい。ほんとうに、うれしい。
を見つけるのに似ている。小さな宝石かもしれないが、キラリと輝く。それを見つけたときは、う
れしい。ほんとうに、うれしい。
が、考えることは、けっして、楽な作業ではない。難解な数学の問題を前にして、その問題を
解くようなもの。考えることには、苦痛や苦労がともなう。しかもその問題は、必ずしも、解ける
とはかぎらない。解答用紙もない。
解くようなもの。考えることには、苦痛や苦労がともなう。しかもその問題は、必ずしも、解ける
とはかぎらない。解答用紙もない。
だからできるなら、考えないですませたいと思う。もっとも手っ取り早い方法は、宗教なら宗教
に身を寄せること。思想をだれかに注入してもらうこと。しかしそれは同時に、その人の「死」を
意味する。
に身を寄せること。思想をだれかに注入してもらうこと。しかしそれは同時に、その人の「死」を
意味する。
パスカルの言葉を借りるまでもなく、たとえか弱く、細いアシであっても、人は、自らの足で立
ち上がる。そこに人が生きる意味があるし、気高さも、そこから生まれる。しかし、その価値は
ある。
ち上がる。そこに人が生きる意味があるし、気高さも、そこから生まれる。しかし、その価値は
ある。
考える人からは、考えない人がどういうものか、よくわかる。反対に考えない人からは、考え
る人がどういうものか、わからないだろう。だからいって、私がその考える人というわけではな
い。つまりは相対的な立場でしかない。
る人がどういうものか、わからないだろう。だからいって、私がその考える人というわけではな
い。つまりは相対的な立場でしかない。
私よりものをよく考える人は、いくらでもいる。そういう人たちから見れば、私など、何も考えな
い部類の人間でしかない。しかし一度、考える習慣を身につけると、それまで見ていた世界が
一変する。
い部類の人間でしかない。しかし一度、考える習慣を身につけると、それまで見ていた世界が
一変する。
それは山登りに似ている。下から見ると低く見える山でも、登ってみると、意外と視野が広い
のには驚く。そのすばらしさは、山に登ったことがある人でないとわからない。
のには驚く。そのすばらしさは、山に登ったことがある人でないとわからない。
同じように、考えることによって、だれでも、思考の山に登ることができる。そしてその視野の
広さに驚くことができる。
広さに驚くことができる。
さあ、あなたも勇気を出して、考えてみよう。あなたも、きっとそのすばらしさを、実感するは
ず。……という結論で、この話は、おしまい。
ず。……という結論で、この話は、おしまい。
(以上、2007年10月記)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●再び、2011年12月(現在へ)
2007年に書いた原稿を、今、こうして読み直してみる。
内容的には、それ以前に、あちこちで書いたものを寄せ集めただけの原稿である。
で、ここが重要だが、そういう原稿を4年前に書きながら、ではその私は、この4年間で、4年
分の進歩をしたかということ。
分の進歩をしたかということ。
答は、「NO」に近い。
ただ情報を一方的に受け入れることだけは、2007年の当時も、今もしていない。
繰り返しになるが、あの3・11大震災を契機に、私は情報のもつ恐ろしさというか、洗脳される
ことの恐ろしさを、いやというほど、思い知らされた。
ことの恐ろしさを、いやというほど、思い知らされた。
政府にせよ、NHKにせよ、「ウソは言わないが、本当のことも言わない」。
その(本当のことも言わない部分)で、私たちは日々に少しずつ、洗脳されていく。
すでに今ですら、「原発事故は片づいた」と考えている人は多い。
少し前だが、中学3年生のOさんですら、そう言った。
学年でもトップクラスの成績を収めている子どもである。
私「何も片づいていないよ」
O「ウッソー!」
私「あのね、被害が出てくるのは、これからだよ。チェルノブイリでも被害が出始めたのは、2
年後から5年後。10年後にピークを迎えた。現在の今でも、チェルノブイリでは被害がつづい
ているよ」
年後から5年後。10年後にピークを迎えた。現在の今でも、チェルノブイリでは被害がつづい
ているよ」
O「今でも……?」
私「今でも、だ。そのとき汚染された子どもが母親になり、その母親が子ども産む。その子ども
に症状が現れている」と。
に症状が現れている」と。
不必要に心配することはない。
しかし必要以上に安心するのも、よくない。
今、「もう片づいた」と考えている子どもがいること自体、私たちが情報に操作されていることを
示す。
示す。
もろもろのどうでもよい情報の洪水の中で、思考力そのものを失っている。
つまり、それが、コ・ワ・イ。
●最後に
ここに書いたことを参考に、(物知りな子ども)と、(賢い子ども)について考えてみてほしい。
遠回しな言い方をしたが、このエッセーで書きたかったことは、この1点に尽きる。
情報が多いことイコール、思考力があるということではない。
情報と思考は、まったく別のもの。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教育
評論 はやし浩司 情報と思想 情報中毒 思考力 反芻と思考 はやし浩司 物知り もの
知り 賢い子ども 考える子ども はやし浩司 情報の反芻 はやし浩司 思想と情報 はやし
浩司 情報論)
評論 はやし浩司 情報と思想 情報中毒 思考力 反芻と思考 はやし浩司 物知り もの
知り 賢い子ども 考える子ども はやし浩司 情報の反芻 はやし浩司 思想と情報 はやし
浩司 情報論)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 18日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
【謹告】まぐまぐプレミアの購読料は、06年10月から、月額300円になります。
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page010.html
★★みなさんのご意見をお聞かせください。★★
(→をクリックして、アンケート用紙へ……)http://form1.fc2.com/form/?id=4749
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【撤退する外資企業・理由は翻訳料と言葉の壁】
●今ごろ、何?(今ごろ外国向けパンフ?)
今ごろ「海外投資家向けの情報発信を強化する」(東証)だって?
+++++++++++++++++++++
●英語教育
どこかのお馬鹿教授がこう言った。
「日本に英語教育は必要ない。英語よりも論語を教えろ」と。
その教授は、小学校での英語教育に猛烈に反対していた。
さらにこうも言っている。
「武士道こそが、日本人の精神的バックボーンである」と。
さらに自著の中で、「恥を教えれば、いじめはなくなる」とも。
子どもを直接教えたことのないお馬鹿教授の戯言(たわごと)。
たしかに今、小学校における英語教育は、さまざまな困難にぶつかっている。
しかし現代というこの時代にあって、「英語が必要ない」とは!
あきれると言うより、馬鹿げている。
私の意見ではない。
以下のような事実を、どれだけ多くの人が知っているだろうか。
●時事通信(2008年記事)より
「……さらに悲しむべきことに、東証一部の外国企業は、とうとう10社になってしまった(2010
年9月現在、(「日本の論点」・文藝春秋))。
年9月現在、(「日本の論点」・文藝春秋))。
ニューヨーク、ロンドン、シンガポールの証券取引所には、それぞれ数百社以上もの外国企業
が上場しているというのに、10社以下。
が上場しているというのに、10社以下。
理由は、翻訳料の負担」(同書)と。
また時事通信社は、「日本語による経営情報の開示など企業側の負担が大きく、
コストに見合う上場メリットが見いだせないことも外資の撤退に拍車を
かけている」と報道している(以上、2008年)。
その結果、外資企業は、拠点をシンガポールへ移してしまった。
アメリカへ行ったことがある人なら、みな知っている。
現在、アジアの経済ニュースは、(日本の経済ニュースも含めて)、シンガポール経由でアメリ
カへ入っている。
カへ入っている。
日本ではない。
シンガポールである。
そのこともあって、国民1人当たりのGDP所得では、日本はシンガポールにさえ、抜かれてい
る。
る。
以前、こんな原稿を書いた。
一部内容が重複するが、許してほしい。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●遅れた教育改革(以下、2009年3月記)
2002年1月の段階で、東証外国部に上場している外国企業は、たったの36社。
この数はピーク時の約3分の1(90年は125社)。
さらに2003年に入って、マクドナルド社やスイスのネスレ社、ドレスナー銀行やボルボも撤退
を決めている。
を決めている。
理由は「売り上げ減少」と「コスト高」。売り上げが減少したのは不況によるものだが、コスト高
の要因の第一は、翻訳料だそうだ(毎日新聞)。
の要因の第一は、翻訳料だそうだ(毎日新聞)。
悲しいかな英語がそのまま通用しない国だから、外国企業は何かにつけて日本語に翻訳しな
ければならない。
ければならない。
これに対して金融庁は、「投資家保護の観点から、上場先(日本)の母国語(日本語)による
情報開示は常識」(同新聞)と開き直っている。
情報開示は常識」(同新聞)と開き直っている。
日本が世界を相手に仕事をしようとすれば。
今どき英語など常識なのだ。
しかしその実力はアジアの中でも、あの北朝鮮とビリ二を争うしまつ。
日本より低い国はモンゴルだけだそうだ(TOEFL・国際英語検定試験で、日本人の成績は、1
65か国中、150位・99年)。
65か国中、150位・99年)。
日本の教育は世界の最高水準と思いたい気持ちはわからないでもないが、それは数学や理
科など、ある特定の科目に限った話。
科など、ある特定の科目に限った話。
日本の教育水準は、今ではさんたんたるもの。
今では分数の足し算、引き算ができない大学生など、珍しくも何ともない。「小学生レベルの問
題で、正解率は59%」(国立文系大学院生について調査、京大・西村)だそうだ。
題で、正解率は59%」(国立文系大学院生について調査、京大・西村)だそうだ。
●日本の現状
東大のある教授(理学部)が、こんなことを話してくれた。
「化学の分野には、1000近い分析方法が確立されている。
が、基本的に日本人が考えたものは、一つもない」と。
オーストラリアあたりでも、どの大学にも、ノーベル賞受賞者がゴロゴロしている。
しかし日本には数えるほどしかいない。
あの天下の東大には1人もいない。ちなみにアメリカだけでも、250人もの受賞者がいる。ヨー
ロッパ全体では、もっと多い。
ロッパ全体では、もっと多い。
「日本の教育は世界最高水準にある」と思うのはその人の勝手だが、その実態は、たいへん
お粗末。今では小学校の入学式当日からの学級崩壊は当たり前。
お粗末。今では小学校の入学式当日からの学級崩壊は当たり前。
はじめて小学校の参観日(小一)に行った母親は、こう言った。
「音楽の授業ということでしたが、まるでプロレスの授業でした」と。
●低下する教育力
こうした傾向は、中学にも、そして高校にも見られる。
やはり数年前だが、東京の都立高校の教師との対話集会に出席したことがある。
その席で、一人の教師が、こんなことを言った。
いわく、「うちの高校では、授業中、運動場でバイクに乗っているのがいる」と。
すると別の教師が、「運動場ならまだいいよ。
うちなんか、廊下でバイクに乗っているのがいる」と。
そこで私が「では、ほかの生徒たちは何をしているのですか」と聞くと、「みんな、自動車の教習
本を読んでいる」と。
本を読んでいる」と。
さらに大学もひどい。
大学が遊園地になったという話は、もう15年以上も前のこと。
日本では大学生のアルバイトは、ごく日常的な光景だが、それを見たアメリカの大学生はこう
言った。「ぼくたちには考えられない」と。
言った。「ぼくたちには考えられない」と。
大学制度そのものも、日本のばあい、疲弊している! つまり何だかんだといっても、「受験」
が、かろうじて日本の教育を支えている。
が、かろうじて日本の教育を支えている。
もしこの日本から受験制度が消えたら、進学塾はもちろんのこと、学校教育だってあぶない。
(以上、2009年3月記)
【教育改革】(以下、2009年3月記)
●この現実を、知っているか?
++++++++++++++++++++
日本の証券取引所から、外国企業の撤退が
つづいている。
現在、東京証券取引所の上場している外国企業は、
「16社と、ピークだった1991年(127社)の
8分の1減少した」
(時事通信・08・12・27)。
かつては127社あったのが、現在は、たったの16社。
(2002年には36社。3分の1に減った。
さらにそれから2分の1以下に減ったことになる。)
その理由として第一にあげられるのが、
「日本語による経営情報の開示など企業側の負担が大きく、
コストに見合う上場メリットが見いだせないこと」(同)
ということ。
+++++++++++++++++++
時事通信(12・27)は、つぎのように伝える。
++++++++++以下、時事通信より++++++++++
外国企業の上場廃止も英金融大手バークレイズなど9社に上り、前年(3社)の3倍になった。
株式取引の低迷に加え、日本語による経営情報の開示など企業側の負担が大きく、コストに
見合う上場メリットが見いだせないことも外資の撤退に拍車を掛けている。
見合う上場メリットが見いだせないことも外資の撤退に拍車を掛けている。
東証上場の外国企業は16社とピークだった1991年(127社)の8分の1に減少した。
(時事通信・12・27)
++++++++++以上、時事通信より++++++++++
日本から逃げた外資企業は、どこは行ったか?
今さら言うまでもなく、その行き先は、シンガポール。
すでに10年ほど前から、アメリカへ入ってくるアジアの経済ニュースは、
シンガポール経由。
東京ではない。
シンガポール。
東京の経済ニュースすら、シンガポール経由である。
いったい、こうした事実を、日本人はどれほど知っているのか。
深刻にとらえているのか。
言葉の問題だけではない。
シンガポールには、アメリカ本土とそっくりそのまま同じ、アメリカ人向けの
医療機関が整っている。
医療保険も、そのまま使える。
だからアメリカ人ならだれしも、アジアのどこかに拠点を構えるとしたら、
東京ではなく、シンガポールを選ぶ。
逆の立場で、考えてみればわかる。
もしあなたがヨーロッパに、あなたの会社の支店を作ろうと考えたとする。
そのときあなたは、言葉もちがい、医療制度もちがう、A国を選ぶだろうか。
それとも、言葉はそのまま使え、医療制度が同じ、B国を選ぶだろうか。
日本の証券取引所は、投資者保護(?)という名目のため、「経営情報の開示」
も含めて、ほとんどの書類を、日本語に翻訳することを義務づけている。
が、この負担が大きい。
日本における経費の大半が、翻訳にかかるという話を聞いたことがある。
だったら、翻訳を義務づけるのをやめればよいということになるのだが……。
こんなことをしていれば、そのうち日本の証券取引所から、外資系企業は
消えることになる。
(事実、すでに消えかかっているが……。)
日本がアジアの経済の中心地という話は、とうの昔の話。
「国際化」などという言葉は、この日本では、絵に描いた餅(もち)の
ようなもの。
日本のどこを、どのようにとったら、そう言えるのか。
東京へ行くにも、へき地の成田空港で降りなければならない。
どうして羽田空港であっては、いけないのか?
もう一度、私が6年前に書いた原稿を読んでみてほしい。
++++++++++++++++++
●日本から逃げる外資
今日、1月4日、日本の株価は、戦後最大とも言える、大暴落を経験した。
終値で616円安。
それについて、東証のS社長は、欧米やアジアの主要株式相場に比べて日本株が出遅れてい
ることに触れ、「(日本株の低迷は東京市場が)投資したい場所としての魅力を失いつつあるこ
とを示唆しているようにも映る」と危機感を募らせたという(日本経済新聞)。
ることに触れ、「(日本株の低迷は東京市場が)投資したい場所としての魅力を失いつつあるこ
とを示唆しているようにも映る」と危機感を募らせたという(日本経済新聞)。
この記事を読んで、数年前に書いた原稿を思い出した。
つぎのが、それである。
日付は、2002年になっている。
+++++++++++++++
【みんなで考えよう、日本の教育改革】(以下、2002年記)
(Open the door and liberate the market)
More and more foreign enterprises are going out of Japan. In 1990, there used to be 125
enterprises in Tokyo Exchange Market but in 2002 there were only 36 enterprises. The
number of enterprises are decreasing. The reason is very simple. It costs a lot of money for
translation from their languages to Japanese. We should open the door to the world and
liberate the market. Or more and more foreign enterprises will go out of Japan. Here is my
article which I wrote 6 years ago in 2002.
●遅れた教育改革
2002年1月の段階で、東証外国部に上場している外国企業は、たったの36社。
この数はピーク時の約3分の1(90年は125社)。
さらに2003年に入って、マクドナルド社やスイスのネスレ社、ドレスナー銀行やボルボも撤退
を決めている。
を決めている。
理由は「売り上げ減少」と「コスト高」。
売り上げが減少したのは不況によるものだが、コスト高の要因の第一は、翻訳料だそうだ(毎
日新聞)。
日新聞)。
悲しいかな英語がそのまま通用しない国だから、外国企業は何かにつけて日本語に翻訳しな
ければならない。
ければならない。
これに対して金融庁は、「投資家保護の観点から、上場先(日本)の母国語(日本語)による
情報開示は常識」(同新聞)と開き直っている。
情報開示は常識」(同新聞)と開き直っている。
日本が世界を相手に仕事をしようとすれば。
今どき英語など常識なのだ。しかしその実力はアジアの中でも、あの北朝鮮とビリ二を争うしま
つ。
つ。
日本より低い国はモンゴルだけだそうだ(TOEFL・国際英語検定試験で、日本人の成績は、1
65か国中、150位・99年)。
65か国中、150位・99年)。
日本の教育は世界の最高水準と思いたい気持ちはわからないでもないが、それは数学や理
科など、ある特定の科目に限った話。
日本の教育水準は、今ではさんたんたるもの。
今では分数の足し算、引き算ができない大学生など、珍しくも何ともない。
「小学生レベルの問題で、正解率は59%」(国立文系大学院生について調査、京大・西村)だ
そうだ。
そうだ。
●日本の現状
東大のある教授(理学部)が、こんなことを話してくれた。
「化学の分野には、1000近い分析方法が確立されている。
が、基本的に日本人が考えたものは、一つもない」と。
オーストラリアあたりでも、どの大学にも、ノーベル賞受賞者がゴロゴロしている。
しかし日本には数えるほどしかいない。
あの天下の東大には1人もいない。
ちなみにアメリカだけでも、250人もの受賞者がいる。
ヨーロッパ全体では、もっと多い。
「日本の教育は世界最高水準にある」と思うのはその人の勝手だが、その実態は、たいへん
お粗末。
お粗末。
今では小学校の入学式当日からの学級崩壊は当たり前。
はじめて小学校の参観日(小一)に行った母親は、こう言った。
「音楽の授業ということでしたが、まるでプロレスの授業でした」と。
●低下する教育力
こうした傾向は、中学にも、そして高校にも見られる。
やはり数年前だが、東京の都立高校の教師との対話集会に出席したことがある。
その席で、一人の教師が、こんなことを言った。
いわく、「うちの高校では、授業中、運動場でバイクに乗っているのがいる」と。
すると別の教師が、「運動場ならまだいいよ。
うちなんか、廊下でバイクに乗っているのがいる」と。
そこで私が「では、ほかの生徒たちは何をしているのですか」と聞くと、「みんな、自動車の教習
本を読んでいる」と。
本を読んでいる」と。
さらに大学もひどい。
大学が遊園地になったという話は、もう15年以上も前のこと。
日本では大学生のアルバイトは、ごく日常的な光景だが、それを見たアメリカの大学生はこう
言った。
言った。
「ぼくたちには考えられない」と。
大学制度そのものも、日本のばあい、疲弊している! つまり何だかんだといっても、「受験」
が、かろうじて日本の教育を支えている。
が、かろうじて日本の教育を支えている。
もしこの日本から受験制度が消えたら、進学塾はもちろんのこと、学校教育そのものも崩壊す
る。
る。
確かに一部の学生は猛烈に勉強する。
しかしそれはあくまでも「一部」。
内閣府の調査でも、「教育は悪い方向に向かっている」と答えた人は、26%もいる(2000
年)。
年)。
98年の調査よりも8%もふえた。むべなるかな、である。
●規制緩和は教育から
日本の銀行は、護送船団方式でつぶれた。
政府の手厚い保護を受け、その中でヌクヌクと生きてきたため、国際競争力をなくしてしまっ
た。
た。
しかし日本の教育は、銀行の比ではない。
護送船団ならぬ、丸抱え方式。
教育というのは、20年先、30年先を見越して、「形」を作らねばならない。
が、文部科学省の教育改革は、すべて後手後手。南オーストラリア州にしても、すでに10年以
上も前から、小学3年生からコンピュータの授業をしている。
上も前から、小学3年生からコンピュータの授業をしている。
メルボルン市にある、ほとんどのグラマースクールでは、中学1年で、中国語、フランス語、ドイ
ツ語、インドネシア語、日本語の中から、1科目選択できるようになっている。
ツ語、インドネシア語、日本語の中から、1科目選択できるようになっている。
もちろん数学、英語、科学、地理、歴史などの科目もあるが、ほかに宗教、体育、芸術、コンピ
ュータの科目もある。
ュータの科目もある。
芸術は、ドラマ、音楽、写真、美術の各科目に分かれ、さらに環境保護の科目もある。
もう一つ「キャンプ」という科目があったので、電話で問い合わせると、それも必須科目の一つ
とのこと(メルボルン・ウェズリー・グラマースクール)。
とのこと(メルボルン・ウェズリー・グラマースクール)。
さらにこんなニュースも伝わっている。
外国の大学や高校で日本語を学ぶ学生が、急減しているという。
カナダのバンクーバーで日本語学校の校長をしているM氏は、こう教えてくれた。
「どこの高等学校でも、日本語クラスの生徒が減っています。
日本語クラスを閉鎖した学校もあります」と。
こういう現状を、日本人はいったいどれくらい知っているのだろうか。
●規制緩和が必要なのは教育界
いろいろ言われているが、地方分権、規制緩和が一番必要なのは、実は教育の世界。
もっとはっきり言えば、文部科学省による中央集権体制を解体する。
地方に任すものは地方に任す。
せめて県単位に任す。
だいたいにおいて、頭ガチガチの文部官僚たちが、日本の教育を支配するほうがおかしい。
日本では明治以来、「教育というのはそういうものだ」と思っている人が多い。
が、それこそまさに世界の非常識。
あの富国強兵時代の亡霊が、いまだに日本の教育界をのさばっている!
今まではよかった。「社会に役立つ人間」「立派な社会人」という出世主義のもと、優良な会社
人間を作ることができた。
人間を作ることができた。
「国のために命を落とせ」という教育が、姿を変えて、「会社のために命を落とせ」という教育に
置きかわった。
置きかわった。
企業戦士は、そういう教育の中から生まれた。
が、これからはそういう時代ではない。
日本が国際社会で、「ふつうの国」「ふつうの国民」と認められるためには、今までのような教育
観は、もう通用しない。
観は、もう通用しない。
いや、それとて、もう手遅れなのかもしれない。
いや、こうした私の意見に対して、D氏(65歳・私立小学校理事長)はこう言った。
「まだ日本語もよくわからない子どもに、英語を教える必要はない」と。
つまり小学校での英語教育は、ムダ、と。
しかしこの論法がまかり通るなら、こうも言える。
「日本もまだよく旅行していないのに、外国旅行をするのはムダ」「地球のこともよくわかってい
ないのに、火星に探査機を送るのはムダ」と。
ないのに、火星に探査機を送るのはムダ」と。
私がそう言うと、D氏は、「国語の時間をさいてまで英語を教える必要はない。
しっかりとした日本語が身についてから、英語の勉強をしても遅くはない」と。
●多様な未来に順応できるようにするのが教育
これについて議論を深める前に、こんな事実がある。
アメリカの中南部の各州の小学校では、公立小学校ですら、カリキュラムを教師と親が相談し
ながら決めている。
ながら決めている。
たとえばルイサ・E・ペリット公立小学校(アーカンソー州・アーカデルフィア)では、4歳児から子
どを預かり、コンピュータの授業をしている。
どを預かり、コンピュータの授業をしている。
近くのヘンダーソン州立大学で講師をしている知人にそのことについて聞くと、こう教えてくれ
た。
た。
「アメリカでは、多様な社会にフレキシブル(柔軟)に対応できる子どもを育てるのが、教育の目
標だ」と。
標だ」と。
事情はイギリスも同じで、在日イギリス大使館のS・ジャック氏も次のように述べている。「(教
育の目的は)多様な未来に対応できる子どもたちを育てること」(長野県経営者協会会合の
席)と。
育の目的は)多様な未来に対応できる子どもたちを育てること」(長野県経営者協会会合の
席)と。
オーストラリアのほか、ドイツやカナダでも、学外クラブが発達していて、子どもたちは学校が
終わると、中国語クラブや日本語クラブへ通っている。こういう時代に、「英語を教える必要は
ない」とは!
終わると、中国語クラブや日本語クラブへ通っている。こういう時代に、「英語を教える必要は
ない」とは!
●文法学者が作った体系
ただ英語教育と言っても、問題がないわけではない。
日本の英語教育は、将来英語の文法学者になるには、すぐれた体系をもっている。
数学も国語もそうだ。
将来その道の学者になるには、すぐれた体系をもっている。
理由は簡単。もともとその道の学者が作った体系だからだ。
だからおもしろくない。だから役に立たない。
こういう教育を「教育」と思い込まされている日本人はかわいそうだ。
子どもたちはもっとかわいそうだ。
たとえば英語という科目にしても、大切なことは、文字や言葉を使って、いかにして自分の意思
を相手に正確に伝えるか、だ。
を相手に正確に伝えるか、だ。
それを動詞だの、3人称単数だの、そんなことばかりにこだわっているから、子どもたちはます
ます英語嫌いになる。
ます英語嫌いになる。
ちなみに中学1年の入学時には、ほとんどの子どもが「英語、好き」と答える。
が、一年の終わりには、ほとんどの子どもが、「英語、嫌い」と答える。
●数学だって、無罪ではない
数学だって、無罪ではない。あの一次方程式や二次方程式にしても、それほど大切なものな
のか。
のか。
さらに進んで、三角形の合同、さらには二次関数や円の性質が、それほど大切なものなのか。
仮に大切なものだとしても、そういうものが、実生活でどれほど役に立つというのか。
こうした教育を正当化する人は、「基礎学力」という言葉を使って、弁護する。
「社会生活を営む上で必要な基礎学力だ」と。
もしそうならそうで、一度子どもたちに、「それがどう必要なのか」、それを説明してほしい。
「なぜ中学1年で一次方程式を学び、3年で二次方程式を学ぶのか。
また学ばねばならないのか」と、それを説明してほしい。
その説明がないまま、問答無用式に上から押しつけても、子どもたちは納得しないだろう。
現に今、中学生の56・5%が、この数学も含めて、「どうしてこんなことを勉強しなければいけ
ないのかと思う」と、疑問に感じているという(ベネッセコーポレーション・「第3回学習基本調
査」2001年)。
ないのかと思う」と、疑問に感じているという(ベネッセコーポレーション・「第3回学習基本調
査」2001年)。
●教育を自由化せよ
さてさきほどの話。
英語教育がムダとか、ムダでないという議論そのものが、意味がない。
こういう議論そのものが、学校万能主義、学校絶対主義の上にのっている。
早くから英語を教えたい親がいる。早くから教えたくない親もいる。
早くから英語を学びたい子どもがいる。
早くから学びたくない子どももいる。
早くから英語を教えるべきだという人がいる。
早くから教える必要はないという人もいる。
大切なことは、それぞれの自由にすればよい。
今、何が問題かと言えば、学校の先生がやる気をなくしてしまっていることだ。
雑務、雑務、その上、また雑務。
しつけから家庭教育まで押しつけられて、学校の先生が今まさに窒息しようとしている。
ある教師(小学5年担任、女性)はこう言った。
「授業中だけが、体を休める場所です」と。
「子どもの生きるの死ぬのという問題をかかえて、何が教材研究ですか」とはき捨てた教師も
いた。
いた。
そのためにはオーストラリアやドイツ、カナダのようにクラブ制にすればよい。
またそれができる環境をつくればよい。
「はじめに学校ありき」ではなく、「はじめに子どもありき」という発想で考える。
それがこれからの教育のあるべき姿ではないのか。
また教師の雑務について、たとえばカナダでは、教師から雑務を完全に解放している。
教師は学校での教育には責任をもつが、教室を離れたところでは一切、責任をもたないという
制度が徹底している。
制度が徹底している。
教師は自分の住所はおろか、電話番号すら、親には教えない。
だからたとえば親がその教師と連絡をとりたいときは、親はまず学校に電話をする。するとし
ばらくすると、教師のほうから親に電話がかかってくる。
ばらくすると、教師のほうから親に電話がかかってくる。
こういう方法がよいのか悪いのかについては、議論が分かれるところだが、しかし実際には、
そういう国のほうが多いことも忘れてはいけない。
そういう国のほうが多いことも忘れてはいけない。
+++++++++++++++
6年前に書いた原稿だが、この6年の間に、日本の教育も大きく変わった。
しかし、それでは不十分。
同じように、日本の経済構造も、旧態依然のまま。東証のS社長の言葉が、それを如実に表
している。(以上、2002年記)
している。(以上、2002年記)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
(注※)東京証券取引所に株式を上場しているオランダの生命保険大手とスイスの大手金融
グループが、来月までに相次いで上場を取りやめることになり、東証で株式を取り引き
グループが、来月までに相次いで上場を取りやめることになり、東証で株式を取り引き
できる外国企業の数は、ピーク時の10分の1まで減少することになりました。
東京証券取引所では、「1部」に株式を上場している外国企業のうち、▽オランダの
大手生命保険会社、「AEGON」が27日、上場廃止となったのに続いて▽スイスの
大手金融グループの「UBS」も来月16日に上場廃止になることが決まっています。
この2社は日本でビジネスは続けますが、これで、東証で株式を取り引きできる
外国企業は13社となり、最も多い127社が上場していた平成3年の時と比べますと、
およそ10分の1にまで落ち込むことになります。
(以上、BIZ速報HP・2010年3月29日より)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
(注※)(参考資料:東京証券取引所の弁明とウソ)(2011年12月12日)
市場開設以降、2004年10月まで、上場外国会社の形態は全て本国市場に上場している重複
上場でした。
上場でした。
この重複上場の形態は、ITが進展した今日、売買が本国市場に集中する傾向が顕著である
ため、重複上場の主目的は、重複上場国における知名度維持・向上や現地通貨での資金調
達にあると一般に考えられます。
ため、重複上場の主目的は、重複上場国における知名度維持・向上や現地通貨での資金調
達にあると一般に考えられます。
これまでの東証からの上場廃止外国会社を見ても、売買高の少なさを主たる理由に挙げた会
社が最も多く、重複上場会社数の減少は、今日の環境下にあっては、ある意味必然的な面も
ありました。
社が最も多く、重複上場会社数の減少は、今日の環境下にあっては、ある意味必然的な面も
ありました。
そこで、東証は、外国会社にも市場機能を十分提供できるよう、2000年以降においては、本国
に上場していない外国会社も上場のターゲットと捉え、特に、アジア地域における資金需要旺
盛な会社に焦点を当ててプロモーション活動を展開し始めました。
に上場していない外国会社も上場のターゲットと捉え、特に、アジア地域における資金需要旺
盛な会社に焦点を当ててプロモーション活動を展開し始めました。
単独上場会社としては、新華ホールディングス(2004年上場)、ジャパンインベスト・グループ
(2006年上場)及びチャイナ・ボーチー(2007年上場)があります。
(2006年上場)及びチャイナ・ボーチー(2007年上場)があります。
2011年3月末現在、単独上場外国会社数は3社となっています。
(以上、東京証券取引所HPより)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●現状(2011年12月12日記)
現在、単独上場外国企業は、たったの「3社」(東京証券取引所)!
東京証券取引所は、こう述べている。
「これまでの東証からの上場廃止外国会社を見ても、売買高の少なさを主たる理由に挙げた
会社が最も多く、重複上場会社数の減少は、今日の環境下にあっては、ある意味必然的な面
もありました」と。
会社が最も多く、重複上場会社数の減少は、今日の環境下にあっては、ある意味必然的な面
もありました」と。
簡単に言えば、外資企業は、規制と規則、それに翻訳料(時事通信)から逃げた。
それを今ごろになって、「海外向け情報誌」?
Bloomberg(2011ー12ー12)の記事を紹介する。
私はこの記事を読んで、「今ごろ?」と、思わず笑ってしまった。
「……12月12日(ブルームバーグ):11月に経営統合を発表した東京証券取引所と大阪証券取
引所が、海外投資家向けの情報発信を強化する。
引所が、海外投資家向けの情報発信を強化する。
国際的な存在感が低下傾向にある日本の株式市場、企業の魅力を訴えることで海外の取引
所に対抗し、日本市場の活性化につなげたい考え。
所に対抗し、日本市場の活性化につなげたい考え。
東証は海外向けの広報誌を創刊、大証は初めてベンチャー企業の海外IR活動を主催する」
(2011ー12-12、Bloomberg)より。
(2011ー12-12、Bloomberg)より。
今まで海外情報誌すらなかった?
この記事を裏から読むと、そうなる。
教育界もそうだが、経済界も、そう。
日本の経済が好調なとき、その上で、あぐらをかいてしまった。
未来を見据え、その準備をすることを忘れてしまった。
その結果が、今。
まことにもって悔しい話だが、私はすでに2000年ごろから、この事実に気づいていた。
原稿も書いてきた。
恐らくこの原稿も無視され、さらに10年後、つまり2020年には、日本の衰退は、より確実な
ものになるだろう。
ものになるだろう。
最後に一言!
いいかげんに、日本よ、日本人よ、目を覚ませ!!!
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 外資企業 東京証券取引所 外
資企業 逃げる外資 はやし浩司 理由は翻訳料 閉鎖主義 鎖国主義 はやし浩司 英語
教育 英語教育論 低下する教育力 東証外国部 上場企業の撤退 はやし浩司撤退する外
資 たったの3社 はやし浩司 TOEFL 北朝鮮とビリ2)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 外資企業 東京証券取引所 外
資企業 逃げる外資 はやし浩司 理由は翻訳料 閉鎖主義 鎖国主義 はやし浩司 英語
教育 英語教育論 低下する教育力 東証外国部 上場企業の撤退 はやし浩司撤退する外
資 たったの3社 はやし浩司 TOEFL 北朝鮮とビリ2)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●はやし浩司 2011-12-11
++++++++++++++++++++++
鳥の餌を庭にまく。
犬のハナが、それを遠巻きにしてながめる。
いつもの光景。
見慣れた光景。
私が居間に戻ると、ハナがそれを食べ始める。
それを見て、ワイフが、こう叫ぶ。
「ハナ! ハナ!」と。
ハナは、一瞬、食べるのをためらうが、また食べ始める。
今度は私が窓を開け、「ハナ! それは鳥の食べ物だ!」と。
ハナはいそいそと、自分の犬小屋に戻っていく。
のどかな冬の日。
空には雲ひとつない。
まっすぐ伸びた白い光線が、木々の葉の上で照り返す。
……居間に入ってきて、ワイフがこう、こぼす。
「犬が、鳥の餌を食べるなんて……」と。
いつも同じ言葉を繰り返す。
++++++++++++++++++++++
●発語障害
こう書くからといって、どうか誤解しないでほしい。
私は幼児を教えて40年以上になる。
が、子どもの発語障害を、私の側から問題にしたことは、一度もない。
知っていても、知らぬフリ。
知らぬフリをして、指導する。
親から相談があったときだけ、それに応じて、発語障害の話をする。
つまり発語障害などというのは、どうでもよい部類の問題。
私はふだんは、そう考えている。
で、その発語障害で多いのが、「サ行障害児」。
「サカナ」を、「シャカナ」と発声したりする。
もっともサ行障害児は、数も多い。
4歳児についてみるなら、20~30%に、その傾向がみられる。
私自身も、サ行障害児ではなかったかと思う。
いまだに「サシスセソ」の発音が苦手。
直りにくいのが、カ行障害児。
「5個」を、「ドット」と発声したりする。
が、そうした発語障害に当てはまらない若い人たちがふえている。
しかも女性ばかり。
実におかしな話し方をする。
息と音が鼻に抜ける。
たとえば「メリー・クリスマス」も、「フムムリー・クリスモォース」などと発音したりする。
もしそんな発声する子どもがいたら、私はただちにそれを正そうとするだろう。
が、子どもには、そんな発声するのはいない。
だからどの発語障害児にも、当てはまらない。
つまりそういう発声は、成人になるにつれ、身につくものと考えてよい。
それにしても、聞きづらい。
本人は、それが「都会風」とでも誤解しているのかもしれない。
……それにしても、へん。
おかしい。
日本語そのものが壊れ始めている。
ついでに発音そのものまで、壊れ始めている。
●列を作らない若者たち
ついでにもうひとつ、気になっていることがある。
先日、ある演奏会のチケットを買いに行ったときのこと。
電話で先に予約したが、チケットはその日、手にすることになっていた。
そこでのこと。
みなは一列に並んでいた。
が、途中に、5人組の若者たちがいた。
彼らだけは、列に並ぼうともしない。
一度、係の人が、「最後尾」というプラカードをもって、やってきた。
そのとき「まっすぐ並んでください」と注意した。
が、それでも、そのまま。
平気で円陣を作り、話しこんでいた。
こうした現象は、今、いたるところで起きている。
駅のプラットフォーム、ショッピングセンター、郵便局などなど。
よく話題になる。
「最近の若い人は、列を作って並ばない」と。
が、それが悪いかというと、そうでもない(?)。
その逆もある。
長く外国の日本人学校で教壇に立っていた、K先生(現在、小学校教諭)が、こう話してくれ
た。
た。
「日本の子どもたちが2列になり、校舎へ入っていくのを見たとき、ぞっとしました」と。
子どもたちが機械仕掛けのロボットに見えたというのだ。
が、そのことと、そうしたチケット売り場で、列を作らないというのは、話は別。
欧米人のばあい、学校での様子は知らないが、そういった場所ではきちんと列を作る。
で、そういう若者が途中にいると、列の秩序、そのものが乱れる。
私自身も、先のプラカードを見るまで、どこか最後尾なのか、わからなかった。
……これも社会現象のひとつと考えてよいのではないか。
世の中、私たちが知らないところで、脳レベルの異変が起きつつある。
●EU金融危機
イタリア政府が、超緊縮政策を発表した(12月10日)。
EU各国は、それを歓迎した。
が、そうでなくても、景気は低迷している。
「緊縮」すれば、景気はますます悪くなる。
ゆいいつ利点があるとすれば、EUからの援助を受けやすくなること。
たとえて言うなら借金漬けの男が、銀行にこう約束した。
「これから支出を抑え、ぜいたくをひかえます」
「だからどうか助けてください」と。
イタリアも、そこまで追い詰められている。
が、それでイタリアが立ち直るとは、だれも思っていない。
つまり一時しのぎ。
EUの金融危機は、それほどまでに深刻。
●「週刊現代」誌
今朝の広告によれば、(今週号は、まだ買っていない)、「週刊現代」には、こうある。
「日本は倒産する。国債を買うのはバカだ」(「週刊現代」)と。
事実は、その通りだから、反論のしようがない。
さらに、こんな記事も。
「年金運用、またも大失敗!」「わずか3か月で、約4兆円負けた!!」と。
興味はあるが、今週号は多分、買わない。
国債は、もっていない。
年金は、もとからアテにしていない。
●「葬式を見ればその人がわかる」(週刊現代)
もうひとつこんな記事も。
「有名も肩書も関係なし。これがあなたの人生の評価だったのです……」(週刊現代)と。
記事は読んでないが、有名であっても、また肩書きがあっても、さみしい死に方をする人はいく
らでもいる……というような記事を載せているらしい。
らでもいる……というような記事を載せているらしい。
が、この意見はおかしい。
●評価
葬式でその人の評価は決まらない。
その人がどんな死に方をしようが、またその葬式がどうであろうが、気にしてはいけない。
日本民族のいやらしさというか、人の価値を裏から見て判断する。
中身ではなく、外見。
表ではなく、裏。
その集約されたものが、葬式。
どこかのカルト教団では、さかんにこう教えている。
「死に顔を見れば、その人の人生がわかる」と。
どこかイヤーナ、言い方!
「有名も肩書も関係なし」というのは、当然。
関係があるとすれば、利害関係と地縁関係。
そのことは派手な葬式をみれば、よくわかる。
何かの組織の「長」の葬式は、派手。
地縁の深い人の葬式は、派手。
この先、60%の人が孤独死、無縁死を迎えるという。
発見までの平均日数は、6日。
派手な葬式どころか、葬式そのものも期待できない。
だったら、居直るしかない。
葬式不要論、おおいに結構。
さみしい葬式で、何が悪い!
●第14回オムニバスタウン展
今朝の新聞(12月11日・中日新聞)に、第14回オムニバスタウン展の表彰式の写真が載
っていた。
っていた。
小学生以下の子どもたち、3793点の応募があったという。
その上位入賞者(20名)の中に、森田さん、大野君の名前があった。
うれしかった。
私の教え子たちである。
おめでとう。
●第九演奏会
これから駅前のアクトタワーで催される、第九演奏会を聴きに行ってくる。
演奏は東京フィル、それに合唱は、地元・浜松のフロイデ合唱団。
それもあって、昨夜は、第九のリハーサルを何度もした。
YOUTUBEの第九(4楽章)に合わせ、何度も歌った。
準備万端、整った。
さあ、行こう!
●第九演奏会
よかった!
第3楽章が終わり、第4楽章に入ったところで、いつものように涙がこぼれてきた。
そしてあの歌……。
♪……おお、友よ、これらのような音ではなく、
もっと快い、歓びに満ちた調べを歌おうではないか……!
冒頭のこの部分は、ベートーヴェン自身が作詞したものと言われている(パンフ)。
が、当のベートーヴェンは、家族の愛にも恵まれず、孤独な死を迎えている。
先の話につなげるなら、「孤独死」。
それに近い形で、死んでいる。
それにベートーヴェンには、友らしい友もいなかった。
そのベートーヴェンが、「♪おお、友よ!」と歌う。
繰り返す。
「週刊現代」は、「葬式を見ればその人がわかる」と説く。
が、この説は、明らかにまちがっている。
どこかのカルト教団や、ヤクザの世界の人たちの葬式を見れば、それがわかる。
彼らは葬式だけは、やたらと派手にやる。
第九を聴きながら、別の心でそんなことを考えた。
●私は私
その人の評価は、葬式を見ればわかる?
ならば聞くが、だれにわかるのか?
どう、わかるのか?
わかったところで、どうなるというのか?
この前、鎌倉で田丸謙二先生に会ったとき、先生はこう言った。
「私は葬式などしてほしくありません。
病院から火葬場まで、直葬で結構です」と。
で、私が「先生はそう言っても、まわりの人がそうはさせませんよ」と言うと、先生はさらに強く
こう言った。
こう言った。
「娘たちにも、しっかりとそう言ってあります」と。
偉大な先生というのは、田丸謙二先生のような人物をいう。
要するに、私は私。
あなたはあなた。
葬式などという結果など気にせず、ただひたすら前だけを見て生きていけばよい。
●12月11日
今日も、もうすぐ終わる。
時刻は今、午後6時16分。
そうそう帰りの車の中で、ワイフがこう言った。
「あなたももう一度、第九を歌ってみたら?」と。
が、私はこう言った。
「時間が、ない。ぼくの寿命も、よくて残り15年。もう回り道をしているヒマはない」と。
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 16日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page009.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【封建時代の清算】(あの江戸時代を不必要に美化してはいけない!)
●恐怖政治(双葉社「江戸残酷物語」を読んで)
+++++++++++++++++++++
江戸時代が、どういう時代であったか。
日本の法制史を少しでも学んだことがある人なら、
それを知っている。
江戸時代という時代は、世界でも類を見ないほど、
暗黒かつ、恐怖政治の時代であった。
たとえば不義密通(不倫)程度のことでも、斬首刑!
その江戸時代の人たちにすれば、現代の北朝鮮ですら、
「天国」に思えるだろう。
裁判にしても、まさに「形」だけ。
自白と拷問。
拷問と自白。
人権の「ジ」の字もない。
それだけで、無数の人たちが、公開で処刑されていった。
また江戸時代の刑罰がいかにすさまじいものであったかは、
今さらここに、改めて書くまでもない。
+++++++++++++++++++++
●徳川家康
あの徳川家康にしても、この静岡県では、「神様」のように扱われている。
それもそのはず。
300年(265年)に渡る江戸時代という時代を通し、徹底的に美化された。
その一方で、徳川家康にまつわる都合の悪い事実は、繰り返し抹消された。
が、証拠がないわけではない。
あの築山殿(徳川家康の正室)にしても、残虐極まりない女性であったという。
侍女の虐待、拷問なども、日常茶飯事。
その息子の信康も、これまたしかり。
「領民を面白半分に殺害することも、たびたびあった」という(「江戸残酷物語」(双葉社))。
徳川家自身が記録した、『当代記』『三河後風土記』などに、記録されているという(同)。
……こう書くと、「林は、負の部分にばかり気を取られている」と批評する人がいるかもしれな
い。
い。
が、事実は、まったくの逆。
その築山にしても、(静岡県では、哀悼の念をこめ、「築山御前」と呼ぶ)、家康の命令により、
佐鳴湖畔(浜松市の西にある湖)のほとりで、殺害されている。
佐鳴湖畔(浜松市の西にある湖)のほとりで、殺害されている。
表向きは、織田信長の命によって殺されたということになっている。
が、実際には、徳川家康が織田信長を悪者にしたて、自ら殺害を企て殺害した。……という説
もある。
もある。
●疑問
私が織田信長に最初に疑問を感じたのは、高校生のときのことだった。
郷里に岐阜城という、山城がある。
その城を訪れたときのこと。
そこに織田信長についての記述が、パネル形式で、壁に張ってあった。
そのひとつに、「織田信長は、毎日、長良川の河畔で、5~60人もの人を処刑した」とあった。
数字については、記憶によるものだから、確かではない。
またいつどのようなときに、織田信長がそうしたのかも覚えていない。
しかしその記述を目にしたとき、それまでの私がもっていた「信長観」は、吹き飛んでしまった。
事実、織田信長は、冷酷無比、残忍な暴君であったようだ。
もうひとつ、こんな例もある。
●新居の関所跡
浜松市の西に、「新居の関所跡」というのが、保存されている。
江戸時代という時代がどういう時代であったかを知る、ひとつの手掛かりになる。
以前にもそれについて書いたことがあるので、その原稿をさがしてみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
2000年ごろ書いた原稿より。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●新居の関所
浜名湖の南西にある新居町には、新居関所がある。
関所の中でも唯一現存する関所ということだが、それほど大きさを感じさせない関所である。
江戸時代という時代のスケールがそのまま反映されていると考えてよいが、驚くのは、その「き
びしさ」。
びしさ」。
関所破りがいかに重罪であったかは、かかげられた史料を読めばわかる。
つかまれば死罪だが、その関所破りを助けたものも同程度の罪が科せられた。
当時は、家族もろとも処刑されるのが、習わしであった。
それだけではない。
たとえば新居の関所破りをして、伊豆でつかまった男は、死体を塩漬けにして新居までもどさ
れ、そこでさらにはりつけに処せられたという記録も残っている※。
れ、そこでさらにはりつけに処せられたという記録も残っている※。
移動の自由がいかにきびしく制限されていたかが、この事実ひとつをとっても、よくわかる。
が、さらに驚いたことがある。
あちこちに史料と並んで、その史料館のだれかによるコメントが書き添えてある。
その中の随所で、「江戸時代は自由であった」「意外と自由であった」「庶民は自由を楽しんで
いた」というような記述があったことである。
いた」というような記述があったことである。
当然といえば当然だが、こうした関所に対する批判的な記事はいっさいなかった。
私と女房は、読んでいて、あまりのチグハグさに思わず笑いだしてしまった。
「江戸時代が自由な時代だったア?」と。
●北朝鮮
もともと自由など知らない人たちだから、こうしたきゅうくつな時代にいても、それをきゅうくつ
とは思わなかっただろうということは、私にもわかる。
とは思わなかっただろうということは、私にもわかる。
あの北朝鮮の人たちだって、「私たちは自由だ」(報道)と言っている。
つまりあの人たちはあの人たちで、「自分たちの国は民主主義国家だ」と主張している。
(北朝鮮の正式国名は、朝鮮人民民主主義国家。)
現在の私たちが、「江戸時代は庶民文化が花を開いた自由な時代であった」(パネルのコメン
ト)と言うことは、「北朝鮮が自由な国だ」というのと同じくらい、おかしなことである。
ト)と言うことは、「北朝鮮が自由な国だ」というのと同じくらい、おかしなことである。
私たちが知りたいのは、江戸時代がいかに暗黒かつ恐怖政治の時代であったかということ。
新居の関所はその象徴ということになる。
たまたま館員の人に説明を受けたが、「番頭は、岡崎藩の家老級の人だった」とか、「新居町
だけが舟渡しを許された」とか、どこか誇らしげであったのが気になる。
だけが舟渡しを許された」とか、どこか誇らしげであったのが気になる。
関所がそれくらい身分の高い人によって守られ、新居町が特権にあずかっていたということだ
が、批判の対象にこそなれ、何ら自慢すべきことではない。
が、批判の対象にこそなれ、何ら自慢すべきことではない。
たいへん否定的なことを書いたが、皆さんも一度はあの関所を訪れてみるとよい。
(そういう意味では、たいへん存在価値のある遺跡である。
それはまちがいない。)
そしてその関所をとおして、江戸時代がどういう時代であったかを、ほんの少しでもよいから肌
で感じてみたらよい。
で感じてみたらよい。
何度もいうが、歴史は歴史だからそれなりの評価はしなければならない。
しかし決して美化してはいけない。美化すればするほど、時代は過去へと逆行する。
そういえば関所の中には、これまた美しい人形が八体ほど並べられていたが、まるで歌舞伎
役者のように美しかった。
役者のように美しかった。
私がここでいう、それこそまさに美化の象徴と考えてよい。
(※こまかい点は、記憶によるものなので、事実と違うかもしれない。)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●武士道を美化する人たち
いまだに武士道なるものを美化する人が多いのには、驚かされる。
「武士道こそ、日本人の精神的根幹である」と主張してやまない。
が、本当に、そうか。
そう考えてよいのか。
これについても、今までに、たくさんの原稿を書いてきた。
さがしてみる。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
2009年ごろ書いた原稿が見つかった。
少し長いが、よく読んでほしい。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●死の美学と隷属意識
武士道の根幹は、死の美学と隷属意識。
++++++++++++++++++++
●武士道(1)
+++++++++++++++++++++++
けっして、死を美化してはいけない。
生を美化することはあっても、死を美化してはいけない。
私たちは、まず、生きることを考える。
生きて生きて、生き抜く。
死はその結果としてやってくるかもしれないが、
そのときは、そのとき。
死の向こうには、何もない。
そこは太虚の世界。
だから、死を美化してはいけない。
武士道を一言で言えば、その底流にあるのは、
死の美学ということになる。
武士の象徴が、「刀」にあるとするなら、その
刀は、人を殺すためのもの。
この原点を踏み外して、武士を論じてはならない。
武士道を論じてはならない。
新渡戸稲造は、「武士道」の中で、あの赤穂浪士を、
最大限の言葉を使って、称賛している(「武士道の世界」
イースト・プレス)。
「義士と呼ばれるこの正直な率直な男子たちの徳は、
宝石のように光り輝き、人々のもっとも高く、褒め
讃えたものだったのである」と。
+++++++++++++++++++++
●真の勇者(?)
新渡戸稲造は、真の勇者について、こうも書いている。
「戦いに臨んで討ち死にすることは、難しいことではない。
それはどのような野人でもできることである。
しかし生きるべきときに生き、死ぬべきときに死ぬることこそ、真の勇者なのである」(同
書、P18)と。
私は一度は、新渡戸稲造の「武士道」を一度は読破しなければならないと、思ってきた。
しかしその機会はなかった。
(20年ほど前、一度、目を通した記憶はあるが……。)
断片的な知識はたくさんもっている。
しかしそれらは、断片的なものでしかない。
で、今度、イースト・プレス発刊の「武士道の世界」という本を買ってみた。
サブタイトルに、「誇るべき日本の原点」とあることからもわかるように、この本は、武士
道を礼賛する内容の本である。
そういう本を使って、私なりに武士道のもつ矛盾を指摘するのは気が引ける。
しかし礼賛する本であるがゆえに、私の脳みそに与える刺激も大きい。
1ページ読むごとに、脳の中で、バチバチと神経細胞が火花を飛ばすのを感じた。
が、この本ほど、「死」「自害」「討ち死に」「戦」という言葉が並ぶのも、そうは多くない。
「武士道の真髄」(P181)というところを紹介する。
「真髄」とあることからもわかるように、武士道の根幹を説明したものである。
+++++++++++++++++++
●『武士道といふは、死ぬ事と見付けたり』(葉隠)。
『武士道といふは、死ぬ事と見付けたり』(葉隠。
このあまりにも衝撃的で有名な言葉は、山本常朝が口述し、田代陣基が筆記、編纂した
『葉隠』の冒頭に記された、武士道の真髄を表すものだ。
主君のためならいつでも自分の命を捧げることができるのが、本当の武士であるという
心得を説いている。
「武士は生と死、どちらかを選ぶ場合、必ず死を選ばなければならない」のである。
「生き恥をさらす」と言われるように、この時代の武士道精神においては、戦に勝てな
いときは、死ぬことで忠義を果たさなければならないと考えられていた。
しかしこの言葉には、さらに深い意味がこめられている。
生に対する執着心や恐怖を手放した瞬間に、自由な自然体に到達し、その武士は本分を全
うするために生き抜くことができるという、悟りの境地を示した教えだと言えるだろう』
と。
++++++++++++++++
●命を捧げる
この部分を読んだとき、まっさきに頭に浮かんだのが、K国の金xx。
あの独裁者。
金xxが読んだら、涙を流して喜ぶにちがいない。
あの国では、幼稚園の子どもですら、「金xx将軍様を、命をかけて守ります」と連呼して
いる。
おとなたちは、「死守」という言葉を使っている。
それはさておき、「主君のためならいつでも自分の命を捧げることができるのが、本当の
武士である」という部分だけでも、バカげている。
もしあなたがまともな思考力をもっている人なら、あなたもそう感ずるだろう。
主義や理想、正義や真理のためなら、命をかけることはある。
しかし「命をかける」イコール、「命を捧げる」ではない。
いわんや、相手が、人間である、「主君」?
こういう思想を、私の世界では、「隷属思想」という。
●主君の主君は?
学生のころ、友人と、こんな議論をしたことがある。
「主君にさらにその上の主君がいたら、そのばあいは、どちらに命を捧げるのか」と。
つまりあなたの仕える主君が、あなたの住む領地を治める領主だったとする。
当然、その領主には、彼が主君とあがめる、藩主がいる。
藩主の上には、将軍がいる。
こういうばあい、あなたという家来は、藩主や将軍に命を捧げる必要はない。
何かを命じられても、それに従う必要もない。
あなたの主君は、あくまでも領主。
領主の命令だけを聞き、その領主のために、命を捧げる。
もう少し話をわかりやすくするために、会社組織で考えてみよう。
あなたが営業課の係長だったとする。
あなたの直接の上司は、営業課の課長。
そんなある日、営業課が入っている制作部の部長から、直接、あなたに命令が届いた。
つまり課長の頭を通り越して、あなたに命令が届いた。
こういうケースのばあい、あなたはその部長の命令に従う義務があるのか。
それともないのか。
会社によって組織の組織形態が異なるので、「従わなければならない」という会社もあれ
ば、「従わなくてもいい」という会社もある。
しかしこと武士の世界では、主君というのは、先のケースでは、あくまでも領主というこ
とになる。
藩主や、将軍の命令に従う必要はない。
命を捧げる相手でもない。
これが学生時代に、私たちが知った結論である。
そのヒントを与えてくれたのが、ヤクザの世界である。
当時、(今でもそうだが……)、ヤクザの世界には、武士道の精神が、そのまま残っていた。
ヤクザの世界では、直接上にいる兄貴分が、武士の世界でいう主君ということになる。
●主従関係
もっとも、封建時代の昔ならいざ知らず、「主君に命を捧げる」という発想は、今は、な
い。
主従関係も、西洋の契約説によって決まる。
わかりやすく言えば、「金の切れ目が縁の切れ目」。
給料がもらえなくなったら、そこで主従関係は、消滅する。
人それぞれだが、私なら、断る。
どう考えても、主君のために命を捧げるという発想そのものが、バカげている。
つまりこんなところにも、武士道が説く、(死の美学)が見え隠れする。
繰り返すが、死を美化してはいけない。
その延長線上に、戦争がある。
その一歩手前に、特攻隊があり、自爆テロがある。
私たちは死ぬために生きているのではない。
生きるために生きている。
この本の著者は、「生に対する執着心や恐怖を手放した瞬間に、自由な自然体に到達し、
その武士は本分を全うするために生き抜くことができるという、悟りの境地を示した教え
だと言えるだろう」と書いている。
それにしても、「生に対する執着心や恐怖を手放した瞬間……悟りの境地に達する」と
は?
いつの間にか、仏教の教えが、そのまま武士道の精神にすり替えられてしまっている?
●武士の作法
戦国時代はともかくも、以後、日本は300年という長い年月の間、太平天国の時代を
迎える。
その間に、武士道も、当初の戦闘を目的としたものから、権威づけのための作法の「道」
として変質する。
作法に始まって、作法に終わる。
それが武士道の柱と考えてよい。
いくつかを拾ってみる。
(1)鞘(さや)当て……武士の世界で、刀と刀の鞘が当たることは、何にもまして「無
礼極まりないこと」だったそうだ。
だから武士どうしは、廊下を歩くときも、左側通行が作法と決められていた。
(2)手はぶら下げて歩く……いつでも刀を抜けるように、手荷物も持たないし、傘もさ
さない。
(3)妻は後ろを歩かせる……妻と並んで歩くなど、軟弱者の証。
襲撃から守るという意味もある。(以上、同書)。
こうした作法が、ズラズラと、それこそ無数にある。
武士の刀をまたいだだけで、切捨て御免になった人も多いという。
また女性は、武士の刀に、直接手を触れることさえできなかったという。
しかしなぜ、「刀」なのか?
●武士と刀
武士の人口は、江戸時代においては、5%前後と言われている※。
しかしこの数字とて控えめなもの。
武士の家族も含まれているため、実際には、刀を差していた武士は、全人口の1~2%以
下だったと推計される。
残りの95%のほとんどが、農民であった。
その1~2%が、為政者として、好き勝手なことをした。
その好き勝手なことをする象徴として、「刀」があった。
武士が刀に執着する理由は、ここにある。
私はこんな話を、直接、その女性から聞いている。
私が住んでいる山荘のある村は、400年以上もの歴史のある、由緒ある村である。
その山荘の隣人に、10年ほど前、88歳で亡くなった女性がいる。
いわく、「明治時代に入ってからも、士族の人たちは、このあたりでは刀を差して歩いてい
た」と。
「刀の鞘どうしがカチャカチャと当たる音が、遠くから聞こえてくると、みな、道路の
脇に寄って、正座し、頭をさげた」と。
言うなれば、95%の日本人が、5%の武士を支えるために、犠牲になっていた。
そういう世界が、いかにおかしな世界であるかは、あなた自身を、その農民の立場に置い
てみればわかる※。
あなた自身の先祖も、その農民であったはず。
(私の先祖も、農民だった。)
一生、土地にしばられ、職業選択の自由もなかった。
当時生きていた人たちもまた、私やあなたと同じ人間であった。
犬や猿とは、ちがう。
そういう人たちを原点に考えるなら、「何が武士道か?」ということになる。
さらに言えば、この武士道が、やがてあの戦陣訓へとつながっていく。
それについては、前にも書いた。
もちろん歴史は歴史だから、それなりの評価は必要である。
しかしそれがもつ(ネガティブな側面)に目を閉じたまま、一方的に武士道なるものを礼
賛することは、危険なことでもある。
どうして武士道が、「誇るべき日本人の原点」(本のタイトル)なのか?
今、武士道を、教育の柱にしようとする動きが活発になっている。
またその種の本が、100万部単位で売れている。
これを民主主義の後退と言わずして、何と言う?
忘れてならないのは、新渡戸稲造が活躍した時代と、同じ時期に、福沢諭吉がいたという
こと。
福沢諭吉らは、やがて明六社に合流し、日本の封建主義を清算しようとした。
私は、福沢諭吉らのしたことのほうが、正道だと思のだが……。
それに「原点」とは何か?
何も原点にこだわる必要もない。
原点が正しいわけでもない。
大切なことは、おかしな復古主義にとらわれないこと。
私たちはいつも新しい原点を求めて、前に進む。
……と、少し頭が熱くなったので、この話は、ここまで。
なお本書(「武士道の世界」)は、つぎのように結んでいる。
『おわりに……そんな現代であるからこそ、日本人としての精神的意識が必要なのであ
る。
不道徳な世相を嘆いていても何も始まらない。
世界に通じる精神体系・武士道を心に携え、今こそ日本人としてのアイデンティティを世
界に発信してほしい』と。
(※注1)明治6年1月調べ・・・旧武士数は平民の16分の1にして総数408,823戸、
1,852,445人であった。幕末においてもこの数字と大差なかったものと考えられる。人口構
成は概数的に6.25%である。(土屋喬雄「幕末武士の階級的本質」)
どの藩も武士の数は軍事機密になっていた。
したがって、今となってはその人口は、推
計する以外にない(筆者注)。
(※注2) 徒士といえども、家老に対しては下駄を脱がざるをえなかったのが実情で、
城下において百姓町人は、足軽以上に出会えばまず平伏・土下座など屈辱的敬礼を強いら
れた。どの階層に属するか、着衣や服装で判断できる社会の仕組みになっていた。(「社会
構造と現代社会HP」より)
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW 武士道 武士の作法 武士道精神 武士の数 葉隠 忠臣蔵 新渡戸
稲造の「武士道」)
稲造の「武士道」)
●真の勇者
繰り返す。
新渡戸稲造は、真の勇者について、こう書いている。
「戦いに臨んで討ち死にすることは、難しいことではない。
それはどのような野人でもできることである。
しかし生きるべきときに生き、死ぬべきときに死ぬることこそ、真の勇者なのである」と。
生きるべきときに生きるのは当然であるとしても、「死ぬべきときに死ぬ」とは?
この思想が、後の、『戦時訓』につながっていった。
++++++++++++++++
戦陣訓について書いた原稿です。
(2009年3月記)
++++++++++++++++
●文明の衝突(2)
++++++++++++++++++++
少し前、「文明の衝突」について、書いた。
それを読みなおす。
読みなおして、それをワイフに話す。
(090412)
++++++++++++++++++++
●日本vsアジア
「黄色い白人」と呼ばれて、一時、日本人が得意になったことがあった。
日本が高度成長の波に乗り、破竹の進撃をつづけていたときのことである。
事実、当時、日本で、「自分はアジア人」と思っている子どもはいなかった。
「ぼくはアジア人ではない。日本人だ」と。
それについては、先の原稿に書いたとおりである。
しかし私たちは今も昔も、立派なアジア人である。
容姿、顔つき、肌の色、すべてが、立派なアジア人である。
むしろ日本人のほうが、骨相学的には、貧相と言われている。
島国で、長い間、鎖国をつづけ、「血の交流」をしなかったためと考えてよい。
で、昔、こんなことがあった。
私がオーストラリアで学生生活を送っていたときのことである。
中国からの留学生が何人かいた席で、だれかが私にこう言った。
「ヒロシ、君たちは中国人に、どんなイメージをもっているか。
それを絵に描いてみてほしい」と。
で、私は、目が釣りあがり、歯が飛び出た中国人を描いてみせた。
当時、新聞など出てくる中国人は、みな、そのような顔をしていた。
が、それを見て、みなが、ドッと笑った。
「ヒロシ、それは日本人の顔だよ」と。
●異種文明
こうした文明のちがいを克服するためには、どうしたらよいのか。
あるいはどうして文明の対立が起きるのか。
異種文明にも距離感がある。
(1) 隣接文明(隣接している文明)
(2) 非隣接文明(隣接していない文明)
先の原稿の中で書いたように、ドイツ人のロシア嫌いには定評(?)がある。
「どうしてそんなにも嫌うのか?」と思うほど、嫌う。
同じように、中国人の日本嫌いにも、定評(?)がある。
「どうしてそんなにも嫌うのか?」と思うほど、嫌う。
それには先の侵略戦争が大きく影響している。
が、それだけではないようだ。
「文明の衝突論」を当てはめてみると、それがうまく説明できる。
中国は、儒教文明圏に属する。
一方、この日本は、儒教文明圏に身を置きながら、西洋文明圏に属する。
つまりそこで「文明の衝突」が起きている。
が、日本とロシア、さらに日本とイラク、イランとの対立は生まれない。
(一部、日本とロシアは、対立しているが……。)
ロシアは、スラブ文明圏に属する。
イラク、イランは、アラブ文明圏属する。
なぜか。
それが「文明の距離」ということになる。
わかりやす言えば、文明の衝突は、それぞれの文明が接したところで起こる。
離れたところでは起きない。
たとえば今度は、スラブ文明とアラブ文明については、それぞれが接している。
だからたがいに仲が悪い。
アラブ人のロシア嫌いにも、これまた定評(?)がある。
非隣接文明についていえば、それは(情報)でしかない。
たとえば私たちがアラブ文明に触れたとき、それは(もの珍しさ)でしかない。
そのため文明の衝突は起きない。
●融和
問題はどうやって、隣接文明と融和していくかということ。
国と国の対立は、それぞれの国同士という(単体)の話しあいで解決できる。
しかし文明の対立となると、そうはいかない。
たとえば日本は、自らを西欧文明の中に身を置き、儒教文明と鋭く対立している。
日本は、儒教文明圏に属しながら、その一方で、自らを西欧文明圏に置いている。
この対立構造が、日本を現在の今、孤立させている。
このことは、相手の立場で考えてみると、よくわかる。
一度、ペキン(北京)という、中国の首都に、視点を置いてみるとよい。
日本は、はるか東の海上。
中国から見れば、大陸の端にへばりついているように見える。
それはたとえて言うなら、東京から、佐渡島を見るようなものではないか。
その日本が、ひとり、「私たちは西洋人」と主張している。
それから生まれる違和感というか、(滑稽さ)には、相当なものがある。
中国人が、日本を受け入れない本当の理由は、そんなところにもある(?)。
では、どうするか?
●儒教文明
最初に書いておきたい。
「儒教文明の再構築」といっても、復古主義的なものであってはいけない。
それについては、あとで「情報革命」のところで書く。
私たちはアジア人であることを再確認する。
それが儒教文明の再構築ということになる。
現在の今、私たちがこうして漢字を使っていること自体、その証拠ということになる。
中に「平仮名やカタカナは、日本人すばらしい発明」と書いている人がいる。
しかしそれはどうか?
平仮名にせよ、カタカナにせよ、漢字の簡略版にすぎない。
略字にすぎない。
「発明」などという大げさなものではなく、一バリエーションに過ぎない。
漢字で、「波也此」と書くより、「はやし」と書いたほうが楽に決まっている。
当時の人たちなら、だれしもそう考えただろう。
つまりこと日本人に関して言えば、私たちは、中国文明圏に属している。
まずそれを率直に認めること。
(だからといって、中国に隷属せよと、そういうことを書いているのではない。
誤解のないように!)
●日本史論
ついでに日本史論。
これについては、すでにたびたび書いてきた。
つまり日本では、日本史を東洋史と切り離して教える。
「日本は日本、東洋とは一線を画す」という思想が、その底流にある。
しかしこれがいかに偏狭なものであるかは、アジアの諸国をながめてみれば、わかる。
韓国を例に出すまでもない。
ほかに若いころ、タイへ行ったときにも、それを感じた。
タイという国は、そういう意味では奇異な国と考えてよい。
私たち日本人から見ると、同じ東南アジア諸国の一員ということになる。
しかし彼らは、そうは思っていない。
タイの人たちは、自分たちの歴史を、東南アジア全体から切り離して考えている。
日本史を東洋史と切り離してしまったところに、日本の歴史の悲劇性が潜む。
少し前も、ニセ石器に踊らされ、歴史の本そのものを書き換えてしまったことがある。
そのとき韓国の人たちは、こう言って笑った。
「日本に、韓国(中国)より古い歴史があるわけがない」と。
しかし日本史を東洋史の中に置いてみると、歴史観が一変する。
あの縄文時代にしても、弥生時代にしても、中国からの渡来民が深く関係している。
戦乱を逃れて、多くの民が、中国大陸から流れてやってきた。
そういう人たちが、大陸の文化を、日本に伝えた。
さらに天皇家のルーツにしても、そうだ。
少なくとも隣の韓国では、天皇家の祖先は、朝鮮からの騎馬民族ということになっている。
日本の天皇ですら、「ゆかり」という言葉を使って、それを臭わせたこともある。
しかし日本史を東洋史と切り離している間は、日本はいつまでも日本のまま。
日本が東洋と融和することは、ありえない。
●情報革命
が、否定的なことばかり言っていてはいけない。
ここで人類は、第二の産業革命とも言える「武器」を手にした。
「情報革命」という武器である。
以前、恩師の田丸先生がこう話してくれたことがある。
「情報革命が進めば、国はなくなりますよ」と。
具体的にはこうだ。
「年々、向こうの若者たちが日本の若者と区別できなくなってきた」と。
「姿、容姿、着ている服装など、「区別ができない」と。
つまりそういう形で、国と国は融合し、やがて文明の対立も解消される、と。
言い換えると、いかにこの情報革命を利用するかという問題に行き着く。
昔は、隣町どうしが、言い争った。
それが県どうしになった。
それが国
さらに文明。
情報革命は、その間を融和させる。
言葉の問題もあるにはある。
しかしたった10年前と比較しただけでも、その進歩にはめざましいものがある。
たとえば私が発行しているHPにしても、外国の人たちが読んでいる。
その中には「米軍」というのもある。
まだ10%程度だが、「10%にしても、すごい!」。
情報革命が進めば進むほど、国どうしの垣根も低くなる。
文明の衝突も、起きにくくなる。
その例が、あのEUである。
ほんの65年前にははげしい戦争を繰りかえしていた。
が、今は、ひとつの国になった!
●文明の衝突
私たちが警戒しなければならないのは、偏狂な民族主義。
その台頭。
「武士道こそ、日本が世界に誇るべき、日本人のアイデンテティ」と説く。
しかし今、どうしてこの日本で、武士道なのか?
仮にそれが「道」であったとしても、それは武士の世界での話。
しかも武士の本質は、軍人。
軍人で悪いなら、官僚。
あるいは警察、役人、特権階級。
何でもよいが、ともかくも支配階級。
私たちの先祖の94、5%は、農民であり、わずかな数の商人、工人であった。
それを忘れて、「武士道」とは?
あの江戸時代にしても、世界でも類を見ないほどの暗黒政治の時代であった。
さらに戦陣訓を例にあげるまでもなく、一方的に礼讃するのはどうか?
「生きて虜囚の……」とかいう、あの戦陣訓は、武士道の精神を拝借している。
そのため、どれだけ多くの日本人が犠牲になったことか!
「負の遺産」に目を当てることもなく、武士道を礼讃するのは、危険なことでもある。
つまり私たちが偏狭な民族主義にこだわればこだわるほど、互いの文明の溝を深くする。
あのアインシュタイン博士も、田丸先生への手紙の中で、「exaggerated nationalism」
という言葉を使って、強く戒めている。
「exaggerated nationalism」、つまり「誇張されたナショナリズム」=「偏狭な
民族主義」ということになる。
●過去から学ぶ
こう書いたからといって、どうか、誤解しないでほしい。
私は何も日本の歴史を否定しているのではない。
歴史は歴史として、当然、評価されなければならない。
しかしここにも書いたように、その「負の遺産」に目をくれることもなく、あの封建時代
を一方的に、美化してはいけない。
もっと言えば、悲しいかな、私たち日本人は、かつてただの一度も、あの封建時代を
清算していない。
たとえば「明治維新」にしても、英語では、「Meiji Restoration」と翻訳されている。
英語で、「レストレーション」というと、「王政復古」をいう。
革命でも、何でもない。
つまり「王政復古」である。
そういうものをもって、日本は近代化の道を歩み始めたとか、さらには江戸時代を清算
したなどとは、思ってはいけない。
清算していないばかりか、ここにも書いたように、むしろ、それを美化している。
この静岡県でも、徳川家康の出身地ということもあるが、徳川家康について悪く書くのは、
いわばタブー視されている。
この静岡県では、敬愛の念をこめて、「家康公」と呼ぶ。
が、こういう姿勢では、私たちは過去から何も学ぶことはできない。
できないばかりか、へたをすれば同じような歴史を繰り返すことになる。
今の今も、国盗り物語よろしく、政治を、己の出世欲を満たすための道具として
利用している人は、いくらでもいる。
●過渡期
話を戻す。
平等という言葉がある。
しかし「平等」というのは、たがいに高い次元で、認めあうことをいう。
民族の融和にしても、さらには文明の融和にしても、その平等感覚がなければならない。
「わが民族は優秀である」と思うのはその人の勝手だが、だからといって、相手に
向って、「あなたがた民族は劣っている」と思ってはいけない。
民族には上下はないし、今はもう民族をうんぬんする時代ではない。
むしろ問題なのは、その上の段階の「文明意識」ということになる。
もう一度、私が書いた、段階論を見てほしい。
家族意識(先祖意識)
↓
同郷意識
↓
同国意識
↓
民族意識
↓
文明意識(無意識)
↓
人間意識(無意識)
↓
生命意識(無意識)
つまり今は、(民族意識)から、(文明意識)への過渡期ということになる。
さらに進めば、(人間意識)→(生命意識)となるが、それはさておき、
この段階あたりで、ウロウロしている。
それがこの極東アジアでも、もろもろの紛争の火種となっている。
●では、どうするか?
言うまでもなく大切なことは、文明の融和である。
そのために第一に、情報の交換をする。
その国の内部の人たちは、外の世界を知る。
外の世界の人たちは、その国の内部を知る。
これを頻繁に、行う。
これができれば文明の融和はできる。
できなければ、できない。
ひとつの例として、あのK国を見ればよい。
今のこの時代にあって、情報を遮断している。
国外に向けてもすらも、ニセ情報を流す。
国内に向けてもすらも、ニセ情報を流す。
その結果、アインシュタインの言った、「exaggerated nationalism」だけが、
異常なまでに肥大化してしまった。
もうおわかりのことと思うが、私たちは、その逆のことをすればよい。
私たちは自分の考えていることを、外の世界に向って、どんどんと発信していく。
と、同時に、外の世界の情報を、どんどんと取り込んでいく。
その結果として、私たちは人間のレベルを、つぎのステージにもちあげることができる。
最後に、よく「インターネットは、第二の産業革命」と言われる。
それが最終的に評価されるのは、もう少し時代を経てからになるが、私はそう断言して
よいほど、インターネットには、秘められた力がある。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
民族意識 文明意識 民族主義からの脱却 インターネット 文明の衝突 誇張された
民族主義 はやし浩司 文明論 民族論)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●江戸時代は悲劇の歴史
こんな原稿を書いたこともある。
一部は、中日新聞に載せてもらったことがある。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●夏休みの宿題(ある女子中学生の宿題より)
+++++++++++++++++++++++
(1) 共通テーマは、武士、700年間の時代の中で、
人々が、幸せに暮らしたのは、いつか。
(2) 社会の安定、自由、繁栄、平和、家族という視点
の中から、ひとつ選んで、追究する。
+++++++++++++++++++++++
中学1年生のKさんが、こんな宿題をもってきた。
春休みの宿題だという。
日本の教育も変わってきた。
もちろん宿題の内容も変わってきた。
これを見たとき、私は、「日本の教育は確実に欧米化している」と感じた。
(暗記)から(思考力)へ。
(ジェネラリスト)から(スペシャリスト)へ。
(従順な子ども)から(問題意識をもった子ども)へ。
その変化は、いろいろな言い方で説明できる。
しかし教育というのは、「学校で学んだことを、すべて忘れてしまったあとに
残っているもの」とするなら、こうした教育は、その(残るもの)を目指した
教育と言える。
すばらしいことだと思う。
で、Kさんには、こう説明した。
(1) 武士の時代といっても、きびしい身分制度が敷かれていた。
武士の立場で考えるか、農民の立場で考えるか、それによって、
見方が大きく変わる。
(2)「幸せ」の定義をしっかりとしておくこと。何をもって「幸せ」というか。
それによっても、見方が、大きく変わる。
(3)「安定、自由、繁栄、平和、家族」の中から、何を選ぶか。
もちろんそのうちのどれを選ぶかで、見方が、これまた大きく変わる。
私「基本的には、あの江戸時代は、世界の歴史の中でも、類をみないほどの
暗黒かつ恐怖政治の時代だった。それを忘れてはいけない」
K「結構、みな、楽しそうだったみたい」
私「だれが、そう教えたの?」
K「……教科書……?」
私「移動の自由もなく、職業選択の自由もない。もちろん言論の自由もない。
きびしい身分制度の中で、生まれながらにして、みな、職業が決まっていたんだよ」
K「武士にとっては、住みやすい時代だったかもしれないわね」
私「そう、武士にとってはね。でも、その武士は、6~7%。農民は、80~85%。
その農民たちは、武士に虐げられていた」
K「そう? 武士って、そんなに少なかったの?」と。
ちなみに、ヤフー・知恵袋によれば、つぎのようにある。
「幕末の人口約3200万人のうちわけは、諸藩の統計を平均して、武士6~7%、農民80~
85%、工商を含む町人5~6%、神官・僧侶1.5%、穢多・非人1.6%と、
85%、工商を含む町人5~6%、神官・僧侶1.5%、穢多・非人1.6%と、
推測されている」と。
つまり人口の6~7%に過ぎない武士が、人口の80~85%もいる農民を虐げ、
好き勝手な生活を楽しんでいた。
「好き勝手」というのは、農民の納める年貢にしても、収穫高の4~5割を自分たちの
ものにしていたことをいう。
身分制度については、こんな話が残っている。
浜松市の西に、江戸時代に代々、庄屋として栄えた農家がある。
そんな農家ですらも、上から下まで、厳格な身分制度が敷かれていた。
小間使いは、一生、小間使い。
代々、小間使い、と。
また恐怖政治については、こんな話が残っている。
私の山荘のある地域では、明治時代に入ってからも、士族たちは、
刀をさして歩いていたという。
歩くたびに、刀の鞘(さや)が、カチャカチャと音をたてたという。
農家の人たちは、その音が聞こえてくると、道路の脇に正座して、頭をさげ、
その氏族という人が通り過ぎるのを待ったという。
この話は、10年ほど前、90歳でなくなった女性から、直接、私が
聞いた話である。
こういう(事実)をすべて無視して、「江戸時代は、自由な時代だった」とは、
私はぜったいに言わせない。
Kさんが、どんなレポートを書くかは、私は知らない。
しかしそれが、江戸時代を考える、新しいきっかけになればよい。
……私はKさんが数学の問題を解いている間、「幸せな暮らし」と何か、
それを考えていた。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
Hiroshi Hayashi education essayist writer Japanese essayist 武士 農民 比率 江戸時代)
Hiroshi Hayashi education essayist writer Japanese essayist 武士 農民 比率 江戸時代)
++++++++++++++++++
前にも取りあげたが、あの信長ですら、
この日本では、英雄(?)になっている。
それについて書いたのが、つぎの原稿。
(中日新聞発表済み)
++++++++++++++++++
●「偉い」を廃語にしよう
●子どもには「尊敬される人になれ」と教えよう
日本語で「偉い人」と言うようなとき、英語では、「尊敬される人」と言う。よく似たよ
うな言葉だが、この二つの言葉の間には。越えがたいほど大きな谷間がある。日本で「偉
い人」と言うときは。地位や肩書きのある人をいう。そうでない人は、あまり偉い人と
は言わない。一方英語では、地位や肩書きというのは、ほとんど問題にしない。
そこである日私は中学生たちに聞いてみた。「信長や秀吉は偉い人か」と。すると皆が、
こう言った。「信長は偉い人だが、秀吉はイメージが悪い」と。で、さらに「どうして?」
と聞くと、「信長は天下を統一したから」と。中学校で使う教科書にもこうある。「信長は
古い体制や社会を打ちこわし、…関所を廃止して、楽市、楽座を出して、自由な商業がで
きるようにしました」(帝国書院版)と。これだけ読むと、信長があたかも自由社会の創始
者であったかのような錯覚すら覚える。しかし……?
実際のところそれから始まる江戸時代は、世界の歴史の中でも類を見ないほどの暗黒か
つ恐怖政治の時代であった。一部の権力者に富と権力が集中する一方、一般庶民(とく
に農民)は極貧の生活を強いられた。
もちろん反対勢力は容赦なく弾圧された。由比正雪らが起こしたとされる「慶安の変」
でも、事件の所在があいまいなまま、その刑は縁者すべてに及んだ。坂本ひさ江氏は、
「(そのため)安部川近くの小川は血で染まり、ききょう川と呼ばれた」(中日新聞コラ
ム)と書いている。家康にしても、その後三〇〇年をかけて徹底的に美化される一方、
彼に都合の悪い事実は、これまた徹底的に消された。私たちがもっている「家康像」は、
あくまでもその結果でしかない。
……と書くと、「封建時代は昔の話だ」と言う人がいる。しかし本当にそうか? そこで
あなた自身に問いかけてみてほしい。あなたはどういう人を偉い人と思っているか、と。
もしあなたが地位や肩書きのある人を偉い人と思っているなら、あなたは封建時代の亡霊
を、いまだに心のどこかで引きずっていることになる。
そこで提言。「偉い」という語を、廃語にしよう。この言葉が残っている限り、偉い人を
めざす出世主義がはびこり、それを支える庶民の隷属意識は消えない。民間でならまだ
しも、政治にそれが利用されると、とんでもないことになる。「私、日本で一番偉い人」
と言った首相すらいた。そういう意識がある間は、日本の民主主義は完成しない。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●福沢諭吉
今の今でも、この日本には、封建主義が色濃く残っている。
それに気づくか気づかないかは、ひとえにその人の問題意識ということになる。
教育の場で、それを考えてみたい。
●血統空想
++++++++++++++
「私だけは特別でありたい」という
思いは、だれにでもある。そのひとつ
が、「血統」。
「私の血統は、特別だ」「だから私は
特別な人間」と。
あのジークムント・フロイトは、
そうした心理を、「血統空想」という
言葉を使って説明した。
年齢で言えば、満10歳前後から
始まると考えられている。
しかしそう思うのは、その人の勝手。
それはそれでかまわない。しかし、その
返す刀で、「私以外は、みな、劣って
いる」と考えるのは、まちがっている。
自己中心性の表れそのものとみる。
EQ論(人格完成論)によれば、
自己中心性の強い人は、それだけ
人格の完成度の遅れている人と
いうことになる。
わかりやすい例でいえば、今でも
家系にこだわる人は多い。ことあるご
とに、「私の先祖は、○○藩の家老だ
った」とか何とか言う。
悪しき封建時代の亡霊とも考えられる。
江戸時代には、「家」が身分であり、
「家」を離れて、個人として生きていく
こと自体、不可能に近かった。
日本人がいまだに、「家」にこだわる
理由は、ここにある。
それはわかるが、それからすでに、
約150年。もうそろそろ日本人も、
そうした亡霊とは縁を切るべきときに
来ているのではないのか。
+++++++++++++++
●人間は平等
かつて福沢諭吉は、こう言った。「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」(「学問
のすすめ」)と。
のすすめ」)と。
その「天は人の上に……」という名言が、生まれた背景として、国際留学協会(IFSA)は、つぎ
のような事実を指摘している。そのまま抜粋させてもらう。
のような事実を指摘している。そのまま抜粋させてもらう。
『……さらに諭吉を驚かせたことは、家柄の問題であった。
諭吉はある時、アメリカ人に「ワシントンの子孫は今どうしているか」と質問した。それに対する
アメリカ人の反応は、実に冷淡なもので、なぜそんな質問をするのかという態度であった。誰も
ワシントンの子孫の行方などに関心を持っていなかったからである。
アメリカ人の反応は、実に冷淡なもので、なぜそんな質問をするのかという態度であった。誰も
ワシントンの子孫の行方などに関心を持っていなかったからである。
ワシントンといえば、アメリカ初の大統領である。日本で言えば、鎌倉幕府を開いた源頼朝や、
徳川幕府を開いた徳川家康に匹敵する存在に思えたのである。その子孫に誰も関心を持って
いないアメリカの社会制度に、諭吉は驚きを隠せなかった。
徳川幕府を開いた徳川家康に匹敵する存在に思えたのである。その子孫に誰も関心を持って
いないアメリカの社会制度に、諭吉は驚きを隠せなかった。
高貴な家柄に生まれたということが、そのまま高い地位を保障することにはならないのだ。諭
吉は新鮮な感動を覚え、興奮した。この体験が、後に「天は人の上に人を造らず、人の下に人
を造らずと言えり」という、『学問のすすめ』の冒頭のかの有名な言葉を生み出すことになる』
と。
吉は新鮮な感動を覚え、興奮した。この体験が、後に「天は人の上に人を造らず、人の下に人
を造らずと言えり」という、『学問のすすめ』の冒頭のかの有名な言葉を生み出すことになる』
と。
意識のちがいというのは、恐ろしい。恐ろしいことは、この一文を読んだだけでもわかる。い
わんや明治の昔。福沢諭吉がそのとき受けた衝撃は、相当なものであったと考えられる。そこ
で福沢諭吉らは、明六社に合流し、悪しき亡霊と闘い始める。
わんや明治の昔。福沢諭吉がそのとき受けた衝撃は、相当なものであったと考えられる。そこ
で福沢諭吉らは、明六社に合流し、悪しき亡霊と闘い始める。
明六社……明治時代に、森有礼(もり・ありのり)という人がいた。1847~1889年の人で
ある。教育家でもあり、のちに文部大臣としても、活躍した人でもある。
ある。教育家でもあり、のちに文部大臣としても、活躍した人でもある。
その森有礼は、西洋的な自由主義者としても知られ、伊藤博文に、「日本産西洋人」と評され
たこともあるという(PHP「哲学」)。それはともかくも、その森有礼が結成したのが、「明六社」。
その明六社には、当時の若い学者たちが、たくさん集まった。
たこともあるという(PHP「哲学」)。それはともかくも、その森有礼が結成したのが、「明六社」。
その明六社には、当時の若い学者たちが、たくさん集まった。
そうした学者たちの中で、とくに活躍したのが、あの福沢諭吉である。
明六社の若い学者たちは、「封建的な身分制度と、それを理論的に支えた儒教思想を否定
し、不合理な権威、因習などから人々を解放しよう」(同書)と、啓蒙運動を始めた。こうした運
動が、日本の民主化の基礎となったことは、言うまでもない。
し、不合理な権威、因習などから人々を解放しよう」(同書)と、啓蒙運動を始めた。こうした運
動が、日本の民主化の基礎となったことは、言うまでもない。
で、もう一度、明六社の、啓蒙運動の中身を見てみよう。明六社は、
(1)封建的な身分制度の否定
(2)その身分制度を理論的に支えた儒教思想の否定
(3)不合理な権威、因習などからの人々の解放、を訴えた。
しかしそれからちょうど100年。私の生まれた年は、1947年。森有礼が生まれた年から、ち
ょうど、100年目にあたる。(こんなことは、どうでもよいが……。)その100年の間に、この日
本は、本当に変わったのかという問題が残る。反対に、江戸時代の封建制度を、美化する人
たちまで現われた。中には、「武士道こそ、日本が誇るべき、精神的基盤」と唱える学者までい
る。
ょうど、100年目にあたる。(こんなことは、どうでもよいが……。)その100年の間に、この日
本は、本当に変わったのかという問題が残る。反対に、江戸時代の封建制度を、美化する人
たちまで現われた。中には、「武士道こそ、日本が誇るべき、精神的基盤」と唱える学者までい
る。
こうした人たちは、自分たちの祖先が、その武士たちに虐(しいた)げられた農民であったこ
とを忘れ、武士の立場で、武士道を礼さんするから、おかしい。悲しい。そして笑える。
とを忘れ、武士の立場で、武士道を礼さんするから、おかしい。悲しい。そして笑える。
武士たちが、刀を振りまわし、為政者として君臨した時代が、どういう時代であったか。そん
なことは、ほんの少しだけ、想像力を働かせば、だれにも、わかるはず。そういったことを、反
省することもなく、一方的に、武士道を礼さんするのも、どうかと思う。少なくとも、あの江戸時
代という時代は、世界の歴史の中でも、類をみないほどの暗黒かつ恐怖政治の時代であった
ことを忘れてはならない。
なことは、ほんの少しだけ、想像力を働かせば、だれにも、わかるはず。そういったことを、反
省することもなく、一方的に、武士道を礼さんするのも、どうかと思う。少なくとも、あの江戸時
代という時代は、世界の歴史の中でも、類をみないほどの暗黒かつ恐怖政治の時代であった
ことを忘れてはならない。
その封建時代の(負の遺産)を、福沢諭吉たちは、清算しようとした。それがその明六社の啓
蒙運動の中に、集約されている。
蒙運動の中に、集約されている。
で、現実には、武士道はともかくも、いまだにこの日本に、封建時代の負の遺産を、ひきずっ
ている人は多い。その亡霊は、私の生活の中のあちこちに、残っている。巣をつくって、潜んで
いる。たとえば、いまだに家父長制度、家制度、長子相続制度、身分意識にこだわっている人
となると、ゴマンといる。
ている人は多い。その亡霊は、私の生活の中のあちこちに、残っている。巣をつくって、潜んで
いる。たとえば、いまだに家父長制度、家制度、長子相続制度、身分意識にこだわっている人
となると、ゴマンといる。
はたから見れば、実におかしな制度であり、意識なのだが、本人たちには、わからない。そ
れが精神的バックボーンになっていることすら、ある。
れが精神的バックボーンになっていることすら、ある。
しかしなぜ、こうした制度なり意識が、いまだに残っているのか?
理由は簡単である。
そのつど、世代から世代へと、制度や意識を受け渡す人たちが、それなりに、努力をしなか
ったからである。何も考えることなく、過去の世代の遺物を、そのままつぎの世代へと、手渡し
てしまった。つまりは、こうした意識は、あくまでも個人的なもの。その個人が変わらないかぎ
り、こうした制度なり意識は、そのままつぎの世代へと、受け渡されてしまう。
ったからである。何も考えることなく、過去の世代の遺物を、そのままつぎの世代へと、手渡し
てしまった。つまりは、こうした意識は、あくまでも個人的なもの。その個人が変わらないかぎ
り、こうした制度なり意識は、そのままつぎの世代へと、受け渡されてしまう。
いくら一部の人たちが、声だかに、啓蒙運動をしても、それに耳を傾けなければ、その個人
にとっては、意味がない。加えて、過去を踏襲するということは、そもそも考える習慣のない人
には、居心地のよい世界でもある。そういう安易な生きザマが、こうした亡霊を、生き残らせて
しまった。
にとっては、意味がない。加えて、過去を踏襲するということは、そもそも考える習慣のない人
には、居心地のよい世界でもある。そういう安易な生きザマが、こうした亡霊を、生き残らせて
しまった。
100年たった今、私たちは、一庶民でありながら、森有礼らの啓蒙運動をこうして、間近で知
ることができる。まさに情報革命のおかげである。であるなら、なおさら、ここで、こうした封建
時代の負の遺産の清算を進めなければならない。
ることができる。まさに情報革命のおかげである。であるなら、なおさら、ここで、こうした封建
時代の負の遺産の清算を進めなければならない。
日本全体の問題として、というよりは、私たち個人個人の問題として、である。
……と話が脱線してしまったが、これだけは覚えておくとよい。
世界広しといえども、「先祖」にこだわる民族は、そうは、いない。少なくとも、欧米先進国に
は、いない。いわんや「家」だの、「血統」だのと言っている民族は、そうは、いない。そういうも
のにこだわるということ自体、ジークムント・フロイトの理論を借りるまでもなく、幼児性の表れと
考えてよい。つまりそれだけ、民族として、人格の完成度が低いということになる。
は、いない。いわんや「家」だの、「血統」だのと言っている民族は、そうは、いない。そういうも
のにこだわるということ自体、ジークムント・フロイトの理論を借りるまでもなく、幼児性の表れと
考えてよい。つまりそれだけ、民族として、人格の完成度が低いということになる。
(付記)
この問題は、結局は、私たちは、何に依存しながら、それを心のより所として生きていくかと
いう問題に行き着く。
いう問題に行き着く。
名誉、財産、地位、学歴、経歴などなど。血統や家柄も、それに含まれる。しかし釈迦の言葉
を借りるまでもなく、心のより所とすべきは、「己(おのれ)」。「己」をおいて、ほかにない。釈迦
はこう説いている。
を借りるまでもなく、心のより所とすべきは、「己(おのれ)」。「己」をおいて、ほかにない。釈迦
はこう説いている。
『己こそ、己のよるべ。己をおきて、誰によるべぞ』(法句経)と。「自由」という言葉も、もともと
は、「自らに由る」という意味である。
は、「自らに由る」という意味である。
あなたも一言でいいから、自分の子どもたちに、こう言ってみたらよい。「先祖? そんなくだ
らないこと考えないで、あなたはあなたはで生きなさい」と。
らないこと考えないで、あなたはあなたはで生きなさい」と。
その一言が、これからの日本を変えていく。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司 血統
空想 封建時代 武士道)
空想 封建時代 武士道)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●水戸黄門
『江戸残酷物語』(双葉社)は、あの水戸黄門についても、触れている。
徳川家康につづく、徳川家光、徳川綱吉、徳川吉宗らが、冷酷無比な暴君であったことは、私
も知っていた。
も知っていた。
このことは、サダム・フセインの息子たち、あるいはカダフィ大佐の息子たちが、どういう息子た
ちであったかを知れば、おおよそ類推できる。
ちであったかを知れば、おおよそ類推できる。
が、水戸黄門……つまり徳川光圀までそうだったということは、知らなかった。
『江戸時代残酷物語』は、つぎのように書いている。
「あの水戸黄門の実像は、血も涙もない冷血漢だった!
命乞いする罪なきものを斬殺、犬も大量に虐殺した無慈悲な副将軍。
……若いころは狼藉の日々、試し切りで、殺人も経験などなど。
その徳川光圀にしても、徳川光圀にとって都合の悪い事実は徹底的に抹消され、その一方
で、ドラマ「水戸黄門」にみるように、徹底的に美化された。
で、ドラマ「水戸黄門」にみるように、徹底的に美化された。
仮にそうであったとするなら、つまりそれほどまでに正義感にあふれた人物なら、なぜその上
の将軍に、その矛先を向けなかったのか。
の将軍に、その矛先を向けなかったのか。
今の今も、その美化は進行中!
時代はあの徳川綱吉の時代。
「生類憐れみの令」などという、まことにもって異常な法律を制定していた時代である。
犬を蹴飛ばしただけで、死罪。
そういう時代だったからこそ、徳川光圀は、マダマシ?
それが今日見られる「美化」の原点になっているのかもしれない。
●封建時代の清算
日本人は歴史の中で、一度とて、あの江戸時代を清算していない。
していないばかりか、いまだに美化してやまない。
その一例が、NHKの大河ドラマということになる。
たとえば新撰組。
あの新撰組のおかげで、京都の町は恐怖のどん底へと叩き落とされた。
『江戸残酷物語』の中にも、こうある(P72)
「……幕末の京は天誅(てんちゅう)の名のもとに、暗殺が横行する無法都市であった。
幕府の治安維持能力は著しく劣化し、もはやあてにならない。
どんな理由で尊王派の標的にされるか知れず、人々は暗殺の恐怖におびえた」と。
それも時代……という形で、私たちは過去を安易に美化してしまう。
日本人特有の精神構造というか、それがあるから日本人はそのつど、歴史を前進させること
ができない。
ができない。
話は変わるが、私は今回の3・11大震災のあと、つぎのことを知った。
NHKをはじめ、公的な報道機関をはじめ、政府は、「ウソこそ言わないが、しかし本当のことも
言わない」と。
言わない」と。
が、今は、そういう時代ではない。
インターネットを通し、私たちは生の情報を、瞬時に手に入れることができる。
あの原発事故のあと、女川原発付近で放射線が観測されたときもそうだ。
政府は、「今、ただちに健康に被害が及ぶものではありません」と、今から思うととんでもない
情報を流布していた。
情報を流布していた。
最後に、私がその3月15日(2011)に書いた原稿を添付する。
「洗脳」という言葉を、心のどこかに置き、この原稿を読んでほしい。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●原発事故(日本沈没)(はやし浩司 2011-03-16記)
恐ろしいことが起きつつある。
政府は、「落ち着いて」とか、「冷静に」とか言っている。
落ち着け?
冷静になれ?
しかし落ち着いているばあいではない。
冷静になれるばあいではない。
アメリカ・ホワイトハウス報道官でさえ、「緊急事態」という言葉を使っている。
「緊急」というのは、「緊急」。
それ以上でも、またそれ以下でもない。
●テレビに釘付け
テレビに釘付け。
じっと見入る。
襲い来る不安感。
政府の役人や東京電力の職員の一言一句に、何も聞き漏らさないと、神経を集中する。
が、どれもおかしい?
まずあのED官房長官。
役人の書いた作文を読んでいるだけ。
それ以上の知識は、ゼロ。
記者の質問には何一つ、答えられない。
質問されそうになると、「私からは以上です」と言って、逃げてしまう。
答えられないばかりか、今朝は、こんな珍説も。
FD官房長官は、こう言った。
「マスコミの無責任は発言は、国民の不安を増大させるだけ。
謹んでほしい」と。
それに対して、すかさず1人の記者が質問した。
「どこのマスコミか?」と。
が、FD官房長官は、それに対して、タジタジ。
FD官房長官の、その発言こそが、「無責任な発言」ということになる。
保安院の役人にしても、そうだ。
イチバン最初に登場してきた役人は、「マイクロ・シーベル」の意味すら知らなかった(?)。
記者に質問されると、一瞬、二瞬、戸惑った表情をして見せた後、「あとで報告します」と。
さらにこんなバカげた返答も。
福島第一原発の北、20キロに、女川原発がある。
そこでは8マイクロ・シーベル・の放射能が検出された(14日)。
それについて、「この放射能は、福島第二原発からのものと思われます。
8マイクロ・シーベルは、まったく心配ない数値です」と。
バカヤロー!
バカ、バカ、バカ!
大バカ!
あのね、放射能の濃度というのは、距離の二乗に反比例するの!
仮に20キロとするなら、20000メートル。
20000x20000=400000000=4億!
つまり放射能の発生元の1メートル四方では、その4億倍の放射能が漏れたことになる。
もちろん風向きにもよるが、実際には、それ以上とも考えられる。
たまたま南風に乗って、女川原発に直行したと考える方が、無理。
8マイクロx4億が、どういう数値になるか、自分で計算してみらたよい。
(この計算によれば、発生元では、32億マイクロシーベル、つまり320万ミリ
シーベル。
とんでもない放射能が漏れ出たことになる!)
……と思っていたら、またまた同じ発言。
今度は、福島第二原発から、100キロ離れた、東海村原子炉周辺で、5マイクロ・
シーベルの放射能が検出された。
それについても、同じ意見。
「(福島第二原発から流れてきた放射能と思われるが)、この程度なら、心配ありません」
(NHKテレビのコメンテイター)と。
今度ほど、私は科学者(?)の脳みそを疑ったことはなかった。
ド素人の官房長官。
役人根性丸出しの東京電力の社員たち。
深刻さを、あえて覆い隠そうとする科学者たち。
「こんな連中が、日本の安全を担っていたのか」と、私は唖然とした。
が、不測の事態は、不測の事態を呼ぶ。
人為的ミスが、それに追い討ちをかける。
電源機が燃料切れで、2時間も停止していた。
こうして1号基、3号基、2号基とつづいて爆発。
今は、4号基まで、爆発。
1号基が爆発したとき、「ほかの原発はだいじょうぶです」と、確か、言っていたぞ!
そのとき2号基、3号基、4号基も併せて、対策を講じていれば、こんな大惨事には
ならなかったはず。
いいか、爆発したこと自体、大惨事!
緊急事態!
私なら総理大臣なら、半径100キロ以内の人たちに、避難命令を出す。
福島第二原発から東京まで、直線距離にして、170キロ。
東京だって、あぶない。
が、管総理は、こう言った。
「関係者は、命がけで、懸命な作業をしています」(記憶、3月15日)と。
前回のときは、「東京電力に、任せるしかない」というようなこと言っていた。
だから、どうなの?
それが、どうしたの?
私には責任逃れの詭弁にしか聞こえなかった。
こういうときほど、ものごとがすべて裏目、裏目と出る。
まるでドミノ倒しのように、それがつづく。
日本の経済も、大きく揺らいだ。
株価は大暴落。
円は急上昇。
円が急上昇したのは、円キャリーの逆流が始まったため。
このあとやってくるのは、国家破綻(デフォルト)。
ハイパーインフレ。
わかりやすく言えば、札が紙くずと化す。
そこで日銀は、昨日(15日)、15兆円のお金を市中にバラまいた。
日本の心臓に、電気ショックを与えた。
メチャメチャな対策としか言いようがない。
ないが、この際、しかたない。
死ぬか、生きるか?
私とて、日本人。
福島第一原発が、このまま静かに収まってくれればよい。
心から、そう願う。
が、このザワザワとした不安感を、払拭することができない。
このままでは、この日本は、本当に沈没してしまう!
2011/03/15
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
さあ、みなさん、勇気を出してあの江戸時代という封建時代を、今、ここで清算しよう。
心の中に潜む、おかしな上下意識、職業意識、身分意識を清算しよう。
でないと、日本人は、いつまでたっても、同じ失敗を繰り返す。
過去を未来にひきずる。
もちろん歴史は歴史だから、それなりの評価はしなければならない。
その歴史がもつ負の遺産に目を閉じたまま、一方的に、あの時代を美化してはいけない。
(はやし浩司 2011-12-10記)
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教育評
論 はやし浩司 封建主義の清算 暗黒 恐怖 恐怖政治 はやし浩司 徳川光圀 水戸黄門
安倍川 由比正雪 はやし浩司 徳川時代 徳川幕府 はやし浩司 3・11大震災 女川
女川原子力発電所 女川発電所)
論 はやし浩司 封建主義の清算 暗黒 恐怖 恐怖政治 はやし浩司 徳川光圀 水戸黄門
安倍川 由比正雪 はやし浩司 徳川時代 徳川幕府 はやし浩司 3・11大震災 女川
女川原子力発電所 女川発電所)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 13日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page008.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【子どもは人の父】(朗読版)byはやし浩司
●「子どもは人の父」(ワーズワース)
子どもの心はいかに形成されていくか
"The Child is Father of the Man"
How the minds of children are formed.
(抄訳)
子どもを知ることによって、私たち自身を知ることができる。あのワーズワースは、『子どもは人
の父』といった。私たち自身にも子ども時代があり、その時代に私という人間が作られていっ
た。子どもの心の形成過程を、乳幼児期から思春期まで、段階的に追いかけてみた。自分発
見の手がかりになればうれしい。
の父』といった。私たち自身にも子ども時代があり、その時代に私という人間が作られていっ
た。子どもの心の形成過程を、乳幼児期から思春期まで、段階的に追いかけてみた。自分発
見の手がかりになればうれしい。
By knowing children, we can know ourselves better.
William Wordsworth once wrote, "The Child is Father of the Man".
Once we were all children and our minds were formed during this age of childhood.
In this article I have written about the process of how the minds of children are formed in
stages from the age of infancy to adolescence.
stages from the age of infancy to adolescence.
I hope this article will be of some help to you in getting to know yourselves better.
(1)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/tBFRUjf_Akw"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1e66n9ORud4"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 自立期 自律期 乳幼児の心理
幼児の心理 発達心理学)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 自立期 自律期 乳幼児の心理
幼児の心理 発達心理学)
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
【主張訓練法】(年中児・4歳、5歳児)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ykHBJ91VAys"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
●主張訓練法(2011-12-03改)
【BW教室の指導から】(主張訓練法)
●「NO!」が、はっきり言える子ども
少し前、「YES」「NO」がはっきり言える
子どもについて書いた。
その根拠というか、それが見つかったので
報告します。
+++++++++++++++
●行動療法
心理学には、「行動療法」というのがある。
その中のひとつに、「主張訓練法」というのがある。
これは子どもに、(おとなでも構わないが)、「YES」「NO」をはっきり言わせることに
よって、「対人場面における、不安感や緊張感を軽減する方法」(臨床心理学・ナツメ出版)で
ある。
ある。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 対人訓練法 主張訓練法 具体
的指導例)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 対人訓練法 主張訓練法 具体
的指導例)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●12月04日【弁天・ジ・オーシャン・ホテルにて】
●東南海大地震
明日起きてもおかしくない。
しかし30年以内に起こる確率は、100%。
それが東南海大地震。
ウィキペディア百科事典には、つぎのようにある。
『……紀伊半島沖から遠州灘にかけての海域(南海トラフの東側)で周期的に発生する海溝型
地震。規模は毎回 M8・0 前後に達する巨大地震で、約100年から150年周期で発生してい
る。東南海大地震(とうなんかいだいじしん)とも呼称される』(ウィキペディア百科事典)と。
地震。規模は毎回 M8・0 前後に達する巨大地震で、約100年から150年周期で発生してい
る。東南海大地震(とうなんかいだいじしん)とも呼称される』(ウィキペディア百科事典)と。
弁天にあるジ・オーシャン・ホテルへ着くと、ワイフがそんな話をした。
ちょうど夕日が沈むころだった。
私はベランダに、ビデオカメラを設置した。
とたん、つまりワイフがその話をしたとたん、安らいだ気分が、しぼんでしまった。
●弁天・ジ・オーシャン・ホテル
ジ・オーシャン・ホテル……来るたびに、少しずつサービスが良くなっていく。
本気度は、いつも通り。
が、ほめてばかりいてはいけない。
今回からは、駐車も別途料金になった。
(残念!)
「この11月から、一泊、800円になりました」と。
先月(11月)の20日に泊まったときには、無料だった。
今年の夏前には、カラオケルームも、無料で使わせてくれた。
が、今夜はどうか?
料理の質も、少しずつ良くなっている。
温泉はいつもの温泉。
が、毎回、客がふえ、その分だけ、温泉は混雑してきた。
私たち、客側にしてみれば、すいているほうがよい。
しかしホテル側にしてみれば、混んでいるほうがよい。
言うまでもなく、ホテル業は、(旅館業もそうだが)、地元のリピーターが多いかどうかで、経営
状態が決まる。
状態が決まる。
地元のリピーターにそっぽを向かれたら、経営は、広告宣伝費ばかりがかさみ、急速に悪化す
る。
る。
●避難
部屋へ入るとすぐ、温泉に向かった。
が、どうも落ち着かない。
「地震が起きたら、どうするか?」と。
(1)今回は、10階のX号室。
耐震性はだいじょうぶか。
このあたりは砂地のはず。
大地震で倒壊する心配もある。
(2)津波はどうか?
このホテルから見える表弁天は、湾になっている。
(注:このあたりの人は、中州を境に、太平洋側を表弁天、北側を裏弁天と呼んでいる。)
その表弁天、周囲は30キロ(目測)ほどあるだろうか。
向こう側は低い砂丘になっている。
しかし大地震の津波なら、難なく乗り越えてくるだろう。
(3)夜中だったどうするか?
地震が夜中に起きたら、どうするか。
電気は切れ、恐らく真っ暗になるはず。
(4)浜岡原発は安全か?
ここから東へ40キロほどのところに、中部電力の浜岡原発がある。
中部電力側は、「安全」と、さかんに主張しているが、さて、どうか?
電力会社が「安全」というときは、「国の基準に合致している」という意味。
「国の基準に合致しているから、万が一のときでも、自分たちには責任はない」という意味で、
「安全」という。
「安全」という。
言うなれば役人論法。
国の基準があてにならないことは、フクシマで証明された。
夕食を待つ間、ワイフと地震のときの行動計画を立てる。
(1)地震が収まるまで、部屋の中でじっとしている。(ベッドの間に身を置く。)
(2)揺れが収まったら、とりあえずの荷物をもち、非常口から3~4階あたりまで下りる。(たま
たまワイフが小さな懐中電灯をもっていた。)
たまワイフが小さな懐中電灯をもっていた。)
(3)津波の情報を手に入れる。(パソコンを使う。)
(4)津波情報が入ったら、そのまま静かにしている。(車は、あきらめる。)
(5)防寒対策をしっかりとし、そのまま徒歩で自宅まで帰る。(避難するとき、毛布を体に巻
く。)
く。)
……そんなことを考えていたら、温泉気分が吹き飛んでしまった。(ホント!)
●家出
話題を変えよう。
昨日、長野市に住む友人と、1時間ほど、電話で話す。
柿を送ってくれた。
その礼の電話が、長くなった。
友人は定年まで、工作機械メーカーに勤務していた。
定年後は、……つまり今は、奥さんが経営している行政書士事務所の手伝いをしている。
その友人が、こんなことを言った。
友「なあ、林君、もし君が家出をしたとするよな。そんなとき、林君を泊めてくれるような友人
は、何人、いる?」
は、何人、いる?」
私「……いないなあ……。1人もいないよ」
友「だろ……。ぼくもいないよ……」
私「ぼくなんか、よく家出するけど、いつもホテルや旅館を回っている」
友「親類は、どうだ?」
私「……いないなあ……」
友「じゃあ、さあ、今度家出したら、俺んチへ来いよ」
私「……ウ~ン、やっぱりできないなあ……。君んとこにも、家族がいるし……」と。
私のばあい、むしろオーストラリアのほうに、そういう友人がいる。
反対に彼らは、2、3か月単位で、我が家に泊まっていく。
しかしオーストラリアまで家出するというわけにはいかない。
●孤独
友人に言わせると、「それが老後の自分だよ」と。
つまりこの先、年を取れば取るほど、そういう友人が少なくなる。
相手の友人が迷惑するというより、その家族が迷惑する。
親戚にしても、そうだ。
仮に配偶者(妻か夫)が亡くなれば、家出と同じ状況になる。
そういったとき、泊めてくれる友人、つまり孤独を慰めてくれる友人は、何人いるだろうか。
友人は、それを言った。
●雑誌『Mr. PC』
ここへ来る途中、書店に寄った。
パソコン雑誌の『Mr. PC』を買った。
ほとんど毎号、買っている。
付録のソフトが楽しい。
今回は、「オリジナル年賀状」というのが、目にとまった。
カードのリンクを相手が開くと、文字がこちらが書いたように動き出すという。
いろいろに応用できそう。
15~20年前なら、こうしたソフトを、1本、1本、4000~6000円で購入していた。
それが今では、100本近く収録されていて、650円(『Mr.PC』)!
温泉から戻ると、さっそく、それを試してみる。
……どうかな?
さっそく1枚、作ってみた。(下をクリック!)
http://www.kaki-kaki.com/draw_mail/view.html?61711257100406
●夕食後
夕食後、ワイフはビデオ。
題名は、『白いカラス』。
が、私はパソコン。
パソコンに向かって、文章を書く。
●白い道
このところ毎日、朝起きるとイチバンに、ウォーキング・マシンの上で汗をかく。
そのときのこと。
たいてい目を閉じて歩くのだが、いつも頭の中に同じ光景が思い浮かんでくる。
……一本の白い道。
舗装された白い道で、それがまっすぐその先にある小山につながっている。
私はその小山に向かって、時速6キロで歩く。
結構、速い。
で、10分、20分……と歩いていくと、だんだんと、その小山が近づいてくる。
通り過ぎる車はない。
人影もない。
ただそこにあるのは白い道。
が、いつも小山のふもとまで来ると、そこで時間切れ。
ちょうど30分になる。
で、1週間ほど前、心に決めた。
「今度こそ、小山のふもとまで行ってやろう」と。
で、その朝、それを実行した。
が、私がそこに見たのは、二階建ての灰色の建物だった。
コンクリートの建物。
窓がいくつかあったが、黒いカーテンで中は見えなかった。
ドアも黒く、見ただけで、開かないことがわかった。
以来、毎日、運動をしていると、その建物が見えるようになった。
●夢判断
白い道は、何を表すか。
灰色の建物は、何を表すか。
ウォーキング・マシンの上で運動をしながら見る夢(?)としては、ありふれたもの。
灰色の建物は、運動のゴールを表す。
が、その建物の中には、入れない。
黒いカーテンとドアで、しっかりと閉じられている。
たぶんそれは、私の想像力の欠落によるものだろう。
あるいは私の脳の奥を象徴しているのかもしれない。
夢といっても、眠っているわけではない。
●『白いカラス』
しっかりと観ているわけではない。
しかしなかなかよさそうな映画。
主演は、アンソニー・ホプキンズ。
ニコール・キッドマンも出てくるはずだが、今のところまだ登場していない。
(この間、2時間ほどDVDを観る。)
……星は4つの、★★★★。
ホーソーンの、『スカーレット・レター(緋文字)』を思わせるような、シリアスな映画だった。
●『行動は思考の敵』
DVDの中で、ニコール・キッドマンがこう言った。
車の中で、アンソニー・ホプキンズに、「行動は思考の敵」と。
どういう意味でそう言ったのかはしらないが、そのヒントはいくつかある。
アンソニー・ホプキンズは、こう言う。
「バイアグラの世話にさえならなければ、今ごろは、学生たちの人生の意味を教えている」(記
憶)と。
憶)と。
アンソノー・ホプキンズは、バイアグラをのみながら、34歳のニコール・キッドマンと関係をもち
つづける。
つづける。
●理性の敵
恋愛ほどすばらしい、人との関わり方はない。
が、同時に恋愛ほど、人間の理性を狂わすものはない。
表に天国、裏に地獄。
恋愛を一言で表現すれば、そういうこと。
で、思考を理性とするなら、恋愛という行動は、即、思考の敵ということになる。
が、私はこう考える。
人生も残り10年になったら、本能から解放されたい、と。
逆の見方をすると、こうだ。
本能の虜(とりこ)になり、10年を無駄にする人は、いくらでもいる。
そういうことは、それができる人に任せておけばいい、と。
どうであれ、私はバイアグラの世話になっていないし、この先も、世話になるつもりもない。
●耳下腺炎
温泉に長くつかっていると、ときどき耳下腺炎になる。
今が、そうだ。
左耳の下あたりが、押さえると、痛む。
こういうときはビタミンC(アスコルビン酸)を飲むとよいが、今は、それがない。
症状がひどくなったら、家に戻ればよい。
ここからなら、家まで、車で20分もかからない。
……かばんの中を探すと、薬箱の中に、バッファリンが見つかった。
菓子パンで胃をごまかしながら、それを1錠のむ。
●翌朝
翌朝は、7時、起き。
朝食は、7時から。
あわてて食堂へ……。
ワイフが部屋を出るとき、こう言った。
「目覚まし時計は、なったの?」と。
こうして今日も、始まった。
みなさん、おはようございます。
(はやし浩司 2011-12-05 浜名湖弁天リゾート・ジ・オーシャンにて)
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
●12月07日【沼津・港八十三番地で夕食+三島・ドーミーインホテルに一泊】
+++++++++++++++++++
今、沼津に向かう列車の中にいる。
明日の朝、三島市で講演をする。
そのため今夜は、三島市で一泊。
ホテルへ入る前に、今夜は夕食は沼津市でとる。
最近、沼津市に新しい食堂街ができたとか。
海産物をふんだんたべさせてくれる。
楽しみ。
そこへ行く。
+++++++++++++++++++
●長寿と長命
「長寿」と「長命」は、ちがうのだそうだ(「週刊現代」記事)。
長寿というのは、健康な状態で長生きすること。
長命というのは、「ただ長生きすること」だ、そうだ。
たとえば寝たきりの状態の人は、たとえ高齢であっても、「長寿」とは言わない。
「長命」と言う、と。
(以上、参考:「週刊現代」誌)
●長生
長寿と長命。
が、私は、これに「長生」を加える。
ただの「長生き」のことではない。
謡い(うたい)に、『鶴亀』というのがある。
その中に、「♪君の齢(よわい)も、長生殿に~」という文句が出てくる。
このばあいの「長生殿」は、「老後の理想郷」をいう。
またそうであってこそ、『鶴亀』!
勝手に私はそう解釈している。
つまり健康に生きるだけでは、足りない。
その足りない部分を補うのが、「前向きな生」。
だから「長生」。
これら3つを並べてみる。
長命……ただの長生き
長寿……健康で長生き
長生……生きがいをもち、健康で長生き
●人は死ぬもの
その「週刊現代」(最近号)の中で、あるドクターがこう言っている。
「いろいろながん患者をみてきたが、人は死ぬものです」と。
聞き方をまちがえると、辛辣(しんらつ)な言葉にも聞こえる。
しかし今までに何千人(同)もの死を、直接見つめてきたドクターだからこそ言える言葉である。
つまり、「がんのような大病になったら、すなおに死を受け入れたほうがいい」(同)と。
具体的には、「70歳を過ぎたら、手術はするな」(同)と。
「たとえ手術をしても、そのあと寝たきりになったら、意味はない」(同)とも。
(以上、手元に「週刊現代」誌がないので、記憶による。)
●生きがい
60歳を過ぎ、生きがいをもって生きるのは、たいへん。
同じ「週刊現代」の別のところでは、年金問題に触れ、ある男性の言葉を紹介していた。
「もう、仕事はこりごり」と。
仕事はこりごり?
……だから退職後は、年金だけで遊んで生きていきたい?
ということで、この数週間、「週刊現代」は、年金の60歳からの繰り下げ受給論を展開してい
る。
る。
その分だけ割り引かれるが、年金は、早めに受給したほうが、得、と。
そうかもしれない。
そうでないかもしれない。
ただ「週刊現代」は、重要な問題を見落としている。
多分、その記事を書いたライターは、若い人なのだろう。
●老後の生きがい
中には「仕事はこりごり」という人もいるかもしれない。
が、みながみな、そうではない。
こりごりということはわかる。
が、仕事をやめたあと、どうするのか?
よく「老後は、庭いじりと孫の世話」と言う人がいる。
しかしそんなことで、老後は過ごせない。
過ごせないことは、自分が老後を迎えてみて、よくわかった。
(私自身は、今の人生を老後とはまだ思ってないが……。)
「仕事はこりごり」と言う人は、よほど不幸な現役時代を送っていたにちがいない。
どんな仕事だったかは、知らない。
毎日が苦痛でたまらなかったのかもしれない。
が、やっとその仕事から解放された。
だから「こりごり」と。
が、たとえそうであっても、そのことと老後の生きがいとは別。
●統合性
もう何度も書いてきたが、いかに統合性を確立するか。
それが老後の第一課題ということになる。
(自分のすべきこと)を発見し、無私、無欲で、(それをする)。
思春期の「自我の同一性」の問題と、中身を同一にする。
若い人は、(自分のしたいこと)を模索し、その(したいこと)に自分を一致させていく。
これを「自我の同一性」という。
その(自分のすべきこと)を発見した老人は、幸福である。
その(すべきこと)に向かって、邁進努力している老人は、幸福である。
そのひとつのヒントとして、心理学の世界では、「真・善・美」という言葉を使う。
「真・善・美のどれかを追求する」と。
●無私、無欲
ここで「無私、無欲」という言葉が出てくる。
功利、打算、利潤の追求が混在すると、「統合性の確立」は霧散する。
無私、無欲でなければならない。
また無私、無欲でするからこそ、統合性を確立することができる。
●年金
年金をもらって生きる……。
若い人たちからみれば、うらやましいような話に聞こえるかもしれない。
(あるいは怒っている人も多いかと思う。)
しかし中には、それをよしとしない人もいる。
たとえばこの私。
年金制度ほど、不公平なものはない。
どう不公平かは、今さら改めて指摘するまでもない。
私も、お金は嫌いではない。
もらえるものは、もらいたい。
しかし国民年金など、もとからアテにしていない。……できない。
1、2年前、通知書が届いたが、それには満65歳から、月額6万4000円(?)とあった。
●繰り上げ受給
週刊現在によるまでもなく、年金はたとえ割引されても、早めにもらったほうがよい。
これを「繰り上げ受給」という。
実際には、老齢基礎年金のことをいう。
その老齢基礎年金について言えば、60歳からもらったほうが、70歳になる時点においては、
600万円ほど、多くなる。
600万円ほど、多くなる。
しかし85歳までもらうとすると、反対に200万円ほど、少なくなる。
(以上、「All Aboutサイト」での試算による。)
その差額を、そう判断するか?
が、それでも年金は、早めにもらったほうがよい。
というのも、早晩、日本の年金制度は、まちがいなく破綻する。
2050年(=38年後)には、1・2人の実労者が1人の高齢者を支える時代になる。
消費税をあげようが、どんなことをしようが、それは不可能。
つまり1・2人の実労者が、1人の老人を支えるのは、不可能。
さらに言えば、この先、日本経済はどうなるか。
猛烈なインフレに襲われる心配もある。
だったら週刊現代が説くように、早めにもらったほうがよい。
が、だからといって、それが老後のあるべき姿ではない。
●労働力不足から粗大ゴミ
15年ほど前から、少子化が叫ばれるようになった。
当時は、少子化問題は、労働力不足問題のことをいった。
「どう労働者を確保するか」が、問題だった。
が、今は、大きく様変わりした。
労働力不足問題は、どこかへ消えてしまった。
職場そのものが、消えてしまった。
つまりとたん、老人は労働者ではなく、「粗大ゴミ」になってしまった。
が、これは(我ら)老人組にとっては、悲しむべき社会現象と考えてよい。
●「老人よ、働こう」
が、それでも私はこう説く。
「老人よ、働こう」と。
統合性を確立した老人は別として、その確立に失敗した老人は、働くしかない。
が、私は老人が働くことを、悲観的にとらえているのではない。
働くことによって、日々の生活の中に、緊張感が生まれる。
この緊張感が、その人をして、生き生きと生きがえさせる。
生きがいも、そこから生まれる。
●昼寝
たとえば私は現在、努めて昼寝を日課としている。
昼寝はボケ防止によいという説もある。
それはその通りで、歳を取ればとるほど、こだわりが強くなる。
(こだわり)は、脳の大敵。
こだわっている部分の脳は活発に働くかもしれないが、それ以外の脳は、休眠状態になる。
つまりその部分から、ボケ始める。
が、昼寝をすることによって、脳みそを一度、リセットすることができる。
カラッポにすることができる。
●緊張感
その昼寝をしているときのこと。
ときどき、ワイフに起こされる。
「あなた、仕事よ!」と。
そういうとき私は、仕事があることを心底、恨む。
「もっと眠っていたい」と思う。
その前に、体が動かない。
その動かない体にムチを打ち、起きあがる。
起きあがって、支度を整え、自転車にまたがる。
それがここでいう緊張感である。
そんなとき、ふと、こう思う。
「もし、仕事がなかったら、1か月でぼくは、病気になってしまうだろうな」と。
●長生
長寿をめざす。
それはそれで重要なことかもしれない。
しかしそれだけでは足りない。
それが「長生」ということになる。
「いかに生きるか」でもよい。
●こだわり
ここで(こだわり)という言葉が出てきたので、一言。
10年ほど前、たいへんこだわりの強い女性(70歳くらい)がいた。
「固執」「固着」「執着」ともいう。
これらの言葉は、それぞれの世界で使われる。
心理学の世界では、「固着」という。
仏教の世界では、「執着」という。
平たく言えば、(こだわり)。
老人の(こだわり)には、注意したほうがよい。
ひとつのことに、こだわればこだわるほど、脳のほかの部分の働きが、おろそかになる。
そうでなくても、脳みそは、不可逆的に退化していく。
その女性は、65歳くらいから、おかしな言動を繰り返すようになった。
突発的に興奮状態になることもあった。
70歳をすぎてから、音信が途絶えたので、様子はわからない。
しかし何かの脳の病気になり始めていたことは、じゅうぶん疑われる。
●こだわり
その女性は、ことあるごとに、弟氏の悪口を並べた。
「法事に来たが、タクシーに乗ってきた」
「夫が話しかけたが、形だけの返事しかしなかった」
「法事というのに、柄物の靴下をはいてきた」
「供養の袋だけで、供物を何ももってこなかった」などなど。
まるでその場をビデオカメラで収めたかのように、悪口を並べた。
が、そうした(こだわり)のほうこそ、大きな問題だった。
その女性は、それに気づいていなかった。
●3つの教訓
最近では、脳の活動の様子を、リアルタイムでそのまま知ることができる。
それによっても、こだわりの強い人というのは、脳のその部分は活動しても、ほかの部分が休
眠状態になることがわかっている。
眠状態になることがわかっている。
このことは、私たちに3つの教訓を与えてくれる。
ひとつは、(こだわり)はもたないほうが、よいということ。
脳はいつも、平均的かつ全体的に、活動していたほうがよい。
もうひとつは、(こだわり)を少なくするため、いつも新しいことに興味をもったほうがよいという
こと。
こと。
平凡は美徳だが、老後の平凡は、美徳でも何でもない。
警戒すべきは、単調な生活。
変化に乏しい生活。
へたをすれば、そのまま死の待合室に直行……ということにもなりかねない。
そして3つ目は、こだわりが強くなったら、脳の変調を疑うということ。
老人性のうつ病の主症状は、(老人にかぎらないが)、こだわりと考えてよい。
うつ病イコール、こだわり。
こだわりイコール、うつ病。
●脳の老化
そうでなくても、脳の老化は、日常的に経験する。
記憶力の低下、集中力、気力の低下など。
好奇心の低下は、そのまま自分の住む世界を、小さくする。
来る日も来る日も、同じことを考え、同じことをするようになったら、脳の老化はすでに危機的
な段階に入っていると考えてよい。
な段階に入っていると考えてよい。
それに(こだわり)が加われば、そのこだわっている部分はともかくも、ほかの部分が一気に
老化する。
老化する。
その女性については、こんなことがあった。
●ボケ症状
ワイフのクラブの会費を、その女性がなくしてしまった。
その数日前まで、こう言っていた。
「会費は青い封筒に入れ、バッグの中にあります」と。
が、ワイフがその数日後に電話すると、こう言った。
「私、そんなお金、知りません」
「青い封筒など、知りません。そんな話をした覚えは、ありません」と。
こういうのを、「ボケ」という。
オーストラリアの友人が、こう教えてくれた。
「小便のあと、(ズボンの)チャックをあげ忘れても、ボケではない。
小便の前、チャックをさげ忘れたら、ボケ」と。
●静岡から沼津へ
今、列車は静岡を出た。
時刻は午後4時、少し前。
窓の外は、すっかり冬景色。
いつものように乗客観察を始める。
服装や話し方、その人のもつ雰囲気で、その人がどんな人物かを、言いあてる。
シャーロック・ホームズが得意とした芸である。
が、今日は、前に座った女性(30歳くらい)が気になった。
この列車に乗ってからというもの、もう1時間以上も、話しつづけている。
声はさほど大きくはない。
が、口が止まらない。
ペチャクチャ、ペチャクチャ……。
となりの女性に、一方的に話しかけている。
●AD・HD
私「AD・HDだよ」
ワ「……AD・HD?」
私「そうだよ、目を見ればわかる。焦点が空を向いているだろ。相手の顔を見ていない……」
ワ「そうね……」
私「相手が何を聞きたがっているか、相手がどの程度理解しているか、そんなことはお構いな
しに話しつづけている」
しに話しつづけている」
ワ「目も、どこかトロンとしているわね」
私「そうだよ。会話になっていない。脳に飛来する情報を、そのまま言葉にしている」と。
AD・HD児というと、男児に多い障害と考えられている。
が、実際には、女児にも多い。
その第一の特徴が、多弁性。
とにかくよくしゃべる。
うるさいほど、よくしゃべる。
注意しても、効果はその場だけ。
つぎの瞬間には、またしゃべり始める。
多動性や騒々しさは、おとなになると消えてくるが、女性のばあい、多弁性だけは残ることが
多い。
多い。
●鈍行列車
書き忘れたが、今日は、鈍行列車を選んだ。
急ぐ旅行ではない。
それに私は、このパソコンを叩きたかった。
新幹線で行けば、一度三島まで行き、そこで少し戻る形で、沼津に行く。
時間は、1時間10分。
鈍行列車では、2時間。
が、今、決めた。
「帰り(明日)は、新幹線にしよう」と。
●接客業
話題を変える。
私は若いころ、……35歳くらいのことではなかったか、旅館経営をしてみたくなった。
「毎日、温泉に入って、ごちそうが食べられる」と。
単純な発想だった。
で、長野市にいた友人に相談すると、すぐ、いくつかの旅館を紹介してくれた。
長野市で、司法書士をしていた。
「○○温泉郷あたりなら、いくらでも売り物件があるよ」と。
が、その直後から、私は山荘建設に取りかかった。
小さな山を丸ごと買い、造成した。
で、その話をしながら、列車の中でワイフとこんな話をした。
「あのとき旅館を買わなくて、よかったね」と。
接客業ならなおさら、人を接客するというのは、大仕事。
そのあと自分で山荘をもってみて、それがヨ~ク、わかった。
●何もしない……
結論を先に言えば、40代以上(当時)の男たちは、何もしなかった。
山荘へ来ても、デンと座っているだけ。
何も手伝わない。
「手伝おうか?」とも、聞かない。
ただ座っているだけ。
「上げ膳、据え膳」……というような生やさしいものではなかった。
風呂の準備から、寝具の用意などなど。
食後のコーヒーまで。
あるとき、こんなことがあった。
高校時代の同級生が泊まったときのこと。
朝、居間でコーヒーを飲みながら、こう言った。
「なあ、林、近くにパルパル(近くの遊園地)というところがあるみたい。そこへ行こうか?」と。
見ると、浜松市内の観光地図がテーブルの上に置いてあった。
で、私はこう言った。
「行くといっても、1時間はかかる」と。
するとその友人は、こう言った。
「バカ言え。ここからなら10分で行くよ」と。
私「あのなあ、1時間というのは、これから洗い物をし、部屋を片づけ、戸締りをするまでに、1
時間かかるということ」
時間かかるということ」
ワ「あとですればいい」
私「またこの山荘へ戻ってくるというわけにも、いかない」と。
人を接待したことがない人には、(現在、50代以上の男性に多いが)、接待の苦労がわから
ない。
ない。
●沼津・港八十三番街
沼津駅をおりると、すぐ「港八十三番街」に向かった。
タクシーでちょうど1000円前後の距離だった。
駅の案内書でもらったチラシには、こうある。
「目の前の沼津港で水揚げされた新鮮な魚介類や地元静岡の食材を使った料理が楽しめま
す」と。
す」と。
タクシーを降りると、店をさがした。
かなりの数の店が並んでいる。
いつか見た台北の居酒屋のようでもある。
香港の裏通りのようでもある。
で、こういうときは、コツがある。
いちばん客の多い店を選ぶ。
……ということで、そのあたりをワイフと2人で歩いた。
で、裏通りへ入ると、ドヤドヤと客が出てきた店があった。
「丸天」という店だった。
中をのぞくと、ガヤガヤと客がいる。
そのほかの店は、どこも、ガランとしていた。
「平日の水曜日なのに、すごい店だな」と。
私たちはその丸天に入った。
●丸天
沼津港周辺にある海鮮料理屋の海鮮料理は、昔から量が多い。
刺身でも、天ぷらでも、はたまた寿司でも、ドカッと出される。
丸天でも、そうだった。
ワイフは海鮮丼。
私はマグロのテール・シチューと、かき揚げ。
その量を見て、驚いた。
マグロのテール・シチューだけでも、食べきれない。
私とワイフは、1時間ほどかけ、ゆっくりと食べた。
途中、汗が出てきた。
暑いというより、食べすぎ?
全体に7割前後食べ、そこでギブアップ。
料金は合計で、3600円。
マグロのテーブル・シチューは、ほかでは食べられない。
握りこぶし大のマグロの肉が、2切れ、大きな皿の上に載っていた。
珍味中の珍味。
おいしかった。
帰りにタクシーの運転手に話すと、運転手は、こう言った。
「ああ、あの店ね。昼は、行列ができる店ですよ」と。
沼津・港三十八番地、裏通り、丸天は、星5つの、★★★★★。
まちがいなし!
●沼津港深海水族館
今日は12月07日。
12月10日から、その食堂街の少し奥に、「深海水族館」なるものがオープンするという。
手にしたチラシによれば、「あのシーラカンスが見られる」とある。
水族館は、外から見た感じでは、それほど大きくなさそう。
しかしシーラカンスというのは、すごい!
冥土のみやげに、一度、見てみたい。
そうそう帰りのタクシーの中で、運転手が、こんな話をした。
あの3・11大震災の後のこと。
しばらくは、そのあたりでは、毎日客ゼロの日が続いたという。
「理由は?」と聞くと、「地震と津波ですよ」と。
運「このあたりも、あんな大きな津波が来たら、ひとたまりもありませんよ」
私「……それで、ですか?」
運「沼津駅あたりまで、津波は押し寄せるでしょうね」
私「……」
運「このあたりも大地震が心配されていますからね」と。
●三島へ
沼津から三島へは、1区間。
が、その1区間が長い。
途中、途切れることなく、街並みが続いている。
「みんな、このあたりの人たちは、どうやって通勤しているのだろう」と、その街並みを見なが
ら、ふとそんなことを考える。
ら、ふとそんなことを考える。
同じ静岡県にありながら、西にある浜松市と、東にある三島市とでは、雰囲気がまったくちが
う。
う。
経済が低迷する浜松市。
東京的な雰囲気を漂わせる三島市。
2年会った県会議員の女性は、こう言った。
「(静岡県の)西では、地価が下がっている。東では上がっている」と。
静岡県は、東西に長い県である。
●三島・ドーミンイン・ホテル
明日(8日)は、講演がある。
私は講演のある日は、食事を抜く。
「腹が減っては、戦はできぬ」という。
が、講演は、逆。
「腹がふくれていては、講演はできぬ」。
講演というのは、そういうもの。
で、今日は、素泊まり。
朝食抜き。
ホテルは、ドーミンイン・ホテル。
1泊、1人、3500(ダブルベッドルーム)。
2人で、7000円。
ポイントが使えたので、2人で、6600円。
「2人で6600円ですか?」と聞くと、「はい、そうです」と。
●ハイテク・ホテル
部屋はややせまいかな……という感じだったが、まさにハイテク・ホテル。
スイッチ類や水道の蛇口まで、今まで見たことがないようなものばかり。
大型の加湿器まで備えてあった。
説明書には、こうある。
「……インフルエンザ対策として、強力除菌噴霧器で各部屋を除菌、各フロアに空気清浄器、
各部屋に自動気化式加湿器を設置しています。
各部屋に自動気化式加湿器を設置しています。
なお以下の各箇所を、アルコール消毒しています」と。
……加えて、無駄がない。
たとえば12階には温泉がある。
小さいが露天風呂とサウナルームも併設。
その風呂場には、洗濯ルームまである。
エレベーターにしても、まさにハイテク。
最新。
なおワイフの話では、女性風呂のほうは、そのつどフロントに電話をかけ、暗証番号を入力し
ないと、ドアが開かないようになっている、とか。
ないと、ドアが開かないようになっている、とか。
で、部屋にはシャワールーム設備のみがあったが、私はそれでじゅうぶんと思う。
内風呂までは、不要。
風呂へ入りたい人は、12階の温泉へ入ればよい。
風呂は、もちろん、オールナイト。
●文句なしの、5つ星
さらにタオル類には、ホテル名が刺繍してある。
(印刷ではなく、刺繍だぞ!)
またホテル全体、通路、部屋が、白と黒で統一されている。
壁は白、ドアは黒、と。
さらにコップと歯ブラシの色も、それに合わせて、それぞれ白と黒の2種類になっていた。
その色が、同じ!
しかもそれぞれが、ドーミーインのネーム入りの袋に入っていた!
私もワイフも、驚いた。
ここまで客を喜ばせるホテルは、そうはない。
料金を勘案すれば、星は文句なしの、5つ星の、★★★★★。
書き忘れたが、部屋は清潔。
汚れひとつない。
正式には、「HOTEL dormy inn」(案内書)という。
サウナで知りあった男性は、「連泊しています」と言った。
●明日(はやし浩司 2011-12-08)
部屋で落ち着くと、睡眠導入剤を、口にした。
いつもよりやや多めの、ひとかけら。
時計を見ると、午後7時30分。
「明日こそは、失敗しないぞ」と、心に誓う。
「うまくやろう」という気持ちは、まったくない。
「失敗しないぞ」と。
テレビを観ながら、床に就く。
●深夜の起床
ぐっすり眠った……と思いながら、夜中に目を覚ました。
が、時計を見ると、午後11時30分!
夢の中に、昔の生徒と母親が出てきた。
何かの議論をしていた。
しばらくそのまま横になったが、ワイフが寝返りを打ったとき、私は起きた。
……パソコンを開き、あちこちのニュースサイトをのぞく。
まず飛び込んできたのが、柔道の金メダリストによる、破廉恥事件。
10代の教え子を、酒に酔わせ、ホテルへ連れ込み、ワイセツ行為に及んだという。
余罪もあるらしい。
去年(2010年)だったか、泥酔中の女性と関係をもったら、強K罪になるという判例が出た。
当の本人は、「合意の上だった」と主張しているようだが、一度、こういう判例が出ると、それは
無理。
無理。
その判例をひっくり返すためには、日ごろからそういう恋愛関係にあったという客観的な証拠
が必要。
が必要。
逆にみれば、その目的を隠しながら、わざとその女性を泥酔させたとも、考えられる。
もしそうなら、犯意は、かぎりなく醜悪。
ネットで経歴を調べてみたが、結婚はしているらしい。
「奥さんがかわいそう」と。
ふと、別の心で、そんなことを考える。
●欲望
「金メダルを取りたい」という欲望。
その欲望は、そのまま性的欲望と、一直線につながっている。
ともにドーパミンの作用による。
心理学でいう「リビドー」をあてはめて考えると、理解しやすい。
ウィキペディア百科事典には、つぎのようにある。
『……リビドー(ラテン語: Libido)とは、日常的には性的欲望または性衝動と同義に用いられ
る。
る。
これはジークムント・フロイトが「性的衝動を発動させる力」とする解釈を当時心理学で使用さ
れていた用語Libidoにあてたことを継承したものである。
れていた用語Libidoにあてたことを継承したものである。
一方で、カール・グスタフ・ユングは、すべての本能のエネルギーのことをLibidoとした』と。
平たく言えば、生きるエネルギーが強力な人ほど、他方で、性的欲望も強力ということ。
『英雄、色を好む』という俗説も、そんなところから生まれた。
が、だからといって、私はその柔道選手を擁護しているわけではない。
バカである。
『バカなことをする人を、バカというのよ。(頭ではないのよ)』(「一期一会・フォレスト・ガンプ」)
と。
と。
●性癖
ワイフにこう聞く。
「もし、ぼくが10代の女性を泥酔させ、ホテルへ連れ込んだと知ったら、どうする?」と。
が、ワイフは即答を避け、こう言った。
「もともとそういう人とは、結婚しないわ」と。
性癖というのは、みな、ちがう。
こと性癖について書くなら、「男はみな……」という論法ほど、アテにならないものはない。
たとえば(スカートの中)。
手鏡を使ってスカートの中をのぞいた、どこかの大学教授がいた。
で、そういう事件を見聞きすると、女性たちは、「男はみな……」と考えるかもしれない。
が、これはここで私はこう、断言できる。
興味の程度には、大きな個人差がある。
興味があっても、実際、そうした行動に出る男もいれば、そのなん歩も手前で、自分を引いてし
まう男もいる。
まう男もいる。
そのエネルギーは、男によって、みなちがう。
私自身も、若いころ、興味がなかったわけではない。
しかしあえて見たいと思ったことはない。
●性癖
ではその男の性癖は、いつごろどのようにして作られるのか。
それには、「抑圧」の問題が、大きくからんでいる。
たとえば私のばあい、思春期のころ銭湯に通っていた。
その銭湯へ行くたびに、入り口のところから、そっと女湯のほうをのぞく
それは楽しみなことでもあった。
が、それはたいへん悪いことでもある。
自分にそう言って聞かせた。
つまり心の中に抑圧し、封印した。
今にしてみると、それが私の性癖を作った。
今でも、入浴後の女性のにおいをかぐと、ふつうでない色気を感ずる。
だから私は若いころから、いつもこう願っていた。
一度は、女性と混浴をしてみたい、と。
いや、一度だけだが、ある。
●混浴
その混浴だが、生涯において、一度だけ、したことがある。
私が大学4年生のときのことだった。
伊豆の堂ヶ島でのことだった。
舟を利用した天然の温泉にひとりつかっていたら、3人の若い女性がそこへ入り込んでき
た。
た。
驚いたのなんのと言ったら、なかった。
が、女性たちは慣れた雰囲気で、そのままジャバジャバと、舟の中へ。
そして私と並んで湯船につかった。
が、それは想像していたのとは、まったくちがっていた。
健康的というか、卑猥(ひわい)感は、まったくなかった。
世間話こそできなかったが、平静だった。
じっと身動きもせず、私はだまったまま、下を向いていた。
私にとっては、生涯忘れえぬ、すばらしい(?)思い出となった。
●リビドー(心的エネルギー)
ついでながら、ウィキペディア百科事典には、つづけて、つぎのようにある。
『……精神分析学ではリビドーを、様々の欲求に変換可能な心的エネルギーであると定義して
いる。
いる。
リビドーはイド(簡単にいえば無意識)を源泉とする。
性にまつわるものだけでなく、より正確には人間の性を非常にバラエティに富んだものへと向
ける本質的な力と考えられている。
ける本質的な力と考えられている。
リビドーが自我によって防衛・中和化されることで、例えば男根期の露出癖が名誉欲に変わる
など、社会適応性を獲得する。
など、社会適応性を獲得する。
また支配欲動が自己に向かい厳格な超自我を形成して強い倫理観を獲得することもある』と。
わかりやすく言えば、こうしたエネルギーは、使い方の問題ということ。
うまく使えば、すばらしい人間になれる。
が、使い方を誤ると、先の柔道選手のようなことをするようになる。
逆に言えば、善人も悪人も、紙一重。
大きく違うようで、どこも違わない。
……これは私の昔からの持論。
●深夜の入浴
これから一風呂浴びてくる。
多分、そのまま、最就寝。
日は替わって、今日は12月08日。
こんな状態で、今日はよい講演ができるのだろうか。
かなり心配になってきた。
●午前6時05分
先ほど、目を覚ました。
時刻は、薄明るくなり始めたころの、午前6時05分。
外は雨模様。
加湿器のおかげで、エアコン独特の、あの乾燥もなく、ぐっすりと眠れた。
起きるとワイフはそのまま温泉へ。
私は、あちこちのニュースサイトに目を通す。
日本が夕方になると、EUが動き出す。
日本が真夜中のうちに、アメリカが動き出す。
日本が朝を迎えるころ、EUやアメリカがその日の結論を出している。
●新聞
風呂から戻ってきたワイフが、新聞をもってきた。
「エレベーターのところに、『ご自由にどうぞ』とあったから」と。
最近では、一流ホテルでも、ここまでのサービスはしない。
……この数日、経済ニュースは読まないようにしている。
どうでもよいというか、狂っている。
ささいな動きをとらえて、ヌカ喜び。
株価は大暴騰。
その翌日には、反対に、取り越し苦労。
株価は大暴落。
1日ごとに、大変動。
それよりも心配なのは、こうしたストレスが、新興国に与える影響。
長引けば長引くほど、その圧力が、それぞれの国で政情不安を引き起こす。
●女性天皇
週刊誌(新聞広告)は、相変わらず女性天皇の問題について論じている。
すでに国民の70%以上(各種世論調査)が、女性天皇を支持している。
が、ここで重要なのは、天皇自身の意思。
天皇自身はどのように考え、願っているのか。
私たちはもう少し天皇の気持ちを、大切にすべきではないのか。
即位に際しても、そうだ。
日本国の象徴であるということは、想像を絶する重責である。
そんな重責を、天皇自身の意思を無視したまま、一方的に押しつけるのも、どうか。
あるいは一度でも、「重責を担(にな)っていただけますか」と、天皇に聞いたことがあるのだろ
うか。
うか。
それもしないで、外野席だけが、ワイワイと勝手に騒ぐ。
ワイワイと騒いで、「これが結論です」と、一方的に天皇家の人たちに、押しつける。
天皇にしても、天皇である前に、1人の人間としての「人権」がある。
その人権を踏みにじりながら、後継問題を論じて、どうする?
どうなる?
さらに一歩踏み込めば、こうも言える。
「どうして日本人は、こうまで『格式』にこだわるのか」と。
今は、もう、そんな時代ではない。
もっと皆が、(もちろん天皇家の人たちも含めて)、自由に自分の意見を言い、したいようにす
る。
る。
その結果としてなら、女性天皇が誕生しても、何もおかしくない。
国民も、(もちろん私も)、喜んでそれを支持する。
●準備完了
時刻は7時50分。
先ほどシャワーを浴び、身支度を整えた。
準備、完了!
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教育
評論 はやし浩司 沼津 第三十八番地 丸天 はやし浩司 三島 ドーミンイン・ホテル は
やし浩司 リビドー 性的エネルギー 心的エネルギー 天皇の人権 皇室問題)2011/12/08
記
評論 はやし浩司 沼津 第三十八番地 丸天 はやし浩司 三島 ドーミンイン・ホテル は
やし浩司 リビドー 性的エネルギー 心的エネルギー 天皇の人権 皇室問題)2011/12/08
記
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
. =∞= // (奇数月用)
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 11日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page007.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●主張訓練法(2011-12-03改)
【BW教室の指導から】(主張訓練法)
●「NO!」が、はっきり言える子ども
少し前、「YES」「NO」がはっきり言える
子どもについて書いた。
その根拠というか、それが見つかったので
報告します。
+++++++++++++++
●行動療法
心理学には、「行動療法」というのがある。
その中のひとつに、「主張訓練法」というのがある。
これは子どもに、(おとなでも構わないが)、「YES」「NO」をはっきり言わせることに
よって、「対人場面における、不安感や緊張感を軽減する方法」(臨床心理学・ナツメ出版)で
ある。
ある。
もう一度、そのとき書いた原稿をここに添付しますので、どうか、参考になさってください。
+++++++++++++++
今週は、どのクラスでも、「NO!(いや!)」とはっきり言える子どもの指導をしている。
指導というよりは、訓練。
大きな声で、しっかりと、「いや!」と言わせる。
この簡単な訓練だけで、子どもから優柔不断さが消える。
+++++++++++++++
今週は、幼児クラスを中心に、「いや!」とはっきり言う訓練をしている。方法は、こうだ。
まず、子どもたちがいやがるような、誘いをかけてみる。
私「ゴキブリ・ハンバーグをあげようか」
子「……いらないよう……」
私「だったら、『いや!』とはっきりと言いなさい!」
子「いや……」
私「そんな声じゃ、だめだよ。いやだったら、はっきりと『いや!』と言わなくては……」
子「いや!」と。
つづけて、
私「ねずみのシッポのからあげをあげようか」
子「いや!」
私「シカのウンチのから揚げをあげようか」
子「いや!」
私「ミミズのラーメンはどう?」
子「いや!」と。
こうしたかけあいを、5~10回繰りかえすと、子どもたちは、大声で、「いや!」と言い出す。
そこでさらに、こう問いかける。
どこかいやらしい中年オジサン風の雰囲気で……。
私「どこかへ連れていってあげようか?」
子「いや!」
私「お菓子を買ってあげようか?」
子「いや!」
私「そんなこと言わないで、車にのってよ」
子「いや!」
私「おもちゃを買ってあげるからさあ」
子「いや!」
私「じゃあ、おじさんのおうちに遊びに来る? お菓子がたくさんあるよ」
子「いや!」と。
こうした方法は、心理学の世界でも、有効性が証明されている。
「YES」「NO」を、はっきりと言わせることによって、自我の確立を、より確かなものにすること
ができる。
ができる。
が、それだけではない。
昨今、子どもを犯罪に巻きこむ事件が、相ついでいる。
この方法は、そうした事件に対する、予防策にもなる。
もしあなたの子どもに、どこか優柔不断で、グズグズした雰囲気があるなら、一度、この方法
を試してみるとよい。
を試してみるとよい。
が、本当は、集団教育の場で、みなが大声を張りあげていうような場面が望ましい。
1人、2人だと、大声を出さない子どもでも、みなが大声を張りあげると、つられて自分も大声を
出すようになる。
出すようになる。
どこかの見知らぬおじさんが、「お菓子を買ってあげるから、いっしょに来ないか?」と声をか
けたとき、子どもが、最初に「いや!」とはっきり言う。
けたとき、子どもが、最初に「いや!」とはっきり言う。
犯罪の防止になるだけではなく、今のこうした社会では、とても大切なことだと思う。
【付記】
この指導法を参観していた母親が、そのあと、こう言った。
「私なんか、セールスがきても、はっきりと断れないため、よくトラブルに巻きこまれてしまいま
す」と。
す」と。
「私ははっきりと、いやと言うのですが、主人が、優柔不断で、困ります」といった母親もいた。
もしそうなら、日ごろから、夫婦の間で、こうした訓練をしておくとよい。
夫「奥さん、おもしろい薬があります」
妻「いりません」
夫「お買い得ですよ」
妻「興味ありません」
夫「奥さん、元気が出ますよ。あのK国製ですから」
妻「いりません。お帰りください」と。
私たち夫婦も、ときどき、この訓練法を自分たちに試している。
私も、若いころは優柔不断なところがあった。
誘われると断りきれず、ついつい……ということがよくあった。
しかし最近は、ない。
この訓練法のおかげである。
なお、教育の場で、この訓練法をしているのは、私が知る限り、私のBW教室だけである。
(ほかの幼児教室は、まねしないように!
……少し心が狭いかな?)
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司 返答
訓練法 自我 YES NO はっきり言う子供 はっきりとした子供 行動療法 対人訓練法
はやし浩司 主張訓練法 子供の心理 はっきりと拒否する)
訓練法 自我 YES NO はっきり言う子供 はっきりとした子供 行動療法 対人訓練法
はやし浩司 主張訓練法 子供の心理 はっきりと拒否する)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【小学1年生と2年生に、四捨五入(およその数)を教える】
●小学1年生と2年生に、四捨五入(およその数)を教えてみました。
もちろん「四捨五入」という言葉そのものは、使いませんでした。
あくまでも「およその数(Rounding Off)」の概念についての指導です。
いつか子どもたちが四捨五入を学校で学ぶようになったとき、サッと理解できるようにする。
それが今回のレッスンの目的です。
結果は、1年生には、やや無理かな……という印象をもちました。
2年生は、ほぼねらい通り、理解してくれました。
大切なのは、こうして新しいことを教えたとき、子どもたちが前向きに食いついてくることです
ね。
ね。
私はそういう子どもたちの姿勢を大切にしています。
わかりやすく言えば、子どもたちを算数好きにする。
子どもたちのもつ、そういった迫力を、このビデオの中から感じ取ってくだされば、うれしいで
す。
す。
【小学1年生クラス】
(1)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/fEsCZ1_Eves"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/codQuTc8dx0"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/zPzl2Af113E"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
【小学2年生クラス】(同じ教材を使いました)
(1)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/kyy_L4aPVSc"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Cmj649hoZLY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/sXmPsWsuCKs"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 四捨五入 およその数 実験教
室 BW子どもクラブ)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 四捨五入 およその数 実験教
室 BW子どもクラブ)
Hiroshi Hayashi++++++Dec. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●12月03日(土曜日)『幼児の自己主張』
++++++++++++++++++++
今朝は、6時に起きた。
左足の小指の爪の端が割れ、それが一晩中、痛かった。
ときどき足をふとんの外に出す。
が、そうすれば、今度は足が冷えてしまう。
つまり一晩中、それを繰り返した。
で、6時に起きた。
爪切りで、割れた爪を切った。
++++++++++++++++++++
【幼児期後期の子どもたち】(自立期の子どもたち)
●自立期(伸びやかな子どもたち)(Active Children, Age 5&6)
自立期の幼児(=幼児期後期)がどういうものかは、つぎの動画を見てもらえばわかる。
この時期、幼児は、つぎの児童期をめざし、はげしくも自己主張を繰り返す。
世の中には、おとなしく、従順で、シャイな子どもほど、「できのいい子」と考える親も多い。
またそういう子どもにするため、子どもを頭から抑えつける親もいる。
しかしこれはとんでもない誤解。
偏見。
誤解や偏見であることは、この動画を見てもらえばわかるはず。
子どもというのは、抑えつけるのは簡単。
伸ばすのはむずかしい。
なお2~3月期(小学校の入学前)になったら、少しずつ、抑えにかかる。
この動画を通して、子どもを伸ばすということがどういうことか、それがわかってもらえばうれし
い。
い。
テーマは、少し早いが、「1年のまとめ」。
(1)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/FW-cpQoOJOw"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(2)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/yWlLGkyVwkQ"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(3)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/qWTQJm5nAaQ"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(4)
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/VJKkRRGMZ3M"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【権威主義】
●12月4日(山岡家のラーメン)
今朝は7時半、起き。
日曜日。
ウォーキング・マシンの上で一汗かく。
書斎へ入る。
……昨夜、近くの『山岡家』というラーメン屋で、ギョーザを食べた。
ワイフはラーメンを食べた。
味は一級!
その山岡家には、テーブルの上に、生ニンニクが用意してある。
土曜日の夜は、それをギョーザやラーメンにたっぷりとかけて、食べる。
が、これがたまらなく、おいしい。
私たちの大好物。
ただし、人に会う前には、それができない。
そこで私たちは、ニンニクをかけて食べるのは、土曜日の夜とか、そういうときに決めている。
そのせいか、体調はすこぶる、よい。
頭の中も、スッキリしている。
ワイフが店を出るとき、こう言った。
「ラーメンにニンニクを入れると、味がさらにおいしくなるわね」と。
……ということで、今日は午後まで、人と会う約束はなし。(……会えない。)
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
【我ら極東アジア人の、民族的上下意識とそれを支える権威主義】
++++++++++++++++++++
12月04日、ネットであちこちの
ニュース・サイトをのぞく。
北朝鮮の記事が、目にとまる。
++++++++++++++++++++
●虚勢
虚勢にも、2種類ある。
外面(そとづら)と、内面(うちづら)。
もう少し正確には、外面虚栄と内面虚栄。
そのことを、今朝、海外の報道記事を読んでいて知った。
●北朝鮮
あの北朝鮮のP市では、目下、急ピッチで、街作りが進んでいるという。
「食糧も足りないのに……」と私たちは考えるが、あの国の独裁者には、そんな声は届かな
い。
い。
で、その街作りが、ものすごい。
たとえば通りに面した部分だけ、ビルを作りなおすとか、などなど。
10数階もあるようなアパートを建設したが、エレベーターはなし。
報道によれば、建設には、学生が動員されているとか。
そのため事故も多く、すでに200人近くの学生が亡くなっているそうだ。
●内面虚勢
こうした報道記事を読んでいると、ではいったい、何のために?、と、そこまで考えてしまう。
報道記事には、「虚勢」という言葉が並ぶ。
しかし外人観光客など、ほとんどいない。
となると、その虚勢は、だれに向けられたものなのか。
……ということで、「内面虚勢」という言葉を思いついた。
虚勢は虚勢でも、国内向けの虚勢。
だから「内面虚勢」
●自尊心
が、内面虚勢が悪いというのではない。
内面虚勢と自尊心は、よく似ている。
区別できない。
私にしても、自尊心があるからこそ、こうしてかろうじて生きていられる。
「私はすばらしい」と自分に言って聞かせる。
あるいは自分のよい面だけを信じ、それが「私」と、自分に言って聞かせる。
わかりやすく言えば、自分で自分に虚勢を張る。
が、これはあくまでも個人の話。
そういう虚勢を張ったところで、だれにも迷惑をかけない。
他人にはバカに見えるかもしれないが、そうであっても、何も構わない。
私は私。
人は人。
つまりそれが国家レベルにまで、巨大化したのが、北朝鮮ということになる。
●極東アジア人
一方、外面虚勢というのもある。
見栄、体裁、虚栄、世間体……。
極東アジア人というのは、民族的に、外見虚勢を重んずる。
それ自体が、生きる目的にもなっている。
今でこそ色あせてきたが、「出世」という言葉も、まだ死語になったわけではない。
半面、オーストラリア人などは、みな、外面虚勢とは無縁の世界で生きている。
すがすがしいほど、無縁の世界で生きている。
が、これは意識の問題だから、私がここでいくら説明しても、極東アジア人には、理解できない
だろう。
だろう。
同じように、オーストラリア人に、外面虚勢についていくら説明しても、理解できないだろう。
「どうして、そんなことを気にするのか?」と、逆に質問されてしまう。
●地位や肩書き
ひとつの例をあげる。
日本では、50歳をすぎると、みなリストラされたり、子会社に左遷されたりする。
中にはそれなりの役職に就き、退職後もそれなりの仕事をする人もいる。
いろいろな人がいるが、退職後も、退職前の地位や肩書きを引きずって生きている人は、多
い。
い。
またその亡霊から抜け出せないまま、生きている人は多い。
そのことは、60歳を過ぎると、よくわかる。
名刺をもらったりすると、さらによくわかる。
もっともらしい地位や肩書きを、ズラズラと並べている。
逆に言えば、中身がないから、そうする。
つまり外面虚勢。
●「自分の人生は何だったのか」
なぜ、極東アジア人は、外面虚勢を重んじるのか。
その理由の第一は、自分自身が、相手を、その外面虚勢で判断しているから。
つまり身分による上下意識が、きわめて強い。
さらにそれを支える権威主義。
極東アジア人は、この権威主義に弱い。
さらにもう一言、付け加えれば、今ここで外面虚勢を否定されてしまうと、「ではいったい、自
分の人生は何だったのか」ということになってしまう。
分の人生は何だったのか」ということになってしまう。
滅私奉公、一社懸命、企業戦士となってがんばってきた人ほど、そうだろう。
だから地位や肩書きにしがみつく。
それこそ退職して、10年とか20年とか過ぎても、しがみつく。
それについては、すでに何度も書いてきた。
いくつか原稿をさがしてみる。
++++++++++++++++++はやし浩司
2006年の12月にBLOGで発表した原稿より。
++++++++++++++++++はやし浩司
●親風、夫風、兄風
+++++++++++++++
私のBW教室では、兄弟(姉妹)が入会して
いるばあいには、できるだけ、同じ
クラスで教えるようにしている。
効果は絶大!
たがいにたがいを刺激しあうだけではなく、
1年単位でみると、たいへん仲がよくなる。
+++++++++++++++
「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」と、上下意識を無意識のうちにも感じながら呼びあうより、兄弟、
姉妹は、名前そのもので呼びあうほうがよい。そのほうが、上下意識がなくなり、いわゆる「友」
として、生涯にわたって、仲がよくなる。
姉妹は、名前そのもので呼びあうほうがよい。そのほうが、上下意識がなくなり、いわゆる「友」
として、生涯にわたって、仲がよくなる。
たとえば、「お兄ちゃん」ではなく、「シンちゃん」。「お姉ちゃん」ではなく、「ミサちゃん」と呼び
あうなど。
あうなど。
このことについては、すでに何度も書いてきたので、ここでは省略する。
ところで最近気がついたのだが、親意識の強い人は、ついでに夫意識が強く、さらに叔父意
識、叔母意識も強い。さらに、兄意識も強く、従兄弟(いとこ)に対しても、ほんの数才しか年が
ちがわないのに、年長意識も強い。
識、叔母意識も強い。さらに、兄意識も強く、従兄弟(いとこ)に対しても、ほんの数才しか年が
ちがわないのに、年長意識も強い。
だから親風を吹かす。夫風を吹かす。叔父、叔母風を吹かす。兄風を吹かす。年長風を吹か
す。はたから見れば、(つまりそういう意識のない人から見れば)、バカげているのだが、本人
は、そうでない。(上意識)だけで、いっぱしの人物のつもりでいる。
す。はたから見れば、(つまりそういう意識のない人から見れば)、バカげているのだが、本人
は、そうでない。(上意識)だけで、いっぱしの人物のつもりでいる。
こういうのを総称して、「権威主義」というが、いまだにその権威主義にこだわっている人は、
少なくない。言うまでもなく、権威主義にこだわればこだわるほど、まわりの人たちの心は離れ
る。それに気がつかないのは、本人だけということになる。
少なくない。言うまでもなく、権威主義にこだわればこだわるほど、まわりの人たちの心は離れ
る。それに気がつかないのは、本人だけということになる。
だから子どもでも、兄弟、姉妹は、名前、もしくは愛称で呼ばせるようにしたほうがよい。その
ほうが上下意識がなくなり、その分だけ、「友」として、相手を迎え入れるようになる。
ほうが上下意識がなくなり、その分だけ、「友」として、相手を迎え入れるようになる。
が、それだけではない。
親から見れば、兄弟、姉妹は、自分の子どもであり、同じように、兄弟、姉妹も、それなりに
仲がよいはずと考えがちである。しかしこれは誤解。
仲がよいはずと考えがちである。しかしこれは誤解。
実際には、兄弟、姉妹でも、他人以上に憎しみあい、疎遠になっているケースは、ゴマンとあ
る。むしろそういうケースのほうが多い。が、それを公(おおやけ)に口に出して言うことができ
ない。だから、自分で自分のクビをしめてしまう。「兄だから」「弟だから」と。そういうケースも、
少なくない。
る。むしろそういうケースのほうが多い。が、それを公(おおやけ)に口に出して言うことができ
ない。だから、自分で自分のクビをしめてしまう。「兄だから」「弟だから」と。そういうケースも、
少なくない。
たとえば私の兄についても、そうである。私より9歳も年上ということもある。子どものころ、い
っしょに遊んだという記憶さえない。そういう兄が、数年前、認知症なった。
っしょに遊んだという記憶さえない。そういう兄が、数年前、認知症なった。
一応、私は弟だから、兄のめんどうをみなければならない。それはわかる。しかし「兄だか
ら、お前は愛情を感じているはず」と、一方的に押しつけられると、言いようのない反感を覚え
る。兄といっても、弟の私から見れば、他人に近い。同年齢の従兄弟たちのほうが、ずっと親
近感がある。
ら、お前は愛情を感じているはず」と、一方的に押しつけられると、言いようのない反感を覚え
る。兄といっても、弟の私から見れば、他人に近い。同年齢の従兄弟たちのほうが、ずっと親
近感がある。
つまりこうした家族のクサリ(=自我群)に苦しんでいる兄弟、姉妹も、多いということ。
では、どうするか。
そのひとつの方法というわけではないが、私の教室(BW)では、ある学年(小学3、4年)にな
ると、兄弟、姉妹は、できるだけ同じクラスで教えるようにしている。その学年になると、それぞ
れの子どもの進度にあわせて、個別レッスンをするので、技術的には可能である。
ると、兄弟、姉妹は、できるだけ同じクラスで教えるようにしている。その学年になると、それぞ
れの子どもの進度にあわせて、個別レッスンをするので、技術的には可能である。
こうすることによって、兄弟、姉妹は、たがいにたがいを刺激しあう。が、それだけではない。
思い出を共有することによって、将来にわたって、仲がよくなる。
思い出を共有することによって、将来にわたって、仲がよくなる。
が、こういう指導に対して、疑問をもつ父母も少なくない。
「兄(姉)が、劣等感を覚えないか」と。たとえば年が離れていない兄弟のばあい、弟のほうが
兄より、勉強がよくできるというケースもないわけではない。
兄より、勉強がよくできるというケースもないわけではない。
しかしそれは、指導力でカバーできる問題と考えてよい。さらにその前提として、生まれなが
らにして、上下意識がなければ、気にすることはない。そのためにも、兄弟、姉妹には、上下意
識をもたせないほうがよい。その前に、親自身も、上下意識をもたないほうがよい。
らにして、上下意識がなければ、気にすることはない。そのためにも、兄弟、姉妹には、上下意
識をもたせないほうがよい。その前に、親自身も、上下意識をもたないほうがよい。
親風、ナンセンス。夫風、ナンセンス。兄風、ナンセンス。
最後に一言。
私たちは自分の子どもを、たとえば、「お兄ちゃん」と呼ぶことによって、無意識のうちにも、
子どもに上下意識を植えつけていることを忘れてはいけない。中には、さらに積極的に、「あな
たはお兄ちゃんでしょでしょ!」「お兄ちゃんらしくしなさい!」と、兄意識を強制する親だってい
る。
子どもに上下意識を植えつけていることを忘れてはいけない。中には、さらに積極的に、「あな
たはお兄ちゃんでしょでしょ!」「お兄ちゃんらしくしなさい!」と、兄意識を強制する親だってい
る。
まことにもって愚かな指導法ということになるが、このつづきは、またの機会に!
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司 兄弟
姉妹 上下意識 権威主義 兄の育て方 姉の育て方)
姉妹 上下意識 権威主義 兄の育て方 姉の育て方)
(付記)
日本人は、もともと家父長意識の強い民族である。またそういう土着的な意識を、文化風習
として背負っている。江戸時代という、とんでもない封建主義時代が、300年以上もつづいたこ
ともある。
として背負っている。江戸時代という、とんでもない封建主義時代が、300年以上もつづいたこ
ともある。
だからいまだに、この権威主義が、大手を振ってのさばっている。またそれを「国家の品格」
と位置づけている人さえいる。
と位置づけている人さえいる。
しかし権威主義が、いかにバカげているかは、ほんの少しでもオーストラリア人でもよいが、
そういう人たちとつきあってみると、わかる。夫婦でも、おもしろいほど、上下意識がない。食後
でも、夫と妻が台所に並んで、洗いものをしている。
そういう人たちとつきあってみると、わかる。夫婦でも、おもしろいほど、上下意識がない。食後
でも、夫と妻が台所に並んで、洗いものをしている。
もちろん兄弟、姉妹でも、愛称で呼びあっている。仲がよいというよりも、友として、相手を認
めあっている。(だから反対に、友でなければ、兄弟、姉妹でも、他人のように疎遠になるという
ケースも、ないわけではない。)
めあっている。(だから反対に、友でなければ、兄弟、姉妹でも、他人のように疎遠になるという
ケースも、ないわけではない。)
つまり(家族)という概念に、日本人ほど、強くはしばられていない。たがいにサバサバとして
いる。横で観察していると、そんな印象をもつ。
いる。横で観察していると、そんな印象をもつ。
要するに、「兄弟(姉妹)だから仲がよいはず」「たがいに愛情を感じているはず」と、子ども
に、それを押しつけてはいけない。これはこれからの子育ての第1歩ということになる。(以上、
2006年12月記)
に、それを押しつけてはいけない。これはこれからの子育ての第1歩ということになる。(以上、
2006年12月記)
++++++++++++++++++はやし浩司
さらに古い原稿だが、日本人の意識の変化を
知るには、よいと思う。
日付は、2001年になっている。
(中日新聞発表済み)
++++++++++++++++++はやし浩司
●上下意識の崩壊
日本人の上下意識は、近年、急速に崩れ始めている。とくに夫婦の間の上下意識にそれが
顕著に表れている。
顕著に表れている。
内閣府は、夫婦別姓問題(選択的夫婦別姓制度)について、次のような世論調査結果を発表
した(2001年)。
した(2001年)。
それによると、同制度導入のための法律改正に賛成するという回答は42・1%で、反対した
人(29・9%)を上回った。
人(29・9%)を上回った。
前回調査(96年)では反対派が多数だったが、賛成派が逆転。
さらに職場や各種証明書などで旧姓(通称)を使用する法改正について容認する人も含めれ
ば、肯定派は計65・1%(前回55・0%)にあがったというのだ。
ば、肯定派は計65・1%(前回55・0%)にあがったというのだ。
調査によると、旧姓使用を含め法律改正を容認する人は女性が68・1%と男性(61・8%)
より多く、世代別では、30代女性の86・6%が最高。別姓問題に直面する可能性が高い20
代、30代では、男女とも容認回答が八割前後の高率。
より多く、世代別では、30代女性の86・6%が最高。別姓問題に直面する可能性が高い20
代、30代では、男女とも容認回答が八割前後の高率。
「姓が違うと家族の一体感に影響が出るか」の質問では、過半数の52・0%が「影響がない」と
答え、「一体感が弱まる」(41・6%)との差は前回調査より広がった。
答え、「一体感が弱まる」(41・6%)との差は前回調査より広がった。
ただ、夫婦別姓が子供に与える影響については、「好ましくない影響がある」が66・0%で、
「影響はない」の26・8%を大きく上回った。
「影響はない」の26・8%を大きく上回った。
調査は2001年5月、全国の20歳以上の5000人を対象に実施され、回収率は69・4%だっ
た。
た。
なお夫婦別姓制度導入のための法改正に賛成する人に対し、実現したばあいに結婚前の姓
を名乗ることを希望するかどうか尋ねたところ、希望者は18・2%にとどまったという。
を名乗ることを希望するかどうか尋ねたところ、希望者は18・2%にとどまったという。
わかりやすく言えば、若い人ほど夫婦別姓に賛成だということだが、夫婦別姓が問題になる
こと自体、私たちの世代では考えられないことであった。
こと自体、私たちの世代では考えられないことであった。
「結婚した女性は、その家に入るもの」という考え方が、常識でもあった。
言いかえると、今、私たちが経験しつつある変化は、まさに革命的とも言えるものである。それ
こそ100年単位でつづいた日本の常識が、ここでひっくり返ろうとしている。
こそ100年単位でつづいた日本の常識が、ここでひっくり返ろうとしている。
そうした目で、この問題を考える必要がある。(2001年記、2011年改)
++++++++++++++++++はやし浩司
●水戸黄門
話せば長くなるが、外面虚勢の裏には、長くつづいた封建制度が深く関わっている。
そのひとつが、上下意識ということになる。
最後にあの「水戸黄門」をあげる。
世界的に見ても、あれほどバカげた番組はないと思うが、それが今でも、この日本では人気番
組のひとつになっている。
組のひとつになっている。
どうして三つ葉葵の紋章を見ただけで、みなはハハーと頭をさげるのか。
++++++++++++++++++はやし浩司
『水戸黄門論』……中日新聞発表済み。
++++++++++++++++++はやし浩司
●権威主義の象徴・水戸黄門
権威主義。その象徴が、あのドラマの『水戸黄門』。側近の者が、葵の紋章を見せ、「控えお
ろう」と一喝すると、皆が、「ははあ」と言って頭をさげる。
ろう」と一喝すると、皆が、「ははあ」と言って頭をさげる。
日本人はそういう場面を見ると、「痛快」と思うかもしれない。
が、欧米では通用しない。オーストラリアの友人はこう言った。
「もし水戸黄門が、悪玉だったらどうするのか」と。
フランス革命以来、あるいはそれ以前から、欧米では、歴史と言えば、権威や権力との闘いを
いう。
いう。
この権威主義。家庭に入ると、親子関係そのものを狂わす。
Mさん(男性)の家もそうだ。長男夫婦と同居して一五年にもなろうというのに、互いの間に、ほ
とんど会話がない。
とんど会話がない。
別居も何度か考えたが、世間体に縛られてそれもできなかった。Mさんは、こうこぼす。「今の
若い者は、先祖を粗末にする」と。
若い者は、先祖を粗末にする」と。
Mさんがいう「先祖」というのは、自分自身のことか。一方長男は長男で、「おやじといるだけ
で、不安になる」と言う。
で、不安になる」と言う。
一度、私も間に入って二人の仲を調整しようとしたことがあるが、結局は無駄だった。
長男のもっているわだかまりは、想像以上のものだった。
問題は、ではなぜ、そうなってしまったかということ。
そう、Mさんは世間体をたいへん気にする人だった。
特に冠婚葬祭については、まったくと言ってよいほど妥協しなかった。
しかも派手。長男の結婚式には、町の助役に仲人になってもらった。
長女の結婚式には、トラック二台分の嫁入り道具を用意した。
そしてことあるごとに、先祖の血筋を自慢した。
Mさんの先祖は、昔、その町内の大半を占めるほどの大地主であった。
ふつうの会話をしていても、「M家は……」と、「家」をつけた。
そしてその勢いを借りて、子どもたちに向かっては、自分の、親としての権威を押しつけた。少
しずつだが、しかしそれが積もり積もって、親子の間にミゾを作った。
しずつだが、しかしそれが積もり積もって、親子の間にミゾを作った。
もともと権威には根拠がない。
でないというのなら、なぜ水戸黄門が偉いのか、それを説明できる人はいるだろうか。
あるいはなぜ、皆が頭をさげるのか。またさげなければならないのか。
だいたいにおいて、「偉い」ということは、どういうことなのか。
権威というのは、ほとんどのばあい、相手を問答無用式に黙らせるための道具として使われ
る。
る。
もう少しわかりやすく言えば、人間の上下関係を位置づけるための道具。
命令と服従、保護と依存の関係と言ってもよい。
そういう関係から、良好な人間関係など生まれるはずがない。
権威を振りかざせばかざすほど、人の心は離れる。親子とて例外ではない。
権威、つまり「私は親だ」という親意識が強ければ強いほど、どうしても指示は親から子どもへ
と、一方的なものになる。
と、一方的なものになる。
そのため子どもは心を閉ざす。Mさん親子は、まさにその典型例と言える。
「親に向かって、何だ、その態度は!」と怒る、Mさん。
しかしそれをそのまま黙って無視する長男。
こういうケースでは、親が権威主義を捨てるのが一番よいが、それはできない。
権威主義的であること自体が、その人の生きざまになっている。
それを否定するということは、自分を否定することになる。
が、これだけは言える。もしあなたが将来、あなたの子どもと良好な親子関係を築きたいと思
っているなら、権威主義は百害あって一利なし。
っているなら、権威主義は百害あって一利なし。
『水戸黄門』をおもしろいと思っている人ほど、あぶない。(1999年ごろ記)
++++++++++++++++++はやし浩司
上述の原稿を、さらに書き改めのが、つぎの原稿。
++++++++++++++++++はやし浩司
●水戸黄門論
テレビドラマに「水戸黄門」というのがある。葵三つ葉の紋章を見せて、側近のものが、「控
え おろう!」と一喝するシーンは、あまりにも有名である。
え おろう!」と一喝するシーンは、あまりにも有名である。
今でも、視聴率が20~25%もあるというから、驚きである。
で、あの水戸黄門というのは、水戸藩二代藩主の徳川光圀(みつくに)と、家来の中山市正と
井上玄洞をモデルとした漫遊記と言われている。
井上玄洞をモデルとした漫遊記と言われている。
隠居した光圀は、水戸の郊外、西山村に移り住み、百姓光右衛門と名乗り、そのとき、先の二
人を連れて、関東を漫遊したという。
人を連れて、関東を漫遊したという。
それが芝居、映画、テレビドラマになり、「水戸黄門」が生まれた。(芝居の中では、二人の家
来は、佐々木助三郎(通称「助さん」)と、渥美格之進(通称「格さん」)になっている。)
来は、佐々木助三郎(通称「助さん」)と、渥美格之進(通称「格さん」)になっている。)
徳川光圀は実在した人物だが、ただ光圀自身は、関東地域からは一歩も出ていない。
それはさておき、水戸黄門は、全国各地を漫遊しながら、悪代官をこらしめたり、仇討ちの助
けをしたりして、大活躍をする。
けをしたりして、大活躍をする。
日本人にはたいへん痛快な物語だが、ではなぜ「痛快」と思うかというところに、大きな問題が
隠されている。
隠されている。
以前、オーストラリアの友人が私にこう聞いた。「ヒロシ、もし水戸黄門が悪いことをしたら、日
本人はどうするのか」と。
本人はどうするのか」と。
そこで私が「水戸黄門は悪いことはしないよ」と言うと、「それはおかしい」と。
考えてみれば、水戸黄門がたまたま善人だったからよいようなものの、もし悪人だったら、そ
の権威と権力を使って、したい放題のことができる。
の権威と権力を使って、したい放題のことができる。
だれか文句を言う人がいたら、それこそ「控えおろう!」と一喝すればすんでしまう。
民衆の私たちは、水戸黄門の善行のみをみて、それをたたえるが、権威や権力というのは、
ひとつ使われ方がまちがうと、とんでもないことになる。
ひとつ使われ方がまちがうと、とんでもないことになる。
だいたいにおいて水戸黄門は封建時代の柱である、身分制度という制度をフルに利用してい
る。
る。
身分制度を巨悪とするなら、代官の悪行など、かわいいものだ。
善行も何も、ない。
「頂点にたつ権力者は悪いことをしない」という錯覚は、恐らく日本人だけがもつ幻想ではない
のか。
のか。
長くつづいた封建制度の中で、日本人は骨のズイまで魂を抜かれてしまった。
もっと言えば、あの番組を痛快と思う人は、無意識のうちにも、封建時代を是認し、身分制度
を是認し、さらに権威主義を是認していることになるのでは……?
を是認し、さらに権威主義を是認していることになるのでは……?
あるいは権威や権力に、あこがれをいだいている……?
教育の世界には、まだ権威や権力がはびこっている。
こうした権威や権力は、その世界に住んでいる人には居心地のよいものらしいが、その外で、
いかに多くの民衆が犠牲になっていることか。
いかに多くの民衆が犠牲になっていることか。
むずかしいことはさておき、あのドラマを見るとき、一度でよいから、水戸黄門の目線ではなく、
その前で頭を地面にこすりつける庶民の目線で、あのドラマを見てほしい。
その前で頭を地面にこすりつける庶民の目線で、あのドラマを見てほしい。
あなたもあのドラマを見る目が変わるはずである。
++++++++++++++++++はやし浩司
さらにダメ押し。
日本の常識は、けっして世界の常識ではない。
++++++++++++++++++はやし浩司
●日本の常識、世界の非常識
● 「水戸黄門」論……日本型権威主義の象徴が、あの「水戸黄門」。あの時代、何がまちが
っているかといっても、身分制度(封建制度)ほどまちがっているものはない。その身分
制度という(巨悪)にどっぷりとつかりながら、正義を説くほうがおかしい。日本人は、
その「おかしさ」がわからないほどまで、この権威主義的なものの考え方を好む。葵の紋
章を見せつけて、人をひれ伏せさせる前に、その矛盾に、水戸黄門は気づくべきではない
のか。仮に水戸黄門が悪いことをしようとしたら、どんなことでもできる。それこそ19
歳の舞妓を、「仕事のこやし」(人間国宝と言われる人物の言葉。不倫が発覚したとき、そ
う言って居直った)と称して、手玉にして遊ぶこともできる。
● 「釣りバカ日誌」論……男どうしで休日を過ごす。それがあのドラマの基本になってい
る。その背景にあるのが、「男は仕事、女は家庭」。その延長線上で、「遊ぶときも、女は関
係なし」と。しかしこれこそまさに、世界の非常識。オーストラリアでも、夫たちが仕事
の同僚と飲み食い(パーティ)をするときは、妻の同伴が原則である。いわんや休日を、
夫たちだけで過ごすということは、ありえない。そんなことをすれば、即、離婚事由。「仕
事第一主義社会」が生んだ、ゆがんだ男性観が、その基本にあるとみる。
● 「森S一のおふくろさん」論……夜空を見あげて、大のおとなが、「ママー、ママー」と
泣く民族は、世界広しといえども、そうはいない。あの歌の中に出てくる母親は、たしか
にすばらしい人だ。しかしすばらしすぎる。「人の傘になれ」とその母親は教えたというが、
こうした美化論にはじゅうぶん注意したほうがよい。マザコン型の人ほど、親を徹底的に
美化することで、自分のマザコン性を正当化する傾向が強い。
●「かあさんの歌」論……窪田S氏作詞の原詩のほうでは、歌の中央部(3行目と4行目)
は、かっこ(「」)つきになっている。「♪木枯らし吹いちゃ冷たかろうて。せっせと編んだ
だよ」「♪おとうは土間で藁打ち仕事。お前もがんばれよ」「♪根雪もとけりゃもうすぐ春だ
で。畑が待ってるよ」と。しかしこれほど、恩着せがましく、お涙ちょうだいの歌はない。
親が子どもに手紙を書くとしたら、「♪村の祭に行ったら、手袋を売っていたよ。あんたに
似合うと思ったから、買っておいたよ」「♪おとうは居間で俳句づくり。新聞にもときどき
載るよ」「♪春になったら、村のみんなと温泉に行ってくるよ」だ。
● 「内助の功」論……封建時代の出世主義社会では、「内助の功」という言葉が好んで用い
られた。しかしこの言葉ほど、女性を蔑視した言葉もない。どう蔑視しているかは、もう
論ずるまでもない。しかし問題は、女性自身がそれを受け入れているケースが多いという
こと。約23%の女性が、「それでいい」と答えている※。決して男性だけの問題ではない
ようだ。
※……全国家庭動向調査(厚生省98)によれば、「夫も家事や育児を平等に負担すべきだ」
という考えに反対した人が、23・3%もいることがわかった。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 日本の常識 世界の非常識 はやし浩司 常識論 アインシュタイン
の常識)
++++++++++++++++++はやし浩司
●外面(そとづら)虚勢からの解放
さあ、あなたも勇気を出して、外面虚勢から、自らを解放してみよう。
そこはまさに、すがすがしい世界。
あなたがあなた自身でいられる世界。
今まで外面虚勢(上下意識、権威主義)で生きてきたなら、なおさら。
60歳を過ぎていても、70歳を過ぎていても、遅すぎるということはない。
方法は簡単。
一度、身ぐるみはいで、裸になればよい。
それともあなたは、最後の最後まで、過去の地位や肩書きにしがみついて生きていくというの
か。
か。
……それにしても我ら極東アジア人というのは、おもしろい。
一方で水戸黄門を美化しながら、他方で北朝鮮を非難する。
ともにその底流で流れている意識は、同じ。
極端な権威主義。
もしこんな矛盾した論理がまかり通りなら、逆に考えてみればよい。
「もし水戸黄門がまちがった指示を出したら、この日本はどうなるのか」と。
あるいは「いくら独裁者でも、よいことをすれば、許されるのか」でもよい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 BW
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 外面虚勢 見栄 体裁 世間体
虚栄心)
はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 外面虚勢 見栄 体裁 世間体
虚栄心)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●EUの金融危機
実に奇妙で、不可解なことが起きている。
金(マネー)を借りたほうは、どこかのんびりムード。
金(マネー)を貸したほうが、あわてまくっている。
わかりやすく説明しよう。
あなたの町内に、深刻な借金をかかえている家族が、3軒ある。
ギリ氏、イタ氏、スペ氏。
が、この3氏、いたってのんき。
いつもどおり、ワインを飲み、夕暮れ時になれば、裏通りでバックギャモンを並べて遊んでい
る。
る。
「借金はどうするのオ?」と聞くと、3氏とも、平気な顔をして、こう言った。
「返せなくなったら、自己破産するよオ」と。
そこで「自己破産したあとは、どうするのオ?」と聞くと、さらにこう言った。
「食い物には困らないし、あとは生活保護でも受けるわさア」と。
困ったのは、ドイ氏とフラ氏。
街の高利貸し。
自己破産されたら、たまらない。
元も子もなくなってしまう。
そこでドイ氏とフラ氏が話し合った。
「どうしよう」「どうしましょう」と。
フラ氏は、「とりあえず銀行から金を借りてきて、あいつらを助けるしかない」と主張。
ドイ氏は、「そんなことをすれば、ますますあいつら、図に乗るだけ。ためにならない」と反対。
が、このままでは、ドイ氏もフラ氏も、共倒れ。
●本当に困っているのは、だれ?
が、ドイ氏もフラ氏も、互いに疑心暗鬼になっている。
本来なら金(マネー)を融通しあい、協力しあわなければならない。
が、手の内を見せない。
いくら貸しつけ、いくら金(マネー)をもっているか、それも明かさない。
つまり資金の流れが止まってしまった。
「さあ、どうするか?」ということで、その上の銀行に泣きついた。
が、銀行とて、困った。
ギリ氏、イタ氏、スペ氏が自己破産するのはかまわない。
が、ドイ氏とフラ氏は、お得意様。
ドイ氏とフラ氏が倒れたら、銀行の屋台骨すら折れかねない。
そこで銀行は、ドイ氏、フラ氏にこう約束した。
「いざとなったら、金(マネー)、いくらでも貸すよ」(IMF)と。
これにドイ氏とフラ氏が喜んだ。
「ワーイ、これでひと安心!」と。
●金融危機
つまり困っているのは、高利貸しのほう。
「金融危機」といっても、ギリシャやイタリア、それにスペインではない。
ドイツやフランスの銀行が、困っている。
……困り切っている。
この視点を踏み外すと、今回の一連の金融危機がどういうものか、わけがわからなくなってし
まう。
まう。
本来なら、助けるべきは、ギリシャやイタリア、それにスペインということになる。
が、先にも書いたように、これらの国は、何も困っていない。
ユーロ圏に入ったことで、かえって豊かな生活ができるようになった。
受けた恩恵は大きい。
冒頭で私が、「実に奇妙で、不可解なことが起きている」と書いたのは、そういう意味。
●資本主義
「銀行だって、企業なのだから、つぶれることもあるし、つぶれても仕方ない」と。
ふつうの人なら、そう考える。
が、そうはいかないところに、特別の事情がある。
「資本主義」という事情である。
平たく言えば、金(マネー)の力。
たとえばアメリカ・ドルなら、世界中で通用する。
世界のどこへもっていっても、そのまま使える。
だからアメリカ政府は、いくらでもドルを印刷することができる。
いくら貿易赤字がつづいても、構わない。
北朝鮮ですら、闇市では、ドルを使っている。
つまり金(マネー)も、需要と供給のバランスの上に成り立っている。
が、たとえば韓国ウォンは、そうではない。
使うにしても、一度アメリカ・ドルに交換してもらわねばならない。
へたに増刷すれば、国内でインフレを引き起こす。
日本の円にしても、そうだ。
今でこそ、国際通貨として通用する。
が、昔は、そうではなかった。
学生時代、オーストラリア国内で日本円を使おうとしたことがある。
1970年当時のことだったが、日本の1万円を銀行で両替しようとしたら、チェック(検査)する
だけで、10分以上も待たされた。
だけで、10分以上も待たされた。
もっと時間がかかったかもしれない。
よく覚えていない。
当時の日本の円は、そんなものだった。
資本主義の世界には、強い通貨と弱い通貨がある。
当然、自国の通貨は、強ければ強いほど、よい。
得!
みなが、ほしがる。
みなが、ためこんでくれる。
だからEUは連合し、共通通貨であるユーロを創設した。
わかりやすく言えば、絵画と同じ。
ピカソの絵は、ちょっとした走り描きでも、何十万円。
ラマ(インド)の絵は、絵描きが1年かかって描いた絵でも、1万円。
●EUの将来
EUは、崩壊しない。
ギリシャにしても、イタリアにしても、スペインにしても、EUにくっついていたほうが、得。
いくら貧乏になっても、ユーロなら世界中で通用する。
自国通貨にしたとたん、紙くずになってしまう。
一方、ドイツやフランスにしても、そうだ。
マルク(ドイツ)やフラン(フランス)だけでは、力不足。
世界の基軸通貨には、ならない。……なりえない。
仲間は多ければ多いほど、よい。
EUが崩壊したら、EU全体で、17~20%の工業生産力を失うという説もある(Bloomberg)。
となると、ここは一致団結するしかない。
●日本の国益
が、日本の国益を考えるなら、EUは、バラバラになったほうがよい。
EUが弱体化すれば、相対的に、日本の地位は浮上する。
日本の円は、アメリカ・ドル、EUのユーロ、中国の元の圧は力を受け、今や風前の灯(ともし
び)。
び)。
ユーロの台頭とともに、ちょうどそれに反比例する形で、日本の円は弱体化した。
だから私がもし日本の宰相なら、表向きはともかくも、裏ではユーロの解体をもくろむ。
……というか、アメリカはそれをねらっている。
ユーロの台頭は、アメリカにとっても、おもしろくない。
ユーロが力をつければつけるほど、相対的にドルの地位は下がる。
ついでに言えば、日本の円も、中国の元の台頭もおもしろくない。
そこでアメリカの逆襲が始まった!
●結局は、アメリカのひとり勝ち
最終的には、結局はアメリカのひとり勝ち。
10年後、20年後のことはわからない。
しかし今回のEUの金融危機の結果は、そうなる。
(これは、はやし浩司の大予言。)
アメリカは、IMFを利用し、EUの大銀行を、つぎつぎと自分の傘下に収める。
ついでにめぼしい企業も、自分の傘下に収める。
「金(マネー)のなる木を、自分の庭に植えかえる」(某経済学者)ことによって、EUを支配す
る。
る。
が、これは即、日本の未来像でもある。
アメリカの戦略は、火を見るより明らか。
EUのつぎは、この日本。
1.急激な円安に誘導する。(=円売りを開始する。)
2.日本国債を暴落させる。
3.日本をIMFの指導下に置く。
4.日本の銀行、企業をつぎつぎと買収する。
実はこの方法の有効性は、1997年の、韓国のあの金融危機で、実証済み。
以後、韓国の名だたる銀行はすべて、アメリカ資本のもとに組み込まれた。
ヒュンダイにせよ、サムスンにせよ、形は韓国の企業だが、中身はアメリカの企業。
このままでは、日本も、やがてそうなる。
(すでにそうなりつつあるが……。)
(これも、はやし浩司の大予言。)
●警戒主義者
私は少し前まで、親米主義者だった。
しかしこのところ、少し風向きが変わってきた。
親米主義者から警戒主義者。
反米主義者まではいかないが、この先、アメリカの動きには、じゅうぶん警戒したらよい。
またすべきかと思う。
現在の野田政権のように、何でもハイハイと言うことを聞いていたら、この日本はたいへんな
ことになる。
ことになる。
そんな危惧感をもっている。
今回のIMFの動きにしてもそうだ。
まずドイツとフランスに自腹を切らせる。
つぎに南欧諸国(ギリシャ、イタリア、スペインほか)に対してはドイツと歩調を合わせ、内政に
干渉していく。
干渉していく。
IMFにジャパン・マネーを使わせるのは、そのあと。
お人よしは禁物。
この際、大国意識を捨て、日本もなりふり構わず、自国防衛に専念すべき。
日本という国の国益を第一に考え、行動する。
現に中国は、そうしている。
「自国の外貨をEUの救済のためには使わない」、
「アメリカ国内のインフラに投資する」※(12月2日)と。
「どうして中国人より10倍も所得があるEUを、中国が救済しなければならないのか」とも。
さらに中国がアメリカに投資すると言い出したのは、当然のことながら、アメリカを自分の支配
下に置くためである。
下に置くためである。
……などなど、と私は考える。
……少し過激な意見で、ごめん!
……それにしても、ドイツのあのメルケル首相という人は、ものすごい女性だね。
日本の野田首相など、メルケル首相とくらべたら、まるでボンボン。
「これだけのことをしてやったから、相手は感謝してくれるはず」という『ハズ論』だけで、国際政
治を考えている。
治を考えている。
が、国際社会は、そんなに甘くない。
甘くないことは、先の3・11大震災を見ればわかる。
どこの国が、(民間支援ではなく)、国として日本を支援してくれたか?
みな、日本から一方的に金(マネー)を受け取るだけ。
韓国などは、日韓スワップ協定を結んだことをよいことに、手持ちの外貨で、せっこらせっこ
らと金(ゴールド)を買いつづけている(2011年12月3日現在)。
らと金(ゴールド)を買いつづけている(2011年12月3日現在)。
以上、はやし浩司という、素人の国際経済論。
あまり本気にしなように!
(はやし浩司 2011-12-03朝記)
(注※)
『中国の陳徳銘商務相は2日、中国が外貨準備の一部を米国のインフラ投資に振り向ける可
能性があることを明らかにした。
能性があることを明らかにした。
同商務相は米国のロック駐中国大使、および米財界人との会合で、「中国は米国債を過度に
保有することは望んでいない。その資金を投資に変えることを望んでいる」と述べた。
保有することは望んでいない。その資金を投資に変えることを望んでいる」と述べた。
そのうえで「電力供給網、鉄道、交通網など、米国のインフラには再建が必要な分野もある」と
し「こうした種類の投資は、米国の失業問題解決の一助となる可能性もある」と述べた』(ロイタ
ー・2011年12月2日)
し「こうした種類の投資は、米国の失業問題解決の一助となる可能性もある」と述べた』(ロイタ
ー・2011年12月2日)
『中国の傅瑩外務次官は2日、欧州諸国を「救済」するために中国は3兆2000億ドル(約249兆
円)の外貨準備を使うことはできないと言明した上で、金融危機をめぐる欧州支援で中国は
「自らの役割を果たしてきた」との認識を示した』(Bloomberg・12月2日)と。
円)の外貨準備を使うことはできないと言明した上で、金融危機をめぐる欧州支援で中国は
「自らの役割を果たしてきた」との認識を示した』(Bloomberg・12月2日)と。
(補記)
どうして日本の首相以下、政府は、こうした主張をしないのか?
もっと自分の意見を、堂々と披露すればよい。
よく言えば、「おとなしい」。
悪く言えば、「八方美人」。
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
●映画『タンタンの冒険』(はやし浩司 2011-12-03夜)
++++++++++++++++++++
今夜、『タンタンの冒険』(日本語吹き替え版)を観てきた。
3D映画。
子ども向け映画。
が、またまた映像技術の進歩に驚く。
『三銃士とダビンチの飛行船』は、すごかった。
今回の『タンタンの冒険』も、これまたすごかった。
いったい、映像技術は、どこまで進むのか。
CG映画だったが、皮膚の質感まで、
リアルすぎるほどリアルに、表現されていた。
(あるいは皮膚、そのもの?)
『スター・ウォーズ』(エピソード・1)が、
近く、封切られる。
あの『スター・ウォーズ』(日本公開・1978年)
のリメイク版らしい。
楽しみ。
プラス、おととい、『第九』演奏会のチケットを申し込んできた。
今年は、S席で聴く。
東京フィル+浜松フロイデ合唱団。
これまた楽しみ。
学生時代は、合唱団員として、毎年歌っていた。
指揮者はいつも、朝比奈隆だった。
言い忘れたが、『タンタンの冒険』は、星4つの★★★★。
『三銃士』を観ていなかったら、星は5つ。
映画館を出たとき、ワイフと「すごい映画だったね」と、
たがいに言いあった。
ボケ防止のためというには、もったいないような映画だった。
なお土曜日の夕方だったが、観客は私たちを含めて、5人だけ。
「営業として成り立つのだろうか」と、心のどこかで、
ふとそんな心配もした。
+++++++++++++++++++++
●宇宙時代
映画『スター・ウォーズ』は、「遠い昔、昔……」という設定になっている。
人間の未来ではなく、過去。
しかし同時に、それは人間の未来でもある。
やがて人間は、この宇宙を自由に行き交うようになる。
それはそれですばらしいこと。
が、利害が対立すれば、当然、紛争も起きるようになる。
戦争も起きるようになる。
科学技術の進歩と、兵器の進歩は、比例する。
多くは、兵器の進歩が科学技術の進歩を先導する。
人間が宇宙を自由に行き交うようになるころには、兵器もより強力になる。
価値観の基準をどこに置くかにもよるが、「未来イコール、善なる世界」ではない。
それを「宇宙時代」と呼ぶなら、宇宙時代はかならずしも、人間にとって好ましい世界とはいえ
ない。
ない。
それこそ爆弾一発で、地球が粉々になる。
そういうことも起こりえる。
まさにそこは、スター・ウォーズ(星間戦争)の世界。
●スター・ウォーズ
ところで私は、かつてスター・ウォーズについて書いたことがあるのだろうか。
記憶というのは、実にいいかげんなもの。
書いたことがあるような気もするし、ないような気もする。
「はやし浩司 スター・ウォーズ」で検索をかけてみる。
……原稿はいろいろ出てきたが、映画『スター・ウォーズ』について、直接書いたものは見つ
からなかった。
からなかった。
やはり映画『スター・ウォーズ』については、何も書いていない。
ただよく覚えているのは、当時、つまり1978年ごろは、よく生徒を連れて映画を観に行ったこ
と。
と。
そのひとつに、『スター・ウォーズ』があった。
が、よく覚えているのは、そのことではない。
その生徒の中に、河合さんという女の子がいたこと。
弟も一緒に来ていた。
その2人のことをよく覚えているのには、理由がある。
その直後に、母親が亡くなったからである。
私とワイフは、その母親の葬儀に出た。
それでその2人のことをよく覚えている。
ここで「河合さん」と書いたが、実名である。
「スター・ウォーズ」という名前を耳にするたびに、どういうわけか、その河合さんを思い出す。
あのころ小学4、5年生だったから、今ごろは、45歳前後になっているはず。
Hiroshi Hayashi+++++++Dec.2011++++++はやし浩司・林浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 9日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page006.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●11月30日朝記
++++++++++++++++++
今朝は、8時半起き。
昨夜は久しぶりに、睡眠導入剤というのをのんだ。
1錠ものむと、頭がおかしくなるので、いつも4分の1とか、
8分の1とかにして、のんでいる。
それでも朝まで、ぐっすりと眠れる。
「頭がおかしくなる」というのは、起きがけに、夢とも現実とも
区別のつかない夢を見ることをいう。
今日の講演は、午後7時から。
それで睡眠導入剤をのんだ。
++++++++++++++++++
●講演レジュメ(概要)
おととい、今夜の講演のレジュメ(概要)ができた。
「やっと……」という感じ。
……といっても、講演の「柱」のみ。
あとは、その場の雰囲気で決める。
私にとって講演というのは、そういうもの。
中にしっかりとした原稿を用意する人もいる。
私も何度か、それを試したことがある。
しかしそれでは聴衆の心をつかむことができない。
ザワついてきたなと感じたら、さっと話題を切りかえる。
そんな芸当も、講演では必要になる。
それに今日は、夜の講演ということで、父親も多いはず。
そういうときは、父親用の話も用意する。
年配の人が多いときは、年配の方用の話も用意する。
それぞれの分量は、そのとき決める。
が、この浜松市では、今年最後の講演会。
力んではいけない。
気合いを入れすぎてもいけない。
普段着で普段話をするつもりで、講演をする。
それが肝心だが、このサワサワとした緊張感は、どうしたものか。
「最後の講演会」という部分で、かなり緊張しているよう。
自分でもそれがよくわかる。
午後からは、運動を2単位こなし、夜に備える。
●酷評
YOUTUBEのほうに、ときどき、辛らつな酷評が書き込まれる。
昨日も、同じ女性から、3通も書き込まれた。
pxxxx04という女性からのものだった。
匿名だから、何とでも書ける。
が、待ったア!
匿名といっても、その気になれば、その女性を特定することは簡単。
まずその「pxxxx04」で検索をかける。
同じハンドルネームをあちこちで使っていることが多い。
検索をかけると、やはり同じハンドルネームで、4~5本のBLOGを発行しているのが
わかった。
そのうちのひとつには、プロフィール欄のところに、「45歳」「女性」とあった。
BLOGのタイトルは、『~~ママの~~日記』。
いくつか記事を読むと、その中に地名が書いてある。
それでおおよその住所がわかる。
「先日、近くの~~庭園へ行ってきました」とか。
さらに記事の内容から、ある特殊な花の栽培に興味をもっているのがわかった。
あとは、その地名と、その花の名前で検索をかければよい。
案の定、その花の専門BLOGに、その女性とのやり取りが書き込まれていた。
こうして私はその女性が、「X県Y町に住んでいる、MR」と、実名(名字)まで知るこ
とができた。
時間にすれば、5分もかからなかった。
が、それでも相手がわからないときは、特殊なフリーソフトを使う。
それを使うと、IP番号から、その人の住んでいる住所を、町名程度まで特定できる。
この方法はきわめて簡単で、ドラク→コピー→張りつけ→Enterキーで、すんでしま
う。
その方法でも、「X県Y町」という地名が出てきた。
(フリーソフトは雑誌などに紹介されている。)
だから返事には、こう書いた。
「幼児教育歴42年になる者です。
きびしいご意見ありがとうございました。
はやし浩司」と。
「教育歴42年」とわざわざ書いたのは、書き込みに「どこのド・シロートか知らない
が、偉そうなこと、ヌカスナ」とあったから。
……ということで、不愉快な書き込みに悩んでいる人も多いかと思う。
そういうときは、ここに書いたことを参考に、相手を調べてみたらよい。
どこに住んでいる人間かがわかるだけでも、気が楽になる。
(=不気味さが、消える。)
また匿名で書き込みをすれば、正体はバレないはずと考えている人もいるかもしれない。
が、今では、かなりのところまで特定できる。
ものを書くなら堂々と、実名を公表して書いたらよい。
(私は、そうしているぞ!)
●復習
講演の話に戻る。
今夜の講演では、(1)善悪論、(2)共鳴性、それに(3)もうひとつの話をすること
になっている。
が、(3)の部分で、つぎの2つのうちのどちらにするかで、迷っている。
(1)自我の同一性にするか、(2)心の抵抗力にするか。
どちらも似たような話だが、切り口がまったく逆。
どちらにしようか。
過去に書いた原稿をさがしてみる。
++++++++++++++++++はやし浩司
2007年に書いた原稿が見つかった。
++++++++++++++++++はやし浩司
【子どもを非行から守る法】
●時事・雑感(Yahoo Newsより)
●性描写漫画の規制条例が成立(東京都)(注※1)
石原都知事が言っているように、こんなことは、当たり前。
石原都知事は、こう言った。「当たり前。日本人の良識だ。
子どもにあんなものを見せられるのか」と。
ただし今となっては、焼け石に水。
手遅れ。
子どもたちの世界は、さらにその先に進んでいる。
漫画やアニメではなく、そのものズバリのDVDを見ている。
また近くに高校があるが、日暮れ時になると、目のやり場に困る。
高校生たちが、木陰の隅のあちこちで抱き合っている。
少し前までは、まだ隠れながらしていた。
が、今は、堂々というか、車のライトに照らされても、平気。
で、その話を、ある中学校教師(中高一貫校)に話すと、こう言った。
「ここ数年、さらに低年齢化してますよ」と。
驚いていると、「放課後なんか、使われていない部屋や道具置き場は、ラブホテル
みたいです」とも。
ほとんどの男子高校生は、コンドームを持ち歩いている。
携帯電話と同じ。
必携品。
「何も今さら……」というのが、私の実感。
こうした規制は、20年近く前、「PT」という女子向き雑誌が、
国会で問題になったとき、しておくべきだった。
が、これに対して、いくつかの団体が、猛反発。
「表現の自由、言論の自由の侵害」「捜索活動を萎縮させる」と。
しかしこういうのを、表現の自由とは言わない。
言論の自由を盾に取って守らなければならない、自由でもない。
むしろ逆。
表現の自由とか、言論の自由とか、そういう言葉を使って、自分たちの
醜い商業主義をカモフラージュしているだけ。
日本には、モラル、哲学、宗教がない。
ないから、法律で規制するしかない。
たとえば援助交際にしても、話題にのぼらなくなったのは、それがなくなったからでは
ない。
あまりにも日常的になり過ぎたからにほかならない。
それがわからなければ、その時間帯(夕暮れ時)に、コンビニをのぞいてみること。
コンビニが待ち合わせ場所になっている。
携帯電話を片手に、女子中学生や高校生が、あやしげな車につぎつぎと乗り込んでいく。
世界でも、ここまで退廃した国は、そうはない。
+++++++++++++以下、Yahoo Newsより++++++++++++
(注※1)【性描写漫画の規制条例が成立】=付帯決議で「慎重な運用を」
過激な性描写のある漫画やアニメの販売規制を目的に、東京都が12月議会に提出してい
た青少年健全育成条例改正案が、15日の都議会本会議で民主、自民、公明各党の賛成多数
により可決、成立した。ただ、「創作活動を萎縮させる」との指摘もあるため、条例の慎重
な運用を求める付帯決議も行った。条例は来年7月1日までに施行される。共産党と生活
者ネットワーク・みらいは反対した。
+++++++++++++以上、Yahoo Newsより++++++++++++
●では、どうすれなよいか
こうした風潮を改めるには、つまりあなたの子どもをこうした風潮から守るためには、
方法は、ただひとつ。
子どもに心の抵抗力をつける。
方法は簡単。
子どもに夢と希望をもたせ、その先に目標をもたせる。
わかりやすく言えば、子どもが好きなことをできる環境を用意する。
それについては、何度も書いてきたので、その原稿を、このあとに添付する。
が、残念なことに、現在の教育環境は、子どものもつ多様性に答えるしくみになって
いない。
「学校以外に道はなく、学校を離れて、夢や希望を育てる方法もない」。
どうして欧米がみなしているように、教育を自由化しないのか。
多様な教育方法を認めないのか。
たとえばドイツやフランスでは、子どもたちはみな、クラブに通っている。
いろいろなクラブがある。
英数国社理のような基本科目は、学校で教えればよい。
しかしそれ以外の科目は、民間に任せればよい。
私が言う「自由化」というのは、それをいう。
何も学校を解体せよと言っているのではない。
+++++++++++++++
心の抵抗力について書いた
原稿をさがしてみました。
2006年に、当時の講演用に
書いた原稿です。
+++++++++++++++
【心を支える、3つの物語】
●私が「私」であるためには、3つの柱が必要です。
(1)(したいこと)を、現実に(している)という実感、つまりは自我の同一性
(2)「いつも、私は、私でいられる」という連続性、一貫性
(3)他者との関係で、いつも良好な人間関係をもつことができるという社会性。
+++++++++++++++++++
「したいことをする」という姿勢の中から、夢や希望、それに目標が生まれます。自
分の描いた自己概念と、現実の自分が一致している。それが「私」でいるための第一条件
ですね。
つぎに、どんなばあいも、私は、自分でいられる。動じない。それが「私」というこ
とになります。
また「私」は、いつも、社会というカガミの中で、映し出されます。そもそも社会性
をもたない「私」は、私ではないということです。
今回は、これら3つの柱を中心に、時間が許すかぎり、私の個人的な過去もふまえて、
子どもの心を伸ばす、3つの物語を、みなさんに、お伝えしたいです。どうか、よろしく
お願いします。
+++++++++++++++++
【意外とシンプルな、心をはぐくむメカニズム】
●(自分のしたいことをする)……それが子ども自身を伸ばす原動力となります。
●(したいこと)をしている子どもは、生き生きとしています。夢や希望もそこから生ま
れ、
その先には、目標が生まれます。
●子どもを守るのは、子ども自身の中の、(心の抵抗力)です。目的がしっかりしている子
どもは、その抵抗力も強くなります。
***************************
●同一性の危機(1)
万引き、自転車盗、薬物濫用、暴走、家庭内暴力、校内暴力、性非行、無断外泊、いじめ
を、非行という(会津若松警察書)。子どもは、(自分のしたいこと)と、(現実にしている
こと)の間に遊離感を覚えたとき、無意識のうちにも、その距離を、縮めようとする。子
どもの耐性にもよるが、それが一定の限界(個人差は当然ある)を超えたとき、子どもの
自我の同一性は、危機に立たされる。
●夢・希望・目的(2)
夢・希望・目的は、子どもを伸ばす、三種の神器。これら夢・希望・目的は、(自分のした
いこと)と、(現実にしていること)が一致しているとき、あるいは、そこに一体感がある
とき、そこから生まれる。「ぼくはサッカー選手になる」「私はケーキ屋さんになる」と。
そしてサッカーの練習をしたり、ケーキを自分で焼いてみたりする。「プロの選手になる」
とか、「パン屋さんになる」とかいう目的は、そこから生まれる。
●子どもの忍耐力(3)
同一性が危機に立たされると、子どもは、それを修復しようとする。(自分のしたいこと)
を、別のものに置きかえたり、(現実にしていること)を、修正しようとしたりする。ある
いは「したくないが、がんばってやってみよう」と考えたりする。ここで登場するのが、
忍耐力ということになる。子どもにとって、忍耐力とは、(いやなことをする力)をいう。
この忍耐力は、幼児期までに、ほぼ完成される。
●同一性の崩壊(4)
同一性を支えきれなくなると、そこで同一性の崩壊が始まる。子ども自身、自分が何をし
たいか、わからなくなってしまう。また何をしてよいのか、わからなくなってしまう。「私
は何だ」「私はだれだ」と。「私はどこへ行けばよいのか」「何をすればよいのか」と。それ
は「混乱」というような、なまやさしいものではない。まさに「自己の崩壊」とも言うべ
きもの。当然、子どもは、目的を見失う。
●顔のない自分(5)
同一性が崩壊すると、いわゆる(顔のない自分)になる。で、このとき、子どもは、大き
く分けて、二つの道へと進む。(1)自分の顔をつくるため、攻撃的かつ暴力的になる(攻
撃型)。(2)顔のない自分のまま、引きこもったり、カラに閉じこもったりする(逃避型)。
ほかに、同情型、依存型、服従型をとる子どももいる。顔のない自分は、最悪のケースで
は、そのまま自己否定(=自殺)へとつながってしまう。
●校内暴力(6)
暴力的な子どもに向かって、「そんなことをすれば、君がみなに嫌われるだけだよ」と諭(さ
と)しても、意味はない。その子どもは、みなに嫌われ、怖れられることで、(自分の顔)
をつくろうとする。(顔のない自分)よりは、(顔のある自分)を選ぶ、。だからみなが、恐
れれば、怖れるほど、その子どもにとっては、居心地のよい世界となる。攻撃型の子ども
の心理的のメカニズムは、こうして説明される。
●子どもの自殺(7)
おとなは、生きるのがいやになって、その結果として、自殺を選ぶ。しかし子どものばあ
いは、(顔のない自分)に耐えきれず、自殺を選ぶ。自殺することによって、(自分の顔)
を主張する。近年ふえているリストカットも、同じように説明できる。リストカットする
ことで、自分を主張し、他人からの注目(同情、あわれみなど)を得ようとする。「贖罪(し
ょくざい)のために、リストカットする」と説く学者もいる(稲富正治氏ほか)。
●自虐的攻撃性(8)
攻撃型といっても、2つのタイプがある。外に向って攻撃的になる(校内暴力)と、内に
向って攻撃的になる(ガリ勉、猛練習)タイプ。「勉強しかしない」「勉強しかできない」「朝
から寝るまで勉強」というタイプは、後者ということになる。決して、勉強を楽しんでい
るのではない。「勉強」という場で、(自分の顔)をつくろうとしていると考えるとわかり
やすい。近年、有名になったスポーツ選手の中には、このタイプの人は少なくない。
●自我の同一性(9)
(子どもがしたがっている)ことに、静かに耳を傾ける。そしてそれができるように、子
どもの環境を整えていく。そうすることで、子どもは、(自分のしたいこと)と、(自分が
していること)を一致させることができる。これを「自我の同一性」という。この両者が
一致している子どもは、夢や希望もあり、当然、目的もあるから、見た目にも、落ちつい
ていて、どっしりとしている。抵抗力もあるから、誘惑にも強い。
●心の抵抗力(10)
「私は~~をしたい」「ぼくは~~する」と、目的と方向性をしっかりともっている子ども
は、心の抵抗力も強い。外部からの誘惑があっても、それをはねのける。小学校の高学年
から中学校にかけては、その誘惑が、激増する。そうした誘惑をはね返していく。が、同
一性が崩壊している子どもは、生きザマが、せつな的、享楽的になるため、悪からの誘い
があると、スーッとその世界に入ってしまう。
●夢や希望を育てる(11)
たとえば子どもが、「花屋さんになりたい」と言ったとする。そのとき重要なことは、親は、
それに答えて、「そうね、花屋さんはすてきね」「明日、球根を買ってきて、育ててみまし
ょうか」「お花の図鑑を買ってきましょうか」と、子どもの夢や希望を、育ててやること。
が、たいていの親は、この段階で、子どもの夢や希望を、つぶしてしまう。そしてこう言
う。「花屋さんも、いいけど、ちゃんと漢字も覚えてね」と。
●子どもを伸ばす三種の神器(12)
子どもを伸ばす、三種の神器が、夢、目的、希望。しかし今、夢のない子どもがふえた。
中学生だと、ほとんどが、夢をもっていない。また「明日は、きっといいことがある」と
思って、一日を終える子どもは、男子30%、女子35%にすぎない(「日本社会子ども学
会」、全国の小学生3226人を対象に、04年度調査)。子どもの夢を大切に、それを伸
ばすのは、親の義務と、心得る。
●役割混乱(13)
子どもは、成長するにつれて、心の充実をはかる。これを内面化というが、そのとき同時
に、「自分らしさ」を形成していく。「花屋さんになりたい」と言った子どもは、いつの間
にか、自分の周囲に、それらしさを作っていく。これを「役割形成」という。子どもを伸
ばすコツは、その役割形成を、じょうずに育てていく。それを破壊すると、子どもは、「役
割混乱」を起こし、精神的にも、情緒的にも、たいへん不安定になり、混乱する。
●思考プロセス(回路)(14)
しかし重要なのは、「思考プロセス」。幼いときは、「花屋さんになりたい」と思ってがんば
っていた子どもが、年齢とともに、今度は、「看護婦さんになりたい」と言うかもしれない。
しかし幼いときに、花屋さんになりたいと思ってがんばっていた道筋、あるいは思考プロ
セスは、そのまま残る。その道筋に、花屋さんにかわって、今度は、看護婦が、そこへ入
る。中身はかわるかもしれないが、今度は、子どもは、看護婦さんになるために、がんば
り始める。
●進学校と受験勉強(15)
たいへんよく誤解されるが、「いい高校」「いい大学」へ入ることは、一昔前までは、目的
になりえたが、今は、そういう時代ではない。学歴の権威を支える、権威主義社会そのも
のが崩壊してしまった。親は、旧態依然の考え方で、「いい大学へ入ることが目的」と考え
やすいが、子どもにとっては、それは、ここでいう目的ではない。「受験が近いから、(好
きな)サッカーをやめて、受験塾へ行きなさい」と子どもを追うことで、親は子どもの夢
をつぶす。「つぶしている」という意識すらないまま……。
●これからはプロの時代(16)
これからはプロが生き残る時代。オールマイティなジェネラリストより、一芸にひいでた
プロのほうが、尊重される。大手のT自動車の面接試験でも、学歴不問。そのかわり、「君
は何ができるか?」と聞かれる時代になってきている。大切なことは、子どもが、生き生
きと、自分の人生を歩んでいくこと。そのためにも、子どもの一芸を大切にする。「これだ
けは、だれにも負けない」というものを、子どもの中につくる。それが将来、子どもを伸
ばす。
●大学生の問題(17)
現在、ほとんどの高校生は、入れる大学の入れる学部という視点で、大学や学部を選んで
いる。もともと、勉強する目的すらもっていない。そのため、入学すると同時に、無気力
になってしまったり、遊びに夢中になってしまう大学生が多い。燃え尽きてしまったり、
荷おろし症候群といって、いわゆる心が宙ぶらりんになってしまう子どもも多い。当然、
誘惑にも弱くなる。
●自我の同一性と役割形成(18)
子どもをまっすぐ伸ばすためには、(子どもがしたがっていること)を、(現在しているこ
と)に一致させていく。そしてそれを励まし、伸ばす。親の価値観だけで、「それはつまら
ない仕事」「そんなことは意味がない」などと、言ってはいけない。繰りかえすが、子ども
が、「お花屋さんになりたい」と言ったら、すかさず、「それはすてきね」と言ってあげる。
こういう育児姿勢が、子どもを、まっすぐ伸ばす基礎をつくる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司●
同一性の危機●夢・希望・目的●子どもの忍耐力●同一性の崩壊●顔のない自分●校内暴
力●子
どもの自殺●自虐的攻撃性●自我の同一性●心の抵抗力●夢や希望を育てる●子どもを伸
ばす
三種の神器●役割混乱●思考プロセス(回路)●進学校と受験勉強●これからはプロの時
代●
大学生の問題●自我の同一性と役割形成 心の抵抗力 自我の同一性)
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 心の抵抗力 子どもを非行から守る法 子どもの心を守る。)
++++++++++++++++++はやし浩司
●心の抵抗力
心にも抵抗力がある。
その抵抗力が弱くなると、子どものばあい、一義的には、非行に走りやすくなる。
言い換えると、非行から子どもを守るためには、心の抵抗力を強くすればよい。
つまり講演の切り口を、(1)「子どもを伸ばすこんな方法」にするか、(2)「子どもを
非行から守る、こんな方法」にするか。
3番目の話が、どうしても決まらない。
どちらにしようか……?
それは講演会場の雰囲気で決めるしかない。
これから運動を2単位(40分x2)、こなしてくる。
2011/11/30記
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●11月30日(水曜日)
風もない。
のどかな小春日和(びより)。
一匹の蛾が、半分枯れた畑の周りを飛んでいる。
左から右へと。
パラパラ、パラパラ……。
せわしない飛び方だ。
が、それを除けば、動くものはない。
葉先を照らす白い光も、今は動きを止めている。
●般若(ハンニャー)
よく耳にしているものの、意味がよくわからないまま使っている言葉というのは、多い。
「般若(ハンニャー)」も、そのひとつ。
ウィキペディア百科事典には、つぎのようにある。
「般若(はんにゃ)、サンスクリット語:praj?? プラジュニャー、パーリ語:パンニャー、
音写:斑若、鉢若、般羅若、鉢羅枳嬢など)は、一般には智慧といい、仏教におけるいろ
いろの修行の結果として得られた「さとり」の智慧をいう」と。
私は子どものころ、「はんにゃ」と聞いたとき、即、能面のひとつの、あの恐ろしい顔を
連想した。
「どうしてそんな恐ろしい話が、お経にあるのか」と。
「般若」が「智慧」を意味することを知ったのは、ずっとあとのことだった。
「いろいろの修行の結果として得られた悟りの智慧」を「ハンニャー」というらしい。
が、ここまで詳しくは知らなかった。
ウィキペディア百科事典によれば、「はんにゃ」は、パーリ語の「パンニャー」に由来する
という。
「般若」は、中国語(漢語)の当て字。
だから「般」とは何かとか、「若」とは何かとか、漢字からその意味をさぐっても、文字通
り、意味はない。
同じように、よく話題になるが、「南無」もそうだ。
「南無」も、サンスクリット語の「ナム」の当て字。
インド大使館の中の領事部に電話で意味を確かめたことがある。
学術部というところがある。
意味は、「Hello(こんにちは)」に相当する言葉だそうだ。
もともとは「帰依します」という言葉だったとか。
が、今は、そんなむずかしい意味で使っている人はいない。
インドでは、「ナマ(=ナム)・ステ(あなたに帰依します)」というように言い、あいさつ
言葉として使っている。
で、その「般若」。
『般若心経(ハンニャーシンギョウ)』は、あまりにも有名である。
正式には『摩訶般若波羅蜜多心経』というのだそうだ。
ここでいう「心」は、「心臓」。
これは当て字ではなく、漢語の「心」を置いた。
「心臓のように重要な」という意味でそうしたらしい。
「経」はもちろん、あとで中国人が勝手につけ足した。
●中国語
多くの経典は、「仏説……」で始まる。
「仏が以下のように、……と言った」という意味である。
が、それにつづく経文は、ほとんどが当て字。
今ではYOUTUBEを使って、チベット僧たちの読経を直接聞くこともできる。
発音が、日本で聞く経典と、たいへんよく似ているのがわかる。
つまり中国人たちは、経典を、日本でいうなら英語をカタカナで書くように、自分たちの
漢字を使って、「音」を表した。
だから今、中国人に、仏教の経典を見せ、意味をたずねても、わかるはずもない。
私も若いころ、何度かそういうことをした経験がある。
つまり経典の意味をたずねたことがある。
が、みなこう言った。
「まったく、プーミンバイ(わからない)」と。
●般若心経
どうしてここで「般若」を取り上げたか?
理由がある。
先日、恩師の1周忌に行ってきた。
その席で、みなが般若心経を僧侶の声に合わせて、読経していた。
が、私はひとり、静かに座っていた。
読経できなかったのは、私だけだった。
軽い屈辱感を覚えた。
以来、……まだ数日だが、ずっと般若心経について考えている。
何度か訳本のようなものは、読んだことがある。
しかしいつも、そのあたりで、思考が停止してしまう。
これにも理由がある。
というのも、般若心経の教えは、一言で表せば、生き様が後ろ向きで、暗い。
何もかも、空しい。
何をしても、空しい。
形あるものは、すべて無、と。
が、60歳を過ぎた今は、考え方がかなり変わってきた。
「空」の意味も、「無」の意味も、おぼろげながら、わかるようになってきた。
●モノ論
たとえばモノ。
このところモノに対する執着心が、どんどんと消えていくのを感ずる。
というか、ほとんど興味がない。
衣服にしても、家具にしても、どうでもよくなってしまった。
置き物や装飾品にしては、さらにそうで、今では世話になった人に、どんどんと分け与え
ている。
例外と言えば、パソコン関連。
パソコンも、モノはモノだが、少し感覚がちがう。
ひとつには、パソコンはモノだが、パソコンというのは、言うなれば別の宇宙への「窓
(WINDOW)」。
それにいくら高価なパソコンであっても、5年もすればただの箱。
今では2~3年ごとに、どんどんと変化していく。
骨董品のように、あとで価値が出てくるということはない。
簡単に言えば、ただの消耗品。
●「家」意識
が、昔の人は、「家」を意識した。
だから財産としてのモノに、大きく執着した。
先祖から自分、自分から子孫へ、と。
私の母がそうだった。
(父はその反面、モノには、まったくといいほど、関心がなかった。)
そういう価値観をもっている人にしてみれば、私のような生き様は理解できないだろう。
モノが、その家の価値を、裏付ける。
「家」意識の残る昔は、そうだった。
が、私も、今から思うと、母の影響を強く受けていた。
だから若いころは、よく骨董品屋を回った。
絵画も買い集めた。
価値のあるモノは、財産だった。
しかし今は、変わった。
●時代の変化
たとえば切手にしても、古銭にしても、今では、ほとんど価値を失った。
切手などは、額面料金でしか、買ってもらえない。
江戸時代の古銭にしても、一枚いくらではなく、目方でいくらというような売買の仕方を
する。
骨董品にいたっては、売ることすらむずかしい。
実際には、買ってもらえない。
実際、モノというのは、そういうものかもしれない。
私たちが「価値あるもの」と信じているものは、幻想のようなもの。
このことを即、『般若心経』に結びつけて考えることはできない。
しかしおぼろげながら、あくまでもおぼろげながら、「無」の意味がわかるようになった。
●人間電子レンジ
話題を変えよう。
数日前、あるところのある通りを歩いた。
一角がビルになっていて、その一室に、老人たち、20~25人が椅子に並んでいるのが
見えた。
何かの健康器具の販売会のようだった。
1人の女性(45歳くらい)が、ツボマッサージ器のような器具をもち、順に何かを説明
していた。
……というような回りくどい言い方はやめよう。
例の「人間電子レンジ」である。
(私は原理的な構造からみて、そう呼んでいる。)
椅子型の人間電子レンジ。
原理的には、電子レンジと同じ。
それに座っていると、体中が、ポカポカと温かくなってくる。
そうした効果が、もろもろの病気に効く……というわけである。
窓ガラスには、「慢性的な頭痛で苦しんでいませんか」「慢性的な腰痛で苦しんでいません
か」というような張り紙が、ぎっしりとしてあった。
「治る」という言葉は、薬事法に抵触するため、使えない。
だからそういう表現にしたのだろう。
もちろん人間電子レンジといっても、家庭で使うような強力な電子レンジではない。
20~30分もすると、何となく温まってきたかな……という程度のもの。
たとえて言うなら、温泉にでもつかったような暖かさを感ずる。
しかも人体の外部からではなく、内部から、その暖かさを感ずる。
●電磁波
が、問題は、それが発する電磁波。
ここに書いた健康器具がそうというわけではない。(誤解のないように!)
たとえば欧米では、電磁波に発ガン性があるということで、高圧線の近くは、学校の建設
すら規制されている(アメリカなど)。
一方、この日本では、電磁波を規制する法律すらない。
健康への影響についても、ほとんど問題になっていない。
もしそれが大きな問題になると、電力会社にとっては、まことにもって都合が悪い。
この日本では、電線がそれこそまさに野放しになっている。
日本の空という空を、それこそ蜘蛛の巣のように張りめぐされている。
家屋から数メートルしか離れていないところに、巨大なトランス(変圧器)が設置されて
いるところもある。
電磁波は、基本的には、危険なものである。
DNAレベルにまで、影響を与えると言われている。
脳腫瘍や小児白血病の原因になると言われている。
が、どの程度危険か……ということになると、それがはっきりしていない。
(参考:くわしくは、ウィキペディア百科事典
……http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%B3%A2)
仮にその住宅に住む人がガンになったとしても、高圧線との因果関係を特定することは、
たいへんむずかしい。
……ということで、野放し。
(この話は、日本の原子力発電所の話とどこか似ている?
電力会社のやることは、どうも信用できない。)
これ以上のことは、私にもわからない。
が、これだけは言える。
人間電子レンジは、健康によいというよりも、(その根拠もないが)、長く使用すれば、そ
れなりの弊害が現れるのではないのか。
その心配はないのか?
ウィキペディア百科事典によれば、いろいろな学者が、安全性や危険性についての論文を
書いている。
鍼灸院や接骨院では、常設しているところもあるという。
ここではあくまでも、「?」としておく。
●浜北区での講演会
夜、浜北区での講演会で講師を務めた。
できは、最悪!
「3つのキーワード」というテーマで話すつもりだったが、当初の予定より、時間が20
分、短縮された。
それもあって、急きょ、3つのテーマを2つにしぼる。
順番を入れ替える。
段階を追いながら……という当初の予定が、崩れる。
演壇にあがるまで、頭の中が混乱する。
……ということで、出だしから、話の内容がめちゃめちゃ。
で、なんとか、2つの話をし終えたところで時計を見ると、残り10分!
10分しかない!
(10分もある!)
さあ、どうしようかと頭の中、さらに混乱する。
10分で、3つ目のテーマについて話すのは無理。
しかし早く終わるわけにはいかない。
……ということで、3つ目のテーマを話し始める。
早口になる。
ハラハラ、ドキドキ……。
が、やはり途中で、時間切れ!
最後は、「3つ目の話は忘れてください」と。
今までに、そんなドジな言い方で、講演を締めくくったことはない。
最後のあいさつがすんだとたん、居場所がなくなってしまった。
落ち着かなかった。
そのまま演壇から消えたかった。
……早く消えたかった。
●帰宅
控え室に入ると、ワイフがつづいて入ってきた。
いつもなら、「どうだった?」と聞くが、その勇気もなかった。
出されたお茶を飲んで、そのまま外へ。
気分が重かった。
ワ「暖かいわね……」
私「……」
ワ「いつもなら、もっと寒いのに……」
私「……」と。
家に戻る途中、レストランで、遅い夕食を食べた。
ときどきワイフが慰めてくれた。
が、家に帰ると、生徒の母親からメールが届いていた。
恐る恐る開くと、こうあった。
「……お世話になります、SGです。
講演会は少し遠かったので迷いましたが、久々に先生のお話が聞けて思い切って行って本
当によかったです。
すばらしいお話をありがとうございました。
また機会がありましたら是非お願い致します。
父の実家が浜北文化センターのすぐそばで、私も3歳までその大家族で育ち、文化センタ
ーが建った昔神社の敷地だった所は、遊び場でした。懐かしい場所です。
先生には長男のTRが小学校1年生の時からですから、もう10年以上もお世話になって
おります。
先生のような方が浜松にいらして、息子達が教えていただけたことは本当に奇跡のような
有り難い事だと思い感謝しております」と。
「……そんなはずはない……」と思いながら、何度も読み返す。
胸が熱くなる。
「1人でもそういう人がいてくれただけでも、うれしい」と、自分に言って聞かす。
で、それを読んだあと、今回、講演会の主宰してくれた、担当のIK先生にメールを書く。
詫びのメールである。
「できは最悪で、申し訳ありませんでした」と。
●潮時
10年ほど前だったら、浜北区(旧浜北市)で講演すれば、いつも会場は、120%の
入りだった。
が、今回は、ガラガラ。
自分の力なさ……というか、限界を感じた。
「そろそろぼくも、潮時だね」と、寝る前にワイフにこぼす。
50代のころのような元気は、もうない。
早口になったとき、言葉がもつれることがある。
気力も弱くなった。
私「50代のころだったら、10分も早く終わるなどというドジなことはしなかった……」
ワ「そんなことないわよ」と。
そのつどワイフは何度も、「そんなことないわよ」と慰めてくれた。
●礼のメール
翌日、IK先生からメールが届いた。
それには、こうあった。
『はやし先生
昨日は、素晴らしいご講演をいただき、本当にありがとうございました。
事務局が不慣れなため、失礼な面が多々あったと思いますが、さわやかに接していただき、
ありがとうございます。
昨日いただいた本は、職員みんなで読ませていただきます。
アンケート結果は、9割の方が「とてもよかった」1割の方が「よかった」と回答していま
した。「子育てを見直す機会となった」「早速実践していきたい」「分かりやすかった」など
の意見とともに、「3つめのキーワードのお話についても、もっと聞きたかった」という意
見もかなりありました。
今朝の職員室でも、「昨日の講演、よかったね」の声が多数聞かれました。
はやし先生にお願いして、本当によかったと思います。
先生のお話は、もっと多くの方に聞いていただきたいので、機会がありましたら、またお
願いしたいと思います。
昨日は、本当にありがとうございました。
メールにて失礼かとも思いましたが、取り急ぎお礼をさせていただきました』と。
???????????????
コピーしてそれをワイフに渡す。
それを読んでワイフがこう言った。
「ほらね、何もあなたは失敗なんかしてないのよ」と。
私は、ただ、「本当かなあ?」を繰り返すのみ。
ふつうなら喜んでよいはずのメールである。
が、今回は、どうしてもそんな気分になれない。
●失敗感
おかしなもので、年を重ねるごとに、講演するのが恐くなってきた。
若いころは、無鉄砲というか、恐いもの知らずというか、平気だった。
が、60歳を過ぎるころから、恐くなってきた。
今は、もっと恐い。
ひとつには、「失敗感」が強くなったことがある。
講演を終えるたびに、ガクリとくる。
「今日も失敗だった」と。
落ち込みがはげしくなった。
とくにこの数年、自分で納得できる講演をしたことがない。
どれもボロボロ。
一応筋書きを書くのだが、その筋書き通りに話したことは、一度もない。
話の途中で、めちゃめちゃになってしまう。
だからいつもこう思う。
「今度こそ……!」と。
しかしそのつど、また失敗する。
その繰り返し。
来週は、三島市での講演がある。
だから今、こう誓う。
「今度こそ、失敗しないぞ!」と。
Hiroshi Hayashi++++++Dec. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●闇路に迷う愚痴人間(はやし浩司 2011-11-29朝記)
+++++++++++++++++
「闇路に迷う愚痴人間」。
まさにその通り。
「愚痴」というのは、「法を知らない愚かな」という意味。
「法」とは、すなわち、「仏法」をいう。
つまり私のこと。
+++++++++++++++++
●週刊現代を読む
昨日、夕食のあと、空き時間があった。
『週刊現代』(2011・12・10)を読む。
改めて、60歳以上の人たちが置かれた立場のきびしさを実感する。
うすうすわかってはいたが、具体的な数字で示されると、衝撃も大きい。
働くといっても、60歳以上の人には、満足な仕事すらない。
ほんの少し前には、少子化による労働力不足が叫ばれた。
が、今は、仕事そのものがない。
働きたくても、また働かなければならなくても、仕事そのものがない。
●ターニング・ポイント
円高から、円安へ。
そのあとこの日本は、一気にハイパーインフレの時代へと突入する。
そのターニング・ポイントはいつか。
その目安となるのが、日本国債の応札倍率と利回り。
国債の利回りが、急激に上昇し始めたとき、あるいは上昇したときが、あぶない。
先日のドイツのように応札倍率が、1倍に満たないとき、つまり「札割れ」したときも、
あぶない。
そのとたん……というより、その瞬間から、日本は一気に円安に向かう。
●札が紙くずに
日本の国家債務が、1000兆円。
地方債務を含めれば、その額は、もっとふくらむ。
国家税収(=収入)が40兆円余りだから、その25倍ということになる。
たとえて言うなら、年収が400万円の人が、1億円の借金を抱えているに等しい。
見た目には豊かでも、中身はガタガタ。
が、私はこの数字を逆に読む。
「日本は、実際には、25年前に逆戻りしてもおかしくない」と。
つまり2011-25=1986年。
1986年だぞ!
それ以後の日本は、まさに砂上の上に築いた楼閣のようなもの。
わかりやすく言えば、1986年以後築いた財産などは、すべて失っても文句は言えない。
●1986年(昭和61年)
1986年という年は、どんな年だったのか。
講談社の「20世紀全記録」によれば、つぎのようにある。
1月……「チャレンジャー」爆発……砕かれた宇宙開発の夢、7人、全員死ぬ
2月……「ピープルズパワー」……マルコス追放
3月……(とくに目立ったニュースなし。)
4月……ハレー彗星接近、そしてあの「チェルノブイリ原子力発電所・爆発!」
5月……チャールズ英皇太子、ダイアナ妃と来日
6月……(とくに目立ったニュースなし。)
7月……ワールドカップ・アルゼンチン優勝……マラドーナの5人抜き
8月……タイタニック号を撮影、円高1ドルが152円に
9月……(とくに目立ったニュースなし。)
10月……第10回、アジア大会、ソウルで開催
11月……レーガン・ゴルバチョフのレイキャビク会談失敗、三原山209年ぶり噴火
12月……数十年ぶり、ヨーロッパ全土に大寒波襲来
「チェルノブイリ原子力発電所・爆発」と書いたとき、心底、ドキッとした。
それから25年。
この日本でも、同じことが起きた!
●精神
しかし60歳以上の人には、さらにきびしい現実が待ち構えている。
仕事だけが問題ではない。
どう精神的に自分を支えていくか……。
実は、こちらの問題のほうが、大きく、かつ深刻。
たとえて言うなら、目的地のわからない暗い夜道を歩くようなもの。
その先に待っているのは、断崖絶壁。
それでも死ぬこともできず、ただひたすら歩きつづける。
そういう中で、自分をどう精神的に支えていくか。
●IMFへの出資比率
昨日、IMFについて書いた。
「日本は大口出資者なのに、ディレクター(理事)のメンバーに加えられていないのはお
かしい」と。
そこで調べてみた。
「大口」(ウィキペディア百科事典)とは、何か。
「間違いだらけの金融知識」サイトにそれが、あった。
……2010年11月5日の理事会で、IMFは新しい出資比率の改定を承認した。
この承認案は2012年の発効を目指しており、また、出資金総額も7557億ドル(約6
1兆円)にほぼ倍増される予定。
背景には、ギリシャやウクライナなどへの金融支援によって、資金基盤の増強が急務であ
ることがあげられている。(以上「間違いだらけの金融知識」より)
(以下、出資比率、単位は(%))
1位 米国 17.407
2位 日本 6.464
3位 中国 6.394
4位 ドイツ 5.586
5位 フランス 4.227
6位 英国 4.227
7位 イタリア 3.161
(以下、つづく)
日本の出資率は、6・464%。
出資金は、61兆円x0・06464=3・94兆円となる。
「今回の増資による出資金は約2兆円」(同サイト)とある。
その後、それだけの出資金を支払ったかどうかは知らない。
(たぶん、日本のことだから、支払ったにちがいないが……。)
「お金がない」と言いながら、どうして日本は外国では、こんなに気前がいいのだろう。
数週間前には、野田首相は、東南アジアで2兆円もばらまいてきた。
●お金
お金で人を助けてはいけない。
助けた方は、「相手は感謝しているはず」と考えがち。
しかしその相手は、その場だけ。
ばあいによっては、逆恨みされる。
「返せ」と言えば、そのとき人間関係は終わる。
が、それだけではない。
一度、保護・依存の関係ができると、それを断ち切るのは容易なことではない。
助けてもらうほうは、いつまでも、それを当然ととらえる。
国際関係を見ていると、それがよくわかる。
あの3・11大震災のときも、民間の義援金の話は耳にした。
とくに台湾からの義援金は、突出していた。
しかしどこかの国が、国として復興費用を支援してくれたという話は聞いていない。
日本は、今まで何をしてきたのか。
そのつどそれぞれの国で、1兆円単位のお金をばらまいてきた。
受け取る方は「Thank You」と言うかもしれない。
しかしいつもそのままで終わってしまう。
●親子でも
親子でも、お金の貸し借りはしてはいけない。
息子や娘のほうは、必要になるたびに、こう言う。
「就職したら返すから」「給料があがったら返すから」と。
が、いまだかって、そういう息子や娘が、親にお金を返したという話も聞いたことがない。
で、親がいよいよ生活に困るようになって、息子や娘にこう言う。
「そろそろ少し返してくれないか?」と。
とたん息子や娘の態度が豹変する。
「家でも土地でも、売ればいい」と。
「お父さんには年金があるだろ」と、息子に直接言われた知人もいる。
さらに「お前は見返りを求めて、オレたちを育ててきたのか」と、息子に怒鳴られた知人
もいる。
今、親子の関係も、ここまで希薄になっている。
●どうでもなれ!
現世に執着するかぎり、私たちはこの闇路から抜け出ることはできない。
抜け出るためには、執着、あるいは執着心を捨てなければならない。
執着があるから、迷い、悩み、苦しむ。
が、ひとたび執着を捨ててしまえば、前の道が、パッと明るくなる。
わかりやすく言えば、「どうでもなれ!」と宣言すればよい。
自分の命すらも、この宇宙という大自然界に託す。
……とまあ、口で言うのは簡単なこと。
しかし実際、そこまで割り切らないと、この複雑怪奇な世界では、楽しく生きていくこと
はできない。
「どうでもなれ!」と。
●闇路に迷う愚痴人間
今日も闇路に迷う。
明日も闇路に迷う。
今までも闇路に迷ってばかり。
いつになったら、執着から解放され、安穏の世界に入ることができるのだろう。
そこにある「現実」を前にすると、かけ声ばかりで、前に進まない。
「とりあえずすべきことは……」と考えたとき、思いつくのは「生活」のことばかり。
「この原稿を書くのが終わったら、30分、運動をしよう」
「今日は胃の調子がよくないから、節食しよう」
「明後日からの教材の準備を始めよう」
「為替の様子を見て、現金を現物資産に交換してこよう」
「AさんとBさんに、暮れの付け届けを送ろう」
「年賀状のデザインを考えよう」などなど。
『六趣輪廻(りんね)』に振り回されながら、それに抵抗する術(すべ)もない。
こんな私には安穏の世界など、夢のまた夢。
ドロドロした現実の中で、今日もこうして生きていく。
ア~ア!
では、みなさん、おはようございます。
こうして私は、すでに1時間も、命を無駄にしてしまった。
もう一度、ア~ア!
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 6日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page005.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●11月27日・日曜日・(恩師の1周忌)『六趣輪廻の因縁』
+++++++++++++++++++++++
起きたときは、それほど寒くは感じなかった。
が、朝ごはんを食べるころ、急に寒さを感じた。
これはどういう現象によるものなのか。
その間、書斎の机に、2時間ほど向かって座っていた。
途中、ワイフがやってきて、茶を出してくれた。
が、私は書斎では、暖房器具を使わない。
ストーブも使わない。
脳みそには、暖気は強敵。
足を暖めただけで、眠くなってしまう。
が、台所では、ストーブがついていた。
気温も22度もあった。
が、それを寒く感じた。
脳みそはともかくも、肉体は、怠けるとすぐ新陳代謝を止めてしまう。
あるいは頭が熱くなると、体は冷えるのか。
どうであるにせよ、寒い!
++++++++++++++++++++++
●老眼用(装着)メガネ
今、恩師の一周忌に向かう車の中にいる。
自宅から車で、1時間。
昨日買った、老眼用のメガネが役に立っている。
老眼用のメガネというのは、ふつうのメガネの上にさらに装着して使うメガネのこと。
「1・5度」という度数が書いてあるが、どういう意味なのか、よくわからない。
それをつけると、車の中でもパソコンの文字が、楽に読める。
●1周忌
昨年の葬儀のときも、寒かった。
今日も、寒い。
が、あれからもう1年。
早いというより、恩師の死が、遠い昔のできごとのように思われる。
いろいろあった。
3・11大震災。
原発事故。
タイの大洪水。
EUの金融危機などなど。
この1年で、日本を取り巻く環境は、一変した。
その恩師。
いつも私の原稿を、私のワイフよりもていねいに読んでくれた。
心の奥底をいかに包み隠して書いても、恩師だけはそれを読み取ってくれた。
●1号線
国道1号線は、この20年あまり、ほとんど変わっていない。
側に並ぶ店も、店の名前も、20年前のまま。
「なあ、一周忌のあと、どうする?」と私。
「うん、帰るよ」とワイフ。
たった今、3、4台の大型バイクが、目前を左から右へ、大きくカーブして横切ってい
った。
「寒くないのだろうか?」と、それを見やりながらそんなことを考えた。
空は灰色。
雲の境目が見えない。
一面、ボヤーッとしている。
私は冬の寒さも、冬景色も、嫌い。
気分まで、重くなる。
●「歩こう会」
気賀の駅を通り過ぎたところで、「歩こう会」※の人たちを追い抜いた。
かなりの人数である。
そういう人たちが、駅から、気賀の関所を通り抜け、突き当りの本陣宿のあたりまで、ず
っと並んで歩いていた。
全部で、4、500人はいただろうか。
まばらだが列は、数キロ先までつづいていた。
私たちもよく「歩こう会」に出るが、これほどまでの人数は見たことがない。
JRかどこか、大きな団体が企画した「歩こう会」なのだろう。
それにしても、すごい。
まるで祭りの日の人出のよう。
(注※:あとで参加者の1人に聞くと、JR主催の「さわやかウォーキング」の会の人たちというこ
とがわかった。)
とがわかった。)
●船酔い
メガネのせいか?
少し船酔いに似ためまいを感じた。
……ここでいったん、パソコンを閉じる。
それにしても、TOSHIBAのR631は、よいパソコンだ。
開いているだけで、指先がもぞもぞしてくる。
ただ残念なのは、私はこのパソコンを発売日の11月11日に買った。
が、それから2週間もたっていないのに、価格が3万円近くも下落した。
ワイフは「少し待っていれば、安く買えたのに……」と言った。
……そういうものでもないのだが……。
パソコンの価格は、それをどう使うかで決まる。
いくら安くても、使わないものは、使わない。
たとえばこの5月に、DOCOMOで携帯端末を買ったとき、ミニパソコンをおまけにく
れた。
が、そのパソコンは、ほとんど使っていない。
机の上のゴミになっている。
これについてもワイフは、こう言う。
「だれかにあげたら……?」と。
しかしパソコンというのは、人にあげるものではない。
リカバリーすれば安心だが、そうでなければ、人にあげるものではない。
どこからどのような情報が他人に漏れるか、わかったものではない。
それがこわい。
●法要
1周忌には、家族全員と親類。
それに恩師の仲間たち、30~40人が集まっていた。
ワイフと控室で待っていると、横に私と同年齢らしき男性が座った。
その男性が、この1年のことをあれこれ話した。
そして「今は、どこも不景気です」と顔をしかめた。
S社(自動車会社)のエンジン部品を製造しているという。
日本でしか作れない部品だから……と安心していたが、3・11大震災、タイの大洪水の
あと、S社は、同じ部品をアメリカの工場に発注してしまったという。
「1年前に戻りたいですよ」と、2、3度、同じことを言った。
どこもかしこも、不景気。
そんな話ばかり。
●臨済宗
1周忌は、臨済宗で執り行われた。
いつものチン・ポン・ジャランはなかった。
その代わり、木魚(もくぎょ)が叩かれた。
ポクポクポク……。
その響きが心地よかった。
久しく正座などしたことがなかったのに、どういうわけか、足が痛くならなかった。
どうしてだろう?
ときどきワイフが心配して、私の足の心配をした。
●法事
1周忌の法事は、1時間足らずですんだ。
私とワイフは、喪主である恩師の奥さんに別れを告げ、寺を出た。
水色の空に、飛行機雲が何本か走っていた。
ワ「どこかへ寄っていかない?」
私「いいよ」
ワ「コンビニはどう?」
私「ミニストップなら、中で食事もできる」と。
結局、私たちは「ガスト」という店に寄った。
日曜日ということもあり、店中は、子ども連れの夫婦で混雑していた。
にぎやかというより、幼稚園の参観日のような雰囲気だった。
私たちは10分ほど、玄関先の長椅子で待ったあと、席に着いた。
で、こんなことがあった。
ガストに入る前、「歩こう会」の夫婦とすれちがった。
そのとき私はこう聞いた。
「どこの会ですか?」と。
妻のほうが、こう答えた。
「さわやかウォーキングです」と。
で、私は「JRの……?」と聞き返したら、数歩先を歩いている夫のほうが、妻を叱った。
「おい、いいから、行くぞ! 放っておけ!」と。
妻はそそくさとその場を離れながら、「JRです」と。
困ったような笑顔が印象的だった。
どこの世界にも、このタイプの夫はいる。
60代、70代の夫婦となると、ほとんどがそうであると言ってよい。
が、どうしてそんなに威張れるのだろう?
威圧的。
昔の武士がどんなだったかは知らない。
しかし武士そのもの。
●ガスト
飲食店は、どこも大不況という。
しかしガストの混み具合を見ていると、「?」と思ってしまう。
なぜこうした店は流行(はや)るのか?
それは私自身の心の中をのぞいてみるとわかる。
(1)安い。
(2)早い。
(3)安心。
(4)おいしい。
(5)清潔。
(6)サービスよし。
「安心」というのは、ガストなら、どこへ行っても同じ味を楽しむことができる。
料金も同じ。
個人経営の店は、(今ではほとんど残っていないが)、その「安心」がない。
実はおけいこ塾も同じ。
学習塾でもよい。
どこかクセのある塾よりは、大手塾のほうが「安心」。
そのため今では、中小塾は、どこも経営がきびしい。
というより、ほとんどが今、開店休業状態。
で、親たちは、チラシを見て、塾を選ぶ。
1色刷のチラシでは、生徒は集まらない。
3色刷のチラシでも、むずかしい。
「4色刷でないと、集まらない」という。
が、個人の塾では、4色刷のチラシを作るのは、経済的にも不可能。
勝敗は、そのとき決まる。
……ガストのメニューは、ほとんどが4色刷。
カラフルであか抜けている。
それをワイフに話しながら、「これは3色刷……。これが4色刷……」と教えてやった。
ワイフはそれを見比べながら、「3色刷になると、ちゃっちぽくなるわね」と言った。
●帰り道
ガストを出たのが、12時45分ごろ。
今は帰りの車の中にいる。
「どこか、温泉でも行きたいね」と私。
「そうね」とワイフ。
……帰り道、床屋へ寄っていく。
髪の毛がかなり伸びた。
「あの店?」とワイフ。
「うん」と私。
私のようなシルバーは、1400円で調髪してもらえる。
そういう店が、私の家の近くにある。
●意識
今朝、夢について書いた。
意識の奥深くから沸き起こってくる夢。
その深遠さについて書いた。
たとえて言うなら、意識というのは、卵でいうなら殻のようなもの。
脳の大部分は、無意識の世界にある。
それについてワイフの話すと、こう聞いた。
「意識って、そんなに薄っぺらいの?」と。
で、私は、こんな例を話した。
たとえば私は、過去、何千人もの子どもたちを教えてきた。
同時に、同じ数だけの親たちに会ってきた。
それもあり、街中を、30分も歩くと、かならずといってよいほど、1人や2人、顔見知
りの人に出会う。
その瞬間のこと。
名前も、いつどこで出会ったかも思い出せない。
しかし顔を見た瞬間、ふと懐かしさがこみあげてくる人もいれば、反対に不快な思いが心
をふさぐこともある。
心のほうが、先に反応してしまう。
よい思い出のある親や子どもに会うと、懐かしさがこみあげてくる。
悪い思い出のある親や子どもに出会うと、不快な思いがこみあげてくる。
名前や、いつどこで出会ったかを思い出すのは、そのあと。
あいさつをしたり、知らぬ顔をして通り過ぎたりしたあと、「あのときの……」となる。
つまり意識としては覚えていなくても、その何十万倍(あるいは何百万倍かもしれない)、
別の心が先に反応してしまう。
私であって、私でない別の心が、先に反応してしまう。
心(=脳)というのは、そういうもの。
夢というのは、その何十万倍(あるいは何百万倍)もの世界から、湧き起きてくる。
もし意識で夢をコントロールできたり、その前日あったできごとのつづきのような夢を
見たら、(たまにそういうこともあるが)、精神状態がふつうでないことを疑ってみたほ
うがよい。
●床屋
私はいつも1000円床屋へ行く。
安いからではない。
近くにあるし、それに早い。
長くて15分程度ですんでしまう。
(洗髪を頼まなければ、10分程度。)
それに無駄な会話がないのも、よい。
こちらも話しかけないし、向こうも話しかけてこない。
洗髪を入れたりすると、1400円になる。
それでも安い。
ふつうの床屋と比べると、半分以下。
床屋にとっても、そのほうがよいのでは?
1回、4200円というと、高い。
1400円というと、安い。
だから料金を気にすることなく、頻繁に行く。
ふつうの床屋へ1回行く分で、3回、行ける。
買い物の帰りに、「ちょっと……」となる。
つまり40分近くかけ、4200円の料金を取るか。
10分ですませ、1400円にし、3回来てもらうか。
●映画『新少林寺』
家に帰ると、ワイフは洗濯物を竿にかけるところだった。
私は服を替えると、そのまま書斎へ。
が、とたんに眠気。
少し油断すると、すぐウトウト状態になってしまう。
今朝も5時半起きだった。
そのまま30分、ウォーキングマシンの上で歩いた。
ふだんなら今ごろは、昼寝タイム。
昨夜見た映画『新少林寺』と、法事で見た僧侶が頭の中でダブる。
ぼんやりしていると、どちらがどちらなのか、わからなくなる。
1時間ほどがんばってみたが、そこでギブアップ。
居間へおりていき、そのままコタツの中に。
●執着
執着を取り除くことは、重要なこと。
今日、法事で僧侶が読んだ一節に、こんなのがあった。
『六趣輪廻(ろくしゅりんね)の因縁は、己が愚痴の闇路なり』と。
「六趣因縁」というのは、衆生が煩悩とその行為によって必然的に「趣く」六つの道(地
獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)をいう。
「因」はある一つの現象を起こす直接的な原因、「縁」とは間接的な原因をいう。
つまり人間は、六趣の世界を、ぐるぐる回っているだけで、そこから抜け出だすことがで
きない。
その原因はと言えば、自分の愚痴によるもの、と。
が、「愚痴」といっても、私たちが日常的に使う「グチ」とは、意味がちがう。
「……仏教でいう『愚痴』は、愚癡とも表記し、仏の智恵に暗いこと、衆生の根本的無知
をさす」(大谷大学HPより)のこと。
ともあれ仏の知恵に暗い人ほど、グチを言いやすい。
愚痴は、グチでもよい。
グチを言う人は、闇路に迷っているようなもの。
その闇路から抜け出るためには、執着を捨てること。
煩悩の虜(とりこ)になっていては、いつまでたっても、闇路から抜け出ることはできな
い。
グチをこぼしたら、自分がバカになっていると思えばよい。
●DVD
夕食後、『タービュランス』というDVDを観ることになっている。
ワイフが数日前に、借りてきた。
「お前はDVDを観ろ。ぼくは、白隠禅師の座禅和讃をもう一度勉強する」と。
それを言うと、「あなたはDVDを観ないの?」とワイフ。
「あのなア、ぼくは天上界に入る人間だよ。お前のように、六趣輪廻の世界をさまよう
餓鬼(がき)とは、中身がちがうの!」
「ハア~。ごちそう様」と。
で、結局私も、DVDを観ることに。
「タービュランスというのは、乱気流のことだよ」と教えてやった。
……ということで、今日の日記はここまで。
明日もがんばります。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教
育評論 はやし浩司 六趣輪廻 因縁 愚痴 闇路 白隠 禅師 座禅和讃 はやし浩司
恩師の一周忌)
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●11月28日(月曜日)・アメリカのEU支配戦略
++++++++++++++++++++
今朝(11月28日)のニュースを読んで驚いた。
IMFが、イタリアの金融危機を救済するため、
6000億ユーロ、つまり約62兆円の支援を
準備しているという。
62兆円!
ブルームバーグは、つぎのように伝えている。
『国際通貨基金(IMF)はイタリアの債務危機が悪化した場合に備えて、6000億ユ
ーロ(約62兆円)の支援を準備している、と同国紙スタンパが伝えた。情報源には言及
していない。
(中略)
同紙によると、金利は4-5%で、融資額は4000億~6000億ユーロとなる公算
がある』と。
もしこれが事実とするなら、Good Newsとまでは言わないが、世界の金融恐慌
も、これで一息つくはず。
……しかし、IMFに、そんなお金があるのか?
そのお金は、だれのものなのか?
+++++++++++++++++++++
●IMF
ウィキペディア百科事典には、つぎのようにある(抜粋)。
今朝は、IMFの勉強から始める。
+++++++++++以下、ウィキペディア百科事典より+++++++++++++
●IMF
英語: International Monetary Fund、IMF)は、通貨と為替相場の安定化を目的とした
国際連合の専門機関。
本部はアメリカ合衆国のワシントンD.C.。
2007年1月現在の加盟国は185ヶ国。
●managing director
「managing director(一般に専務理事と訳される)」は、理事会の議長と国際通貨基金
の代表を務める。
国際通貨基金の専務理事には欧州出身者、世界銀行の総裁には米国出身者が選出される
の
の
が暗黙の了解になっている。
●問題点
日本の場合、大口出資国で有る等の立場から財務官僚が多く出向しており、融資が行わ
れていないにもかかわらず、「消費税を上げるべきだ」等のIMFの討議内容の報道がなされ
る。
これは、IMFの正式発表ではなく、財務官僚が出向者を使い、さも、まるで、IMFが全体
がその様に述べているかのように見せ、自分たちの都合の良いようにマスコミを通じ国内
世論を操作する道具にしている。
+++++++++++以上、ウィキペディア百科事典より+++++++++++++
●貸し倒れ?
わかりやすく言えば、IMFは、Bank of Banks(銀行の中の銀行)とい
うことになる。
『各国の中央銀行の取りまとめ役のような役割を負う』(ウィキペディア百科事典)とある。
が、気になるのは、「総裁には米国出身者が選出」という部分と、「日本が大口出資者で
ある」という点。
つまりIMFがイタリアを救済するということは、アメリカと日本が救済するというに等
しい。
その額、62兆円!
果たして貸し倒れはないのか?
ウィキペディア百科事典によれば、「かつては……成果があがらない国も多く、踏み倒しも
横行した」とある。
そこであれこれ対策は練られてはいるのだろうが、それにしても額がちがう。
本当に貸し倒れの心配は、ないのだろうか。
その前に、今の日本に、そんな余裕はあるのだろうか。
『財務官僚が出向者を使い、さも、まるで、IMFが全体がその様に述べているかのように見
せ、自分たちの都合の良いようにマスコミを通じ国内世論を操作する道具にしている』(同)
という部分も気になる。
●ネガティブ思考
ものごとはポジティブに考えたい。
今回のIMFの動きを、Good Newsと考えたい。
これでイタリアが立ちなおれば、EUの金融危機も、ひとまず遠ざかる。
またそうであってほしい。
が、私はどうしてもネガティブにものを考えてしまう。
その第一。
そんなことをすれば、ドイツのメルケル首相が心配しているように、モラル・ハザードを
起こしてしまう。
怠惰な国が、ますます怠惰になってしまう。
それだけではない。
一度、保護=依存の関係ができると、それを断ち切ることは、容易なことではない。
もしイタリアが、「またつぎもIMFが助けてくれるさ」と考えるようになったら、さらに
事態は悪化する。
さらに言えば、救済の仕方をまちがえると、かえって逆恨みされる。
韓国の例をあげるまでもない。
●韓国の例
……ここで「韓国」と書いて、しかし、ピンと来た。
現在、韓国は、経済的にはアメリカの属国と化している。
銀行のほとんどは、アメリカの資本下にある。
サムスンにしても、ヒュンダイにしても、アメリカの会社と考えたほうが、わかりやすい。
が、肝心の韓国の国民は、それに気づいていない。
「働けど、働けど、我が身楽にならず」という、つまりは国民全体が、ワーキングプアの
状態にある。
つまり韓国が現在の韓国になったのは、1997年の、あの金融危機に起因している。
……つまり、アメリカはジャパン・マネーを利用し、今度はEU支配をもくろんでいる!
●日本は……
しかしEUの金融危機は、何としても収めねばならない。
火事は火事でも、大きすぎる。
このままでは、火の粉が飛んでくるどころか、日本も延焼してしまう。
アメリカにしてもそうだろう。
が、その前に重要なことは、ドイツ自身の自腹を切らせることではないのか。
IMFのメンバーを見ると、さらにその感が強くなる。
メンバーの出身国は、つぎのようになっている。
ベルギー 1名
スウェーデン2名
フランス 5名
オランダ 1名
ドイツ 1名
アメリカ 2名(総裁を除く)
スペイン 1名
大口出資者である日本は、Managing Directorには、入っていない?
ウィキペディア百科事典によれば、そうなっている。
つまりIMFは、EUの準付属機関と考えてよい。
どうしてそんな機関で、日本が大口出資者なのか?
たいへんネガティブな見方をすれば、こうだ。
EUとアメリカは、日本のマネー(Japan Money)を使って、EUを救済し
ようとしている。
が、かたやその日本はといえば、お人好しのボンボン。
欧米に相手にしてもらえただけで、大喜び。
日本の官僚たちにしても、まさに特権階級。
日本が破産しても、食いはぐれることはない。
(戦後直後にしても、またあの3・11大震災直後にしても、官僚+役人たちだけは、満
額の給料が支給されていた。
文部省(終戦直後当時)の役人にしても、クビになった役人は、1人もいない。)
●大国意識は捨てよう
果たしてGood News なのか?
それともBad Newsなのか?
私には、わからない。
もともと狂った世界の話だから、このままさらに狂っても、私は驚かない。
しかし今回も、最後のババを引くのは、この日本。
IMFへの出資金にしても、もとはといえば、日本が戦後、懸命に働いてためたお金。
EU(=IMF)にしても、仮に貸し倒れになっても、(そうなる可能性はきわめて高いが)、
痛くもかゆくもない。
日本よ、日本人よ、こんなお人好しは、もうやめよう。
大国意識を捨て、もう一度、原点に立ち戻り、そこからはい上がろう。
このままでは、EUよりも先に、日本が沈没してしまう。
……今朝の私のものの考え方は、やはりネガティブか?
ただの杞憂か?
今日の日本の株価は、IMFの発表を受け、急上昇に転ずるはず。
ノー天気な日本、ここに極まれり。
みなさん、おはようございます!
2011/11/28朝記。
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
●11月27日(朝記)「己との闘い」
++++++++++++++++++++
寒さが少し緩んだ。
起きるとすぐ、そのままウォーキングマシンの上に。
30分、歩く。
時速6キロ。
結構な速さである。
ときどき足がもつれる。
書斎に入ったのが、午前6時5分前。
あたりはまだ真っ暗。
メールを読み、ニュースに目を通す。
日曜日の朝ということもあり、とくに目新しい記事はなし。
ただアフリカのジンバブエで、象が200頭死んだという記事が気になった。
猛暑と渇水が原因という(新華社)。
「毎週100頭の割合で死んでいる」とも。
その象の数。
毎年、減少している。
ウィキペディア百科事典によれば、
1970年代……2,700,000頭、
1980年 ……1,000,000頭、
1988年 …… 620,000頭と推定されている。
1995年 ……約280,000頭が確認され、580,000頭と推定されている、とある。
この数字が正しいとするなら、この1970年から1995年までの間に、
270万頭から、58万頭に減ったことになる。
約4~5分の1。
2000年に入ってからはどうなのだろう。
+++++++++++++++++++
●夢
今朝も、起きがけに何かの夢を見ていた。
見ていたが、思い出せない。
時間がたつと、乾いた砂が風に舞うように、記憶が消えていく。
何の夢だったのだろう。
どうしても思い出せない。
ただここで言えることは、同じような夢は、めったに見ないということ。
毎朝、違う。
今朝見た夢も、また別の夢だった。
脳がもつ奥深さに、改めて驚く。
●兄
数年前、兄が他界した。
子どものころから、体が弱かった。
それもあり、9歳年上の兄だったが、兄弟関係がいつの間にか逆転した。
私が兄、兄が弟。
そういう関係になった。
晩年の兄は、うつ病になっていたと思う。
人は認知症になったと言ったが、頭はしっかりとしていた。
老人のうつ病と認知症は、専門医でも区別がむずかしいという。
それはさておき、その兄からは電話がよくかかってきた。
いつもこう言った。
「お客さんが、ござらん(=来ない)」と。
兄は兄なりに、不安だったのだろう。
さびれいく町に、さびれゆく商店街。
そういう中にあって、兄は当時、65歳を過ぎていた。
その兄が、昨日、夢の中に出てきた。
その夢のことは、よく覚えている。
……あの町の通りを2人で歩いていた。
私が兄の腕を片側から支えていた。
その兄がこう言った。
「お客さんが、ござらん」と。
いつもの口癖である。
私はそれを聞き、精一杯気丈夫なふりをしながら、こう言った。
「心配せんでもいい。何とかしてやるから」と。
●貧乏
貧乏が、こわいというのではない。
貧乏に至る負け戦が、こわい。
とくに商店街では、貧乏は長い時間をかけ、ゆっくりとやってくる。
ジワジワ、ジワジワ……と。
5年とか、10年とか、それくらい長い月日をかけて、やってくる。
それがこわい。
人はこう言う。
「先を読め」「先手を打て」「頭を切り換えろ」と。
あるいはさらに無責任な人になると、こう言う。
「それも時代の流れ」と。
しかしそれは言葉。
実際には、「明日は何とかなるだろう」という甘い期待を抱きつつ、毎晩床に入る。
が、その明日も、昨日と同じ。
これを繰り返しているうちに、5年とか10年とかが過ぎてしまう。
●シャッター街
私の実家には、シャッターこそなかった。
ガラス戸と薄いカーテンだけ。
しかしいつの間にか、ガラス戸は閉まり、カーテンも閉ざされるようになった。
だからというわけでもないが、私は「シャッター街」という言葉を耳にするたびに、その
言葉がドシリと胸に響く。
響くというより、胸をつぶす。
外から見ればただのシャッター街だが、その向こうに商店主だった人たちの重苦しい思いを
感じてしまう。
感じてしまう。
負け戦はつらい。
本当につらい。
真綿で首を絞めるような閉塞感。
いくら虚勢を張り、明るく振る舞っても、その笑い声は地には着かない。
先の見えない不安感。
孤独感。
「私は何をしてきたのだろう」という自己否定。
来る日も来る日も、それと闘う。
●強迫観念
私は社会に出てから、懸命に働いた。
仕事をしたくて、働いたわけではない。
貧乏がこわかった。
貧乏になるのが、こわかった。
だからといって、金持ちになったわけではない。
振り返っても、私が受け取った(他人のお金)は、ほとんどない。
子どもたちの出産時に手にした、それぞれ10万円前後の祝い金。
それに義父が亡くなったとき受け取った、10万円。
それだけ。
だからいつも孤立無援。
失敗が許されないという孤立感。
ただひたすら、がむしゃらに働いた。
それが今でも、私が見る夢の原点になっている。
そう、悪夢といえば、電車やバスに乗り遅れる夢。
ホテルで寝過ごして、飛行機に乗り遅れる夢。
そんな夢ばかり。
心理学的では、強迫観念という言葉を使う。
医学的には、不安神経症という言葉を使う。
どちらでもよい。
私は子どものころから、そういう不安感から抜け出すことができないでいる。
きっと兄もそうだったのだろう。
「お客さんが、ござらん」と。
●戦争
が、だれの責任でもない。
父や母にしても、あの時代を懸命に生きてきた。
もし悪いとすれば、あの戦争。
あの戦争が悪い。
戦後生まれの私だが、みな、あの戦争の後遺症を傷深く背負っていた。
それが姿、形を変え、私の「心」となっていった。
だから今でも、こう思う。
イラクにせよ、アフガニスタンにせよ、仮に戦争が終わっても、その後遺症は、何世代
にも渡ってつづいていくのだろうな、と。
罪もない、子どもたちが、将来に渡って苦しむだろうな、と。
兄が子どものころから体が弱かったのも、元はと言えば、栄養失調。
兄が育った時代の日本には、満足な食糧すらなかった。
●「やっと死ねる」
64歳になった。
その今でも、こう思う。
「いつになったら、平安が訪れるのだろう」と。
……というか、もうとっくの昔にあきらめた。
だから今は、こう言う。
「死ぬまでつづくだろうな」と。
だから去年の正月に廊下で倒れたときも、こう思った。
「ああ、これで死ねる」と。
死にまつわるはずの恐怖感は、まったく感じなかった。
「やっと死ねる」という感じに近かった。
ただ不要な心配をかけたくないので、その理由について書いておく。
そのとき、何か大病があって、倒れたというわけではない。
私はときどき、不用意に首をひねったようなとき、後頭部にはげしい神経痛を覚えること
がある。
(重篤な病気の前兆ということも考えられるが……。)
そのときはそれが、いつもになくひどかった。
それが原因で、廊下に倒れた。
●平安
仏教で言えば「執着(しゅうじゃく)」。
心理学で言えば「固着」。
俗な言葉を借りれば、「こだわり」。
これを取り除かないかぎり、私の心に、平安は訪れない。
それはよくわかっている。
「心の傷」というのは、そういうもの。
ただ誤解してはいけないことがある。
心の傷などというものは、だれにでもある。
ない人はいない。
みな、ある。
それに気づいている人もいるが、気づいていない人もいる。
気づかないまま、いつもそれに振り回される。
同じ失敗を、繰り返す。
だから今は、そういう相談があるたびに、こう言う。
「心の傷なんてものは、死ぬまで消えませんよ。
仲よくつきあっていくしかないですよ」と。
●精進
今朝の夢も、悪夢に近かった。
よく覚えていないが、いやな夢だった。
断片的に覚えているのは、どこかの部屋にいたこと。
ガラス窓が見えた。
……あとは、覚えていない。
そう、その悪夢にしても、私はこの先、死ぬまで仲よくつきあっていくしかない。
脳というのは、そういもの。
いくら楽しい思い出で上書きしても、その上書きを突き破って、古い思い出が顔を出す。
しかも皮肉なことに、加齢とともに、上書きされた部分が、どんどんと崩落していく。
いやな自分に逆戻りしていく。
だから……と書くと、安っぽい映画の主題のように思う人もいるかもしれない。
しかし結論は、ひとつ。
だから、日々に精進あるのみ。
日々に鍛錬し、前向きに生きていく。
己(自分)に負けたとき、負け戦は、本当に負け戦になってしまう。
何としても、それだけは避けなければならない。
……ということで、今朝も始まった。
先ほど(7時過ぎ)、ワイフが茶を届けてくれた。
それをゆっくりと飲みなおす。
時刻は午前7時半。
もう1時間も、過ぎた。
みなさん、おはようございます。2011/11/27朝記
Hiroshi Hayashi++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 4日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
http://bwhayashi2.fc2web.com/page004.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【映画・新少林寺を観る】2011/11/26
++++++++++++++++++はやし浩司
昼寝をしたあと、ワイフと映画『新少林寺』を観てきた。
星は5つの、★★★★★。
文句なしの5つ星。
過去、いろいろな映画を観てきた。
が、最後の『The End』の文字まで観たのは、
この数年で、この映画が、はじめて。
熱い涙が止まらなかった。
同時に、こう思い知らされた。
「私は仏教徒だったんだなあ」と。
私の体の中には、仏教が染みこんでいた。
子どものころからの思い出が、つぎつぎと
現れては消えた。
歓びや悲しみ、楽しかった思い出や、つらかった思い出……。
それが内なる世界から、熱い涙を押し出した。
映画『新少林寺』は、最後の10分間で、
これから私が生きる道に、大きな示唆を与えてくれた。
すばらしい映画だった。
もし『新少林寺』を観る機会があったら、
最後の最後まで観てほしい。
「The End」の文字が、しっかりと止まるまで……。
++++++++++++++++++はやし浩司
【欲望論】(本能とは)
●白い太もも(大腿部)
家を出たとき、若い男と女が道路を歩いていた。
どこか物欲しそうに、しかし怪しげな歩き方だった。
が、何よりも目についたのは、女の白い太もも。
大腿部。
短いパンツに、ロング・ブーツをはいていた。
太ももは、99%、露出していた。
99%。
最後の1%で、左右のパンツがつながっていた。
●ミューチュアル・アタッチメント(相互愛着)
2000年に入ってから、ミューチュアル・アッタチメント(相互愛着)という言葉が
使われるようになった。
母親(父親)と乳幼児の関係についていったもの。
つまりそれまでは、母親と乳幼児の関係は、一方的なものと考えられていた。
母親側から乳幼児へ。
しかしそうではないことがわかってきた。
つまり乳幼児のほうからも、母親側に働きかけがあることがわかってきた。
あの乳幼児が、母親に、である。
わかりやすく言えば、乳幼児は、自ら、自分の(かわいさ)を演出することによって、親
の愛情を自分側にひきつけようとする。
エンゼル・スマイルもそのひとつと言われている。
このことは逆に考えてみれば、よくわかる。
もし生まれたての赤ん坊が、母親に向かって、こう言ったとする。
「おい、ババア、乳よこせ!」と。
とたん母親は乳をくれるのをやめてしまうだろう。
つまりその時点で、人類は絶滅の危機に立たされる。
●赤ちゃん返り
幼児期によく知られた、愛情飢餓による現象に、「赤ちゃん返り」というのがある。
ほとんどは「下の子」が生まれたことにより、「上の子」が、赤ちゃんぽくなる現象をいう。
あの赤ちゃん返りは、本能的な部分に根ざしているため、叱ったり、説教しても意味はな
い。
そういうことをすれば、症状は、ますますひどくなる。
ばあいによっては、慢性的な発熱など、身体的症状などを伴うこともある。
つまり乳幼児でも幼児でも、無意識のうちに、求める相手を自分に引きつけようとする。
ここにも書いたように、本能に近い部分から命令が発せられるため、本人がそれを意識す
ることはない。
●本題
さて本題。
太もも(大腿部)を99%見せて歩く、若い女。
明らかに男のS欲(禁止用語)を、刺激している。
しかしもちろん、本人には、その意識はない(……だろう)。
「どうしてそんな服装をしているの?」と聞けば、こう答えるにちがいない。
「ファッションよ」と。
つまり、オシャレ、と。
しかし私はそうは考えない。
その理由のひとつが、ミューチュアル・アタッチメント。
乳幼児でも、その程度の本能がある。
いわんや思春期の娘、をや。
●無意識下の行動
私の行動には、無意識に支配されるものが多い。
その例として赤ちゃん返りをあげた。
今までに何百という例を見てきた。
その子どもは、外から見たところ、本人の意思で行動しているように見える。
その延長線上に、あの「太もも」がある。
そう考えたところで、論理的に無理はない。
つまり女性は無意識のうちにも、男性を誘惑するように行動する。
言い換えると、男性のほうが女性のそういった服装を見て、興奮するのではない。
女性のほうが、男性をして、そう思わせるように仕向ける。
先にも書いたように、本能に根ざしているだけに、本人がそれを意識することはない。
無意識のまま、そうする。
●「形あるものは、すべて無」(「新少林寺」)
映画『新少林寺』で受けた感動が、まだ残っている。
その余韻もあって、過去に書いた原稿をいくつか探してみる。
++++++++++++++++++はやし浩司
●希望と期待
希望にせよ、期待にせよ、それが「欲望」から発したものであれば、それは未来を約束
した希望や期待にはならない。
よく「光」という言葉を使う人がいる。
「希望は光」と。
しかしそれは光ではない。
身を焦がす炎(ほのお)である。
たとえば子を育てる親の希望や期待には、際限がない。
受験にしても、やっとB高校へ入る力がついてくると、「何とかしてA高校へ」となる。
そのA高校が視野に入ってくると、今度は、「S高校へ」となる。
こうして希望や期待は、際限なくふくらんでいく。
その結果、いつまでたっても、安穏たる日々はやってこない。
ひとつの希望や期待がかなえられるたびに、その先でまた新たなる苦悩がやってくる。
処し方をまちがえると、家庭騒動、親子断絶、さらには家族崩壊へとつづく。
ただの「光」ではすまない。
つまり「炎」。
なぜか?
それが冒頭に書いたことである。
欲望から発しているからである。
●老後の希望
若いうちは、まだよい。
それが意味のないものであっても、その希望や期待に、酔いしれることができる。
時間を無駄にしても、そこにはありあまるほどの余裕がある。
(本当は、余裕などないのだが……。)
が、歳を取ると、そういうわけにはいかない。
刻一刻と、時間は短くなっていく。
無駄にできる時間など、一瞬一秒もない。
そこで何度も書くが、エリクソンという学者は、「統合性の確立」という言葉を使った。
老齢期の生き方を説いたものである。
3年前に書いた原稿だが、参考になると思う。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●自我の統合性と世代性(我々は、どう生きるべきか?)08年記
(Do we have what we should do? If you have something that you should do, your life
after you retire from your job, would be fruitful. If not, you will despair in a
miserable age.)
+++++++++++++++++
乳児期の信頼関係の構築を、人生の
入り口とするなら、老年期の自我の
統合性は、その出口ということになる。
人は、この入り口から、人生に入り、
そしてやがて、人生の出口にたどりつく。
出口イコール、「死」ではない。
出口から出て、今度は、自分の(命)を、
つぎの世代に還元しようとする。
こうした一連の心理作用を、エリクソンは、
「世代性」と呼んだ。
+++++++++++++++++
我々は何をなすべきか。
「何をしたいか」ではない。
「何をなすべきか」。
その(なすべきこと)の先に見えてくるのが、エリクソンが説いた、「世代性」である。
我々は、誕生と同時に、「生」を受ける。
が、その「生」には、限界がある。
その限界状況の中で、自分の晩年はどうあるべきかを考える。
その(どうあるべきか)という部分で、我々は、自分たちのもっている経験、知識、哲学、
倫理、道徳を、つぎの世代に伝えようとする。
つぎの世代が、よりよい人生を享受できるように努める。
それが世代性ということになる。
その条件として、私は、つぎの5つを考える。
(1) 普遍性(=世界的に通用する。歴史に左右されない。)
(2) 没利己性(=利己主義であってはいけない。)
(3) 無私、無欲性(=私の子孫、私の財産という考え方をしない。)
(4) 高邁(こうまい)性(=真・善・美の追求。)
(5) 還元性(=教育を通して、後世に伝える。)
この世代性の構築に失敗すると、その人の晩年は、あわれでみじめなものになる。
エリクソンは、「絶望」という言葉すら使っている(エリクソン「心理社会的発達理論」)。
何がこわいかといって、老年期の絶望ほど、こわいものはない。
言葉はきついが、それこそまさに、「地獄」。「無間地獄」。
つまり自我の統合性に失敗すれば、その先で待っているものは、地獄ということになる。
来る日も、来る日も、ただ死を待つだけの人生ということになる。
健康であるとか、ないとかいうことは、問題ではない。
大切なことは、(やるべきこと)と、(現実にしていること)を一致させること。
が、その統合性は、何度も書くが、一朝一夕に確立できるものではない。
それこそ10年単位の熟成期間、あるいは準備期間が必要である。
「定年で退職しました。明日から、ゴビの砂漠で、ヤナギの木を植えてきます」というわ
けにはいかない。
またそうした行動には、意味はない。
さらに言えば、功利、打算が入ったとたん、ここでいう統合性は、そのまま霧散する。
私は、条件のひとつとして、「無私、無欲性」をあげたが、無私、無欲をクリアしないかぎ
り、統合性の確立は不可能と言ってよい。
我々は、何のために生きているのか。
どう生きるべきなのか。
その結論を出すのが、成人後期から晩年期ということになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
Hiroshi Hayashi education essayist writer Japanese essayist 人生の統合性 世代性
統合性の確立 無私 無我)
(追記)
(やるべきこと)の基礎をつくる時期は、「人生の正午」(エリクソン)と言われる40歳
前後である。もちろんこの年齢にこだわる必要はない。早ければ早いほど、よい。
その時期から、先にあげた5つの条件を常に念頭に置きながら、行動を開始する。
この問題だけは、そのときになって、あわてて始めても、意味はない。
たとえばボランティア活動があるが、そういう活動をしたこともない人が、いきなり
ボランティア活動をしたところで、意味はない。
身につかない。
……ではどうするか?、ということになるが、しかしこれは「ではどうするか?」という
問題ではない。
もしそれがわからなければ、あなたの周囲にいる老人たちを静かに観察してみればよい。
孫の世話に庭いじりをしている老人は、まだよいほうかもしれない。
中には、小銭にこだわり、守銭奴になっている人もいる。
来世に望みを託したり、宗教に走る老人もいる。
利己主義で自分勝手な老人となると、それこそゴマンといる。
しかしそういう方法では、この絶望感から逃れることはできない。
忘れることはできるかもしれないが、それで絶望感が消えるわけではない。
もしゆいいつ、この絶望感から逃れる方法があるとするなら、人間であることをやめるこ
とがある。
認知症か何かになって、何も考えない人間になること。
もし、それでもよいというのなら、それでもかまわない。
しかし、だれがそんな人間を、あるべき私たちの老人像と考えるだろうか。
(付記)
統合性を確立するためのひとつの方法として、常に、自分に、「だからどうなの?」と自問
してみるという方法がある。
「おいしいものを食べた」……だから、それがどうしたの?、と。
「高級外車を買った」……だから、それがどうしたの?、と。
ところがときどき、「だからどうなの?」と自問してみたとき、ぐぐっと、跳ね返ってくる
ものを感ずるときがある。
真・善・美のどれかに接したときほど、そうかもしれない。
それがあなたが探し求めている、「使命」ということになる。
なおこの使命というのは、みな、ちがう。
人それぞれ。
その人が置かれた境遇、境涯によって、みな、ちがう。
大切なことは、自分なりの使命を見出し、それに向かって進むということ。
50歳を過ぎると、その熱意は急速に冷えてくる。
持病も出てくるし、頭の活動も鈍くなる。
60歳をすぎれば、さらにそうである。
我々に残された時間は、あまりにも少ない。
私の実感としては、40歳から始めても、遅すぎるのではないかと思う。
早ければ早いほど、よい。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●「無」
統合性を確立するためには、欲望を捨て、「無」の状態でなければならない。
功利、打算が入ったとたん、統合性は、霧散する。
ボランティア活動にしても、「無」でするから、意味がある。
何も期待しない。
見返りを求めない。
ただひたすら自分がすべきことをする。
それが「無」ということになる。
で、2500年前に釈迦が説いた「無」と、近代に入ってサルトルが説いた「無の概念」
が、一致するということは、たいへん興味深い。
宗教の世界を、「観念論の世界」という。
一方、サルトルらが説いた世界を、「実存主義の世界」という。
まったく相反する世界の哲学が、最終的には、ひとつの世界に融合する。
(私自身は、釈迦は、宗教ではなく、現在に通ずる実存主義を説いたものと解釈している。
その釈迦の教えを、無理に宗教化したのは、後世の学者たちと解釈している。)
釈迦は、「無」を哲学の根幹に置いた。
(いろいろ異論もあろうが……。)
一方、サルトルは、自由へのあくなき追求を経て、最終的には「無の概念」にたどりつく。
これについても、私はたびたび原稿を書いてきた。
サルトルについて書いた原稿をさがしてみた。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【自由であること】2009年記
+++++++++++++++++
自由であることは、よいことばかりで
はない。
自由であるということは、まさに自ら
に由(よ)って、生きること。
その(生きること)にすべての責任を
負わねばならない。
それは、「刑」というに、ふさわしい。
あのサルトルも、「自由刑」という言葉
を使って、それを説明した。
+++++++++++++++++
私は私らしく生きる。……結構。
あるがままの私を、あるがままにさらけ出して、あるがままに生きる。……結構。
しかしその自由には、いつも代償がともなう。「苦しみ」という代償である。自由とは、
『自らに由(よ)る』という意味。わかりやすく言えば、自分で考え、自分で行動し、自
分で責任をとるという意味。
毎日が、難解な数学の問題を解きながら、生きるようなもの。
話はそれるが、そういう意味では、K国の人たちは、気が楽だろうなと思う。明けても
暮れても、「将軍様」「将軍様」と、それだけを考えていればよい。「自由がないから、さぞ
かし、つらいだろうな」と心配するのは、日本人だけ。自由の国に住んでいる、私たち日
本人だけ。(日本人も、本当に自由かと問われれば、そうでないような気もするが……。)
そういう「苦しみ」を、サルトル(ジャン・ポール・サルトル、ノーベル文学賞受賞者・1905~1
980)は、「自由刑」という言葉を使って、説明した。
980)は、「自由刑」という言葉を使って、説明した。
そう、それはまさに「刑」というにふさわしい。人間が人間になったとき、その瞬間か
ら、人間は、その「苦しみ」を背負ったことになる。
そこで、サルトルは、「自由からの逃走」という言葉まで、考えた。わかりやすく言えば、
自ら自由を放棄して、自由でない世界に身を寄せることをいう。よい例として、何かの狂
信的なカルト教団に身を寄せることがある。
ある日、突然、それまで平凡な暮らしをしていた家庭の主婦が、カルト教団に入信する
という例は、少なくない。そしてその教団の指示に従って、修行をしたり、布教活動に出
歩くようになる。
傍(はた)から見ると、「たいへんな世界だな」と思うが、結構、本人たちは、それでハ
ッピー。ウソだと思うなら、布教活動をしながら通りをあるく人たちを見ればよい。みな、
それぞれ、結構楽しそうである。
が、何といっても、「自由」であることの最大の代償と言えば、「死への恐怖」である。「私」
をつきつめていくと、最後の最後のところでは、その「私」が、私でなくなってしまう。
つまり、「私」は、「死」によって、すべてを奪われてしまう。いくら「私は私だ」と叫
んだところで、死を前にしては、なすすべも、ない。わかりやすく言えば、その時点で、
私たちは、死刑を宣告され、死刑を執行される。
そこで「自由」を考えたら、同時に、「いかにすれば、その死の恐怖から、自らを解放さ
せることができるか」を考えなければならない。しかしそれこそ、超難解な数学の問題を
解くようなもの。
こうしたたとえは正しくないかもしれないが、それは幼稚園児が、三角関数の微積分の
問題を解くようなものではないか。少なくとも、今の私には、それくらい、むずかしい問
題のように思える。
決して不可能ではないのだろうが、つまりいつか、人間はこの問題に決着をつけるとき
がくるだろが、それには、まだ、気が遠くなるほどの時間がかかるのではないか。個人の
立場でいうなら、200年や300年、寿命が延びたところで、どうしようもない。
そこで多くの人たちは、宗教に身を寄せることで、つまりわかりやすく言えば、手っ取
り早く(失礼!)、この問題を解決しようとする。自由であることによる苦しみを考えたら、
布教活動のために、朝から夜まで歩きつづけることなど、なんでもない。
が、だからといって、決して、あきらめてはいけない。サルトルは、最後には、「無の概
念」をもって、この問題を解決しようとした。しかし「無の概念」とは何か? 私はこの
問題を、学生時代から、ずっと考えつづけてきたように思う。そしてそれが、私の「自由
論」の、最大のネックになっていた。
が、あるとき、そのヒントを手に入れた。
それについて書いたのが、つぎの原稿(中日新聞投稿済み)です。字数を限られていた
ため、どこかぶっきらぼうな感じがする原稿ですが、読んでいただければ、うれしいです。
Hiroshi Hayashi+++++++++++はやし浩司
●真の自由を子どもに教えられるとき
私のような生き方をしているものにとっては、死は、恐怖以外の何ものでもない。
「私は自由だ」といくら叫んでも、そこには限界がある。死は、私からあらゆる自由を奪
う。が、もしその恐怖から逃れることができたら、私は真の自由を手にすることになる。
しかしそれは可能なのか……? その方法はあるのか……?
一つのヒントだが、もし私から「私」をなくしてしまえば、ひょっとしたら私は、死の恐
怖から、自分を解放することができるかもしれない。自分の子育ての中で、私はこんな経
験をした。
●無条件の愛
息子の一人が、アメリカ人の女性と結婚することになったときのこと。息子とこんな会
話をした。
息子「アメリカで就職したい」
私「いいだろ」
息子「結婚式はアメリカでしたい。アメリカのその地方では、花嫁の居住地で式をあげる
習わしになっている。結婚式には来てくれるか」
私「いいだろ」
息子「洗礼を受けてクリスチャンになる」
私「いいだろ」と。
その一つずつの段階で、私は「私の息子」というときの「私の」という意識を、グイグイ
と押し殺さなければならなかった。苦しかった。つらかった。しかし次の会話のときは、
さすがに私も声が震えた。
息子「アメリカ国籍を取る」
私「……日本人をやめる、ということか……」
息子「そう……」、私「……いいだろ」と。
私は息子に妥協したのではない。息子をあきらめたのでもない。息子を信じ、愛するがゆ
えに、一人の人間として息子を許し、受け入れた。
英語には『無条件の愛』という言葉がある。私が感じたのは、まさにその愛だった。しか
しその愛を実感したとき、同時に私は、自分の心が抜けるほど軽くなったのを知った。
●息子に教えられたこと
「私」を取り去るということは、自分を捨てることではない。生きることをやめること
でもない。「私」を取り去るということは、つまり身のまわりのありとあらゆる人やものを、
許し、愛し、受け入れるということ。
「私」があるから、死がこわい。が、「私」がなければ、死をこわがる理由などない。一文
なしの人は、どろぼうを恐れない。それと同じ理屈だ。
死がやってきたとき、「ああ、おいでになりましたか。では一緒に参りましょう」と言うこ
とができる。そしてそれができれば、私は死を克服したことになる。真の自由を手に入れ
たことになる。
その境地に達することができるようになるかどうかは、今のところ自信はない。ないが、
しかし一つの目標にはなる。息子がそれを、私に教えてくれた。
Hiroshi Hayashi+++++++++++はやし浩司
くだらないことだが、この日本には、どうでもよいことについて、ギャーギャーと騒ぐ
自由はある。またそういう自由をもって、「自由」と誤解している。そういう人は多い。し
かしそれはここでいう「自由」ではない。
自由とは、(私はこうあるべきだ)という(自己概念)と、(私はこうだ)という(現実
自己)を一致させながら、冒頭に書いたように、『私らしく、あるがままの私を、あるがま
まにさらけ出して、あるがままに生きる』ことをいう。
だれにも命令されず、だれにも命令を受けず、自分で考え、自分で行動し、自分で責任
をとることをいう。どこまでも研ぎすまされた「私」だけを見つめながら生きることをい
う。
しかしそれがいかにむずかしいことであるかは、今さら、ここに書くまでもない。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
自由論 自由とは サルトル 無条件の愛 無私の愛 無の概念)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●釈迦の説く「無」
では、釈迦は、「無」をどのように考えていたのか。
直接的には「空(くう)」という言葉を使った。
つぎの原稿は2006年に発表したものである。
が、本当は、もっと前に書いたかもしれない。
私はよく過去に書いた原稿を呼び出し、その原稿を改めるということをよくする。
しかし少なくとも、仏教と実存主義の融合に気づいたのは、このころということになる。
そのまま紹介する。
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
【東洋哲学と西洋近代哲学の融合】2006年記
●生・老・病・死
+++++++++++++++++
生・老・病・死の4つを、原始仏教では、
四苦と位置づける。
四苦八苦の「四苦」である。
では、あとの4つは、何か?
+++++++++++++++++
生・老・病・死の4つを、原始仏教では、四苦と位置づける。四苦八苦の「四苦」であ
る。では、あとの4つは何か。
(1) 愛別離苦(あいべつりく)
(2) 怨憎会苦(おんぞうえく)
(3) 求不得苦(ぐふとっく)
(4) 五蘊盛苦(ごうんじょうく)の、4つと教える。
(1) 別離苦(あいべつりく)というのは、愛する人と別れたり、死別したりすることに
よる苦しみをいう。
(2) 怨憎会苦(おんぞうえく)というのは、憎しみをいだいた人と会うことによる苦し
みをいう。
(3) 求不得苦(ぐふとっく)というのは、求めても求められないことによる苦しみをい
う。
(4) 五蘊盛苦(ごうんじょうく)というのは、少しわかりにくい。
簡単に言えば、人間の心身を構成する5つの要素(色=肉体、受=感受、想=表象の構成、
行=意思、識=認識)の働きが盛んになりすぎることから生まれる苦しみをいう。
こうした苦しみから逃れるためには、では、私たちは、どうすればよいのか。話は少し
前後するが、原始仏教では、「4つの諦(たい)」という言葉を使って、(苦しみのないよう)
→(苦しみの原因)→(苦しみのない世界)→(苦しみのない世界へ入る方法)を、順に、
説明する。
(1) 苦諦(くたい)
(2) 集諦(しゅうたい)
(3) 滅諦(めったい)
(4) 道諦(どうたい)の、4つである。
(1) 苦諦(くたい)というのは、ここに書いた、「四苦八苦」のこと。
(2) 集諦(しゅうたい)というのは、苦しみとなる原因のこと。つまりなぜ私たちが苦
しむかといえば、かぎりない欲望と、かぎりない生への執着があるからということになる。
無知、無学が、その原因となることもある。
(3) 滅諦(めったい)というのは、そうした欲望や執着を捨てた、理想の境地、つまり
涅槃(ねはん)の世界へ入ることをいう。
(4) 道諦(どうたい)というのは、涅槃の世界へ入るための、具体的な方法ということ
になる。原始仏教では、涅槃の世界へ入るための修道法として、「八正道」を教える。
以前、八正道について書いたことがある。八正道というのは、正見、正思惟、正語、正業、正
命、正精進、正念、正定の8つのことをいう。
命、正精進、正念、正定の8つのことをいう。
+++++++++++++++
●八正道(はっしょうどう)……すべて「空」
大乗仏教といえば、「空(くう)」。この空の思想が、大乗仏教の根幹をなしているといっ
ても過言ではない。つまり、この世のすべてのものは、幻想にすぎなく、実体のあるもの
は、何もない、と。
この話は、どこか、映画、『マトリックス』の世界と似ている。あるいは、
コンピュータの中の世界かもしれない。
たとえば今、目の前に、コンピュータの画面がある。しかしそれを見ているのは、私の
目。そのキーボードに触れているのは、私の手の指、ということになる。そしてその画面
には、ただの光の信号が集合されているだけ。
私たちはそれを見て、感動し、ときに怒りを覚えたりする。
しかし目から入ってくる視覚的刺激も、指で触れる触覚的刺激も、すべて神経を介在し
て、脳に伝えられた信号にすぎない。「ある」と思うから、そこにあるだけ(?)。
こうした「空」の思想を完成したのは、実は、釈迦ではない。
釈迦滅後、数百年後を経て、紀元後200年ごろ、竜樹(りゅうじゅ)という人によって、
完成されたと言われている。
釈迦の生誕年については、諸説があるが、日本では、紀元前463年ごろとされている。
ということは、私たちが現在、「大乗仏教」と呼んでいるところのものは、釈迦滅後、6
00年以上もたってから、その形ができたということになる。そのころ、般若経や
法華経などの、大乗経典も、できあがっている。
しかし竜樹の知恵を借りるまでもなく、私もこのところ、すべてのものは、空ではない
かと思い始めている。私という存在にしても、実体があると思っているだけで、実は、ひ
ょっとしたら、何もないのではないか、と。
たとえば、ゆっくりと呼吸に合わせて上下するこの体にしても、ときどき、どうしてこ
れが私なのかと思ってしまう。
同じように、意識にしても、いつも、私というより、私でないものによって、動かされ
ている。仏教でも、そういった意識を、末那識(まなしき)、さらにその奥深くにあるもの
を、阿頼那識(あらやしき)と呼んでいる。心理学でいう、無意識、もしくは深層心理と、
同じに考えてよいのではないか。
こう考えていくと、肉体にせよ、精神にせよ、「私」である部分というのは、ほんの限ら
れた部分でしかないことがわかる。いくら「私は私だ」と声高に叫んでみても、だれかに、
「本当にそうか?」と聞かれたら、「私」そのものが、しぼんでしまう。
さらに、生前の自分、死後の自分を思いやるとよい。生前の自分は、どこにいたのか。
億年の億倍の過去の間、私は、どこにいたのか。そしてもし私が死ねば、私は灰となって、
この大地に消える。と、同時に、この宇宙もろとも、すべてのものが、私とともに消える。
そんなわけで、「すべてが空」と言われても、今の私は、すなおに、「そうだろうな」と
思ってしまう。ただ、誤解しないでほしいのは、だからといって、すべてのものが無意味
であるとか、虚(むな)しいとか言っているのではない。私が言いたいのは、その逆。
私たちの(命)は、あまりにも、無意味で、虚しいものに毒されているのではないかと
いうこと。私であって、私でないものに、振りまわされているのではないかということ。
そういうものに振りまわされれば振りまわされるほど、私たちは、自分の時間を、無駄に
することになる。
●自分をみがく
そこで仏教では、修行を重んじる。その方法として、たとえば、八正道(はっしょうど
う)がある。これについては、すでに何度も書いてきたので、ここでは省略する。正見、
正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定の8つをもって、八正道という。
が、それでは足りないとして生まれたのが、六波羅密ということになる。六波羅密では、
布施、持戒、忍辱、精進、善定、知恵を、6つの徳目と位置づける。
八正道が、どちらかというと、自己鍛錬のための修行法であるのに対して、六波羅密は、「布
施」という項目があることからもわかるように、より利他的である。
施」という項目があることからもわかるように、より利他的である。
しかし私は、こうしてものごとを、教条的に分類して考えるのは、あまり好きではない。
こうした教条で、すべてが語りつくされるとは思わないし、逆に、それ以外の、ものの考
え方が否定されてしまうという危険性もある。「まあ、そういう考え方もあるのだな」とい
う程度で、よいのではないか。
で、仏教では、「修行」という言葉をよく使う。で、その修行には、いろいろあるらしい。
中には、わざと体や心を痛めつけてするものもあるという。怠(なま)けた体には、そう
いう修行も必要かもしれない。しかし、私は、ごめん。
大切なことは、ごくふつうの人間として、ごくふつうの生活をし、その生活を通して、
その中で、自分をみがいていくことではないか。悩んだり、苦しんだりしながらして、自
分をみがいていくことではないか。奇をてらった修行をしたからといって、その人の人格
が高邁(こうまい)になるとか、そういうことはありえない。
その一例というわけでもないが、よい例が、カルト教団の信者たちである。信者になっ
たとたん、どこか世離れしたような笑みを浮かべて、さも自分は、すぐれた人物ですとい
うような雰囲気を漂わせる。「お前たち、凡人とは、ちがうのだ」と。
だから私たちは、もっと自由に考えればよい。八正道や、六波羅密も参考にしながら、
私たちは、私たちで、それ以上のものを、考えればよい。こうした言葉の遊び(失礼!)
に、こだわる必要はない。少なくとも、今は、そういう時代ではない。
私たちは、懸命に考えながら生きる。それが正しいとか、まちがっているとか、そんな
ことを考える必要はない。その結果として、失敗もするだろう。ヘマもするだろう。まち
がったこともするかもしれない。
しかしそれが人間ではないか。不完全で未熟かもしれないが、自分の足で立つところに、
「私」がいる。無数のドラマもそこから生まれるし、そのドラマにこそ、人間が人間とし
て、生きる意味がある。
今は、この程度のことしかわからない。このつづきは、もう少し頭を冷やしてから、考
えてみたい。
(050925記)
(はやし浩司 八正道 六波羅密 竜樹 大乗仏教 末那識 阿頼那識 無の概念 空)
+++++++++++++++++++
もう一作、八正道について書いた
原稿を、再収録します。
+++++++++++++++++++
●正精進
釈迦の教えを、もっともわかりやすくまとめたのが、「八正道(はっしょうどう)」とい
うことになる。仏の道に至る、修行の基本と考えると、わかりやすい。
が、ここでいう「正」は、「正しい」という意味ではない。釈迦が説いた「正」は、「中
正」の「正」である。つまり八正道というのは、「八つの中正なる修行の道」という意味で
ある。
怠惰な修行もいけないが、さりとて、メチャメチャにきびしい修行も、いけない。「ほど
ほど」が、何ごとにおいても、好ましいということになる。が、しかし、いいかげんとい
う意味でもない。
で、その八正道とは、(1)正見、(2)正思惟、(3)正語、(4)正業、(5)正命、(6)
正念、(7)正精進(8)正定、をいう。広辞苑には、「すなわち、正しい見解、決意、言
葉、行為、生活、努力、思念、瞑想」とある。
このうち、私は、とくに(8)の正精進を、第一に考える。釈迦が説いた精進というの
は、日々の絶えまない努力と、真理への探究心をいう。そこには、いつも、追いつめられ
たような緊迫感がともなう。その緊迫感を大切にする。
ゴールは、ない。死ぬまで、努力に努力を重ねる。それが精進である。で、その精進に
ついても、やはり、「ほどほどの精進」が、好ましいということになる。少なくとも、
釈迦は、そう説いている。
方法としては、いつも新しいことに興味をもち、探究心を忘れない。努力する。がんば
る。が、そのつど、音楽を聞いたり、絵画を見たり、本を読んだりする。が、何よりも重
要なのは、自分の頭で、自分で考えること。「考える」という行為をしないと、せっかく得
た情報も、穴のあいたバケツから水がこぼれるように、どこかへこぼれてしまう。
しかし何度も書いてきたが、考えるという行為には、ある種の苦痛がともなう。寒い朝
に、ジョギングに行く前に感ずるような苦痛である。だからたいていの人は、無意識のう
ちにも、考えるという行為を避けようとする。
このことは、子どもたちを見るとわかる。何かの数学パズルを出してやったとき、「や
る!」「やりたい!」と食いついてくる子どももいれば、逃げ腰になる子どももいる。中に
は、となりの子どもの答をこっそりと、盗み見する子どももいる。
子どもだから、考えるのが好きと決めてかかるのは、誤解である。そしてやがて、その
考えるという行為は、その人の習慣となって、定着する。
考えることが好きな人は、それだけで、それを意識しなくても、釈迦が説く精進を、生
活の中でしていることになる。そうでない人は、そうでない。そしてそういう習慣のちが
いが、10年、20年、さらには30年と、積もりに積もって、大きな差となって現れる。
ただ、ここで大きな問題にぶつかる。利口な人からは、バカな人がわかる。賢い人から
は、愚かな人がわかる。考える人からは、考えない人がわかる。しかしバカな人からは、
利口な人がわからない。愚かな人からは、賢い人がわからない。考えない人からは、考え
る人がわからない。
日光に住む野猿にしても、野猿たちは、自分たちは、人間より、劣っているとは思って
いないだろう。ひょっとしたら、人間のほうを、バカだと思っているかもしれない。エサ
をよこせと、キーキーと人間を威嚇している姿を見ると、そう感ずる。
つまりここでいう「差」というのは、あくまでも、利口な人、賢い人、考える人が、心
の中で感ずる差のことをいう。
さて、そこで釈迦は、「中正」という言葉を使った。何はともあれ、私は、この言葉を、
カルト教団で、信者の獲得に狂奔している信者の方に、わかってもらいたい。彼らは、「自
分たちは絶対正しい」という信念のもと、その返す刀で、「あなたはまちがっている」と、
相手を切って捨てる。
こうした急進性、ごう慢性、狂信性は、そもそも釈迦が説く「中正」とは、異質のもの
である。とくに原理主義にこだわり、コチコチの頭になっている人ほど、注意したらよい。
(はやし浩司 八正道 精進 正精進)
【補足】
子どもの教育について言えば、いかにすれば、考えることが好きな子どもにするかが、
一つの重要なポイントということになる。要するに「考えることを楽しむ子ども」にすれ
ばよい。
++++++++++++++++++
話をもとにもどす。
あのサルトルは、「自由」の追求の中で、最後は、「無の概念」という言葉を使って、自
由であることの限界、つまり死の克服を考えた。
この考え方は、最終的には、原始仏教で説く、釈迦の教えと一致するところである。私
はここに、東洋哲学と西洋近代哲学の融合を見る。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 東洋哲学と西洋哲学の融合 無の概念 無 はやし浩司 空)
Hiroshi Hayashi++++++はやし浩司
●欲望の克服
私たちが「欲望」と呼んでいるもの。
それらはすべて「無」に発する。
「性欲」を例にあげるまでもない。
ただの排泄欲にすぎない性欲が、人間社会そのものを支配している。
フロイトですら、「性的エネルギー」という言葉を使っている。
つまり「性的エネルギー」が、あらゆる動物(もちろん人間も含む)の生命力の根幹にな
っている、と。
(これに対して、フロイトの弟子のユングは、「生的エネルギー」という言葉を使っている。)
人間は絶え間なく、この欲望の支配下に置かれ、奴隷となり、それに振り回される。
が、たいへん悲しいことに、そうでありながら、ほとんどの人は、それに気づくこともな
い。
「私は私」と思い込んでいる。
ただの奴隷でありながら、それが「私」と思い込んでいる。
よい例が、電車の中で化粧をする若い女性。
自分の意思で化粧していると本人は思い込んでいる。
「あなたは自分の意思で化粧をしているのですか」と聞いても、その女性はこう答えるだ
ろう。
「もちろん、そうです」と。
が、その女性とて、その奥深くから発せられる「性的エネルギー」の奴隷でしかない。
その「奴隷である」という部分が、加齢とともに、やがてわかってくる。
●では、どうするか
ここから先は、製品で言えば、まだ試作品(プロトタイプ)。
が、今の私は、こう考える。
希望や期待が、欲望に根ざすものであるなら、希望や期待をもたないこと。
へたに希望や期待をもつから、そのつど壁にぶつかり、葛藤を繰り返す。
怒りもそこから生まれる。
恨みも、ねたみも、そこから生まれる。
ある賢人は、こう言った。
『人を恨むというのは、ネズミを殺すために、家を燃やすようなものだ』と。
あとでそれについて書いた原稿をさがしてみるが、怒りが強ければ強いほど、あるいは恨
みやねたみが強ければ強いほど、その人自身の人間性が破壊される。
が、希望や期待を捨てれば、怒ることはない。
人を恨んだり、ねたんだりすることもない。
……と書くと、では、「人は何のために、何を目標に生きればいいのか」と考える人もいる。
が、答は、シンプル。
『そのとき、その場で、やるべきことを、けんめいにすればいい』と。
トルストイをはじめ、多くの賢人たちも、異口同音に、「そこに生きる意味がある」と説く。
つまり懸命に生きるところに意味がある、と。
釈迦もその1人。
結局は、そこへ行き着く。
「結果」というのは、かならず、あとからついてくる。
ここにも書いたように、これは試作品としての結論ということになる。
このつづきは、一度、頭を冷やしたあとに、書いてみたい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 欲望(煩悩)論 煩悩論 欲望論)
(補記)2010年7月記
●『Hating people is like burning down your house to kill a rat ー Henry Fosdick
人を恨むというのは、ネズミを殺すために、家を燃やすようなものだ』(H・フォスディッ
ク)
+++++++++++++++++++++
人を恨んではいけない。
恨めば恨むほど、心が小さくなり、そこでよどむ。
よどんで腐る。
だからこう言う。
『人を恨むというのは、ネズミを殺すために、家を燃やすようなものだ』と。
解釈の仕方はいろいろあるだろう。
しかし簡単に言えば、(ネズミ)は(恨みの念)、
(家)は、もちろん(心)をいう。
(人生)でもよい。
ネズミを追い出すために、家に火をつける人はいない。
もったいないというより、バカげている。
「人を恨む」というのは、つまりそれくらいバカげているという意味。
+++++++++++++++++++++++++
●ある女性(67歳)
ついでながら、東洋医学(黄帝内経)でも、「恨みの気持ち」をきびしく戒めている(上
古天真論編)。
『(健康の奥義は)、精神的にも悩みはなく、平静楽観を旨とし、自足を事とす
る』『八風(自然)の理によく順応し、世俗の習慣にみずからの趣向を無理なく適応させ、
恨み怒りの気持ちはさらにない。行動や服飾もすべて俗世間の人と異なることなく、みず
からの崇高性を表面にあらわすこともない。身体的には働きすぎず、過労に陥ることもな
く、精神的にも悩みはなく、平静楽観を旨とし、自足を事とする』と。
恨みは、健康の大敵というわけである。
しかし恨みから逃れるのは、(あるいは晴らすのは)、容易なことではない。
妄想と重なりやすい。
「あいつのせいで、こうなった」と。
ものの考え方も、後ろ向きになる。
ある女性(68歳)は、ことあるごとに弟氏の悪口を言いふらしていた。
口のうまい人で、悪口の言い方も、これまたうまかった。
たいていはまず自分の苦労話を並べ、そのあと弟氏が何もしてくれなかった
という話につなげる。
同情を買いながら、相手が悪いという話につなげる。
自分がしたこと、あるいは自分がしなかったことをすべて棚にあげ、ことさら自分を飾る。
まわりの人に理由を聞くと、こう話してくれた。
「親が死んだとき、遺産の分け前をもらえなかったから」と。
が、いくら悪口を言っても、何も解決しない。
ただの腹いせ。
愚痴。
聞くほうも、疲れる。
●復讐
恨みといえば、「四谷怪談」がある。
近くテレビでも映画が紹介されるという。
恐ろしいと言えば、あれほど恐ろしい話はない。
「四谷怪談」と聞いただけで、私は今でも背筋がぞっとする。
「四谷怪談」にまつわる思い出は多い。
子どものころ、怪談と言えば、「四谷怪談」だった。
(はかに「牡丹灯籠(ぼたんどうろう)」というのもあった。
若い人たちは知らないかもしれない。)
「四谷怪談」のばあいは、男のエゴに振り回されたあげく、1人の女性が
毒殺される。
その女性が復讐のため、幽霊となって男を繰り返し襲う。
そのものすごさ。
執念深さ。
子どものころ映画館に入ると、通路の脇にローソクと線香が立てられていた。
それだけで私たち子どもは、震えあがった。
そのこともあって、「恨み」イコール「復讐」というイメージが、私のばあい、
どうしても強い。
そういうイメージが焼きついてしまった。
先に書いた「恨みを晴らす」というのは、「復讐して、相手をこらしめる」
という意味である。
●詐欺
自分の人生を振り返ってみる。
こまかいことも含めると、人を恨んだことは、山のようにある。
反対に自分では気がつかなかったが、恨まれたこともたくさんあるはず。
恨んだり、恨まれたり・・・。
しかし結論から言うと、生きていく以上、トラブルはつきもの。
恨みも生まれる。
しかし恨むなら、さっさと事務的に復讐して終わる。
「事務的に」だ。
そのために法律というものがある。
それができないなら、これまたさっさと忘れて、その問題から遠ざかる。
ぐずぐずすればするほど、その深みにはまってしまう。
身動きが取れなくなってしまう。
こんな人がいた。
当初、500万円くらいの私財をその不動産会社に投資した。
ついで役職を買う形で、さらに1000万円を投資した。
時は折りしも、土地バブル経済時代。
1か月で、1億円の収益をあげたこともある。
で、親から譲り受けた土地を、会社にころがしたところで、バブル経済が崩壊。
結局、元も子も失ってしまった。
ふつうならそこで損切をした上で、会社をやめる。
が、その男性はそのあと、8年もその会社にしがみついた。
「しがみついた」というより、恨みを晴らそうとした。
土地の価格が再び暴騰するのを待った。
で、現在はどうかというと、家も借家もすべて失い、息子氏の家に居候(いそうろう)
をしている。
今にして思うと、その男性は、(恨み)の呪縛から身をはずすことができなかった。
そういうことになる。
●心的エネルギー
(恨み)の基底には、欲得がからんでいる。
満たされなかった欲望、中途半端に終わった欲望、裏切られた欲望など。
「四谷怪談」のお岩さんには、金銭的な欲得はなかったが、たいていは
金銭的な欲得がからんでいる。
しかし人を恨むのも、疲れる。
私も若いころ信じていた伯父に、二束三文の荒地を、600万円という高額
で買わされたことがある。
これは事実。
そのあとも10年近くに渡って、「管理費」と称して、毎年8~10万円の
現金を支払っていた。
これも事実。
(その伯父はことあるごとに、私のほうを、「たわけ坊主(=郷里の言葉で、バカ坊主)」
と呼んでいる。)
が、それから35年。
つまり数年前、その土地が、70万円で売れた。
値段にすれば10分の1ということになる。
が、おかげで私は自分の中に巣食っていた(恨み)と決別することができた。
それを思えば、530万円の損失など、何でもない。
・・・というほど、(恨み)というのは、精神を腐らす。
心の壁にぺったりと張りついて、いつ晴れるともなく、悶々とした気分にする。
●『人を恨むというのは、ネズミを殺すために、家を燃やすようなものだ』
私はこの言葉を知ったとき、「そうだった!」と確信した。
『人を恨むというのは、ネズミを殺すために、家を燃やすようなものだ』と。
『怒りは、人格を崩壊させる』と説く賢者もいる。
心を腐らすくらいなら、損は損として早くその損とは決別する。
決別して忘れる。
忘れて、一歩前に進む。
でないと、それこそ「家に火をつける」ようなことになってしまう。
つまり人生そのものを、無駄にしてしまう。
人生も無限なら、それもよいだろう。
しかし人生には限りがある。
その人生は、お金では買えない。
実のところ私も、この7か月間、大きな恨みを覚えていた。
理由はともあれ、先にも書いたように、人を恨むのも疲れる。
甚大なエネルギーを消耗する。
だから自ら、恨むのをやめようと努力した。
が、そうは簡単に消えない。
時折、心をふさいだ。
不愉快な気分になった。
しかし「家に火をつけるようなもの」とはっきり言われて、自分の心に
けじめをつけることができた。
とたん心が軽くなった。
恨みが消えたわけではないが、消える方向に向かって、心がまっすぐ動き出した。
それが実感として、自分でもよくわかる。
最後にこの言葉を書き残したHenry Fosdickという人は、どんな人なのか。
たいへん興味をもったので、調べてみた。
●Henry Fosdick
英米では、その名前を知らない人がないほど、著名な作家だった。
こんな言葉も残している。
The tragedy of war is that it uses man's best to do man's worst.
(戦争の悲劇は、人間がもつ最善のものを、最悪のために使うところにある。)
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 恨み 恨み論 人を恨む ネズミを追い出す 家に火をつける)
●結論
いろいろ書いてきたが、人間は欲望の奴隷と考えてよい。
その欲望が、さまざまな感情を生む。
東洋医学でも、そう教える。
その感情の中でも、「怒り」「うらみ」「ねたみ」は、心を腐らす。
ときには人格を崩壊させる。
そこで重要なことは、つまり日々の生活の中で重要なことは、この怒りをどう手なずけ
ていくかということ。
それを自己管理能力といい、その能力のあるなしで、その人の人格の完成度が決まる。
釈迦も「怒り」をきびしく戒めている。
フォスディックの言葉を借りると、こうなる。
●『Anger is like burning down your house to kill a rat ー Henry Fosdick
人を怒るということは、ネズミを殺すために、家を燃やすようなものだ』と。
今朝のキーワードは、「怒り」ということになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 幼児教室 育児 教育論 Japan はやし浩司 新少林寺 空 無の概
念 正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定の8つをもって、八正道 四
苦八苦 仏教 はやし浩司 怒り 恨み)
Hiroshi Hayashi+++++++June. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
【BW生・募集中!】
(案内書の請求)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html
(教室の案内)
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html
●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。
■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
★
★
★
★
☆☆☆この電子マガジンは、購読を登録した方のみに、配信しています☆☆☆
. mQQQm
. Q ⌒ ⌒ Q ♪♪♪……
.QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m 彡彡ミミ
. /~~~\ ⌒ ⌒
. みなさん、 o o β
.こんにちは! (″ ▽ ゛)○
. =∞= //
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 2012年 1月 2日
□■□□□□□□□□□□□□□■□ =================
謹賀新年
明けましておめでとうございます。
2012年です!
今年もよろしくお願いします!
★★★HTML版★★★
HTML(カラー・写真版)を用意しました。
どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。)
************************
*
http://bwhayashi2.fc2web.com/page003.html
★★みなさんのご意見をお聞かせください。★★
(→をクリックして、アンケート用紙へ……)http://form1.fc2.com/form/?id=4749
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【不安にかられる母親たち】(気をつけたい不安先行型育児観)
++++++++++++++++++++++
こういう世相。
EUの金融危機。
景気も悪い。
加えて原発事故。
雨が降るたびに、今日はだいじょうぶかと思う。
不安でいない人をさがすほうが、むずかしい。
++++++++++++++++++++++
●みんな不安?
ある母親がテレビで紹介されていた。
関東地方のある都市に住む母親である。
その母親は1歳になる子どものために、野菜類は北海道や九州から仕入れているという。
たまたま野菜(キャベツ)を調理しているところだった。
キャベツの葉を一枚ずつめくり、水で洗い、さらにペットボトルの水で表面をこするよう
にして洗う。
一枚ずつ、ていねいに、ていねいに……
気持ちは、よくわかる。
心配なのは、よくわかる。
しかし……。
関東地方あたりまでくると、心配なのは、放射性物質だけではない。
環境ホルモン、農薬、食品添加物、遺伝子操作野菜などなど。
放射性物質は、その中のワンオブゼムに過ぎない。
しかも放射性物質というのは、水で洗って流し落とせるようなものではない。
野菜そのものの中に、取り込まれている。
私はその番組を見ていたとき、20年近くも前の話を思い出した。
ある母親が私のところへ来て、こう言った。
「相談したいことがある」ということだったので、相談にのった。
いわく、「今度、幼稚園で英会話を教えてくれることになった。
しかし講師の先生は、アイルランド人です。
アイルランドなまりの英語が身につくのではないかと、心配です」と。
アイルランド英語というのは、たしかにある。
たとえば「w」の発音を長く言う。
たとえば「what」でも、「ウォーワット」と。
しかしふつう聞いて、それがアイルランドなまりかどうか、それがわかる人はいない。
……当時はいなかった。
この時期、親、とくに母親は、何かにつけ、神経質になりやすい。
それが悪いというのではない。
とくに今回は、放射性物質である。
色も、においも、何もない。
それだけに、不気味。
恐ろしい。
それはわかるが、(正しく)心配しないと、ときとして過剰反応を引き起こす。
つまり、その母親にはきびしい意見になると思うが、(放射性物質への心配)と、(過剰
反応)は、別物。
どこかで一線を引かねばならない。
●限度
さて、一般論。
子育ては人生の一大事だが、しかしそれがすべてではない。
ほかの動物や植物とちがい、人間には、(限度)がある。
その限度を踏み越えてまで、子育てに埋没してはいけない。
わかりやすく言えば、本能は本能。
その本能に溺れてしまってはいけない。
……と書くのは、書きすぎだろうか。
もちろんそれぞれの親には、それぞれの思いがある。
哲学もあれば、同時に心の問題もある。
だから子育てには基準もなければ、標準もない。
家庭の事情も、みな、ちがう。
私は私。
あなたはあなた。
人それぞれということになる。
が、それでも、「?」と思うことはある。
私の理解の範囲を超えることがある。
それが先に書いた母親である。
(だからといって、その母親のしていることが、まちがっているとかそんなことを書いて
いるのではない。
誤解のないように!)
私が書きたいのは、こうした母親の反応に対して、だれかが適切に指導をしないと、そ
れが子育てのベースになってしまうということ。
放射性物質の危険性についても、そうである。
どの程度、危険なのか。
またどうすれば危険を防げるか、など。
経済的に余裕のある家族は、まだよい。
ペットボトルの水を、ふんだんに使うことができる。
そうでない家族は、どうなのか。
それもしないで、「今ただちに、害はありません」などというウソをつくから、母親た
ちは不安になり、心配になる。
が、その一方で、子育ての世界で、何が悪いかといって、過保護、過関心、過干渉、溺
愛ほど、悪いものはない。
子どもの心をゆがめるだけではない。
母親自身の心までゆがめてしまう。
育児ノイローゼもそのひとつ。
●父親の役割
『母親は子どもを産み育てる』。
では、父親の役目は何か。
その答は、発達心理学の世界では、2つ用意されている。
1.母子関係の是正
2.社会性の構築
「母子関係の是正」というのは、子育てというのは、母親だけに任せておいてはいけな
いということ。
父親がその間に割って入り、母子関係にクサビを打ち込む。
また「社会性の構築」というのは、要するに「狩りの仕方」ということになる。
自立して生きるための能力と技術を、子どもに授ける。
●花柄パンツ
が、この日本では、それが大きく狂った。
狂って、今の状況を生みだした。
その第一が、男性の女性化。
男性ホルモンの分泌が弱くなり、精子の数そのものも減ってきているという。
原因のひとつとして、環境ホルモン説が声高に叫ばれるようになって、もう15年になる。
が、原因が何であれ、10年単位で、子どもたち、とくに男児の質が変化してきたこと
は、まぎれもない事実。
35年前、花柄パンツをはいている高校生を知って、私は驚いた。
中日新聞でのコラムで、それについて書いた。
が、今では、小学生でも赤やピンクのパンツ(下着)を、ごくふつうにはいている。
どんなものを着ようが、中身(精神力)とは関係ない。
それはわかるが、私が感ずるこの違和感は、いったいどこから来るのか。
●母子関係の是正
母子関係は、濃密なものである。
それもそのはず。
子どもは母親の胎内で、10か月近く過ごす。
生まれてからも、母親から乳を受ける。
が、そのままの状態が、正しいというわけではない。
概して言えば、母子関係が是正されないと、子どもはマザコン化する。
これには男児も女児もない。
(「マザコン」というと、母親と息子だけの関係と思う人は多い。
しかし実際には、母親と娘の関係においても、子どもがマザコン化することも、それ以上
に多い。)
子どもは自立できないまま、母親とベタベタの人間関係を構築する。
子どもと母親が一体化する。
母親は母親で、そうであることを、親の深い愛によるものと錯覚する。
●一億、総マザコン
が、今では、マザコン化していない子どもを探すほうが、難しい。
おとなでも、難しい。
本来なら、父親が、その間に割って入り、母子関係を是正しなければならない。
が、その父親自身が、マザコン化している。
自分の子どもが母親との関係で、マザコン化していても、それに気がつかない。
またそうであることを、よい親子関係と思い込んでいる。
こうして日本人全体が、一億、総マザコン化した。
このことと直接結びつけてよいかどうか、わからない。
しかし「草食系」という言葉も、そこから生まれた?
どこかナヨナヨし、ハキがない男性(女性)を、「草食系」というらしい。
平たく言えば、野性的なたくましさに欠ける。
それが悪いと決めつけるわけにもいかない。
しかし今では男性でも整形をほどこし、朝の化粧に、半時間もかける。
が、こうした現象は、少なくとも、私が若いころには、考えられなかったことである。
●国際経済
時、折しも、世界的なリセッション(景気後退)期。
今朝のニュースを読んでも、明るいことは何もない。
EUの崩壊すら、可能性として論じられるようになっている。
もちろん日本の経済に与える影響も、深刻。
すでに日本国債の金利もジワジワと上昇し始めている。
1000兆円以上という借金をかかえ、日本は今、身動きが取れない状態にある。
へたをすれば、日本経済はこのまま奈落の底へと落ちていく。
あの3・11大震災の前ですら、「(日本経済の崩壊は)、可能性の問題ではない。
時間の問題」と言われていた。
書店に並ぶ、経済誌は、みな、そう書いていた。
が、そこへあの3・11大震災。
「復興特需」とやらで、皮肉なことに経済は一息ついたが、しかし根本的な問題は何も解
決していない。
むしろ悪化している。
●マスコミの責任
私も今回、EUが、こんなひどい状況とは知らなかった。
たとえばスペインにしても、建設途中で放棄されたマンションや別荘が、あちこちにある。
セスナ機しか着陸できないような飛行場の周辺にまで、リゾート地を建設したところもあ
るという(報道)。
そのあたり一帯は、ゴーストタウン化している。
しかしそれとて、ネットで知ったこと。
テレビではない。
むしろテレビのほうは、「世界のグルメ、食べ歩き」とか、「列車の旅」とか、どこかノ
ー天気な番組ばかりを流している。……流していた。
あるいは意味のないバラエティ番組ばかり。
ギリシャにしても、そうだ。
チャンネル数もふえた。
画面も美しくなった。
旅行番組的なものは、見た記憶がある。
しかしギリシャの現状は、ネットで調べて私ははじめて知った。
これを「大本営発表」と言わずして、何という。
報道の精神は、どこへ消えた?
あるいは、報道とは何か?
どうしてNHKならNHKでもよいが、「今、スペインはこんな状況になりつつある」と
いうような報道を、どうしてしてくれなかったのか。
それがあれば、被害者は、もっと少なくてすんだはず。
銀行や証券会社に勧められるまま、インチキ外債を買わされた人は、ゴマンといる。
●「現実内」
冒頭の母親には悪いが、そんなことで放射性物質を避けることはできない。
放射性物質というのは、いわば空気のようなもの。
空気以下の、「気」のようなもの。
どんな形であれ、1年とか2年とか、そういう年月をかけ、ありとあらゆるものから浸
み込んでくる。
今、身に着けている衣服からも、浸み込んでくる。
風呂の水からも、浸み込んでくる。
その母親がどうこう書いているのではない。
この日本は、また東京電力は、それほどまでに深刻な事故を引き起こしてしまったという
こと。
また原子力発電所というのは、それほどまでに危険なものであるということ。
「想定外」などという言葉に、だまされてはいけない。
そこに原子力発電所があり、日本は地震国であるという事実は、「現実内」である。
そしてこの先、多くの国民が、その後遺的症状に苦しむことになる。
これもまぎれもない「現実内」である。
●無力感
この無力感。
この脱力感。
そういう母親がそこにいても、またそのそばに子どもがいても、みなが見て見ぬフリをし
ている。
正直に、「そんなことをしても、あまり意味がありませんよ」と伝える人もいない。
本来なら、そういう不安をかかえる母親や子どもを、もっと遠くに避難させるのがよい。
しかしその国力は、もうこの日本にはない。
ないから、放射性物質を避ける、ひとつの方法として、こうした母親の行為を全国に流し
てしまう。
おそらくあの番組を見た多くの母親たちは、同じことを始めていることだろう。
キャベツの葉を一枚ずつめくり、水で洗い、さらにペットボトルの水で表面をこするよう
にして洗う。
何とも痛ましい光景だが、だれがそうした母親たちの行為を批判することができるだろう
か。
●終わりに……
放射性物質はともかくも、(不安になってもしかたないと思うが)、親のもつ不安感は、
かならず子どもに伝播する。
何かにつけ、親は不安先行型の子育てをしてしまう。
子ども自身も、不安の連鎖から抜け出られなくなってしまう。
またそれが一度、子育てのリズムになると、そのまま親の育児観として定着してしまう。
親子関係の基本になってしまう。
子どもが20歳を過ぎても、30歳を過ぎても、「不安だ……」「不安だ……」となって
しまう。
そのため親は、子どもに対して、過干渉になったり、過関心になったりする。
症状は様々だが、子どもの精神の発育にも、悪い影響を与える。
子ども自身も自立できなくなってしまう。
今回の放射性物質の問題はともかくも、不安先行型の子育てには、注意したらよい。
(はやし浩司 教育 林 浩司 林浩司 Hiroshi Hayashi 幼児教育 教育評論 幼児教
育評論 はやし浩司 親の心配 不安 不安先行型子育て 過剰心配 神経質になる母親
はやし浩司 過干渉 過関心)はやし浩司 2011-11-26記
+++++++++++++++
不安先行型の子育てについて書いた
原稿を探してみる。
+++++++++++++++
●パソコンの傷
子どものことでトラブルが起きたら、一に静観、ニに静観、三、四がなくて、五に親に
相談。
少子化の流れの中で、親たちは子育てにますます神経質になる傾向をみせている。
そうであるからこそなおさら、「静観」。
子どもにキズがつくことを恐れてはいけない。
子どもというのはキズだらけになって成長する。で、ここでいう「親」というのは、一、
二歳年上の子どもをもつ親をいう。
そういう親に相談すると、「うちもこんなことがありましたよ」「あら、そうですか」と
いうような会話で、ほとんどの問題は解決する。
話が少しそれるが、私は少し前、ノートパソコンを通信販売で買った。
が、そのパソコンには一本のスリキズがついていた。最初私はそのキズが気になってしか
たなかった。
子どももそうだ。子どもが小さいうちというのは、ささいなキズでも気になってしかたな
いもの。こんなことを相談してきた母親がいた。
何でもその幼稚園に外人の講師がやってきて、英会話を教えることになったという。
それについて、「先生はアイルランド人です。ヘンなアクセントが身につくのではないか
と心配です」と。
子育てに関心をもつことは大切なことだが、それが度を超すと、親はそんなことまで心配
するようになる。
さらに話がそれるが、子どものことでこまかいことが気になり始めたら、育児ノイロー
ゼを疑う。
症状としては、つぎのようなものがある。
(1)生気感情(ハツラツとした感情)の沈滞、
(2)思考障害(頭が働かない、思考がまとまらない、迷う、堂々巡りばかりする、記憶
力の低下)、
(3)精神障害(感情の鈍化、楽しみや喜びなどの欠如、悲観的になる、趣味や興味の喪
失、日常活動への興味の喪失)、
(4)睡眠障害(早朝覚醒に不眠)など。さらにその状態が進むと、Aさんのように、
(5)風呂に熱湯を入れても、それに気づかなかったり(注意力欠陥障害)、
(6)ムダ買いや目的のない外出を繰り返す(行為障害)、
(7)ささいなことで極度の不安状態になる(不安障害)、
(8)同じようにささいなことで激怒したり、子どもを虐待するなど感情のコントロール
ができなくなる(感情障害)、
(9)他人との接触を嫌う(回避性障害)、
(10)過食や拒食(摂食障害)を起こしたりするようになる。
(11)また必要以上に自分を責めたり、罪悪感をもつこともある(妄想性)。
こうした兆候が見られたら、黄信号ととらえる。
育児ノイローゼが、悲惨な事件につながることも珍しくない。子どもが間にからんでいる
ため、子どもが犠牲になることも多い。
要するに風とおしをよくするということ。
そのためにも、同年齢もしくはやや年齢が上の子どもをもつ親と情報交換をするとよい。
とくに長男、長女は親も神経質になりやすいので、そうする。……そうそう、そう言えば、
今では私のパソコンもキズだらけ。
しかし使い勝手はずっとよくなった。そういうパソコンを使いながら、「子どもも同じ」
と、今、つくづくとそう思っている。(中日新聞発表済み)
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【子育てが不安でならない】
●【佐賀県にお住まいの、Kさん(母親)より、はやし浩司へ】
++++++++++++++++++++++++++++++
佐賀県にお住まいの、Kさん(母親)より、こんな相談のメールが
届いています。
子どもの不登校の問題です。
この問題を、みなさんといっしょに、考えてみたいと思います。
++++++++++++++++++++++++++++++
【Kさんより、はやし浩司へ】
こんばんは。
メールのお返事本当にありがとうございました。パソコンに不慣れなもので、このメール
も送れているのか心配ですが・・・。
文字化けした部分は母子登校を続けるべきなのかということです。学校恐怖症というのも
拝見しました。
実は今日先生とお話して明日から送迎はするけれど、教室まではついていかないようにす
るという取り決めをしてきたのです。でもメールを拝見するとそれはかえってよくなさそ
うですね・・・。
でも私のなかでまだ学校は行かなくてはならないところという気持ちが、100%に近い
です。引きずってでも連れていくのは、私はしたくありませんが、私がついていくなら学
校へ行くというならついていって連れていくべきなのでしょうか? そして教室にいるべ
きでしょうか? 私自身、教室にいるとほかの子と比べたり、なんで私だけここにいるの
だろうと、悲しくなってきます。
親としては今行かないとずっといけなくなる不安が襲ってきます。これが高学年とか中学
生なら休ませているでしょうが、私は低学年からいかないなんて、どんな将来があるのか
と思ってしまいます。
今までの息子に対する子育ては本当に大変でした。まわりの人たちに、いい子だねとよく
言われるのです。私はそれがずっと嫌で私が息子に圧力をかけてしまっていたと反省の
日々でした。私の身近に精神病を抱えた人がいて、その人がまさに小さい頃いい子だねと
か親のいうことをよくきく子ででもある時から親を困らせていて、自分もこんな未来が待
っているのかと毎日考えてしまいます。
息子はとにかく人前ではにこにこ明るくあまりもめごとをしないことです。でも今まで家
ではいちいち文句いったり、癇癪をおこしたり、てこずる場面が多くて障害があるのかと
考える時もあります。
私からみた息子は感受性が強く、小さな頃から大人の会話に混ざろうとしたり、まだわか
らなくていいことがわかったり、カンが強くていろんなことをわかりすぎる半面、幼さゆ
えに処理しきれなくて悩むといったところが、私の見たところだけですが、そう感じます。
よくいろんなことに気がつくしいろんな状況をみて判断したりできる半面、あんなことで
きるのにここができないの?と、思ってしまう部分もあります。小さなときから大人と話
しているみたいで、私も子供ではなく大人と話している気分になってしまい、息子の返答
がおかしなときに、子供らしいと思ったり、大人っぽくみずぎて、この子おかしいと思っ
たりしてしまいます。ついつい7歳ということを忘れてしまいます。
気になる点は多々ありますが、なかなか次の行動にすんなりうつることができないことで
す。お風呂とか小さいころからすんなりいきません。あと記憶力がものすごいです。こち
らがこわくなるほどです。
息子は本当に今まさに私の不安定さを見事に見抜いています。ついついぼーっとしてしま
うと楽しくないの?とか、ご機嫌取りしにきます。分離不安の症状がでてから、すごく私
の言うことを聞こうとしていて、私はそれが気持ち悪いのです。今の私は息子に対して否
定的でほんとにいけないなあとおもいます。
たぶん何か言ったことに対して反抗的ならほんとうにこの子は言うことを聞かないからお
かしい、と思い素直に、はいと返事されると気持悪いしといったかんじです。今は見捨て
られ不安のためすごく言うことを聞いていたり、わかっていることをわざわざ言いにきた
りそういうときに、私がいらっとした態度や表情をしてしまいます。
先週、学校に行けなかったときに水族館に出かけてきました。そのこともまわりから賛否
両論で私は家で、テレビを見たり、ゲームをやってたら腐っちゃうと思って連れ出したの
ですがまわりから楽しませたら、余計行きたくないんじゃないかといわれましたが、メー
ルをみて安心しました。
今の私は日々が辛くて辛くて、もしもう一度人生があり、結婚したならば子供を持たない
という選択をしてしまうぐらいどん底です。かけがえのない宝なのですが・・・今の私は
子育てが辛いです。でも守るのは私たちしかいないですもんね。私自身、小さなころから
感受性が強く、今の息子みたいにいろいろなことを感じてしまい、辛い思いもしてきて、
今の息子をよみとろうとしすぎる部分も、私自身を追い込んでるきがします。間違ってと
らえたりもしているだろうけど、昔の自分と重ねてしまっているなあと思います。
書きたいことがいろいろありすぎて何からかけばいいのか、てんでばらばらな文章になっ
てしまいましたがすみません。きっと忙しい方だからメールくるなんておもってもみませ
んでした。本当にありがとうございます。少し気持ちが楽になりました。またきっと不安
になってメールすると思います。よろしくお願いいたします。
【はやし浩司より、Kさんへ】
「子どもを、全幅に心を開いて信じきれない、母親の葛藤」ということになります。
子どもというのは、親の心をそのまま引き継いでしまいます。
親が「不安だ、不安だ」と思っていると、子どもの方も、自分に自信がもてなく、自己評
価力をさげてしまいます。「ぼくは、ダメな子なんだ」とです。
そういう点では、子どもは、親の(思い)どおりの子どもになるということです。
「うちの子は、すばらしい」「できがいい」と思っていると、その子どもはハツラツとし
てきます。そうでないと、そうでない。
不安先行型の子育てのこわいところは、ここにあります。
Kさんの不安、心配は、恐らく妊娠したときから始まっています。
それが出産→育児→現在……とつながっています。
原因は、母子関係の不全ということになりますが、さらにさかのぼれば、Kさん自身と、
Kさんの母親との関係が、疑われます。
KさんとKさんの母親との関係も、不全だったということになります。
これを子育ての世界では、「世代連鎖」と呼んでいます。
つまりKさんは今、自分が受けた子育てを、そっくりそのまま、自分の子育てで再現して
いるということです。
Kさん、あなたは、あなたのお母さんの前で、いい子(=人形子)だった。
言いたいことも言えず、がまんし、心を開いて、甘えることもできなかった。
あなたはいい子でいることで、母親に認められようとしていた……。
少しきびしいことを書きましたが、実のところ、あなたは自分の子どもにさえ心を開け
ないでいます。
ひょっとしたら、あなたの夫に対してさえも、心を開けないでいるのかもしれません。
「もっと心を開きなさい!」と書きたいのですが、この問題を解決するためには、この先、
5年とか、10年とか、長い年月がかかります。
しかしそうであることに気がつけば、長い年月をかけても、この問題は解決します。
そのつど努力して、自分の心を開いてみてください。
(いい人)ぶるのを、やめるのです。
居直るのです。
「私は私だ」と、です。
で、今、あなたの子どもが、同じことを繰り返しています。
あなたはそういう子どもの中に、自分の過去を見ています。
それが不安の原因と考えてください。
昨日もらったメール(一部、文字化け)を、そのまま紹介させてください。
++++++++++++++++++
【Kさんより、はやし浩司へ】
息子の分離不安で悩んでおります。9月の5連休ごろから様子がおかしくなり、ママがい
なくなるのが怖いといい、登校しぶりがでています。保育園時代から毎年年に1回1か月
ほど登園拒否があります。いつも秋ごろでだいたい同じ時期にでます。年中までは登園拒
否でしたが、ママがいなくなるという不安を訴えるのは、去年の登園拒否のときからです。
その時は1か月ほどでぱたっとなくなりました。でもまた今年も同じ症状がでて対応にこ
まっております。家の中でも私を探したり、友達と遊びに行くのもお迎えの時間を何度も
確認して絶対迎えにきてねと念をおします。現在学校へは母子登校しています。今身体的
にでている症状は腹痛、頭痛、吐き気、チックです。
特に朝腹痛をうったえます。授業中も集中力がとぎれると、おなか痛い、寒い、疲れた、
もうやりたくないと私に助けを求めます。頑張れている時もあるのですが、私が学校にい
ることが彼にとっていいのかぎもんです。私がいることによって甘えがでてしまい逃げ出
す姿勢にさせてしまっているのではないかとおもってしまいます。先生は無理して学校に
こなくていい、早退する?それともお母さんにずっといてもら
……(以下、文字化け)……
……息子には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ちいさなころから甘えさせてなか
ったり突き放した態度ばかりで下の子たちの入院で1か月以上離れて生活したり、執拗に
怒りすぎたり手もあげたりしました。本当に今は反省の日々です。もう過去にはもどれな
いけど今からでも間に合うのでしょうか。彼の心に傷をつけたと自分を責める毎日です。
小さなころから育てにくく癇癪をおこしたり、何か障害があるんじゃないかと思ったこと
もあります。ここに書ききれないくらいいろいろありますが今家族みんなが不安定で下の
子たちも不安定になっていきて私自身子育てが辛すぎて苦しい日々です。少しでもお力を
御貸しいただけることを、ねがっております。
++++++++++++++++++
【Kさんへ、はやし浩司より】
子どもは、あくまでも家族の(代表)です。
子どもに何か問題(?)があると、親は、懸命に、子どもに向かってそれを直そうとします。
しかしこの見方は、親の身勝手というものです(失礼!)。
子どもに何か問題が起きたら、まず自分を疑ってみる。
子どもは、家族のかかえる問題を、別の形で表現しているだけです。
「代表」というのは、そういう意味です。
以下、気がついたことを、箇条書きにしてみます。
●「どうしてうち子だけが……
子どもに何か問題(?)が起きると、ほとんどの親は、「どうしてうちの子だけが……」
と悩みます。
これは共通した親の心理と考えてください。
しかし実際には、問題のない子どもはいないし、みな、そうした問題をかかえながら、必
死に闘
っているのです。
(外からはわかりませんが……。)
Kさんのメールを読んでいて気になるのは、その視野の狭さ(失礼!)です。
読んでいるだけでも、読んでいる私の方が窮屈に感ずるほどです。
「学校とは、100%、行かねばならないところ」という部分もそうですが、人生観その
ものが、狭い(失礼!)。
「まだ幼いうちからこうでは、先が心配でならない」という部分も、そうです。
Kさんの子どもは、いわば、心の風邪をひいて、熱を出している。
それを見て、「将来が心配」は、少し飛躍しすぎています。
それともKさん自身が、子どものころ、「学校とは行かねばならないところ」と、親にも
迫られ、Kさん自身も、そういう形で、自分を追い込んでいた(?)。
学校神話というのは、それを言います。
日本人は、明治の昔から、そういう意識を叩きこまれていますから、それが今でも亡霊と
なって、親や子どもたちを苦しめているのです。
アメリカ人でも、オーストラリア人でも、彼らは、学校に対して、もっとおおらかに考
えていますよ。
カナダ人は、もっとそうです。
学校の設立そのものが、自由です。
教科書なんて、もちろんありません。
どの子も、小学生のときから、落第(ドロップアウト)を自由に経験しています。
が、日本人だけは、「学校、学校、学校……!」と。
バカみたいと言ったら、失礼かもしれませんが、少なくとも外国の人から見れば、そうで
しょうね。
●母子登校
母子登校など、何でもないことですよ。
いっしょに学校へ行ってあげてください。
他人の目が気になるようでしたら、そういう人たちは、河原の石ころとでも思えばよいの
です。
まず、あなた自身が、心を開き、大きくなることです。
子どもの心だけを見て、行動すればよいのです。
最近では、子どもを見る親たちの姿勢も変化してきました。
あなたが明るく、さわやかに母子登校をつづければ、みなも、あなたを暖かく見守ってく
れるで
しょうし、あなたのすばらしさ(=度量の広さ)に感銘を受けるはずです。
もっと自分に、そして自分のしていることに自信をもちなさい!
「私はすばらしい親だ」とです。
ただ誤解がひとつ、あります。
症状だけを見ると、母子分離不安症のようにも思えますが、神経症による症状もいくつか
出ていますので、やはり「学校恐怖症」に準じて考えたほうがよいでしょう。
7歳という年齢からして、母子分離不安症だけでは、そういった症状は出てきません。
学校恐怖症については、「はやし浩司 学校恐怖症」で検索してみてください。
(これは前回の返事で書いたとおりです。)
ときどきパニック状態になりますが、どうかじょうずに、パニック期を乗り越えてくだ
さい。
コツは、「学校恐怖症」のところで書いたように、無理をしないことです。
ここで無理をすると、本当に不登校児ということになってしまいます。
しかも、長期の、です。
●カルト抜き
Kさんの心には、学校神話が、骨のズイまでしみ込んでいます。
「学校絶対教」と言ってもよいかもしれません。
それを抜くのは、たいへんなことです。
しかし現実には、アメリカだけでも、ホームスクーラー(=家庭で教育を受ける子ども)
が、200万人を超えていますし、EUでは、さらに教育が自由化されています。
みんな学校などほったらかしで、クラブ活動に専念しています。
そういう(自由ぽさ)を見るたびに、「何だ、この日本は!」と、私は感じてしまいます。
あえて言うなら、Kさんも視野を広めて、もう少し高い視点から、一度、子育てを考え直
してみたらいかがでしょうか。
大切なことは、子どもが生き生きと、自分のしたいことをしながら、自分を見つけてい
くことです。
Kさんは、自分の子どもがいい子ぶることを心配していますが、そういう子どもにしてい
るのは、Kさん自身なのですね。
つまりあなた自身が、子どもにその「型」をあてはめようとしている。
子どもにしても、あなたは息苦しい母親だと思います。
何をしても、親が心配そうな目つきで、自分をながめている。
何をしても、「あれはだめ」「これはだめ」と言われる。
私があなたの子どもだったら、「バカヤロー!」と言って、家を飛び出してしまうかもし
れませんよ。
仮に、あなたの子どもが学校へすんなりと通うようになっても、あなたの心配や不安は
消えません。
あなたはまた別の新たな心配や不安の種を見つけてきては、心配し、不安に思うのです。
「うちの子は、B中学校に入れるかしら?」
「友だちと仲よくやっていかれるかしら?」とか、など。
●これはあなたの問題です
あなたはあなたで、好きなことをすればよいのです。
目が一方的に、子どもの方ばかりに向いている。
過関心というのは、今のあなたのような状態をいいます。
親ではなく、妻でもなく、女でもなく、ひとりの人間として、したいことをさがし、そ
れに向かって進みます。
そういう形で、自分の中から、子どもを消していきます。
(あるいは、これはあくまでも私の推測ですが、ひょっとしたら、あなたは、あなたの
夫に対して、おおきなわだかまりをもっているのかもしれません。
不本意な結婚であったとか、あるいは愛情を感じない結婚生活であったとか、など。
それが子どもの問題として、転移している(?)。
そういう可能性もありますから、一度、考えてみてください。)
どうであるにせよ、ここは自然体で!
あまり深く考えないで、学校の先生と相談して、母子登校が必要であれば、すればよいで
しょう。
「取り決め」などという、恐ろしい言葉は使わないこと!
そんなものを取り決めて、どうするのですか?
子どもの心と、そのときの状況を見て、自然体で判断してください。
また、今、そうであるからといって、この先も、ずっとそうであると考えてはいけませ
ん。
そういうのを、「取り越し苦労」と言います。
へたをすれば、あなた自身が、育児ノイローゼ(=うつ病)になってしまいます。
すでにその傾向が強く見られます。
それについても、「はやし浩司 育児ノイローゼ」で検索してみてください。
いくつか記事をヒットできるはずです。
●子どもが親を育てる
悪いことばかりではありません。
今、こうして問題にぶつかりながら、実は、あなたは成長しているのです。
あなたは自分の子どもを見ながら、自分の過去まで見ようとしている。
自分を知ろうとしている。
コツは、「十字架のひとつやふたつ、背負ってやろうではないか」と居直ることです。
その思いっきりのよさというか、割り切りが、あなたの心に風の穴を開けます。
風通しをよくします。
大切なことは、今、そこにある(運命)を受け入れてしまうということです。
あなたの子どもがそうであるなら、そうであると、受け入れてしまうことです。
運命というのは、それを避けようとすればするほど、キバをむいて、あなたに襲いかか
ってきます。
しかし一度受け入れてしまえば、向うから、シッポを巻いて退散していきます。
童心に返って、母子登校を、いっしょに楽しみなさい!
楽しむのです。
人生は一度しかありませんよ!
それにそういう思い出……つまり、子どもの心を守り切ったという思い出ほど、あとあ
と光り輝きます。
親子の絆をすばらしいものにします。
仮に万が一、不登校児になったとしても、です。
そしてあなたはあなたで、自分の運命を受け入れます。
もうそろそろその時期に来ています。
「私は私」と、自分を受け入れてしまうのです。
そこは実におおらかで、すがすがしい世界です。
『あきらめは、悟りの境地』という格言は、私が考えた格言ですが、あなたも一度、経験
してみてください。
●では、どうするか?
『許して、忘れる』……何か苦しいことがあったら、この言葉を、心の中で何度も念じ
てみてください。
昔、私が学生のとき、オーストラリアの友人が教えてくれた言葉です。
私の子育て観の根幹にもなっている言葉です。
これも、「はやし浩司 許して忘れる」で検索してみてください。
その意味をわかってもらえると思います。
それとやはり心配なのは、Kさん、あなた自身の心の問題です。
私にも似たようなところがあります。
そういうときは、カルシウム分、カリウム分、マグネシウム分の多い食生活(=海産物)
に心がけ、あとはハーブ系の安定剤を服用しています。
内科でも、軽い安定剤を処方してくれますので、ひどいときには、それを口の中で溶かし
てのんでいます。
一度、ドクターと相談してみてください。
(1)求めてきたら、すかさず。
これについては、先に書いたとおりです。
(2)二番底、三番底に注意
こうした問題には、必ず、二番底、三番底がありますから、注意してください。
多くの親は、こうした問題をかかえると、「今が最悪」と思います。
しかしその下には、さらに最悪の状態が、待ち構えています。
ですから、「最悪」と感じたら、今の状態をこれ以上悪くしないことだけを考えて、対処
します。
なおそうとか、そういうふうに考えていけません。
とにかく現状維持です。
今は、何とか学校に通っていますから、今の状況を大切に!
あとは半年単位、1年単位で、子どもの様子を観察します。
1~2週間程度の範囲で、一喜一憂してはいけません。
また今こそ、あなたの真の愛が試されているときです。
親は子どもを産むことで、親になりますが、しかし真の愛への道は、遠くて険しいもので
す。
ですから勇気をもって、前に進んでください。
そういう姿に、みなが、気高さを感ずるようになるでしょう。
顔をゆがめてはいけません。
暗い表情をしてみせてはいけません。
明るく、さわやかに、みなにこう笑って言うのです。
「ハハハ、うちも母子登校ですよ」と。
(3)先生と父親との連携プレーを大切に
この問題は、あなたひとりでは、荷が重すぎます。
ですから、学校の先生や、あなたの夫との連携プレーを大切に。
今のあなたはひとりで問題を抱え込みすぎています。
自分に責任を求めすぎています。
いいですか、今、あなたがかかえている問題など、何でもありませんよ!
今どき、不登校など、何でもない問題です。
母子登校にしても、保健室登校にしても、何でもない問題です。
それで子育てに失敗したとか、私はだめな母親だとか、そういうふうに考えて、自分を追
い詰めないこと。
私のマガジンでも読んで、もっと視野を広くしてください。
たまたま昨日、別の母親から、こんなメールが届いています。
紹介します。
++++++++++++++
M件のEさんより
++++++++++++++
はやし浩司 様
いつもHPの記事で勉強させていただいております。
5歳の息子と2歳の息子がいます。
先生があちこちで何度もおっしゃっている通り、
上の息子に対しては、不安先行、心配先行の子育てをしてきました。
(今でもその気はまだあると思います…)
若干、上の息子に神経質な面があると感じられるのは、そのせいだと思います。
…ここまで書いて、あとが続かず、そのままメールソフトの下書きに保存していました。
当時、5歳と2歳だった息子は、7歳と4歳になりました。
上述のようなことを自分で書いていたことが信じられないほど、
今は、楽な気持ちで子どもと過ごしています。
イライラしたりすることもありますが、
子どもたちに対して、不安や心配に思うことは、ほとんどありません。
子どもたちを見て、そのままでいいと思い、細かいことにこだわらない。
それだけで、こんなに楽になるとは思いませんでした。
神経質な面があるなと思っていた上の息子が、
意外と動じないところがあったり、飄々としていたり、
こんな子だったんだ、と面食らう思いです。
下の息子は、最初から、ものすごくあけっぴろげで、
いつもニコニコしており、
「ありがとう」「ごめんね」「可愛いね」「きれいだね」
という言葉を、なんのてらいもなくスッと口にできる子どもです。
荷物を持っていれば、「持ってあげる!○○、力持ちだから!」と言い、
私が台所で何かしていると、「手伝ってあげる!これ、洗うね」と言い、
うーん、逆にオジャマなんだけどなぁと苦笑しつつ、
苦笑してしまうしかないくらい、ものすごく可愛げのある子どもなのです。
この下の息子が、非常にストレートに愛情を表現し、
上の息子は、それに比べるとわかりにくい感じだったのですが、
ここ最近は、素直に甘えてくるようになり、ああ、なんだか変わったなぁと思っています。
私の受け取り方、見る目が変わっただけかもしれません。
子育ての癖・心の癖は、なかなか治らないものだと思いますので、
できるだけ頻繁に先生の記事を読み、
いつも頭の中にあるよう、意識して心がけて行きたいと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いします。
先生とご家族の皆様のご健康をお祈りいたします。
++++++++++++++
【Kさんへ】
では、今朝はこれで失礼します。
「心を解き放て! 体はあとからついてくる!」
おはようございます。
浜松市・はやし浩司
Hiroshi Hayashi+++++++Nov. 2011++++++はやし浩司・林浩司
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m~= ○
. ○ ~~~\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
|
